新刊書籍
レーベルで絞り込む :
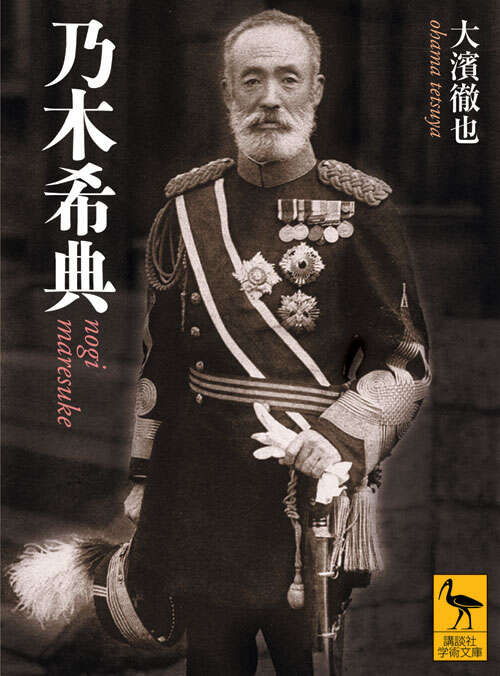
2014.10.24発売
乃木希典
講談社学術文庫
度を越した遊興、4度の休職と隠遁、東郷平八郎との明暗。「殉死」に沸騰する世論と、公表時に改竄された遺書。乃木希典とは、「明治国家」と根本的に相容れない人間性にもかかわらず、常に「国家意思」によって生かされ続けた人物だった。漱石、鴎外、西田幾多郎らの乃木評から小学生の作文まで網羅して描く「軍神」の実像と、近代日本の精神のドラマ。(講談社学術文庫)
「軍神」の実像と近代日本の宿痾を抉る名著。常に国家意思と結びつくことで生かされてきた「明治の軍神」の生涯と人物像を、一般庶民から、漱石や鴎外、西田幾多郎らの乃木評までを織り込みながら描き出す。
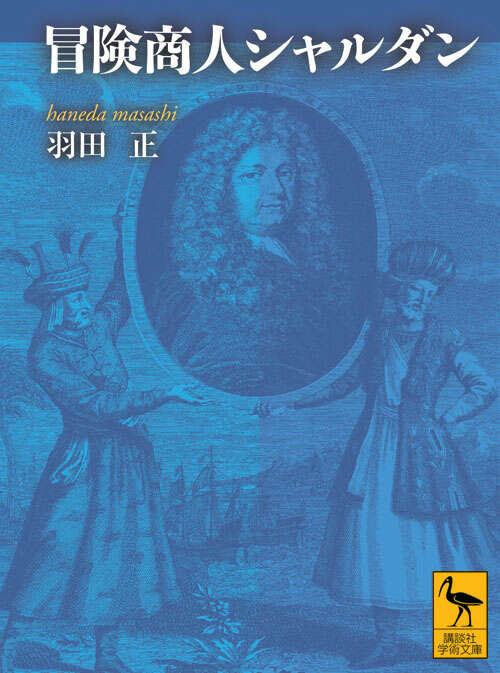
2014.10.24発売
冒険商人シャルダン
講談社学術文庫
多様な宗教と言語が行き交うペルシアで成功を収めた商人にして旅行記作家のジャン・シャルダンは、新教への迫害が続く息苦しい故郷・パリを捨ててロンドンに移住し、爵位を得た。しかし、彼の最大の悩みは、怠け者の長男の行く末だった――。時代に翻弄されつつ「一級史料」を書き残した市井の人物の生涯と、彼らが生きた17世紀の社会を活写する。(講談社学術文庫)
世界を旅し、記録した「マイナーな男」の波瀾万丈
時代に翻弄され、家庭に悩んだ旅行記作家の生涯。歴史の小さな襞から、17世紀の<世界>を照らし出す。
多様な宗教と言語が行き交うペルシアで成功を収めた商人にして旅行記作家のジャン・シャルダンは、新教への迫害が続く息苦しい故郷・パリを捨ててロンドンに移住し、爵位を得た。しかし、彼の最大の悩みは、怠け者の長男の行く末だった――。時代に翻弄されつつ「一級史料」を書き残した市井の人物の生涯と、彼らが生きた17世紀の社会を活写する。
はじめは、300年も前のこんな「マイナーな人物」に関して十分な史料があるのだろうか、と疑っていたのだが、出るわ出るわ、こんなことまでと思うほどたくさんの新しい事実が明らかになり、私はシャルダン研究に夢中になっていった。第4章の冒頭にも記したように、史料としてまだほとんど使われていないシャルダン関係の大量の手紙や文書類をイェール大学で「発見」した時、私の興奮は最高潮に達した。――<「おわりに」より>
※本書の原本は、『勲爵士シャルダンの生涯――十七世紀のヨーロッパとイスラーム世界』として、1999年に中央公論新社より刊行されました。

2014.10.24発売
チーズのきた道
講談社学術文庫
「乳の生化学」の第一人者が明かす、チーズの起源と分類法、そしてそれらを育んだ風土。栄養価が高く保存性に優れたチーズを、各地の部族は、その存亡をかけて育ててきた。モンゴルのホロート、古代ローマのチーズ菓子、フランスのカマンベール、日本の酥(そ)など、古今東西の文献を渉猟し、乳文化を実地に探訪。「人類にとっての食文化」に考察は及ぶ。(講談社学術文庫)
「乳の生化学者」が調べ上げた起源と歴史、育んだ風土
ヨーロッパ・中東から、インド・モンゴル・日本まで世界のチーズと乳文化を探訪
「乳の生化学」の第一人者が明かす、チーズの起源と分類法、そしてそれらを育んだ風土。栄養価が高く保存性に優れたチーズを、各地の部族は、その存亡をかけて育ててきた。モンゴルのホロート、古代ローマのチーズ菓子、フランスのカマンベール、日本の酥(そ)など、古今東西の文献を渉猟し、乳文化を実地に探訪。「人類にとっての食文化」に考察は及ぶ。
※本書の原本は、1977年、河出書房新社より刊行されました。
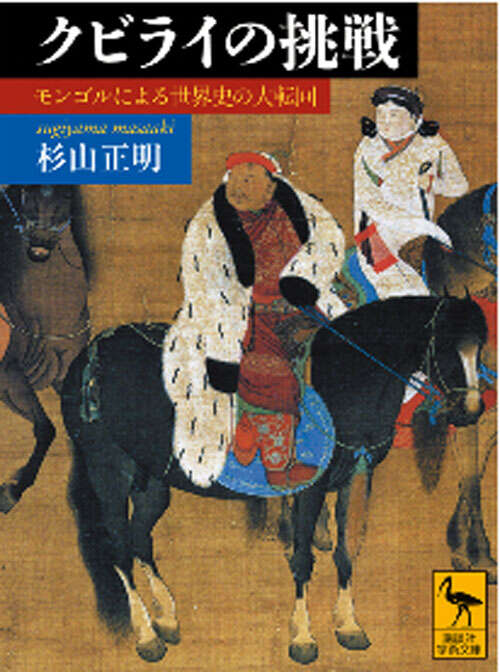
2014.10.24発売
クビライの挑戦 モンゴルによる世界史の大転回
講談社学術文庫
13世紀初頭に忽然と現れた遊牧国家モンゴルは、ユーラシアの東西をたちまち統合し、世界史に画期をもたらした。チンギス・カンの孫、クビライが構想した世界国家と経済のシステムとは。「元寇」や「タタルのくびき」など「野蛮な破壊者」というイメージを覆し、西欧中心・中華中心の歴史観を超える新たな世界史像を描く。サントリー学芸賞受賞作。(講談社学術文庫)
「モンゴル時代」こそが世界史の転機だった。チンギス・カンの孫クビライは、ユーラシアの東西を海陸からゆるやかに統合した。人類史上に類のない帝国「大モンゴル」の興亡を描き、新たな世界史像を提示する。
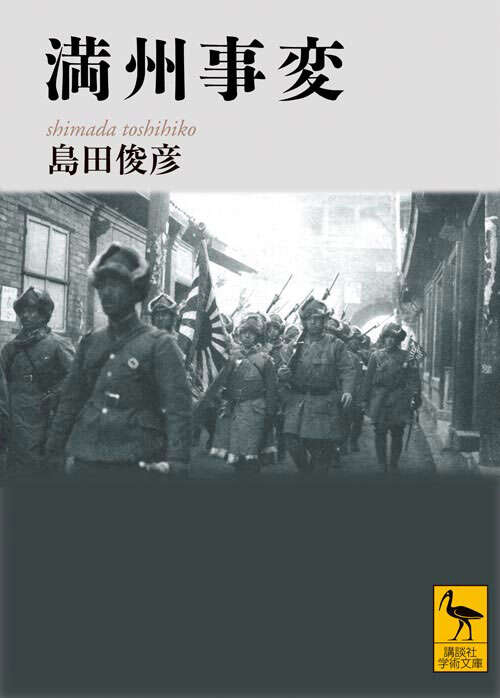
2014.10.24発売
満州事変
講談社学術文庫
1931年9月18日、奉天郊外の柳条湖で南満州鉄道の線路が爆破された。この事件を契機に、大陸での勢力拡大を目論む関東軍は満州(現・中国東北部)全土を占領する。膨大な史料の精緻な読みをとおして、第一次山東出兵、張作霖爆殺事件から、関東軍の暴走、満州国建国、国際連盟脱退まで、当時の状況を詳細に再現、近現代史の問題点を抉剔する。(講談社学術文庫)
十五年戦争の契機となった紛争の実像とは? 現在の日中関係にも影を落とす満州事変。山東出兵、張作霖爆殺、満州国建国、国際連盟脱退――。膨大な史料の精緻な読みによって、事件の全貌を鮮やかに再現する。

2014.10.24発売
「日本人論」再考
講談社学術文庫
明治以降、夥しい数の日本人論が刊行されてきた。『武士道』『菊と刀』『「甘え」の構造』などの本はなぜ書かれ、読まれ、そして好評を博すのか。そこには、私たちを繰り返し襲う「不安」がある。欧米文明に遭遇し、戸惑う近代日本人のアイデンティティの不安の在処を抉り出す。本書は、日本人論の総決算であり、150年間の近代日本の物語でもある。(講談社学術文庫)
2000冊を超える「日本人論」を総括する。明治以降、近代化の中で、原理的アイデンティティ不安に苛まれた日本人は数多の「論」を紡ぎ出した。時代の空気が生んだ「論」を検証し、日本人の無意識を探る。
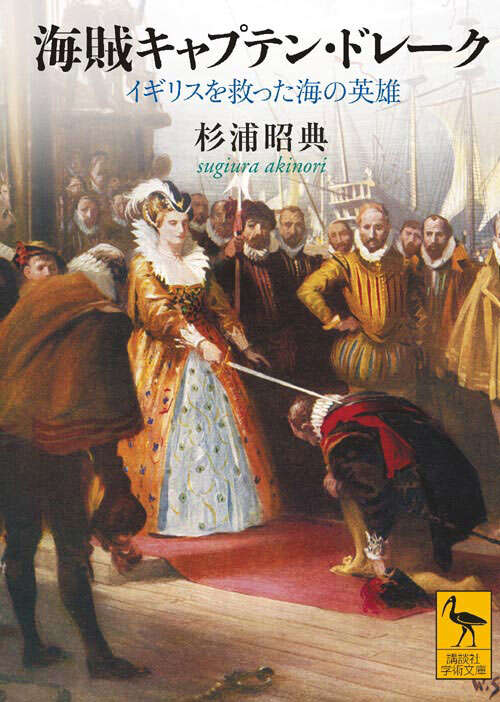
2014.10.24発売
海賊キャプテン・ドレーク イギリスを救った海の英雄
講談社学術文庫
10歳にしてテームズ川の船乗りになり、マゼランの半世紀後、史上二人目の世界周航者となったキャプテン・ドレーク。奴隷貿易とスペイン植民地襲撃で、巨万の富を手に入れる一方、エリザベス女王にサーの称号を受け、イギリス海軍提督として無敵艦隊を撃退する。16世紀、海上という無法地帯を舞台に、大暴れした男たちの野望と冒険を活写する。(講談社学術文庫)
英国の伝説的英雄の野心とロマン溢れる生涯。16世紀。無敵艦隊を擁する当時最大の海洋王国スペインと植民地拡大を狙うイギリス。海の覇権争いの時代を、掠奪者・軍人・冒険家ドレークを通して、活写する。
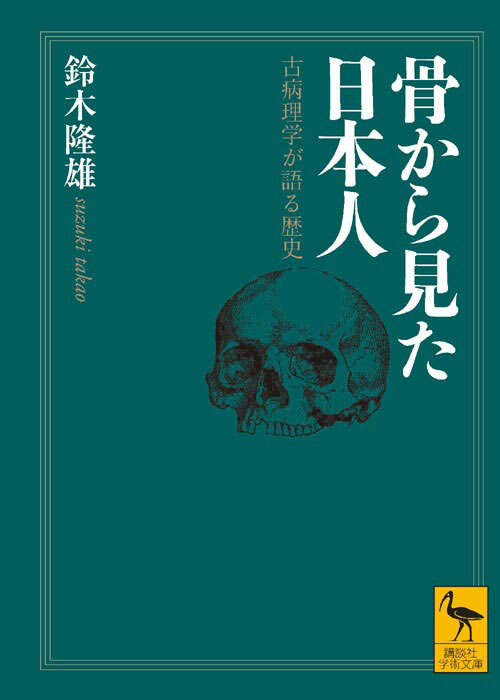
2014.10.24発売
骨から見た日本人 古病理学が語る歴史
講談社学術文庫
骨は情報の宝庫である。古病理学は古人骨を研究対象とし、現代の医学で診断し、その個体の病気の経過と症状を明らかにする。骨にあらわれたヒト化の道のり、縄文人の戦闘傷痕と障害者介護、弥生時代以降の結核流行、江戸時代に猖獗をきわめた梅毒と殿様のガン……。発掘された人骨を丹念に調べあげ、過去の社会構造と各時代の与件とを明らかにする。(講談社学術文庫)
歴史の襞に埋もれた骨が語るもう一つの歴史
縄文人の戦闘傷痕、古墳時代の結核流行、江戸時代に猖獗をきわめた梅毒……。
情報の宝庫である古人骨を丹念に調べ、過去の社会構造と時代の与件を明らかにする。

2014.10.24発売
中国人の機智 『世説新語』の世界
講談社学術文庫
諧謔性に富んだ反射神経、自負心の誇示、侮蔑への鮮やかな反撃……。一筋縄ではいかぬ誇り高き人々の不退転の反俗・反逆の精神を切れ味鋭い機智に乗せて演じきった舞台、それが『世説新語』の世界である。内乱、戦争、めまぐるしい王朝交替。暗く険悪な乱世を生き抜く魂は、悲哀、憂鬱を乗り越え、豪放洒脱な生き様は究極の言語表現を生み出した。(講談社学術文庫)
乱世に花咲いた嘲弄と逆襲
機智とは抗いつつ生きる者の武器である。後漢末(2世紀末)から東晋末(5世紀初め)。豪放洒脱な竹林の七賢が登場し、「清談」が大流行した時代。当意即妙、鋭い舌鋒……。命がけの言語表現に酔う。諧謔性に富んだ反射神経、自負心の誇示、侮蔑への鮮やかな反撃……。一筋縄ではいかぬ誇り高き人々の不退転の反俗・反逆の精神を切れ味鋭い機智に乗せて演じきった舞台、それが『世説新語』の世界である。内乱、戦争、めまぐるしい王朝交替。暗く険悪な乱世を生き抜く魂は、悲哀、憂鬱を乗り越え、豪放洒脱な生き様は究極の言語表現を生み出した。
王濛{もう}と劉諠倍たん}はつねづね蔡{さい}公に敬意をはらっていなかった。二人はあるとき蔡を訪問して語り合い、しばらくたってから、蔡にたずねていった。--あなたは自分で夷{い}甫{ほ}(王衍{えん})とくらべてみてどうだとお思いですか。
蔡はこたえた。--わたしは夷甫にかないません。王と劉は目くばせして笑いながらいった。--どの点でかなわないのですか。蔡はこたえた。--夷甫には君たちのような客がいない。(排調諠髏?)

2014.10.24発売
ことば遊び
講談社学術文庫
「世の中はすむと濁るの違いにて、刷毛に毛があり禿に毛が無し」。平安以来、歌詠みも、連歌作者も、俳諧の宗匠も、ことばの動き、その変わり身の様々な相を追求した。「回文」「早口ことば」「しゃれ」「地口」「なぞ」「解きと心」……。百花繚乱の言語遊戯を誇る日本語。ことばの可能性を極限まで発掘しようとする行為としてのことば遊びの歴史を辿る。(講談社学術文庫)
ゆたかなる日本語の世界へ
地口、尻取りことば、口合、回文、こせごと、なぞ……和歌の掛詞から、現代のなぞなぞまで、その変遷史を辿る。
「世の中はすむと濁るの違いにて、刷{は}毛{け}に毛があり禿に毛が無し」。平安以来、歌詠みも、連歌作者も、俳諧の宗匠も、ことばの動き、その変わり身の様々な相を追求した。「回文」「早口ことば」「しゃれ」「地口」「なぞ」「解きと心」……。百花繚乱の言語遊戯を誇る日本語。ことばの可能性を極限まで発掘しようとする行為としてのことば遊びの歴史を辿る。
ことばの機能の眠っている部分を揺り起こし、潜在していた変化の万華相と、その面白さ美しさを見付け出したという実績が、ことば遊びの歴史にはある(中略)しゃれを愛するのは、日本人の国民性であるといってよい。(中略)しゃれのわからぬ日本人は、ユーモアを解しないというだけでなく、風流の嗜{たしな}みに欠ける人間と考えられた。(本文より抜粋)

2014.10.24発売
シチリア・マフィアの世界
講談社学術文庫
「シチリア。道化芝居と悲劇が絶え間なく繰り返されるその人間の大スペクタクルをよりよく理解するには、マフィアをわかる必要がある」 シチリアの過酷な風土と圧政とが育んだマフィア。大土地所有制の下で、18世紀に台頭した農村ブルジョワ層は、暴力と脅迫でイタリア近・現代政治をも支配した。謎の組織の誕生と発展の歴史を辿る。(講談社学術文庫)
名誉、沈黙、暴力、犯罪。マフィアとは何か。シチリアの過酷な風土と圧政が育んだマフィア。18世紀に台頭する農村ブルジョワ層は、暴力と脅迫でイタリア近・現代政治を支配した。謎の組織の実像を解明する。

2014.10.24発売
最後のロシア皇帝ニコライ二世の日記
講談社学術文庫
帝政ロシア最後の皇帝となったニコライ二世。その生涯は歴史の流れの大転換を一身に体現するものであった。訪日の際の大津事件、日露戦争、第一次世界大戦への突入、革命の進行に伴う退位と抑留等、歴史的事件の渦中で彼は何を見、どう動いたのか。処刑の直前まで書き続けられた日記から、日常の政務、革命への態度、人間関係、日本観などを読み解く。(講談社学術文庫)
帝国の終焉に立ち会ってしまった男の生涯。1882年14歳の時から1918年銃殺される三日前まで書かれた日記。大津事件、日露戦争、二月革命などの大事件をどう見ていたのか。激動の時代が映される。

2014.10.24発売
北欧神話と伝説
講談社学術文庫
荒涼峻厳な世界で育まれた北の民の精神を語るエッダ、サガ、神話、伝説を読む。ヨーロッパ北部周縁の民=ゲルマン人は、キリスト教とは異なる独自の北方的世界観を有していた。古の神々と英雄を謳い伝える『エッダ』と『サガ』。善悪二元の対立抗争、馬への強い信仰、バイキングに受け継がれた復讐の義務……。荒涼にして寒貧な世界で育まれた峻厳偉大なる精神を描く伝説の魅力に迫る。北欧人の奥深い神話と信仰世界への入門書。

2014.10.24発売
学術都市アレクサンドリア
講談社学術文庫
プトレマイオスの庇護の下、ギリシアや東方の知を集めた思想・宗教・民族の坩堝。芸術・文学・科学の殿堂ムーセイオンや世界中の書物を集めた大図書館、さらに巨大な灯台がそびえ立つ地中海の中心都市。アレクサンドロス大王を継ぐプトレマイオス朝の「愛知」の志向はギリシア世界から東方から一流の知性を集め、学術の一大センターを築き上げた。古代における学問の隆盛を担い、やがて消えていった謎のヘレニズム都市の姿に迫る。
プトレマイオスの庇護の下、ギリシアや東方の知を集めた思想・宗教・民族の坩堝
芸術・文学・科学の殿堂ムーセイオンや世界中の書物を集めた大図書館、さらに巨大な灯台がそびえ立つ地中海の中心都市。アレクサンドロス大王を継ぐプトレマイオス朝の「愛知」の志向はギリシア世界から東方から一流の知性を集め、学術の一大センターを築き上げた。古代における学問の隆盛を担い、やがて消えていった謎のヘレニズム都市の姿に迫る。
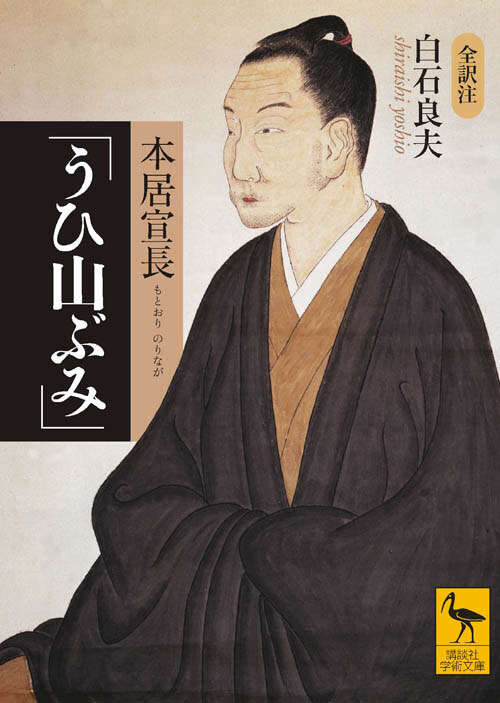
2014.10.24発売
本居宣長「うひ山ぶみ」
講談社学術文庫
師と仰ぐ賀茂真淵との生涯一度きりの対面=「松坂の夜」以来、刻苦勉励を重ねること35年。寛政10年(1798)、畢生の大作『古事記伝』を仕上げた宣長は、古学の入門書『うひ山ぶみ』を一気に書き上げた。古学の扱う範囲、学ぶ者の心構え、学問のあるべき姿、契沖に始まる近世古学の歴史的意味、古学の目的とその研究方法など、国学の大人(うし)が初学者に授けた学びの要諦とは?(講談社学術文庫)
国学の大偉人が弟子に教えた学問の要諦とは。「からごころ」を排して「やまとたましい」を堅持することで、真実の「いにしえの道」へと至ることが学問の道である。契沖に始まる国学の目的と方法を説く入門書。

2014.10.24発売
ことばとは何か 言語学という冒険
講談社学術文庫
時の流れや社会規範によって姿を変える「ことば」。地球上にある何千種類もの言語、変化を続けるとらえどころのない対象の本質に、言語学はどこまで迫れたのか。ソシュールをはじめとした近現代の言語学の成果を検証、理論では説明しきれない言語の特別な性質をさらけ出し、グローバリゼーションの中で現代世界が直面する言語問題にも鋭く切り込む。(講談社学術文庫)
言語学は「ことば」をどこまで理解したのか。人間と切り離せない「ことば」。その本質に言語学はどこまで迫れているのか。日本を代表する言語学者が、その成果と現代世界が直面する言語問題に鋭く切り込む。

2014.10.24発売
有田川
講談社文芸文庫
私は川上のどことも知れぬところで誰とも知れぬ親に産んでもらった――けれども人間はいずれ生れて川に流されるものではないのか。どんな人でも多かれ少なかれ水に流されながら生きて行くのではないのか――。有田川の氾濫のたびに出自を失いながら、流れ着いた先で新たな生を掴み取る紀州女、千代の数奇な生涯。『紀ノ川』『日高川』に並ぶ、有吉文学における紀州三部作。
私は川上のどことも知れぬところで誰とも知れぬ親に
産んでもらった――けれども人間はいずれ生れて
川に流されるものではないのか。どんな人でも多かれ少なかれ
水に流されながら生きて行くのではないのか――。
有田川の氾濫のたびに出自を失いながら、流れ着いた先で
新たな生を掴み取る紀州女、千代の数奇な生涯。
『紀ノ川』『日高川』に並ぶ、有吉文学における紀州三部作。

2014.10.24発売
思索の源泉としての鉄道
講談社現代新書
東日本大震災で起きた日本の鉄道史上未曾有の事態……それから3年半、断たれた鉄路はどうなっているのか? なぜ「あまちゃん」にはJRが映らなかったのか? 車窓に目をこらし、歴史に耳を澄ませ、日本を読み解く、唯一無二の“鉄”コラム集!
なぜ「あまちゃん」にはJRが映らなかったのか?
常磐線の断たれた鉄路はどうなっているか?
三陸鉄道が復興できて、JRが復興できない理由とは?
車窓に目をこらし、歴史に耳を澄ませ、日本を読み解く
唯一無二の「鉄」コラム集!
【目 次】
第1章 東日本大震災と鉄道
第2章 天皇・皇居と鉄道
第3章 沿線文化の起源
第4章 断たれた鉄路をゆく
第5章 鉄道をめぐる記憶と文学
第6章 乗客の横顔
第7章 鉄道復興の軌跡
第8章 海外の鉄道で考える
第9章 よみがえる「つばめ」「はと」

2014.10.24発売
デジタルは人間を奪うのか
講談社現代新書
健常者の記録を破る義足アスリートの出現、脳とコンピュータの接続、デジタル認知症……デジタルテクノロジーはわれわれをどこに連れていくのか。デジタルの第一線で活動する著者による、最新トピック満載の書。デジタルによって豊かな未来が創造されるはずだが、同時に忍び寄る「不気味さ」の正体とは何か。「デジタルの船からは、もはや降りられない」「モノのネット化で変わる生活」「ロボットに仕事を奪われる日」など。
脳とコンピュータの接続、デジタル認知症、健常者の記録を破る義足アスリート……デジタルテクノロジーはわれわれをどこに連れていくのか。最新トピック満載の書。
<本書の主な内容>
序章 デジタルの船からは、もはや降りられない
「ただ楽になっただけ」/とめどなき情報量爆発/「つながっていても孤独」という不可思議 ほか
第1章 デジタル社会の光と影
SNSが生む経済損失/携帯電話で脳腫瘍が増加する/評判を求め過ぎる子供たち/デジタル写真を撮影するほど記憶が薄れる/ソーシャルメディアが失言を誘発する/サイバー攻撃で死者が出る ほか
第2章 モノのネット化で変わる生活
あらゆるモノがネットとつながる社会/替え時を教えてくれる「おむつ」/ウェアラブルコンピュータの危険性/「コンピュテーショナル・ファッション」/グーグルとアップルが自動車産業を支配する? ほか
第3章 ロボットに仕事を奪われる日
『鉄腕アトム』はもはや夢物語ではない/躍進するロボット記者/コンピュータ小説家/人間の仕事の多くが消滅する
第4章 仮想と現実の境界線が溶ける
「仮想国家」は現実の国家になるか/「オープンガバメント」と個人/「インターネット政党」/就職人気ランキング1位は仮想企業/貨幣制度を揺さぶる仮想通貨 ほか
第5章 脳と肉体にデジタルが融合する未来
人間の脳を超えるコンピュータ/思考する人工知能/記憶の複製/夢の解読/人間の脳が戦場に?/発電装置になる心臓/眼球が人間とコンピュータをつなぐ/人工筋肉で人間に近づくロボット/デジタルとの共存共栄のために ほか
第6章「考える葦」であり続ける
ペンはキーボードよりも強し/ネット断食/アマゾンがリコメンデーションできないもの/ジョブズとカリグラフィー/「外部脳」の弊害/脳の活動のブレイクスルー/情報は知識でも思考でもない/教室を変えたデジタルの力/思考する努力 ほか
終章 デジタルは人間を奪うのか
『マトリックス』が現実化する未来/人工知能に恋をする/子育てとデジタル/スマートフォンに忠誠を誓う人間/紙の新聞の購読をやめない理由/デジタルの力でもかなわないもの/不気味さこそが可能性の証

2014.10.24発売
ヴァロワ朝 フランス王朝史2
講談社現代新書
カペー、ヴァロワ、ブルボンと続くフランス王朝の歴史を描けるのは、この人しかいない!ヴァロワ朝の歴史を描く待望の第2弾。イングランドとの百年戦争、イタリアへの夢、皇帝との確執、そして血みどろの宗教戦争……。相次ぐ戦争と金策の日々。歴代王の心労絶えない260年間は、後に続くブルボンの輝く絶対王政への長き助走期間だったか。
カペー、ヴァロワ、ブルボンと続くフランス王朝の歴史を描けるのは、
この人しかいない!
ヴァロワ朝の歴史を描く待望の第2弾。
ヴァロワ朝創設より始まったイングランドとの百年戦争、
国内有力諸侯との駆け引き。
イタリアへの夢、神聖ローマ帝国皇帝との確執、
そして血みどろの宗教戦争……。
相次ぐ戦争と金策の日々。
歴代王の心労絶えない260年間は、
後に続くブルボンの輝く絶対王政への長き助走期間だったか。
フランスを救え──。
百年戦争のときのジャンヌ・ダルクの叫びはフランス人の心を鼓舞したが……。
神のためには死ねる。しかしフランスのためには死ねるか?
ましてやフランス王のためには??
こうした中でも一歩一歩、王家の国造りは進む。