ブルーバックス作品一覧

ランニングする前に読む本 最短で結果を出す科学的トレーニング
ブルーバックス
本来、走ることは決して苦しい運動ではない。誰でも持っている「走る才能」を100%発揮するには、フォアフット着地で、ラクなペースで走ること。「スロージョギング」から始めれば、一流選手のスキルが簡単に習得できる。準備運動も筋トレもいらない、膝や心臓への負担もない。それでいて、消費カロリーはウォーキングの2倍!弱点を克服し、確実に結果を出す方法を徹底解説。初心者からサブスリーを狙う上級者まで。
運動生理学の研究から生まれた「走るための最強メソッド」が登場!
走ることは、本来、決して苦しい運動ではありません。
誰でも持っている「走る才能」を100%発揮するには、フォアフット着地で、ラクなペースで走ること。
「スロージョギング」から始めれば、一流ランナーと同等のスキルが簡単に習得できます。
準備運動も筋トレもいらない、膝や心臓への負担もない。
それでいて、消費カロリーはウォーキングの2倍。
初心者から、サブスリーを目指す上級者まで、ランナーの弱点を克服し、確実に結果を出す「科学的なノウハウ」を徹底解説。
今から始めても、3ヵ月でフルマラソンは完走できる!
運動生理学から導かれたもっとも身体にやさしい走り方「スロージョギング」とは?
あなたの「ランニングの常識」が変わる!
・苦しいペースで走ってはいけない
・かかとから着地してはいけない
・初心者でも厚底のシューズはNG
・準備運動は必要ない
・「走れる身体」を作るための筋トレは必要ない
・1分の細切れ運動でもOK
・膝が痛くならない、心臓に負担もかからない
・ウォーキングの2倍、カロリーが消費できる
・血圧・血糖値が低下、善玉コレステロール値上昇、脳が活性化
・何歳からでも始められる
■おもな内容
第0章 この本の効果的な使い方 ~ランナーの悩み、始める前の疑問を解消する
第1章 走るための基礎知識〈理論編〉~ウォーキングよりランニングがいい理由
第2章 走るための基礎知識〈実践編〉~スロージョギングが、マラソン完走・サブスリーへのいちばんの近道
第3章 ランニングとダイエット ~ランニングで効率よく痩せる、痩せて効率よく走る
第4章 ランニングの生理学 ~メカニズムを知れば、効果が上がる
第5章 マラソンへ向けたトレーニング ~フルマラソン完走、サブスリーを目指す
第6章 レースのコンディショニング ~レース直前からレース後の注意点
第7章 ランニングと健康 ~継続して走ることが身体にもたらす効果

人類と気候の10万年史 過去に何が起きたのか、これから何が起こるのか
ブルーバックス
福井県・水月湖に堆積する「年縞」。何万年も前の出来事を年輪のように1年刻みで記録した地層で、現在、年代測定の世界標準となっている。その年縞が明らかにしたのが、現代の温暖化を遥かにしのぐ「激変する気候」だった。人類は誕生から20万年、そのほとんどを現代とはまるで似ていない、気候激変の時代を生き延びてきたのだった。過去の詳細な記録から気候変動のメカニズムに迫り、人類史のスケールで現代を見つめ直します。
人類は、たいへんな時代を生きてきた! 驚きの地球気候史
福井県にある風光明媚な三方五湖のひとつ、水月湖に堆積する「年縞」。何万年も前の出来事を年輪のように1年刻みで記録した地層で、現在、年代測定の世界標準となっている。その水月湖の年縞が明らかにしたのが、現代の温暖化を遥かにしのぐ「激変する気候」だった。
人類は誕生してから20万年、そのほとんどを現代とはまるで似ていない、気候激変の時代を生き延びてきたのだった。過去の精密な記録から気候変動のメカニズムに迫り、人類史のスケールで現代を見つめなおします。
○氷期と間氷期が繰り返す中、人類誕生以来、その歴史の大半は氷期だった。
○現代の温暖化予想は100年で最大5℃の上昇だが、今から1万1600年前、わずか数年で7℃にも及ぶ温暖化が起きていた。
○東京がモスクワになるような、今より10℃も気温が低下した寒冷化の時代が繰り返し訪れていた。
○温暖化と寒冷化のあいだで、海面水位は100メートル以上も変動した。
○縄文人はなぜ豊かな暮らしを営めたのか。
○平均気温が毎年激しく変わるほどの異常気象が何百年も続く時代があった。
○農耕が1万年前に始まった本当の理由。
「年縞」とは?
年縞とは、堆積物が地層のように積み重なり縞模様を成しているもので、樹木の年輪に相当します。2012年、福井県にある風光明媚は三方五湖のひとつ「水月湖」の年縞が、世界の年代測定の基準=「標準時計」になりました。世界中の研究が、その年代特定で福井県水月湖の「年縞」を参照するようになったのです。この快挙を実現したプロジェクトを率いたのが著者です。
「プロローグ」より
水月湖では、地質時代に「何が」起きたかだけではなく、それが「いつ」だったのかを世界最高の精度で知ることができる。タイミングが正確に分かるということは、変化のスピードや伝播の経路が正確に分かるということでもある。(中略)水月湖の年縞堆積物から気候変動を読み解くプロジェクトはまだ進行中であり、今も続々と新しい知見が得られつつある。本書ではそれらの新しい発見のうち、とくに私たち自身の未来と関連の深いものについて、なるべく分かりやすく紹介してみようと思う。

素数はめぐる 循環小数で語る数論の世界
ブルーバックス
142857と、先頭の1を末尾に回した428571。2等分して足すと、どちらも答えは999!(142+857、428+571)428571の先頭の4を末尾に回した285714でも同じ現象が!(285+714=999)ぐるぐる回る“ダイヤル数”のふしぎを生み出すのが素数!?「1÷素数」が描き出す定理と法則を探訪する、初等整数論への新しいアプローチ!
「1÷素数」から見えてくる奥深い数の神秘。
シンプルな割り算から生まれる循環小数には、おどろきに満ちた数のふしぎがいっぱい!
背後にひそむ素数の性質をやさしく解き明かす、極上の数学ミステリー――。
142857と、先頭の1を末尾に回した428571。
2等分して足すと、どちらも答えは999!
(142+857、428+571)
428571の先頭の4を末尾に回した285714でも同じ現象が!
(285+714=999)
142857を3等分して足すと、こんどは99!
(14+28+57)
ぐるぐる回る“ダイヤル数”のふしぎを生み出すのが素数!?
簡単な四則演算で数の神秘を味わいながら、「1÷素数」が描き出す定理と法則を探訪する。
初等整数論への新しいアプローチ!

地学ノススメ 「日本列島のいま」を知るために
ブルーバックス
東日本大震災を境に、日本列島は「大地変動の時代」に入ってしまった! 複数のプレートがひしめく恐るべき地理的条件にあるこの国で生き延びるには、「地学」の知識が不可欠だ。しかし、高校での履修率は低く、多くの人の地学リテラシーは中学レベルで止まったままである。ご存じ「地学の伝道師」が、地学の「おもしろいところ」「ためになるところ」だけを一冊に詰め込んだ、すべての日本人に捧げるサバイバルのための地学入門。

ブルーバックス科学手帳 2017年度版
ブルーバックス
日々の生活にもっとサイエンスを! 宇宙図や数学公式が持ち歩ける。科学ファンのみなさんにおくる情報満載のスケジュール手帳です。

人工知能はいかにして強くなるのか? 対戦型AIで学ぶ基本のしくみ
ブルーバックス
AIが「学ぶ」とは、「考える」とは、「判断を下す」とはどんなことなのか。つまり、人工知能の思考構造がどうなっているのかを、基本から学びます。「深層学習とは何か」「画像認識の原理とは」「評価関数の意味」「完全解析の思考法」など、最新技術の核心にも触れていきます。さらに、囲碁のAlphaGo、チェスのDEEP BLUEなど、対戦型AIの進化を振り返ることからも、「人工知能(AI)とは何か」に迫ります。
2016年3月9日、Googleの研究部門が開発した囲碁プログラムAlphaGoが、李世石との5番勝負の第1局に勝ったという一報が流れました。人工知能(AI)が、囲碁においてはまだ人間に及ばないと考えられていた中での驚くべきニュースでした。
本書では、AIが「学ぶ」とはどんなことなのか。AIが「考える」とはどんなことなのか。AIが「判断を下す」とはどんなことなのか。つまり、人工知能の思考構造はどうなっているのかを基本からわかりやすく理解することができます。「深層学習とは何か」「画像認識の原理とは」「評価関数の意味」「完全解析の思考法」など、AIの最新技術の核心を学んでいきます。
また、囲碁のAlphaGo、チェスのDEEP BLUE、チェッカーのCHINOOKなど、人間と対戦してきた対戦型AIの進化を振り返ることからも、人工知能(AI)とは何か、そして人工知能はいかにして人間を超えて強くなってきたのかを見ていきます。
ますます進化を遂げ、人間を超えていく人工知能。そのしくみを基本から学べる一冊です。

日本列島100万年史 大地に刻まれた壮大な物語
ブルーバックス
伊豆半島衝突、富士山噴火、海に沈んだ東京・大阪・京都、消えた縄文文化、移動する琵琶湖、瀬戸内海をナウマンゾウが闊歩する──。1500万年前、ユーラシア大陸の東の端から分かれて生まれた日本列島。現在、私たちが目にする風景・地形も、時代をさかのぼると全く違った顔を表します。本書ではおもに100万年前以降を中心に、複雑な地形に富んだ列島の成り立ちを解き明かします。驚きに満ちた日本列島史!
伊豆半島衝突、富士山噴火、海に沈んだ東京・大阪・京都、消えた縄文文化、移動する琵琶湖、瀬戸内海をナウマンゾウが闊歩する──
日本列島はなぜ弓形をしているのか? 1500万年前、ユーラシア大陸の東の端から分かれて生まれた日本列島。現在、私たちが目にする風景・地形も、時代をさかのぼると全く違った顔を表します。本書ではおもに現代の列島を形作った100万年前以降(第四紀後半)を中心に、複雑な地形に富んだ列島の成り立ちを解き明かします。驚きに満ちた日本列島史。足下に広がるドラマチックワールドへようこそ!

カラー図解Excel「超」効率化マニュアル 面倒な入力作業を楽にする
ブルーバックス
Excelを使ううえで避けて通れない「データ入力作業」を早く正確に行える仕組みの作り方を解説します。VBAなどの高度な機能は使わずに、オートフィルや表示形式、データの入力規則、VLOOKUP関数、OFFSET関数、条件付き書式などの基本機能を上手に組み合わせ、日付や曜日、金額データの入力などの自動処理を実現。面倒なデータ入力作業の手間や時間、ミスを激減させ、作業効率を大幅にアップさせます。
「わかりやすい!」と好評をいただいている「入門者のExcel VBA」の著者が、あらゆる職場で欠かせないExcelのデータ入力作業を、早く正確に行える仕組みの作り方について、カラーで見やすい図を用いて丁寧に解説します。
「データ入力作業を効率的に行えるかどうかは入力する人次第」と考えがちですが、作業を行うExcel側の仕組みを整えることも重要です。Excelの機能を上手に組み合わせると、一部の入力を自動処理できるようになるなど、入力の手間を大幅に減らし、誰が作業しても(たとえデータ入力が苦手な人でも)早く正確にデータ入力を行えるようになります。
本書では、Excelが得意な部分はExcelの機能に頼り、入力する人の作業をできるだけ減らしていくことの有益さを、実例をとおして学ぶことができます。なお、VBAのような習得に時間のかかる機能は使いません。簡単な機能を適切に連携させるだけなので、週末に覚えて月曜から作業の現場にすぐ導入することも可能です。
「データ入力に時間がかかるし、入力後のチェックにも時間がかかる」という方や、「部下にデータ入力を依頼しているけど、正確に入力できているか心配」という方。本書で、入力ミスさせない仕組みの作り方を学んでみませんか。

カラー図解 進化の教科書 第2巻 進化の理論
ブルーバックス
進化は集団内にいかに広がるのか、あるいは消えてしまうのか? その鍵を握るのが「対立遺伝子」の存在だ。進化のメカニズムには大きく分けて、遺伝的浮動、自然淘汰、移動、そして突然変異の4つが関係している。ここでは、これらの要因がどのように進化、とりわけ対立遺伝子の振る舞いに関係しているかを数理モデルによって検証していく。
さらに自然淘汰による進化は、自然淘汰そのものが変化することが最近の研究から明らかになり、野生の個体群でも人為淘汰と同じくらい速く進化的変化が起こることが観察されているという。
進化にとって、無性生殖が有利か有性生殖が有利か? 性淘汰で繰り広げられる生物進化の物語から、あらためて人類がいまここに存在する意味を投げかける。

結果から原因を推理する 「超」入門 ベイズ統計
ブルーバックス
推理ストーリーを楽しむうちに、ベイズ統計のポイントが分かる! 近年注目を集める新しい統計学「ベイズ統計」。“原因の確率を結果から予測する”、それがベイズ統計のポイントです。この本では、ミステリー仕立ての愉快なストーリーを読みながら、「ベイズの定理」を中心に学んでいきます。ベイズ統計のはじめの一歩に最適です。
【推理ストーリーを楽しむうちに、
ベイズ統計のポイントが分かる!】
近年注目を集める新しい統計学「ベイズ統計」。
“原因の確率を結果から予測する”、
それがベイズ統計のポイントです。
この本では、ミステリー仕立ての
愉快なストーリーを読みながら、
「ベイズの定理」を中心に学んでいきます。
ベイズ統計のはじめの一歩に最適です。
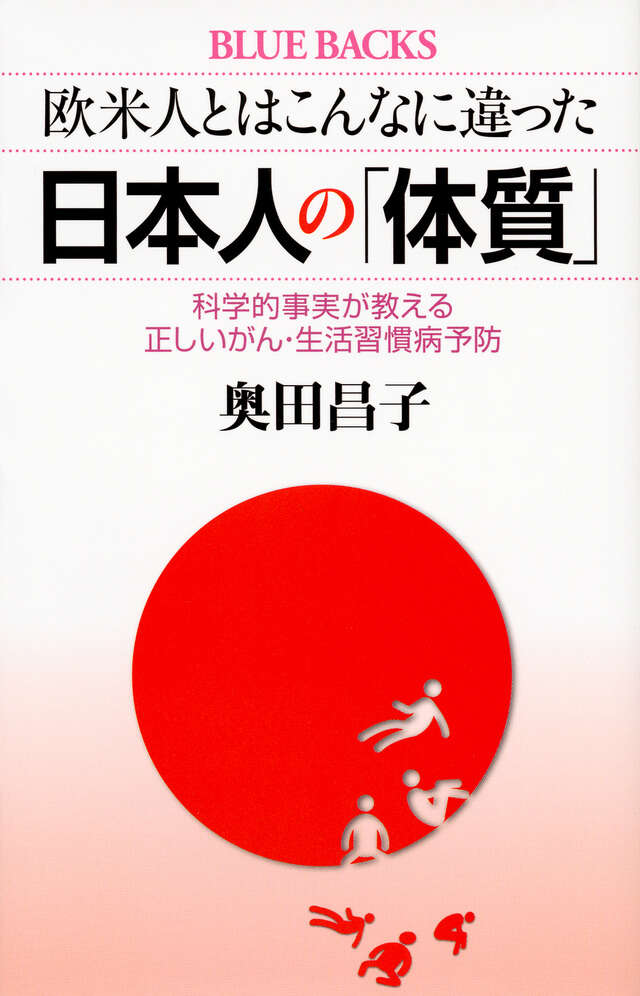
欧米人とはこんなに違った 日本人の「体質」 科学的事実が教える正しいがん・生活習慣病予防
ブルーバックス
日本人には、日本人のための病気予防法がある!同じ人間でも外見や言語が違うように、人種によって「体質」も異なります。そして、体質が違えば、病気のなりやすさや発症のしかたも変わることがわかってきています。欧米人と同じ健康法を取り入れても意味がなく、むしろ逆効果ということさえあるのです。見落とされがちだった「体の人種差」の視点から、日本人が病気にならないための方法を徹底解説!
日本人には、日本人のための病気予防法がある!
同じ人間であっても、外見や言語が違うように、人種によって「体質」も異なります。
そして、体質が違えば、病気のなりやすさや発症のしかたも変わることがわかってきています。
欧米人と同じ健康法を取り入れても意味がなく、むしろ、逆効果ということさえあるのです。
見落とされがちだった「体の人種差」の視点から、日本人が病気にならないための方法を、徹底解説!
・日本人は炭水化物を控えてはいけない
・日本人がオリーブオイルを摂りすぎると生活習慣病に
・筋トレをしても、日本人は“やせ体質”にはなれない
・血圧のために減塩すればいいとは限らない
・生活習慣が同じなら、日本人は欧米人より大腸がんになりやすい
・日本人は、欧米人より乳がんになりやすいタイプの乳房を持つ人が多い
・日本人が感染する東アジア型のピロリ菌は、欧米型のピロリ菌と違って胃がんを起こす力が強い
・日本人は、飲酒によって血圧が上がりやすく、すべてのがんの発症率も上がる
・・・・・・など、知られていなかった「日本人ならではの体質」の新常識が満載!

体の中の異物「毒」の科学 ふつうの食べものに含まれる危ない物質
ブルーバックス
ポテトチップに含まれる発がん物質。マーガリンを構成する不飽和脂肪酸。受動喫煙で浴びる活性酸素。野菜や漬け物に含まれる微量ミネラル……。ごくふつうの食生活から無数の毒性物質が取り込まれている!精妙な解毒システムで対抗する人体だが、時には自ら毒物を活性化してしまうことも。食の安全や健康の維持に不可欠な「毒」と「解毒」のサイエンス。
ヒトが口にするものは、すべて毒である――。
医薬品はもちろん、米でさえ毒性物質を含む。
生体が備える解毒システムはどう戦っているのか?
生体異物から見た生命のふしぎ。
ポテトチップに含まれる発がん物質。
マーガリンを構成する不飽和脂肪酸。
受動喫煙で浴びる活性酸素。
野菜や漬け物に含まれる微量ミネラル……。
ごくふつうの食生活から無数の毒性物質が取り込まれている!
精妙な解毒システムで対抗する人体だが、時には自ら毒物を活性化してしまう。
水や塩でさえ健康被害を及ぼしうる一方、ヒ素のような強毒が、少量であれば有用となることも。
食の安全や健康の維持に不可欠な「毒」と「解毒」のサイエンス。

活断層地震はどこまで予測できるか 日本列島で今起きていること
ブルーバックス
熊本、鳥取、福島沖──なぜ、大地震が頻発するのか? 地震の連鎖は「活動期」に入ったからなのか? 日本列島に走る活断層の数はなんと2000以上、次の地震を引き起こす「火種」は今もどこかでくすぶりつづけている──。活断層とは何か? 直下型地震はどうして起きるのか? 今知りたい疑問に答えます。
熊本、鳥取、福島沖──なぜ、大地震が頻発するのか?
活断層の動きが活発化する「地震の活動期」に入ったのか?
日本列島に走る活断層の数は2000以上。
活断層とは何か? 直下型地震はどうして起きるのか?
今知りたい疑問に答えます。
地震とは、地殻内にたまった歪みが断層を通じて一瞬のうちに解放される現象です。日本列島には、確認されているだけで2000以上の活断層が存在し、互いに複雑に影響しあっています。ひとたび地震が起きれば、その歪みが別の活断層へと伝播し、新たな地震へと連鎖する構造になっているのです。今もどこかで次の地震を引き起こす「火種」はくすぶりつづけている──これが私たちが住む日本列島なのです。次の地震はいつ、どこで起きるのか? 活断層と直下型地震のメカニズムと最新の研究成果を豊富な図と写真でわかりやすく解説します。
これからも容赦なく大地震は起こり続けます。建物は強くできても、地震を制御できるわけではありません。過密化した都市直下での内陸地震は、まだ阪神・淡路大震災以降経験していません。今後想定もしていない被害がもたらされる可能性があります。私の行ってきた活断層研究が地震の予測や防災・減災にすぐに役立つとは考えていませんが、地学現象のひとつとしての活断層を理解していただくことが、防災・減災にも遠回しに繋がるのではないかと考えています。(あとがきより)

チーズの科学 ミルクの力、発酵・熟成の神秘
ブルーバックス
ネズミが顔を出しそうな穴あきチーズ、学校給食が懐かしい三角形のチーズ、あなたは「チーズ」と聞いて何を思い出す? じつは人それぞれにイメージが違う変幻自在さこそが、地球の食品にほかにない、チーズならではの特徴なのです! その秘密は母から子へ与えるミルクの力にあります。そしてミルクを菌やカビの力で発酵・熟成させるという大発見を人間はなしとげました。文化と科学の両面から、この奥深い食べものに迫ります。
ネズミが顔を出しそうな穴あきチーズ、学校給食が懐かしい三角形のチーズ、あなたは「チーズ」と聞いて何を思い出す?
じつは人それぞれにイメージが違う変幻自在さこそが、地球上の食べものにほかにない、チーズならではの特徴なのです!
その秘密は、母から子へ与えるためにつくられた「ミルク」の力にあります。思わず唸る凄い力が、ミルクには満載されているのです。
そして人間は、そのミルクを菌やカビという小さな生きものたちの力を借りて「発酵」「熟成」させるという大発明をなしとげます。
ただでさえ凄いミルクが、息をのむほど神秘的なこれらの現象によって大変身をとげたチーズの絶妙さが、いま科学によって次々と解明されつつあります。
おいしい理由、身体にいい理由から世界のさまざまなチーズの薀蓄まで、この奥深い食べものの深淵に迫ります。

つながる脳科学 「心のしくみ」に迫る脳研究の最前線
ブルーバックス
ものごとを考え、記憶し、日々の出来事に感情を揺さぶられる……謎めいていた脳のはたらきが、明らかになりつつある。グリア細胞とニューロン、進化と可塑性、場所細胞と空間記憶、情動と消去学習、海馬と扁桃体とエングラムセオリー――頭の中には、さまざまな「つながり」があった!?9つの最新研究から、心を生み出す脳に迫る!
頭の中にある“人類最大の謎”に挑む
ものごとを考え、記憶し、日々の出来事に感情を揺さぶられる……
謎めいていた脳のはたらきが、明らかになりつつある。
グリア細胞とニューロン、進化と可塑性、場所細胞と空間記憶、情動と消去学習、海馬と扁桃体とエングラムセオリー――
頭の中には、さまざまな「つながり」があった!?
9つの最新研究から、心を生み出す脳に迫る!
―――――
第1章 記憶をつなげる脳
理化学研究所脳科学総合研究センター センター長 利根川進
第2章 脳と時空間のつながり
システム神経生理学研究チーム チームリーダー 藤澤茂義
第3章 ニューロンをつなぐ情報伝達
シナプス可塑性・回路制御研究チーム チームリーダー 合田裕紀子
第4章 外界とつながる脳
知覚神経回路機構研究チーム チームリーダー 風間北斗
第5章 数理モデルでつなげる脳の仕組み
神経適応理論研究チーム チームリーダー 豊泉太郎
第6章 脳と感情をつなげる神経回路
記憶神経回路研究チーム チームリーダー Joshua Johansen
第7章 脳研究をつなげる最新技術
細胞機能探索技術開発チーム チームリーダー 宮脇敦史
第8章 脳の病の治療につなげる
精神疾患動態研究チーム チームリーダー 加藤忠史
第9章 親子のつながりをつくる脳
親和性社会行動研究チーム チームリーダー 黒田公美

カラー図解 進化の教科書 第1巻 進化の歴史
ブルーバックス
ハーバード大学、プリンストン大学他全米の200校以上の大学で採用!
世界中でもっとも読まれている進化の教科書の決定版。
「我々はどこから来て、どこに向かうのか?」
生物の進化を理解することは、我々が向かうべき道を探索するもっとも知的で適応的な活動だ。生命の痕跡を求めて地を這い、生命の歴史を明らかにする。化石は何十億年の生態系を復元してくれる。生命はいつ、どのように誕生したのか?
色鮮やかな、臨場感あふれる38億年の旅がここからはじまる。
カール・ジンマーとダグラス・エムレンのテンポのよい語りで、進化の歴史から最先端の研究成果までをわかりやすく解説する。
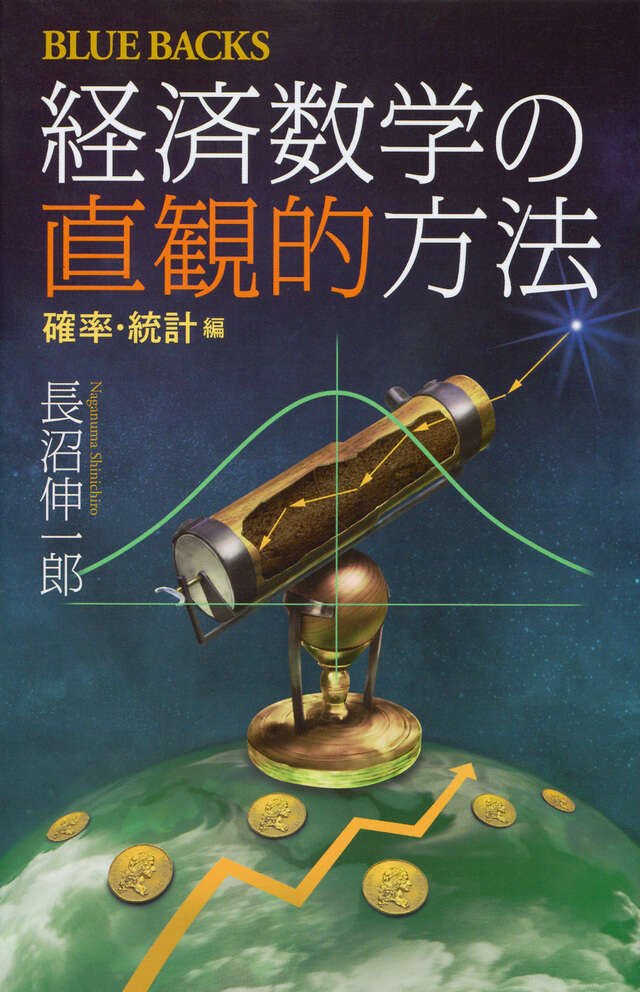
経済数学の直観的方法 確率・統計編
ブルーバックス
高度に発展した経済数学の本質を、70点に及ぶ図・グラフを中心に、直観的に理解していきます。本書では、「確率・統計編」として、正規分布曲線ができるメカニズムを学び、確率統計論で最も重要な原理とされる、中心極限定理の不思議に触れ、教養としてのブラック・ショールズ理論を身につけていきます。
現代社会を浮き彫りにする経済学。この経済学を表す経済数学は高度に発展してきました。なかでも、マクロ経済学の「動的マクロ均衡理論」と、金融工学の「ブラック・ショールズ理論」は「二大難解理論」として、その頂上をなしています。
この『経済数学の直観的方法』の2冊では、目標をこの「二大難解理論」にしぼっています。これらを直観的に理解してしまえば、そのツートップの頂上から経済数学全体を見渡す格好になり、今までのミクロ経済学などのたくさんの数学的メソッドを、余裕をもって見ることができるという狙いです。
本書では、「確率・統計編」として、現代の金融工学の礎となる「ブラック・ショールズ理論」を身につけます。70点に及ぶ図・グラフを中心に、「正規分布曲線が生まれるメカニズム」「標準偏差、分散の意味」「最小2乗法の基本思想」「中心極限理論の不思議」「確率過程とランダム・ウォーク」「ブラウン運動とブラック・ショールズ理論」「伊藤のレンマと確率微分方程式」「測度とルベーグ積分」など、重要テーマの本質的理解を試み、教養としてのブラック・ショールズ理論を身につけていきます。

入門者のLinux 素朴な疑問を解消しながら学ぶ
ブルーバックス
さまざまな事情からLinuxを使い始める(学び始める)人が増えています。そうしたLinux初心者がまず戸惑うのは、コマンドを使って操作する点ではないでしょうか。WindowsやMacならマウスを使う操作を、なぜコマンドで行うのか。本書では、実際に数々のコマンドを打ち込みながら、その理由を学んでいきます。本格的にLinuxを学び始める前に知っておくと便利なことを、さくっと読める一冊です。
本書は、Linuxを学ぼうとする人の多くが知りたいと思う「Linuxってどういうものなのだろか」を主なテーマに書かれたものです。
「進学や就職などの事情で、Linuxを使わねばならなくなった!」
「Raspberry PiでLinux系のOSを使い始め、コマンド操作に興味を持った!」
「WindowsやMacはある程度使えているから、今度はLinuxも使えるようになりたい!」
といった方々が、「Linuxらしい使い方」を心地よく理解できるように構成されています。
また、「Linux専門の厚めの入門書にチャレンジしようかと迷っている」といった方にとっては、気軽に読みやすい一冊です。
LinuxをLinuxらしく使うために、避けて通れないのがコマンドを使う操作です。コマンドを上手に使うことによって、多様で複雑・繊細な要求を、シンプル・柔軟にコンピュータに伝えることができます。本書では、実際に数々のコマンドを打ち込んで、その操作結果を確認しながら学習を進めていきます。コマンドは、シンプルなものから、ウェブカメラの画像を用いて動画を作成するといった少し複雑なものまで、単に暗記してもらうためではなく、Linuxの特徴を楽しみながら学べるものを選出。読み終える頃には、ご自身のLinuxへの理解が深まっていることを実感できます。
なお、本書に掲載しているコマンドは、Ubuntu 16.04 LTSとRaspbian(NOOBS v1.9.2とv1.9.3)で動作することを確認しています。またシェルはbashを前提としています。
できるだけ多くのLinux(やUnix)で動作するコマンドを掲載する方針で選定していますが、ここで紹介した以外の環境の場合、本書の内容と同じように動作しない可能性があります(掲載されている情報は2016年9月のものです)。

40歳からの「認知症予防」入門 リスクを最小限に抑える考え方と実践法
ブルーバックス
画像診断で萎縮が確認できる段階では、病状はすでに、深刻なレベルに到達している。脳内の病変や異常タンパク質の蓄積は、40歳から始まる。働き盛り世代からの予防策だけが、認知症の発症リスクを低下させる。食事や運動、人との交流や読書習慣など、何をどれくらい、どのように取り組めばいいのか。豊富な診察経験をもつ著者が、科学的エビデンスに基づく予防法を、やさしく詳しく解説する。
脳が縮み始める、その前に――。
画像診断で萎縮が確認できる段階では、病状はすでに、深刻なレベルに到達している。
脳内の病変や異常タンパク質の蓄積は、40歳から始まる。
働き盛り世代からの予防策だけが、認知症の発症リスクを低下させる。
食事や運動、人との交流や読書習慣など、何をどれくらい、どのように取り組めばいいのか。
高齢期の愛と性が、認知症に与える影響とは?
初代認知症サポート医の一人で、豊富な診察経験をもつ著者が、科学的エビデンスに基づく予防法を、やさしく詳しく解説する。

怖いくらい通じるカタカナ英語の法則 ネット対応版 ネイティブも認めた画期的発音術
ブルーバックス
すでに日本語の音にカスタマイズされてしまった私たち大人の脳にとって、残念ながらネイティブ発音を身につけるのは至難の業。脳科学者である著者もアメリカ留学時代、発音の習得に苦しみました。その経験から編み出したのが全く新しい「英語→カタカナ変換」の法則です。ネイティブスピーカーからも「これなら通じる」とお墨付き。脳のしくみに着目し、もっとも合理的にネイティブ発音に近づく画期的方法を音声つきで紹介します。
累計10万部突破、ネイティブも認めた「通じる発音」にガラリと変わる目からウロコの合理的メソッド。
すでに日本語の音にカスタマイズされてしまった私たち大人の脳にとって、残念ながらネイティブ発音を身につけるのは至難の業。脳科学者である著者もアメリカ留学時代、発音の習得に苦しみました。その経験から編み出したのが全く新しい「英語→カタカナ変換」の法則です。ネイティブスピーカーからも「これなら通じる」とお墨付き。脳のしくみに着目し、もっとも合理的にネイティブ発音に近づく画期的方法を音声つきで紹介します。
(著者からひと言)
初心者が英語で何かを伝えたい場面で、とくに気を付けなければならない点は、いかに文法が正しいかということや、いかに表現が適切かということよりも、いかに発音が“それっぽい”かという音の技術です。極言すれば「通じない英語は、下手な発音が原因である」とさえ言えるでしょう。
ここまで問題点が明確ならば、それに対する解答は簡単です。そうです。発音を修正すればよいのです。しかし、脳の成長の観点からは「外国語を正しく発音する能力は、一般に9歳を境に急激に低下する」といわれています。となれば、私たち大人に残された道はただ一つしかありません。そう、開き直ることです。
本書では、私がアメリカに留学した際に、試行錯誤の末に見出した13の発音法則を収録しました。この法則に基づいて適切なカタカナ読みをすれば、自分の言いたいことをネイティブに伝えることができるようになるはずです。
「べつにカタカナ英語だっていいじゃないか。理想を求めることは潔くあきらめよう。どうせ、私たちには発音するための脳回路がないのだから。」
少なくとも私は、こう開き直った瞬間、肩の荷が降りたように気分が楽になりました。本書が、英語学習で行き詰まりを覚えている方のお役に立てれば、著者としてもこの上ない幸せです。