ブルーバックス作品一覧

宇宙は「もつれ」でできている 「量子論最大の難問」はどう解き明かされたか
ブルーバックス
一人の天才の独創が生んだ相対論に対し、量子論は多数の物理学者たちの努力によって構築されてきた。その精緻化のプロセスで、彼らを最も悩ませた奇妙な現象=「量子もつれ」。因果律を破るようにみえる謎の量子状態は、どう理解されてきたのか。EPRパラドックス、隠れた変数、ベルの不等式……。当事者たちの論文や書簡、討論などを渉猟し、8年をかけて気鋭の科学ジャーナリストがリアルに再現した、物理学史上最大のドラマ。
アインシュタインが生涯信じなかった“幽霊現象”――。
最高の頭脳を翻弄した“量子の奇妙なふるまい”が、「宇宙観」に革命をもたらした!
量子力学100年の発展史を一気読み。
直観と論理の狭間で、物理学者がもがく!
一人の天才の独創によって誕生した相対論に対し、量子論は、多数の物理学者たちの努力によって構築されてきた。
数十年におよぶ精緻化のプロセスで、彼らを最も悩ませた奇妙な現象=「量子もつれ」。
たとえ100億km離れていても瞬時に情報が伝わる、すなわち、因果律を破るようにみえる謎の量子状態は、どんな論争を経て、理解されてきたのか。
EPRパラドックス、隠れた変数、ベルの不等式、局所性と非局所性、そして量子の実在をめぐる議論……。
当事者たちの論文や書簡、公の場での発言、討論などを渉猟し尽くし、8年の歳月をかけて気鋭の科学ジャーナリストがリアルに再現した、物理学史上最大のドラマ――。

重力波とはなにか 「時空のさざなみ」が拓く新たな宇宙論
ブルーバックス
2016年2月に大ニュースとなった重力波の初観測。それはいったいどんな意味をもつのか? 地球と太陽の間を「髪の毛の100万分の1」だけ伸び縮みさせるという小さな「時空のさざなみ」の観測が、なぜ人類にとって偉大な進歩なのか? 人類の究極の疑問である「宇宙のはじまり」を解き明かす鍵といわれる重力波の本質を、日本の重力波研究をリードする著者がやさしく、濃く、解説!
“ We did it ! ”(われわれはやりました!)
(2016年2月11日、記者会見に臨んだLIGOプロジェクトリーダー、デイヴィット・ライツェの第一声)
地球から太陽までの距離が、「水素原子1個分」伸び縮みするだけ――この絶望的に小さな波の観測に
人類は本気で挑みつづけ、アインシュタインの予言から100年で、ついに成功した!
いったいどうすれば、こんな小さな波が見つけられるのか?
その波によって、なぜ「宇宙のはじまり」が見えるのか?
本書では日本の重力波研究の第一人者が、こうした根本的な疑問にやさしく答えていくとともに、
「宇宙の地平線」を出た重力波が「凍りつく」とはどういうことか?
一般相対性理論は、重力波によってどのように検証されるのか?
といった、これからの宇宙論や重力理論における最先端の話題も、濃く、深く紹介していきます。
重力波発見の意義が本質からわかる、わが国初の一般向け解説書です。

ひとりで学べる電磁気学 大切なポイントを余さず理解
ブルーバックス
【電磁気学の理解が面白いほど深まる!】電磁気学の理解のためには数式ではなく、まず電場や磁場を「電気力線」「磁力線」によって、物理的なモノとして捉えることが大切です。「力線」の運動の法則、その集大成が電磁気学なのです。本書では、ファラデーによる「力線」の着想を軸に、現代物理につながるように電磁気学を説明します。スマートフォンやICカードなどの応用技術にも触れ、読めば電磁気学の全体像がよく分かります。
【電磁気学の理解が面白いほど深まる!】
電磁気学の理解のためには数式ではなく、
まず電場や磁場を「電気力線」「磁力線」によって、
物理的なモノとして捉えることが大切です。
「力線」の運動の法則、その集大成が電磁気学なのです。
本書では、ファラデーによる「力線」の着想を軸に、
現代物理につながるように電磁気学を説明します。
スマートフォンやICカードなどの応用技術にも触れ、
読めば電磁気学の全体像がよく分かります。

経済数学の直観的方法 マクロ経済学編
ブルーバックス
理系学生伝説の参考書『物理数学の直観的方法』の著者による、画期的な経済数学の入門書。理系と文系の中央位置から、双方を視野に入れる独自のアプローチで直観的な理解の道を拓いていきます。本書「マクロ経済学編」では、現代経済学の最重要理論であり「二大難解理論」の一方の「動学的マクロ均衡理論」を一気に理解することを可能にします。
理系学生伝説の参考書『物理数学の直観的方法』の著者による、画期的な経済数学の入門書。
現代の経済学は、物理学に基づく高度な数学を取り入れているため、難解なイメージがあります。本書では、理系と文系の中央位置から、双方を視野に入れる独自のアプローチを取っているため、直観的な理解の道を拓くことができます。
経済数学の二大難解理論である「動学的マクロ均衡理論」「ブラック・ショールズ理論」。この2つの理論の頂上部分を直観的に理解することで、今まで難物だった他のこまごまとした数学技法を、ちょうど一番高い2つの山からそれより低い山を見下ろす要領で、精神的に呑んでかかって楽に理解できるようにします。
本書「マクロ経済学編」では、二大難解理論の一方で、経済学の最重要理論である「動学的マクロ均衡理論」を一気に理解することを可能にします。
本書では、専門課程の学生のための本格的な数学的部分を後半部分に集中させることで、前半部分は一般読者でも読めるように工夫されています。そのため経済学部の学生が本書を数学の難所突破の特効薬として使うのはもちろん、一般読者の方々も、本書を数少ないこれらの一般向けの解説書として使うこともできます。
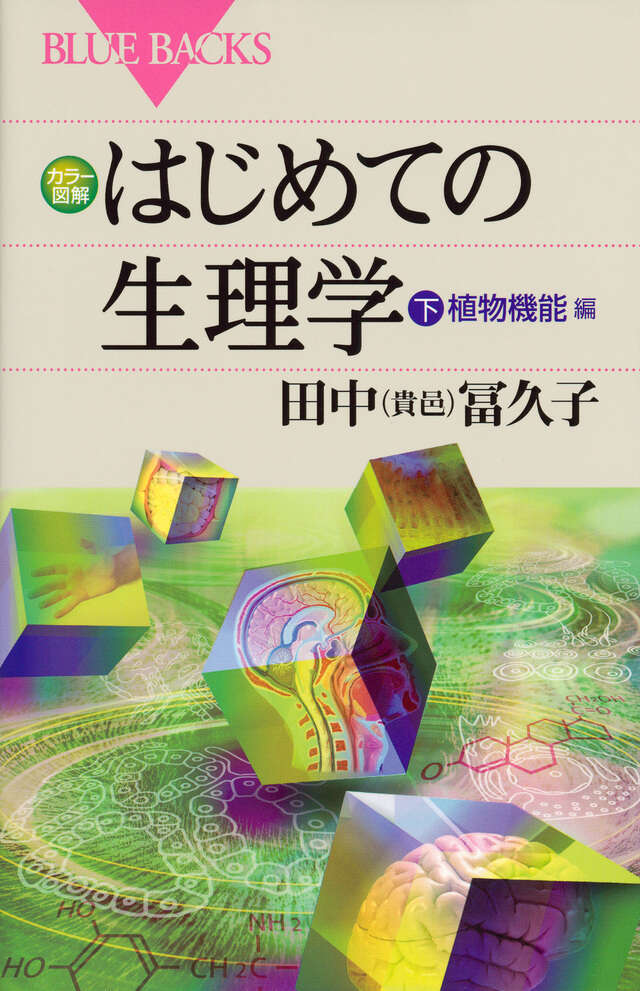
カラー図解 はじめての生理学 下 植物機能編
ブルーバックス
人間の生命現象である、脳・神経系の働き、骨格系と筋肉、呼吸器、循環器、消化、排泄、生殖の仕組み、さらには、それらを行っている膜の働き、物質輸送、シナプス伝送、電位の発生、興奮、制御など、人体のあらゆる生理の仕組みと働きを扱う科学分野を「生理学」と言います。下巻は「植物機能編」とし、内分泌系、循環系、呼吸器系、消化器系、泌尿器系、生殖器系、免疫系をカバーします。
人間の生命現象である、脳・神経系の働き、骨格系と筋肉、呼吸器、循環器、消化、排泄、生殖の仕組み、さらには、それらを行っている膜の働き、物質輸送、シナプス伝送、電位の発生、興奮、制御など、人体のあらゆる生理現象の仕組みと働きを扱う科学分野を「生理学」と言います。生理学は基礎医学の中心である同時に、私たち自身の驚嘆するほど精巧な「ミクロコスモス」の存在を教えてくれます。
本書では、生理学研究の第一人者の著者により、専門家でない一般の読者向けに、整理された分かりやすい生理学の入門書を目指しました。
下巻「植物性機能編」は、内分泌系、循環系、呼吸器系、消化器系、泌尿器系、生殖器系、免疫系をカバーします。

光と電磁気 ファラデーとマクスウェルが考えたこと 電場とは何か? 磁場とは何か?
ブルーバックス
電磁気学なくして、相対性理論は生まれなかった! 自然界のすべての力を説明する究極の理論への第一歩、電気と磁気の統一はどのように成し遂げられたのか。貧しく満足な教育を受けられなかったにもかかわらず、天性の実験センスで科学を切り拓いたファラデー。ケンブリッジ大卒のエリートで若くから数学に特別な才能を発揮したマクスウェル。対照的な二人の天才の共演によって、電磁気学が完成される過程をたどる。
電磁気学なくして、相対性理論は生まれなかった! 自然界のすべての力を説明する究極の理論への第一歩、電気と磁気の統一はどのように成し遂げられたのか。
貧しく満足な教育を受けられなかったにもかかわらず、天性の実験センスで科学を切り拓いたファラデー。大地主の跡取りでケンブリッジ大卒のエリート、若くから数学に特別な才能を発揮したマクスウェル。育った環境も、科学へのアプローチも対照的な二人の天才の共演によって、電磁気学が完成されていく過程をたどる。
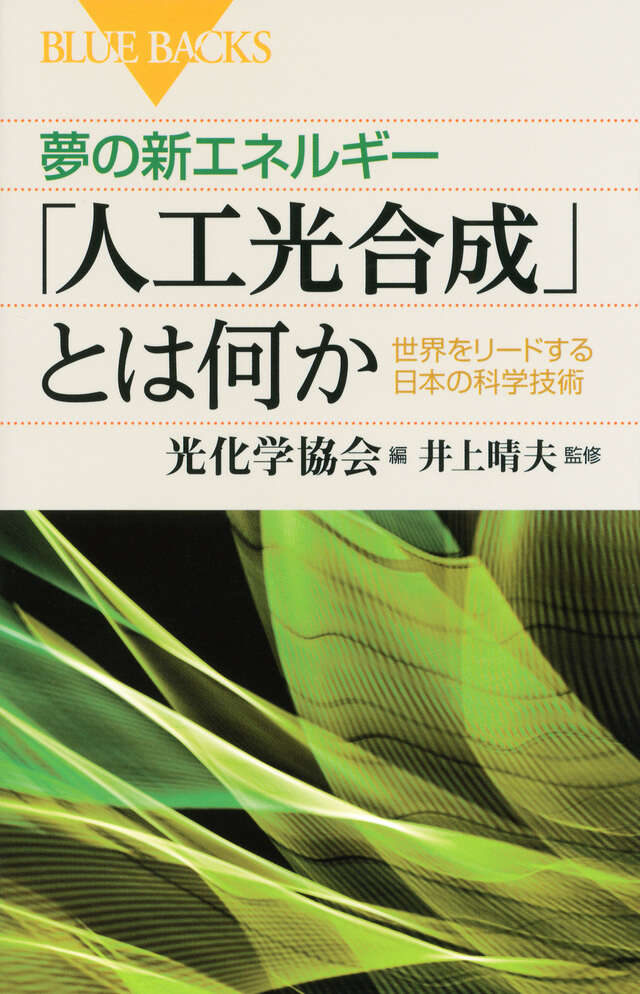
夢の新エネルギー「人工光合成」とは何か 世界をリードする日本の科学技術
ブルーバックス
「人工光合成」は太陽光エネルギーと水を原料にして、水素などの高エネルギー物質を創り出す技術です。温暖化の原因とされる二酸化炭素を抑え、再利用することで、環境にもやさしいエネルギーです。日本人が発明したこの技術こそ、地球のエネルギー問題を救えると世界中から注目されています。2050年の実用化をめざすプロジェクトの全容をわかりやすく解説します。
自然に学び、自然を超える
生物に必要な地球上の酸素とエネルギーは
植物や藻類が長い時間をかけて
「光合成」と呼ばれる太陽光を利用した
生化学反応によって蓄積されてきた。
近い将来直面するエネルギー問題はやはり、
太陽と水だけで高エネルギーを創り出し、
二酸化炭素を再利用するクリーンな
「人工光合成」に頼るしかないのか?!
生物の進化を支えてきた光合成のしくみから、
夢の新エネルギーを実現するための
要素技術までをわかりやすく解説する。
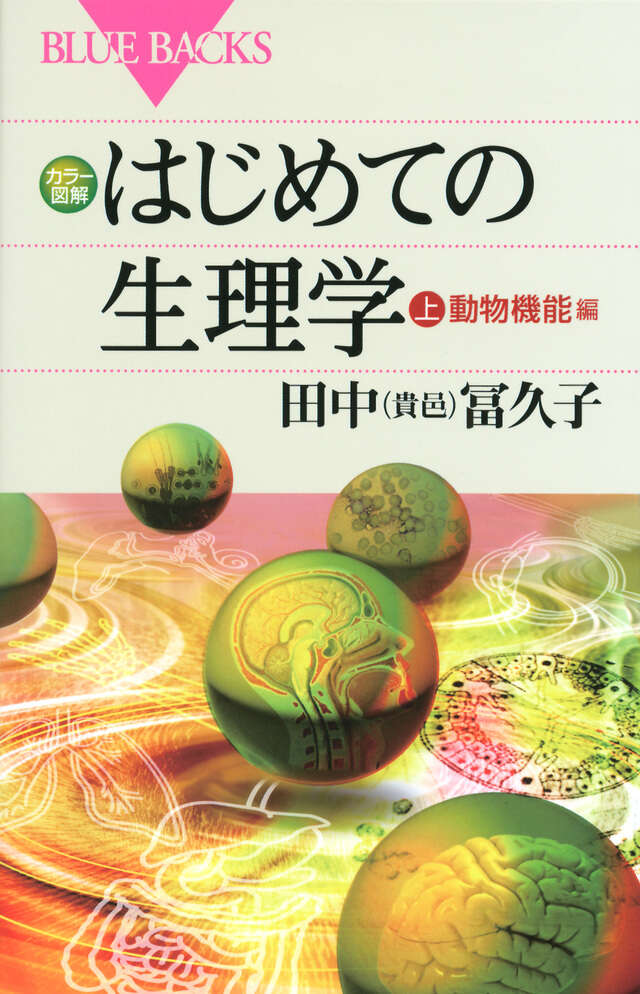
カラー図解 はじめての生理学 上 動物機能編
ブルーバックス
人間の生命現象である、脳・神経系の働き、骨格系と筋肉、呼吸器、循環器、消化、排泄、生殖の仕組み、さらには、それらを行っている膜の働き、物質輸送、シナプス伝送、電位の発生、興奮、制御など、人体のあらゆる生理の仕組みと働きを扱う科学分野を「生理学」と言います。上巻は「動物機能編」とし、感覚器、神経、運動器をカバーします。
人間の生命現象である、脳・神経系の働き、骨格系と筋肉、呼吸器、循環器、消化、排泄、生殖の仕組み、さらには、それらを行っている膜の働き、物質輸送、シナプス伝送、電位の発生、興奮、制御など、人体のあらゆる生理現象の仕組みと働きを扱う科学分野を「生理学」と言います。生理学は基礎医学の中心である同時に、私たち自身の驚嘆するほど精巧な「ミクロコスモス」の存在を教えてくれます。
本書では、生理学研究の第一人者の著者により、専門家でない一般の読者向けに、整理された分かりやすい生理学の入門書を目指しました。上巻は「動物機能編」とし、感覚器、神経、運動器を、下巻を「植物機能編」とし、血液循環、生殖、外分泌および内分泌機能をカバーします。

カラー図解 最新 Raspberry Piで学ぶ電子工作 作って動かしてしくみがわかる
ブルーバックス
丁寧な解説が好評の『Raspberry Piで学ぶ電子工作』が全ページカラーでリニューアル! 電子工作の超定番からスマホやタブレットと連携させる応用まで。さまざまな演習を通して話題のラズパイを使った電子工作をきっちり学べます。掲載内容は16年5月時点のもので、刊行後の更新情報をサポートページにて公開予定です。
2014年11月の刊行以来、ネットのレビューなどでご好評いただいている『Raspberry Piで学ぶ電子工作』が、全ページカラーでリニューアル! Raspberry Pi 3に完全対応し、2016年5月リリースのOS(NOOBS1.9.2)向けの操作解説を中心に、旧世代OS(NOOBS1.4.1)での操作を補足掲載。電子工作超初歩のLチカから、温度センサ、モーターなどを扱う基礎的な演習からスマホやタブレット端末と連携する演習まで、ラズパイならではの電子工作のいろはをきっちり学べます。
実際に回路を組む際に便利な回路図のPDFファイル、40ページを超える応用情報を掲載したPDFファイルはダウンロードしてご利用いただけます(応用情報PDFは、電子版では巻末に収録)。
・本書で対応するRaspberry Piの機種
Raspberry Pi Model B+、Raspberry Pi 2 Model B、Raspberry Pi 3 Model B
・対応するRaspbian(Raspberry Pi 用のOS)…… NOOBS v1.4.1またはv1.9.2
本書刊行後にリリースされる機種やOSへの対応については、サポートページにて公開していく予定です。
また、本書の演習で使うLEDや抵抗、ブレッドボード、モーターなどのパーツを集めたパーツセットを秋月電子通商さんにて販売中(通販&店舗)です。
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-10852/
(なお、秋月電子通商さん以外で販売される本書名を冠したパーツセットは公式のものではありません。それらのパーツセットには、本書の演習でのご利用が難しいパーツが含まれていることがあり得ますのでご注意ください。)

不妊治療を考えたら読む本 科学でわかる「妊娠への近道」
ブルーバックス
知っていますか? じつは日本は、世界でいちばん「妊娠できない不妊治療」が行われている国なのです。本書では、誰も教えてくれなかった「妊娠への近道」を解説します!「検査で異常なし=すぐ妊娠できる」は間違い/もっとも妊娠しやすいのは「排卵日2日前」/胚を凍結したほうが妊娠率があがる/「身体に優しい治療」は妊娠率が低い/治療施設が公開している高い妊娠率のカラクリ/費用や通院回数も詳しく解説
「このままで本当に妊娠できる?」
――3万人の疑問に答えた「妊活本 決定版」!
知っていますか?
体外受精の実施件数は世界一なのに、出産率は世界最低
――じつは日本は、世界でいちばん「妊娠できない不妊治療」が行われている国なのです。
治療をしても妊娠できないのはなぜなのか?
第1線の専門医と出産ジャーナリストが、科学的根拠のある「妊娠のコツ」を解説します。
不妊治療を始めようか迷っている人から、治療に行き詰まっている人までの必読書。
誰も教えてくれなかった「妊娠への近道」がわかります。
・限られた「時間」と「お金」の使い方が結果を左右する
・治療施設が公開している高い妊娠率のカラクリ
・「検査で異常なし=すぐ妊娠できる」は間違い
・「身体に優しい治療」は妊娠率が低い
・もっとも妊娠しやすいのは「排卵日2日前」
・胚を凍結したほうが妊娠率があがる
・顕微授精では、精子が1個しか得られなくても妊娠が可能
・大切なのは「自然な方法」ではなく「自分に合った方法」を見つけること
・卵子はたくさん採れても質は落ちない
・「卵子の在庫がわかる検査」は、結果がゼロでも妊娠できる
・「基礎体温計測」は超音波も血液検査もなかった昔の妊活
・「痛くない卵管造影検査」もある
・排卵誘発剤の副作用は、激減している
・費用や通院回数もよくわかる!
……最新研究からみた、妊娠するために「本当に必要なこと」とは?
第1章 不妊治療大国・日本の現実 --治療を受けても妊娠できない国だった?
第2章 命のはじまり --ここまでわかってきた卵子の世界
第3章 不妊検査の最新事情
第4章 一般不妊治療と卵巣刺激法
第5章 体外受精と顕微授精
第6章 胚の移植と凍結

マンガ 現代物理学を築いた巨人 ニールス・ボーアの量子論
ブルーバックス
「現在から振り返ると、ボーアの仕事はそれを受け継ぎ発展させた後輩たちの仕事の下に埋もれてしまったように感じる。だが、もっとも困難な過渡期の基礎的な仕事をボーアがなしとげたからこそ、その後のはなばなしい発展があったのである。…ひとつの新しい分野をきりひらいたボーアの模索のプロセスから学び、その業績を改めて見直すことは今、意義深いことだと思う」(「訳者あとがき」より)
1885年、デンマークに生まれ育ったボーアは
弟のハラルとともに高校に入ると天才振りを発揮。
大学を卒業後、放射能研究の第一人者ラザフォードに師事しつつ、
独自に思考を重ね、「ボーアの原子モデル」を考案し
1922年、ノーベル物理学賞を受賞。
ここに量子力学の扉が開かれます。
時を同じくして若きハイゼンベルク、パウリ、
シュレーディンガー、ディラックといった
天才物理学者が出現し、彼らとの議論を通して
現代の量子力学の基礎が築かれていきます。
アインシュタインと論争をくり返し、
ユダヤ人への弾圧から多くの研究者を援助し、
また軍拡競争を予見したりと、現代物理学を牽引した
科学者であり思想家であった偉人の生涯を解説。

海の教科書 波の不思議から海洋大循環まで
ブルーバックス
海のさまざまな現象を知ると、地球の素顔が見えてくる。海水はなぜ塩辛い? 波はどうして起きるのか? 親潮や黒潮はどこからやってくる? 熱帯で起こるエルニーニョ現象が、なぜ日本の気候に影響する? 数千年もかかって海水が地球をめぐる「海洋大循環」とは? あなたの知らない海の姿を、最新科学で徹底解説。目に見える海の現象から、目に見えない地球規模の活動まで、海をまるごと解説する、海洋学の入門書です。
身近なのに意外と知らない「海」を最新科学で解き明かす!
【海のさまざまな現象を知ると、地球の素顔が見えてくる】
海水はなぜ塩辛い?
波はどうして起きるのか?
月が潮の満ち引きを起こしているって本当?
親潮や黒潮はどこからやってくる?
熱帯で起こるエルニーニョ現象が、なぜ日本の気候に影響する?
数千年もかかって海水が地球をめぐる「海洋大循環」とは?
あなたの知らない海の姿を、最新科学で徹底解説。
目に見える海の現象から、目に見えない地球規模の活動まで、
海をまるごと解説する、海洋学の入門書です。

マンガ 「解析学」超入門 微分積分の本質を理解する
ブルーバックス
解析学の第一歩としての微分積分を、直感的なイラストで完全理解!解析学の最初の難所ε-δ(イプシロン・デルタ)論法を使った極限の定義から微分積分までじっくりと解説。言葉だけではわかりにくい、複雑な概念や考え方も、目からウロコのイラストですっきり理解。なぜこうなるのか、どんな意味があるのか、なっとくしながら学べる。
解析学の第一歩としての微分積分を、直感的なイラストで完全理解!
解析学の最初の難所ε-δ(イプシロン・デルタ)論法を使った極限の定義から微分積分までじっくりと解説。言葉だけではわかりにくい、複雑な概念や考え方も、目からウロコのイラストですっきり理解。なぜこうなるのか、どんな意味があるのか、なっとくしながら学べる。

「健康食品」ウソ・ホント 「効能・効果」の科学的根拠を検証する
ブルーバックス
「脂肪の吸収を抑え、排出を増加させる」トクホコーラ。「10分のジョギングと同じ消費カロリー効果がある」高濃度茶カテキン飲料。「腸内フローラを良好にし、便通を改善する」ビフィズス菌配合サプリメント。国の制度によって「効能・効果」を大々的にアピールするトクホや機能性表示食品などの「保健機能食品」。“根拠”とされる論文を解読してわかった驚きの実態とは?
トクホ誕生から25年、機能性表示食品の登場から1年。
その“科学的根拠”、信じていいですか?
・コラーゲンが潤すのは「お肌ではなく喉」だった
・ふつうの豆乳とトクホ豆乳の中身はまったく同じ
・「体脂肪を減らす」お茶で体重が増えた
・「内臓脂肪面積を減らす」ヨーグルトで体脂肪率が上昇した
・血糖値が上がりにくい人は「食後血糖値を抑える」青汁で血糖値がむしろ増加した
(本文は実名表記です)
論文を読み解き、メーカーに問いただしてわかった、
「効果の限界」と「隠されていた不都合な真実」――。
それでも、買いますか?
誇張された宣伝文句を“誤読”しないためのヒントも満載。

へんな星たち 天体物理学が挑んだ10の恒星
ブルーバックス
夜空に瞬く恒星は、どれも小さな点にしか見えない。だがじつは、どいつもこいつもとんでもない!星とは思えぬ異様な姿、奇想天外なふるまい……はるか遠くの彼らの想像を絶する「生きざま」が、いま観測技術と天体物理学の進歩によって、少しずつ明らかになってきている。恒星研究のプロフェッショナル厳選、10個のへんな星たちに驚き笑い呆れながら、星の物理を学べる本。
夜空に瞬く恒星は、どれも小さな点にしか見えない。
だがじつは、どいつもこいつもとんでもない!
星とは思えぬ異様な姿、奇想天外なふるまい……
はるか遠くの彼らの想像を絶する「生きざま」が、
いま観測技術と天体物理学の進歩によって、
少しずつ明らかになってきている。
恒星研究のプロフェッショナル厳選、
10個のへんな星たちに驚き笑い呆れながら、
星の物理を学べる本。
宇宙には、こんな星たちが実在している!
★フィギュアスケートの選手みたいにイナバウアーしている
☆恒星のくせにバカバカしいほど長い尾を引きずっている
★墨を吐いて自分の姿をくらますタコなやつ
☆蚊取り線香みたいなやつ
★遠距離恋愛のカップルが久しぶりに会ったような盛り上がりのペア
☆盛り上がりすぎてついにくっついてしまったペア
★世界中の天文学者が推理バトルを繰り広げた謎の幽霊星 ほか

高校数学でわかる光とレンズ 光の性質から、幾何光学、波動光学の核心まで
ブルーバックス
本書では主に、光を光線として扱う幾何光学と呼ばれる分野を解説し、特にレンズの働きを明らかにします。光学機器として、現代において大活躍しているカメラやメガネ、そして望遠鏡、顕微鏡、それらのレンズに関する物理を基礎から解説していきます。高校数学の知識を身に着けていれば、現代光学の知識をひとつひとつ確実に理解していくことができます。定評のある「高校数学でわかる」シリーズの記念すべき10作目!!
私たちの周りには「光」が満ち溢れています。
その光によって、私たちは周りの世界を見ることができます。
そして、レンズを使ったさまざまな光学機器の発明により、私たちが見ることのできる世界は、はてしなく広がりました。
本書では主に、光を光線として扱う幾何光学と呼ばれる分野を解説し、特にレンズの働きを明らかにします。光学機器としては、カメラやメガネ、そして望遠鏡、顕微鏡が大活躍しています。この光学機器のレンズに関する物理を基礎から解説していきます。
本書は、大学の学部レベルの光学の基礎的な知識と体系を、高校数学の知識を身に着けていれば理解できるように工夫してあります。大学で光学を学び始めたばかりの学生のみなさんや、大学の光学をはやくのぞいてみたい高校生のみなさん、そして少し本格的に光学を勉強してみたいと思っている社会人のみなさんのお役に立てるものになっています。
「カメラのF値ってなに?」「写真を撮るとき、背景をぼかすしくみは?」「望遠鏡は上下が逆に見えるけど、双眼鏡はさかさまにならない」「顕微鏡の対物レンズ、接眼レンズって?」など、科学ファンのみならず、シャッターチャンスを狙うカメラファン、夜空を楽しむ天体ファン、顕微鏡をのぞく生物ファンの好奇心にも応えます。
定評のある「高校数学でわかる」シリーズの記念すべき10作目!!
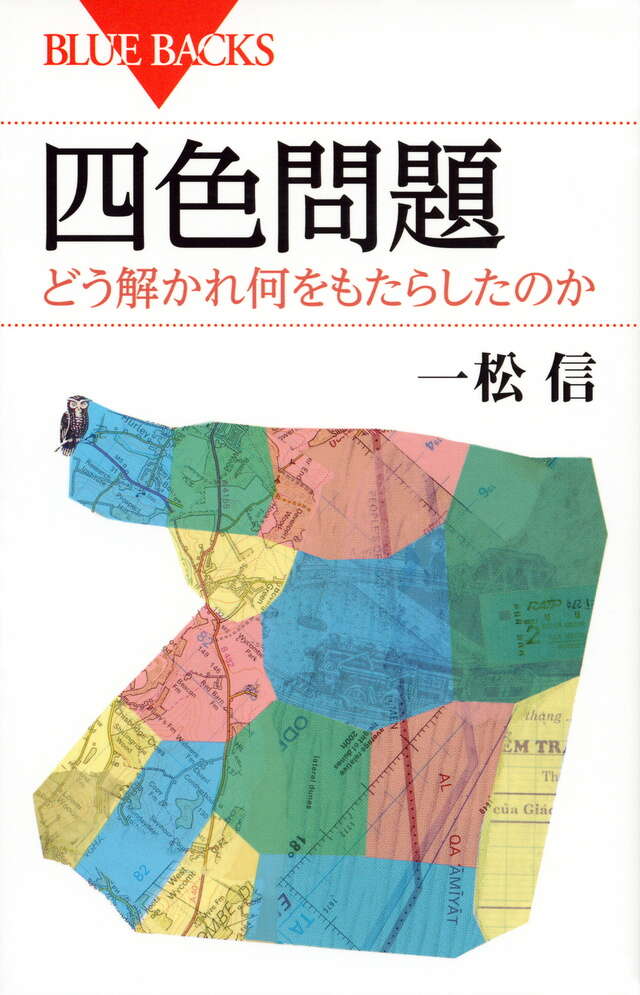
四色問題 どう解かれ何をもたらしたのか
ブルーバックス
埋もれたままの古典的な数学の未解決問題はもはや人工知能に任せるしかないのか?! 物議をよんだ未解決問題は「解決した」と言えるのか? 現代の視点から再考する。
数学的証明とは何か
数学の未解決問題として有名だった四色問題――
平面上の地図は四色で塗り分けられる――は、
1976年の夏、イリノイ大学の二人の数学者、
K・アッペルとW・ハーケンによって解決された。
しかし、それは計算機による膨大な検証という、
従来の数学の証明法とは全く異なるものだった。
四色問題の誕生から最終的解決にいたるまでの
先人たちの苦闘の歴史を踏まえ、
計算機に依存した現代の数学的証明の意義を
あらためて考える

脳・心・人工知能 数理で脳を解き明かす
ブルーバックス
数理で「脳」と「心」がここまでわかった!囲碁や将棋で、AIが人間に勝利を遂げた。2045年、人工知能が人間の能力を超える「シンギュラリティ」は、本当に訪れるのか?数学の理論で脳の仕組みを解き明かせれば、ロボットが心を持つことも可能になるのだろうか?AI研究の基礎となった「数理脳科学」の第一人者が語る、不思議で魅惑的な脳の世界。
数理で「脳」と「心」がここまでわかった!
囲碁や将棋で、AIが人間に勝利を遂げた。
2045年、人工知能が人間の能力を超える「シンギュラリティ」は、本当に訪れるのか?
数学の理論で脳の仕組みを解き明かせれば、ロボットが心を持つことも可能になるのだろうか?
AI研究の基礎となった「数理脳科学」の第一人者が語る、不思議で魅惑的な脳の世界。
第1章 脳を宇宙誌からみよう
まずは脳がいつどのように誕生したかをみていこう。その起源をたどるには、宇宙のはじまりを知らなくてはならない。生命が脳を持ち、人に「心」が宿ったのはなぜなのだろう。
第2章 脳とはなんだろう
私たちの脳には1000 億もの神経細胞が詰まっていて、それが思考を担い、心を司っている。そもそも脳とは、どのような器官なのだろうか。最新研究で明らかになってきた脳のメカニズムを紹介しよう。
第3章 「理論」で脳はどう考えられてきたのか
現在ブームとなっている人工知能は、脳にヒントを得て1950 年代に提唱された理論モデルから誕生した。「理論」で脳の仕組みを考えるとは、どういうことなのか。その歴史をたどってみよう。
第4章 数理で脳を紐解く(1):神経興奮の力学と情報処理のしくみ
数学の理論を使って脳の仕組みを考えるのが「数理脳科学」である。本当にそんなことができるのか、数理の世界を披露したい。神経回路はどのように興奮し、記憶はどうやって蓄えられるのだろうか?
第5章 数理で脳を紐解く(2):「神経学習」の理論とは
数理の視点から、脳がどのように学習するのかを考えてみよう。これは、最近注目を集めている人工知能の「ディープラーニング」の基礎になっている理論である。
第6章 人工知能の歴史とこれから
技術がさらに発展すれば、人工知能が人間を超える「シンギュラリティ」が本当にやってくるのではと騒がれている。その歴史を振り返り、未来を考えてみたい。
第7章 心に迫ろう
これまでみてきたように、脳の仕組みが次第に明らかになってきている。だが、脳科学の最終的な目標は「心」を知ることである。それが叶えば、心を持つ人工知能が誕生する日も訪れるのだろうか?

細胞の中の分子生物学 最新・生命科学入門
ブルーバックス
今やさまざまな生命現象が細胞・分子レベルで解明され、生命の本質への理解が格段に深まっています。生命活動の基本は、DNAの暗号を解読してタンパク質を正しく作りつづけること。これが私たちの体のすみずみの、細胞ひとつひとつで24時間休みなく行われることによって、生命が維持されているのです。その要となる仕組みを解明した日本を代表する世界的研究者が、細胞内で働く巧妙なメカニズムをやさしくひもときます。
私たちの細胞内で休みなく働きつづける、生命を紡ぐ絶妙なメカニズム──。
世界的研究者による、京大名物講義をもとにした最新の生命科学入門!
今やさまざまな生命現象が細胞・分子レベルで解明され、生命の本質への理解が格段に深まっています。生命活動の基本は、DNAの暗号を解読し、タンパク質を正しく作りつづけること。これが私たちの体のすみずみの、細胞ひとつひとつで24時間休みなく行われることによって、生命が維持されているのです。その過程には、何段階ものステップがあり、そのたびにエラーを訂正する巧妙な機能が組み込まれています。
本書では、細胞内で繰り広げられる生命現象を、基本からやさしくひもときながら、最後は現在もっともホットな分野である「タンパク質の品質管理メカニズム」=「小胞体ストレス応答」研究の最先端を紹介します。
小胞体ストレス応答とはまだ一般には耳慣れない言葉ですが、生命の基盤としてタンパク質合成の要となり、糖尿病、アルツハイマー、動脈硬化、がんなど、さまざまな病気に関与しているとして世界中から注目を集めています。著者は、その仕組みを解明し、ノーベル賞の前哨戦と言われる数ある国際的な科学賞を総なめにした日本を代表する研究者。その著者が、10年以上にわたって磨きをかけてきた京都大学の名物講義をもとに書き下ろした、生命科学入門の決定版です。

世の中の真実がわかる「確率」入門 偶然を味方につける数学的思考力
ブルーバックス
確率だらけの人生を、知的に楽しくサバイバル! 生命保険のカラクリ、「大地震が起きる確率」、株の値動き、スマホゲームの「ガチャ」、視聴率や内閣支持率などなど……。「確率」を通して考えると、世の中のさまざまな真実が見えてきます。本書では、順列・組合せの基礎からベイズの定理まで、直感を裏切る「確率」の世界を数学の正しい考え方で読み解いていきます。偶然と必然を見極め、人生を渡る基礎力が身につきます!
「30年以内に大地震が起こる確率90%」なら
1年以内は3%……は間違い!!
――数学的に正しく判断し、賢く行動する――
【確率だらけの人生を、知的に楽しくサバイバル!】
平均寿命、生命保険のカラクリ、「大地震が起きる確率」、
株の値動き、視聴率や内閣支持率などなど……。
「確率」を通して考えると、
世の中のさまざまな真実が見えてきます。
本書では、順列・組合せの基礎からベイズの定理まで、
直感を裏切る「確率」の世界を
数学の正しい考え方で読み解いていきます。
偶然と必然を見極め、人生を渡る基礎力が身につきます!
【世の中のカラクリを、「確率」で楽しく読み解く!】
・120歳まで長生きできる確率はいくら?
・生命保険会社は絶対に損をしないのか?
・スマホゲームの「ガチャ」を無理なく楽しむには?
・同業各社のシェアは確率で予測できる?
・「大地震が起きる確率」を正しく怖がれるか?