ブルーバックス作品一覧

最新 ウイスキーの科学 熟成の香味を生む驚きのプロセス
ブルーバックス
大好評『ウイスキーの科学』から8年、「ハイボール」「マッサン」のブームに沸いたジャパニーズウイスキーは、いま世界でトップランクの評価を得ている。そのまろやかな香味が「熟成」によって生まれるまでに「樽」という小宇宙の中では何が起きているのか? 人智の及ばない摩訶不思議な現象に、人智の限りを尽くして挑んだ研究の最新成果を満載して贈る、知れば知るほど旨くなるウイスキーの香りと味の科学!
世界の五大ウイスキーの中で、いまトップランクの評価を得ているのがジャパニーズ、すなわち日本産ウイスキーだ。その大きな理由は「まろやかさ」にあるとされるが、ではウイスキーの「まろやかさ」とは何だろうか。この問いに答えることは、簡単ではない。
全工程の99%の期間を占める貯蔵によって、ウイスキーの香味はどう変化するのか?
そのとき、樽の中で起きている「熟成」という人智を超えた現象を、科学はどこまで解明できたのか?
そして、「酒の味」に人が甘さ、旨さ、まろやかさを感じる意外なしくみとは?
好評既刊『ウイスキーの科学』から8年、「ハイボール」「マッサン」のブームやジャパニーズの高評価によってウイスキーをめぐる状況は一変し、「まろやかさ」の謎を追い求める研究も進歩した。前作に新たな成果を大幅に採り入れて改訂し、今宵のオン・ザ・ロックにさらに知的な味わいを加える最新の「ウイスキーの科学」。
第1部 ウイスキーのプロフィール
第1章 それは偶然から始まった
第2章 世界のウイスキー群像
第3章 ウイスキーができるまで
第2部 ウイスキーの少年時代
第4章 麦芽の科学
第5章 仕込みの科学
第6章 発酵の科学
第7章 蒸留の科学
第8章 樽の科学
第9章 貯蔵の科学
第3部 熟成の科学
第10章 「香り」の構造
第11章 樽は溶けている
第12章 「味」に関する考察
第13章 「多様さ」の謎を追う
第14章 「まろやか」になる理由
第15章 ウイスキーは考えている

方程式のガロア群 深遠な解の仕組みを理解する
ブルーバックス
19世紀前半、フランスの天才数学者エヴァリスト・ガロアが方程式に関して行った考察は、その後の数学や物理学の発展に重要な役割を占めることになりました。方程式の解の関係性を表すガロア群。具体的な方程式のガロア群を計算することで、複雑に見えていた解の構造が浮かび上がります。
そもそも、「方程式を解く」とは、どのようなことだろうか。そして、方程式を「代数的に解く」とは、どのように解くことなのだろうか。2次方程式の公式のようなものは、3次方程式、4次方程式、5次方程式……と、どんな場合でも作れるのか。その答えのカギとなるのが、数学者・ガロアのアイディアだ!
特別なタイプの2項方程式や、円の分割を定める円周等分方程式などの具体例から、ガロアには見えていた不思議な仕組みや、振る舞い方が明らかになっていきます。
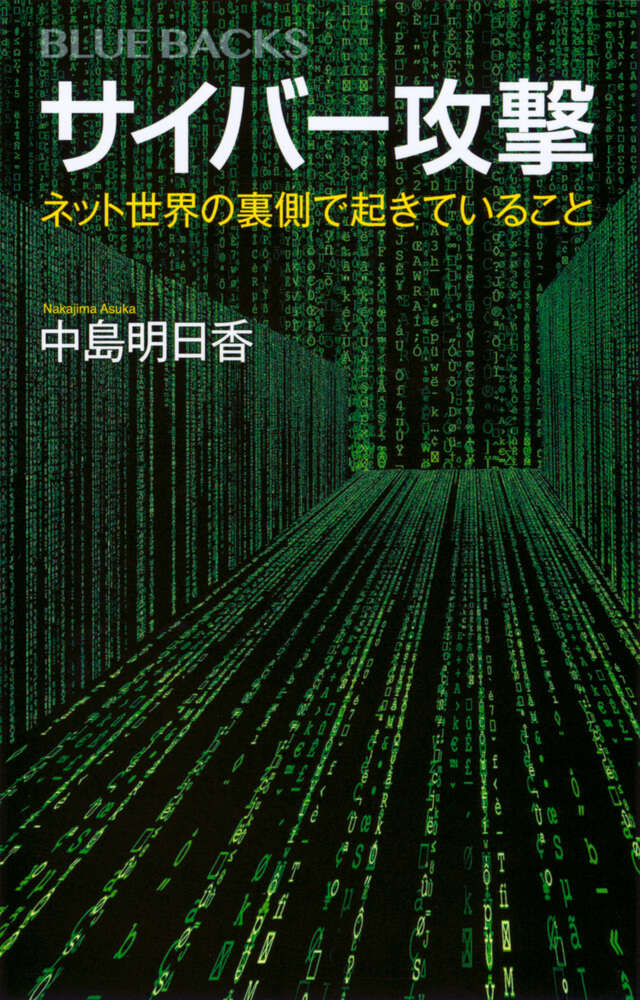
サイバー攻撃 ネット世界の裏側で起きていること
ブルーバックス
サイバー攻撃から身を守るには、攻撃者の手口を知る必要がある。サイバー攻撃の足がかりとなるソフトウェアの「脆弱性」は、なぜ生まれてしまうのか? 脆弱性はどのように悪用されるのか? 脆弱性が発見されると、誰がどんな対応をとるのか? さまざまな事例を使い、情報セキュリティの舞台裏で繰り広げられる攻防戦を解説する。さらに、脆弱性情報が売買される巨大市場や、すでに起きているサイバー戦争を紹介する。
村井純氏(慶應義塾大学環境情報学部 教授) 推薦!
「インターネットを前提としたデジタル文明が開化した。
テクノロジーは善用するのが前提だけど悪用する奴もいる。
セキュリティ研究の先端研究に携わる著者がネットのリスクについて丁寧に解説する。
すべての人に読んでもらいたい。」
サイバー攻撃から身を守るには、攻撃者の手口を知る必要がある。気鋭の研究者による、情報セキュリティの超入門書!
サイバー攻撃の足がかりとなるソフトウェアの「脆弱性」は、なぜ生まれてしまうのか? 脆弱性はどのように悪用されるのか? 脆弱性が発見されると、誰がどんな対応をとるのか? さまざまな事例を使い、情報セキュリティの舞台裏で繰り広げられる攻防戦を解説する。さらに、脆弱性情報が売買される巨大市場や、すでに起きているサイバー戦争を紹介する。
【おもな内容】
第1章 サイバー攻撃で悪用される「脆弱性」とは何か
第2章 サイバー攻撃は防げるか:脆弱性の発見・管理・修正
第3章 プログラムの制御はいかにして乗っ取られるか:バッファオーバーフローの脆弱性
第4章 文字列の整形機能はいかにして攻撃に悪用されるか:書式指定文字列の脆弱性
第5章 いかにしてWebサイトに悪意あるコードが埋め込まれるか:クロスサイト・スクリプティングの脆弱性
第6章 機密情報はいかにして盗まれるか:SQLインジェクションの脆弱性
第7章 脆弱性と社会:脆弱性市場からサイバー戦争まで

日本の伝統 発酵の科学 微生物が生み出す「旨さ」の秘密
ブルーバックス
味噌、醤油、納豆、清酒、酢、漬物、鰹節──。微生物を巧みに使いこなし、豊かな発酵文化を築いてきた日本。室町時代にはすでに麹菌を造る「種麹屋」が存在し、発酵の技術は古来から職人技として受け継がれてきました。多様な発酵食品の歴史をたどりながら、現代科学の視点からも理にかなった伝統の技を紹介、和食文化を支える世界に類を見ない多彩な発酵食品、その奥深い世界へと読者を誘います。
味噌、醤油、納豆、清酒、酢、漬物、鰹節──。微生物を巧みに使いこなし、豊かな発酵文化を築いてきた日本。室町時代にはすでに麹菌を造る「種麹屋」が存在し、発酵の技術は職人技として受け継がれてきました。多様な発酵食品の歴史をたどりながら、現代科学の視点からも理にかなった伝統の技を紹介、和食文化を支える世界に類を見ない多彩な発酵食品、その奥深い世界へと読者を誘います。
”素材の旨味を引き出す名脇役である調味料の多くは、微生物の力を借りて作られる発酵食品である。「さしすせそ」と覚える日本料理の基本調味料は、「さ」砂糖、「し」塩、「す」酢、「せ」醤油、「そ」味噌の5つだが、そのうち「す」「せ」「そ」の3つが発酵食品である。さらに、漬物はもちろん、納豆、鰹節、清酒、さらにうま味調味料の製造にも微生物の力は欠かせない。”(「はじめに」より)
第1章 発酵食品と文化
第2章 発酵の基礎知識
第3章 発酵をになう微生物たち
第4章 納豆・味噌・醤油──大豆発酵食品と調味料
第5章 乳酸菌発酵食品
第6章 ひと味加える調味料と小麦生地の発酵

ひらめきを生む「算数」思考術 問題解決力を高める厳選43題
ブルーバックス
なぜ算数を学ぶのか――スキルアップである。鶴亀算、過不足算、仕事算、……いまではなんとなく解けてしまうかもしれない。その解法の背景には、論理的思考力が隠されている。問題を把握し、わかりやすい形に変換し、解決への道筋を計画し、実践する。これは、算数に限らずあらゆる問題解決に共通するプロセスである。あらためて算数の問題の解き方を学ぶことで、学生から社会人まですべての人に求められるスキルが養われる!

理系のための 微分・積分復習帳 高校の微積分からテイラー展開まで
ブルーバックス
科学・技術を学ぶ上で、最も重要な数学が、微分と積分です変化を記述する微分、面積や体積、量を計算する積分。この2つは、科学や工学、さらには経済学でも最も重要な数学です。どちらも、基本はすべて高校で学びますが、「あやふやな人」が多いのも、この2つです。法則や定理を正確に理解するために、もう一度、しっかり復習してみましょう。
竹内淳先生のブルーバックス「高校数学でわかる」シリーズは、『高校数学でわかるマクスウェル方程式』以来すでに10タイトルに及び、電子書籍も含めた累計発行部数は総計30万部を超え、読者の大きな支持を得ています。
このシリーズでいう「高校数学」とは、微分と積分のこと。「高校数学でわかる」シリーズは、高校で学習する微分と積分を理解していることが前提になっています。
物理学や化学、工学さらには経済学などで必須な、最も重要な数学は微分と積分です。しかし、数学嫌いにとっては微分・積分は、文字通り五里霧中、意味不明であり、また高校で習ったはずの理系出身者であっても、あやふやだったり、公式を忘れたり、そんな読者も多いと思います。
法則や定理を正確に理解するために、もう一度はじめから復習してみましょう。

時計の科学 人と時間の5000年の歴史
ブルーバックス
人類が「時間」の存在に気付いたのは、いまから5000年以上も前のことです。太陽の動き利用した「日時計」から始まり、周期を人工的につくりだす「機械時計」の誕生、精度に革命を起こした「クオーツ時計」、そして時間の概念を変えた「原子時計」まで、時代の最先端技術がつぎ込まれた時計の歴史を余すところなく解説します。
人類が「時間」の存在に気付いたのは、いまから5000年以上も前のことです。
太陽の動き利用した「日時計」から始まり、周期を人工的につくりだす「機械時計」の誕生、精度に革命を起こした「クオーツ時計」、そして時間の概念を変えた「原子時計」まで、時代の最先端技術がつぎ込まれた時計の歴史を余すところなく解説します。

ペンローズのねじれた四次元〈増補新版〉 時空はいかにして生まれたのか
ブルーバックス
現代物理学の奇才=ロジャー・ペンローズの宇宙観を、エキサイティングに解きほぐす――。相対論と量子論の“はざま”に生まれた鬼っ子「スピノール」。この奇妙な“物体”を無数に集めてネットワーク化すると、そこに「時空」が生まれる!? 宇宙の終わりに「次の宇宙」の始まりがある世界。相対論と量子論は、果たして「ねじれた四次元」で邂逅するのか。
読み始めたら止まらない! 疾走する時空のミステリー。
竹内薫衝撃のデビュー作。
新章を加えてバージョンアップ!
現代物理学の奇才=ロジャー・ペンローズの宇宙観を、エキサイティングに解きほぐす――。
相対論と量子論の“はざま”に生まれた鬼っ子「スピノール」。
この奇妙な“物体”を無数に集めてネットワーク化すると、そこに「時空」が生まれる!?
私たちの宇宙はなぜ「四」次元なのか?
そして、四次元だけがもつ特異な性質とは?
宇宙の終わりに「次の宇宙」の始まりがある世界。
相対論と量子論は、果たして「ねじれた四次元」で邂逅するのか。

我々はなぜ我々だけなのか アジアから消えた多様な「人類」たち
ブルーバックス
我々ホモ・サピエンスの出現以前、地球には実に多様な「人類」がいた。教科書に載っているジャワ原人や北京原人だけではない。身長わずか110cmのフローレス原人、台湾の海底で見つかった澎湖人など、とくにアジアの「人類模様」は、目もくらむほどだった。しかし彼らはすべて滅び去り、いま人類は「我々」しかいない。なぜ我々は我々だけなのか? 答えを追い続けた著者が人類進化学の第一人者に導かれて出会った衝撃の仮説!
我々ホモ・サピエンスが出現する前、地球には実に多様な「人類」がいた。
教科書に載っているジャワ原人や北京原人、ネアンデルタール人だけではない。
身長わずか110cm、「人類の定義」さえ揺るがしたフローレス原人、
台湾の海底で見つかった「アジア第4の原人」澎湖人など、
とくにアジアの「人類模様」は、目もくらむほど多種多様だった。
しかし、彼らはすべて滅び去り、いま人類は「我々」しかいない。
なぜ我々は我々だけなのか? 彼らと我々のあいだには、いったい何があったのか?
人類進化学の第一人者に導かれ、答えを追い続けた著者が出会った衝撃の仮説とは?
「サピエンス以前」の人類史が、いまアジアから塗り替えられる!
目次
プロローグ 「アジアの原人」を発掘する
第1章 人類進化を俯瞰する
第2章 ジャワ原人をめぐる冒険
第3章 ジャワ原人を科学する現場
第4章 フローレス原人の衝撃
第5章 ソア盆地での大発見
第6章 台湾の海底から
終章 我々はなぜ我々だけなのか
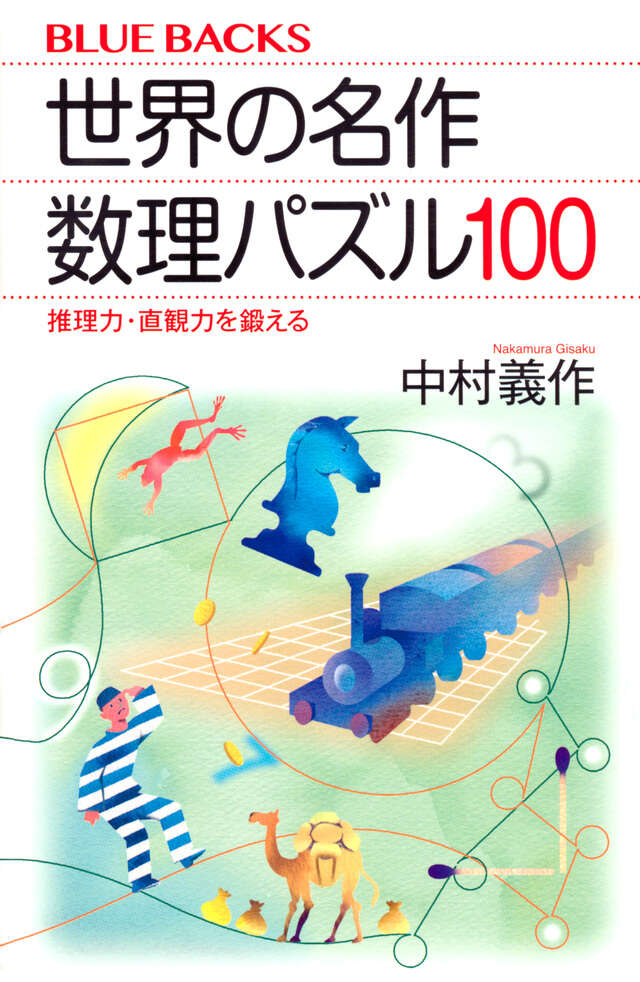
世界の名作 数理パズル100 推理力・直観力を鍛える
ブルーバックス
世界中で多くの人が楽しんでいるパズル。気がつけば簡単に解けるものから、数学などの高度な知識が必要なものまで、じつに多種多様です。本書は、パズル愛好家さえも唸らせる「名作」ばかり集めました。古典をはじめ、数学者フェルマーが17世紀に提案した問題や、歴代のパズル書より選びに選び抜いた問題を、推理力や直観力をフル稼働してお楽しみください。
世の中には、じつにさまざまなパズルが存在して、日々人々を悩まし、そして楽しませています。いざ問題を解こうとすると、小学生でも解ける簡単なものから、高度な知識を持った大人でも難渋するものまで多種多様です。直観ですぐに解けるものは電車の中でも楽しめます。また、洞察力や推理力を必要とするものは、本格的に取り組むことを要求します。
この本では、多くのパズル愛好家を唸らせる名作パズルを集めました。発想ひとつで解ける問題であっても、その発想は読者を驚嘆させる見事なものばかりです。また、相当の努力をしないと解けない問題であっても、解いたあとに残る爽快さは、その人にしか味わえない魅惑的なものを選びました。
古典をはじめ、数学者フェルマーが17世紀に提案した問題や、歴代のパズル書より選びに選び抜いた問題の数々を、推理力や直観力をフル稼働してお楽しみください。

城の科学 個性豊かな天守の「超」技術
ブルーバックス
全国各地で訪れる人々を魅了する日本の城。「城」といって多くの人がまず思い浮かべるのは、高くそびえ、圧倒的な存在感をもつ「天守」です。上下の階を貫く「通し柱」や、あえて古材を再利用する工夫など、さまざまな城造りの技術が見られます。ふたつとして同じものがない天守。国宝に指定された姫路城、松本城、松江城、彦根城、犬山城を中心に、その構造や素材、装飾を解説していきます。
全国各地で訪れる人々を魅了しつづける日本の城。
「城」といって多くの人がまず思い浮かべるのは、高くそびえ、圧倒的な存在感をもつ「天守」です。現代でいう高層建築の天守は、400年以上前から、当時の最高の建築技術によって造られました。そこには様々な役割や目的、工夫の数々。また、上下の階を貫く「通し柱」や、あえて古材を再利用する工夫など、さまざまな城造りの技術が見られます。ふたつとして同じものがないのも天守の魅力です。全国に現存している12の天守、そしてとくに国宝に指定された姫路城、松本城、松江城、彦根城、犬山城を中心に、その構造や素材、装飾、工夫を、美・知・技の見地から読み解いていきます。

美しすぎる「数」の世界 「金子みすゞの詩」で語る数論
ブルーバックス
「みえぬけれども あるんだよ」――数の宇宙にひそんでいる、思いがけない現象におどろく。ごくありふれた日常の情景を感性豊かにとらえた金子みすゞの詩。ごくありふれた顔つきに見える数たちもまた、それぞれに個性的で、ふしぎな性質をもっている。完全数、フェルマー数から、素数定理、相互法則まで。まったく新しいアプローチで数論の魅力を語る入門書。
「みえぬけれども あるんだよ」
――数の宇宙にひそんでいる、思いがけない現象におどろく。
ごくありふれた日常の情景を感性豊かにとらえた金子みすゞの詩。
ごくありふれた顔つきに見える数たちもまた、それぞれに個性的で、ふしぎな性質をもっている。
みすゞの詩に導かれて、数の世界の「美しさ」を知る旅へ――。
完全数、フェルマー数から、素数定理、相互法則まで。
まったく新しいアプローチで数論の魅力を語る入門書。
詩と美と数学と――。
●みんなちがって、みんないい――数にも個性がある
●かみさまは ちっちゃな はちのなかに――2つの素数のふしぎな関係
●みえぬけれども あるんだよ――素数の法則
●たあれが つくる――素因数の法則
●そらの おくには なにが ある――素数分布の法則を求めて
●ふしぎな まほうの せかいなの――2次式の奥へ
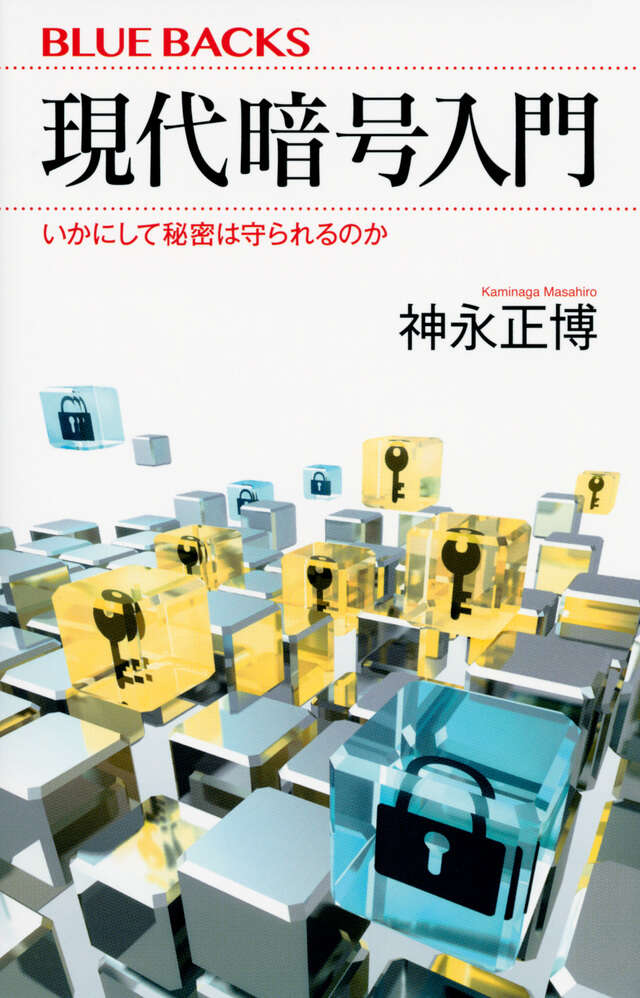
現代暗号入門 いかにして秘密は守られるのか
ブルーバックス
現代の暗号技術には、純粋数学者が追究した緻密で膨大な研究成果が惜しみなく投入されている。開発者と攻撃者の熾烈な争いを追いながら、実際に使われている暗号技術を解説する。現代的な暗号の基本要素である「共通鍵暗号」「ハッシュ関数」「公開鍵暗号」にくわえ、類書ではほとんど解説のなかった、ハードウェアの面からの暗号解読についても紹介する。
ネットも、携帯も、SUICAなどのカードもみんな暗号で守られている現代社会、でも果たして安全か!? サイバー空間ではハッカーたちとどのような攻防が繰り広げられているのか、暗号はどのように守られ、あるいは破られるのか、その舞台裏を実際に起きた事件や実例をもとに描きながら、社会の隅々に浸透した暗号技術の実態(どのように実装されているか)と、現代暗号の進化とその仕組みについて分かりやすく解説します。

DNAの98%は謎 生命の鍵を握る「非コードDNA」とは何か
ブルーバックス
サルとヒトで遺伝子はほとんど同じなのに、なぜ見た目はこんなにも違うのだろう? ヒトゲノムのうち遺伝子部分はわずか2%。遺伝子ではない「98%」にヒトの秘密が隠されていた! かつてはゴミ扱いされた”ジャンクDNA”が生命の謎を解き明かす。
●サルとヒトで遺伝子はほとんど同じなのに、なぜ見た目はこんなにも違うのだろう?
ヒトゲノム(ヒトの全遺伝情報)のうち、遺伝子部分はわずか2%。残りの98%は「非コードDNA」と呼ばれ、意味のない無駄なものと長らく考えられてきました。意味がない=ゴミということで「ジャンクDNA」とさえ呼ばれていたのです。ところが、じつはこの”ゴミ”こそが生命の不思議に迫る重要な役割を担っていることが近年になって分かってきました。サルとヒトの違いを生み出し、老化と寿命に関わり、進化の原動力ともなる「非コードDNA」の仕組み、そして驚きの発見の数々をエピソード豊富に紹介します。
【著者紹介】小林武彦(こばやし・たけひこ)
1963年生まれ。九州大学大学院修了(理学博士)、基礎生物学研究所、米国ロシュ分子生物学研究所、米国国立衛生研究所、国立遺伝学研究所を経て、東京大学分子細胞生物学研究所教授。日本遺伝学会会長。科研費新学術領域研究「ゲノムを支える非コードDNA領域の機能」代表。生命の連続性を支えるゲノムの再生(若返り)機構を解き明かすべく日夜研究に励む。海と演劇をこよなく愛する。著書に『寿命はなぜ決まっているのか──長生き遺伝子のヒミツ』(岩波書店)など。
~~「はじめに」より~~
あなたの体で無駄な部分はありますか?
私の場合はお腹についた脂肪くらいで、他の部分はないと困るところばかりです。髪の毛はだいぶ薄くなってきましたが、別にいらないわけではありません。「日除け」としても働いているし、全部なくなると冬はおそらく寒いです。(中略)
進化の法則によると、「個体」のレベルでは環境に適応できたものは生き残り、そうでないものは絶滅していきます。この法則からすれば、体の中には不要なものなどあるはずがないということになります。(中略)
ところが、じつはヒトゲノムの98%は「遺伝子」の情報を持たない領域だったのです。いわば「意味のない無駄な情報」といえます。しかし、生物はこんな無駄を許すのでしょうか? じつはこの領域こそが生命を誕生させ、ヒトをヒトたらしめ、進化の原動力として働いた重要な装置であることが分かってきました。本書ではこの謎に満ちた暗黒領域「非コードDNA」に光をあて、最新の情報をもとにその役割について解説します。
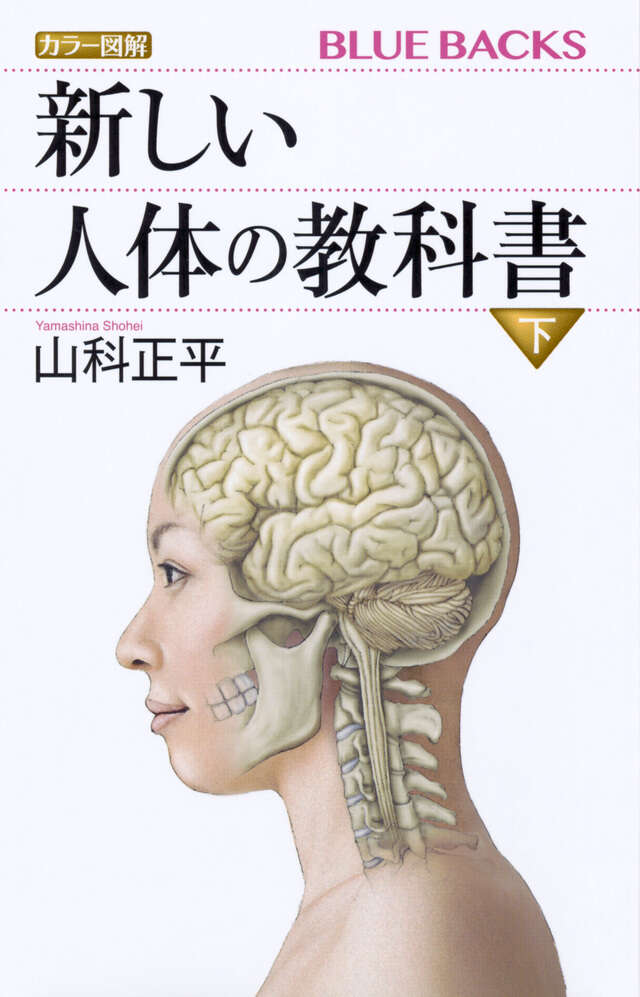
カラー図解 新しい人体の教科書 下
ブルーバックス
福岡伸一氏 大絶賛の新しい解剖生理学の教科書分子生物学、解剖学、生理学など必須知識を網羅し、人体の構造と機能を徹底的にわかりやすく解説。圧倒的な迫力のメディカルイラストを惜しみなく使ったハンディサイズの画期的な「教科書」が誕生!
福岡伸一氏 大絶賛の新しい解剖生理学の教科書
分子生物学、解剖学、生理学など必須知識を網羅し、人体の構造と機能を徹底的にわかりやすく解説。圧倒的な迫力のメディカルイラストを惜しみなく使ったハンディサイズの画期的な「教科書」が誕生!
本シリーズの特徴
●分子生物学、解剖学、生理学などの必須知識を網羅
しているので、医療関連の資格試験の教科書として活用できる
●難解な解剖学を平易かつ明快に講義することで定評のある
著者が8年をかけて書き上げた「渾身の一作」
●人体解剖学で実績にある実力派イラストレーターによる
分かりやすく、美しいメディカルイラストを惜しげもなく掲載
●徹底的に分かりやすさにこだわったレイアウト。極力、ページを
捲り直す必要がないように配慮しているので、ストレスなく読める

佐藤文隆先生の量子論 干渉実験・量子もつれ・解釈問題
ブルーバックス
アインシュタイン方程式の「トミマツ‐サトウ解」の発見で世界的に知られる著者が、量子力学の本質に迫る! 最先端の量子力学実験は、我々の科学認識に大きな変更を要求している。「観測」とはなにか? 「物理量」は実在するのか?二重スリット実験を巧妙に発展させた、最先端の干渉実験はなにを教えてくれるのか? 佐藤文隆先生による新しい量子論。
アインシュタイン方程式の「トミマツ‐サトウ解」の発見で世界的に知られる著者が、量子力学の本質に迫る!
最先端の量子力学実験は、我々の科学認識に大きな変更を要求している。
「観測」とはなにか? 「物理量」は実在するのか?
二重スリット実験を巧妙に発展させた、最先端の干渉実験はなにを教えてくれるのか?
量子力学の腑に落ちない感覚を見つめ直す、佐藤文隆先生による新しい量子論。

時間とはなんだろう 最新物理学で探る「時」の正体
ブルーバックス
誰にでも同じように流れて、逆回しにできないもの――普段思い描く時間の姿は、実はごく限られた一面。最先端の物理学では、時間は、〈空間・物質・力を含む巨大な構造の一部〉と考えられはじめています。ニュートン力学、カオス、特殊相対性理論、一般相対性理論、電磁気学、場の量子論、超弦理論……物理学の歴史を辿っていくと、美しく壮大な、時間の真の姿が見えてくる!
「実感はあるのに実体がない」。
不思議な「時間」の本質を捉える旅へ!
誰にでも同じように流れて、逆回しにできないもの
――普段思い描く時間の姿は、実はごく限られた一面。
最先端の物理学では、時間は、
〈空間・物質・力を含む巨大な構造の一部〉
と考えられはじめています。
ニュートン力学、カオス、特殊相対性理論、
一般相対性理論、電磁気学、場の量子論、超弦理論……
物理学の歴史を辿っていくと、
美しく壮大な、時間の真の姿が見えてくる!
なぜ「時間」が存在するのか?
時間はいつ生まれたのか?
時間は逆方向に進まないのか?
本当に時間は「流れて」いるのか?
――科学が示す驚きの“時間観”とは!?
■おもな内容
第1章 時を数えるということ
第2章 古典的時間観 ――ガリレオとニュートンが生み出したもの
第3章 時間の方向を決めるもの ――「時間の矢」の問題
第4章 光が導く新しい時間観の夜明け ―― 特殊相対性理論
第5章 揺れ動く時空と重力の正体 ―― 一般相対性理論
第6章 時空を満たす「場」の働き ―― マクスウェルの理論と量子としての光
第7章 ミクロ世界の力と物質 ―― 全ては量子場でできている
第8章 量子重力という名の大統一 ―― 時間とはなんだろう?

生命を支えるATPエネルギー メカニズムから医療への応用まで
ブルーバックス
生命を維持するエネルギーの正体は何か、どんなメカニズムで作られ、どのように使われるか、その過程を繙いていく1冊。高校生物でも登場する「ATP(アデノシン三リン酸)」がその鍵を握ります。本書前半では、ATPとそれを取り巻くしくみを、後半では、メカニズムを知ることでわかる、病気の原因について解説します。様々な病気に関わるATPやATPを合成する酵素。薬や診断法など医療への応用も期待されます。
生命を維持するエネルギーの正体とは? そしてそれはどんなメカニズムで作られ、どのように使われるか、壮大なドラマとも言える過程を繙いていく1冊です。
そのドラマの主役は、高校生物でも登場する「ATP(アデノシン三リン酸)」。
本書前半では、ATPとそれを取り巻くしくみを詳しく解説します。後半では、メカニズムを知ることでわかる、病気の原因について解説します。
様々な難病、ガン、胃潰瘍、骨粗鬆症、アルツハイマー型認知症といった病気に、ATPやATPを合成する酵素が大きく関わっているのです。さらに、そのような病気の薬や、診断法などの医療への応用に役立てている研究について、これまでの科学者の足跡をたどりながら、今後の展望についても語ります。

元素118の新知識 引いて重宝、読んでおもしろい
ブルーバックス
アジア初・日本発の新元素「ニホニウム」記載!それぞれに個性的で、独自の働きや機能をもつ118個の元素たち。その全貌がよくわかる「読む元素事典」の決定版!本書の4大特徴!1:元素の本質をいきいきと描き出す。2:各元素の特性や用途など、重要ポイントが一目瞭然。3:生命と元素の関わりがよくわかる。4:半減期や同位体の存在比など、充実した元素データ。
アジア初・日本発の新元素「ニホニウム」記載!
累計16万部突破の定番「元素本」が最新版にバージョンアップ!
それぞれに個性的で、独自の働きや機能をもつ118個の元素たち。
その全貌がよくわかる「読む元素事典」の決定版!
本書の4大特徴!
1:元素の本質をいきいきと描き出す。
事典的な要素を備えながら、読み物としてもおもしろい。
具体的なエピソード満載で、各元素の個性を紹介。
2:各元素の特性や用途など、重要ポイントが一目瞭然。
化合物や現象の列挙にとどまらず、その原因やメカニズムを掘り下げて解説。
3:生命と元素の関わりがよくわかる。
生命活動に必須の元素から、いまだその存在が謎に包まれている元素まで、健康や病気にどう影響するかを詳述。意外な元素が、生命と関係をもっていた!
4:充実した元素データ。
同位体の種類やその存在比、半減期から電子配置、原子量まで。
元素に関する最新の各数値を網羅。

重力波で見える宇宙のはじまり 「時空のゆがみ」から宇宙進化を探る
ブルーバックス
宇宙の進化を司っているのは「重力」だった!重力――もっとも弱く、謎に包まれていた力が、この宇宙に大きな影響を与えている。アインシュタインが重力波を予言してから100年。重力波天文学によって、我々の宇宙観はどう変わるのか? インフレーション、ブラックホール、量子真空、ダークエネルギー、量子重力理論……。宇宙を理解する上で欠かせない問題をやさしく解説しながら、宇宙誕生と進化の謎に迫る。
宇宙の進化を司っているのは「重力」だった!
「重力波天文学」が明らかにする新しい宇宙の姿
重力――もっとも弱く、謎に包まれていた力が、この宇宙に大きな影響を与えている。
アインシュタインが重力波を予言してから100年。
“アインシュタイン最後の宿題”と言われた重力波の観測が成功したことで、「重力波天文学」がついに幕を開けた。
それによって、我々の宇宙観はどのように変わるのだろうか?
インフレーション、ブラックホール、量子真空、ダークエネルギー、量子重力理論……。
宇宙を理解する上で欠かせない問題をやさしく解説しながら、宇宙誕生と進化の謎に迫る。
■おもな内容
序章 変貌する宇宙
第1章 重力、この未知なるもの ――ガリレイ、ニュートン、アインシュタインの見解
第2章 一般相対性理論 ――重力の理論から宇宙の理論まで
第3章 宇宙を観察する
第4章 2つの無限 ――両者は共存できるか?
第5章 宇宙誕生の瞬間 ――インフレーションから最初の光が現れるまで
第6章 ダークエネルギーと量子真空
第7章 闇を学ぶ ――ブラックホール
第8章 重力のさざ波 ――重力波とは何か
第9章 重力波の直接探知に成功 ――We did it!
第10章 宇宙の未来