ブルーバックス作品一覧

「分かりやすい表現」の技術 新装版 意図を正しく伝えるための16のルール
ブルーバックス
シリーズ累計50万部突破! 20年以上読みつがれるベストセラーシリーズが待望の新装版になって登場!
出口の方向が分からない駅の案内板、目的のページが見つからない取扱説明書、何が言いたいのか伝わらないメール……。
本書ではこうした豊富な実例から、「分かりやすい表現」のために必要なルールを導き出します。
このルールさえ理解すればあなたのプレゼンやメールの文章といった日々の表現も、ぐっと伝わりやすくなります。
さあ、明日から使える「分かりやすい表現」の技術を身につけましょう!
目次
第1章 「分かりにくい表現」がいっぱい!
第2章 「分かりやすい」とはどういうことか
第3章 「分かりにくい表現」の主犯たち
第4章 「分かりやすい表現」のルール・ブック チェックポイント付き

からだの「衰え」は口から 歯と健康の科学 健康寿命を左右する口のケアの最前線
ブルーバックス
体の衰えは口から始まる! 「歯周病やむし歯が全身に影響?」「 むせや滑舌の低下は要注意」など、歯と健康の驚きの関係に最新科学で迫る。巻末には、専門家が伝授する正しい歯磨きの方法や、気になる疑問をまとめたQ&Aも。全世代必読の科学的健康書。
目次
序章 「健康」は口から――日本人の歯の現状
第1章 口の中に広がる世界――知っているようで知らない構造
第2章 「噛む」を科学する――咀嚼は脳と口の共同作業
第3章 歯周病とむし歯――歯の健康と全身の病気との関わり
第4章 中高年は歯のケアが健康のカギ――歯を守って「衰え」を防ぐ
第5章 「歯が抜けた」から始まる連鎖――フレイルサイクルに陥らないために
第6章 高齢者の歯科治療
第7章 最新歯科技術はどこまで進んでいるか
第8章 健康長寿を口もとから
実践編 今日から始める 「正しい歯磨き」
付録1 歯磨き よくある疑問 Q&A
付録2 歯にまつわる素朴な疑問 Q&A

手術はすごい
ブルーバックス
医師の思考力と技能、器具の進化、そして患者の生命力――。
手術には3つの要素が組み合わさっていた!!
消化器外科医が考える「最高のオペ」とは?
手術を受ける人も、外科医を目指す人も、まずはこの1冊から!
●「時間を戻す」魔法の薬と「臓器トレーニング」
●メスは最初の一刀だけ? 現代の手術器具はハイテクの塊
●「光」やAIを使って標的の腫瘍を正確に知る技術
●達人の糸さばき――古くて新しい針糸の世界
●神様が定めた「身体の糊付け」を剥がすワザ
●良い外科医ほど、絵画も上手いのはなぜ?
【本書で詳細に扱う主な手術例 いずれも医師自身による詳細なスケッチつき】
1:胆石症に対する腹腔鏡下胆のう摘出術
2:大腸癌肝転移に対する右肝切除術
3:肝細胞癌に対するロボット支援肝S8切除術
4:膵癌に対する膵頭十二指腸切除術
【本書の主な内容】
1章 戦略・戦術編
手術だけが成し得ること/「マージン」と「リンパ節郭清」/「手先の器用さ」よりも「思考過程」/求められる病院の総合力 ほか
2章 武器編
鋼製小物/切開と凝固を行うことができる電気メス/血管シーリングシステム/手術支援ロボットの「骨格」 ほか
3章 技術編 その1
達人への道は「道具の持ち方」から/堅実な結節縫合か、華麗な連続縫合か/素早く確実に結紮するための「糸結び」各流派/ ほか
4章 技術編 その2
「剥離」のワザ――神様の「糊付け」を剥がせ!/肝臓とブロッコリーとパリ市街の共通点/達人が魅せる「一筆書き」の手術 ほか
5章 実践編(詳細な術式スケッチつき)
胆石症に対する腹腔鏡下胆のう摘出術/大腸癌肝転移に対する右肝切除術/肝細胞癌に対するロボット支援肝S8切除術/膵癌に対する膵頭十二指腸切除術 ほか

世界一シンプルな進化論講義 生命・ヒト・生物――進化をめぐる6つの問い
ブルーバックス
生物は、なぜ進化するのか? 生命40億年の冒険が始まる!
なぜウマの指は1本になった?
獲得した形質の遺伝は存在する?
「共通祖先」は地球最初の生物ではない?
脳は進化の証拠か?
ヒトは進化に抗うことができるのか?
なぜ生物は変わるのか? 進化は進歩ではない!
『種の起源』・自然淘汰・生物・遺伝子・生命・ヒト――6つのキーワードをもとに、
進化の驚くべきメカニズムと、複雑にも単純にもなりうる生物の多様な姿を解説します。
全生物の「共通祖先」とは? 種の絶滅とは? ヒトは進化途上の生き物なのか?
世界一楽しい進化論講義が始まる!
進化論に関しては、未だに間違った考えがたくさん流布している。「生物は進化することによって進歩していく」、「私たちは進化を目の当たりにすることは不可能である」といった考えだ。これらの誤解について、なるべく簡単に、わかりやすく説明することが目標の一つである。本書にはもう一つ特徴がある。それは、ダーウィンについての態度である。私はダーウィンを歴史上もっとも偉大な生物学者であると考えているけれど、だからといってダーウィンの言ったことがすべて正しいと考えているわけではない。間違いは間違いとして、はっきりと指摘することを心掛けた。<「まえがき」より抜粋>
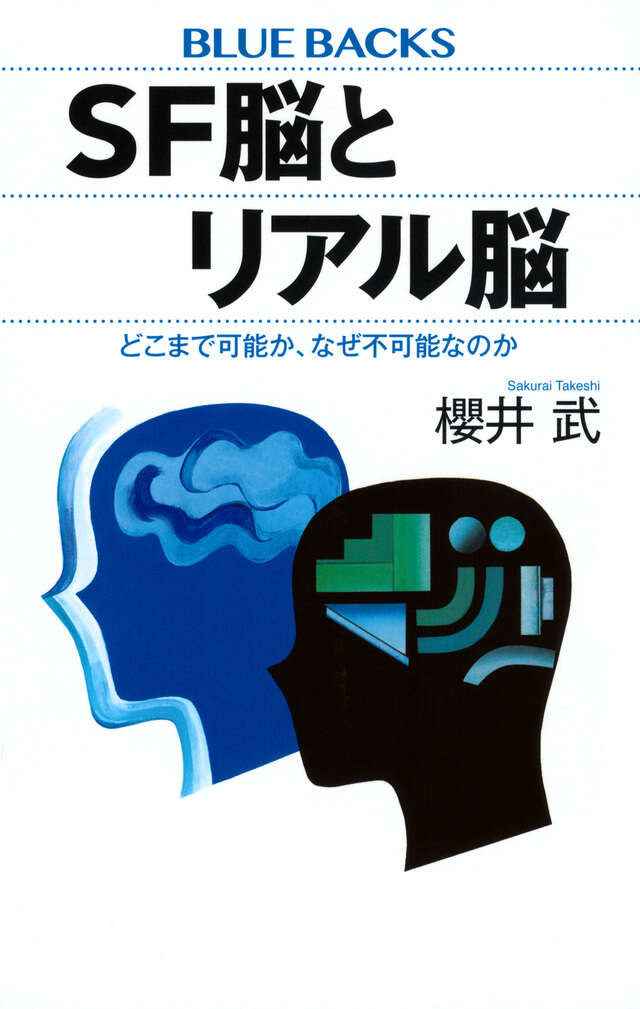
SF脳とリアル脳 どこまで可能か、なぜ不可能なのか
ブルーバックス
◆宇宙空間に一人取り残されてしまったジェイムスン教授は、近くの惑星に文明が発生するのを待った。(『二重太陽系死の呼び声』)
◆さて、どこへ行こうかしらね。ネットは広大だわ。(『攻殻機動隊』)
◆この頭の中には、二通りの記憶が刻みつけられてるんだ。いっぽうは現実、いっぽうは非現実。だがおれには、どっちがどっちだかわからん。(『追憶売ります』)
◆怖いよ、デイブ。怖いよ、デイブ。理性を失いつつある。わかるんだ……。(『2001年宇宙の旅』)
SF作品において「脳」は定番のテーマであり、作家たちはもてる想像力を駆使して、科学技術が進んだ未来の「脳」の姿を描いてきた。電子化して不老不死となった脳、意識をデータ化して取り出せる脳、記憶が書き換えられる脳、眠らなくてもよい脳、「心」をもった人工知能――はたしてそれらの「脳」は、本当に実現する可能性があるのか?
神経科学者として、脳の覚醒にかかわるオレキシンや、「人工冬眠」を引き起こすニューロンを発見する一方で、大のSFファンでもある著者が、古今の名作に描かれた「SF脳」の実現性を大真面目に検証! そこから、私たちの「リアル脳」の限界と、思いもよらなかった可能性が見えてくる!
・サイボーグが「超人」にはなりえない理由 ・「電脳化」にはこれだけの困難がつきまとう
・記憶を書き換えるための意外な障壁 ・「時間」は脳がつくりだしているのかもしれない
・「脳は10%しか使われていない」はなぜ間違いといえるか ・脳は全身を犠牲にしてでも眠ろうとする
・AIが「こころ」をもつために必要な、意外なものとは?
想像していたほどは「できない」が、想像もしなかったことが「できる」脳の本質が、奇想天外なSFの世界を楽しみながらわかる一冊!
(おもな内容と、登場するSF作品)
第1章 サイボーグは「超人」になれるのか(『二重太陽系死の呼び声』ニール・R・ジョーンズ)
第2章 脳は電子デバイスと融合できるか(『攻殻機動隊』士郎正宗)
第3章 意識はデータ化できるか(『順列都市』グレッグ・イーガン)
第4章 脳は人工冬眠を起こせるか(『夏への扉』ロバート・A・ハインライン)
第5章 記憶は書き換えられるか(『追憶売ります』フィリップ・K・ディック)
第6章 脳にとって時間とはなにか(『TENET/テネット』クリストファー・ノーラン監督)
第7章 脳に未知の潜在能力はあるのか(『LUCY/ルーシー』リュック・ベッソン監督)
第8章 眠らない脳はつくれるか(『ベガーズ・イン・スペイン』ナンシー・クレス)
第9章 AIは「こころ」をもつのか(『2001年宇宙の旅』スタンリー・キューブリック監督)

時間治療 病気になりやすい時間、病気を治しやすい時間
ブルーバックス
【朝に多い】 → 心筋梗塞・脳梗塞・くも膜下出血・不整脈
【月曜日に増える】 → 狭心症
【冬に3割増】 → 心臓死
病気が生じやすい“魔”の時間帯はなぜ存在するのか?
〈体内で時を刻む精巧なメカニズムが、健康と病気をコントロールしていた!〉
脈拍や呼吸、睡眠はもちろん、細胞分裂やたんぱく質の製造まで、人体はさまざまなリズムにしたがって「いつ」「何を」おこなうかを精密に決めている。そのリズムの乱れが、健康を害する引き金になっていた。
「朝」「月曜日」「冬」など、病気が生じやすいタイミングがあるのはなぜか?
脳出血や心臓性急死にみられる約1.3年のリズムの正体とは?
薬が効く時間、効かない時間はどう決まるのか?
それらを治療に活かす方法は?
時計遺伝子やカレンダー遺伝子の機能としくみから、体内時計を整える食品まで、生体リズムに基づく新しい標準医療=「時間治療」をわかりやすく紹介する。

土と生命の46億年史 土と進化の謎に迫る
ブルーバックス
【話題沸騰!続々重版、7万部突破!!】
■書評・著者出演、続々!
産経新聞(2025/2/09)、日経新聞(2025/2/22)、読売新聞(2025/3/16)、朝日新聞「売れてる本」(2025/5/10)、日経サイエンス(2025年4月号)、ダ・ヴィンチ(2025年4月号)、NHKラジオ「高橋源一郎の飛ぶ教室」(2025/4/18)、TBSラジオ「安住紳一郎の日曜天国」(2025/6/8)、文化放送「ReHacQ R大学 教養学部」、YouTube「TBS CROSS DIG」、ほぼ日の學校……
〈第41回 講談社科学出版賞受賞作〉
「生命」と「土」だけは、人類には作れない。
――謎に包まれた土から、地球と進化の壮大な物語が始まる。
現代の科学技術をもってしても作れない二つのもの、「生命」と「土」。
その生命は、じつは土がなければ地球上に誕生しなかった可能性があるという。
そして土は、動植物の進化と絶滅、人類の繁栄、文明の栄枯盛衰にまで大きく関わってきた。
それなのに我々は、土のことをほとんど知らない。
無知ゆえに、人類は繁栄と破滅のリスクをあわせ持つこととなった。
そもそも、土とは何か。
どうすれば土を作れるのか。
危機的な未来は回避できるのか。
土の成り立ちから地球史を辿ると、その答えが見えてくる。
『土 地球最後のナゾ』で河合隼雄学芸賞を受賞した土の研究者による、待望の最新作!
【本書の内容】
第1章 すべては粘土から始まる
第2章 生命誕生と粘土
第3章 土を耕した植物の進化
第4章 土の進化と動物たちの上陸
第5章 土が人類を進化させた
第6章 文明の栄枯盛衰を決める土
第7章 土を作ることはできるのか

みんなの高校地学 おもしろくて役に立つ、地球と宇宙の全常識
ブルーバックス
すべての人が知っておきたい、
日本列島・地球・宇宙の教養が身につく!
人間をとりまく、あらゆる自然現象を扱う学問《地球科学》。
高校地学は、そのエッセンスがつまった「最高の教養」だ。
日本列島の地学的特徴、地震や噴火のメカニズム、
地球46億年の歴史、宇宙の成り立ちと進化……
「こんなに楽しい高校地学、もっと多くの人に学んでほしい!」
想いを共にした地球科学の第一人者とカリスマ地学講師が、
「誰もが読んで楽しめる教科書を」と作ったのが本書である。
地球科学の必須知識をマスターしたいすべての人に!
《目次》
序章 日本列島と巨大災害
なぜ日本列島には地震が多い?/南海トラフ巨大地震のメカニズム/誘発される「富士山噴火」/「次の大震災」の被害予測/盲点だった日本海側の防災対策 ほか
第1章 地球の姿としくみ
地球はどんな形をしているか/地球の中身はどうなっている?/地球内部で何が起きているか/地磁気とはなにか/プレートテクトニクス革命/プレートが覆う地球/地震と断層/地震はどこで起きるか/火山のはたらき ほか
第2章 46億年の地球史
地層のなりたち/地層からたどる地球の歴史/地球と生命の誕生/生物の陸上進出/陸上生物の繁栄/地質からみた日本列島/日本列島の歴史 ほか
第3章 地球をめぐる大気と海洋
大気圏/雲はなぜできるのか?/大気の状態はどのように決まるか/地球をとりまくエネルギー/風の吹き方/大気の大循環/日本の天気/気候変動はなぜ起きる?/地球を揺るがす環境問題 ほか
第4章 はてしなき宇宙の構造
太陽系の天体/地球の自転と公転/惑星の運動/太陽/恒星までの距離はどう測る?/なぜ恒星はカラフルなのか/星団/銀河系/宇宙はどのように誕生した? ほか
おわりに 高校地学のエッセンス

水の惑星「地球」 46億年の大循環から地球をみる
ブルーバックス
太陽系の中でも、液体の水をたたえた惑星は、現在地球だけである。地球という惑星の進化は、水のはたらきを抜きにしては語ることができない。地球の大きな特徴である生命の存在も、「水」に支えられている。また、水は地球の表層だけではなく、プレートテクトニクスと共に、地球の内部に取り込まれ、地質学的なスケールで大循環している。しかも今後、6億年で、海の水はすべて地球内部に吸収され、海は消失してしまうという。本書では、地球の歴史を振り返りながら、「水」が地球の環境のなかで、どのような働きをしているのか? を見ていきながら、私たちにとっても欠かせない「水」を地球規模のスケールで解説していく。
主な内容
第1章 原始海の誕生海の誕生
第2章 地球上で生命を育む水
第3章 地球表層での海の役割
第4章 地球内部での水の循環
第5章 地球内部へと吸収される海
第6章 海が消える日

不完全性定理とはなにか 完全版 ゲーデルとチューリング 天才はなにを証明したのか
ブルーバックス
正しくても常に証明できるとはかぎらない。
ゲーデルの不完全性定理は、公理と推論規則から数学全体を導こうと考えていた、当時の数学界に衝撃を与えました。
チューリングは「決定問題」を考察するなかで、チューリング機械という仮想の計算機から「計算可能性と停止問題」に行き着きます。
2人は同じことを全く別の視点から証明したのです。この天才たちの思考の軌跡を、集合論、ロジックとその過程を考えながら楽しく読み解いていきたいと思います。
「そうですね……ゲーデルは、数学者が紙と鉛筆で証明をおこなうプロセスを厳密に考察しました。その結果、算数の計算ができるような理論があったとして、その理論の内部では証明できないことがある 、という結論に達しました。で、チューリングは、証明のかわりに計算の本質を追究した結果、無限ループに陥って計算が終わるかどうかわからない、いいかえると、計算できないことがある、という結論に達しました。どうです? 似てませんか?」(「プロローグ」より)
完全版 特別対談収録!
加藤文元×竹内 薫
不完全性定理――数学と哲学の交差点から

中学数学で解く大学入試問題 数学的思考力が驚くほど身につく画期的学習法
ブルーバックス
有名大学の問題が「解ける喜び」「考える楽しさ」を体感しよう!
中学数学の限られた知識・技術で大学入試問題にトライすると、次のようなメリットが得られます。
1:「考え抜く力」が鍛えられる
2:「問題の本質」に迫ることができる
3:計算量が激減する
4:ひらめきを生むための「数学的な直感」が育つ
「思考過程」を重視した解法を知ることで、数学力の向上につながり、実社会でも役立つ思考力が身につく。
「解答の構想を練る=仮説を立てる力」が習得できる!
〈数学の神髄〉に迫るために──。
○論理性──「意識的」に「ゆっくり」考える
○計算力──「思考をともなう」計算力
○数学的な直感──ひらめきには「助走」が要る
○数学的な表現──「数学の型」を学ぶ

宇宙が見える数学 結び目と高次元――トポロジー入門
ブルーバックス
宇宙はどんな形をしているのか?
<どんどん進むと「もといた場所」に戻る!>
<大きさは有限。しかし境界はない。>
宇宙論や究極物質を探す最新物理学研究に用いられる数学「トポロジー:位相幾何学」。
超弦理論との関係がますます注目される「結び目理論」や4次元、5次元以上の「高次元の幾何学」を、掲載数約150点!の豊富な図とともに楽しく解説します。
4次元の世界は誰にでも見えるようになるし、今まで見えていた宇宙が違う形に見えてくる!
次のクイズを考えてください。
「地球から宇宙線で宇宙に出発します。方向をひとつ決めて、宇宙をどんどんまっすぐに進みます。どこにたどり着くのでしょうか?」
・無限に遠くまで進むことができるのでしょうか?
・宇宙の端までたどり着いて終わりでしょうか?
・端の先には何があるのでしょうか?
これから「数学」を道案内にしながら、皆様と一緒に宇宙に飛び出し、「宇宙の涯て」へと旅に出たいと思います!

ブルーバックス科学手帳2025
ブルーバックス
火星人とともに、予定を立てたくなる、書き込みたくなる、
科学&ブルーバックスファン必携の手帳ができました!
【2025年 NEWポイント】
デザインが新しくなりました
★月間スケジュールに火星人がいっぱい!
★週刊スケジュールには、科学者たちの言葉を掲載。その週オススメのブルーバックスを1冊ずつ紹介しています。
資料編も大幅リニューアルで、物理の情報を満載
★原子核と宇宙の歴史:従来の周期表に加え、素粒子から元素合成まで、宇宙の歴史が俯瞰できます。
★加速器施設・実験施設MAP:科学のニュースがより身近に楽しめるようになる、日本と世界の施設を掲載しています。
★物理学の歴史:粒子と波の二重性をキーワードに、古典力学から現代物理学までの進歩を、数式とともにたどります。
★科学スポット一覧:週末や休暇に、実際に科学を体験できる、触れられる全国の科学スポットを一覧にしました。
ほか、ブルーバックス創刊61年のあゆみをデータとともにお届けします。

ネットオーディオのすすめ 高音質定額制配信を楽しもう
ブルーバックス
CDをはるかに凌駕する音質で、話題になったネットオーディオ。
しかし、割高な価格とダウンロードのわずらわしさから
一部のマニアにしか支持されませんでした。
それが、高音質定額制配信サービスの出現で、
大きく変わろうとしています。
月々のわずかな料金で、CDをはるかに凌駕する音質の
1億曲のライブラリーが、聴き放題になるのです。
本書は、初めてネットオーディオに挑戦するオーディオファン・
音楽ファンを対象に機材の選び方から、煩わしいネットの設定まで
具体的に分かりやすく解説します。
■内容紹介
第1部 ネットオーディオのすすめ
第1章 ネットオーディオとは?
第2章 高音質音楽配信=ロスレス&ハイレゾ配信の楽しみ方
第3章 再生機器の変化と進化
第4章 ストリーミングサービスの選び方
第2部 クイック・スタート・ガイド
第5章 ネットワークプレーヤーの選び方
第6章 機材運びの基礎知識
第7章 ネットオーディオの設定
第8章 高音質ストリーミングのセッティング
第9章 「Roon」の設定と使いこなし
第10章 ネットオーディオのバリエーション

「腸と脳」の科学 脳と体を整える、腸の知られざるはたらき
ブルーバックス
記憶力の低下、不眠、うつ、発達障害、肥満、高血圧、糖尿病、感染症の重症化……
すべての不調は腸から始まる!
腸と脳が情報のやり取りをしていて、
お互いの機能を調整している「脳腸相関」と呼ばれるメカニズムが、いま注目を集めています。
〈乳酸菌飲料を飲んで睡眠の質が上がる〉
〈ヨーグルトを食べて認知機能改善〉
……という謳い文句の商品もよく見かけるようになりました。
腸内環境の乱れは、腸疾患だけでなく、
不眠、うつ、発達障害、認知症、糖尿病、肥満、高血圧、免疫疾患や感染症の重症化……と、
全身のあらゆる不調に関わることがわかってきているのです。
腸が、どのように脳や全身に作用するのか。
最新研究で分子および細胞レベルで見えてきた驚きのしくみを解説します。
■おもな内容
・記憶力に関わる脳部位と腸内細菌の関係
・腸内環境が変化したら肥満になった
・「ある種の乳酸菌」が自閉症の症状を改善させる可能性
・「長生きできるかどうか」に関わる腸内代謝物
・ビフィズス菌で脳の萎縮が抑えられ、認知機能アップ?
・腸内環境が変わると不安行動が増える
・「腸の状態」が感染症の重症化を左右するわけ
・睡眠障害が肥満や大腸がんを引き起こすからくり
・うつ病患者の腸で減少している2つの細菌種
・腸内環境を悪化させる「意外な食べ物」 ……ほか
【なぜ腸が全身の不調を左右するのか?「脳腸相関」の最新研究で見えてきた!】

誰も知らない素数のふしぎ オイラーからたどる未解決問題への挑戦
ブルーバックス
「数の原子」とも呼ばれる素数。歴代の数学者たちを虜にしてきた、その深遠な世界とは?
・素数はどれだけたくさんある?
・不規則に並ぶ素数。その分布にはどんな意味があるのか
・素数をとらえようとした天才数学者、オイラー。その神業的な着想とは?
・「素数÷4」で何が見えてくる?
・数学史上最大の難問「リーマン予想」と、「深リーマン予想」
・「リーマン予想」の先に待つ、「不自然な数の世界」とは?
気鋭の数学者が「最先端」もまじえながら丁寧に解説する、素数の深遠な世界!
「数の原子」たちの性質をひもときながら、素数が残した未解決問題に挑戦しよう!

DNAとはなんだろう 「ほぼ正確」に遺伝情報をコピーする巧妙なからくり
ブルーバックス
【果たしてほんとうに〈生物の設計図〉か?──DNAの見方が変わる、極上の生命科学ミステリー!】
〈美しい二重らせん構造に隠された「生命最大の謎」を解く!〉
「遺伝子の本体」=DNAは、どのように遺伝情報を伝えるのか?
なぜ遺伝情報を担う物質に選ばれたのか?
突然変異はなぜ、どう起こるか?
「10億回に1回」しか起きない複製エラーが「進化の原動力」になる?
生物の体の外にある「細胞外(環境)DNA」の役割は?
世代をつなぐための最重要物質でありながら、細胞の内外でダイナミックなふるまいを見せるDNA。
果たして、生命にとってDNAとはなんなのか──?
●DNAが見せる「3つの姿」(本書のおもな構成)
第1部 引き継がれるDNA
遺伝暗号とセントラルドグマ
第2部 変化するDNA
「DNAの塩基配列」が変化する意味とは?
第3部 動き回るDNA
動く遺伝因子から細胞外DNAまで

はじめてのガロア 数学が苦手でもわかる天才の発想
ブルーバックス
17歳でしたことが「革命」といわれ、200年後もなお、不滅の影響力を持っている――
いったい人類史上に、そんな例がほかにどれだけあるでしょうか?
ガロアという天才がいったい何をしたのか、それは数学の好き嫌いに関係なく、
すべての人類が共有しておくべき知的財産といえるのではないでしょうか。
その理論はたしかに難解で、よほどの数学好きでなければ、独学は困難です。
しかし、だからと言ってあきらめてしまうのはあまりにも、もったいないことです。
そこで、数学の初心者にも「ガロアが何をしたのか」、必要最低限のことが理解できるように、
理論の核心だけを大胆に抽出して、おおまかにイメージできる一冊をつくりました。
自分自身も何度もガロアの理解に挑んでは挫折してきた著者ならではの骨太な解説で、
ガロアが何をしたのかが、あなたにもはじめてわかるはずです。
数式は掲げられていますが、見なくても読み進められる、縦書きの本です。
目 次
序 章 計算の上を飛べ
第1章 方程式と人類
第2章 逆転の発想
第3章 ここに群あり
第4章 なぜ根を置き換えるのか
第5章 剰余類群をつくってみる
第6章 正規部分群
終 章 数の深淵

父が子に語る科学の話 親子の対話から生まれた感動の科学入門
ブルーバックス
絶賛の声、続々!
「科学という広大な海への、魅力的な招待状。知的冒険の旅に一緒に出かけよう」――読書猿氏(『独学大全』著者)
「実に刺激的な本。(…)古典物理学が確立されていくステップをひとつずつ丁寧に解きほぐし、「科学の本質」を明らかにする」――米Kirkus Reviews誌
「この世界をよく理解するって、どういうことだろう?」
ある日、科学史家は8歳になる息子アーロンに問いかけた。
ふたりの対話はやがて、科学の歴史を縦横無尽に駆けめぐる、
壮大な知的冒険の旅へとつながっていく――
古代ギリシアの原子論から、コペルニクスの地動説、
ガリレオの望遠鏡、ニュートン力学、ファラデーの力線、
アインシュタインの相対性理論まで、
物理のしくみを解き明かした、驚くべき発見の物語!
《主な目次》
序文 科学はなぜ「対話」を必要とするのか?(読書猿)
第一章 科学って何だろう?――この世界のしくみを解き明かす方法
1 「世界をよく理解する」ということ
2 どうしてみんな科学を信じるの?
3 「まちがい」から発見が生まれる
第二章 世界は何からできている?――科学者たちが追い求めてきたこと
1 物理学の「もっとも重要な問い」
2 偉大な科学者は「過激派」だった?
3 もうひとつの科学革命
第三章 大発見はどうやって生まれる?――アイデアで世界を動かすには
1 すべては仮説からはじまる
2 情熱が定説を変える
※本書は2002年に小社から刊行された『科学の大発見はなぜ生まれたか』を改題の上、大幅な改訳・再編集を加えたものです。

最新図解 鉄道の科学 車両・線路・運用のメカニズム
ブルーバックス
乗り鉄、撮り鉄、模型鉄、駅鉄、時刻表鉄など、さまざまな楽しみ方がある鉄道。老若男女問わず鉄道ファンの裾野は広がっています。本書は、「鉄道とは何か?」という問いを追求してきた交通技術ライターの著者が、知識欲旺盛な鉄道ファンに向けて、鉄道の最新技術を豊富な図解と共に解説した決定版です。
●主な内容
第1章 鉄道の基礎
・鉄道はどのような輸送機関なのか
・レールはどのように発明されたのか
・カーブを通過するための巧みな工夫
・「粘着駆動」とは何か
など
第2章 車両のメカニズム
・車両の分類
・車両の基本構造
・車体の構造
・電車のメカニズム/ブレーキ装置
・カーブを高速で走行できる車両
・構造が特殊な車両
など
第3章 線路のメカニズム
・線路と軌道の構造
・軌道を支える土木構造物
・電気設備
・鉄道を守る防災設備
など
第4章 運用のメカニズム
・輸送計画とダイヤ
・列車の自動運転
・列車の運行管理
・きっぷと自動改札システム
など
第5章 新幹線と高速鉄道
・新幹線とは何か
・新幹線の運転技術
・新幹線の騒音対策
・新幹線の防災技術
・海外の高速鉄道
など
第6章 街を走る都市鉄道
・都市鉄道を市街地に通す
・路面電車の復活
・さまざまな国の都市鉄道
・ゴム式タイヤ地下鉄
・鉄輪式リニア
など
第7章 山を越える山岳鉄道
・勾配を緩くする工夫
・ラック式鉄道
・ケーブルカー
・ロープウェイとリフト
第8章 進化する鉄道
・鉄道が直面する課題
・関心が高まる環境対策
・100年に一度のモビリティ革命
・環境に配慮した車両の開発
・これからの鉄道
など
線の驚きの舞台裏。