ブルーバックス作品一覧
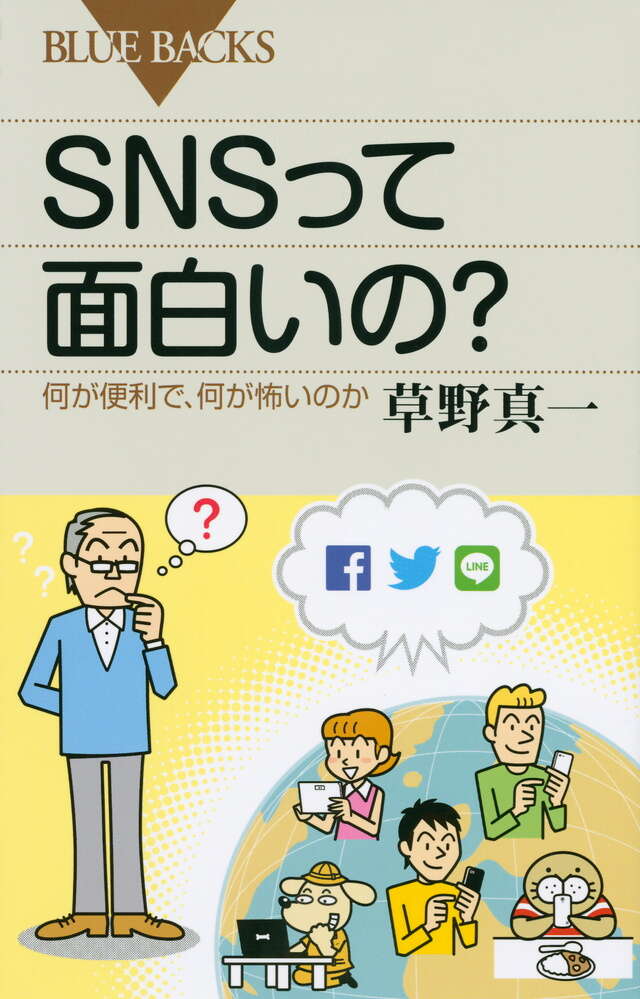
SNSって面白いの? 何が便利で、何が怖いのか
ブルーバックス
フェイスブックにツイッター、LINEなど、「SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)」を使ったことのない人にとってSNSはなんともつかみどころがないものだ。今さら誰にもきけないし、何からきけばよいかわからない。本書では、そうした未経験者のためにSNSが出てきた経緯から、しくみ、メリット、リスクなどを平易に解説する。使わなくてもSNSの概要がわかってくる。
テレビのニュースや新聞記事の中で、フェイスブックやツイッター、LINEといった「SNS」(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の名前が出てくることは珍しくありません。たとえば、「アメリカの大統領がツイッターを始めました」「この番組のフェイスブックページもどうぞご覧ください」「事件にかかわった少年たちは通信ソフトLINEでやり取りしていました」といったものです。SNSを使ったことがない人にとっては、「なんだかわからないけど、新しいものがひろまっている」、という印象かもしれません。
いつの間にか普及している感のあるSNSですが、普及した経緯を追うと、インターネットやコンピュータといったIT関連のテクノロジーの発展と深く関係(特にスマホとの)していることがわかります。
また、SNSの用途が、わたしたちの日常生活ですでに行っていた行動だったことも見逃せません。「情報を仕入れる」「仕入れた情報を人に伝える」「誰かに連絡を取る」「誰かと意見交換する」といったことを、SNSによってより簡単に行えるようになったのです。
SNSが普及することによって、さまざまな分野で影響が出てきています。影響の規模は、表面上わかりにくいのですが、社会全体の変化につながっています。
本書では、フェイスブックやツイッター、LINEなどの操作方法についての解説はありません(操作方法は、運営会社の都合でたびたび変更されます)。
その代わり、SNSが出てきた経緯、しくみ、メリット、リスクについて、わかりやすい例を交えながら紹介していきます。本書を読むことで、フェイスブックやツイッター、LINEなどを実際に使ってみなくても、「どういうものなのか」がわかります。
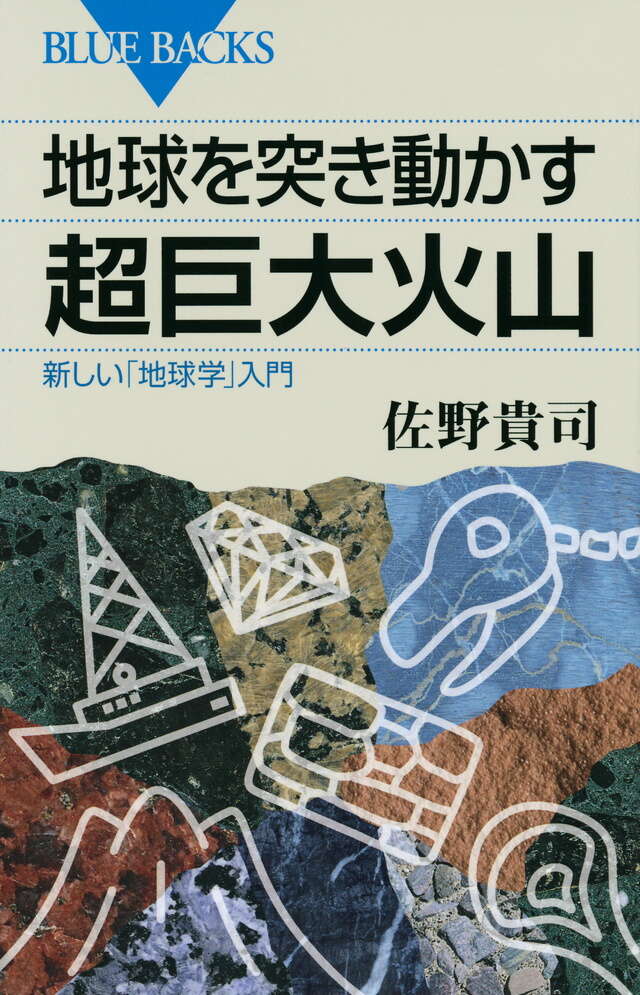
地球を突き動かす超巨大火山 新しい「地球学」入門
ブルーバックス
2009年、日本から約1500キロメートル東の太平洋の深海底で高さ30キロメートル、面積は日本の国土に匹敵する超巨大火山が見つかった。1億年以上前にはこうした超巨大火山があちらこちらで活発に噴火活動をして、 大地を引き裂きながら、広大な大地を形成し、いまの地球をつくりあげてきたと考えられている。いったい超巨大火山はどうやってつくられたのか?
マグマがつくられ、大地が形成され、大陸は時々刻々動き続けている
2009年、日本から約1500キロメートル東の太平洋の深海底で高さ30キロメートル、面積は日本の国土に匹敵する超巨大火山が見つかった。1億年以上前にはこうした超巨大火山があちらこちらで活発に噴火活動をして、大地を引き裂きながら、広大な大地を形成し、いまの地球をつくりあげてきたと考えられている。いったい超巨大火山はどうやってつくられたのか?
じつは超巨大火山こそが地球の全マントルを循環させ、 地球を突き動かしてきた張本人だったとしたら……。大陸移動やプレートテクトニクスの原動力を生み出すマグマとマントルと地球内部のふしぎな関係が見えてくる。

謎解き・津波と波浪の物理 波長と水深のふしぎな関係
ブルーバックス
先を急ぐ波、ゆっくり進む波。孤高の波、群れる波。生まれたての波、成熟した波。そして、海底を感じる波、感じない波――。波が海底を感じるとはどういうことか? 波のふるまいを左右する「波長」と「水深」のフクザツな関係とは? 身近なふしぎ現象を、数式なしでわかりやすく解き明かす。
海底を感じるかどうか、それが問題だ!
広大な海をわたる波には、2つの種類がある。
「海底を感じる波」と、「海底を感じない波」だ。
時速700kmもの猛スピードで進む津波は、つねに海底を感じている。
南極近海で生まれ、アメリカ西海岸へと到達する「うねり」は、海底を感じることなく1万kmもの長旅をこなす。
波が海底を感じるとはどういうことか?
波のふるまいを左右する「波長」と「水深」のフクザツな関係とは?
身近なふしぎ現象を、数式なしでわかりやすく解き明かす。
ご存じですか? 波の意外な素顔。
・波はどう成長するのか?――波にも「年齢」がある!
・「停止した波」はなぜ存在しない?――これ以上遅くなれない「最低スピード」がある!
・海水浴で危ないのはどこ?――「波の静かな場所」が要注意!
・「波の高さ」って?――じつは、予報の2倍の高さの波が来る!

コミュ障 動物性を失った人類 正しく理解し能力を引き出す
ブルーバックス
周りから注目されたい、聞く耳を持たない、話をしているときに相手と目を合わせない、悪意のない欺き、ひきこもり、……。学校や会社、就活でも挫折しない! 現代社会で生きづらい思いをしている人たちへの処方箋。(ブルーバックス・2015年6月刊)
最近、学校や会社の中で人と上手に話ができなかったり、他人の話をちゃんと聞けない人が目立つという。自分の言いたいことだけ言ったら、他の人の言うことには耳を貸さない、相手の目を見て話ができない、等々。いったい、「コミュ障」とはどういう人なのか? 本書では、「コミュ障」の人たちの特異な言動を、脳の情報処理系から分析していきます。すると、意外な発見が……。じつはコミュ障の人には他の人にはない社会を突き動かす能力が備わっているというのです。さらに、こうした情報処理能力は、動物的な処理経路を捨て去ることで実現していると。つまり、コミュ障の人たちは、より人間らしい人間と言い換えることができるのです。ますます住みにくくなってきた現代社会をどう生き抜いていったらいのか、そのヒントがここにあります。

分子レベルで見た触媒の働き 反応はなぜ速く進むのか
ブルーバックス
化学反応には触媒が必要であるということは、化学を学んだ人なら誰でも知っていることです。では、なぜ触媒は、触媒としての働きをするのでしょうか? それを解き明かすには、触媒の表面で起こっていることを、分子レベルで調べる必要があります。本書は最新の表面科学の研究で明らかになったミクロでダイナミックな触媒の働きを、高校化学のレベルの化学の知識で、興味深くかつ分かり易く解説します。
透明な液体の過酸化水素水に二酸化マンガンの真っ黒な粉を入れると、ブクブクと酸素の泡が発生した。多くの人にとって、触媒との出会いはこの実験だったと思います。化学を学んだ人にとっては、触媒の重要性は言うまでもないでしょう。化学反応を進めるためには、触媒はほぼ必須です。
では、なぜ触媒は「触媒の働き」を示すのでしょうか?
本書は、最新の表面科学によって明らかにされつつある「触媒の働く仕組み」を、やさしく興味深く解説します。

数学ロングトレイル 「大学への数学」に挑戦 じっくり着実に理解を深める
ブルーバックス
初めは面倒かもしれないがそのうち慣れてきて、だんだんスピードも上がってくるはず。受験生なら自分の使った教科書を、大人なら子供さんのものをちょっと借り、それらを傍らにおいて、自分の知識を確認しつつ読み進めていってほしい。(「はしがき」より) (ブルーバックス・2015年6月刊)
時間をかけて楽しみながら問題にアプローチする。数学はよく山登りにたとえられます。本書は本格的な登山(現代数学)ではなく、高校数学を基本とした丘陵歩きが目的です。とはいえ、最初はきついかもしれませんが、ベースとコツさえつかめれば最後まで読み通せて、また次の頂に挑戦したくなる、珠玉の問題満載の一冊です。現役の高校生はもちろん、学び直しを志す数学の初心者や社会人に最適です。

理系のための研究ルールガイド 上手に付き合い、戦略的に使いこなす
ブルーバックス
実験、論文、学会発表、研究費、特許など、サイエンスの世界で生きる研究者には、知っておくべき数多くのルールがある。研究者として成功するには、ルールを熟知したうえで、ルールを思い切り使いこなす必要がある。本書では、サイエンスの世界の基本的なルールをわかりやすく解説したうえで、「ルールを戦略的に使いこなす」ためのノウハウを多く盛り込んで解説する。(ブルーバックス・2015年6月刊)
実験、論文、学会発表、研究費、特許など、サイエンスの世界で生きる研究者には、知っておくべき数多くのルールがある。こうしたルールは大切だが、ただ守ればいい、という単純なことでもない。研究者として成功するには、ルールを熟知したうえで、ルールを思い切り使いこなす必要がある。
本書は、サイエンスの世界の基本的なルールをわかりやすく解説したうえで、「ルールを戦略的に使いこなす」ためのノウハウを多く盛り込んだ。研究者は大きなビジョンと夢を持ってサイエンスに取り組むことが大切だが、しっかりとルールにしたがって細部を詰められてこそ、大きな仕事になる。あまりにもルールを知らなさすぎたりするのも問題だが、逆にルール違反を恐れて畏縮するのも避けなければならない。
本書は研究者になって間もないか、これから研究者を目指すような、研究者のタマゴといえる方々向けに書いた本だが、ルールを戦略的に使いこなしたいと考えている中堅研究者にも役に立つだろう。

「説得力」を強くする 必ず相手を納得させる14の作戦
ブルーバックス
人間は、ふだんは論理的思考をしていない!「アナロジー思考」+「論理的思考」で迫る、まったく新しい説得力増強法。
説得力とは、自分の主張の味方を増やす現代人最大の武器。なぜ説得に失敗するのか? 人が納得するのはどういうときか? 相手の論理的思考だけでなく、直観を操るアナロジー思考にも働きかけ、スピーディに説得する技法を伝授します。『「分かりやすい説明」の技術』など、累計65万部を超える著者一連の「コミュニケーション・スキル」シリーズの集大成の一冊。これまでのシリーズのエッセンスも惜しみなく詰め込んだ実践決定版です。

世界を動かす技術思考 要素からシステムへ
ブルーバックス
かつて日本は「技術立国」と称され、世界中から注目を浴びていた。ところが日本の技術文化の象徴である「ものづくり」に足を引っ張られる形で世界が推し進めるシステム化に乗り遅れてしまった。いったい、日本の科学技術はかつてのように世界を制することができるのだろうか? その鍵を握るのが「システム科学技術」。「ものづくり」に固執しない、柔軟な発想力に日本の未来がかかっている。
技術立国ニッポンの復活の鍵は「ものづくり精神」からの脱却しかない!
かつて日本は「技術立国」と称され、世界中から注目を浴びていた。ところが日本の技術文化の象徴である「ものづくり」に足を引っ張られる形で世界が推し進めるシステム化に乗り遅れてしまった。いったい、日本の科学技術はかつてのように世界を制することができるのだろうか?
その鍵を握るのが「システム科学技術」だ。「ものづくり」に固執するのではなく、「要素」と「目的」を「適切に結び付ける」柔軟な発想力に日本の未来がかかっている。

群論入門 対称性をはかる数学
ブルーバックス
群の歴史は、方程式の研究に遡ります。1変数のn次方程式の解法について、古代バビロニアから、カルダノ、フェラリ、ラグランジュ、ルフィニ、アーベル、そしてガロアの群論へと発展します。本書は、高校数学の知識でも理解できるようにていねいに解説した群論の初心者のための入門書です。
群論の世界を視覚的に捉える!
あみだくじ、駐車場の移動問題を通して、集合や写像の考え方をまずおさらい。さらに、正多面体、正多角形、15ゲームを通してさまざまな群論の性質に触れ、ガロアの群論の基礎をなす5次交代群とオイラーの「36人士官の問題」を遡りながら群によってあぶりだされる対称性の性質や特徴を垣間見ていきます。
ゲーム感覚で見えてくる群論の不思議な世界が堪能できる。
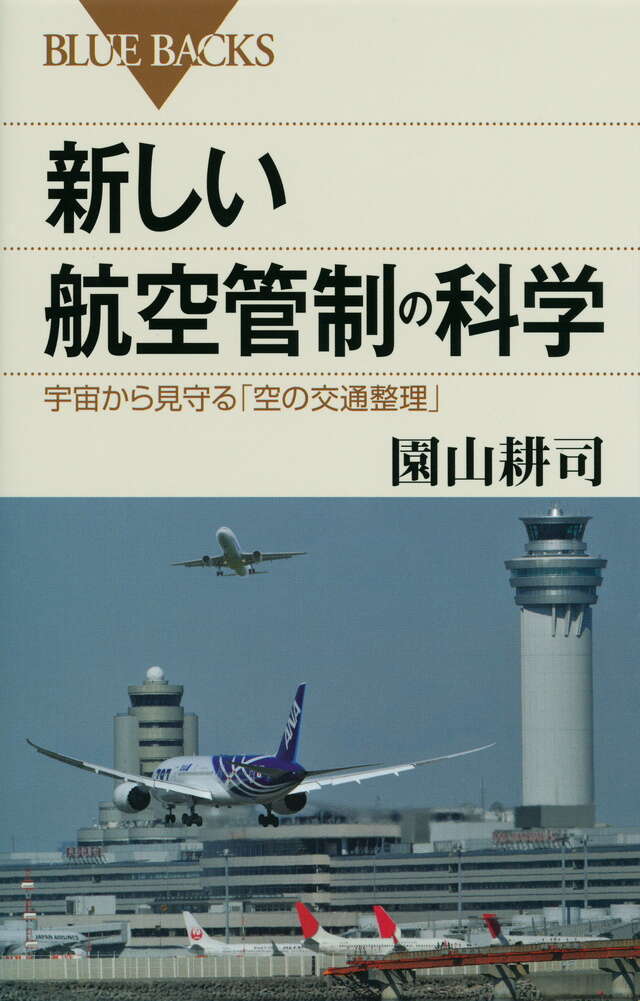
新しい航空管制の科学 宇宙から見守る「空の交通整理」
ブルーバックス
この10年で航空管制は大きく変わりました。人工衛星を利用して空の道を作り、交通整理をすることで、かつて四国ほどの広さに1機しか飛べなかった空に、いまやその3倍以上が航行できるようになっています。本書では、宇宙技術を利用した最新の航空管制システムの全貌を、航空管制の原則や設備・装置、管制官とパイロットのやりとりなども交えて紹介します。
広いと思える「空の道」航空路は絶え間なく飛び交う航空機で意外にもラッシュ。その膨大な航空交通を支える重要な業務の1つが航空管制で、頻繁に離発着し飛び交う航空機が、安全にしかも効率よく航行できるように「交通整理」する仕事です。
この10年で、航空管制には人工衛星を使った技術が大幅に取り入れられ、大きく変わってきました。発展した宇宙技術が、はるか下、地球の対流圏や成層圏を飛ぶ航空機の交通整理にも活かされています。衛星を利用して空の道を作り、衛星を利用して交通整理をすることで、飛び交う航空機が安全に秩序正しく運航できるのです。
現在、日本発着の太平洋路線では、衛星を利用した自動管制が全便数の約半分に達しています。かつて四国ほどの広さに1機しか飛べなかった空に、いまやその3倍以上が航行できるようになっています。コンピューターを搭載し、人工衛星を利用して航行するハイテク機が、飛行の世界に革命をもたらしたのです。
本書では、宇宙技術を利用した最新の航空管制システムの全貌を、航空管制の原則や設備・装置、管制官とパイロットのやりとりなども交えて紹介します。

理系のための英語最重要「キー動詞」43 600超の例文で独特の用法を完全マスター!
ブルーバックス
基本動詞の「理系的」活用法がわかる! 動詞を制する者が、理系英語を制す! 実験報告や特許の出願から、論文執筆まで。徹底した実例主義で、関連表現も同時に習得! (ブルーバックス・2015年5月刊)
科学英語攻略のバイブル! シリーズ10万部突破!
基本動詞の「理系的」活用法がわかる!
「正確に読む」にも「的確に書く」にも動詞が要。
「このデータが証拠となる」はprovideで表現するのが正解。
「方法やプロセスの特徴」を述べるにはinvolveを使う。
同じ「合う」でも、fitとmatch、accommodateはどう使い分ける?
議論に不可欠なassume、「説明や定義」で活躍するbe動詞から、条件が「有利に働く」favor、分析を「受ける」subjectまで。
辞書では見つからない意味・用法がわかり、科学英語の読み書きに必要な英語力が身につく「超実践的」活用辞典。
25年以上かけて収集した活きた実例に学ぶ「原田式」科学英語攻略法。
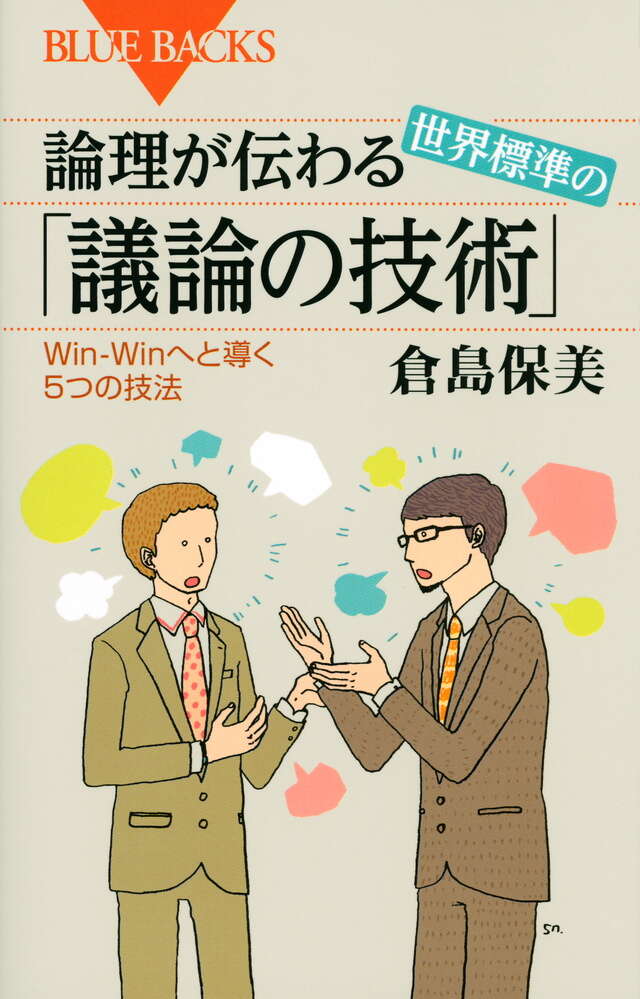
論理が伝わる 世界標準の「議論の技術」 Win-Winへと導く5つの技法
ブルーバックス
日本人は議論が下手、とよく言われます。もしあなたも「議論するのは苦手」だとしたら、それは正しい議論のしかたを知らないからです。議論とは、自分の主張を押し通したり、相手を打ち負かしたりするような勝敗を競うものではありません。Win-Winでベストな成果を導き出す、論理的で生産的な話し合いです。5つの基本技術と、思わず「なるほど」と膝を打つ実例で、議論上手になるテクニックを学んでいきます。
〈内容紹介〉議論を成功させる5つの基本技術
1 伝達の技術 分かりやすい話し方とは?
2 傾聴の技術 議論の流れを正しく把握する方法
3 質問の技術 論点を深める効果的な聞き方とは?
4 検証の技術 間違った意見に惑わされない方法
5 準備の技術 議論のシナリオを作り予防線を張る

やじうま入試数学 問題に秘められた味わいのツボ
ブルーバックス
入試問題の数学といえば、つらい思い出しかないという方は少なくないはず。数学がいやで文系に進んだ人……入試のときのトラウマのせいで数学嫌いにった人は、世に跡を絶ちません。しかし、制限時間とか将来の人生といったプレッシャー抜きに問題をながめれば、入試数学はそれほどイヤな奴ではありません。出題者の意図をあれこれ探りつつ、にっくき入試数学の出来不出来を評価しながら観賞するのも一興でしょう。
入試問題の数学といえば、つらい思い出しかないという方は少なくないはず。数学のせいで志望校に落ちた人、
数学がいやで文系に進んだ人……入試のときのトラウマのせいで数学嫌いになった人は、世に跡を絶ちません。
しかし、制限時間とか将来の人生といったプレッシャー抜きに問題をながめれば、入試数学はそれほどイヤな奴ではありません。
出題者も血の通った人間、そして何より数学が好きな人たちです。問題からは彼らがそこに込めた思いが、意外なほど見えてくるのです。
数学のウンチクを語りたがる問題、受験生に熱いメッセージを贈る問題、世の中の厳しさを教えようとしている問題、
数学のおもしろさを堪能できる問題、思いもよらない答えになる問題、見かけのわりに深みがない問題など……
出題者の意図をあれこれ探りつつ、にっくき入試数学を逆に、出来不出来を評価しながら観賞するのも一興ではないでしょうか。
歴史作家にして数学書『13歳の娘に語るガロアの数学』(岩波書店)で日本数学会出版賞も受賞している著者が、中学から大学まで、
膨大な入試問題を渉猟して選んだ29題の「ネタになる入試問題」。ぜひ気楽に、寝ころがってながめてみてください。
数学好きの方はおおいにマニア心をくすぐられ、数学嫌いの方も久しぶりに会う仇の意外に憎めない素顔に気づくはずです。
※たとえばこんな問題があります。
●古代エジプトの分数にあやかった問題 ●「ダイハード3」に登場した油分算 ●未解決問題「コラッツ・角谷予想」からとった問題
●フェルマーの定理をモチーフにした問題 ●優しそうに見えて鬼畜のような問題 ●1が99個(!)並ぶ問題 ●世界一短い?問題
●ゆとり教育批判と言われた東大の問題 ●受験参考書が間違えた問題など(くわしくは目次をご覧ください)

マンガ おはなし物理学史 物理学400年の流れを概観する
ブルーバックス
物理学者たちはいかに新しい理論を生み出したのか――実験と理論の融合、電気と磁気の統一、超ミクロの世界、光速と重力場。古典物理学の時代では力学と電磁気学を学び、電気と磁気が統一される前夜に遭遇。現代物理学の時代では量子力学と相対性理論という、光速に近い運動や重力場といった、われわれの想像を超えた領域に引き込まれていきます。(ブルーバックス・2015年4月刊)
舞台は大きく2つの時代で繰り広げられます。古典物理学の時代では力学と電磁気学を学び、
電気と磁気が統一される前夜に遭遇。
現代物理学の時代では量子力学と相対性理論という、光速に近い運動や重力場といった、われわれの想像を超えた領域に引き込まれていきます。
高校生3人組が歴史上の科学者たちを直撃しながら、物理学発展の舞台裏を臨場感豊かにレポートします。
第1章 力学―――――ガリレオ、ケプラー、ニュートン
第2章 電磁気学―――ホイヘンス、ヤング、フレネル、フーコー、ファラデー、マクスウェル、
第3章 量子力学―――プランク、レントゲン、ベクレル、J.J.トムソン、ラザフォード、ボーア、パウリ、ボルツマン、ハイゼンベルク、シュレーディンガー
第4章 相対性理論――ローレンツ、ポアンカレ、アインシュタイン、ディラック、ミンコフスキー
エピローグ――――――湯川秀樹、朝永振一郎、小柴昌俊、南部陽一郎、益川敏英、小林誠
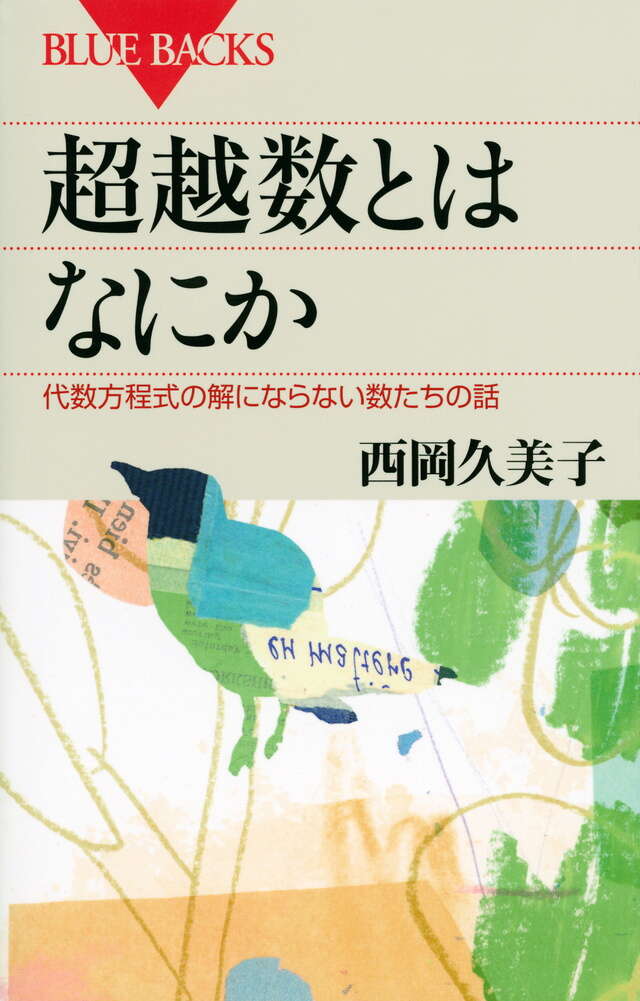
超越数とはなにか 代数方程式の解にならない数たちの話
ブルーバックス
無理数の中には、さらに「超越数」と呼ばれる不思議な数たちがいます。πやe、2のルート2乗がその代表です。超越数は無理数の中でも、「代数方程式の根にならない無理数」のことです。つまりπやeは、どのような代数方程式を作っても、その根になることはありません。本書では超越数の性質やその調べ方を、できるだけ易しく解説します。数学好きの読者へのプレゼントです。(ブルーバックス・2015年4月刊)
πやeを解とする代数方程式は
決して作ることはできません。
さらに2のルート2乗を解とする代数方程式も
作ることができません。
無理数の中には、さらに「超越数」と呼ばれる
不思議な数たちがいます。
無理数であるにもかかわらず、
どんな代数方程式の解にならない数たちです。
本書ではこの不思議な数たちの性質や調べ方を、
できるだけ易しく解説します

研究を深める5つの問い 「科学」の転換期における研究者思考
ブルーバックス
科学や技術を取り巻く状況が変化していくなか、研究者はどのように考え、行動すべきなのか。それらの根源となる「研究者思考」を自力で探究できるようにするのが本書である。1000件を超すプレゼン指導経験から著者が見いだした「研究の本質」について、未来ある若手研究者に向けてわかりやすい言葉で問いかけながら案内する。(ブルーバックス・2015年4月刊)
科学や技術に対する社会の信頼が揺らいでいます。このような時代において、これまでと同じように「論文を書いていればいい」「自分の専門領域を対象とした研究をがんばればいい」というだけでは、優れた研究成果をあげることが難しくなっています。では、研究者はどのように考え、行動すべきでしょうか。その根源となる「研究者思考」を、研究者自身で探究できるようにするのが本書です。
スライドやポスターの添削など、これまで1000件を超すプレゼン指導経験から著者が見いだした「研究の本質」について、未来ある若手研究者に向けてわかりやすい言葉で問いかけながら案内していきます。
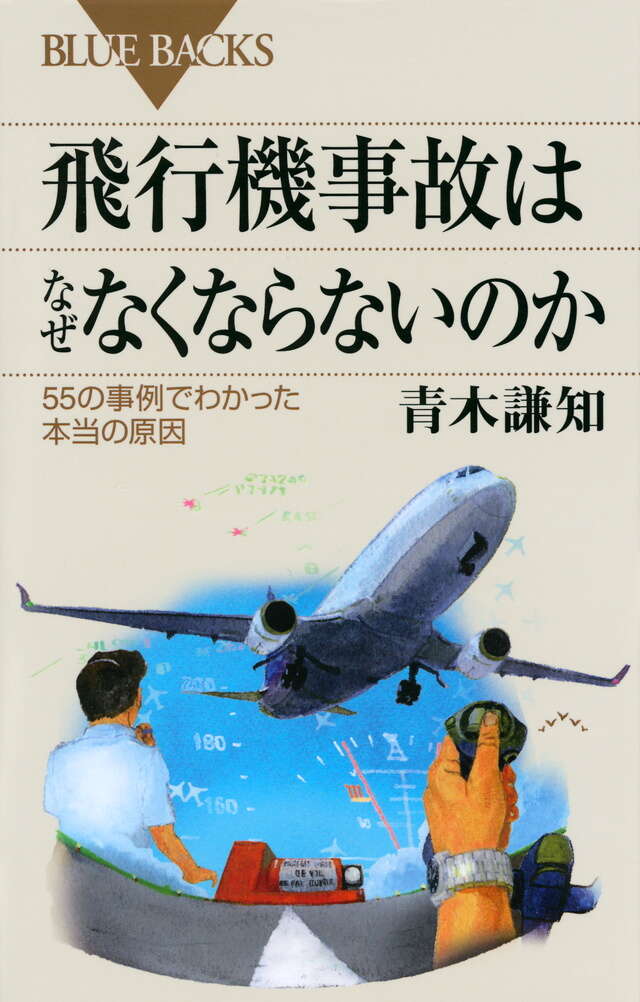
飛行機事故はなぜなくならないのか 55の事例でわかった本当の原因
ブルーバックス
飛行機事故による死者は、全世界で年間500人程度である。飛行機による重大事故の発生率は年々減る傾向にあるが、事故はゼロになっていないし、今後ゼロになることもあり得ない。一方で、事故をゼロに近づけようという努力は常に続けられてきている。本書では、過去の飛行機事故の事例を分析し、事故はなぜ起きたかを検証したうえで、事故を減らすために機材や安全装置がどのように進歩してきたかを解説する。
飛行機事故による死者は、全世界で年間500人程度である。自動車事故に較べると飛行機事故で死ぬ確率は圧倒的に低い。しかし、確率論でいえば、ジャンボ宝くじの1等にあたる確率よりも高い。飛行機による重大事故の発生率は年々減る傾向にあるが、事故はゼロになっていないし、今後ゼロになることもあり得ない。
一方で、事故をゼロに近づけようという努力は常に続けられてきている。本書では、過去の飛行機事故の事例を分析し、事故はなぜ起きたかを検証したうえで、事故を減らすために機材や安全装置がどのように進歩してきたかを解説する。
空の旅は絶対に安全とはいえないが、制度や技術などは常に更新され、安全性は高まってきている。そのことを理解して、空の旅を安らぎを持って楽しんで頂く一助になれば幸いである。

サイエンス異人伝 科学が残した「夢の痕跡」
ブルーバックス
過剰な刺激を欲し続ける現代人にとって、20世紀科学の発明・発見の舞台裏こそリアリティを体感できる大人の遊園地だ。
かつて、電気から電波、エレクトロニクスへと発展していくにつれて消え去った「実体」が、21世紀になって、「科学家電」と呼ぶべきスマホなどの登場でよみがえり、科学が「手触り」の世界に戻ってきた。科学がふたたび人間と機械を通して語られ、未来の科学はもはやSFではなくなった。20世紀に突如として現れた発明品と発明者の伝記を読み解くことで、いままた現代科学が「素人にも理解できる」機械と人間からなる実体(リアル)へと変わる。

ロジックの世界 論理学の哲人たちがあなたの思考を変える
ブルーバックス
論理学はこんなにすごい!
論理学というと、哲学や思考力を鍛えるものというイメージの方が多いのではないでしょうか? 実は、論理学は哲学だけでなく、数学や物理など近代科学の基礎になっているものでもあります。本書では、そんな豊かで実力十分の「ロジック」の世界を、歴史を追いながら、応用も含めて解説していきます。