講談社文芸文庫作品一覧

ルイズ 父に貰いし名は
講談社文芸文庫
講談社ノンフィクション賞!
運命の子から、自立した人へ事実に肉迫する記録者の目が人と時代を照射する
国家権力によって虐殺されたアナキスト大杉栄と伊藤野枝。父母の遺骨を前に無邪気にはしゃいでいた末娘のルイズは、父の名づけた革命家の名と“主義者の子”の十字架を背負い、戦前戦後を平凡に生きた。そして、やがて訪れた、一人の自立した人間としての目覚め。一年六ヵ月に亘る聞き取りと事実に肉迫する記録者の視線が、一女性の人生と昭和という時代を鮮やかに照射する。講談社ノンフィクション賞受賞作。
鎌田 慧
この作品のサブタイトルが、「父に貰いし名は」と題されているのは、せっかく両親がつけた革命的な名前を、改名させた社会の圧迫への抗議がこめられている。(略)留意子がルイにもどるまでの喘ぎが、この作品の重い通低音となっているのだが、苦難の生活のなかから、彼女はしだいに両親の活動を意識するようになり、それをすこしでも引き受けようとする。さわやかに自立の道を歩きはじめたルイと出会った著者の感動が、熱烈な取材交渉と長期のインタビューとなって、ここに結実した。――<「解説」より>
※本書は『松下竜一 その仕事17 ルイズ――父に貰いし名は』(平成十二年三月、河出書房新社刊)を底本としました。

私の東京地図
講談社文芸文庫
講談社文芸文庫スタンダード006
知らぬ道にも踏みいり、袋小路に迷いぬいたこともある。ある時は、人に連れ立たれて、歩調を揃えて気負って歩いた道。それらの東京の街は、あらかた焼け崩れた。焼けた東京の街に立って、私は私の地図を展げる。私の中に染みついてしまった地図は、私自身の姿だ。
芥川龍之介、中野重治、小林多喜二らとの出会い、結婚、自殺未遂、出産、離婚、同棲……といった人生を、作家活動や非合法活動で当局に弾圧を受け始めた太平洋戦争へと突入する時代を背景にし、上野、日本橋、神楽坂など、親しんだ東京の街々を生き生きとした人々の息吹のなかに描いた連作短篇集。自らの過去を探り、自らを確かめるような筆が心に響く。
東京が佐多稲子の心象風景として鮮やかに描かれる
――東京の日常――押上橋を渡って京成電車の停留所の横の狭い道を抜けてゆく。石畳の道は、魚屋の水に濡れて、どろどろになっている。ひと山十銭、五銭と盛り上げた八百屋、うどんの玉を売っている店、豆腐屋などごたごたした道は、おかみさんや労働者ですれちがって歩くほど。――そして、関東大震災――大きな建物ごと、ガチャーン、ガチャーンと揺すられるたびに、私は自分を、大きな箱の中に入れられた玩具のひとつのように感じた。だがその箱の周囲は広くて、高くて、箱そのものがいつもの高い天井よりもずうっと恐ろしかった。
講談社文芸文庫スタンダードは、時代の原基としての存在感をたたえ、今なお輝きを放つ作品を精選した新装版です。
※本書は、講談社『佐多稲子全集』第四巻(昭和53年3月刊)を底本としました。

順番が来るまで
講談社文芸文庫
文士が生きた昭和の風景!
「年のせいか、ふしぎとほんとうのものが見えるようになった」
昭和文壇を生き抜いた老文士。珠玉のメモワール集!
「世上のくるしみをくるしみとすべからず」――貧窮の底で筆一本に己を託した樋口一葉。その存在を光とし、長い不遇に堪えた最晩年『接木の台』『暗い流れ』を著し文学史にその名を刻んだ和田芳恵最後の随筆集。生家が破産、石もて追われた故郷北海道の思い出、編集者として接した林芙美子ら作家の愛憎交々の回想、死の“順番”を待つ老年の心境を明澄に描く表題作五二篇。削りに徹した滋味深い文章は正に職人芸!
大村彦次郎
この歳月の前後、日本の文士社会は衰滅した。よくもわるくも文壇を代表するような、個性的なキャラクターの持主が相次いで姿を消していった。(略)時代が変ったのである。それまで文士の生きかたを支えてきた社会的基盤が崩れ去った。和田さんはその最期に立ち会うかのように、文壇を船にたとえれば、その船の<底荷>のような役割を果たして、消えていったような思いがする。――<「解説」より>
※本書は、北洋社刊『順番が来るまで』(昭和53年1月)を底本としました。

小林秀雄全文芸時評集 下
講談社文芸文庫
時代を超えた若き「文芸時評集」
文学と時代を語り文芸時評の行く末をも見定めた小林秀雄
昭和九年の後半から、文芸時評から身を退く昭和十六年八月までの二十七篇を収録。時代は日中戦争へ、さらには太平洋戦争へと緊迫するなか、マルクス主義壊滅後の中心的批評家として、いかなる文芸時評が可能であったか。戦争目的の是非を論ずることの無意味さをいだきつつ、「当麻」「無常といふ事」「西行」など一連の古典論へと沈潜していくその後の小林を予感させる、貴重な一冊。
山城むつみ
どんなに緻密な解釈であれ、解釈は原文に限りなく漸近することができるだけで、決してこれに追いつくことはできない、いわんや追い越すことなどありえない。これは昭和十年以降、小林が自分に課した「批評的創作」の命法にほかならない。――<「解説」より>
※本集は、掲載紙誌において、「文芸時評」「文芸月評」と銘打たれた作品を集成したものです。底本は、新潮社刊『小林秀雄全作品』5~14(二〇〇三年二月~二〇〇三年十一月)としました。

第三の新人名作選
講談社文芸文庫
戦後新世代の魅力的作家群
近代文学でもっとも人気も実力もある「第三の新人」。
その魅力的短篇選。
第三の新人、と称された戦後新世代の作家達は、のちに、文壇の中心的存在となっていく。十人十作品を精選。阿川弘之「年年歳歳」、遠藤周作「アデンまで」、小沼丹「白孔雀のいるホテル」、近藤啓太郎「海人舟」、小島信夫「アメリカン・スクール」、島尾敏雄「湾内の入江で」、庄野潤三「プールサイド小景」、三浦朱門「冥府山水図」、安岡章太郎「ガラスの靴」、吉行淳之介「驟雨」収録。
富岡幸一郎
読者は本書の各作品を通読すれば納得されるだろうが、ここには今日でも(いや、むしろ現在の地平においてこそ)、まさに「新しい」と驚嘆させずにはおかない文学の瑞々しい魅力が溢れているからだ。一個一個の短編は、当然のことながらその主題も内容、個性も全く異にする。しかし、作品の言葉の奥底に降りていくと、ある共通する普遍的ともいえる感性の層に突き当る。――<「解説」より>

小林秀雄全文芸時評集 上
講談社文芸文庫
知性のドラマを批評へとたかめ近代を拓いた新しい文芸時評
懸賞評論「様々なる意匠」二席入選の翌年(昭和五年)、「アシルと亀の子」で、文芸時評家として文壇に登場した小林秀雄。当時隆盛を極めたマルクス主義文学の観念性を衝き、また心理小説、私小説、行動主義等、あらゆる文学潮流にも与することなく、孤高を持し、本質的で独創的な論を展開。そこには個々の作品を論じつつも、批評という行為それ自体を問う、<近代批評>誕生のドラマがあった。
小林秀雄
文学という形はその影をもっている。瞬時も同じ格好をしていない人間の心という影をもっている。作品という死物に、命を与える人間の心は、社会の鏡でもなければ、又、社会は人間の心の鏡でもないのである。文学に関する困難は、ただこの影の世界を覗くにある。――<本書収録「文学と風潮」より>
※本集は、掲載紙誌において「文芸時評」「文芸月評」と銘打たれた作品を集成したものです。底本は、新潮社刊『小林秀雄全作品』1~5(二〇〇二年十月~二〇〇三年二月)としました。

現代沖縄文学作品選
講談社文芸文庫
戦争、占領、基地に呻吟し続ける沖縄の心を鮮やかに描出する秀作十篇。
独自の文化の基層をもつ美ら国・沖縄。また、戦争・占領・基地に、今なお翻弄される沖縄の心を鮮烈に描出する秀作短篇十。
大城立裕「棒兵隊」
安達征一郎「鱶に曳きずられて沖へ」
又吉栄喜「カーニバル闘牛大会」
山入端信子「鬼火」
目取真俊「軍鶏」
大城貞俊「K共同墓地死亡者名簿」
長堂英吉「伊佐浜心中」
崎山麻夫「ダバオ巡礼」
山之口獏「野宿」
崎山多美「見えないマチからションカネーが」
川村 湊
(近代の)作品が、そうした“二重性”(日本本土と沖縄)の葛藤にその存在の根を下ろしていたのに対し、沖縄の「戦後小説」は、むしろ日本を相対化するアジア的な広がりや、アメリカと対峙する沖縄の政治的な緊張関係のなかに位置づけられていたといってもよい。(中略)それは、戦前のヤマト世(ゆ)としての日本の半植民地支配、そして戦後のアメリカ軍政支配下の時代(いわゆるアメリカ世(ゆ))の双方から沖縄が独立することの方向性を模索していた(後略)。――<「解説」より>
※本書は、下記の雑誌及び刊本を底本として使用しました。
安達征一郎『憎しみの海・怨の儀式』インパクト出版会/2009年5月
大城貞俊『G米軍野戦病院跡辺り』人文書館/2008年4月
大城立裕『大城立裕全集9』勉誠出版/2002年6月
崎山麻夫『沖縄短編小説集2』琉球新報社/2003年5月
崎山多美「すばる」集英社/2006年5月
長堂英吉『エンパイア・ステートビルの紙ヒコーキ』新潮社/1994年2月
又吉栄喜『パラシュート兵のプレゼント』海風社/1988年1月
目取真俊『魂込め』朝日新聞社/1999年8月
山入端信子『沖縄文学全集9』国書刊行会/1990年9月
山之口獏『沖縄文学全集6』国書刊行会/1993年3月

交遊録
講談社文芸文庫
牧野伸顕、河上徹太郎、中村光夫、石川淳、D・キーン、吉田茂……
生きる勇気を与えてくれる友達がいることの喜び――。
生きる勇気を与えてくれる、友達がいるということの喜び――生涯に出逢った友達のことを順番に綴る交遊録。幼少の頃から親しみ、尊敬してやまなかった祖父・牧野伸顕、ケンブリッジ留学時代の恩師・ディッキンソンとルカス、文学の師・河上徹太郎はじめ、中村光夫、横光利一、福原麟太郎、石川淳、D・キーンら文士達、そして父・吉田茂。時間の流れの中で、成熟してゆく友情を見事に描いた名エッセイ。
池内 紀
吉田健一の『交遊録』は日本語で書かれた人物エッセイのなかで、とびきり個性的で、そしてもっとも優れたものだろう。あとにも先にもこれに並ぶものが二度とあらわれるとは思えない。一つには書き手の条件とかかわっていて、当然のことながら、資質、才能、人物を見る眼が必要である。いま一つには――こちらがより大きな理由だが――書かれる側の条件と関係していて、一人の人間が生涯に、これだけ書くに値する人物と出くわすなど、まずありえないことだろうからだ。――<「解説」より>
※本書は、1993年6月新潮社刊『吉田健一集成3』を底本としました。

黙阿弥
講談社文芸文庫
黙阿弥の真の姿と心の奥の風景を描く曾孫からの鎮魂の評伝。
ーー坪内逍遙に“明治の近松、我国のシェークスピア”と称された河竹黙阿弥。その78年の生涯を、秘蔵の原稿や手記をもとに、曾孫にあたる著者が心をこめて描いた評伝。幕末から明治への激動の時代を生きた黙阿弥の作者魂と、江戸作者の矜持。それは現代にも通じるひとつの「生」の記録でもある。
◎松井今朝子 黙阿弥没後百年目に上梓された単行本の「あとがき」に、著者は「私が書こうとしたのは、狭義にいう伝記でも論文でも、評論でもない」と記しているが、書き出しはまるで時代小説のようだ。そして読み進めるうちに、その資料の厚みと考察の確かさによって、へたな時代小説よりもはるかに面白い読み物だということに気づかされる。演劇学の泰斗にこれほど読みやすくて面白い著作があれば、もはや小説書きの出番はなかろう。――<「解説」より>
※本書の初出は、「別冊文藝春秋」(1991年夏~1992年秋)に「孤影の人」という題で発表され、単行本は、文藝春秋より1993年2月に『黙阿弥』と改題され刊行しました。底本は、文春文庫『黙阿弥』(1996年)を使用し、著者により若干の訂正をいたしました。

風媒花
講談社文芸文庫
講談社文芸文庫スタンダード005(講談社文芸文庫スタンダードは、時代の原基としての存在感をたたえ、今なお輝きを放つ作品を精選した新装版です。)
日本と中国との間には断崖がそびえ、深淵が横わっている。その崖と淵は、どんな器用な政治家でも、埋められないし、跳び越せもしない。そこには新しい鉄の橋のための、必死の架設作業が必要だった。頽れる堤と頽れる堤のあいだに、何度、いいかげんな橋を渡しても、無駄であった。贋の橋や仮りの橋は、押し流されるより先に、ひとりでに腐り落ちた。峯たちには、架けねばならぬ新しい橋の姿が、おぼろげながら想像できた。
作家・峯三郎を視点とし戦争直後の中国文化研究会に焦点をあて、群像劇にとどまらず……拳銃の暴発、青酸カリ混入、といった事件の大きな波に登場人物たちが飲み込まれていく姿を描く。憧れの象徴である中国大陸の文化と歴史に対する、さまざまな立場からの考証が作品の底に流れる戦後文学の記念碑的傑作であり、著者の代表作。
<中国文化研究会のメンバー>
●軍地先生――頭のハチ割れそうな難しい顔つきしているけれど、みんなをギューギューいじめっころがす。
●新聞社の西さん――気の弱そうなやさ男だけど、可哀そうなほど正直なひと。
●失業中の中井さん――三亀松の声色もへたなくせに、いつまでも「湯島天神お蔦涙の別れ」を止めようとしなかった。
●梅村先生――エンサイクロペジアって悪口言うけど、何を聴いても「アッそれは」って答えられるから、たいしたもんだわ。……そして作家の峯三郎などなど。
彼らと情人蜜枝、桃代が織り成す戦後文学の記念碑的作品
※本書は、筑摩書房『武田泰淳全集』第4巻(1971年8月刊)を底本として、講談社文芸文庫版(1989年3月刊行)を適宜参照し多少ふりがなを加えました。

読書清遊 富士川英郎随筆選
講談社文芸文庫
詩を愛し本に遊ぶ最後の文人学者 富士川英郎の高雅な世界
独文学者が五十代半ば過ぎて著した『江戸後期の詩人たち』。日本に漢詩人ありと知らしめ、読書界を驚倒させた著者が、以後堰を切って上梓した文学随想から二九篇と詩三篇を精選。リルケ、ゲーテらドイツの詩人、菅茶山始め江戸漢詩人と並び、幼い頃、市電で乗り合わせた「神采奕々」の老紳士森鴎外を追想する「父富士川游のこと」、愛してやまぬ萩原朔太郎を語る「郷愁の詩人」など、“最後の文人学者”富士川の悠々闊達な世界。
高橋英夫
文人の拠って立つ詩、詩文と、学者の拠りどころ学問とは、近くもあるが隔り、ずれもある。次元が違うともいえよう。ところが僅かな幾刻か、微妙なタイミングによってなのか、詩文と学問とが重なり合うことがときどきある。ただ、重なりによって濁りは生ぜず、結ぼれがほどけたような晴れ晴れとした気圏がそこに拡がる。そういう気圏を感知し、その気圏の中に立ちつくす人、それが文人学者であろう。――<「解説」より>

折口信夫天皇論集
講談社文芸文庫
日本的な権威とはなにか? 折口学の新たな視座
日本人の宗教とはいかなるものか? また、神道とは日本人にとっての宗教なのか? 近代人として生きながら、自在に古代との間を往還する精神を持ちえた民俗学者が迫った日本的な政治や権力のあり方の本質とは――
『折口信夫文芸論集』編者安藤礼二によるオリジナル編集でうかびあがる、知の巨人・折口信夫の新たな姿。
安藤礼二
折口信夫は生涯、天皇という存在に取り憑かれていた。一体なぜ天皇だったのか。それは、折口信夫が民俗学者であると同時に国文学者だったからだ。しかも折口の国文学の起源は、近代のアカデミズムには存在していない。折口は自身のことを、江戸期の本居宣長、そして平田篤胤が異様な情熱とともに確立することを目指した「国学」に連なる最後の思想家として位置づけていた(柳田國男も同様である)。――<「解説」より>
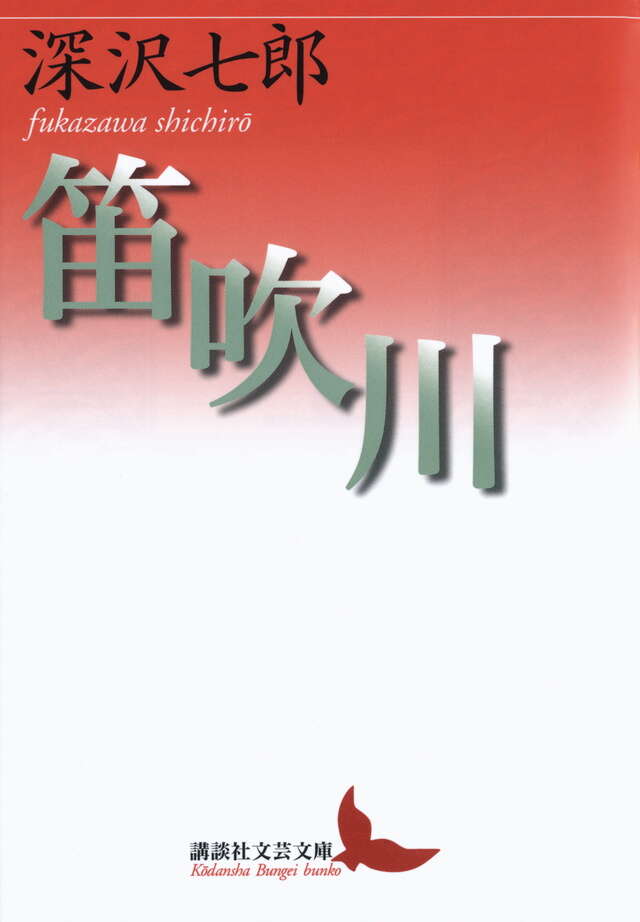
笛吹川
講談社文芸文庫
生まれては殺される、その無慈悲な反復。
甲州武田家の盛衰と、農民一家の酸鼻な運命。
信玄の誕生から勝頼の死まで、武田家の盛衰とともに生きた、笛吹川沿いの農民一家六代にわたる物語。生まれては殺される、その無慈悲な反復を、説話と土俗的語りで鮮烈なイメージに昇華した文学史上の問題作。平野謙との<「笛吹川」論争>で、花田清輝をして「近代芸術を止揚する方法」と言わしめ、また後年、開高健をして「私のなかにある古い日本の血に点火しながらこの作品は現代そのもの」とも言わしめる。
町田康
一般の調節された言葉は、一族の多くの者がそのために殺害されたのにもかかわらず、それを、先祖代々お屋形様のおかげになって、と言い換えることができる。しかし、この小説の言葉は、そう言い換えてしまう人間の哀しみを描きつつ、それすらも無言の側に押し流してしまう。そして、その圧倒的で、どうしようもない事態は、始まりと終わりを持たず循環する。――<「解説」より>

天安門
講談社文芸文庫
アメリカ生まれの著者が、初めて訪れた中国。都市を離れて、中国の奥へ奥へ――そこには現代があった。国境、言語を越え、歴史を遡るアイデンティティの旅。自身に流れる血を通して、自己の存在を、「仮」と「真」の中で映し出そうとした衝撃の作品群。一人の越境者の魂の漂泊は、現代中国の真の姿を求める。伊藤整賞受賞作「仮の水」を含む、鮮烈の短篇五作。

傷ある翼
講談社文芸文庫
“生きて、飛ぶことを願った”ひとりの女の物語。
戦争にのめり込んでゆく時代を舞台に、一子の母となった主人公・宗像滋子の打算的な結婚生活の不幸――粗野な夫への憎悪と軽蔑、先輩作家との逢瀬を続けながらも、離婚にも踏み切れない理性と情念の相剋を描く。夫婦とは、家庭とは、愛とは、性とは何かを追求し、「傷のある翼をもった鳥のように生きて、飛ぶことを願った」円地文学の内奥に迫る力作。谷崎賞受賞作『朱を奪うもの』三部作の第二部。
岩橋邦枝
この豊潤な小説は、夫婦の相剋が日常化した結婚生活にしても、滋子のかかえる鬱屈にしても、私小説的リアリズムで書けば陰々滅々としたものになるだろう。作者は、私小説の主人公中心の書き方もしていない。滋子が宗像へあびせる苛烈で意地悪な目は、彼女にも向けられる。彼女のみじんも甘えのない自己批評、自己認識は、一人の知的な女性の内面をえぐって読者を納得させる。――<「解説より」>

柄谷行人中上健次全対話
講談社文芸文庫
若き日の出会い以来、常に世界的視野で表現を続けた批評家と作家の軌跡
一九六八年、遠藤周作が編集長をつとめる「三田文学」編集室に若い批評家と小説家が呼び出された。
この奇蹟の出会いによる鮮烈な印象は、互いの記憶に深く刻みこまれた。やがて日本文学の立役者となった二人は、常に相手を、さらに世界を強く意識し、「協働」するに至る――
批評家・柄谷行人と小説家・中上健次の全対談と往復書簡を収録する画期的な対話集!
中上
正義は正義だ。不正義は不正義だ。それを言わないとどうしようもない、というところに来ています。このままでは、文学が成り立たなくなる。
柄谷
僕は、ちまちましたポストモダン的シニシズムとかイロニーとかにうんざりしている。あんなのは自意識の欠落だよ。シュレーゲルが言ってるんだけど、イロニーの最終形態は真面目になることだ、と(笑)。だから素直にやろう。――<本文より>
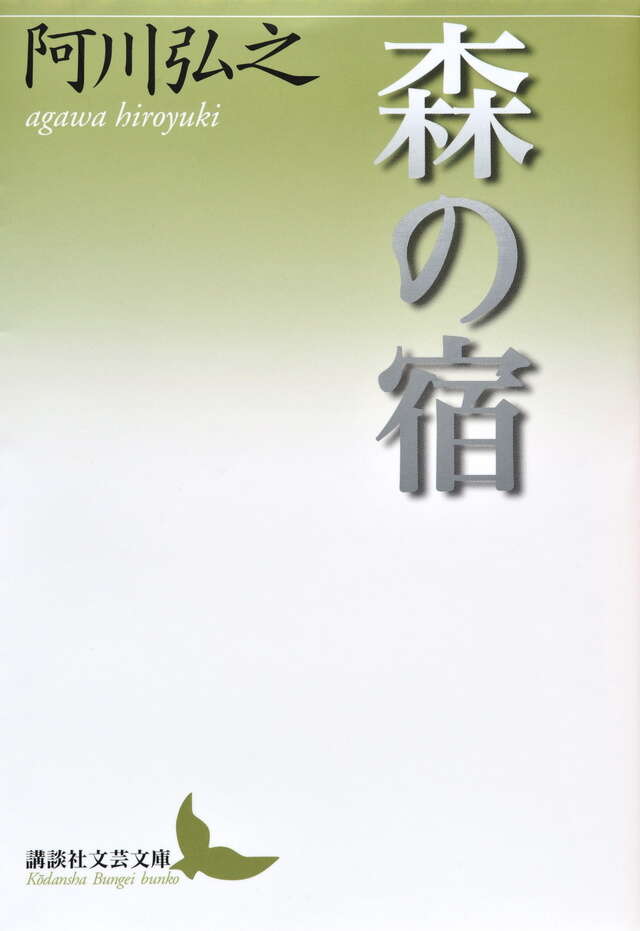
森の宿
講談社文芸文庫
大学生時代、東京と郷里広島との往き返り、尾道を通るのはいつも眼の楽しみであった。船と海が好きだったせいもあるけれど、その頃私は志賀直哉の作品を耽読していて、汽車が尾道にかかると、「暗夜行路」に描かれている通りの風景が車窓にあらわれて来る。対岸は向島、島と本土の間が潮の流れのきつい河のような狭水路になっていて、釣舟がいる、渡しがいる……――<本文より> 愛してやまない鉄道・空・船の旅をめぐる名随筆
愛してやまない鉄道の旅。そして空の旅 海の旅。
文章の達人・阿川弘之の名随筆。旅を楽しみ、乗り物を愛す著者の電車の旅、航空機の旅、船の旅。師と仰ぐ志賀直哉、そして様々な文学者達への思い。
『鮎の宿』『桃の宿』に続く珠玉の随筆集。
阿川弘之
大学生時代、東京と郷里広島との往き返り、尾道を通るのはいつも眼の楽しみであった。船と海が好きだったせいもあるけれど、その頃私は志賀直哉の作品を耽読していて、汽車が尾道にかかると、「暗夜行路」に描かれている通りの風景が車窓にあらわれて来る。対岸は向島、島と本土の間が潮の流れのきつい河のような狭水路になっていて、釣舟がいる、渡しがいる……――<本文より>
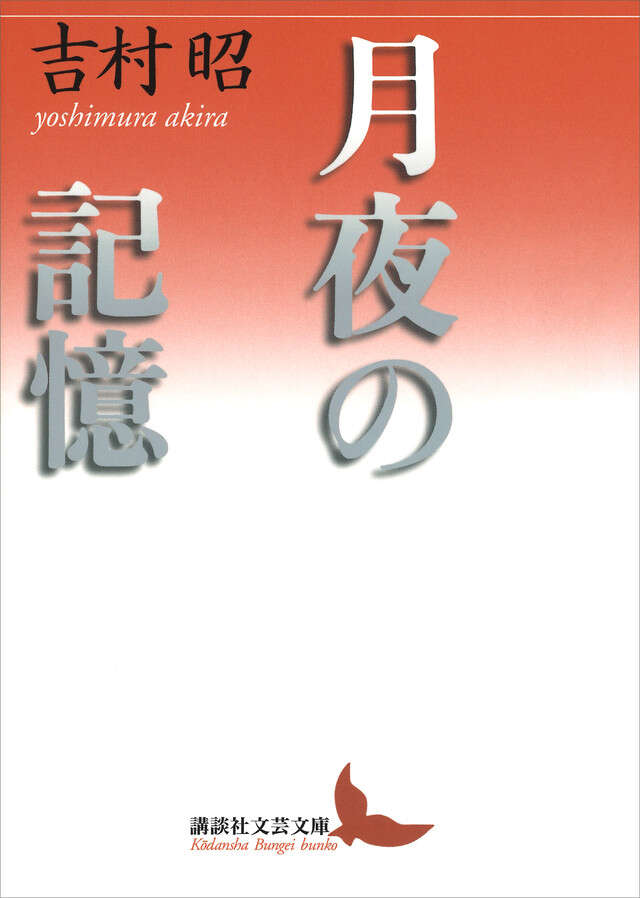
月夜の記憶
講談社文芸文庫
人間の根柢へ、文学の原理へ、深まりゆく作家精神の軌跡!
死を賭して受けた胸部手術、病室から見た月、隣室の線香の匂い、そして人間の業……。終戦からほどない、21歳の夏の一夜を描いた表題作をはじめ、人間の生と死を見据え、事実に肉迫する吉村昭の文学の原点を鮮やかに示す随筆集。自らの戦争体験、肉親の死、文学修業時代と愛する文学作品、旅と酒について、そして家族のことなど、ときに厳しく、ときにユーモラスに綴る。
◎秋山駿ーーこの随筆集は、何を果したのか。読んでいるうちに、わたしは面白いことに気が付いた。かなり以前からわたしは、日本ではあれほど「私小説」が全盛であったのに、なぜ「私哲学」といったものがそれほど出現しないのか、疑問に思っていた。この「随筆」は、数々の優れた長篇小説と対比して言うのだが、吉村さんの「私哲学」だったのではあるまいか。これが、急所だ。(中略)作家吉村昭の全身像が現われる。だから、この随筆集こそ、吉村さんの代表作といっていいものであろう。<「解説」より>

大陸の細道
講談社文芸文庫
講談社文芸文庫スタンダード004(講談社文芸文庫スタンダードは、時代の原基としての存在感をたたえ、今なお輝きを放つ作品を精選した新装版です。)
日本の冬の服装でいきなり満洲にとび込んで来た正介を、満洲の空気は、薄みにつけ込んで、先ず彼の胸のあたりから牙をたてて来たのだ。理由はともかく、最初猛烈な咳が五分間もつづいて、今にも息が切れそうになった。そして焼火箸でも突っこむように胸が疼いて来た時には、正介は自分の命も今夜かぎりかと思った。
すでに日本の敗色は濃厚な昭和十九年暮れ、M農地開発公社嘱託として極寒の満洲に赴いた木川正介は慣れない土地で喘息と神経痛の持病に苦しんでいた。さらに、中立を破り突如参戦したソ連軍を迎え撃つため四十二歳にして軍に召集されてしまう。
世渡り下手な中年作家が生き残りを賭け闘う姿をあたたかく飄逸味あふれる描写で綴った、私小説の傑作。
敗色濃い戦争末期
酷寒の満洲へ渡った木川正介
様々な理不尽に諧謔で挑む文土――
著者渾身の傑作ユーモア長篇

西行百首
講談社文芸文庫
伝統短歌の革命者塚本邦雄が宿敵・西行に挑む最後の闘い。
幻の傑作評論初刊行!
北面の武士として鳥羽上皇の寵愛を受けながら出家遁世した漂泊の人。又、伝説に彩られ、日本人に愛され続ける名歌をあまた残した歌人・西行。伝統短歌への叛逆者にして、「西行嫌ひ」を公言して憚らなかった塚本が、晩年に至って、渾身の力と愛憎を込めて宿敵・西行に闘いを挑んだ快著。高名な歌を情け容赦なく切り捨てる一方、知られざる名歌に眩い光をあてる百選は、正に塚本美学の精髄! 本文庫、初刊。
島内景二
邦雄の西行嫌いは夙(つと)に有名だが、好きでもない歌人の和歌を、百首も評釈することなど不可能である。邦雄にとって、「西行的な和歌」は自らの歌の母胎だった。(中略)『西行百首』は、西行に代表される「日本的な和歌の伝統」と最終決戦を繰り広げるために構想された。邦雄は、自らの内なる西行を斬った。伝統を止揚せねば、正統は結晶できないからである。――<「解説」より>