講談社文芸文庫作品一覧

ボードレールと私
講談社文芸文庫
永遠なるアヴァン・ギャルド
戦前の新詩運動のなかで生み出された画期的な処女詩論「超現実主義詩論」から、晩年の詩的自伝ともいえる随想「ボードレールと私」まで、ボードレールの与えた影響とその変容を軸に、代表的詩論4篇を精選。詩的言語により経験生活を超克し、芸術のための芸術を追究してきた、偉大なる学殖詩人・西脇順三郎。そのアヴァン・ギャルドとしての革新的な試みの背景を理解するための貴重な1冊。
井上輝夫
ここに収められた4編の詩論は、日本近・現代文学が生み出したもっともスリリングな必読の詩論であり芸術論でもある。(中略)西脇の詩作品は普通に考える「詩らしさ」を破るような作法で書かれていて、伝統的詩歌や近代詩あるいは自然主義的な文芸に馴染んだ読者を驚かせる。(中略)それだけ西脇の詩作品が日本の近代文学の流れの中で画期的でアヴァン・ギャルド(前衛)としての革新性をもっていたことになる。(中略)こうした人の意表をつく西脇作品がどのような考えのもとに作られていたのかを理解しようとすると、ここに収録された4編の詩論を読むことは不可欠となる。――<「解説」より>

無限抱擁
講談社文芸文庫
日本近代文学史上屈指の名品
男と女が出会ったのは吉原。春に出会い晩秋に別れた。それから3年目の春、2人は再会する。そしてその年の冬、男は求婚し結婚した。……出会ってから6年目、1月に雪、2月の或る朝、女は息を引き取った。血を吐き死んだ。――著者のストイックな実体験を、切ない純粋な恋愛小説に昇華させ、<稀有の恋愛小説>と川端康成に激賞された不朽の名作。日本近代文学史上屈指の作品。
古井由吉
自分の屈折にかまけて人のことがまるで見えないという難が往々にして、私小説にたいする人の拒絶反応の元になるが、この小説の主人公は、自分が気がついていないということに、やがてまともに気がつく。自己省察は馴れ合いに堕しやすく、気づいたところからさらに屈折の中へ解けて、私小説においてもっとも始末のつかぬところであるのにひきかえ、この主人公の自己省察は際限のなさへ崩れずに立つ。人のことが見えない性格のようで、節々で見えている。――<「解説」より>

わが子キリスト
講談社文芸文庫
征服地ユダヤの完全支配をもくろむローマ政府顧問官の政治的意図によって作り出された救世主、神の子イエス。顧問官の部下で、キリストの実父だというローマ軍の隊長は、ぬきさしならぬ状況の中でイエスの復活を演じることに……。独特の聖書解釈によって生まれた異色のイエス像を描いた「わが子キリスト」に、中国を舞台とした歴史小説2篇を併録。武田泰淳の政治・歴史観を大胆に映した傑作集。
欲望する<世界>が作り出したイエスの誕生、磔刑、そして復活。
征服地ユダヤの完全支配をもくろむローマ政府顧問官の政治的意図によって作り出された救世主、神の子イエス。顧問官の部下で、キリストの実父だというローマ軍の隊長は、ぬきさしならぬ状況の中でイエスの復活を演じることに……。独特の聖書解釈によって生まれた異色のイエス像を描いた「わが子キリスト」に、中国を舞台とした歴史小説2篇を併録。武田泰淳の政治・歴史観を大胆に映した傑作集。
井口時男
「神の子」を自称するイエスは、政治にも経済にも関心がなかったろう。(中略)純粋たらんとする「精神」は無力である。「復活」がその無力な「精神」の究極の勝利を意味するにしても、(中略)この「復活」は、顧問官と「おれ」とユダとマリアと無数の民衆と、つまりは支配も被支配も政治も経済も肉体もひっくるめたこの地上的なるもののいっさいが、協力・合作して成就させたのである。地上的世界は「精神」を排除するが、しかし、その「精神」の「復活」を希求するのもこの地上的世界にほかならない。これは「精神」をめぐる逆説である。――<「解説」より>

日本の童話名作選 昭和篇
講談社文芸文庫
川端康成から壺井栄まで“昭和”の光と影を映し出す名品20!
「赤い鳥」により芸術性を獲得した童話は、昭和に入ると、「少年倶楽部」に代表される大衆化の道を辿った。一方、子どものリアルな現実をとらえる生活童話が書かれ、宮沢賢治、新美南吉など童話作家も登場、独創的な日本のファンタジーが誕生した。お伽噺から文芸の豊かな1ジャンルに変貌をとげる時代の、川端康成、林芙美子、太宰治、坪田譲治、室生犀星、壺井栄など19作家の名品を収録する。
千葉幹夫
「童話の読者が誰であるか……相手は子供であつて文学青年ではない。そこで今日の童話は、物語性を取り戻す事に努力を払はねばならない。大人の文学が物語性を持たないからとて、どうしてそれを真似る必要があらう」(新美南吉/1941年)
昭和の児童文学は困難な時代と共に歩みながら、決して未来への希望を失うことはなかった。また、大正期の童心主義童話と異なり、物語性も獲得した。(略)大人と子供を同時代の目で見るという文学の重要な視点も持ち得たことは、昭和30年代中葉からの高揚期を迎える為に重要な点であった。――<「解説」より>
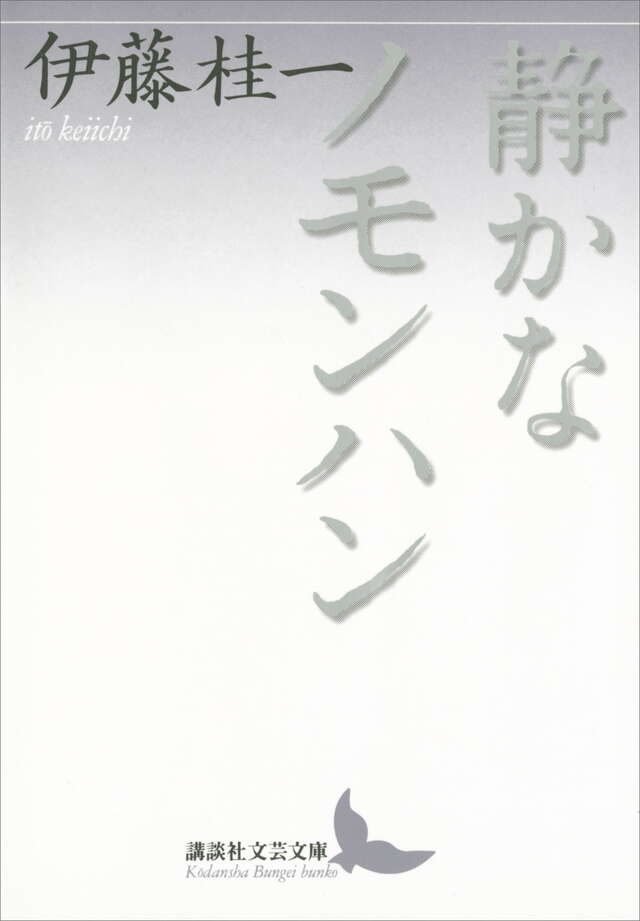
静かなノモンハン
講談社文芸文庫
昭和14年5月、満蒙国境で始まった小競り合いは、関東軍、ソ蒙軍間の4ヵ月に亘る凄絶な戦闘に発展した。襲いかかる大戦車群に、徒手空拳の軽装備で対し、水さえない砂また砂の戦場に斃れた死者8千余。生還した3人の体験談をもとに戦場の実状と兵士達の生理と心理を克明に記録、抑制された描写が無告の兵士の悲しみを今に呼び返す。芸術選奨文部大臣賞、吉川英治文学賞受賞の戦争文学の傑作。

石原吉郎詩文集
講談社文芸文庫
憎むとは待つことだ
きりきりと音のするまで
待ちつくすことだ
詩とは「書くまい」とする衝動であり、詩の言葉は、沈黙を語るための言葉、沈黙するための言葉である――敗戦後、8年におよぶ苛酷な労働と飢餓のソ連徒刑体験は、被害者意識や告発をも超克した<沈黙の詩学>をもたらし、失語の一歩手前で踏みとどまろうとする意志は、思索的で静謐な詩の世界に強度を与えた。この単独者の稀有なる魂の軌跡を、詩、批評、ノートの三部構成でたどる。
石原吉郎
海が見たい、と私は切実に思った。私には、わたるべき海があった。そして、その海の最初の渚と私を、三千キロにわたる草原(ステップ)と凍土(ツンドラ)がへだてていた。望郷の想いをその渚へ、私は限らざるをえなかった。(中略)1949年夏カラガンダの刑務所で、号泣に近い思慕を海にかけたとき、海は私にとって、実在する最後の空間であり、その空間が石に変貌したとき、私は石に変貌せざるをえなかったのである。(中略)望郷のあてどをうしなったとき、陸は一挙に遠のき、海のみがその行手に残った。海であることにおいて、それはほとんどひとつの倫理となったのである。――<本文「望郷と海」より>
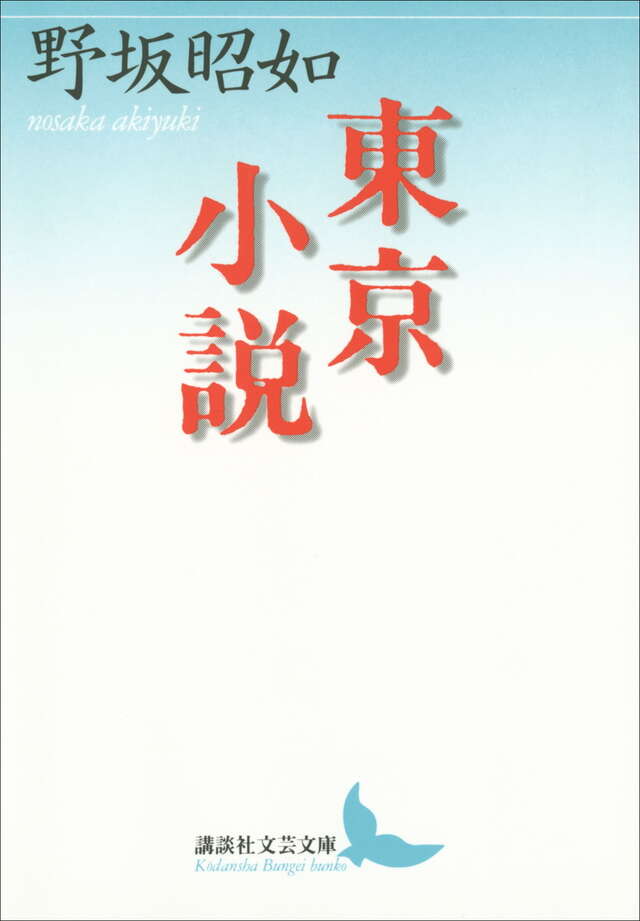
東京小説
講談社文芸文庫
予言者、野坂昭如の東京昨日今日明日。うつつか幻か、郊外の小さな公園のベンチに坐る場所柄につかわしくない粧いの女、その数奇な身の上話に耳をかたむける、これもまた身をもてあまし気味の私。時は春。東京にはさまざまな世間があるのだ。「家庭篇」から始まり告白的「私篇」、そして巨大都市・東京の行末を暗示する「山椒媼」まで饒舌かつ猛スピードで語られる14の断章。
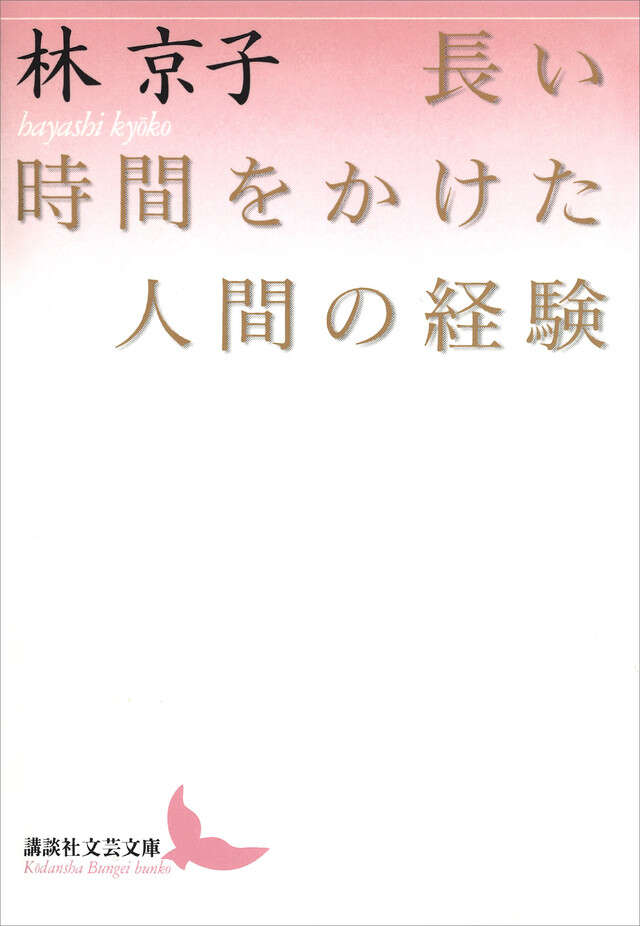
長い時間をかけた人間の経験
講談社文芸文庫
圧倒的事実の<生と死>ーー8月9日に、すでに壊された<私>。死と共存する<私>は、古希を目前にして遍路の旅に出る。<私>の半生とは、いったい何であったのか……。生の意味を問う表題作のほか、1945年7月、世界最初の核実験が行われた場所・ニューメキシコ州トリニティ。グランド・ゼロの地点に立ち《人間の原点》を見た著者の苦渋に満ちた想いを刻す「トリニティからトリニティへ」を併録。野間文芸賞受賞作品。
◎林京子ーー私は立ちすくんだ。地平線まで見渡せる荒野には風もない。風にそよぐ草もない。虫の音もない静まった荒野は自然でありながら、これほど不自然に硬直した自然はなかった。荒野は、原子爆弾の閃光をあびた日以来、沈黙し、君臨していたガラガラ蛇の生さえ受けつけなかった。大地は病んでいたのである。<「著者から読者へ」より>
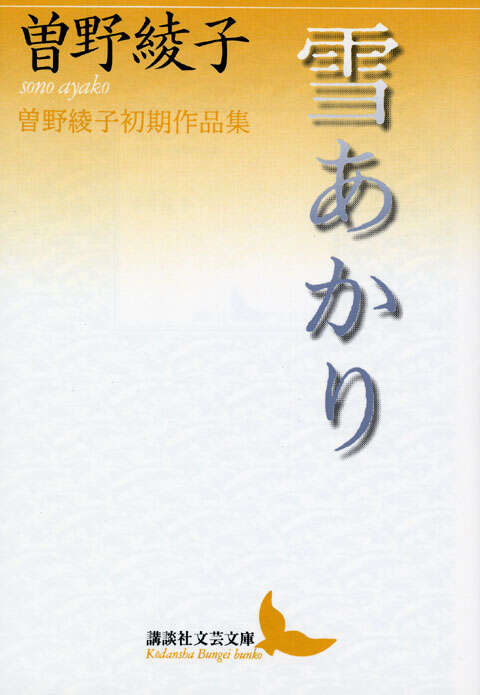
雪あかり 曽野綾子初期作品集
講談社文芸文庫
新鮮清澄、才気迸る源流の光景。初期の代表作7篇収録ーー進駐軍の接収ホテルで働く19歳の波子の眼をとおし、敗戦直後の日本人従業員と米国軍人らとの平穏な日常が淡々と描かれた、吉行淳之介の「驟雨」と芥川賞を競い、清澄で新鮮な作風と高く評価された出世作「遠来の客たち」をはじめ、「鸚哥とクリスマス」「海の御墓」「身欠きにしん」「蒼ざめた日曜日」「冬の油虫」、表題作「雪あかり」を収録。才気溢れ、知的で軽妙な文体の、初期の作品7篇を精選。
◎「ここに集められた作品はすべて、壁の手前の若書きの作品である。この頃以来半世紀間、私は書き続けて来た。平均して一年間に二千枚、それより多い年も少ない年もあるけれど、多分トータルで十万枚は書いたように思う。十万枚、絵でも書でも書けば、どんな凡人でも一つの世界は作るだろう。源流の光景を見て頂くのは、申しわけないが、光栄である。」<「著者から読者へ」より>

日本の童話名作選 明治・大正篇
講談社文芸文庫
鏡花から夢二まで子どもへの愛に溢れた珠玉の童話16篇!
明治・大正期、近代文学の黎明と共に子どもの文学にも一大変革が起きた。親から子に語られる昔話や外国童話の翻案に代わり、紅葉・鏡花等錚々たる文豪達が競って筆を執り、子どもへの愛に溢れた香気高い童話が数多く生み出された。日本の童話の嚆矢とされる巌谷小波「こがね丸」始め、押川春浪、与謝野晶子、菊池寛、芥川龍之介、有島武郎、島崎藤村、佐藤春夫、竹久夢二等15名の珠玉の童話を精選。
神宮輝夫
大正期に子どもの文学の総称となった「童話」は間口の広い文学形式と言える。(中略)ひろげればそのまま優れた小説になるのだが、それを小さなまとまりのある世界にとどめているところに「童話」の意味がある。それは、逃避的な桃源郷幻想ではなく、人間と社会についての強固な理想をこめた文学であって、子どもの文学発達の一時期のものではなく、今もなくてはならない領域である。――<「解説」より>

作家は行動する
講談社文芸文庫
「人間の行動はすべて一種のことばである」ーー文体は書きあらわされた行動の過程、人間の行動の軌跡である。ニュー・クリティシズムやサルトルの想像力論の批判的摂取を媒介に、作家の主体的行為としての文体を論じた先駆的業績であり、著者自らの若々しい世代的立場を鮮烈に示した初期批評の代表作。石原慎太郎、大江健三郎らの同世代の文学と併走しつつ、文学の新たな可能性の地平を提示する。
戦後批評の<青春>溢れる初期代表作
人間の行動はすべて一種のことばである。
文体は書きあらわされた行動の過程――人間の行動の軌跡である。ニュー・クリティシズムやサルトルの想像力論の批判的摂取を媒介に、作家の主体的行為としての文体を論じた先駆的業績であり、著者自らの若々しい世代的立場を鮮烈に示した初期批評の代表作。石原慎太郎、大江健三郎らの同世代の文学と併走しつつ、文学の新たな可能性の地平を提示する。
大久保喬樹
ここには、『小林秀雄』にも『漱石とその時代』にも劣らない、命をかけた――当時の言い回しで言うなら実存をかけた若き江藤の文学創造の行程が刻みこまれているのである。この行程を一歩一歩自分の足でたどり、その軌跡を確認したからこそ、その後の成熟期への展開が開けてきたのである。そして、それは、(中略)江藤個人の青春であるとともに、戦後日本批評、戦後日本社会の青春をも体現するものだったのだ。――<「解説」より>
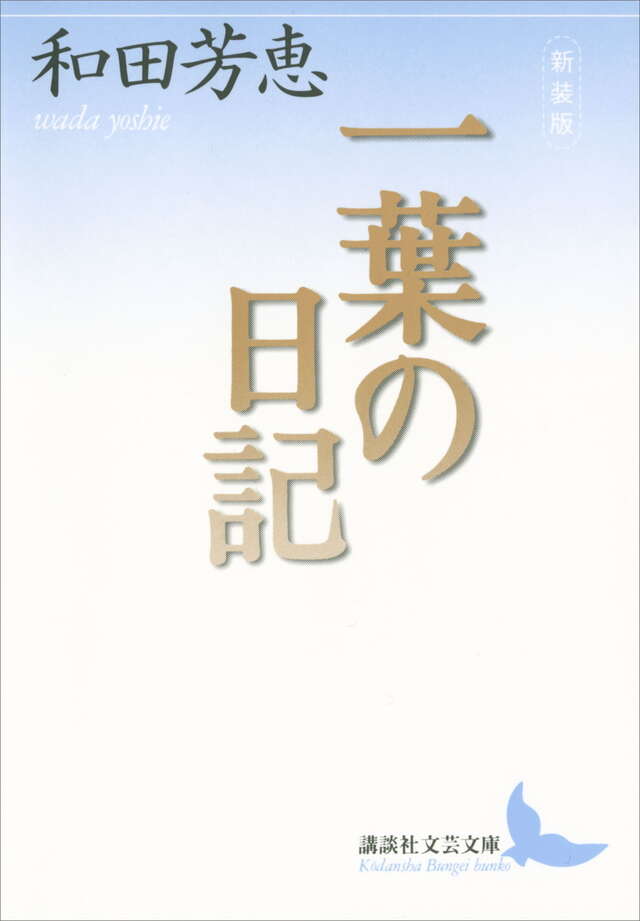
新装版 一葉の日記
講談社文芸文庫
一葉は、いつも庶民のなかにいた。そして、頭のなかでは、社会のありかたの不当さをいつも考えていた。(本文より)樋口一葉の研究に没頭して伝記・評論を書き続け、全集の実務にも携わった作家・和田芳恵が、一葉16歳から死に到る25歳までの日記を、鋭い洞察力で丹念に分析。一葉文学の本質を描出し評伝文学の白眉といわれた。著者畢生の仕事である一葉研究の集大成。日本芸術院賞受賞。
近代日本の夜明けに生きた<一葉の生涯>
一葉は、いつも庶民のなかにいた。そして、頭のなかでは、社会のありかたの不当さをいつも考えていた。(本文より)樋口一葉の研究に没頭して伝記・評論を書き続け、全集の実務にも携わった作家・和田芳恵が、一葉16歳から死に到る25歳までの日記を、鋭い洞察力で丹念に分析。一葉文学の本質を描出し評伝文学の白眉といわれた。著者畢生の仕事である一葉研究の集大成。日本芸術院賞受賞。
松坂俊夫
それはとりもなおさず一葉の日記を、日記文学――実在の人物の登場する私小説と考えていることである。(略)『一葉の日記』はこうした著者の考えを起点とも原点ともしながら、著者というよりもひとりの作家の、一字一句をもゆるがせにしない、みずからの存在を賭けた読みの成果である。著者が一葉の日記を読むことは、自己の作家としての存在を確認することであり、それは自己の作品を読むにもひとしかった。――<「解説」より>
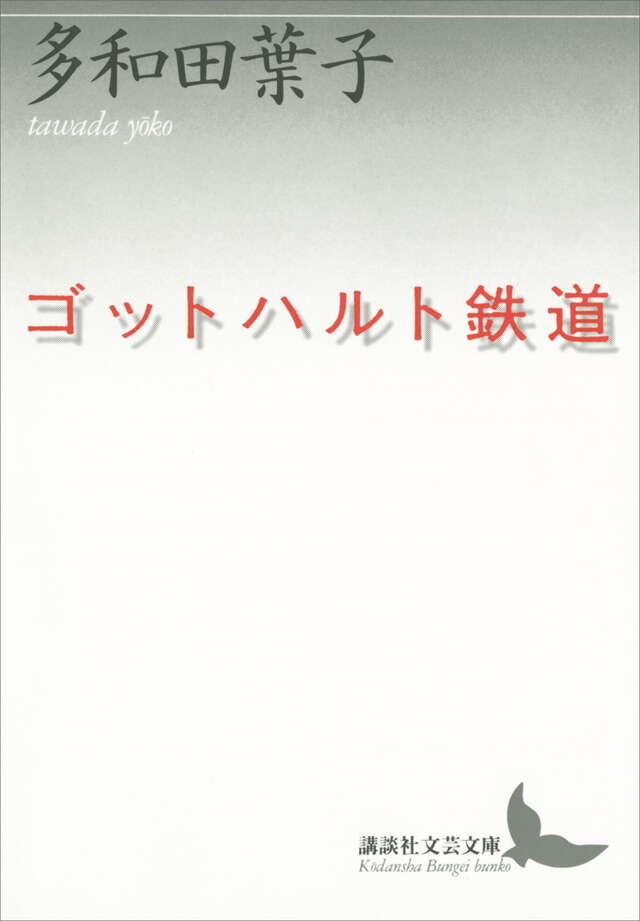
ゴットハルト鉄道
講談社文芸文庫
“ゴット(神)ハルト(硬い)は、わたしという粘膜に炎症を起こさせた”ヨーロッパの中央に横たわる巨大な山塊ゴットハルト。暗く長いトンネルの旅を“聖人のお腹”を通り抜ける陶酔と感じる「わたし」の微妙な身体感覚を詩的メタファーを秘めた文体で描く表題作他2篇。日独両言語で創作する著者は、国・文明・性など既成の領域を軽々と越境、変幻する言葉のマジックが奔放な詩的イメージを紡ぎ出す。
変幻自在、越境する言葉のマジック!
“ゴット(神)ハルト(硬い)は、わたしという粘膜に炎症を起こさせた”ヨーロッパの中央に横たわる巨大な山塊ゴットハルト。暗く長いトンネルの旅を“聖人のお腹”を通り抜ける陶酔と感じる「わたし」の微妙な身体感覚を詩的メタファーを秘めた文体で描く表題作他2篇。日独両言語で創作する著者は、国・文明・性など既成の領域を軽々と越境、変幻する言葉のマジックが奔放な詩的イメージを紡ぎ出す。
室井光広
多和田文学のキャラクターたちを形容するにふさわしい言葉を今次もうひとつ見つけた。――あやかしの歩行巫女(あるきみこ)。(略)アルキミコたちは男流的押しつけがましさを軽くいなしながら、奥を幻視する。閉じ込められた奥ではどんなあやしの幻術がおこなわれるのか。それは決して「偉大なもの」ではなく、たとえば本書に何度か使われている言葉をかりて簡単にいうなら「壁」を、皮膚の暖かさをもつ皺のイメージにも重なる「襞」に変異させるような術だ。――<「解説」より>

婉という女・正妻
講談社文芸文庫
土佐藩執政、父・野中兼山(良継)の失脚後、4歳にして一族とともに幽囚の身となった婉。男子の係累が死に絶えた40年後、赦免が訪れ、自由となったものの、そこで見たのは、再び政争の中で滅びてゆく愛する男の姿であった……。無慙な政治の中を哀しくも勁く生きた女を描き、野間文芸賞、毎日出版文化賞を受賞した名作「婉という女」に、関連作「正妻」「日陰の姉妹」の2篇を付し、完本とする。
哀しくも勁く生きた女たち
土佐藩執政、父・野中兼山(良継)の失脚後、4歳にして一族とともに幽囚の身となった婉。男子の係累が死に絶えた40年後、赦免が訪れ、自由となったものの、そこで見たのは、再び政争の中で滅びてゆく愛する男の姿であった……。無慙な政治の中を哀しくも勁く生きた女を描き、野間文芸賞、毎日出版文化賞を受賞した名作「婉という女」に、関連作「正妻」「日陰の姉妹」の2篇を付し、完本とする。
高橋英夫
野中婉はその聡明さと気性の激しさによって、わが身の「一身二生」を覚った女性だった。そのことを覚って、そこから身を立て、何者かになってゆこうと心に念じた女性だった。大原富枝が野中婉を作品の女主人公に選んだのは、野中婉のそうした人生と思念のかたちに強く惹かれたからであったのは、明らかなことである。(略)志をもった女性によって書かれた、志ある女のすがたと心がここにはある。――<「解説」より>

新編 物いう小箱
講談社文芸文庫
読むことと、書くことと――生涯をこの2つに凝集し、膨大な資料の渉猟と丹念な読み込みから、世に名高い森史学は生まれた。そのかたわら、資料から離れ、虚実の間に筆を遊ばせるかのような本書収載の珠玉の小品が書かれた。『怪談』を愛してやまなかった著者が、「八雲に聴かせたい」との思いで書き綴った怪異談、中国の説話に想を得た作品など、44篇を収める新編集の増補版。

雲のゆき来
講談社文芸文庫
現代文学の可能性を拓く
彦根藩2代目藩主の生母・春光院の弟、青春時代には江戸の噂になるほどの艶名を売り、やがて隠棲、僧侶としても文筆家としても一代の名声を担った元政上人。彼の清冽な詩の世界に遊び、事蹟を訪ねる旅に出ようとした「私」は、父への憎しみを跡付けるための旅をする1人の国際女優と同道することに。幸と不幸の間で揺れ続ける2つの旅の終着は……。現代文学の可能性を拓く詩的で知的な冒険。
鈴木貞美
われわれは、この長篇小説に、20世紀日本が生んだ、この稀有な文人(オム・ド・レットル)の中で20世紀のヨーロッパと日本、平安時代の王朝文化と徳川時代の文化が、どのようなつながりをもちながら並存し、旺盛な関心を呼び起こしていたのかを、読みとることになるだろう。――<「解説」より>
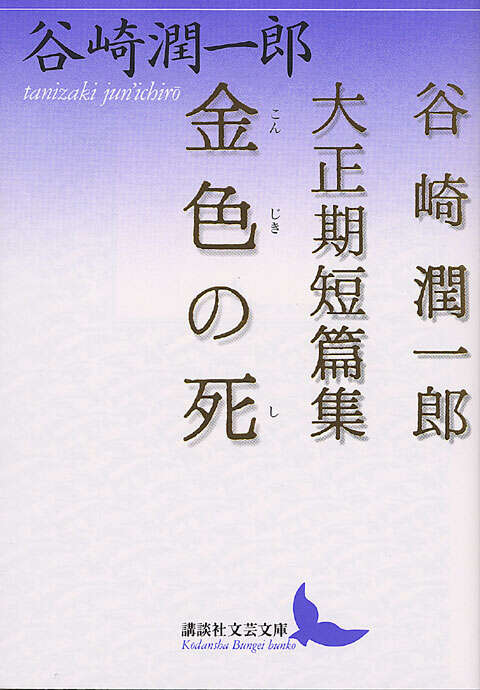
金色の死
講談社文芸文庫
潜在的な<妻殺し>を断罪
江戸川乱歩の「パノラマ島綺譚」に影響を与えたとされる怪奇的幻想小説「金色の死」、私立探偵を名乗る見知らぬ男に突然呼びとめられ、妻の死の顚末を問われ、たたみ掛ける様にその死を糾弾する探偵と、追い込まれる主人公の恐怖の心理を絶妙に描いて、日本の探偵小説の濫觴といわれた「途上」、ほかに「人面疽」「小さな王国」「母を恋ふる記」「青い花」など谷崎の多彩な個性が発揮される大正期の作品群7篇。
清水良典
『小さな王国』のような政治小説も、探偵小説も、怪奇幻想小説も、足フェチ小説も、母恋い小説も、みんな谷崎文学という偉大な大樹の、大正期の枝に生った果実である。昭和に入って谷崎文学は急速に日本の伝統に近づき、大家として飛躍的な成長を遂げた。(中略)谷崎の大正期は、決して失われた時代ではない。むしろ作家谷崎が、全力を傾けて拡大と成長に努めた時代だったのであり、その土台が彼を「大谷崎」へと押し上げたのである。――<「解説」より>

吉本隆明対談選
講談社文芸文庫
その時々の社会情況、文学・思想情況に対して、果敢な発言を行い、時代を先導してきた思想家・吉本隆明。その思想の歩みを対談で辿り、時代と思想的課題の推移を、今、改めて問い直す。江藤淳、鶴見俊輔、ミシェル・フーコー、佐藤泰正、大西巨人、高橋源一郎、谷川俊太郎との、時代を象徴する7篇の対談は、互いの立場を超えた鋭い問題意識の応酬で、読者を白熱した場へと連れ出す。精選された1冊。
松岡祥男
吉本隆明の対談は、対談相手が変わっても、話題や論点がその場限りのものではなく、内在的な思想過程がその基底に脈々と流れていて、ひとつの大河をなしている(略)だから、どんな小さなインタビューでも、ないがしろにすることはできないのだ。それは対談やインタビューに限らず、吉本隆明の<全表現>を貫く、著しい特長である。――<「解説」より>

夏の流れ
講談社文芸文庫
平凡な家庭を持つ刑務官の平穏な日常と、死を目前にした死刑囚の非日常を対比させ、死刑執行日に到るまでの担当刑務官と死刑囚の心の動きを、緊迫感のある会話と硬質な文体で簡潔に綴る、芥川賞受賞作「夏の流れ」。稲妻に染まるイヌワシを幻想的に描いた「稲妻の鳥」。ほかに、「その日は船で」「雁風呂」「血と水の匂い」「夜は真夜中」「チャボと湖」など、初期の代表作7篇を収録。
◎「丸山健二の文学性は、ジェームズ・ジョイスに通じる。本作品集に収録されている初期短編を改めて読みながら、私はそう思った。(中略)すぐれた芸術家は生涯を通して変貌を続けるが、若き日の作品群は作品を受容する側にとっての定点を提供する。ピカソのキュビズムは、初期の見事な絵画によって担保される。このような文脈において、本文庫に収められた初期の短編の数々は、弱冠23歳で芥川賞を受賞し、長年文壇と一線を画して孤高の道を歩んできた丸山健二の文学の全体像を理解する上で、重要な意味を持つのではないか。」<茂木健一郎「解説」より>

腕一本・巴里の横顔
講談社文芸文庫
26歳で渡仏、絵を燃やして暖をとる貧しい修業生活を経て、神秘的な「乳白色の肌」の裸婦像が絶賛を浴びる“エコール・ド・パリ”時代の栄光。一方故国日本では絵の正当な評価を得られぬ煩悶と失意から、やがてフランスに帰化、異郷に没した藤田。本書は1940年以前に書かれた随筆から、厚いベールに包まれた画家の芸術と人生を明かす作品を精選、さらに未発表の貴重な2作を発掘収録する。
近藤史人
藤田嗣治ほど栄光と挫折の間を行き来する起伏に富んだ生涯を送った日本人画家はいないだろう。エコール・ド・パリという舞台への華やかな登場。画風をがらりと変えて打ち込んだ戦争記録画。そして戦後の失意。(略)藤田は、明治の知識人がそうであったように、生涯を通して日本人としてのアイデンティティーを求め続けていたのではないか、と思う。にもかかわらず、フランスへの帰化という苦渋の選択をせざるを得なかった藤田の失意と哀しみ。その前では、この国の明治以降の近代化の歴史も、戦後のめざましい復興も、色褪せて見えるのである。――<「解説」より>