講談社文芸文庫作品一覧

徳利と酒盃・漁陶紀行
講談社文芸文庫
やきものを愛し 酒を愛し 人を愛した天衣無縫
静かでうれいに満ちた美しさをもつ李朝彫三島扁壺、端正で気品のある中国陶磁の至宝、北宋汝官窯青磁輪花碗、枯淡なうちにほのぼのした明るさをたたえた信楽の壺、わが愛すべきやきものに寄せた『骨董百話』をはじめ数々の名随筆をのこした陶磁研究の第一人者、小山冨士夫。みずからもすぐれた陶芸家であった、その美への探究心をあますところなく伝える随筆集。
森孝一
信楽の楽斎窯(らくさいがま)では、「この土に少し酒を飲ませたほうがいい。ほろ酔いがいい」と独り言をいいながら轆轤を挽いていたという。<ほろ酔い>という表現は、いかにも小山の作品のかたちをいい得て妙である。人の性格も土の性格も、ほろ酔い加減の時が一番素直に現われるというのであろうか。そうした作陶は、まさに小山の天性のものであり、近代の陶芸家の中でもこれほど自分の個性を、しかも自然体で表現出来た陶芸家も稀である。――<「解説」より>
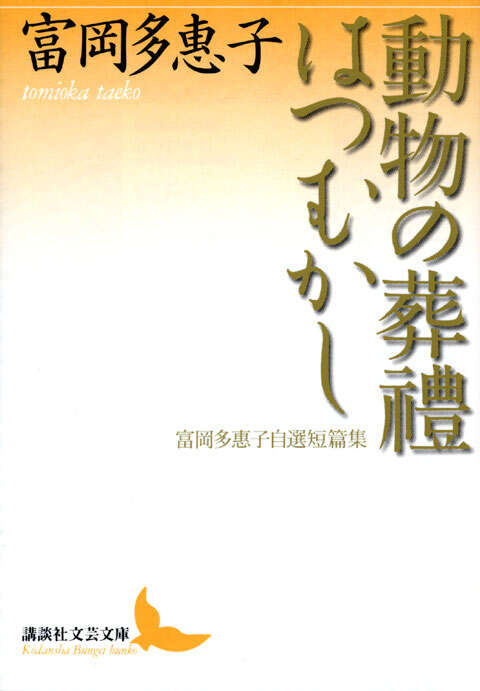
動物の葬禮・はつむかし
講談社文芸文庫
二十代に詩を書き始め、三十代で「うた」と訣れ小説家に。生まれ育った大阪の言葉がもつ軽妙さと批評性を武器に、家族、愛、性の幻想から「人間という生き物」を解き放ちつつ現代文学の尖端でラジカルな表現を続ける。孤独な青年の死を周囲のドタバタ騒ぎに映して鮮やかに浮き彫りにする「動物の葬禮」、親を殺し子を捨てる男の衝動を実存の闇として描く「末黒野」など、著者自選の九篇。

対談・文学と人生
講談社文芸文庫
独自の創作理論を打ち立てた、二大巨人による実践的文学論。文学の<現在>はここから始まるーー独自の文学世界を打ち立てた二大巨人=小島信夫&森敦による長篇対談。昭和20年代半ばからの知己である二人が、これまでの交遊を振り返りつつ、創作理論の<現在>を縦横に語り合う。悲劇と喜劇、内部と外部、小説におけるモデル問題、夢と幻想、演劇論など、多岐にわたるテーマを通して、二人の文学の根柢に迫る、スリリングでアットホームな試み。幻の未刊長篇対談、待望の文庫化。
◎小島信夫「この対話は色々の問題をもってきて、互いに論じるというようなものとは大分ちがう。問題も材料も互い自身である。これは息苦しいものであるし、空を切ることもあるので、ときどき散歩をすることもある。ときには、自分自身をダマす必要もある。(略)今月、悲劇、喜劇という言葉が出現して、私は刺戟をうけた。まどろみかけた目がひらいた思いがした。(略)今回のような談話の中での文脈の中でおどり出たのだから、これは生きた言葉である。生きた言葉であるだけに、今後何度も俎上にのぼり、たのしまなければならない。」<「第四回・追記」より>
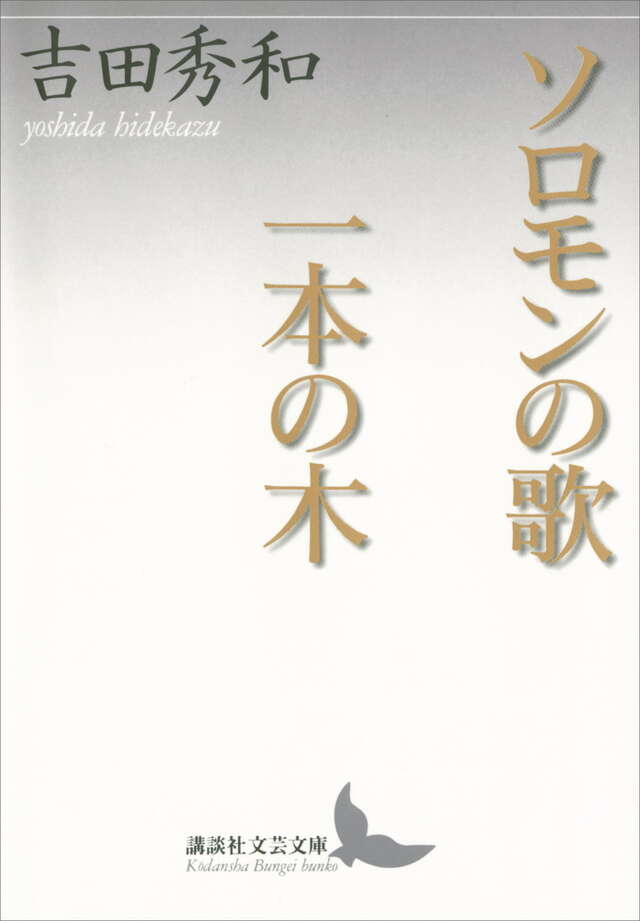
ソロモンの歌・一本の木
講談社文芸文庫
戦後日本の音楽批評をリードしてきた吉田秀和は、青春期に吉田一穂に私淑、中原中也との交遊や小林秀雄の影響を通してポエジーの精髄に触れた。音楽はもとより、文学や美術を論じた著作によって、豊饒なる批評精神を構築してきた著者が、幼児期から詩との出会いまでを綴り、その批評の原点を明かす表題作をはじめ珠玉の随想12篇を収録。巻末の荷風論は、日本近代の宿命を巡る鋭い洞察に満ちた文明論である。
青春期の中原中也や小林秀雄との邂逅。
クレーの絵の謎解き。音楽へのめざめ。
多彩な芸術随想12篇。
戦後日本の音楽批評をリードしてきた吉田秀和は、青春期に吉田一穂に私淑、中原中也との交遊や小林秀雄の影響を通してポエジーの精髄に触れた。音楽はもとより、文学や美術を論じた著作によって、豊饒なる批評精神を構築してきた著者が、幼児期から詩との出会いまでを綴り、その批評の原点を明かす表題作をはじめ珠玉の随想12篇を収録。巻末の荷風論は、日本近代の宿命を巡る鋭い洞察に満ちた文明論である。
大久保喬樹
戦前の東京下町ですごした子供の頃まだ明けやらぬ床の中で聞いた櫓太鼓の音から始まって、戦後欧米各地で接した前衛音楽まで、さまざまな音、また、さまざまな色や形、言葉や暮らしを吉田さんは経験し、それら経験の意味を考え、そうした作業を積み重ねてひとつの精神の秩序を築きあげていった。それが吉田さんにとっての批評ということだった。――<「解説」より>
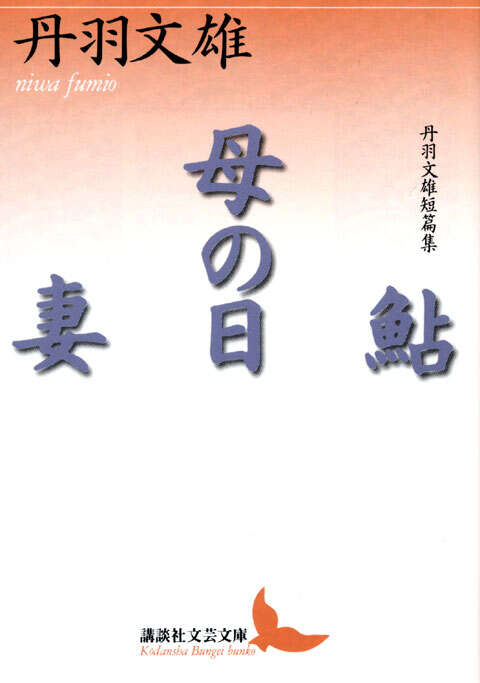
鮎・母の日・妻
講談社文芸文庫
幼くして生母と離別し、母への思慕と追憶は、作家・丹羽文雄の原点ともなった。処女作「秋」から出世作「鮎」、後年の「妻」に至る、丹羽文学の核となる作品群。時に肉親の熱いまなざしで、時に非情な冷徹さで眺める作家の<眼>は、人間の煩悩を鮮烈に浮かび上がらせる。執拗に描かれる生母への愛憎、老残の母への醜悪感……。思慕と愛憎と非情な<眼>による、「贅肉」「母の日」「うなずく」「悔いの色」ほか10篇。
〇中島国彦 もっと丹羽文雄の創作の根源、感性の原点を示す作品を、いつでも読めるようにしたい――そうした思いを、多くの丹羽文学愛好者が持ったのではなかろうか。丹羽文雄は移り行く時代の風俗を巧みに描きながら、一方で自己の周辺の家族にかかわる体験に生涯こだわった作家でもあった。とりわけ、生母こうが、文雄四歳の時に家を出てしまった出来事は、その後の丹羽文雄の心情を規定することとなった。<「解説」より>

三田の詩人たち
講談社文芸文庫
久保田万太郎
折口信夫
佐藤春夫
堀口大學
西脇順三郎
永井荷風
文芸のグルマン篠田一士のポエジー讃歌!
短歌と俳句と現代詩――20世紀日本の詩的創造を、ポエジーのひとつの流れとして捉えた、画期的な試み。現代詩のアマトゥール・篠田一士が、詩的言語の成立過程のなかで、重要な結節点に位置する久保田万太郎、折口信夫、佐藤春夫、堀口大學、西脇順三郎の5人に永井荷風を加え、現代詩の全貌を明かした名講義録。日本語のゆたかな富を奪還する、詩への限りない愛。
池内紀
いい作品に惹かれ、感動する。なぜ惹かれ、どのような魅力を感じたのか。その文学体験を深め、洗練させるのが批評というもの。詩的言語に国境はない。また古今ともかかわらない。さらにジャンルも問わないだろう。おおかたの文芸批評家が小説以外は見向きもしないなかで、篠田一士は伝記や紀行記や日記やノンフィクションをよく読んでいた。批評文はもとよりである。そしてこよなく詩を愛した。――<「解説」より>

蝶が飛ぶ 葉っぱが飛ぶ
講談社文芸文庫
生涯一陶工として、土と火に祈りを込めた河井の純粋なる魂
陶芸家としての名声に自ら背を向け同志柳宗悦、濱田庄司と民芸運動を立ち上げた河井。「美を追っかける」世界から、名もなき職人仕事、工業製品の如き「美が追っかける」世界へ、さらに晩年は用途を超えた自由奔放な造形美の宇宙へ……。京都五条坂に登り窯をすえ、暮らし、仕事、美の三位一体、生涯を一陶工として貫徹した河井の純粋なる魂の表白。平易でありながら深遠な味わい深い文章を精選して収録。
河井寛次郎
私は木の中にいる石の中にいる、鉄や真鍮の中にもいる、人の中にもいる。1度も見た事のない私が沢山いる。始終こんな私は出してくれとせがむ。私はそれを掘り出したい。出してやりたい。私は今自分で作ろうが人が作ろうがそんな事はどうでもよい。新しかろうが古かろうが西で出来たものでも東で出来たものでも、そんな事はどうでもよい、すきなものの中には必ず私はいる。私は習慣から身をねじる、未だ見ぬ私が見たいから。――<本文「手考足思」より>

世界漫遊随筆抄
講談社文芸文庫
昭和初期の世界へ旅立ち、そこに住まう人々と愚直に向きあう赤裸な記録
世界の激動を予感させる昭和初期、3年、11年と2度の欧米旅行に発ち、10年には樺太、中国等を訪れた正宗白鳥。文豪の眼に世界はどう映ったのか……。名エッセイ「六十の手習い」「髑髏と酒場」「郷愁――伯林の宿」を含む21篇を精選。新興国アメリカとヨーロッパの比較、イタリア、フランスの芸術、スターリンのソ連、ヒトラーのドイツ、外地で出会う不思議な邦人のことなど、簡潔な文体で直截に印象を記す好随筆集。
大嶋仁
彼の外国旅行記には、他の作家たちの同類のものとはまったくちがった味がある。あれほど長期にわたって多くの国々を見て回ったのに、異国情緒がまったくないというのもその一つだし、物珍しい風物に驚いているようでいて、結局は人間の本性はどこでも変わらないと見抜く眼力が光っているのも白鳥ならではの特徴である。――<「解説」より>

維納の殺人容疑者
講談社文芸文庫
「日本探偵小説中興の祖」と称される著者の描く異色の法廷ミステリー
江戸川乱歩が「日本探偵小説中興の祖」の1人として名を挙げる文豪・佐藤春夫の描いた異色の「法廷ミステリー」。1928年7月、ウィーン郊外で起こった女性殺害事件――グスタフ・バウアー事件の裁判を、「述べて作らぬ」という<纂述>の形を借りながらも、人間心理の深奥に迫るドラマへと昇華した冒険作。被告、検事、弁護士、そして様々な証人たちの手に汗を握る虚実のかけひきの末に出された判決は……。
横井司
バウアーが犯人かどうかよりも、バウアーという個人が審理を通して抽象化されていく過程を、いわず語らずのうちに浮かび上がらせているかのようだ。(略)探偵小説の愛読者は多くの作品に接するうちに、作り物であることに飽き足らなくなり、犯罪実話へと関心を向けると、かつてよくいわれたものだった。その当否は別にして、犯罪実話が必ずしも血の通った人間を現出させるばかりではなく、権力による冷徹な犯罪(者)処理システムを暴露していくものでもあり、時として作りもののキャラクター以上に人間性を剥奪されるありさまを見せつけるというのも、皮肉な話ではないだろうか。――<「解説」より>

幾度目かの最期
講談社文芸文庫
18歳の時に書いた作品で芥川賞候補となり、21歳で自殺した幻の作家・久坂葉子。神話化した天才作家の心の翳りを映す精選作品集。
今も惜しまれる元祖天才文学少女、その青春の光と影――。18歳の時書いた作品で芥川賞候補となり、そのわずか3年後に、列車に身を投げた久坂葉子。名門の出という重圧に抗いつつ、敗戦後の倦怠と自由の空気の中で、生きることの辛さを全身で表すかのように、華やかな言動の陰で繰り返される自殺劇……。遺書的作品「幾度目かの最期」を中心に、神話化された幻の作家の心の翳りを映す貴重な1冊。
久坂部羊
自殺の当日に完成されたのが、本書収録の『幾度目かの最期』である。この作品を読んだときの衝撃は、今も忘れられない。自分の死と文学をこれほど一致させた作品がほかにあるだろうか。自らの死を1編の小説に結晶させ、その作品の予告通りに死ぬ。それは芥川にも太宰にも三島にもなし得なかったことである。――<「解説」より>
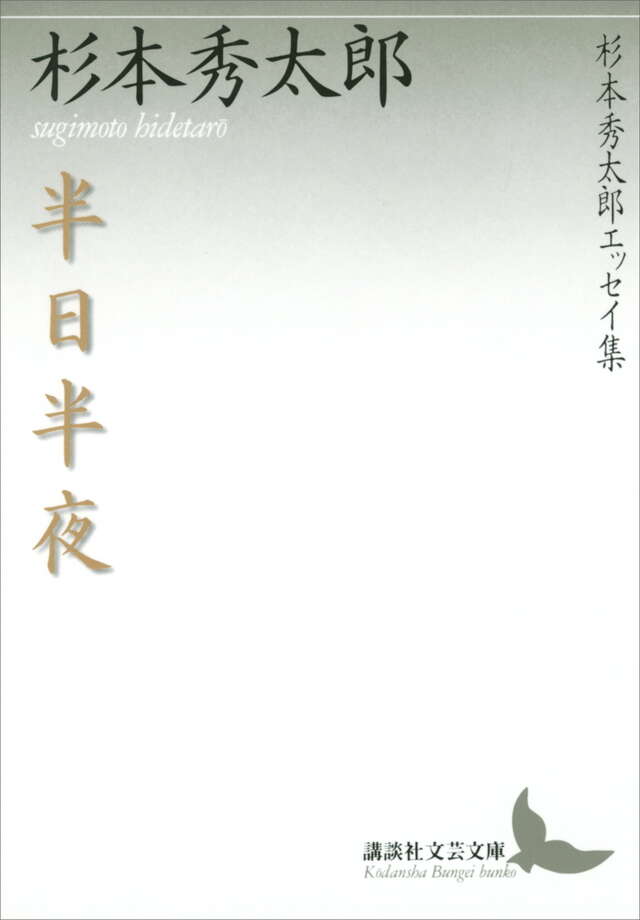
半日半夜 杉本秀太郎エッセイ集
講談社文芸文庫
よりすぐりの随筆をよむそのここちよさは 蜂蜜の甘い滴りにも似て――冬至を控えて宿り木を採りに山に入る。赤い紐で根本を結び天井から逆さに吊るすのだ。昔、年末のパリの街かどで宿り木を求め孤独な年越をして以来、クリスマスの頃になると、こうして飾ることにしている。耳をひそめてしぐれをきき、目をこらして面影を追う日々――。洛中に生まれ育ちパリにすごした歳月の軌跡を描く重厚だが洒脱なエッセイから29篇を厳選。

日日の麺麭・風貌
講談社文芸文庫
太宰治にその才能を愛され、市井に生きる人々の小さな人生を描き続けた、不遇な作家の稀有なる文業
明治の匂い香る新吉原、その地で過ごした幼少期を温かい筆致で振り返る「桜林」、妻に先立たれ、幼い娘を連れておでんの屋台を曳く男の日常を静かに辿った「日日の麺麭」等、清純な眼差しで、市井に生きる人々の小さな人生を愛情深く描いた小説9篇に、太宰、井伏についての随筆を併録。師・太宰治にその才能を愛され、不遇で短い生涯において、孤独と慰め、祈りに溢れる文学を遺した小山清の精選作品集。
小山清
私は太宰さんと会って、太宰さんの人柄が、またその生活が、作品と1枚のものであることを知った。太宰さんはまた非常に率直な人であった。いつ死んでも悔いのないように、好きな人にはこだわりなく好きだと云っておけと云っていたが、すべてにそんなところがあった。見ていてはらはらするほど率直なところがあった。――<「風貌」より>

丘の一族 小林信彦自選作品集
講談社文芸文庫
<物語>と<私>のあいだ
『オヨヨ島の冒険』に始まる笑いと諷刺の作品群、『冬の神話』に刻まれる小林信彦の原点、多彩な作品は著者の鋭い批評精神に支えられ、独得の世界を構築する。敗戦直後の日常を、東京下町に生まれ育った中学生の<眼>をとおし捉えた「八月の視野」、戦前の下町の風情を彷彿させる遊び人・清さんを主人公に描く「みずすましの街」、ほかに表題作及び「家の旗」。著者自選。傑作中篇小説4篇。
小林信彦
私小説はきらいではないが、書くのは向かないと思っていた。30代に入り、小説を日常的に書くようになると、そうも言っていられないようになった。日本の<文壇>というのは、逆に、<作者の告白=私小説>を要求しているらしい、とわかってきた。もちろん、それは古めかしい私小説ではなく、<私の内面のとめどない追究>といったものだが、ぼくの好みとはまったく違っていた。そこで、というか、やむをえず、というか、とりあえず、<物語>と<私>をくっつけてしまおうと考えた。それが「丘の一族」である。――<「著者から読者へ」より>

柳田國男文芸論集
講談社文芸文庫
笑い、恋、夢。庶民の暮しに日本人の心を発見する柳田文芸論の白眉28篇!
古来日本人が絶えることなく語り伝えた昔話や伝説は、笑い、歌、夢が咲き誇る肥沃な物語の土壌であった。詩人として、花袋、藤村等と近代文学の青春を共にしながらやがて彼等の批判者となった柳田は、好奇心や空想力を衰弱させた自然主義に反し、庶民の暮らしの中にこそ真の文芸があると説く。文芸に関わる主要論考、随筆から近代文学が捨象した豊穣な世界に詩的直感を以て分け入る28篇を精選。
井口時男
柳田の民俗学は近代文学との深い交渉から誕生したのであって、その中心に、近代文学と同じまなざしを共有している。いわば、柳田の民俗学は近代文学の隣人である。(略)今日、近代文学はもう終ってしまったのではないか、というささやきがしきりに聞こえる。この「終焉」の時代に、「誕生」の時からの助言者であり批判者であった隣人の言葉に耳を傾けてみてはどうか。――<「解説」より>

乳を売る・朝の霧
講談社文芸文庫
女性たちの痛切な生の姿を刻む9作品
わが子に与えるべき母乳すら売らねばならぬ貧しき女性の痛切な姿を刻む「乳を売る」、女だけの催し<五月飯>の日の老女らのユーモラスな振る舞いを通し、哀しくも逞しく生きる寒村の女を力強く描いた「朝の霧」等、戦前・戦中の7作品に、自らの文学の核となった少女期を回顧した晩年の作2篇を併録。プロレタリア文学に母性という視点を加え、虐げられてきた女性の新たな目覚めを追究する著者の精選作品集。
高橋秀晴
松田解子の眼は、文学や政治の手前にある虐げられし人々の姿をも凝視していた。同時にその眼は、遥か彼方にある生きることの意味や命の尊厳をも遠望していた。結果、文学性と政治性の高次に於ける両立乃至融合を果たし得たのだった。――<「解説」より>
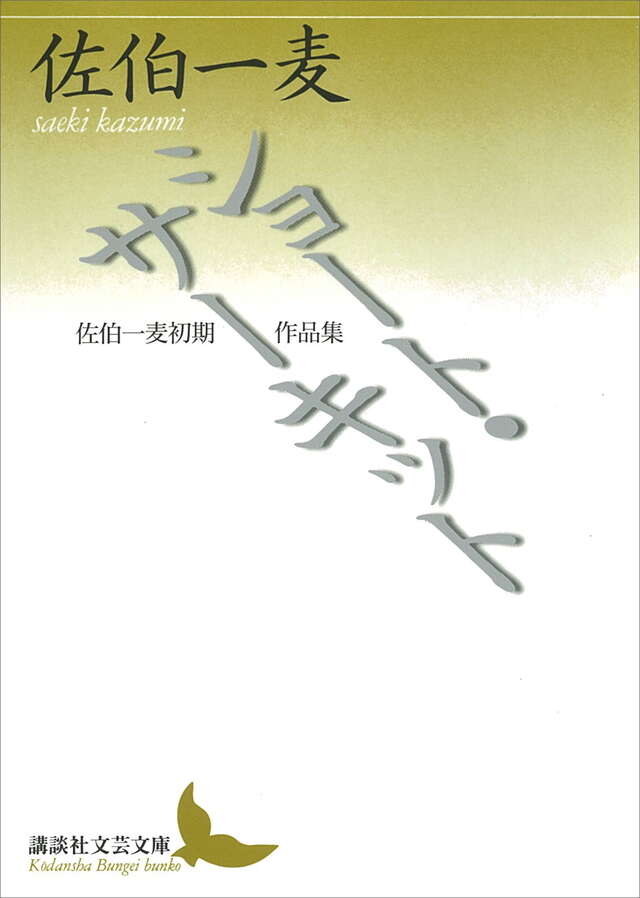
ショート・サーキット
講談社文芸文庫
若くして父となったかれは生活のため配電工となった。都市生活者の現実に直面するうち3人の子供の父となり、妻はすでに子供たちのものになってしまった。今日も短絡事故(ショート・サーキット)が起こり、現場にかけつける――。野間文芸新人賞受賞の表題作に、海燕新人文学賞受賞のデビュー作「木を接ぐ」をはじめ、働くということ、生きるということをつきつめた瑞々しい初期作品5篇を収録。
都市生活者の暗部に直面する電気工のかれ自らもまた危うさをはらんでいる
若くして父となったかれは生活のため配電工となった。都市生活者の現実に直面するうち3人の子供の父となり、妻はすでに子供たちのものになってしまった。今日も短絡事故(ショート・サーキット)が起こり、現場にかけつける――。野間文芸新人賞受賞の表題作に、海燕新人文学賞受賞のデビュー作「木を接ぐ」をはじめ、働くということ、生きるということをつきつめた瑞々しい初期作品5篇を収録。
佐伯一麦
多くの夢をみた。ほとんど、電気工の頃の夢。目覚めたとき、「ショート・サーキット」執筆の腹づもりが完全に固まっていた。労働の悲惨さというものは確かにあるが、その内側では、そのこと自体をも肯定している精神状態が確と存在しているということ。労働する人間に不幸をもたらす原因を取り除くのは、労働に美しさを取り返させること。元来病弱だったヴェイユが、命懸けでつかんだ労働の観察の結果と認識を、自分もまた手放すことなく作品で描こう。夜、O氏から電話がありタイトル名を正式に伝える。――<「著者から読者へ」より>
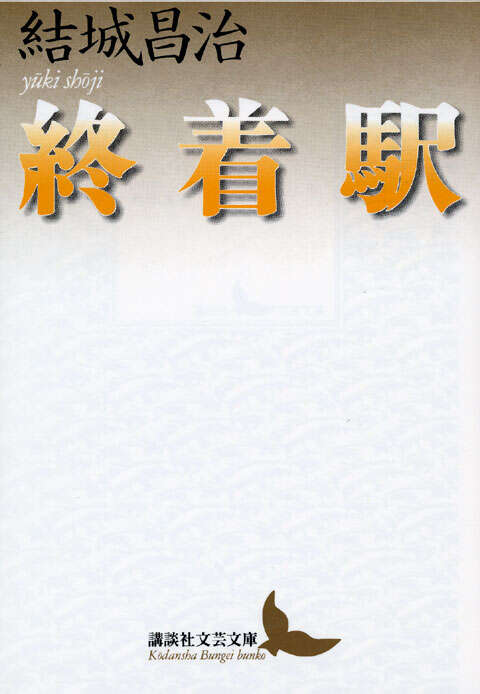
終着駅
講談社文芸文庫
敗戦直後の焼け跡・東京で、ウニ三という正体不明の男が、どぶにはまって変死。その位牌は、まるで死のバトンの如く引き受けた男たちに、つぎつぎと無造作な死を招き寄せる。絶対的価値が崩壊した後、庶民はいかに生き、いかに死んでいったのか? 独白体、落語体、書簡体など、章ごとに文体を変え、虚無と希望の交錯する時代を活写。『軍旗はためく下に』の戦争テーマを深化した、純度高い傑作。焼け跡闇市に生き、死んだ、無名の人たちへの哀歌! 吉川英治文学賞受賞作品。
◎常盤新平 『終着駅』に登場するのは敗戦直後の焼け跡にうごめいているその日暮らしの人たちです。彼らの生と死が章ごとに変わる文体で語られていきます。独白もあれば、落語の話術、返信のない手紙の連続、饒舌と多彩です。(中略)『終着駅』は推理小説仕立てですが、推理小説という枠を借りてその枠をこえてしまった小説なのです。結城さんは敗戦直後の体験をもとに自分の「終着駅」と思いさだめた小説を書いたのです。(「解説」より)

俳句の世界
講談社文芸文庫
俳句に関する考察の全貌を示す名著
<自己の文学観の最も大切な部分を折口信夫から受けている>と語った山本健吉が、現代文学を基軸にして古典文学を探求。俳句固有の性格や方法を明確にする一方「日本の詩の歴史」のうち、俳句が占める位置を示して複眼的な批評を展開、文学の根本問題に迫る。表題作のほか「挨拶と滑稽」「純粋俳句」「芭蕉と現代」「時評的俳句論」など著者の俳句・俳諧についての考察を網羅した名著。
山本健吉
俳句は短歌の上の句を独立させた詩型であり、完結詩型を中断することによって、作為的に成立せしめられた詩型である。短歌が、それ自身で完全に抒情詩としての性格を具え、一定の時間的持続のうちに詩的律動をうち出すことができるのに対して、五・七・五の俳句詩型になると、そこに質的変化が起り、そのような時間的性格から背馳しようとする傾向が認められる。――<本文より>

小林秀雄対話集
講談社文芸文庫
近代日本最高の知性が語る美の真実と人生の妙味
日本を代表する最高の知性・小林秀雄が、戦後に残した歴史的対話12篇――。坂口安吾、正宗白鳥、青山二郎、大岡昇平、永井龍男、河上徹太郎、三島由紀夫、江藤淳、中村光夫、福田恆存、岩田豊雄、田中美知太郎の12名を相手に、文学、美術、作家の生き方等、多彩なテーマを自由闊達に語り合い、人生の妙味と真実に迫る感銘深い1巻。格調高い精神のドラマが交響する第一級の文学史的資料。
小林秀雄
美術や音楽は、僕に文学的な余りに文学的な考えの誤りを教えてくれるだけなのだ。妙な言い方だがね。文学というものは文学者が普通考えているより、実は遥かに文学的なものではない。僕はそういう考えを持つに至った。この考え方は文学的ではないか。せいぜいそんな考えに達するのに高い価を払ったものさ。考えてみれば妙な世界だよ。――<「伝統と反逆」より>
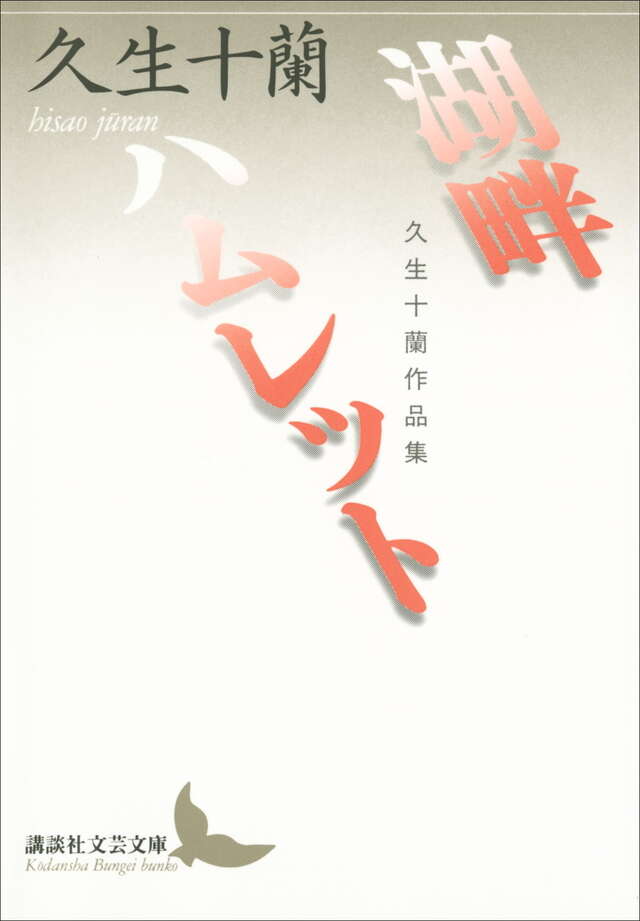
湖畔・ハムレット
講談社文芸文庫
女装、泥酔、放火――、模範少年はなぜ一見、脈絡のない事件を起こしたのか? 少年の心理を過去現在の交錯する戦後空間に追い、母と息子の残酷極まりない愛の悲劇に至る傑作「母子像」(世界短編小説コンクール第一席)、黒田騒動に材を採り破滅に傾斜する人間像を描破した「鈴木主水」(直木賞)等、凝りに凝った小説技巧、変幻自在なストーリーテリングで「小説の魔術師」と評される十蘭の先駆性を示す代表的7篇。
正体をくらますリュパン? 遁走するファントマ? “小説の魔術師”十蘭の傑作7篇
女装、泥酔、放火――、模範少年はなぜ一見、脈絡のない事件を起こしたのか? 少年の心理を過去現在の交錯する戦後空間に追い、母と息子の残酷極まりない愛の悲劇に至る傑作「母子像」(世界短編小説コンクール第一席)、黒田騒動に材を採り破滅に傾斜する人間像を描破した「鈴木主水」(直木賞)等、凝りに凝った小説技巧、変幻自在なストーリーテリングで「小説の魔術師」と評される十蘭の先駆性を示す代表的7篇。
江口雄輔
ジャンルにこだわらない作品傾向とそれにふさわしい多彩な文体、十蘭は安住することなくつねに文体実験を試みた。安住できなかったといったほうが正しいかもしれない。どこかにあるはずの理想郷がどうしても捕捉できないもどかしさがあり、他方、目の前の現実には満たされないもの、欠落している部分があったからだ。何が欠けているのか、それは本人にもわからない。それだけいっそう現実世界から隔絶した十全たる世界で、しかもそれにふさわしい久生十蘭の刻印がしっかり押されている世界を求めた。――<「解説」より>