講談社文芸文庫作品一覧

怒りの子
講談社文芸文庫
自分を掴もうとして空転を重ねる美央子。そんな美央子を姉のように見詰める、超然とした初子。美央子と同じアパートに住み、常に彼女にまつわりつく、虚言癖を持つますみ。3人の女性の緊迫した心理の劇は、美央子の松男への強引な思い入れを契機に、破局へと突き進む。昭和50年代後半の京都の町家を舞台に、周密な言葉運びと夢の持つ暗示力で、人間の内面の混濁の諸相を描破した、読売文学賞受賞作。
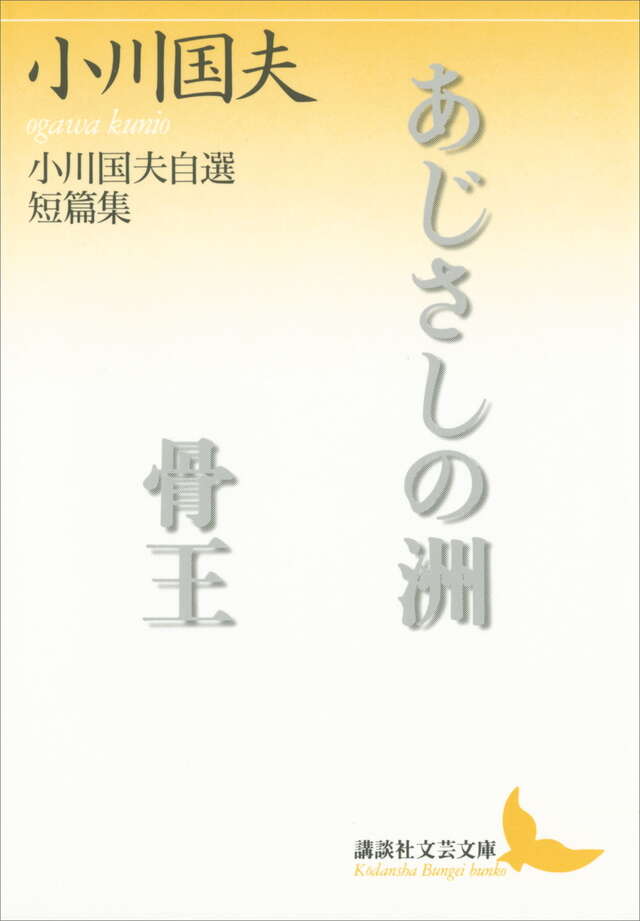
あじさしの洲・骨王
講談社文芸文庫
叔母の悲しみとそれに寄り添う少年の想いが原初的風景へと還元される名品「あじさしの洲」、旧約的世界を背景に、部族王の誕生とその最期を、心象の劇として描いた「骨王」、読売文学賞受賞作「ハシッシ・ギャング」等、初期作品から近作まで11篇を収録。簡勁な文体で人間の原質を彫琢し、影の暗示力が、生と死の流転の相を炙り出す。小川文学の魅力をあますところなく示す自選短篇集。

思想への望郷
講談社文芸文庫
読書論・わらべ歌考・抵抗論・死生観と短歌…。感性と知性を混合(ブレンド)した味わい深い対談集
[対談者]鶴見俊輔/三島由紀夫/塚本邦雄/別役実/種村季弘/岸田秀/吉本隆明
「書を捨てよ、街へ出よう」に象徴される寺山の思想。時代を牽引する7人の思想者との対論により、内蔵する逆理の根源が浮彫りにされる。鶴見俊輔との対話「読書論」、三島由紀夫「抵抗論」、塚本邦雄「ことば」、別役実「わらべ歌考」、種村季弘「都市とスペクタクル」、岸田秀「物語としての<宗教>」、死を可視した寺山の希求により実現した吉本隆明との対話「死生観と短歌」、代表的対談7篇を精選収録。
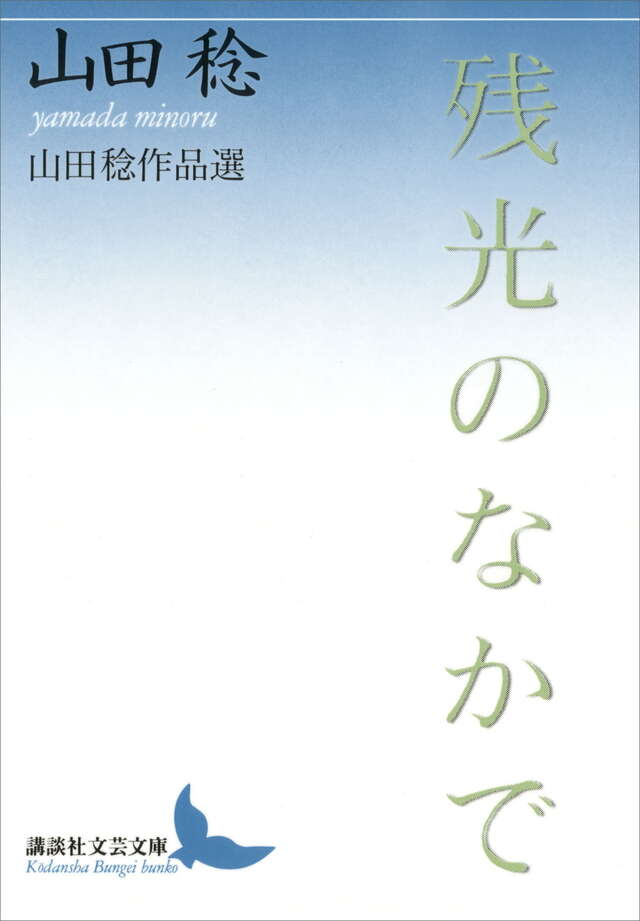
残光のなかで
講談社文芸文庫
ゾラを偲ぶ旅で出会った老文学者の孤独な姿を描いた「残光のなかで」、パリの街とそこで勁くつましく暮らす人々をやさしく見つめる「メルシー」「シネマ支配人」等、フランス滞在に材を求めた作品群に、記憶のあわいの中でゆらめく生の光景を追った「糺の森」「リサ伯母さん」等、8篇を収録。ユーモアとペーソスの滲む澄明な文体で、ひそやかで端正な世界を創り出した山田稔の精選作品集。

尾崎放哉随筆集
講談社文芸文庫
――咳をしても1人
大正15年4月、小豆島土庄町西光寺南郷庵で死去。「乞食坊主」と呼ばれ、人に嫌われ、失意と諦観の果てに所有した無常観。定型俳句を超え、洒脱諧謔をそなえた独得の自由律俳句により、染み入るような孤独を表出する。破天荒に生きた放哉の生活・文学・思想が彷彿とする作品群。俳句・エッセイ・書簡を精選収録。
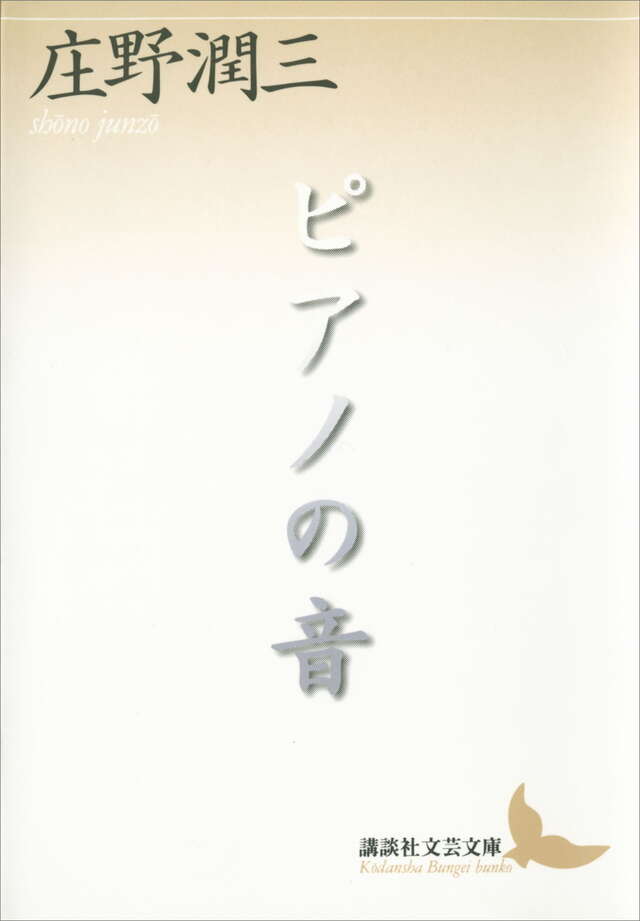
ピアノの音
講談社文芸文庫
小高い丘の家に住まう晩年の夫婦の穏やかな生活。娘や息子たちは独立して家を去ったが、夫々家族を伴って“山の上”を訪れ、手紙や折々の到来物が心を通わせる。夜になれば、妻が弾くピアノに合わせ、私はハーモニカ……。自分の掌でなでさすった人生を書き綴る。師伊東静雄の言葉を小説作法の指針に書き続けてきた著者が、自らの家庭を素材に、明澄な文体で奏でる人生の嬉遊曲。
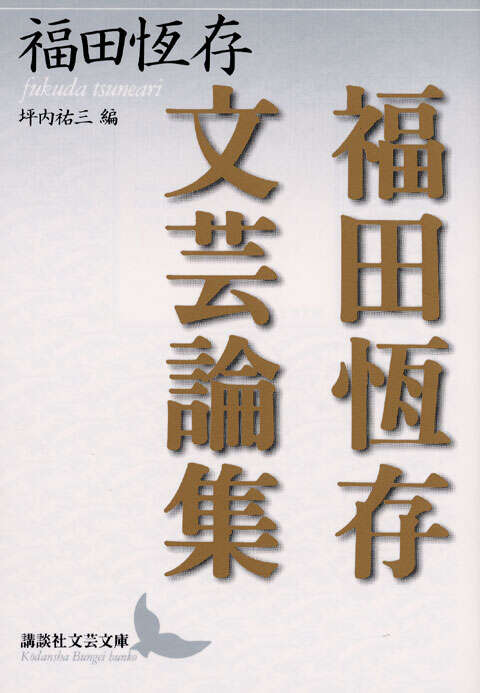
福田恆存文芸論集
講談社文芸文庫
日本近代の特殊性を反映した文学の諸潮流――私小説、左翼文学、さらには風俗小説等――が内包した歪みに対し、鋭い批判を展開した福田恆存。透徹した論理と卓抜なレトリックをもったその批評は、文学史の徹底した見直しを迫ってくる。戦前作から文壇文学を離脱するまでの代表的文芸批評18篇を収録。昭和の論客・福田恆存の批評精神あふれる鮮やかな軌跡がいま甦る。

埴谷雄高文学論集
講談社文芸文庫
孤高を持する思想者の世界 文学理論の根源を語る
全3巻完結
『死霊』自序に始まり、第1部 文学の原質、第2部 批評の本質とその機能、第3部 存在への接近、後書に『不合理ゆえに吾信ず』「遠くからの返事」で構成される第3巻。深遠な意識を表出する文学理論の根源が語られ、『死霊』に到る著者の表現世界が示唆的、啓示的に実証される。時代を超えて聳立する孤高を持した思想者埴谷雄高の評論選書全3巻完結。

なまみこ物語・源氏物語私見
講談社文芸文庫
贋招人(にせよりまし)姉妹によるいつわりの生霊騒動等、時の権力者・藤原道長の様々な追い落とし策謀に抗する、中宮定子の誇り高き愛を描いた女流文学賞受賞作「なまみこ物語」、『源氏物語』の現代語訳の過程で生まれた創見に満ちた随想「源氏物語私見」の二作を収録。円地文子の王朝文学への深い造詣と幼い頃からの親和に、現代作家としての卓抜な構想力が融合した二大傑作。
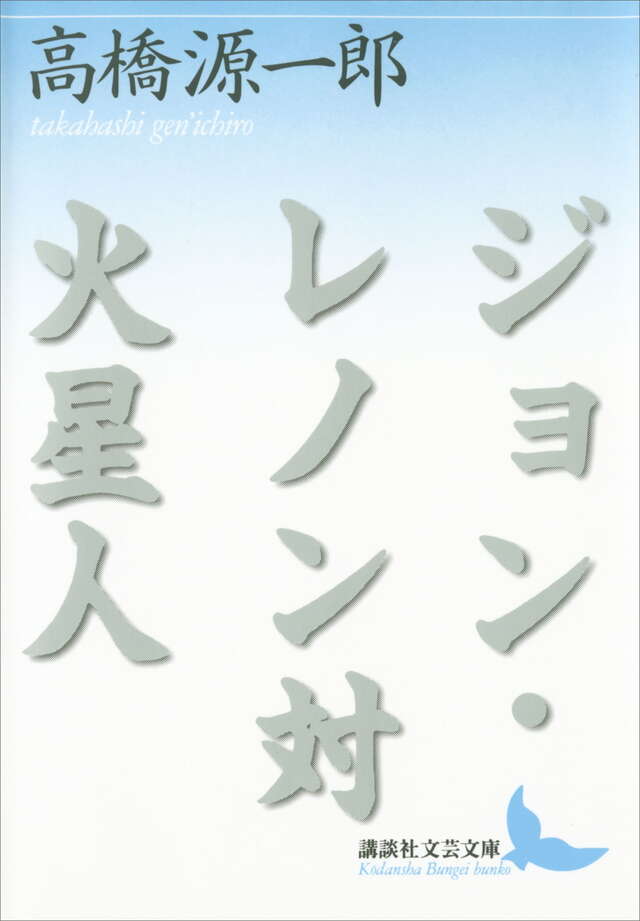
ジョン・レノン対火星人
講談社文芸文庫
住所はなく、消印は「葛飾」、そして差し出し人の名前は、「すばらしい日本の戦争」……名作『さようなら、ギャングたち』に先立つこと1年、闘争、拘置所体験、その後の失語した肉体労働の10年が沸騰点に達し、本書は生まれた。<言葉・革命・セックス>を描きフットワーク抜群、現代文学を牽引する高橋源一郎のラジカル&リリカルな原質がきらめく幻のデビュー作。
住所はなく、消印は「葛飾」、そして差し出し人の名前は、「すばらしい日本の戦争」…………
名作『さようなら、ギャングたち』に先立つこと1年、闘争、拘置所体験、その後の失語した肉体労働の10年が沸騰点に達し、本書は生まれた。<言葉・革命・セックス>を描きフットワーク抜群、現代文学を牽引する高橋源一郎のラジカル&リリカルな原質がきらめく幻のデビュー作。

埴谷雄高思想論集
講談社文芸文庫
存在の本質を根源的に追究
深遠・豊潤な思想世界
存在の本質を根源的に追究した埴谷雄高の思想世界。周到、緻密、重厚、凝縮された精神世界が鮮明に提示される。終焉を拒む未完の長篇『死霊』に限りなく接近し続ける深遠な思考。「『標的者』序詞」「目的は手段を浄化しうるか」「透視の文学」「政治の周辺」「夜の思想」「闇のなかの思想」「ニヒリズムとデカダンス」「自由とは何か」「夢と人生」「宇宙のなかの人間」等を収める評論選書第2巻。
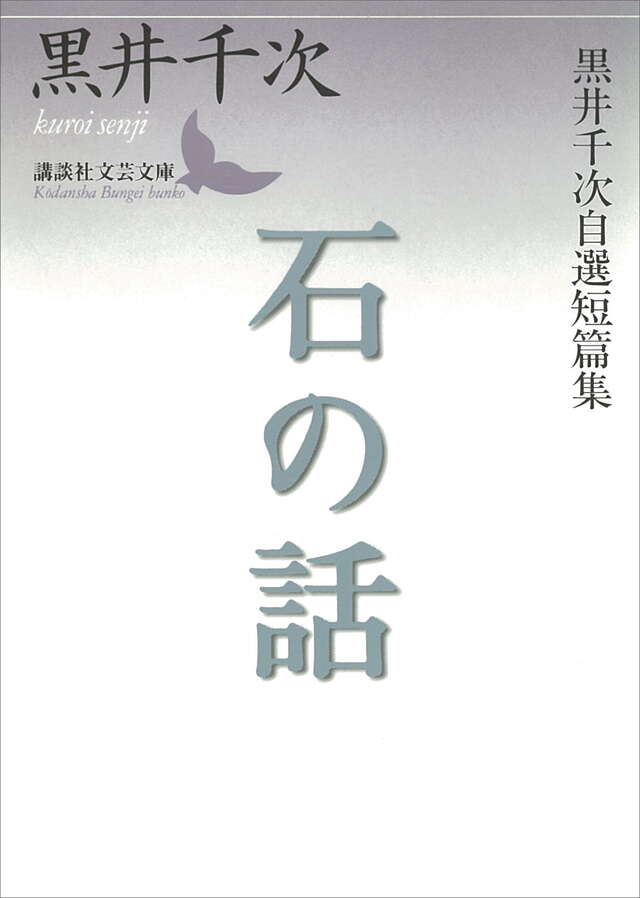
石の話 黒井千次自選短篇集
講談社文芸文庫
夫婦の間に流れた時間の持つ意味の落差を象徴的に捉えた表題作「石の話」、上司との関係にしこりを生んだネクタイをめぐる騒動を追った「首にまく布」、隣家の庭に出現したプレハブの子供部屋の日ごとの変貌がもたらす波紋を綴った「庭の男」等、家庭や職場に紛れ込んでくる違和を妙趣あふれた筆致で描いた9作品を収録。初期作品から近作まで、著者の歩みを辿る自選短篇集。

世相・競馬
講談社文芸文庫
終戦直後の大阪の混沌たる姿に、自らの心情を重ねた代表作「世相」、横紙破りの棋風で異彩を放つ大阪方棋士・坂田三吉の人間に迫る「聴雨」、嫉妬から競馬におぼれる律儀で小心な男を描いた「競馬」、敬愛する武田麟太郎を追悼した「四月馬鹿」等、小説8篇に、大阪人の気質を追究した評論「大阪論」を併録。自由な精神で大阪の街と人を活写した織田作之助の代表作集。
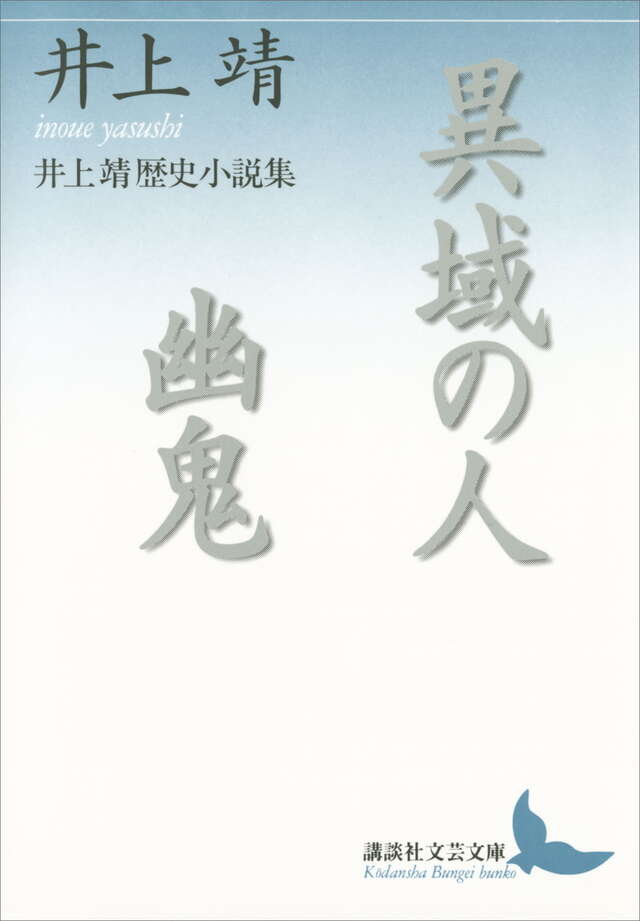
異域の人・幽鬼
講談社文芸文庫
半生を西域に捧げた後漢の人・班超の苦難に満ちた道と孤独な魂の彷徨を追った「異域の人」、留学僧・行賀の在唐31年の軌跡と、入唐した日本人のさまざまな生の選択を描いた「僧行賀の涙」、謀反へと明智光秀を導く心の闇に巣くった亡者に迫る「幽鬼」など、歴史小説の名作8篇を収録。時代の激動を生きぬいた人間の姿を比類なき語りの力で描破する井上文学の魅力溢れる1冊。
班超、松永久秀、明智光秀・・・
時代の激動を生きた男たち。
半生を西域に捧げた後漢の人・班超の苦難に満ちた道と孤独な魂の彷徨を追った「異域の人」、留学僧・行賀の在唐31年の軌跡と、入唐した日本人のさまざまな生の選択を描いた「僧行賀の涙」、謀反へと明智光秀を導く心の闇に巣くった亡者に迫る「幽鬼」など、歴史小説の名作8篇を収録。時代の激動を生きぬいた人間の姿を比類なき語りの力で描破する井上文学の魅力溢れる1冊。
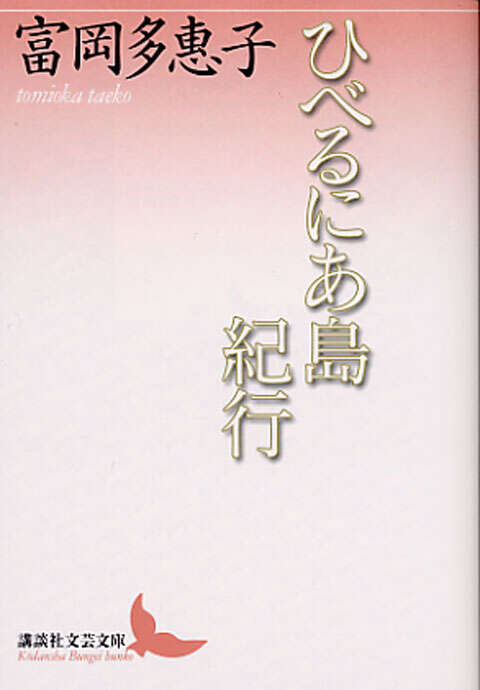
ひべるにあ島紀行
講談社文芸文庫
冬の国(ひべるにあ)=アイルランド。スイフトの『ガリヴァー旅行記』に導かれ冬の国(ヒベルニア)=アイルランドを訪れた「わたし」。謎めいたスイフトの生涯を、一人の女性への「激しい友情」を核に読み解くタテ糸。「わたし」と妖精のような男たちとの「優しい性愛」を物語るヨコ糸。さらに、架空の国・ナパアイをガリヴァーのように旅する「わたし」が目にする、グロテスクな意匠。重層的な表現でタペストリのごとく織られた、富岡文学の達成。孤絶した魂が谺し合う交響詩! 野間文芸賞受賞作品。

埴谷雄高政治論集
講談社文芸文庫
戦後世代に深く影響を与えた埴谷雄高の思想集成。全3巻
戦後世代の思想形成に深く影響を与えた埴谷雄高。思考の小説化を試み、思索的想像力によって創出された『死霊』を裏打ちする想像力、政治理論、文学論等を埋込んだ「埴谷雄高評論選書」全3巻のうち、政治的考察を展開する第1巻〈政治論集〉、「政治をめぐる断想」「政治のなかの死」「現実政治の狙撃」「死滅せざる『国家』について」など収録。『死霊』に続く埴谷雄高の評論集初の文庫化。

私の文学放浪
講談社文芸文庫
旧制高校に入学した頃の文学との出逢い、詩作、敗戦後の同人雑誌参加、大学中退、大衆雑誌記者時代、肺結核。芥川賞受賞までのエピソードや、父吉行エイスケのこと等著者の交友・文学の“核”を明晰な文体で瑞々しく回想。ほかに「拾遺・文学放浪」「註解および詩十二篇」を収める。
自分が天才でないことは、はっきりしている。しかし、才能はあるはずだ。たしかに翼は……(本文より)
旧制高校に入学した頃の文学との出逢い、詩作、敗戦後の同人雑誌参加、大学中退、大衆雑誌記者時代、肺結核。芥川賞受賞までのエピソードや、父吉行エイスケのこと等著者の交友・文学の“核”を明晰な文体で瑞々しく回想。ほかに「拾遺・文学放浪」「註解および詩十二篇」を収める。

奈良登大路町・妙高の秋
講談社文芸文庫
奈良へと出郷していく少年期の回想とともに、家族、故郷への想いを謳った読売文学賞受賞作「妙高の秋」、奈良の美術出版社・飛鳥園を舞台に、美しき出会いと別れを綴る「奈良登大路町」、戦時下、師・志賀直哉、瀧井孝作との愛情溢れる交流を描いた「焦土」など、寡作で知られる作家の珠玉の8作品を収録。端正な文体で創り出される純度の高い抒情的世界の魅力を凝縮した名作集。

戦後短篇小説再発見18
講談社文芸文庫
人間の深層に辿りつくための言葉の冒険――ユニークな着想によって読者を奇妙な世界に誘う寓話、幻想譚11篇
・日影丈吉「かむなぎうた」
・矢川澄子「ワ゛ッケル氏とその犬」
・谷崎潤一郎「過酸化マンガン水の夢」
・星新一「ピーターパンの島」
・色川武大「蒼」
・吉行淳之介「蠅」
・中井英夫「鏡に棲む男」
・村上龍「ハワイアン・ラプソディ」
・村田喜代子「百のトイレ」
・川上弘美「消える」
・室井光広「どしょまくれ」

月の十日
講談社文芸文庫
何を急ぐ旅でもないのにせかせかと鞄をまとめたのは、空模様の悪い11月半ばであった。(本文より)
日本の各地を訪れ、折々の旅情を綴った表題作「月の十日」、“のっへら棒の東京に何かしら飢えに似たものを感じた”と書き、敗戦後の風俗を鮮やかにとらえた「東京雑記」、ほかに「燈下言」、「随筆四題」を収録。名文家で知られた孤高の詩人・三好達治の珠玉のエッセイ群。