講談社文芸文庫作品一覧

神の道化師・媒妁人
講談社文芸文庫
「わい、知りまへんのや。乞食だっしゃろ」家出少年が、無料宿泊所で見た最底辺の庶民の救いの無い生。そこから脱出を企てた時、少年は親切を尽くしてくれた男を冷然と切り捨てる。「ペテロのイエスの否認を思いださせる短編の傑作」と埴谷雄高が評した自伝的小説「神の道化師」等6篇。共産主義からキリスト教へと遍歴を重ねた著者が、実存的リアリズムと突き抜けたユーモアで描く秀作を精選。
井口時男
このささやかなアンソロジーを、私は「椎名麟三ユーモア小説集」とでも呼びたく思う。(略)椎名麟三のユーモアはそれ自体独特な神学である。(略)この国の貧乏な庶民生活のなかの粗末でありふれた事物だけを使って書かれたユニークな「神学小説」。(略)共同体が壊れ、人間と人間、国家と国家のこわばった関係が自己絶対化に根ざす凶悪な暴力を生みだしている今日、(略)このアンソロジーは、そうした時代に向けて差し出す1冊でもある。――<「解説」より>

窪田空穂歌文集
講談社文芸文庫
鉦(かね)鳴らし信濃の国を行き行かばありしながらの母見るらむか
空穂の代表的な短歌、それに対峙する三部構成の散文。「母の写真」「不惑の齢」「老の顔」ほかで、わが来し方を綴り、「歌人和泉式部」「橘曙覧の歌幅」「与謝野寛氏の思い出」「斎藤茂吉『寒雲』の技巧」などで和歌、短歌論に及び、「香気」「電車の中で」「年賀状」では日常の様々を記して柔らかな心を表出。著者の偉業の精髄を凝縮し編纂。
あらゆる植物にはその物に限っての香がある。別けて香の強いのは花で、かの雄蕊は雌蕊を、雌蕊は雄蕊をと、相思う力が熾(さか)んに、花粉の授受の行われる時には、芳香はさながら蔵の戸の開かれたがようにその中より限りもなく吐き出される。これは花粉を授受する為よりか、又はその媒介の役をする蝶、蜂を招く為であるか、何れにもせよ生殖を中心として起り来ることだ。そして我等の香水と称する物は、この時において獲られる。――<本文「香気」より>

五里霧
講談社文芸文庫
2.26事件、戦争、召集、労働運動、差別、左翼文学、東欧民主化、フェミニズム、エイズ……。1931年から1992年までの、ある年ある月の出来事を手懸りに、当時の時代相を鋭く抉り、人間の生き方を問い直す12の物語で構成された短篇オムニバス「十二か月物語」。俗情との結託を排し、厳格で論理的な文体により、時代の流れと生の意味の根源へと遡行する意欲作。
鎌田哲哉
大西巨人が自らの短編で絶えず提示したのは、「ひとりで立つ」ことを試みる者達が、互いの差異を維持しつつ古い言葉を破砕され、新たな言葉と出会って行く活動の原光景なのである。だが改めて考えれば、それは他ならぬ『神聖喜劇』の様々な急所にも存在したはずだ。――<「解説」より>

改訂 文学入門
講談社文芸文庫
1954年初刷刊行以来絶讃され、実験的実作による研究成果が盛り込まれ、増補改訂が加えられた。「できるだけ分かりやすい形で、文学の形式、その感動、その文体、他芸術との比較」の諸点から一般読者に向けて書かれ、1979年には40刷の版を重ねた。<芸術とは何か>を追求した伊藤整の文学理論を集大成し、文学の本質を平易に解きあかした文学入門書の白眉。
近代日本文学という、世界文学の中での特異な性格の芸術を、ヨーロッパ文学と比較して考えてゆくあいだに、両方の条件を満足させるところの文学の本質というものを、想定せざるをえない立場に追いこまれた。それで私は、近代日本文学、とくに私小説とヨーロッパ文学とを同時に満足させうるところの、芸術の本質は何かということを、追求した。――<「あとがき」より>
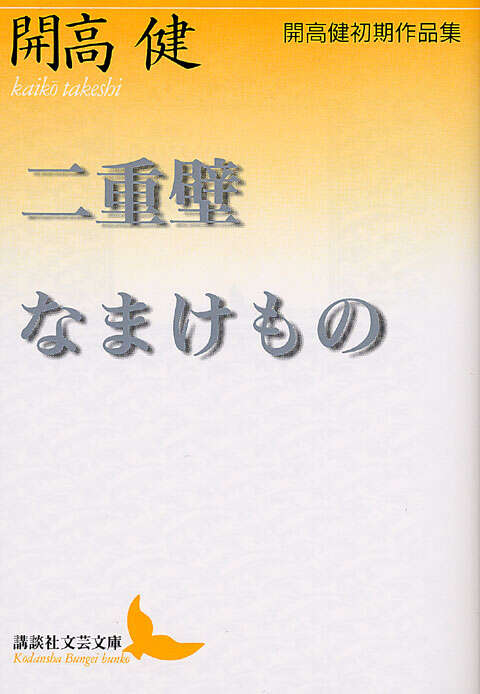
二重壁・なまけもの 開高健初期作品集
講談社文芸文庫
食うや食わずの苦学生、堀内と沢田。様々なアルバイトの末に、意にそわぬ選挙活動を手伝うことに……。敗戦後の闇市を舞台に、混沌たる世相とそこで生きぬく若い世代を、濃密な文体で描破した「なまけもの」。企業の空しい宣伝合戦の顛末記「巨人と玩具」など、小説3篇に、東京の街のスケッチ、ヴェトナム戦争をめぐるエッセイを併録。リアリズムの新たな可能性を拓いた<行動する作家>の初期作品を精選。
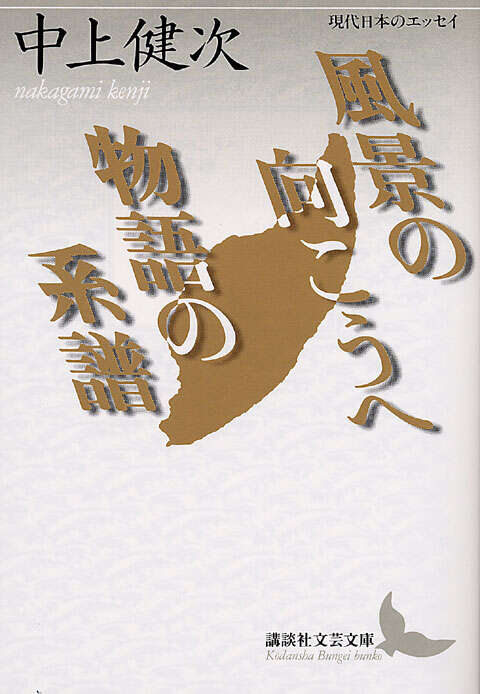
風景の向こうへ・物語の系譜 現代日本のエッセイ
講談社文芸文庫
風景の彼方に草木1本だに見つけられぬ熱砂があるのか、地の果てにはあの名づけられない森羅万象の空洞があるのか、読者と共に見定める覚悟を今、改めて確認する。韓国をめぐって書かれた表題作、たゆまず続けてきた佐藤春夫、折口信夫らの物語の解読の試み――。それらの1回目の報告、と著者自らが語る『地の果て 至上の時』に呼応する第3エッセイ集。
リキに会ったのは東京に着いた日の次の日、私が18歳のとき、新宿のモダンジャズ喫茶店「ジャズ・ヴィレッジ」で、である。それから何年経ったろう、私はこの夏44歳になった。(略)私は、方々に旅はしたが、ずっと東京にいた。当時書いていた詩をやめたが、小説は書いている。まだこれからも書き続けるはずだ。――<「新装版序文」より>

袋小路の休日
講談社文芸文庫
世に捨てられ老残の人生を送る著名な元雑誌編集者、不遇な映画監督、漂流する中国人青年、不器用なテレビ・タレント、都電、急激に変貌する東京の街……。1960年以降、喪失してしまった日常の深部の塊は、雑文書きを狂言回しにして増殖してゆく。「隅の老人」「北の青年」「路面電車」「ホテル・ピカディリー」「街」など<時代の違和>を描く連作短篇小説7篇。
坪内祐三
素晴らしい短篇集だと思った。完璧な作品集である。純文学(芥川賞的作品世界)であるとか読物文学(直木賞的作品世界)であるとかいった枠組みを越えて、まさに文学である。その作品世界の味わいは、例えば、アメリカのジョン・チーバーやジョン・アップダイクのそれに似ている。チーバーやアップダイクはいわゆる『ニューヨーカー』派の作家であるが、実際『袋小路の休日』に収められている連作短篇は、発表当時、そのまま英訳されて『ニューヨーカー』の誌面を飾っていたとしても何の異和感もなかっただろう。――<「解説」より>

骨の火
講談社文芸文庫
少年の持つ純粋さから、カトリックに入信した漆山。高校時代、級友を傷つけ、その告解の機会を逃したことから、神に背き、淪落の道へと迷い込む。大学時代、寄宿先の母娘と通じ、後に2人を死へ追いやったことで、後半生、精神の病に囚われるが、影のようにまといつく娘の父親の存在が、漆山に終末の日を迫る。人間の深奥にある欲望と、罪の意識の相剋の劇を描破した、異色のカトリック文学。
森内俊雄
のっけから難問を突きつけてきた。彼は私に尋ねた。自分はいったい、何のために生きているのだろうか。人が生きる、その本当の目的は、何であるのか、それが知りたい。彼は真面目で真剣だった。私は自分の作品『骨の火』の主人公、漆山陽三がうつし身として蘇り、出現してきたような気がした。漆山より遥に純粋一途な人間が、私を詰問しにやってきた、と思った。――<「著者から読者へ」より>

白秋 青春詩歌集
講談社文芸文庫
九州柳河の豪商の子として生い立ち、乳母日傘の幼い日々の性の目覚めを鮮烈に歌う「思ひ出」。文学を志し上京、詩壇の寵児となった青年の才気と野心が眩しい「邪宗門」。人妻との姦通で告訴され「三八七番」という囚人の身となる20代後半の痛切な恋愛体験に基づく歌集「桐の花」――など。初期の詩と歌に、詩的散文「わが生ひ立ち」はじめ珠玉の随筆を加え、生命感沸き立つ青春像を浮き彫りにする。
熱い生の奔流
白秋にとっての<青春>は、どこまでがそう呼ぶにふさわしい時期か、と考えた。(略)松下俊子との恋愛は、白秋20代後半の4年間を占める大事件だった。(略)白秋をもっとも白秋たらしめている作品はこの時期に書かれた。この恋愛体験は、それほど決定的なものだった。それでわたしは、初期白秋を特徴づける詩歌集の紹介をしながら、この甘美にして切実、悲痛きわまる恋愛の経過・行く末がたどっていけるように、この「詩歌集」を編集してみた。――三木卓(編者)

大観伝
講談社文芸文庫
岡倉天心を師と仰ぎ、師の理想と精神を継承して日本画の近代化に苦闘した横山大観。明治・大正・昭和の三代に亘り侠骨の画人と謳われた巨人・大観の波瀾の生涯を、東京美術学校日本画科卒の経歴を持ちながら、絵を捨て文学に転じた著者が、渾身の力を傾注し書き綴った大観伝。多彩な資料を駆使し、大観の内面を掘りさげ、苦闘の内実を鮮やかに描出。著者の新生面を拓いた画期的評伝。

詩人のノート
講談社文芸文庫
移り住んだ鎌倉の風物、様々な交遊と若き日の回想、旅での逸話の数々、愛すべき酒と書物……。自作をはじめ、数多くの詩の引用を導きとして、詩人をとりまく日常を、四季を通じて描いたエッセイ42篇。ユーモア溢れる各篇から、戦後詩を切り拓き、常に詩の最前線で活躍し続けた著者の、円熟した詩想と自由なる精神が漂う珠玉の随筆集。読書の悦びを満喫する1冊。

寂兮寥兮
講談社文芸文庫
幼なじみの万有子と泊は、ごっこ遊びの延長の如き微妙な愛情関係にあったが、それぞれの夫と妻の裏切りの死を契機に……。ふたりを軸に三世代の織りなす人間模様は、過去と今、夢とうつつが混じり合い、愛も性もアモラルな自他の境なき幽明に帰してゆく。デビュー以来、西欧への違和を表現してきた著者が親炙する老子の思想に触発され、生と性の不可解さを前衛的手法で描いた谷崎潤一郎賞受賞作。
幼なじみの万有子と泊は、ごっこ遊びの延長の如き微妙な愛情関係にあったが、それぞれの夫と妻の裏切りの死を契機に……。ふたりを軸に三世代の織りなす人間模様は、過去と今、夢とうつつが混じり合い、愛も性もアモラルな自他の境なき幽明に帰してゆく。デビュー以来、西欧への違和を表現してきた著者が親炙する老子の思想に触発され、生と性の不可解さを前衛的手法で描いた谷崎賞受賞作。

批評の精神
講談社文芸文庫
批評とは何かに答えるものもまた、批評である。批評は……人間を精神というかたちに限定してとらえる
小林秀雄の呪縛を受け苦悩した著者が、小林の存在を客観化させる試みの中で、彼の青春に深くかかわった河上徹太郎・大岡昇平・福田恆存・神西清・林達夫等に注目。さらに折口信夫を加え、その批評精神の構造を解き批評の原点を追究した第一評論集。亀井勝一郎賞受賞。
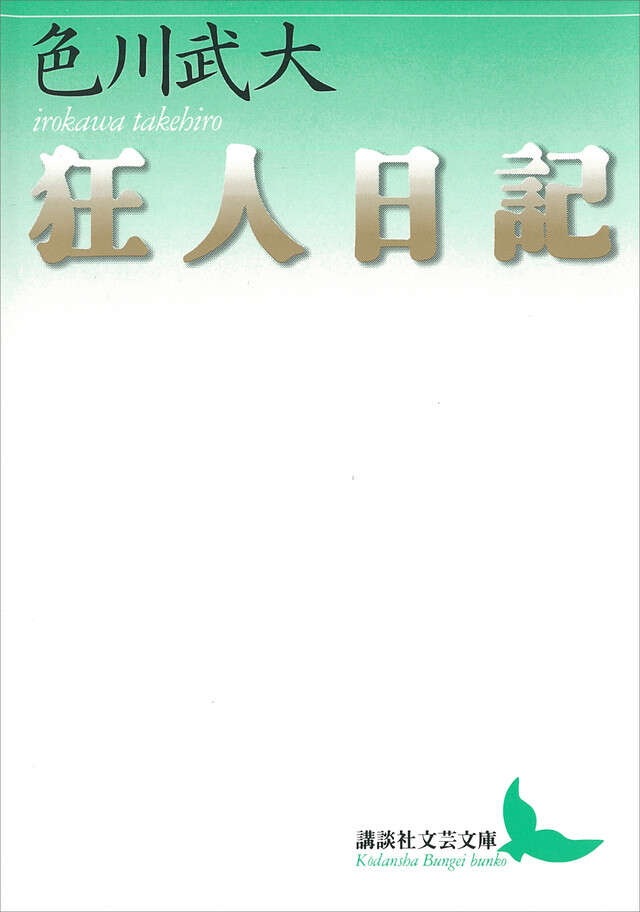
狂人日記
講談社文芸文庫
狂気と正気の間を激しく揺れ動きつつ、自ら死を選ぶ男の凄絶なる魂の告白の書。醒めては幻視・幻聴に悩まされ、眠っては夢の重圧に押し潰され、赤裸にされた心は、それでも他者を求める。弟、母親、病院で出会った圭子――彼らとの関わりのなかで真実の優しさに目醒めながらも、男は孤絶を深めていく。現代人の彷徨う精神の行方を見据えた著者の、読売文学賞を受賞した最後の長篇小説。
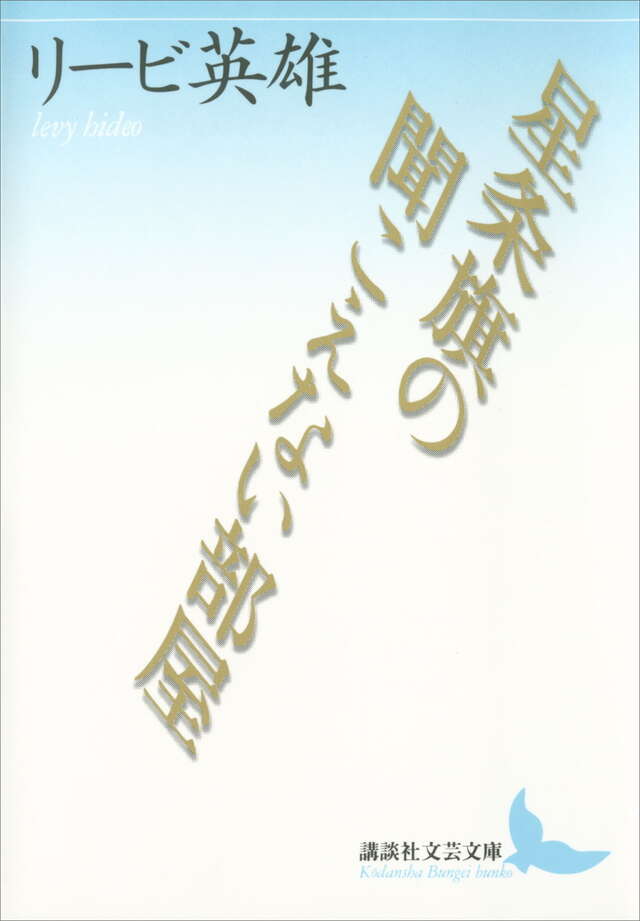
星条旗の聞こえない部屋
講談社文芸文庫
横浜の領事館で暮らす17歳のベン・アイザック。父を捨て、アメリカを捨て、新宿に向かう。1960年代末の街の喧騒を背景に、言葉、文化、制度の差を超え、人間が直接に向き合える場所を求めてさすらう柔らかな精神を描く野間文芸新人賞受賞の連作3篇。「日本人の血を一滴も持たない」アメリカ生まれの著者が、母語を離れ、日本語で書いた鮮烈なデビュー作。
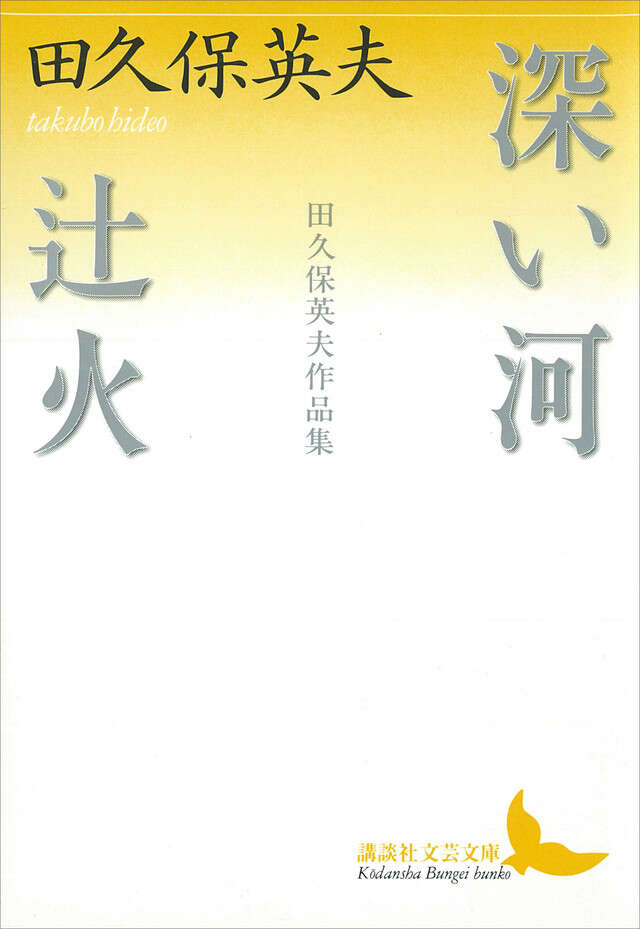
深い河・辻火
講談社文芸文庫
朝鮮戦争中の九州の兵站基地で、置きざりにされた徴用馬の世話をする青年の苦悩に迫る、芥川賞受賞作「深い河」。親戚の恋愛騒動を契機に訪れた、夏の下町の人間模様を描く、川端康成賞受賞作「辻火」。出生地の曖昧さに気づいた初老の男の地番を探す過去への旅を追った「生魄」。ほか、初期から晩年に至る7篇を収録。ストイシズムを底に秘め、気品ある世界を創った「短篇の名手」田久保英夫の、魅力溢れる代表作集。
朝鮮戦争中の九州の兵站基地で、置きざりにされた徴用馬の世話をする青年の苦悩に迫る芥川賞受賞作「深い河」、親戚の恋愛騒動を契機に訪れた、夏の下町の人間模様を描く川端賞受賞作「辻火」、出生地の曖昧さに気づいた初老の男の地番を探す過去への旅を追った「生魄」等、初期から晩年に至る7篇を収録。ストイシズムを底に秘め、気品ある世界を創った「短篇の名手」田久保英夫の魅力溢れる代表作集。

妣たちの国
講談社文芸文庫
「苦海浄土」三部作を完結させた石牟礼道子の、詩と散文による《魂の文学》60年の軌跡!
不治疾のゆふやけ抱けば母たちの海ねむることなくしづけし天草に生まれ不知火海に抱かれて生い立つ。実直な生活を歌う病弱な詩人は、近代の業苦と言うべき水俣の悲劇に遭い、声を奪われた人たち、動物植物等あらゆる生類、山河にざわめく祖霊と交感、怒りと祈りと幻想に満ちた「独創的な巫女文学」(鶴見和子)を結晶させる。60年に亘る石牟礼道子の軌跡を、短歌・詩・随筆で辿る精選集。

日本文学史早わかり
講談社文芸文庫
古来、日本人の教養は詩文にあった。だから歴代の天皇は詞華集を編ませ、それが宮廷文化を開花させ、日本の文化史を形づくってきたのだ。明治以降、西洋文学史の枠組に押し込まれて、わかりにくくなってしまった日本文学史を、詞華集にそって検討してみると、どのような流れが見えてくるのか? 日本文学史再考を通して試みる、文明批評の一冊。詞華集と宮廷文化の衰微を対照化させた早わかり表付。
古来、日本人の教養は詩文にあった。だから歴代の天皇は詞華集を編ませ、それが宮廷文化を開花させ日本の文化史を形づくってきたのだ。明治以降、西洋文学史の枠組に押し込まれてわかりにくくなってしまった日本文学史を、詞華集にそって検討してみると、どのような流れが見えてくるのか。日本文学史再考を通して試みる文明批評の1冊。詞華集と宮廷文化の衰微を対照化させた早わかり表付。

花衣
講談社文芸文庫
人生の落日を心身に自覚した男と、いのちの盛りの女。俗にいえば中年の男女のありふれた情事。だが昇りつめた2人を死の影が一閃、恋は華やぎの極点で幻の如く頽れる。満開の桜の恐ろしいまでに静まった美(「花衣」)、満潮には海に没する砂嘴の夢幻の美(「岬」)等、歌人にして作家上田三四二が、磨きぬかれた日本語の粋と、大患で得た生死一如の感覚をもって、究極のエロスを描く連作短篇集。

念珠集
講談社文芸文庫
大正12年7月、郷里山形の実父が世を去った。滞欧の茂吉はその死を知り悲しみにおそわれる。幼少の頃の父に纏わる様々が哀調を帯びて湧き上る。想い出の1つ1つを念珠の玉のように連らね、父を悼み懐かしむという意向で記された表題作「念珠集」をはじめ、「アララギ」同門・島木赤彦の終焉を克明に描写した「島木赤彦臨終記」、小品「山峡小記」「長崎追憶」など35篇を収めた第一随筆集。