講談社文芸文庫作品一覧

小林秀雄対話集
講談社文芸文庫
三島由紀夫、坂口安吾、大岡昇平、江藤淳、正宗白鳥、福田恒存、田中美知太郎、中村光夫ら12名と繰り広げる第一級の精神のドラマ。

猫道 単身転々小説集
講談社文芸文庫
失礼ですが御主人は? 収入は? 本籍地は? 保証人は? バブル後期の東京で“単身女性の安全な住まい”を求めて漂流する長編「居場所もなかった」に加え、後の“家族”キャト、ドーラ、ギドウ、モイラ、ルウルウをめぐる住居転々の短編。さらに不意の別れを描く「モイラの事」、その悲しみを越える単行本未収録の「この街に、妻がいる」、作者と猫の書き下ろし近況エッセイ二編も収録。
私は猫と出会ってこそ人間になった。
猫を知らぬころの悲しみと知ってからの喜怒哀楽をひとつながりに眺めて、笙野文学の確かな足跡を示す作品集。
<内容紹介>
失礼ですが御主人は? 収入は? 本籍地は? 保証人は? あなたは大家さんから好かれない、……学生専用となるワンルームを追われる独身中年女性、どこにも属せない無名作家が……イラク戦争下、バブル後期、家賃高騰中の東京において、“女性の安全なひとり住まい用ワンルーム”を求めて漂流する、絶版十五年ついに“復刊”の長編に加えその後の“家族”との出会い、キャト、ドーラ、ギドウ、モイラ、ルウルウを巡る住居転々の短編。
川端賞候補作「増殖商店街」、ふいの別れを描く「モイラの事」、その悲しみを越える、記念号掲載の未収録作品「この街に、妻がいる」さらに、書き下ろしお馴染み作者と猫の近況報告エッセイ二編収録。
猫をしらぬころの悲しみと知ってからの喜怒哀楽をひとつながりに眺める。「私だけが知っている、本屋にろくに置いてないけと大好きな」作家の恍惚、悲嘆、超克の猫出世街道。
<目次>
前書き 猫道、――それは人間への道
冬眠
居場所もなかった
増殖商店街
こんな仕事はこれで終りにする
生きているのかでででのでんでん虫よ
モイラの事
この街に、妻がいる(単行本未収録作品)
後書き 家路、――それは猫へ続く道
解説:平田俊子/年譜・著書目録:山崎眞紀子

建築文学傑作選
講談社文芸文庫
建築学科の必読書は谷崎「陰翳礼讃」であるという。
文学と建築。まったく異なるジャンルでありながら、
そのたたずまいやなりたちに文学を思わせる建築、
そして構造、手法に建築を思わせる文学がある。
構成、位相、運動、幾何学、連続/不連続――
日本を代表する建築家が選び抜いた、
既存の読みを覆す傑作“建築文学”十篇。
収録作品
須賀敦子「ヴェネチアの悲しみ」
開高健「流亡記」
筒井康隆「中隊長」
川崎長太郎「蝋燭」
青木淳悟「ふるさと以外のことは知らない」
澁澤龍彦「鳥と少女」
芥川龍之介「蜃気楼」
幸田文「台所のおと」
平出隆「日は階段なり」
立原道造「長崎紀行」

明日なき身
講談社文芸文庫
離婚を繰り返し、生活に困窮して生活保護と年金で生きる老人の日常の壮絶。高齢化社会を迎えた今、貧困のなかで私小説作家は、いかに生きるべきか……。下流老人の世界を赤裸々に描きつつも、不思議に悲愴感はない。自分勝手なダンディズムを貫き哀感とユーモアを滲ませる、二十一世紀の老人文学。
離婚を繰り返し、生活に困窮した作家、生活保護と年金で生きる老人の日常の壮絶。高齢化社会を迎えた今、貧困のなかで私小説作家は、いかに生きるべきか……。下流老人の世界を赤裸々に描きつつも、不思議に、悲愴感は感じられず自分勝手を貫く、二十一世紀の老人文学。

昔話
講談社文芸文庫
シェイクスピア、ワイルド、チャーチル、清少納言、鴎外…。古今東西を自在に渉猟し、類稀な知性で「世界」を読み解く最晩年の傑作。

K
講談社文芸文庫
詩人として出発し、小説、児童文学など幅広く活躍してきた著者が、詩への志を同じくする配偶者との出会いから末期癌による辛い闘病生活の末の最期までを愛惜とともに描いた私小説。貧しい暮らしをものともしない生き方、自我のぶつかり合いによって築き上げられた特異な夫婦生活、常軌を逸した子供との結びつき、詩と学問への執着、どこか平静な病気との向き合い方などを通して浮かび上がる「K」の孤高の魂が感動を呼ぶ長篇小説。
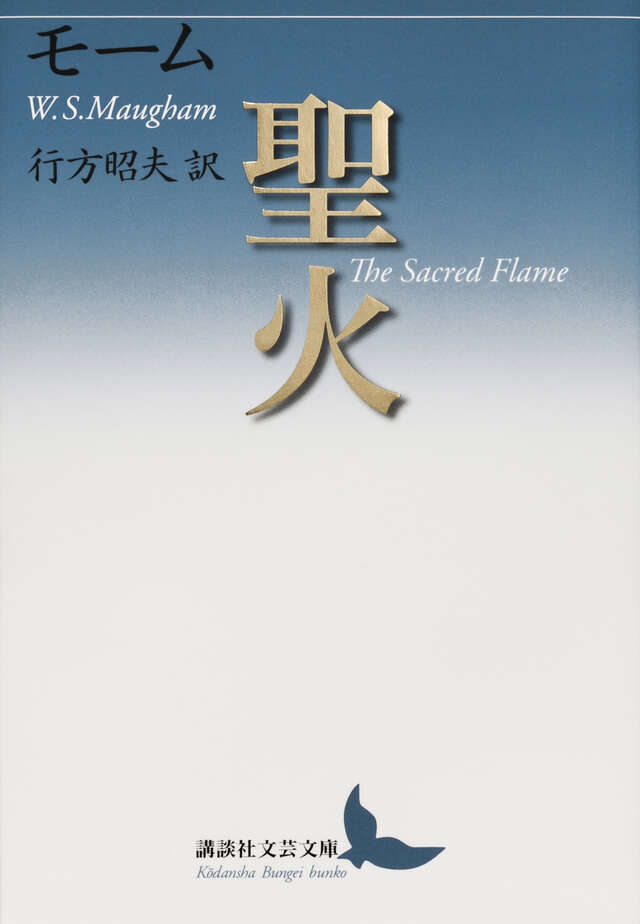
聖火
講談社文芸文庫
モームの問題劇を名翻訳者が訳し下した待望の書。穏やかな上流家庭の情景が一転、推理劇に。真の愛とは何か、幸福とは何かを問う傑作
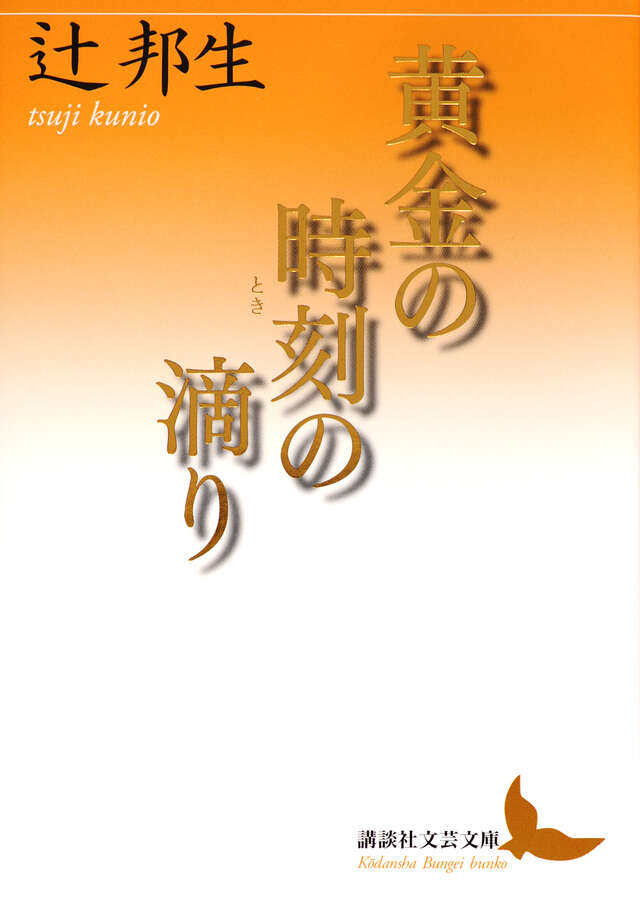
黄金の時刻の滴り
講談社文芸文庫
夢中で読んできた小説家や詩人の生きた時に分け入り、その一人一人の心を創作へと突き動かし、ときに重苦しい沈黙を余儀なくさせてきた思いの根源に迫る十二の物語。それは「黄金の時刻」である現在を生きる喜びを喚起し、あるいは冥府へと下降していく作家の姿を描き出す。永遠の美の探求者が研き上げた典雅な文体で紡ぎ出す、瑞々しい詩情のほとばしる傑作小説集。
今を生きる。
死を想う。
トーマス・マン、ヘミングウェイ、カフカ、スタンダール、トルストイ、漱石、
モーム、エミリ・ディキンスン、ゲーテ、リルケ、ヴァージニア・ウルフ……
東西の文豪たちの人生を垂直に貫く創作への熱情の核心
〈内容紹介〉
夢中で読んできた小説家や詩人の生きた時に分け入り、その一人一人の心を創作へと突き動かし、ときに重苦しい沈黙を余儀なくさせてきた思いの根源に迫る十二の物語。それは「黄金の時刻」である現在を生きる喜びを喚起し、あるいは冥府へと下降していく作家の姿を描き出す。永遠の美の探求者が研き上げた典雅な文体で紡ぎ出す、瑞々しい詩情のほとばしる傑作小説集。

黄金の時刻の滴り
講談社文芸文庫
著者が夢中で読んできた世界の小説家たちに憑依し、深い読みに裏打ちされた自在な想像力によって彼らの「生」の時間を描いた連作集。

日和下駄 一名 東京散策記
講談社文芸文庫
「一名 東京散策記」の通り「江戸切図」を持った永井荷風が、
思いのまま東京の裏町を歩き、横道に入り市中を散策する。
「第一 日和下駄」「第二 淫祠」「第三 樹」「第四 地図」
「第五 寺」「第六 水 附 渡船」「第七 路地」「第八 閑地」
「第九 崖」「第十 坂」「第十一 夕陽 附 富士眺望」の十一の
章立てに、周囲を見る荷風の独特の視座が感じられる。
消えゆく東京の町を記し、江戸の往時を偲ぶ荷風随筆の名作。

三木清教養論集
講談社文芸文庫
「教養といわれるのは単に専門的乃至職業的知識のことでなく、人間が真に人間らしくなるために必要な知識のことである。」ファシズムが台頭する昭和初期の日本社会で、のびやかに思考し時代と共に息づく教養の重要性を説いた孤高の哲学者、三木清。読書論・教養論・知性論の三部構成で、その思想の真髄に迫る。
「教養といわれるのは単に専門的乃至職業的知識のことでなく、人間が真に人間らしくなるために必要な知識のことである。」
ファシズムが台頭する昭和初期の日本社会で、のびやかに思考し時代と共に息づく教養の重要性を説いた孤高の哲学者、三木清。
読書論・教養論・知性論の三部構成で、その思想の真髄に迫る。
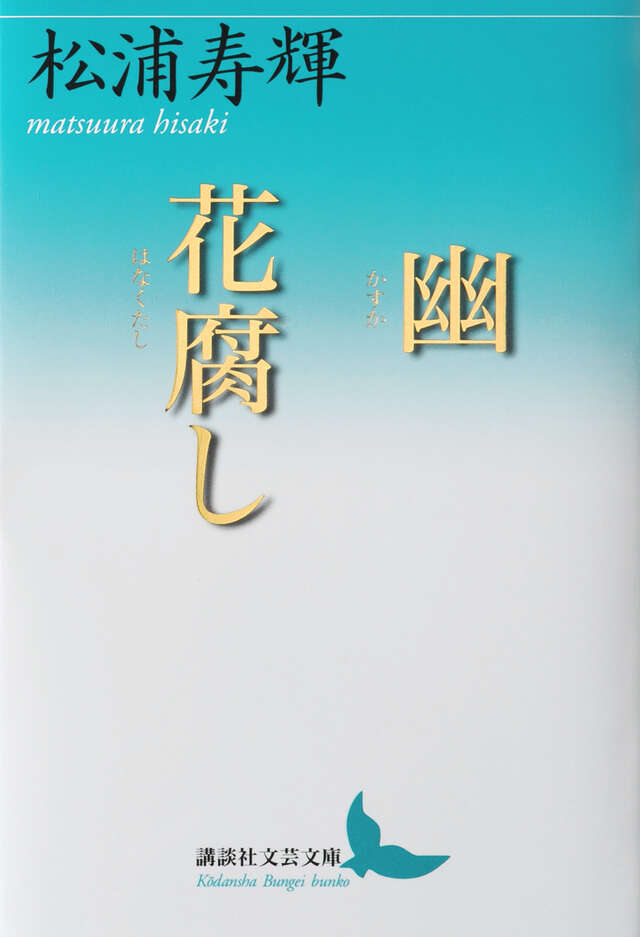
幽 花腐し
講談社文芸文庫
中華街のバーで、二十年以上前に遇った女の幻影に翻弄される男の一夜を描く、事実上の初小説「シャンチーの宵」、芥川賞候補作「幽」、同受賞作「花腐し」ほか全6篇。知的かつ幻想的で、悲哀と官能を湛えた初期秀作群。社会から外れた男が生きる過去と現在を、類稀な魅力を放つ文体で生々しく再現し、小説の醍醐味が横溢する作品集。

抱擁家族
講談社文芸文庫
「僕たちが外国から受け入れたものは、矛盾をうんでいる。その皺よせは家の中へ来るさ」
妻の情事と病。子供たちの離反。
夫は崩れゆく家庭をつなぎ止めようと、進行する悲劇とは裏腹に喜劇を演じ続ける。
鬼才の文名を決定づけた、戦後文学の金字塔。
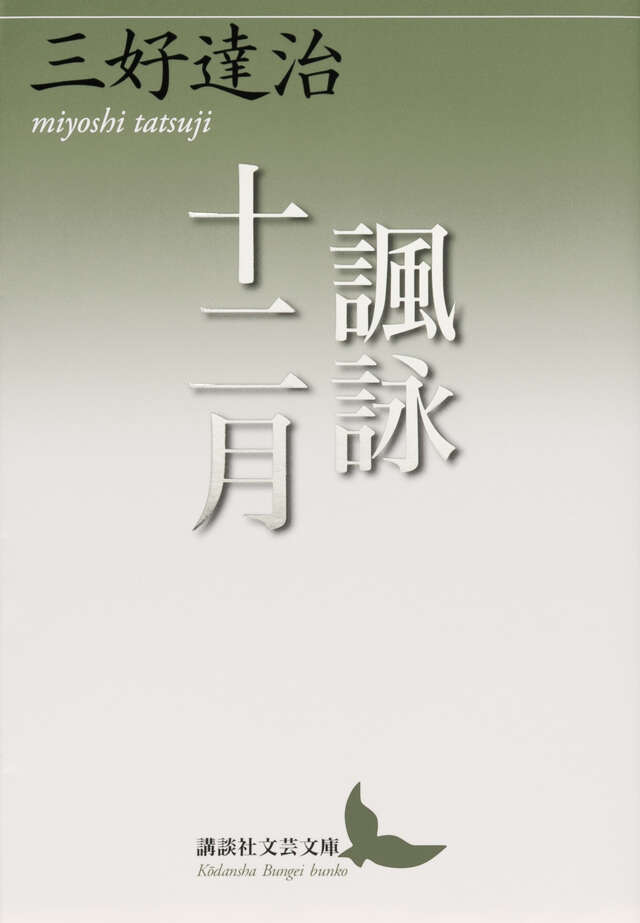
諷詠十二月
講談社文芸文庫
「この書は詩歌の理解に熱心な、あるいは熱心ならんと欲せらるる、比較的年少の初学の読者を聴者として、著者の素懐を仮りに題を設けて説かんと企てたもの……」。昭和17年9月、太平洋戦争のさなかに書下された本書は、万葉から西行、子規、晶子の短歌、菅原道真、新井白石、頼山陽の漢詩、芭蕉、蕪村、虚子の句、朔太郎、犀星の詩等々、秀作を鑑賞し、美と真髄を明かす、詩歌入門の不朽の名著。
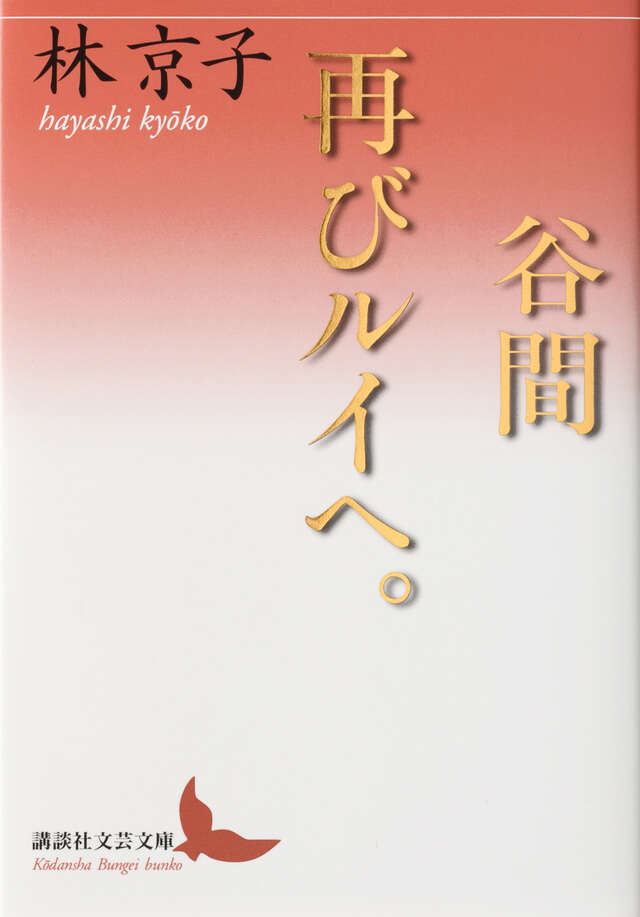
谷間/再びルイへ。
講談社文芸文庫
昭和20年、長崎の兵器工場学徒動員で、被爆。多くの死をくぐり抜け、少女は生き残った。結婚、出産、幼い命を育てるのは、恐怖との闘いであった。20数年後の離婚、それは個の崩壊であり、8月9日の闇なのか。80歳を越えて書いた小説「再びルイへ。」は、著者の歩んだ人生への回答、あるいは到達でもある。川端賞受賞作「三界の家」を含む、心うつ短篇小説集。
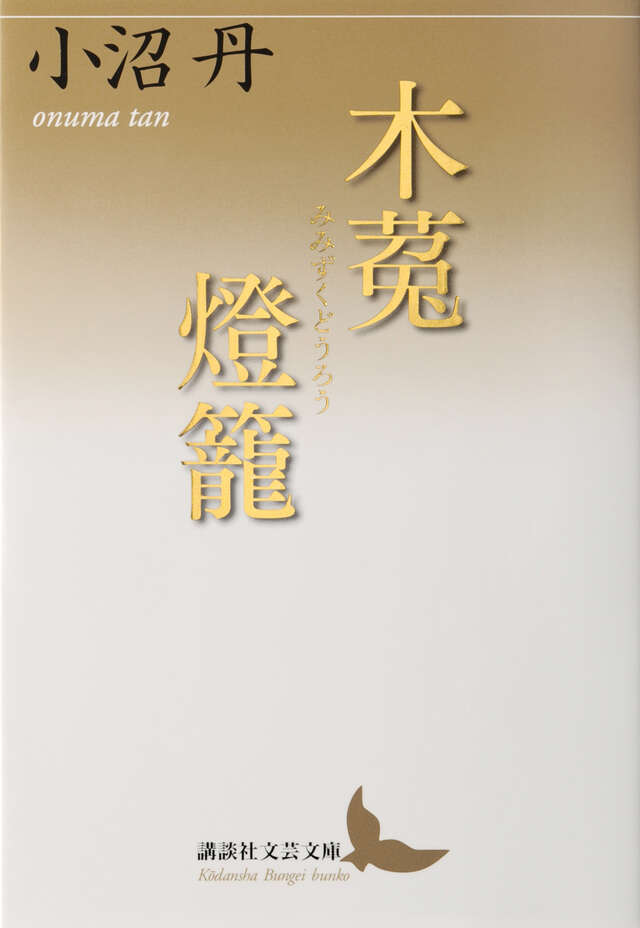
木菟燈籠
講談社文芸文庫
そこはかとないユーモアやはにかみを湛えたかざりのない文章でどこか懐かしいような風景を描き上げて多くのファンを持つ“小沼文学の世界”。季節や時代の移ろいに先輩の作家や同僚の教員、学生時代の友人など愛すべき人々の風貌を髣髴とさせる、この著者ならではの好短篇集。
<内容紹介>
好きが高じていきなり露地の奥で小鳥屋を始めた教員仲間。商売はやはりうまく行かず復職の世話をする成り行きに店先に据えてあった立派な石燈籠が我が家の庭に……。
日常のなかで関わってきた人々の、ふとしたときに垣間見る思いがけない振る舞いやうかがい知れない心のありようを、井伏鱒二ゆずりの柔らかい眼差しと軽妙な筆致で描き出した小沼文学ならではのじわりと胸に沁みるような作品集。

長春五馬路
講談社文芸文庫
長春で敗戦を迎えた木川正介は、毎日五馬路に出掛ける。
知り合いの朝鮮人の配下となり、大道ボロ屋を開業して生きのびている。
飄々として掴みどころなく生きながら、強靱な怒りにささえられた庶民の反骨の心情は揺るがない。
深い悲しみも恨みもすべて日常の底に沈めて、さりげなく悠然と生きる。
想像を絶する圧倒的現実を形象化した木山文学の真骨頂。
著者最後の傑作中篇小説。

自伝的女流文壇史
講談社文芸文庫
少女小説作家として一世を風靡し、若くして文壇にデビューした吉屋信子が描き上げた、「女流文壇」の草分けともいうべき十人の肖像。男性が中心だった近代日本の文壇史において「女流」と一括りにされながら個性豊かに輝いた女性作家たちの魅力を、折に触れての交流の中から余すところなくすくい上げた自伝的エッセイ。章ごとに一人の作家にフォーカスした構成になっていますので、どこからでも読むことができます。
文学で結ばれた女性たちの肖像
深い洞察と追慕の思いあふれる吉屋流〈私小説〉
<内容紹介>
田村俊子、岡本かの子、林芙美子、宮本百合子……。
早熟にして高等女学校に入学した頃から雑誌への投稿を始め、十代の終わりには上京して文壇へと飛び込んだ吉屋信子。一世を風靡した少女小説に加えて数々の新聞小説を手がけ、人望あつく昭和初期の女流文学者会を牽引してきた著者が、強く心に残った先達、同輩の文学者たちの在りし日の面影を直截にして真情こまやかに書き綴った貴重な時代の記録。

戦後的思考
講談社文芸文庫
1995年、戦後50年目に発表された「敗戦後論」は、単行本刊行後、百を越える批判を左右両翼から浴びた。本書はその反響の醒めぬなか、それらを正面から受け止め、「批判者たちの『息の根』をとめるつもり」で書き始められた。「戦後的思考」とは何か。戦前と戦後はなぜ「つながらない」のか? 今こそ我々に必要な、生きた思想と格闘する画期的論考を、増補改訂を施し、21世紀に再度問う。
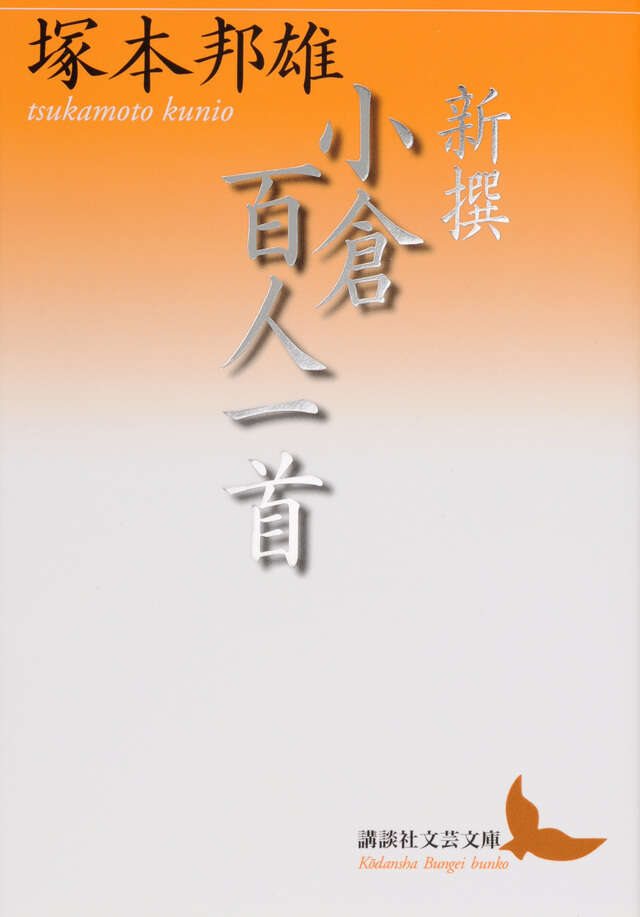
新撰 小倉百人一首
講談社文芸文庫
「沖の石の讃岐以外は悉皆非代表歌、式子と定家とあと二、三人を除けば、他は一切凡作――」。定家の百人一首が「凡作」揃いだとの批判は多い。だがあえて定家と同じ人選で、まったく別の「百人一首」を編んだ強者はいない。本書は前衛歌人・豪腕アンソロジストが放つ、定家への挑戦状である。どちらが秀歌か。読者ひとりひとりの判断を待つ。