講談社文芸文庫作品一覧

『深い河』創作日記
講談社文芸文庫
遠藤周作最期の、純文学書き下ろし長篇小説は、病魔と闘いながら、魂と体力のすべてをかけて書かれた。
『深い河』は遠藤周作の思考の行き着く果ての神についての、ひとつの結論であった。
構想から執筆までの苦悩。壮絶な日々。
書くこととは、神とは、を身をもって証明した著者の死後に発見された、感動の記録。
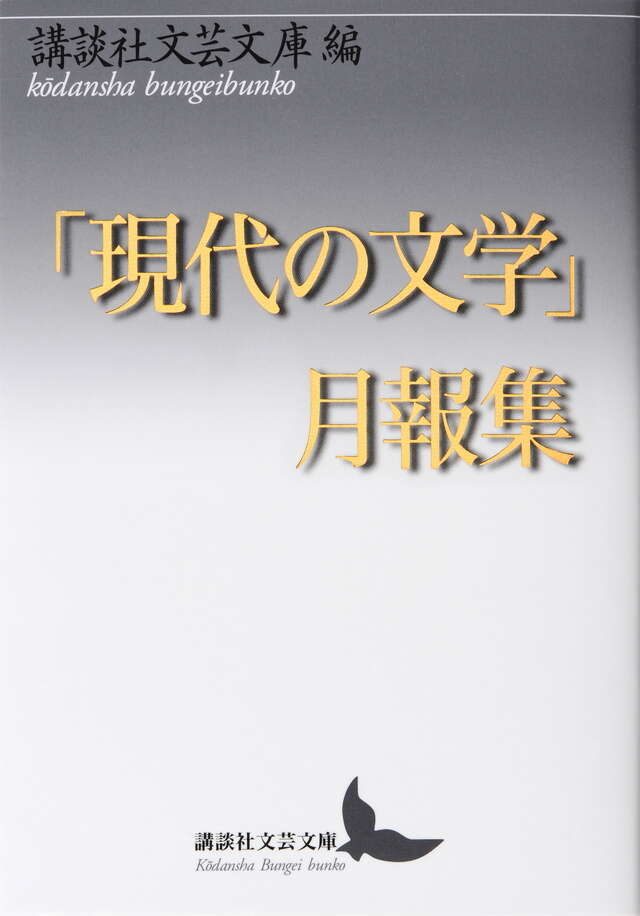
「現代の文学」月報集
講談社文芸文庫
1970年代前半、第一線の作家の代表作・名品を結集し、新時代の沃饒たる文学境域を提示した全集「現代の文学」。39巻に及ぶ全集購入者の特典として附された月報には、作家をよく知る書き手たちが、彼らの人間像と文学性をプライベートな眼差しで綴った多様な随筆を寄稿している。戦後派、第三の新人、内向の世代らが切磋する時代様相と、作家たちの知られざる横顔を堪能する月報集第4弾。

寺田寅彦セレクション2
講談社文芸文庫
科学者の眼で森羅万象を見つめ、平易でかつ芸術的味わい深い言葉で表現した文章を収める随筆選第二集。本巻には『柿の種』『物質と言葉』『蒸発皿』『触媒』『蛍光板』と没後刊『橡の実』から、「科学者とあたま」「津浪と人間」「夏目漱石先生の追憶」「鳶と油揚」等に加え、単行本未収の「茶碗の湯」「日本人の自然観」を併録。日本の近代随筆史上、最高にして極上のエッセンス。

哀歌
講談社文芸文庫
肉体の恐怖の前には精神など全く意味を失ってしまう。
臆病に生き臆病に埋もれて、自分がどんなに卑怯なのかどんなに弱いのか、たっぷり承知している――弱者。
弱者を凝視して聖書とキリストの意味を追求し、『沈黙』への展開を示唆した注目すべき短篇集。
人間の深層によどむ〈哀しみの歌〉を表題に据え、「その前日」「四十歳の男」「大部屋」「雲仙」など十二編を収める。

光の曼陀羅 日本文学論
講談社文芸文庫
埴谷雄高、稲垣足穂、南方熊楠、江戸川乱歩、中井英夫ら、「死者たちのための文学」を紡ぐ表現者の連なりを描き出す第一部「宇宙的なるものの系譜」。折口信夫の謎めく作品『死者の書』と関連資料を綿密に読み込み、物語の核心と新たな折口像を刺戟的に呈示する第二部「光の曼陀羅」。『死者の書』を起点に、特異な文学者の稜線を照射する気宇壮大な評論集。大江健三郎賞、伊藤整文学賞受賞。

「文壇」の崩壊
講談社文芸文庫
文壇事情に精通し、匿名批評も多くし、四十九歳で世を去った昭和の文芸批評家、十返肇。軽評論家と称され、正当な評価を受けていたとは言いがたい彼はしかし、文学への深い愛と理解力、該博な知識をもって、昭和という激動の時代の文学の現場に、生き証人として立ち会い続けた希有なる評論家であった。今なお先駆的かつ本質的な、知られざる豊饒の文芸批評群。
文壇事情に精通し、匿名批評も多くし、四十九歳で世を去った昭和の文芸批評家、十返肇。
軽評論家と称され、正当な評価を受けていたとは言いがたい彼はしかし、文学への深い愛と理解力、該博な知識をもって、昭和という激動の時代の文学の現場に、生き証人として立ち会い続けた希有なる評論家であった。
今なお先駆的かつ本質的な、知られざる豊饒の文芸批評群。

30代作家が選ぶ太宰治
講談社文芸文庫
「ときどき何だか恋しくなって、うっかりページをひらいてしまう」(朝吹真理子選「親友交歓」)、
「悲嘆にくれながら笑い、怒りながらおどける。背反を抱え、そのまま抱きしめ続ける人」(滝口悠生選「葉」)、
「儚くて、かわいくて、切実で」(西加奈子選「皮膚と心」)――
三十八歳で歿した太宰の短篇を、七人の現代作家が同世代の眼で選んだ作品選。

神楽坂・茶粥の記 矢田津世子作品集
講談社文芸文庫
昭和5年、「文学時代」懸賞小説に当選し文壇にデビュー。繊細な筆致で庶民生活の心理の葛藤を情感豊かに描き、「神楽坂」は芥川賞補作となる。表題作のほか生地秋田を題材にした「凍雲」、「父」「旅役者の妻より」「女心拾遺」「く女抄録」「鴻ノ巣女房」を収録。胸を病み37歳で逝去、坂口安吾によって伝説化された薄命の女性作家矢田津世子の代表的短篇小説8篇。

絵空ごと・百鬼の会
講談社文芸文庫
一風変った或る男が、同じ酒場の定連客らと語らって、自分ら好みで理想のサロンをもちたいと、遂には、18世紀英国風の至れり尽せりの洋館を作る仕儀となる。芳醇な酒と程よい会話と。時の流れは静かに開かれてゆく。虚実皮膜の間に夢かの如くに現れる。“至福の体験”の喜びを絶妙な文体で綴った長篇『絵空ごと』。短篇『百鬼の会』。奔放にして優雅、独特の想像力漲る吉田健一の真髄2篇。

草のつるぎ/一滴の夏 野呂邦暢作品集
講談社文芸文庫
「言葉の風景画家」と称される著者が、硬質な透明感と静謐さの漂う筆致で描く青春の焦燥。生の実感を求め自衛隊に入隊した青年の、大地と草と照りつける太陽に溶け合う訓練の日々を淡々と綴った芥川賞受賞作「草のつるぎ」、除隊後ふるさとに帰り、友人と過ごすやるせない日常を追う「一滴の夏」――長崎・諫早の地に根を下ろし、42歳で急逝した野呂邦暢の、初期短篇を含む5篇を収録。

戦後文学を読む
講談社文芸文庫
野間宏、武田泰淳、大岡昇平、梅崎春生、小島信夫ら、戦後文学作家の代表作を、現代の作家たちが読み、合評形式で論じ合う「群像」のシリーズ企画。奥泉光、高橋源一郎、島田雅彦、町田康、保坂和志らの現代文学の牽引者から、川上未映子、青山七恵、朝吹真理子、島本理生など若手まで、それぞれの作家たちが、各々の視点と感性で、戦後文学を俎上に侃侃諤諤の文学論を展開。
第二次大戦後の極限状況のなか、戦争と戦後社会への峻厳で実存的な眼差しで描かれた〈新しい文学〉は、「いまなお最も批評性が高い」(奥泉光)小説群である。野間宏、武田泰淳、梅崎春生、大岡昇平、小島信夫ら戦後派九人の代表作を、現代文学を牽引する作家・評論家たちが、群像の「創作合評」形式に読み、論じ合う。終戦から七〇年を経て浮き彫りになる、戦後文学の精神とは。
序章 対談 高橋源一郎・奥泉光
一章 野間宏 「暗い絵」「顔の中の赤い月」
合評/奥泉光・中村文則・島本理生
二章 武田泰淳 「蝮のすえ」「わが子キリスト」
合評/奥泉光・松永美穂・鹿島田真希
三章 椎名麟三 「深夜の酒宴」「重き流れのなかに」
合評/奥泉光・佐伯一麦・辻村深月
四章 梅崎春生 「桜島」「幻化」
合評/奥泉光・福永信・朝吹真理子
五章 大岡昇平 「野火」「武蔵野夫人」
合評/奥泉光・岡田利規・青山七恵
六章 石原吉郎 「ペシミストの勇気について」「棒をのんだ話」
合評/奥泉光・山城むつみ・川上未映子
七章 藤枝静男 「田紳有楽」「悲しいだけ」
合評/奥泉光・堀江敏幸・桜庭一樹
八章 小島信夫 「アメリカン・スクール」「月光」
合評/奥泉光・保坂和志・青木淳悟
九章 大江健三郎 「芽むしり仔撃ち」
合評/奥泉光・野崎歓・町田康
終章 対談 島田雅彦・奥泉光

風の系譜
講談社文芸文庫
遠い先ばかり見つめていた父は、絶望している。堅実な実際家の母は、希望をかけている。父と母の半生を中心に、複雑な一族の系譜を私小説作家が揺るぎなく描ききった長篇小説。新たに発見された、著者の手の入った原稿で野口冨士男の処女作ともいえる作品を七十余年の時を経て、初文庫化。
遠い先ばかり見つめていた父は、絶望している。
堅実な実際家の母は、希望をかけている。
父と母の半生を中心に、複雑な一族の系譜を私小説作家が揺るぎなく描ききった長篇小説。
新たに発見された、著者の手の入った原稿で野口冨士男の処女作ともいえる作品を七十余年の時を経て、初文庫化。

木下杢太郎随筆集
講談社文芸文庫
北原白秋らと「パンの会」を組織し、小説家、劇作家、美術家、キリシタン史研究家として活躍した耽美派の詩人は、医師としてハンセン病根絶に尽力した智と義の人でもあった。三島由紀夫が「いちばん美しい紀行文」と称した「クウバ紀行」、加藤周一が鴎外以後、荷風と共に「高雅な余韻」を伝えると評する史伝(「森鴎外」)他を収録。広い教養と思惟の深さを具えた巨人が遺した散文の精髄。

やすらかに今はねむり給え/道
講談社文芸文庫
昭和二十年、長崎の兵器工場で奪われた女学生達の青春。
やがて作られた報告書には「不明」の文字がならんでいた。
消えてしまった「生」の記録を日記・資料を基に綿密に綴った事実の被爆体験。
無数の嘆きと理不尽さ、その年の五月から原爆投下の八月九日までの日々を、
忘れないように、繰り返さないように、という鎮魂の願い。
林京子の原典でもある谷崎潤一郎小受賞作。他「道」を収録。

原色の呪文 現代の芸術精神
講談社文芸文庫
独創的な芸術作品のみならず、優れた芸術論やエッセイも多数遺した岡本太郎。1968年刊行の『原色の呪文』から、現代芸術に関する文章を抜粋、「黒い太陽」「わが友、ジョルジュ・バタイユ」「対極主義」「ピカソへの挑戦」「坐ることを拒否する椅子」「芸術の価値転換」「モダーニズム克服のために」などを収録。若き芸術家たちに絶大な影響を与えた芸術論の名著。

寺田寅彦セレクション1
講談社文芸文庫
「天災は忘れた頃にやってくる」など、後世に今も残る数々の言葉を生み、物理学者として世界的な業績をあげた寺田寅彦は夏目漱石の高弟として、透徹した観察眼で散文詩的美しさを湛えた文章を物し、科学と芸術の融合を果たした。本巻には『冬彦集』『藪柑子集』『万華鏡』『続冬彦集』から、内田百間に「昭和年代の随筆として後生に遺る第一のもの」と言わしめた、随筆家の真骨頂を示す名品を厳選収録する。

酔いざめ日記
講談社文芸文庫
昭和七年(二七歳)から、亡くなる直前の昭和四三年(六四歳)までの木山捷平の日記、初文庫化。詩から始まり、昭和八年に太宰治たちと同人誌「海豹」創刊後、小説を発表し、様々な作家と交遊を深めた木山。生活は困窮をきわめ、体調をくずしながらも書き続けた日々。作家の心情、家庭生活、そして何よりも、自らの死までも、じっと作家の眼で冷静に描ききった生涯の記。
昭和七年(二七歳)から、亡くなる直前の昭和四三年(六四歳)までの木山捷平の日記、初文庫化。
詩から始まり、昭和八年に太宰治たちと同人誌「海豹」創刊後、小説を発表し、様々な作家と交遊を深めた木山。
生活は困窮をきわめ、体調をくずしながらも書き続けた日々。
作家の心情、家庭生活、そして何よりも、自らの死までも、じっと作家の眼で冷静に描ききった生涯の記。

埴谷雄高
講談社文芸文庫
思想界の巨人・鶴見俊輔が、戦後文学に屹立する埴谷雄高と傑作「死霊」に迫る評論、対論集。ふたつの「知」が交わり拡がる思考の宇宙

「内向の世代」初期作品アンソロジー
講談社文芸文庫
後藤明生、黒井千次、阿部昭、坂上弘、古井由吉の初期短中篇を黒井氏が精選。再評価の声が高まる「内向の世代」の、必読アンソロジー
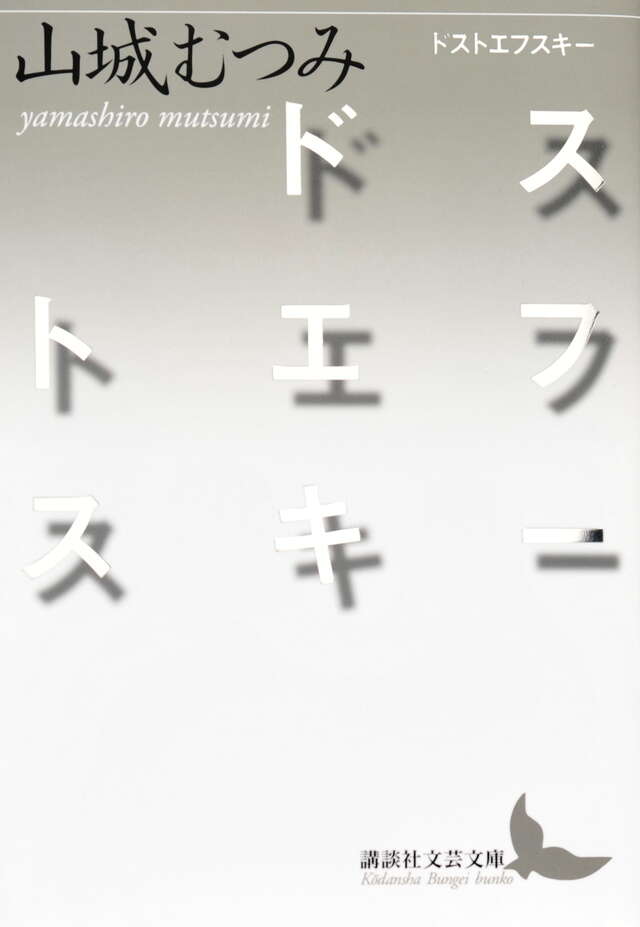
ドストエフスキー
講談社文芸文庫
同じ言葉でも誰がどんな状況で語るかで、その意味は異なり、ときに正反対に受け取れる。このラズノグラーシエ=異和こそがドストエフスーを読む鍵となる。登場人物は対話の中で絶えず異和と不協和に晒され、そのダイナミズムが読む者を強烈に惹きつけるのだ。批評家バフチンを起点に、しかし著者単独で小説内部に分け入り、文学的核心を精緻に照射する。ドストエフスキー論史の転換点を成す衝撃的論考。