講談社現代新書作品一覧

東京裁判
講談社現代新書
「東京裁判から60年。ようやく〈事実〉に基づく、冷静かつ実証的な研究がなされる時代がきたとの感に打たれた。〈歴史〉が待ち望んでいた書だ」――保坂正康(ノンフィクション作家) 東京裁判は「国際政治」の産物以上のものではない。イデオロギーを排し、「文明の裁き」と「勝者の報復」をめぐっての不毛な論争に終止符を打つ。第30回サントリー学芸賞<思想・歴史部門>受賞作。
「東京裁判から60年。ようやく〈事実〉に基づく、冷静かつ実証的な研究がなされる時代がきたとの感に打たれた。〈歴史〉が待ち望んでいた書だ。」――保坂正康(ノンフィクション作家)
東京裁判は「国際政治」の産物以上のものではない。イデオロギーを排し、徹底的な実証と醒めた認識で「文明の裁き」と「勝者の報復」をめぐっての不毛な論争にいまこそ終止符を打つ。
すでに東京裁判の開廷から60年余の歳月が経過している。「東京裁判開廷60年」の2006年に朝日新聞社が実施した日本国内の世論調査では、東京裁判をどの程度知っているかという質問にたいして、「裁判があったことは知っているが内容は知らない」が53パーセント、「裁判があったことも知らない」が17パーセント、合計70パーセントが、「知らない」という結果が出た(『朝日新聞』2006年5月2日)。……この数字にはなかなか驚くべきものがあると思う。二世代(60年)のあいだにこれだけ忘れられているなら、そろそろ冷静な議論も可能になっていそうなものだが、しかし現実は「逆である。……日本のマスメディアには「A級戦犯」「東京裁判」といった用語が飛びかい、旧態依然とした裁判の肯定・否定論争もかまびすしい。冷静で生産的な論争であれば、大いにやってもらいたいものである。しかし、この肯定・否定論争では、紋切り型の、ときには誤った知見が繰り返されるばかりだ。1980年代後半以降、東京裁判についての新しい事実がかなり発見されてきたが、それらは専門家の世界にとどまり、一般にはあまり普及していない。本書を世に問うのは、このためである。――<本文より>
第30回サントリー学芸賞<思想・歴史部門>受賞

ニッポンの大学
講談社現代新書
様々なランキングから見えてきた大学のいま。1995年以来続いている『大学ランキング』。人気の大学・学部から学生の生活、就職先から教授の実像まで。ランキングから見えてきたのは揺れる大学の姿だった。(講談社現代新書)
様々なランキングから見えてきた大学のいま。1995年以来続いている『大学ランキング』。人気の大学・学部から学生の生活、就職先から教授の実像まで。ランキングから見えてきたのは揺れる大学の姿だった。

国家・個人・宗教 近現代日本の精神
講談社現代新書
愛国心問題とスピリチュアル・ブームの共通点とは?
国家神道という特異な宗教で国民をまとめた戦前、宗教を語らない戦後の知識人。国家とは?個人とは?現代のスピリチュアルブーム、愛国心騒動につながる問題に鋭く切り込む。
私たちは南原繁の残した宿題に答えていない!
なぜ戦後日本で、「人間と神との対決」がまともに論壇のテーマにならないのか。なかなか答えるのが難しい問いだ。しかし実は非常に重要な問いである。ある意味では、近代日本の出発点にまで引き戻される問いだからだ。近代日本の精神構造やアイデンティティーに絡む根深い問題だからである。「人間と神との対決」、これが「宗教への問い」ということであれば、近代日本の出発点がすえられたときに、すでにこの問いはゆがんだ形で封印されてしまったのである。――<本文より>

モテたい理由 男の受難・女の業
講談社現代新書
もう疲れたよ……でも、止まれない。女たちを包囲する“モテ”の真実! モテ服にモテ子……女性誌はなぜ「モテ」を大合唱するのか? エビちゃんブームの深層、蔓延する自分語りの文法から恋愛至上主義とオタクの関係まで、混迷する男女の今をえぐる! (講談社現代新書)
女性誌がふりまく幻想に踊る女、逃走する男なぜエビちゃんOLが流行るのか? 次々に現れては消える理想のライフスタイル。女性ファッション誌に伏流する主題を、グルーブ感あふれる文章で明快に読み解く。

発達障害の子どもたち
講談社現代新書
言葉が幼い、落ち着きがない、情緒が不安定。
育ちの遅れが見られる子に、どのように治療や養護を進めるか。
長年にわたって子どもと向き合ってきた第一人者がやさしく教える。
第1章──発達障害は治るのか
第2章──「生まれつき」か「環境」か
第3章──精神遅滞と境界知能
第4章──自閉症という文化
第5章──アスペルガー問題
第6章──ADHDと学習障害
第7章──子ども虐待という発達障害
第8章──発達障害の早期療育
第9章──どのクラスで学ぶか―特別支援教育を考える
第10章─薬は必要か

日本を降りる若者たち
講談社現代新書
なぜ、彼らは海外で「こもる」のか?
バンコクはじめアジアの街で、何もせずただダラダラと生活する若者たちが増えている。彼らの生き方から映し出される日本社会の現実。

国語審議会 迷走の60年
講談社現代新書
「正しく、美しい」国語をめぐるドタバタ劇は敗戦からはじまった。漢字制限、仮名遣い、敬語……。みんなが従うべき規範をいったいどこに求めたらいいのか。面白くてやがて哀しい、もうひとつの戦後史。

日本人はなぜキツネにだまされなくなったのか
講談社現代新書
ターニングポイントは1965年だった! 私たちの自然観、死生観にそのときどんな地殻変動がおきたか? 「キツネにだまされていた時代」の歴史をいまどう語りうるのか? まったく新しい歴史哲学講義。(講談社現代新書)
ターニングポイントは1965年だった! 私たちの自然観、死生観にそのときどんな地殻変動がおきたか? 「キツネにだまされていた時代」の歴史をいまどう語りうるのか? まったく新しい歴史哲学講義。

ベートーヴェンの交響曲
講談社現代新書
第1番 ハ長調 「喜びにあふれた幕開け」 第2番 ニ長調 「絶望を乗り越えた大傑作」 第3番 変ホ長調 『英雄』「新時代を切り拓いた『英雄』」 第4番 変ロ長調「素晴らしいリズム感と躍動感」 第5番 ハ短調「完璧に構築された究極の構造物」 第6番 へ長調『田園』「地上に舞い降りた天国」 第7番 イ長調「百人百様に感動した、狂乱の舞踏」 第8番 へ長調「ベートーヴェン本人が最も愛した楽曲」
第1番にして「革命的」、5番は「完全無欠な構築物」、7番は「狂乱の舞踏のリズム」……。九つの交響曲はみな個性的。深く知れば知るほど、クラシックの虜になってしまうはず!

複数の「古代」
講談社現代新書
「歴史」はひとつではない。『古事記』と『日本書紀』の違いは何を意味するのか。
「聖徳太子」はいかに完成したのか。『万葉集』はなぜ「歴史」なのか。
「古代」の見方をくつがえす一冊。

あなたの会社の評判を守る法
講談社現代新書
消費者が「風評」を信じたとき、「単なる事故」は「社会的事件」となる。
致命的不祥事となるか、災い転じて福となすかはあなたしだい。
一連の消費者関連法改正をふまえ、適切かつ効果的な対応を伝授する。
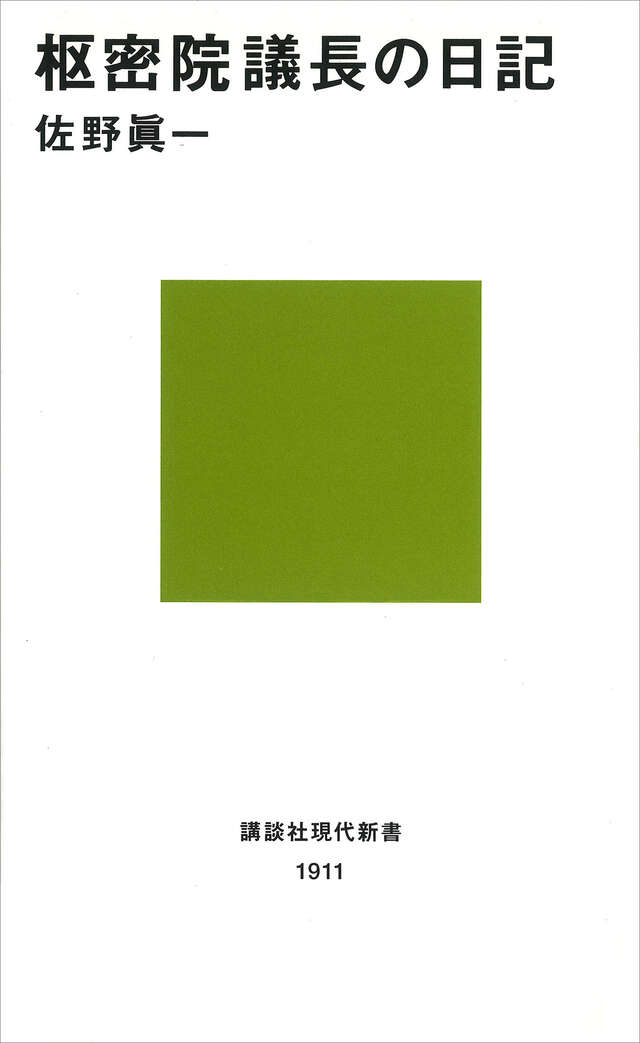
枢密院議長の日記
講談社現代新書
大正期、激動の宮中におそるべき“記録魔”がいた。その名も倉富勇三郎。宮中某重大事件、皇族・華族のスキャンダル、摂政問題……。誰も読み通せなかった超一級史料にノンフィクションの鬼才・佐野眞一が挑む。幕末に生まれ、明治、大正、昭和を生き、三代の天皇に仕えた倉富は、時代の変遷をどう見つめ、年月の足音をどう聞いて、記録にとどめたのか?いざ、前人未到の倉富ワールドへ!
大正期、激動の宮中におそるべき“記録魔”がいた!
宮中某重大事件、皇族・華族のスキャンダル、摂政問題……。
誰も読み通せなかった超一級史料にノンフィクションの鬼才が挑む。

リストカット
講談社現代新書
人はなぜ自らの身体を傷つけようとするのか。近年、社会・学校に蔓延する自傷行為。そのメカニズムと対処法を最新の知見と医療現場の症例をもとに解説。自傷行為に苦しむ人々に回復への道筋を提示する一冊。(講談社現代新書)
近年、若い女性を中心に自傷行為が広がっている。なぜ自らの体を傷つけようとするのか。
そのメカニズムを探り、自傷者への対処法を、豊富な症例をもとに解説する、はじめての入門書。

キャラ化するニッポン
講談社現代新書
キャラなしでは生きていけない!
アニメキャラそのもののコスチュームで街を闊歩する若者たち。「生身の私」より「キャラとしての私」のほうにリアリティを感じる人たち。キャラクターと日本人の強固な精神的絆を読み解く。

学校は誰のものか 学習者主権をめざして
講談社現代新書
教職員の差別意識、板挟みになる校長、教育委員会の闇……
教育現場はなぜ混乱したか
「よい先生」のいる「よい学校」に学びたい。こんな簡単な望みがどうしてかなわないのか。親、子ども不在の不毛な議論はもうごめんだ! 教育界の闇、「しがらみ共同体」にメスを入れ、究極の処方箋=教育バウチャー制を提言する。

世界の宗教を読む事典
講談社現代新書
世界がわかる101のキーワード
「ヨーガ」の本来の意味とは?
「三位一体」の父と子と聖霊とは誰のこと?
「ラマダーン」は何のためにある?
現代人必須、世界の宗教の基礎知識を101個のキーワードで解説。充実の用語索引も備え、世界の宗教がこの一冊でわかる!

秀吉神話をくつがえす
講談社現代新書
天下人の虚像を剥ぐ。出自の秘密、大出世、本能寺の変、中国大返し、豊臣平和令。「太閤さん」と愛される不世出の英雄。しかしその素顔は、権力欲のためには手段を選ばない非情な謀略家だった! 中国大返しの真実など「天下人」の謎を解き、その虚像を剥ぐ一冊。(講談社現代新書)
「神話」に隠された秀吉の暗い実像に迫る! 日本史最大のヒーロー、豊臣秀吉の実像は、暗い策謀家だった! 数々の「秀吉神話」を覆し、その奥に隠れた素顔を暴いて戦国時代の常識に挑む意欲作!

労働CSR入門
講談社現代新書
アメリカが仕掛けてくる「ソーシャルラベリングの罠」に気をつけろ!
「私たちは適正な労働条件を遵守、維持しています」。そんなこと、いったい誰が決めるのか。日に日に権威を獲得しつつある民間認証機構の背後に見え隠れするアメリカの思惑。今後、日本企業の死命を制する概念をやさしく説く。企業法務、労務関係者必携の1冊。

甲骨文字の読み方
講談社現代新書
漢字がわかれば甲骨文字は読める!
三千年前の中国王朝・殷の社会を記した甲骨文字をユニークで豊富な問題を通して平易に解説。クイズ感覚で漢字の源流へと誘う異色の古代文字入門。

裁判員制度の正体
講談社現代新書
手抜き審理の横行、裁判員に及ぶ迷惑など、問題山積の新制度が日本の司法を、国民の生活を滅ぼす!長らく判事を務めた大学教授が「現代の赤紙」から逃れる方法を伝授し、警鐘を鳴らす1冊。
手抜き審理の横行、裁判員に及ぶ迷惑など、問題山積の新制度が日本の司法を、国民の生活を滅ぼす!
元判事の大学教授が「現代の赤紙」から逃れる方法を伝授し、警鐘を鳴らす1冊。
●国民の過半数は不要論
●違憲のデパートというべき制度
●手抜き審理が横行する
●真相の追求が図られなくなる
●巨額の税金がかかる
●犯罪被害者の心の傷
●裁判員候補者にプライバシーはない
●会社を休んでも本当に給与は出るのか
●国のために奉仕すべしという思想