講談社現代新書作品一覧

民族とは何か
講談社現代新書
知られざる「民族」の根本!
なぜ「民族」が地球上に成立し、しかも現代世界を読み解く上で欠かせない要素なのか。聖書の世界からヨーロッパの成立、現在の紛争までを明確に見通す。

今なぜ戦後補償か
講談社現代新書
すべての戦争は補償義務を免れない!
日本の「戦後」は本当に終わったのか――アジア・太平洋地域に今も残る戦争被害者への補償を終えることによって、初めて日本は世界における真の名誉と信用を得ることができる。
戦争被害者は個人でも、加害国や関係した企業に補償を求めることができる!――
戦争の加害国が被害者個人に対して「償う」という観点から生まれたのが「戦後補償」ということばである。「戦後責任」が原状に回復するための作業であるとすれば、戦後補償とは戦争被害者の人権救済として、具体的な金銭的補償を行うことである。(中略)戦後処理の過程で国家間で行う「戦後賠償」に対し、被害者個人による加害国家に対する請求を「戦後補償」としたのである。(中略)それまでは、戦後処理を国家間で解決するための枠組みの議論はされたが、戦争によって、被害を受けた民間人の立場の権利回復は、真剣に議論されなかった。英語においても明確な区別はなかった。しかし現在では、国家間の賠償は「レパレイション(reparation)」、個人への補償は「コンペンセイション(compensation)」として区別されるようになった。――(本書より)

<希望>の心理学―時間的展望をどうもつか
講談社現代新書
年齢とともに時間が速くなるのはなぜか
悲観主義と楽観主義はどちらが正しいか
人生を豊かにする考え方!
ひとが生きるうえで最も必要なのは希望をもつことである。現在・過去・未来の統合=「時間的ふくらみ」の重要性を解説し、絶望を乗り越え、未来を構想するための方法論を説く。
プロローグ――何が大切といって、私はひとが生き続けることが何よりも大切ではないかと思う。そして、生き続けるうえで最も必要なことは希望をもつことだと考えている。ただし、「生きていれば、いつかよいことがある」「きっと苦労は報われる」「結局はなんとかなるだろう」などという希望ではない。……
何ともならなくてもいいと思えること、このことのなかに希望がある。このことに希望が持てなければ……すべてのひとが絶望の淵にたたき込まれ、とうてい生き続けることはできないように思われるのである。本書は、どのようにしたら希望を持つことができるのか、過去へのこだわりとどのように向かい合って未来を構想できるのか、現在を大切に生きるとはどのようなことをいうのかについて、時間的展望の心理学の立場から考えたものである。――本書より
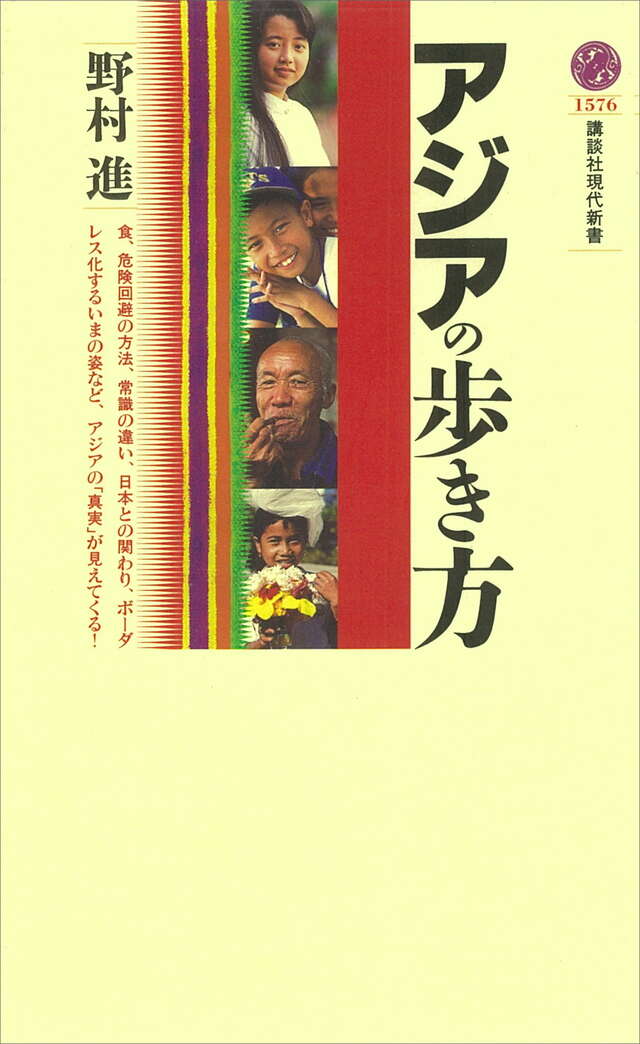
アジアの歩き方
講談社現代新書
大宅賞作家が案内するアジアのおもしろさ。20年あまりにわたりアジアとディープに付き合う著者が、食からはじまり、感覚の違い、日本との関わり、ボーダレス化する今の姿など、アジアの「真実」を浮かび上がらせる。アジアはいつも深くておもしろい!
アジアはいつも深くておもしろい
食、危機回避の方法、常識の違い、日本との関わり、ボーダレス化するいまの姿など、アジアの「真実」がみえてくる!
スラムほど安全な場所はない――スラムや下町の住民は、自分たちの住む地区をタガログ語で「ロオバン」(内部)と呼ぶ。この「内部」に暮らしていると、フィリピン庶民の社会は一見規範が崩れているようで実は崩れていない、それなりに落ち着いた生活圏であることがわかってくる。たとえばお年寄りは日本よりもはるかに敬われ、大切にされている。男女関係でも、いきなり2人きりで映画館に行くなんて、もってのほか。男性が相手の女性の家に何度か通い、先方の親の承諾を得ないと、外でデートもできない。また、兄弟姉妹では、年長者が年少者の面倒を見る習わしで、だから日本に出稼ぎに来るフィリピン人女性には長女が多いと言われている。下宿先の周りには、知的障害を持つ子供や青年が何人かいた。彼らはからかわれたり、子供のあいだではときにいじめにもあっていたが、“隔離”や“排除”の対象では決してなかった。――本書より
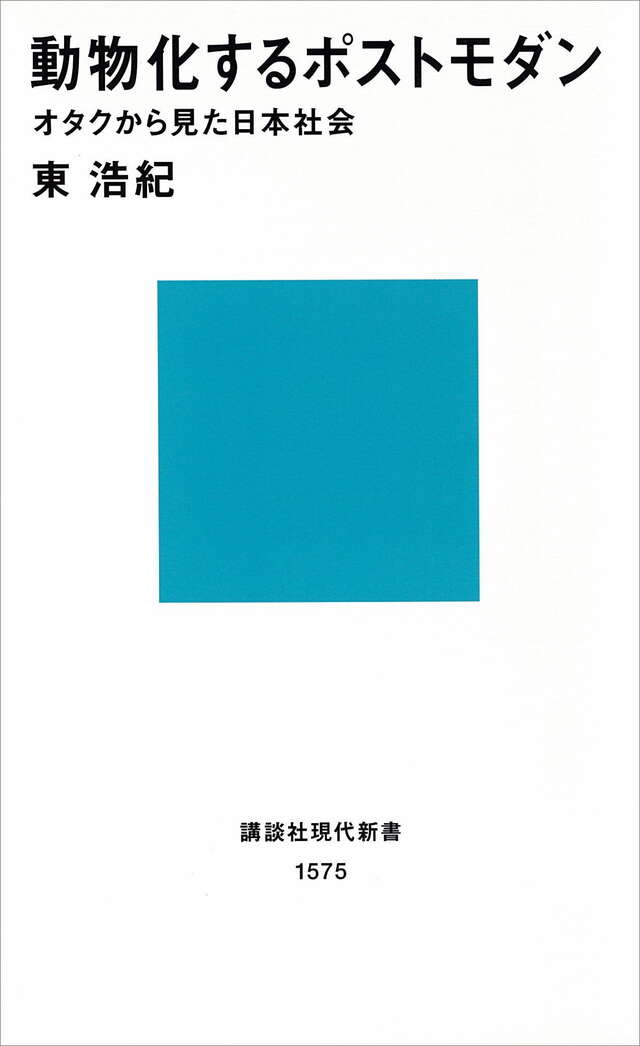
動物化するポストモダン オタクから見た日本社会
講談社現代新書
気鋭の批評家による画期的な現代日本文化論! オタク系文化のいまの担い手は1980年前後生まれ第三世代。物語消費からデータベース消費へ。「動物化」したオタクが文化状況を劇的に変える。
哲学の本でもなく、社会学の本でもなく、文化研究でもなく、サブカル評論でもなく、社会評論でもなく。
浅田彰と宮台真司と大塚英志と岡田斗司夫とフラットに並べて論じ、
サブカルチャーとハイカルチャーを行き来するはじめての書として、
2000年代以降の批評の方向を決定づけた歴史的論考。
また本書で語られているデータベース消費、解離的な人間といった分析は、
本が出てから十数年を経過した今日では、さらに有効性をもったキーワードとなっている。
これは、2001年当時は、本書のサブタイトルである「オタクから見た日本社会」であったものが、
いまでは「オタク」という言葉をつける必要がなくなっていることを意味している。
2000年代を代表する重要論考であるのと同時に、
2010年代も引き続き参照され続ける射程の長い批評書。

成果主義と人事評価
講談社現代新書
目標管理制度、管理会計、コンピテンシー評価――
現役人事マンでなければ書けない雇用制度の虚実
人を活かす人事システムとは!?
安易な人事改定が会社を滅ぼす!成果主義はなぜ危険か。どう活用すればよいのか。真に価値を生む雇用制度を考える。
成果主義と人事評価――目次より
●「偉さ」の証明
●成果をどう評価するか
●経営者はなぜ成果主義にすがるのか
●組織を横断したチームワークと人事評価
●利益の奪い合いへの抵抗
●拡散する不安
●価値の発見
●人材への投資とリストラ
●人事評価と報酬のリンク
●成果を生む土壌

テレビゲーム文化論―インタラクティブ・メディアのゆくえ
講談社現代新書
なぜ宇宙が舞台に?ポケモンは日本文化か?テレビゲームはロボットである?誕生から30年、「相手をしてくれるメディア」は何を変えたのか。文化としてのテレビゲームを検証する。
遊び相手ロボット――テレビゲームをメディアとして考えた場合、その特徴のひとつはインタラクティブであることといわれる。わかりやすくいいかえれば遊び相手をしてくれることだろう。攻撃してくる敵のいないインベーダー、追いかけてくる鬼がいないパックマンはあり得ない。テレビゲームは、原始的な形ながら、明らかに、遊び相手ロボットだったのだ。こう考えると、一見別々の流れにあるようないくつかの現象が、ひとつの大きなうねりとして、まとまって見えてこないだろうか。テレビゲームの登場(70年代)、パソコンの普及(80年代)、「たまごっち」などの「育てゲーム」の流行(90年代)、娯楽ロボットへの注目(2000年代)……。――本書より

ユダヤ人とローマ帝国
講談社現代新書
ユダヤ人はなぜ迫害され祖国を追われたのか。
「キリスト殺し」の汚名を着せられ、その証人として「生かさず、殺さず」の運命を背負わされたユダヤ人の歴史とは。古代ローマ時代の貴重な資料に基づいて検証。
離散、放浪、迫害そして……「悲劇の原点」がここにある!

社会保障入門―何が変わったかこれからどうなるか
講談社現代新書
〈不安の時代〉を生きる基礎知識!
医療費自己負担増のゆくえは?年金制度は大丈夫?
医療・年金・雇用などの複雑な仕組みをわかりやすく解説し、今後の課題をともに考える1冊。
社会保障入門――目次より
●社会保障の現在
●増え続ける老人医療費をどう効率化するか
●政管健保も組合健保も財政危機
●年金保険制度をどうするか
●最近の3つの年金改正
●失業保険から雇用保険へ
●介護保険の課題
●進む社会福祉改革
●年金スリム化論の是非
●社会保障と構造改革

紛争の心理学
講談社現代新書
プロセス指向心理学の驚くべき実践!
対立・衝突の炎を溶かす内なる力に目覚めよ!
民族紛争、人種差別から「公然の虐待」まで、あらゆるレベルの人間関係の紛争や対立をどう解決するか。世界中でワークを実践している著者の衝撃的な主著。
「ワーク」という言葉は、おもにアメリカ西海岸を中心に発達したニューエイジ心理学のなかでよく使われてきた表現である。一般的には、心理学プロセスを解放するさまざまな方法と実践という意味をもっている。ミンデルの場合、個人、カップル、昏睡状態など、多様な関係を場としており、とくに集団討論の形をとるワールドワークは、きわめてユニークなものだ。プロセス指向心理学のもっとも大切な前提は、心理的、精神的、感情的混乱や運動の過程は、それ自体、知恵を内包しているということだ。変化と成長をうながす兆しとして、内外の出来事の全体は起こってくる。そのプロセスの全体を尊重することが重要だとミンデルは考える。それによって、新しいより柔軟で知恵に満ちたものの見方や存在のあり方が生れてくる。たえず変化していく生命のありようを信頼し、尊重し、そこから知恵を引き出しながら、自己を成長させていく。――本書より

日本一周ローカル線温泉旅
講談社現代新書
嵐山流旅行術の集大成! いま国内旅が贅択だ極上の湯、寿司、ラーメンを求めて東へ西へ。活気みなぎる繁華街や廃れゆく観光地の隠れた魅力を堀りおこし根室から鹿児島まで走破した、極私的旅行ガイド登場。(講談社現代新書)
嵐山流旅行術の集大成! いま国内旅が贅択だ極上の湯、寿司、ラーメンを求めて東へ西へ。活気みなぎる繁華街や廃れゆく観光地の隠れた魅力を堀りおこし根室から鹿児島まで走破した、極私的旅行ガイド登場。

謎とき 日本合戦史
講談社現代新書
新しい歴史観をみがくための9つの「なぜ?」
華やかな騎馬武者による源平の一騎打ち、川中島の決戦、信長鉄砲隊の三段撃ち……。日本史を彩る数々の合戦はどのように戦われたのか?我々に語り継がれた「歴史常識」を問い直し、日本人の戦い方を明快推理する。

<子どもの虐待>を考える
講談社現代新書
なぜ起きるのか。どう向き合うか。誰にでも起こりうる家族の問題として語る。
読者の方たちへ――私は、この本をふたつの読者層を想定しながら書いた。ひとつは、虐待の問題に最前線で対応しようとしている人たちである。そうした人たちが、必ずしも心理学や精神医学の専門用語に精通しているわけではない。だから、可能な限り「ふだんのことば」で理解できるような文章で、「虐待とは何なのか」を考えてもらえるように心がけたつもりである。もうひとつの読者層は、「自分のしていることは虐待なのではないか?自分は子どもの心を歪めてしまっているのではないか?」と感じ、その不安を誰にも受けとめてもらえずに苦しんでいる親の方たちである。――本書より

英語力を身につける
講談社現代新書
速読もリスニングもこうすればできる!
ラジオ講座や映画をどう利用するか?速読、リスニングのコツは?大人に適した学習メソッドを具体的に示す。

江戸奥女中物語
講談社現代新書
「奥奉公」の知られざる実像!
奥奉公は、花嫁修業か女の一生の職業か。出世のゴールは、御部屋様か老女か。
面接と歌舞音曲、城の日常、暇(いとま)後の人生。史料を通し、知られざる実像を描く。

サラリーマン社会小事典
講談社現代新書
マトリックス組織、コア・コンピタンス経営、フレックスタイム制、転籍、出向、ワーキング・ランチ、社内恋愛……
サラリーマン必須の基礎用語184項目!
新しい雇用の形や人材開発のシステム、能力主義の可能性など、用語から解く、激変する会社と仕事の姿。

悪の恋愛術
講談社現代新書
「もてる」技術と戦略!
恋愛とは支配と影響のパワーゲームである
自分がエゴイストであることを認め、「いい人」であることを捨てなければ真実の恋愛は生まれない――。プレゼント術から嫉妬の有効活用法まで、芳醇な果実を得るための方法論を満載。

馬の世界史
講談社現代新書
人が馬に乗ったとき世界は変わった!戦車と騎馬が生んだ戦争のかたち、東西の道、世界帝国。馬から歴史を捉え直す。
古代の戦車から、騎馬遊牧民の世界帝国、アラブ馬の伝説、最強の競走馬まで
馬がいなければ、まだ古代が続いていた!?

学級再生
講談社現代新書
「学級崩壊」はなぜかくも広がったか。問題解決と予防のコツとは何か――。教育臨床心理学の現場から説く、画期的「教育再生論」。
「学級崩壊」を予防し、解決する必須ノウハウ!学校は子どもを守れるか

メジャーリーグvs日本野球――スウィング理論の冒険
講談社現代新書
松井秀喜VS.ボンズ、松坂大輔VS.ジョンソン、そしてイチロー、新庄の秘密――。日米の一流選手を徹底分析し、その違いを鮮やかに示す。
イチロー、松坂、ジョンソン、ボンズ、松井 超細密!パラパラ・アニメ105カット掲載
違いはどこにあるのか!?