講談社現代新書作品一覧

ハイデガー=存在神秘の哲学
講談社現代新書
この世に〈在る〉ことに何の意味があるのだろう。
難解なハイデガーの思索を解きほぐし、存在の深奥を見通す!
この世と出会い直すために――
この本を書くにあたり、なにより導きの糸になったのはハイデガーである。だが、それにしてもなぜことさら、ハイデガーなのか。理由はじつに簡単。存在の味(意味)について、まともに考え、ちゃんと応接してくれる哲学者は、かれひとりしかいないからだ。
ぼくもあなたも死ぬ。その死のとき、こうして生まれ、この世に存在し、そして死ぬことの意味を得心して死にたいとおもう。すくなくとも、ぼくはそうおもっている。
哲学。それはまさに、そんな得心のための思考のいとなみのはずである。だが、にもかかわらず、哲学の歴史をみるとき、ぼくたちのそんな質朴だが痛切な問題に、こたえてはこなかったようにおもわれる。
生きて在るって、どういうことだろう。この世はなぜ存在するのか。そんなこの世にぼくが存在しているのはなぜか。
この本は、そんな「存在への問い」をもういちど堀りおこしながら、それにこたえていこうというものだ。――(本書より)

戦争の日本近現代史
講談社現代新書
日本はなぜ太平洋戦争に突入していったのか。為政者はどんな理屈で戦争への道筋をつくり、国民はどんな感覚で参戦を納得し支持したのか。気鋭の学者が日清戦争以降の「戦争の論理」を解明した画期的日本論! (講談社現代新書)
日本はなぜ太平洋戦争に突入していったのか。為政者はどんな理屈で戦争への道筋をつくり、国民はどんな感覚で参戦を納得し支持したのか。気鋭の学者が日清戦争以降の「戦争の論理」を解明した画期的日本論!

日本経済50の大疑問
講談社現代新書
デフレ、不良債権、構造改革、国債暴落、ペイオフ対策、中国の脅威……
日本経済はなぜダメなのか、根本から答えます!
●不良債権はなぜ、いつまでたっても増えつづけるのですか?
●債権放棄などの借金棒引きは、なぜ許されるのですか?
●財政再建と景気回復は、本当に両立するのですか?
●アメリカは本当に市場主義で強くなったのですか?
●日本の経済政策は誰の意見で決まっているのですか?
●「インフレターゲット」は正しいのですか?
●「痛み」とは、誰がどのように受けるのですか?
●少額の預金でも銀行口座は移したほうがいい?
●「中国の脅威」に日本の製造業は対抗できますか?
●経済成長は、本当にしなければならないものでしょうか?
「デフレ不況」って何だろう?――経済に底はなく、無限に落ちていく可能性があるのです。意図的に落としていこうと思ったら、いくらでも落ちていきますし、最終的にはゼロになるまで落ちるというのが基本的な特徴なのです。この底割れの恐怖を理解していない人が、信じられないほどたくさんいるのが、悲しいことに日本の現状です。
日本経済の景気の底が割れてしまうかどうかについては、これから先の経済政策がカギを握っています。政府も多くの識者たちも、基本的には「市場原理主義」の立場でこれからの経済の舵取りを行おうとしています。彼らのコンセンサスは、効率の悪い企業をどんどんつぶさなければ日本経済は立ち直れない、だから不良債権処理を断行して、強い企業だけを残していこう、ということです。その改革が遅れれば遅れるほど、日本経済の回復は遅れるというわけです。しかし、本当にそうなのでしょうか。私はまったく間違っていると思います。――(本書より)

失敗を生かす仕事術
講談社現代新書
個人にも組織にも必要なこれからの仕事術。めまぐるしく社会の状況が変わるいまの時代は、今日の成功は明日の失敗へとすぐ変わる。失敗と真正面から向き合い、よりよい仕事をするための考え方を明快に説く。(講談社現代新書)
個人にも組織にも必要なこれからの仕事術。めまぐるしく社会の状況が変わるいまの時代は、今日の成功は明日の失敗へとすぐ変わる。失敗と真正面から向き合い、よりよい仕事をするための考え方を明快に説く。

無敵のラーメン論
講談社現代新書
鶏ガラスープの復活、煮干しダシの多彩な味わい。
戦前創業の老舗に急成長の新興勢力。
旭川から鹿児島まで全国の麺、スープ、具を徹底解剖。
●ダシとタレの基礎知識
魚ダシ――節系と煮干し
新しい味噌ラーメン文化の誕生
●麺の基礎知識
加水率で麺の食感が変わる
●具の基礎知識
もやしに地域性が出る
●東京ラーメンの「系列」を知る
3つの「大勝軒」
●ラーメンの日本地図

最新・アメリカの軍事力
講談社現代新書
地下軍事施設をどう攻撃するか。テロ対策は万全か。
宇宙空間を支配する計画・とは。偵察・管理能力を高める方策は――。
急ピッチで進む米軍の改編を検証する。
21世紀の米軍――W・ブッシュ政権はクリントン政権後期時代のペースを上回る国防予算増額計画を発表、21世紀の任務に対応できるように米軍を改編する「トランスフォーメーション」の推進や、米本土の弾道ミサイル防衛計画を加速・強化するなどの新国防政策を次々と打ち出していったが、その政策が具体化し始めようとしていた2001年9月11日、ニューヨークとワシントンDCにおける、いわゆる同時多発テロ事件が発生した。この日を境に、米国は(そして世界も)大きく変わったといわれる。特に安全保障では180度に近い転換が生まれている。米本土防衛「ホームランド・ディフェンス」の重視である。効率を求める米軍の戦略は、また海外における米軍部隊の常駐を少なくする代わりに、常に短時間で展開できる態勢を確保しておくという政策を促すであろう。好むと好まざるとにかかわらず、米国の軍事戦略は世界のあらゆる国、地域、人々に大きな影響を与える。今、21世紀の米軍は、その役割と姿を大きく変えようとしている。――(本書より)

フロイト思想のキーワード
講談社現代新書
これがフロイトだ!
夢解釈の理論確立の経緯、ユダヤ人としての苦悩、そして知られざる私生活……。フロイト論の決定版!
フロイト思想のキーワード――(目次より)
●死の本能――「死」への迂路としての「生」
●快感原則と現実原則
●無意識とは
●喪の仕事
●エディプス・コンプレックス
●近親姦による心的外傷
●国家悪と戦争の告発
●ユダヤ人フロイト
●フロイトからフロイト以後の精神分析へ
●裏から見たフロイト思想
-現代の課題とフロイト思想-
――もしもフロイトが現存していたら、是非とも出会ってほしかった現代の課題がある。
まずその1つは、イスラエル――パレスチナ問題である。フロイト自身は、超民族的、超国家的な普遍的知性による連帯こそユダヤ人のアイデンティティであると考えて、晩年も当時のイスラエル化運動に懐疑的であった。……もしフロイトがこの世にあったら、イスラエル、いや現代のユダヤの人々を、より開かれた普遍的知性による知の連帯の方向に導く現代のモーゼになってくれたのではないだろうか。……
第2に、現代の相も変わらぬ民族紛争、そして、「文明の衝突」とも評されるような深刻な対立と葛藤が世界的規模で起こっていることである。……フロイト思想は……欧米の自由主義思想と微妙な相性のよさを発揮してきたが、これからもなおフロイト思想は、この二大世界観の衝突と葛藤の対処に何らかの形で寄与することができるのではないか。――(本書より)

進化論という考えかた
講談社現代新書
進化論はいま、人の心や行動、「文化」の謎にまで迫りつつある。
科学と人間をつなぐ思想として読み直す。
「人間性」も進化した?――問題は、人間がほかの動物から進化してきたということから、「人間性」も進化したと考えるかどうか、である。人間の歴史を、ほんの少し――数百年ほど――過去に伸ばせば、サルの進化になる。ならば、自分たちの来し方行く末を考えるときに、動物からはじまる人類の進化に思いを寄せるのは当然のことである。人間がサルから進化したならば、人間の心も人間性も、サルと連続していると考えるのは当然だろう。――(本書より)

地名で読むヨーロッパ
講談社現代新書
パリの由来は?スペインとはどんな意味か。
神話や英雄物語から生まれ、先人たちの生活ぶりを伝える地名の不思議。
パリの起源とモンマルトル――ケルト語起源の都市名の代表的なものにパリ(Paris)があります。この地名はケルトの部族名パリシー(Parisii)が語源です。パリシーはケルト語par(船)に由来すると考えられていて……パリ市役所(Hotel de Ville)の表玄関のドアには、荒波にもまれながら1枚の広い帆を掲げセーヌ川をさかのぼるガレー船をあしらったものがはめられています。2階の幾つもの窓に飾られた紋章にはラテン語でFluctuat nec mergiturと書かれています。それは「荒波にもまれるも沈没せず」と訳せます。……
モンマルトルという地名は「殉教者の丘」(Mount of Martyr)という意味で、……伝説によると、パリの初代司教聖ドニはこの地で首を切られて殉教しますが、自分の首をもって北へ10キロ離れた所まで歩いて行って倒れました。そして、彼が倒れた地がサン・ドニと呼ばれるようになるのです。――(本書より)

明るく乗りきる男と女の更年期
講談社現代新書
知っていれば安心!!
更年期外来のある全国病院リスト付き
更年期障害を克服する第一歩は正しい知識を持つこと。その診断と最新の治療法から快適に過ごすヒントまでをやさしく解説する。
「更年期」は収穫の秋――人間の一生のなかで、生殖のために費やす時間は、それほど多くないのが普通である。半分以上の時間は、仕事や家事、趣味などを通して、社会と関わり合うことに費やされているはずなのだ。何十年もの経験に裏打ちされた実績、仕事上のノウハウでも、ハウスキーピングの腕でも、何でもいい、その積み重ねこそが、人の生きてきた証、価値ではないだろうか。……
仕事だけに明け暮れていたあなたには、少し立ち止まって、これまでの生き方を振り返る時期だろう。実りの秋を享受する前に、心と身体のオーバーホールを勧めたい。1週間ほど休みを取って、何もしないでボーッとして過ごすのがいいと思う。そして、最後の日に健康診断を受ければ、完璧な休暇となる。もし、心か身体のどこかが痛んでいたら、カウンセリングを受けるなり、専門医の治療を受けるなどのきちんとしたメインテナンスを行うことで、これからの人生を明るく過ごせるはずである。どこも悪くなかったら、それは本当に幸せそのもの。「健康」であれば、いかなる苦難にも耐えていけるだろう。――本書より

大学はどこへ行く
講談社現代新書
大学選別の時代が始まった!!日本の大学は生まれ変われるか?
「学力低下」から独立行政法人化まで、一橋大学長が語り尽くす「大学改革の行方」。
護送船団方式からの訣別――宇宙大爆発を意味するビッグバンが、国立大学の改革を引き金に日本の大学にも同じように生じたと考えるべきであろう。大学間の競争と選別を軸とする変革の時代、つまり大学ビッグバンの時代を迎えたのである。国立大学はこれまで、長いこと政府・文部科学省によって庇護されてきた。強い規制の下に置かれているとはいえ、経営上さしたる問題もなく多少の不自由さはあっても概して温かく保護されてきたといってよい。現在99ある国立大学は、いわば文部科学省の護送船団方式による大学行政にどっぷり浸かり、そのオンブにダッコの境遇にすっかり慣れ親しんできた。「入口」の入試で学生を選抜するが、あとはさしたる教育もせず安易に「出口」から卒業生を送り出すスタイルを踏襲してきた。大学のレジャーランド化が指摘されてから久しい時が経つ。このような護送船団方式の下での大学の現状が、もはや存続することは不可能であろう。――本書より

エロイカの世紀
講談社現代新書
ナポレオン革命とベートーヴェンはどう交錯したか。ヘーゲルは馬上の英雄に何を見たか……近代とともに誕生した「世界史的偉人」を通じて、革命の世紀を生き生きと描く。
英雄の世紀――ナポレオンという「英雄」は、ことによると、ひとつの幻影にすぎないかもしれない。だが、多数の「世界史の偉人」たちが、まだまだ肩をならべて、「エロイカの時代」を演じているのではないか。変革にたずさわった政治家・軍人たち、つまりワシントンやフランクリンも、ロベスピエールも英雄と名づけてよかろう。
いや、政治ばかりか産業にも芸術にも英雄の名にあたいする巨人たちが頭をならべる。そもそも、ベートーヴェンとヘーゲルという、おない歳のドイツ人こそが、英雄の筆頭にたっているようにもみえる。
ときは、「エロイカの世紀」であった。わたしは、これからその「エロイカの世紀」を、たどりたいと考えている。「世界精神の事業遂行者たる使命をおびた世界史的個人」(ヘーゲル)としてのエロイカは、あらゆる領域に姿をあらわすことであろう。――本書より
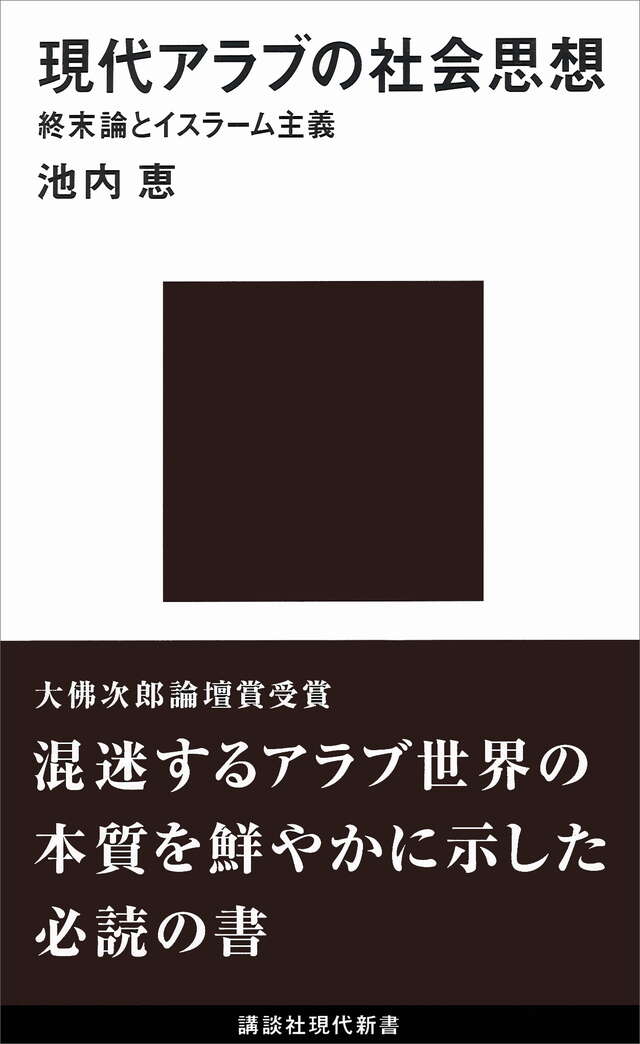
現代アラブの社会思想
講談社現代新書
なぜ今、終末論なのか。
なぜ「イスラームが解決」なのか。
学術書からヒットソングまで渉猟し、苦難の歴史を見直しながら描く「アラブ世界」の現在。
終末論の地層――イスラーム教の古典的要素にさかのぼることのできる要素の上に、近代に入ってから流入した陰謀史観の要素と、現在に流入したオカルト思想の要素が、いわば地層のように堆積して、現代の終末論は成り立っている。そして、イスラーム教の古典終末論の要素にも、また積み重ねがある。イスラーム教はユダヤ教・キリスト教から続く「セム的一神教」のひとつである。ユダヤ教とキリスト教が発展させた終末論体系を基本的に継承しており、両宗教から受け継いだモチーフがかなり多い。その上に「コーラン」や「ハーディス集」によってイスラーム教独自の修正や潤色が加えられている。――本書より

傭兵の二千年史
講談社現代新書
ヨーロッパ興亡史の鍵は、傭兵にあった! 古代ギリシャからはじまり、ローマ帝国を経て中世の騎士の時代から王国割拠、近代国家成立まで、時代の大きな転換点では、常に傭兵が大きな役割を果たしてきた。(講談社現代新書)
ヨーロッパ興亡史の鍵は、傭兵にあった! 古代ギリシャからはじまり、ローマ帝国を経て中世の騎士の時代から王国割拠、近代国家成立まで、時代の大きな転換点では、常に傭兵が大きな役割を果たしてきた。
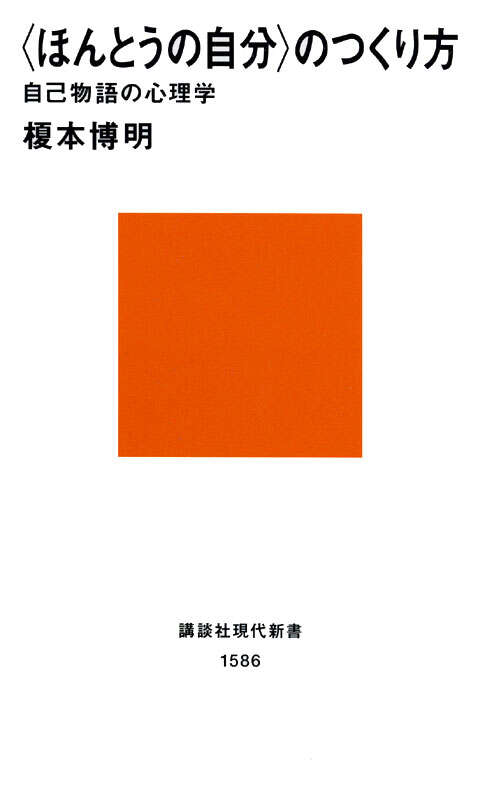
<ほんとうの自分>のつくり方
講談社現代新書
「自分って何?」の答えは、聞き手に自己を物語る中で形成される。〈自分〉を見つめ直し、たしかな生き方をつかむ方法を説く。
〈自分〉は発見されるのではない。
それは聞き手との語り合いの中からつくられる――
人生の意味というものは、どこかに転がっていたり、埋もれていたりするものを、そのまま拾ったり掘り起こしたりして見つかるといった類のものではない。自分なりの解釈のもとに自己を語り、聞き手の解釈を理解する努力をし、その聞き手の理解の枠組みからもわかってもらえるように工夫しながら語り直し、再び聞き手の反応を確認する。こういった作業の積み重ねの中で、自分が経験してきたことがらの意味が、ひいては人生の意味が、知らず知らずのうちに生み出されているのである。――本書より

自衛隊は誰のものか
講談社現代新書
「戦力なき軍隊」の理想と現実、なしくずし再軍備、旧軍人の策動、社会党の揺れ――国民不在のまま政争の具として翻弄されつづけた半世紀を問う。
自衛隊をめぐる焦点の移り変わり――
警察予備隊から自衛隊になるまでのあいだ首相だった吉田茂は、これが旧軍の復活にならないよう気をくばり、とくに旧軍人を採用するにあたっては細心の注意をはらった。吉田は、将来は新しい「国軍」に発展させるつもりで自衛隊を生んだのであった。吉田の弟子にあたる池田勇人も佐藤栄作も吉田がやり残したことに手をつけず、防衛政策はそのままなし崩しにすすんだ。結局、吉田が生んだ自衛隊を誰も責任をもって育てなかったのである。そうであれば当然、毎年自動的に予算が増えていくなかで、官僚の手でいささか無責任に自衛隊は育っていった。陸・海・空を統合した戦略もなにもなく、各自衛隊はばらばらの官僚機構にすぎなかった。――本書より

日本破綻―デフレと財政インフレを断て
講談社現代新書
〈緊急提言〉まずデフレを止めよ!
このまま放置すれば構造改革は失敗、不良債権は急増し、銀行、生保の破綻が続出、制御不能のインフレが起こる――日本の金融システムを精査した気鋭の学者による緊急提言。
デフレ阻止へ舵を切れ――小泉純一郎首相の掲げる構造改革、すなわち不良債権処理、財政の全面的な見直しと赤字の削減、政府系金融機関などの特殊法人民営化と補助金の撤廃は、いずれも欠くことのできない政策であり、筆者も全面的に賛成である。しかしデフレを放置すれば、すべてが水泡に帰する。その理由は、日本の国家財政の破綻と財政インフレである。1930年代の世界を振り返れば、デフレとインフレという2つの恐怖があった。デフレによる倒産と失業、財政赤字の拡大による財政破綻とインフレである。日本はいま、この2つのリスクに直面している。デフレを早期に断たないと財政破綻によるインフレリスクが急速に高まる。本書はそのメカニズムをわかりやすく説明すると同時に、それに対する具体的な政策対応を提言することを企図した緊急出版である。――(本書より)

ロボットの心-7つの哲学物語
講談社現代新書
ロボットも心は持てる――脳科学や哲学の最新理論をふまえつつ、機械、知性、道徳など現代人の課題に迫る思考実験。
プロローグ――本書のテーマは一言でいうと、ロボットに心がもてるか、ということである。この質問をいきなり大学生にすると、学生の大半はあまり迷いもせずに「No」と答える。そこで、その理由は何か、とたたみかけて尋ねると実にさまざまな答えが返ってくる。曰く、「ロボットには計算ができても、人の気持ちは分かるはずがない」「ロボットはプログラムされたこと以外のことをする創造性をもっていない」「心とは人間の本質だ、それをロボットがもったらそれはもう人間だ、だから定義によりロボットは心をもてない、証明おわり」……
そこで彼らの言い分をひとしきり聞いた後で、「じゃ、ドラえもんには心がないわけ?」と反撃(?)すると、彼らは一様にのけぞって、「えっ、そりゃ、ずるいよ」といわんばかりの顔をする。しかし、本当のところはどうなんだろう。ロボットが心をもつというのは原理的には可能なのだろうか。これからの話を面白くするために、私は、「可能だ」という陣営に身を投ずることにする。――(本書より)

先端医療のルール-人体利用はどこまで許されるのか
講談社現代新書
受精卵、遺伝子、ES細胞、人クローン、臓器移植……。
何をどこまで許すのか。新たな全体の見取り図と倫理原則を説く。
人体要素の「格付け」――たとえば、髪の毛や爪も人体の一部だが、その扱いについて倫理的問題があるだろうか。床屋で散髪するのは臓器の摘出と一緒だから明確な説明に基づく自由な同意がいる、倫理委員会のチェックもいる、という人はいないだろう。髪の毛を鬘メーカーに売るのは人体の商品化につながり人の尊厳に反する、という人もいないだろう(と私は思うが、いかがだろうか)。逆に人体のなかで、他とは違う特別な価値をもち、それゆえに一段と厳しい保護・規制をしなければいけない要素はあるだろうか。移植医学や再生医学で直面する問題と、これまでの諸外国の対応を参考に、実際に考えるべき格付けのポイントを概観してみたい。――(本書より)

新宗教と巨大建築
講談社現代新書
「信仰の空間」を解読する!
なぜ前近代の宗教建築は賞賛され、近代以降の教殿はいかがわしいまなざしで見られるのか。天理、大本、金光、PLなどの建築と都市を直視する。
建築史における近代宗教――英雄的な建築家の営みとアヴァンギャルドの連続で語られる近代建築史と、寺社建築を軸に構成される日本建築史の狭間にあって、ほとんど顧みられなかったのが近代の宗教建築である。……
日本の戦後建築は、モダニズムを民主主義のための建築と規定し、宗教的な要素を切り捨てることで出発した。神社が現代建築から撤退し、進歩史観的な建築史が確立するとともに、宗教建築は近代以前のものとして理解される。……
本書の目的は新宗教の空間を考察することになろう。その際、教団の思想から空間の概念を読みとり、いかに現実の空間に反映させたのかを検証する。いずれも19世紀に登場した天理教、金光教、大本教を具体的にとりあげ、さらに戦後の新宗教建築を幾つか概観する。――(本書より)