こころライブラリー作品一覧

医者を悩ます「ニュータイプなうつ病」がわかる本
こころライブラリー
誰でもかかる可能性がある!こころの花粉症
現代日本において、うつ病が急増している。それも典型的な旧タイプではなく「ニュータイプなうつ病」が。軽症、治りづらい、他罰的…医者をも悩ます病の正体とは

アスペルガー症候群 就労支援編
こころライブラリー
不思議な「心」のメカニズムが一目でわかる
《講談社 こころライブラリーイラスト版》
【自分にぴったりの仕事が必ず見つかる! 就労支援完全ガイド】
アスペルガー症候群への就労支援が広がっている。
その特性が生かせる仕事は? 支援の現状は?
現場や当事者からの実践的なアドバイスが満載の完全ガイド。
(まえがきより)
本書には、アスペルガー症候群の人々の就労に関して必要な、アイデア、事実、事例などのすべてが、優れたイラストと要約された文章の組み合わせによって広く提示されています。この作業は、この領域の実践と研究にわが国でパイオニア的役割を果たしてきた、共同監修者の梅永雄二氏に負うところが大きいのです。
さらにまた、アスペルガー症候群の人々の実際の就労の場で、日常的に支援し共同して働いている現場の人々の協力が、どれほど大きなものであったかは、読者のみなさんが実感してくださると思います。アスペルガー症候群の人々の就労に、協力を惜しまない関係者の共同作業として、本書はできあがったのです。(佐々木正美)
【本書のおもな内容】
第1章 就職してがんばっている人の声
(ケース例)パソコン操作の知識をいかして働くAさん
(ケース例)ホテルの調理場で評価されているBさん
(ケース例)IT企業の総務人事部で戦力になっているCさん
第2章 アスペルガー症候群の人の就職活動
(相談する)まず、支援機関に希望や悩みを伝える
(支援を受ける)定期的に面談を受け、自己理解を深める
(就職活動)3ヵ月のトライアル雇用を利用する
第3章 専門的な支援がはじまっている
(支援を受ける)チャートでわかる!自分にぴったりの相談先
(支援機関)発達障害者支援センター
第4章 就職してから、受けられる支援
(支援を受ける)ジョブコーチに仕事の悩みを相談する
(自分でできること)人間関係のトラブルは、小さいうちに防ぐ
第5章 ライフスキルも少しずつ身につける
(生活の注意点)社交性ではなく、生活術を向上させる
(ライフスキル)余暇が安定すると、生活全体が安定する
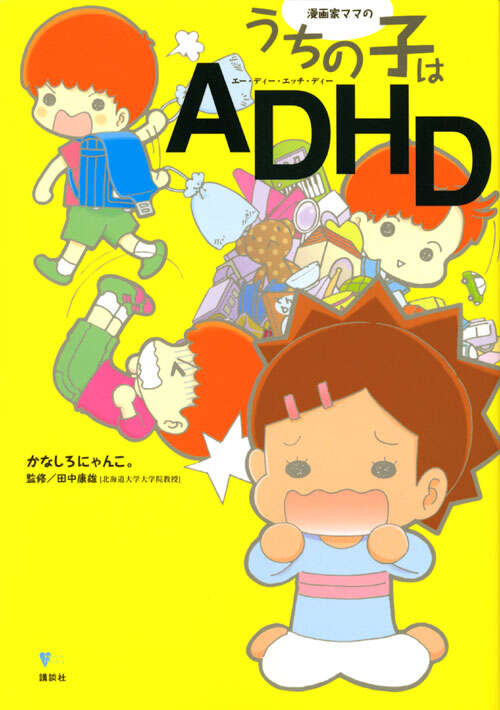
漫画家ママの うちの子はADHD
こころライブラリー
片付けができない、モノをよくなくす、学校ではケンカばかり……、そんな問題だらけの息子、実は発達障害でした! 「愛情不足じゃないか」と言われて落ち込んだ幼稚園時代、息子と友達の家に謝りに行った小学校のあの日、そして大ケガをきっかけに相談所へ。児童精神科医が下したのは、ADHDの診断だった。いろいろあるけど、かわいい息子との悪戦苦闘の日々を、漫画家ママがていねいに描いた傑作コミック。電子版も登場!
涙と笑いと感動の、ADHD育児日記! 注意欠陥多動性障害を抱える小学生・リュウ太君と母親の日々の葛藤と成長のストーリー。育児に悩むすべてのお父さん、お母さんにおすすめの、心温まる一冊です。

大人のAD/HD
こころライブラリー
不思議な「心」のメカニズムが一目でわかる
《講談社 こころライブラリーイラスト版》
仕事でミスを重ねる、衝動買いが止まらない……。
その問題の原因はAD/HDの行動特性にあるのでは?
生きづらさに悩む当事者の現状、苦しみを理解できる一冊。
日常生活で役立つヒントや支援法も紹介する。
(第1章より)
かつて、AD/HDは子どもに特有の行動特徴だと思われていました。しかし最近では、多くの大人がAD/HDの特性に悩み、仕事上や生活上の困難を抱えていることがわかってきています。
AD/HDの特性の一部は、大人になっても残ります。その現状を、当事者たちの苦しさを、どうか理解してください。
【本書のおもな構成】
《第1章 大人になってもAD/HDは残る》
子ども/多動性・衝動性・不注意に悩む
大人/多動性は弱まり、不注意が際立つ
大人/「片付けられない」のは男性も同じ
大人/女性は多動がみられない人が多い
【事例1】診断を受け、生活が安定したAさん
《第2章 いつも不注意な自分が嫌になる》
仕事の悩み/忘れ物が多く、周囲に申し訳ない
仕事の悩み/上司に意見して、あとで悔やむ
【事例2】転職で不注意を克服したBさん
生活の悩み/家事を効率よくできず、疲れる
【事例3】道具を使って家事をこなすCさん
《第3章 ミスに疲れて、生きる意欲を失う》
関連する障害/ほかの発達障害が併存しやすい
二次障害/うつ病や不安障害などを発症する
【事例4】うつ病をきっかけに特性を知ったDさん
《第4章 互いにねぎらい、赦し合っていく》
田中先生に聞く/大人のAD/HD相談先リスト
【事例5】地域ネットワークで支えを得たEさん
連携/家族やパートナーに伝えたいこと
連携/学校や勤務先への報告は必要か
《第5章 治療法は日々、変化している》
田中先生に聞く/どのような治療が受けられるのか
受診/発達障害の専門医は、多くない
治療/基本は、暮らし方と生活環境を見直すこと
治療/2007年に大きく変わった薬物療法

多重人格者 あの人の二面性は病気か、ただの性格か
こころライブラリー
心の中に住む別人。本当の自分は誰なのか? 多重人格者が生じる原因の多くは幼児期の虐待だが、日本では母子関係による極度のストレスも注目されている。驚くべき発症過程とその症状をイラストで徹底解説。

思春期のアスペルガー症候群
こころライブラリー
不思議な「心」のメカニズムが一目でわかる
《講談社こころライブラリーイラスト版》
【子どもたちの悩みを正しく理解し、問題を解決する決定版】
友達と同じように行動できない、相手の気持ちがわからない、自分は「ふつう」じゃないの!?
障害を自覚しはじめる思春期に子どもたちが直面する悩みとは?
豊富なイラストで子どもたちのこころの変化を解説し、適切なサポート法をアドバイスする一冊。
(まえがきから)
本書では、自己形成がおこなわれる大事な思春期に、アスペルガー症候群の子が劣等感に苦しんだり、自己否定的な考えに陥ったりしないようにするためのヒントを紹介しています。友達への仲間意識から恋愛感情、そして性欲まで、思春期に子どもたちが直面する、みずみずしく、それゆえに複雑な感情の、受け止め方のヒントです。
アスペルガー症候群の子が、周囲の無理解な対応や、家族や友達との衝突に悩み、青春の輝かしい時期を悲しみのなかで送ることのないよう、本書を役立てていただければ嬉しく思います。
【本書のおもな内容】
第1章 思春期独特の悩みとは
[行動特徴]ほかの子にあわせて行動できない/こだわりが強い子だと言われる
[思春期の悩み]自分は「ふつう」じゃないと感じる
第2章 友達と対等に付き合いたい
[自意識]自分は人より劣っていると思いこむ/人の意見に耳をかそうとしない
[ケンカ・対立]ほかの子のミスを執拗に指摘する/金銭トラブルに巻きこまれやすい
第3章 恋の仕方がよくわからない
[恋愛感情]相手の気持ちを考えずにアプローチ/発達障害の人は、結婚できるのか
[性の意識]マンガの通りに交際しようとする/手がふれあうことにストレスを感じる
第4章 将来への不安がぬぐいきれない
[挫折感]不登校・ひきこもりになって苦しむ/感情表現ができず、家庭内暴力に
[将来への不安]自分にあった仕事がわからない/不安をつのらせ、うつ病になる子も
第5章 家族や友達に理解してほしいこと
[本人の思い]命令しないで、話を聞いてほしい/公私の境界線をはっきり知りたい/理解してくれる相手に出会いたい

不安・恐怖症のこころ模様 パニック障害患者の心性と人間像
こころライブラリー
理由なく湧きあがってくる不安に襲われるパニック発作。パニック発作を中心症状とするパニック障害はどうして起こるのだろうか。不安の根源、患者特有の精神症状、うつとの関係。これまで一般には示されていなかったパニック障害患者の人間像を、日本における治療・研究の第一人者が実例をあげて解き明かす。不安・恐怖の病は人をどう変えていくのか。パニック障害患者がたどる、こころの曲折と変貌がわかる。
「私の苦しみをどうかわかってください」
不安・恐怖の病は人をどう変えていくのか!?
パニック障害患者がたどる、こころの曲折と変貌を日本における治療・研究の第一人者が解き明かす

こころのエクササイズ-つらい気持ちを楽にする38のアイデア
こころライブラリー
もっと元気になりたい人のために認知療法の第一人者Dr.大野が教える、 つらさ・苦しさの「整理術」。なんだか気分が晴れない、最近ちょっと疲れ気味、もっとポジティブな性格になりたい、……こんな気持ちによく効きます。私たちの誰もが持っている「心の自然治癒力」を上手に引き出して、生活の中にひそむ「憂うつ」を解消します。大好評『こころの自然治癒力』の「実践編」。
自分のこころの育て方&ケアの方法教えます 「性格を変えたい……」とか、「なぜか分からないけどツライ」などと悩んでいる人の「憂うつ」を解消し、心の健康を回復・維持するための実践的方法を徹底解説

11歳の身の上相談 悩むわが子に元気と力を与える本
こころライブラリー
12歳でも13歳でもありません。11歳こそ、思春期の入り口であり、子供が大きな困難に直面するときです。大人への階段を登り始めたわが子の心を、親はどのように伸ばしてあげればよいのでしょうか。習い事をやめたい、携帯電話が欲しい、親のサイフからお金をとった――あなたは、こんな子供の言葉・行動にどう対応しますか? そんな悩みに分かりやすくお答えする一冊です。
【子供の言葉・行動にどう対応する?】
12歳でも13歳でもありません。11歳こそ、思春期の入り口であり、子供が大きな困難に直面するときです。大人への階段を登り始めたわが子の心を、親はどのように伸ばしてあげればよいのでしょうか。習い事をやめたい、携帯電話が欲しい、親のサイフからお金をとった――あなたは、こんな子供の言葉・行動にどう対応しますか? そんな悩みに分かりやすくお答えする一冊です。
【相談例】
・ピアノのレッスンをやめたい
・私立中に行きたくない
・携帯電話が欲しい
・弟なんていなければいい
・親の財布からお金をとった
・太っている自分をなんとかしたい
・友達ができない
・いじめられている子がかわいそう
・給食時間がつらい
・仲間外れにされるのがコワイ
ほか多数

大人のアスペルガー症候群
こころライブラリー
ひと目でわかるイラスト図解
《講談社 こころライブラリーイラスト版》
【うまく生きられないのは、障害があるため?】
社会に出てからアスペルガー症候群で苦しんでいる人は多い。
本人は仕事ができず、友だちが作れずに悩んでいる。
障害のもつ特性が、どう心に影響するかを徹底解説
自分では一生懸命がんばっているつもりなのに、
上司や同僚から「仕事ができない」「常識や礼儀が身についていない」と
批判されるのが、アスペルガー症候群の人に多い悩みです。
よい人間関係が構築できず、職場を転々として、
じょじょに自信を失っていってしまいます。 (第3章より)
【本書のおもな内容】
《第1章 なぜうまく生きられないのか》
●アスペルガー症候群/ よくも悪くも目立つ、三つの特性
●行動特徴/ 社会性がなく、失礼な言動をする
●どう考えるべきか/ こころの病気ではなく、脳機能のかたより
《第2章 人にあわせられない疎外感》
●付き合いの悩み/ 友達のつくり方がわからない
●子ども時代は……/ 少数の友達とだけ、仲がよかった
●どう考えるべきか/ 付き合いの幅を無理に広げない
●column 友人に頼みたいこと/ 悪意がないことを知ってもらう
《第3章 職場に定着できない無力感》
●仕事への無力感/ 指示されないと、自分からは動けない
●学生時代は……/ 天才肌で、得意科目に自信があった
●どう考えるべきか/ 指示があれば、期待に応えて働ける
●column 同僚に頼みたいこと/ 独特の行動への理解を求める
《第4章 誤解と非難がもたらす劣等感》
●誤解/ 家族が障害を認めないことに苦しむ
●二次障害/ 非難され続けて、劣等感や絶望を抱く
●どう考えるべきか/ 二次障害は対応次第で防げること
●家族に頼みたいこと/ 障害にいっしょにとりくんでいく
《第5章 支援を受けると、生活が安定する》
●生活支援/ 療育手帳や福祉手帳は取得できるのか
●就労支援/ 支援センターを利用して適職をみつける

友だちをいじめる子どもの心がわかる本
こころライブラリー
大人の想像を絶するひどいいじめをする子。一人ひとりは悪い子とは思えないのに友だちをいじめているときは悪意のかたまり。本書では現実のいじめの実態にもとづき、なぜ友だちをいじめるのか、なぜクラス全員で特定のひとりをいじめる「いじめの構図」ができあがるのか、いじめられている子がなぜ親にも言わないで耐えているのかなど、いじめる子や加担する子、いじめられている子の心理を徹底解明。対応策も紹介します。
親も教師も見抜けない「いじめ」の正体とは エスカレートするいじめ。いじめる側の心理が理解できないと解決できない。今、大人がすべきことは何か? 問題の核心に迫り、対応へのアドバイスも充実の一冊。

相談しがいのある人になる 1時間で相手を勇気づける方法
こころライブラリー
相談力がたちまちアップ! どんな場面でも必ず役立つ! プロのテクニック教えます。●まず30分、徹底的に聞き続ける●3分で劇的に変わる!3つのテクニック●「裏メッセージ」に取られたときの対処法●あなたの「支援者癖」に気づくこと
人の話を“聞く技術”が身につく方法とは? 職場や家族間で相談相手が短時間で満足できるコミュニケーション法がある。著者独自のメッセージコントロール理論を一般の人にも応用した「聞き上手」の決定版!

親に暴力をふるう子どもの心がわかる本
こころライブラリー
あんなに良い子だったのになぜ? 普通の良い子が突然キレる、暴言・暴力に走る……そんな子どもたちの内面にあるのは、言葉にならない苦しみです。暴力は、その苦しさの訴え、表に出た「症状」ともいえるのです。なにが不満なのか? どうしてほしいのか? 本書では暴力に隠された子どもの心理をわかりやすく図解。最終章では、親が陥りがちなパターンを紹介し、親が巻き込まれずにできることを紹介します。
「依存」と「過剰な甘え」の裏返しが暴力に!
普通のよい子が荒れていく。
なにが不満なのか?
どうしてほしいのか?
暴力に隠された子どもの心理を徹底図解。

子どもを愛せなくなる母親の心がわかる本
こころライブラリー
気づいたら怒りの感情にふりまわされ、子どもに手をあげている。くり返すうちに感覚がマヒして子どもの心身を傷つけることが平気になっていく――。わが子なのに可愛く思えないのはなぜ? これって虐待? 取り返しがつかなくなる前に、自分の心を見つめ直して。本書では深まる母親の心の闇をイラスト図解。夫をはじめ周囲の人ができることや本人にできることなど解決の糸口になる対策も紹介。読めば心が軽くなる本です。
わたしは母親失格?
わが子なのに可愛く思えないのはなぜ?
毎日の育児にイラつき、悩み、神経をすり減らしていく母親の心理を徹底分析。読めば、心が軽くなる!

夫をうとましく思う妻の心がわかる本
こころライブラリー
妻の8割は、「夫がストレス」症候群?!
なぜ、二人の心は大きくすれ違い、夫と一緒にいるだけでイライラしてしまうのか?
通じあえない夫婦の心理を徹底解明!

子どもの心の発達がわかる本
こころライブラリー
心は脳の働きの一部です。赤ちゃんにとって、体を動かすことは脳を育てること。ねんねからお座り、ハイハイ、たっち……日々赤ちゃんは成長し、周りの世界との関係を身につけていきます。赤ちゃんのしぐさのすべてが心を発達させる準備なのです。本書では、生まれてから就学前の5歳ごろまでに、子どもがどのように育ち、周囲の人との関係を築いていくか、子どもの心の成長と発達をたくさんのイラストを入れて解説します。
不思議な「心」のメカニズムが一目でわかる
《講談社 こころライブラリーイラスト版》
【赤ちゃんの心と脳はどんなふうに成長するの?】
ママの顔はどう見える?
自分の存在に気づくのはいつ?
言葉はどうやって覚える?
早期教育は必要?
反抗期は、どうして必要?
子どもが持つ「育つ力」は想像以上にハイレベル。
心と脳はどのように成長していくのかをやさしく図解する。
(まえがきより)
私たちは、まだまだ赤ちゃんについて知らないことがある! そんな気持ちで始めたのが「日本赤ちゃん学会」です。小児専門医だけでなく、発達心理学、脳科学、果ては人口知能の専門家まで巻き込んで、赤ちゃんの優れた「育つ力」を科学しています。
ところが一方で、こうした科学的な情報がなかなか育児の現場に活かされないという問題があります。「子どもの能力は3歳までで決まる」などの情報が、育児をになうお母さんを追い込んでいるのです。
この本は、生まれてから就学前の5歳ごろまでに、子どもがどのように育ち、どのように周囲の人との関係を築いていくか、子どものこころの成長と発達について紹介していきます。(小西行郎)
【本書のおもな内容】
《第1章 赤ちゃんは育つもの? 育てるもの?》
想像以上? 生まれたばかりの赤ちゃんの知恵
脳の成長
赤ちゃんの力
《第2章 体とこころの二人三脚》
赤ちゃんに備わっている育ちの3つのプログラム
脳のしくみ/ 自分発見 /手は語る
自我の芽生え/ ハイハイと社会/ 歩く!
《第3章 言葉の世界はこうして広がる》
“会話はキャッチボール”赤ちゃんとでも同じこと
通じ合い/ 表情を読む
言葉の練習/ 言葉の爆発/ 言葉の成長/ 読むと書く
《第4章 自分に気づく、人のこころに気づく》
反抗は、成長前のエネルギーの爆発
自立への第一歩/ 自画像/ 状況を読む/ 論理の誕生
うそとつもり/ まねの進化/ 思いやり
《第5章 家族、仲間は社会への第一歩》
子どもの世界は広く、奥深いもの
人とふれ合う/ 父と母/ きょうだい/ 友達

自我崩壊――心を病む 不条理を生きる
こころライブラリー
真冬に全裸で徘徊する女子高生
1億まで繰り返し数え続ける男
自分の手首を切り落とした運転手
奇妙すぎる行動、不可解な思考
なぜ人の心はこれほどまでに壊れてしまうのか?
精神疾患のもたらすさまざまな症状は、一見日常世界からはかけ離れているかのように思えることが多いが、実はわれわれの感性の深い部分と親和性が大きい。その激しい破壊性、衝動性、ある意味でたらめな豊饒さは、創造的、芸術的な活動と強く関連しているものであるし、われわれはそのような姿に恐れおののく一方で、強く惹かれもする。――<本文48ページより>
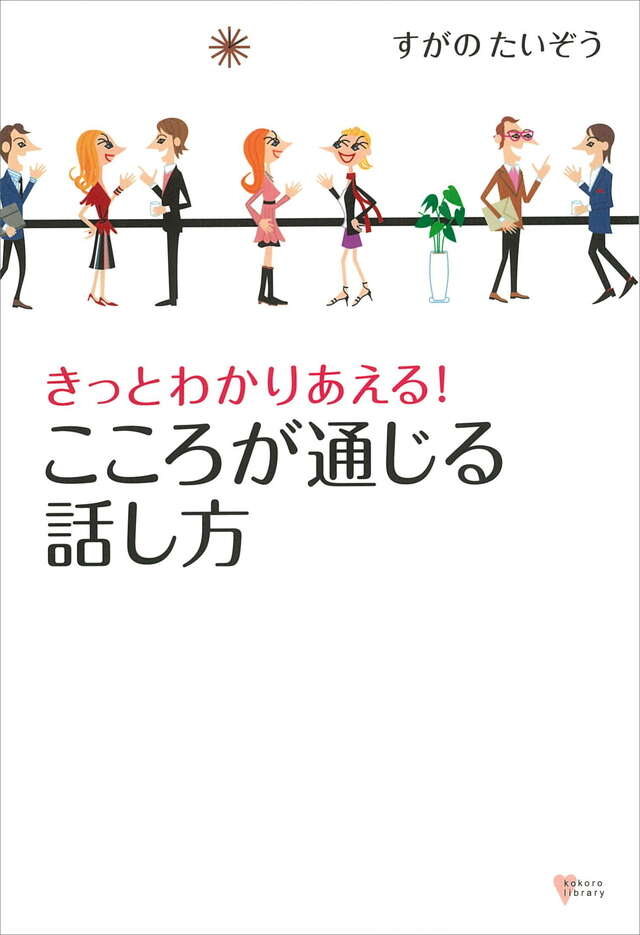
きっとわかりあえる! こころが通じる話し方
こころライブラリー
人気プロカウンセラーが教える対話のヒント集。話のうまい人は、いつも相手の立場に立つことを忘れない。上司対部下、夫対妻、親対子、教師対生徒など、人間関係で悩むすべての人に役立つ対話コミュニケーションのヒントが満載。対話力を身につければ、職場で、家庭で、学校で、あなたのこころが通じて人間関係もスッキリ変わる。巻末に「対話のための7つの心のルール」をまとめた。
職場で、家庭で、学校で じっくり聞いて、じっくり話せば
人間関係がスッキリ!変わる
気持ちがほぐれる対話コミュニケーションのヒント
話のうまい人というのは、いつも相手の立場に立つことを忘れません。
「今は不景気で大変ですが、みなさん、なんとかがんばっていきましょう」と伝えるにしても、聴衆がもし登山の愛好家だったら、「今の苦しさは、山登りでいえば、8合目あたりで胸突き八丁のところですが……」と喩えることによって、相手にスムースに伝わるようになるわけです。――<第2章より>

仕事中だけ「うつ病」になる人たち 30代うつ、甘えと自己愛の心理分析
こころライブラリー
病気休暇中に海外旅行。
不調になったのは会社のせい。
自分の「うつ病」をあちこちに言って回る。
心の病の休職者による企業損失が年間約1兆円とも言われる時代。30代に、新しいタイプの「うつ病」が急増している。果たして彼らは、ほんとうに病気なのか?それとも――!?
いまどき若年層ビジネスマンの心理を、当代一の人気精神科医が、切り口鋭く読み解く!
こんな「うつ」が30代に増えている――
●職場では不調だが、好きな趣味は精力的に行える
●学歴が高く、まじめだが、やや自己中心的
●自分が「うつ」であることの自覚が強い
●一定のレベルまで回復するが、なかなか復職に踏み切れない
●不安感、恐怖感、あせりといった感情の動揺がひどい
など
ツグオさん(31歳)はブログを開設したのだが、そこでは会社の不当な扱いに加えて、「今日もうつだ」「もう死んだほうがいいのかな」「気がついてみたらビルの屋上に立っていた」といったうつ症状、希死念慮をほのめかす記述が目立った。しかし、一方では好きなアーティストのライブに行ったり学生時代の友だちとキャンプに行ったり、と元気な様子も記されていた。会社の相談室から紹介された精神科に通って、かなり大量の抗うつ薬を服用しているらしかった。――<本文より>

死のまぎわに見る夢
こころライブラリー
死の前に見る夢は、臨床心理の専門家たちの間でずいぶん前から人生最後の創造性として話題になっている。専門的な知識がない人にも読みやすく書かれた本書は、その理解と「救い」や「癒し」のための入門書である。――(深層心理学者・きたやま おさむ)
長いすに横たわっている自分自身の姿が見える。
主治医が妻に「ご主人はお亡くなりになりました」と言うと、夢からすべてのものが消えていく。それまで動いていた時計の針が止まったそのとき、時計の後ろに窓が現れ、明るい光が注ぎ込んできた。光は輝く道となり、わたしはその光の道を進んでいった。――ある精神分析家の父親の夢