講談社文芸文庫作品一覧
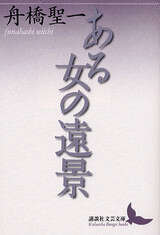
ある女の遠景
講談社文芸文庫
愛慕する年若い叔母・伊勢子の、自裁の謎を追ううちに、維子は、不実な男・泉中紋哉との官能の罠に、みずから墜ちていく。性愛に囚われた維子の現在、ミステリアスな伊勢子の過去、さらに情熱の歌人・和泉式部の生きた遠い昔……時空を隔てた3人の女人像を、巧緻な遠近法でとらえ、王朝文化と戦後風俗という「聖」と「俗」のあわいに、独得の官能美の世界を現出させた、筆者晩年の傑作。毎日芸術賞受賞作品。

戦後短篇小説再発見17
講談社文芸文庫
組織の力に抗して、自由を希求する闘いの軌跡――軍隊、会社など集団の中の個人の挫折と希望を描く十篇。
・中山義秀「あやめ太刀」
・梶山季之「族譜」
・中野重治「第三班長と木島一等兵」
・新田次郎「八甲田山」
・富士正晴「足の裏」
・城山三郎「調子はずれ」
・佐多稲子「疵あと」
・黒井千次「椅子」
・石原慎太郎「院内」
・辻原登「松藾」

耽溺・毒薬を飲む女
講談社文芸文庫
岩野泡鳴自身をモデルにした主人公・田村義雄は、或る夏脚本を書くため国府津に出掛ける。そこで土地の男と芸者吉弥を張り合うことになるが……
出世作「耽溺」のほか、樺太に渡り蟹の缶詰事業を試み失敗し北海道を放浪する経緯を描いた自伝的小説、自然主義文学中特異といわれた〈泡鳴五部作〉のうちの1篇「毒薬を飲む女」を収める。
作家的地位を確立した代表作2篇。

花づとめ
講談社文芸文庫
現代詩の前衛にして、加藤楸邨を師と仰ぐ俳人。また、芭蕉、蕪村、藤原定家の独創的評釈で知られる古典探究者。昭和46年から48年、芭蕉の連句評釈に心魂を傾ける傍ら、二巡りする四季に寄せて万葉から現代俳句まで、秘愛の歌へのオマージュを「季節のうた」として書き続けた。俗解を斥け、鍛えぬかれた言葉で読み解く103篇の短章は、正に「秋水一閃」の達人の技を思わせる。

戦後短篇小説再発見16「私」という迷宮
講談社文芸文庫
夢、幻想、欲望の中に浮遊する<私>というカオス――
さまざまな仕掛けで存在の謎と闇に迫る11篇。
・梅崎春生「鏡」
・遠藤周作「イヤな奴」
・高橋たか子「骨の城」
・吉田健一「一人旅」
・島尾敏雄「夢屑」
・安部公房「ユープケッチャ」
・中里恒子「家の中」
・小川国夫「天の本国」
・三田誠広「鹿の王」
・小林恭二「磔」
・森瑤子「死者の声」

林芙美子・宮本百合子
講談社文芸文庫
ともに明治生まれ、大正昭和の激動を生き、「その並び立つ姿は文壇空前の壮観」(広津和郎)と言われた三女流。平林たい子が著した本書は、同時代を生きた好敵手ニ人の「文学」と「人生」を遠慮会釈なく、だが底に熱い人間的共感をこめて描き、評伝文学として無類の面白さをもつ。情熱の人・芙美子、知性の人・百合子、評するは稀代のリアリストたい子――三者三様の強烈な個性が躍如とする一冊。

徳山道助の帰郷・殉愛
講談社文芸文庫
陸軍中将にまで昇りつめた華々しい経歴と、その後の不如意な暮らし――時代の転変とともに屈折していく出郷者の想いを追った芥川賞受賞作「徳山道助の帰郷」ほか、フランス人女性と結婚した画家の秘密めいた生活に迫る「殉愛」、祖母の葬儀の顛末を記す「坐棺」の三作品を収録。平明な文体で、人生の様々な局面をおおらかに描いた早世の作家・柏原兵三の世界をあますところなく示す。

戦後短篇小説再発見15 笑いの源泉
講談社文芸文庫
戯画化、誇張、諷刺によって浮かび上がる人間の姿――
硬直した精神に鋭い一撃を与え、笑いの中に真実を探る十一篇。
・獅子文六「無頼の英霊」
・舟橋聖一「華燭」
・正宗白鳥「狸の腹鼓」
・小沼丹「カンチク先生」
・開高健「ユーモレスク」
・堀田善衛「ルイス・カトウ・カトウ君」
・花田清輝「伊勢氏家訓」
・筒井康隆「寝る方法」
・北杜夫「箪笥とミカン」
・杉浦明平「海中の忘れもの」
・椎名誠「日本読書公社」

文芸時評
講談社文芸文庫
大正10年「招魂祭一景」で注目された著者は翌11年、文芸時評家として文壇に登場、小説を書く傍ら20年に亘り時評を書き続けた。本書には「永井荷風氏の『つゆのあとさき』」、「谷崎潤一郎氏の『春琴抄』」のほか横光利一の純粋小説論にふれた「『純粋小説論』の反響」など昭和6年から13年までの時評を収録。自ら激動の時代を反映。ノーベル賞作家川端康成の出発点を刻す文芸時評。

戦後短篇小説再発見14 自然と人間
講談社文芸文庫
自然の中に揺曳する生の原風景――故郷の山河、庭の草木、思い出の道、風の音……自然の姿に想いを仮託する10篇。
・火野葦平―――「鯉」
・近藤啓太郎――「赤いパンツ」
・井上靖――――「道」
・上林暁――――「四万十川幻想」
・竹西寛子―――「鶴」
・尾崎一雄―――「閑な老人」
・丸山健二―――「チャボと湖」
・阪田寛夫―――「菜の花さくら」
・加藤幸子―――「主人公のいない場所」
・多和田葉子――「ゴットハルト鉄道」

花筐・白雲悠々
講談社文芸文庫
10代の男女の純粋な魂を抒情豊かに描いた青春の饗宴「花筐」、戦後の混乱期の中で破滅へと傾斜する誇り高き男を描く「元帥」、類稀な作家魂で愛妻リツ子の死に迫る「終りの火」、戦後世相の中に無頼の生き方を浮かび上らせる「白雲悠々」など6篇を収録。天然の旅情の指し示すまま、憧憬と彷徨の生涯を貫いた“浪漫的放浪者”檀一雄の特質を伝える短篇集。

美を求める心
講談社文芸文庫
沖縄戦での許嫁の死、生家の破産、離婚……。病弱な女ひとりの境涯を支えるため、細々とラジオに寄稿し始めて50年、一貫して無名の庶民の心性に寄り添い、魂の深部から響いてくる真実の言葉を刻み続ける。自然の風景に、仏像の佇まいに、平凡な暮らしの道具に、そして何より人の心の中に美を求める、珠玉の88篇が、厳しくもしなやかな半生の美への巡礼の足跡を指し示す。

大阪の宿
講談社文芸文庫
保険会社に勤務する著者は実業家として活躍する一方 三田派の中心メンバーとして文筆活動を続けた。大阪勤務時代に材を取った本書は、江戸っ子会社員を主人公に下宿先の旅館酔月の女将、下働きの女たち、新聞記者、芸者お葉……等々の人間模様を織り込み潔癖性で正義感の強い東京山の手育ちの主人公が見聞する大阪の世相、風俗、気質等を巧みに描いた傑作長篇小説。

戦後短篇小説再発見13
講談社文芸文庫
男女のエロスの深淵から放たれた衝撃の十篇日常から非日常へ、さらには死へと導くエロス、その絶対的な力の前で苦悶する様々な男女を描く。坂口安吾、円地文子、北原武夫、野口冨士男、三枝和子等を収録。

対談・人間と文学
講談社文芸文庫
近代文学を代表する評論家中村光夫と作家三島由紀夫が小説・戯曲・評論の各分野に亘り対談。「近代的自我について」「小説を書くということ」「文学者の死について」等をテーマに文学とは何か、文学者とは何かを問う。文学観、人間観を拮抗させ、はぎれのよい対話を展開、文学の魅力を縦横に語る。死へと傾斜してゆく三島を静かに予感させる話が随所に埋め込まれた興味深い対談集。

身心快楽
講談社文芸文庫
滅亡は私たちだけの運命ではない。生存するすべてのものにある。滅亡の真の意味は、それが全的滅亡であることにある。戦後文学の巨人、『司馬遷――史記の世界』の著者・武田泰淳の全体像に迫る精選随筆集。代表的エッセイ「滅亡について」をはじめとし、武田文学に思想的重量感をもたらすことになった中国での戦争体験、敗戦の騒然たる体験へのあくなき思索、同時代文学と自作への問いかけ、自伝等、28篇を収録。
滅亡は私たちdけの運命ではない。生存するすべてのものにある。
滅亡の真の意味は、それが全的滅亡であることにある。戦後文学の巨人、『司馬遷――史記の世界』の著者・武田泰淳の全体像に迫る精選随筆集。代表的エッセイ「滅亡について」をはじめとし、武田文学に思想的重量感をもたらすことになった中国での戦争体験、敗戦の騒然たる体験へのあくなき思索、同時代文学と自作への問いかけ、自伝等、28篇を収録。
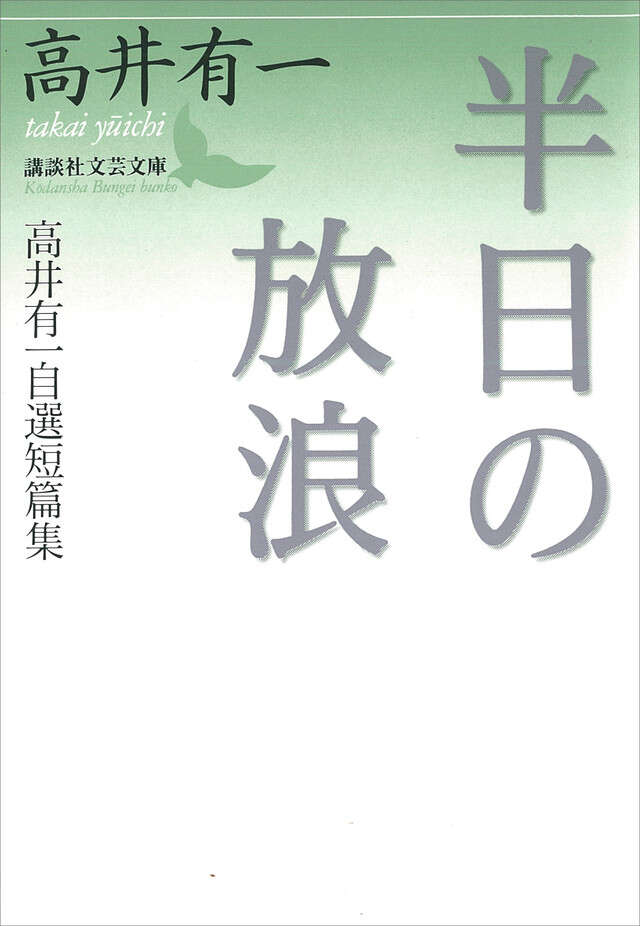
半日の放浪 高井有一自選短篇集
講談社文芸文庫
疎開先で入水した母の遺骸を凝っと見つめる、少年の目。二世帯住宅にするため、明日は家を取り壊すという日、嬉々とする妻をよそに、街に彷徨い出た初老の男の目。――戦争と母の自死を鮮烈に描いて文学的出発を告げた、芥川賞受賞作「北の河」、人も街も変質する世情への微妙な違和感を描く「半日の放浪」など、透徹した観察眼で昭和という時代を丸ごと凝視し続ける、高井有一の自選7短篇。

杉田久女随筆集
講談社文芸文庫
足袋つぐやノラともならず教師妻
花衣ぬぐやまつはる紐いろいろ
大正期、俳誌「ホトトギス」に身近な台所雑詠を投句、目覚めつつある女性の心の叫びを鮮烈に詠み、天才と謳われながら、師・虚子に破門されるや一転、孤立のなか窮死。
強烈な自我と時代の軋轢に苦しみながらひたむきに生きた杉田久女の人生を、俳句、随筆、俳論の3部で構成。

独断的作家論
講談社文芸文庫
<文学の鬼>と称された著者の多彩な作家論斎藤茂吉、永井荷風、川崎長太郎、島木健作等の人と作品を論じるほか、親しかった牧野信一、嘉村礒多等の思い出を機知に富んだ独得の筆で綴る宇野浩二の真骨頂。

戦後短篇小説再発見 12
講談社文芸文庫
第二期 全8巻84篇の秀作ここに!
時代の波に漂う恋の行方――
若い男女の熱い想いと挫折を鮮やかに描き、青春の思い出の一齣を甦らせる恋の物語11篇。
野間宏――「二つの肉体」
石坂洋次郎――「草を刈る娘」
川崎長太郎――「夜の家にて」
原田康子――「サビタの記憶」
福田章二――「蝶をちぎった男の話」
三浦哲郎――「初夜」
川端康成――「木の上」
唐十郎――「恋のアマリリス」
向田邦子――「花の名前」
水上勉―――「箒川」
三木卓――「ボトル」
編纂委員=井口時男・川村湊・清水良典・富岡幸一郎