講談社文芸文庫作品一覧

時間
講談社文芸文庫
人生の中で時間が流れていく、ということの意味を考え現代文明の偏見を脱して捉われの無い自由な自分となる。文化の真の円熟や優雅さは18世紀西欧にあるとの『ヨオロツパの世紀末』を著した著者が、その最晩年に到達した人間的考察の頂点にして、心和む哲学的な時間論。『時間』を書き上げると残っているものを全部出したと感じる、と述懐した批評家吉田健一の代表作。

若い詩人の肖像
講談社文芸文庫
小樽高等商業学校に入学した「私」は野望と怖れ、性の問題等に苦悩しつつ青春を過ごす。昭和3年待望の上京、北川冬彦、梶井基二郎ら「青空」同人達との交遊、そして父の危篤……。純粋で強い自我の成長過程を小林多喜二、萩原朔太郎ら多くの詩人・作家の実名と共に客観的に描く。詩集『雪明りの路』『冬夜』誕生の時期を、著者50歳円熟の筆で捉えた伊藤文学の方向・方法を原初的に明かす自伝的長篇小説。

ミドルマ-チ(二)
講談社文芸文庫
ドロシアと結婚した27歳年上のカソーボン牧師は、妻に好意をよせるいとこのラディスローへの嫉妬に苦しむ。この物語のもう一方の主要人物である有能な青年医師リドゲイドは、ミドルマーチ市長の娘ロザモンドと結ばれる。イングランド中部の商業都市ミドルマーチを舞台に多彩な人間模様を描写した、ヴィクトリア朝を代表する女流作家ジョージ・エリオットの代表作。(全4巻)
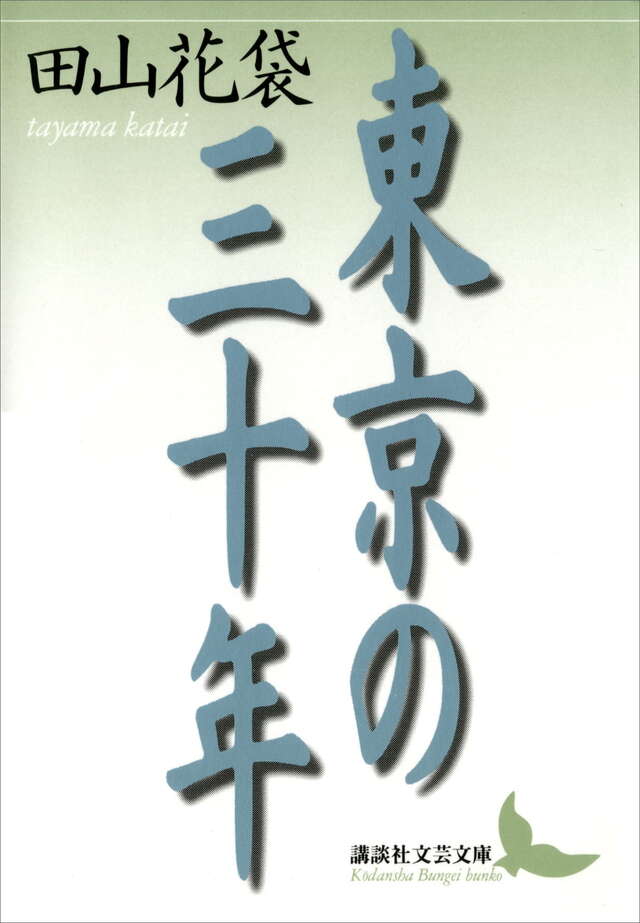
東京の三十年
講談社文芸文庫
明治初年幼くして上州館林から上京、丁稚奉公から始まる苦しい文学修行を経て『蒲団』『田舎教師』などを著し、日本自然主義文学の代表的作家となった著者の文壇回想記。島崎藤村、柳田国男、国木田独歩等との交友、明治から大正への激動する時代の新思潮、生、死を縦横に捉えて、自然主義文学の盛衰、文壇の側面、数十年に亘る〈東京〉の風俗・文化・市街風景の変遷変貌を生き生きと描く。
明治初年幼くして上州館林から上京、丁稚奉公から始まる苦しい文学修行を経て『蒲団』『田舎教師』などを著し、日本自然主義文学の代表的作家となった著者の文壇回想記。島崎藤村、柳田国男、国木田独歩等との交友、明治から大正への激動する時代の新思潮、生、死を縦横に捉えて、自然主義文学の盛衰、文壇の側面、数10年に亘る〈東京〉の風俗・文化・市街風景の変遷変貌を生き生きと描く。

業苦・崖の下
講談社文芸文庫
嘉村磯多は山口県の農家に生まれ、短躯色黒のために劣等感に悩まされた。初恋の相手とは両親の反対で挫折し、結ばれた別の女性とは婚前の不品行を疑い、妻子を捨てて愛人小川ちとせと出奔上京、その体験を『業苦』に書いた。小説の本領は自分の事を書く“私小説”にあるとの当時の思潮を愚直に実践し、自己暴露的な私小説20余篇を残し昭和8年37歳で早逝した特異な私小説作家の秀作群。

女たちへのエレジ-
講談社文芸文庫
「ニッパ椰子の唄」「洗面器」「シンガポール羅衛街にて」等の若き日のアジアへの放浪の旅が生んだ「南方詩集」と「畫廊と書架」他の3部構成詩集『女たちへのエレジー』。女性への憧憬、愛着、切なさをうたう連作詩「愛情69」。時代に抗し生涯にわたり魂の自由を求めた詩人の生きる証として書かれた詩集2冊を収録。

日本文壇史23 大正文学の擡頭
講談社文芸文庫
「行人」連載中、三たび胃潰瘍に倒れた漱石の推薦で「朝日」に無名の中勘助「銀の匙」載る。大正3年、第3次「新思潮」創刊。漱石『こヽろ』岩波書店より刊。蘆花『黒い眼と茶色の目』刊。4年、萩原朔太郎、室生犀星「卓上噴水」創刊。第1次大戦下のパリの藤村、軍医総監鴎外の日々。「カチューシャの唄」一世を風靡。若き菊池寛、芥川龍之介、倉田百三ら。長塚節の死。5年。「青鞜」終焉。大正文学擡頭明治文壇の関係を観る。

ミドルマ-チ(一)
講談社文芸文庫
美しいドロシアとその妹シーリアは両親をうしない、伯父のブルック氏のもとに身を寄せている。宗教的理想に燃えるドロシアは、大地主の青年チェッタム卿を退け、27歳年上のカソーボン牧師との結婚をえらぶ。イングランド中部の商業都市ミドルマーチを舞台に多彩な人間模様を描写した、ヴィクトリア朝を代表する女流作家ジョージ・エリオットの代表作。(全4巻)

志賀直哉交友録
講談社文芸文庫
志賀直哉は文豪にふさわしい豊かな文学世界をつくりあげたが、私生活では人なつこく、遊びごとのトランプや麻雀を楽しんだという。本書で志賀門下の阿川弘之が、直哉と縁のあった40人を選んで交友録を編んだ。夏目漱石、内村鑑三、清水澄から始まり、「白樺」の同人の武者小路実篤、長与善郎など、画家の梅原龍三郎や、門下の瀧井孝作、尾崎一雄以下そのひろがりは1つの時代史ともなっている。

鳳仙花
講談社文芸文庫
小田原の魚屋の息子に生まれたが、文学への夢が捨てきれず家督を弟に譲って上京するも、小説家として一本立ち出来ずに郷里に逃げ帰る。そんな前半生と売れない老残の作家の娼婦との交遊が、地べたを這うような低い視点からの一種の諧謔味をおびた川崎文学をつくりだす。本書は「鳳仙花」「乾いた河」などの代表作のほかに中山義秀との交友を描いた「忍び草」など7篇収録。

私小説作家論
講談社文芸文庫
己を没却し、対象の小説家の心に成り切った著者は岡本かの子を描けば妄想は何時しか悩ましい雰囲気を醸し、嘉村礒多を描けば愛の懊悩、業苦と共にのたうち廻る。宇野浩二、志賀直哉、原民喜ら12の鮮烈な肖像から、批判されつつも抗し難い私小説の魅力の秘密を解明し、近代日本の私小説が持つ倫理性と宗教性に説き及ぶ。山本健吉の文学的生涯の出発を告げた論稿。

アブサロム、アブサロム!(下)
講談社文芸文庫
少年時代に受けた屈辱により、南部で人間として認められるには「土地と黒人と立派な家」を持たなければならないと思い知らされたサトペンは、その野望の達成に向けて邁進する。しかし最初の妻に黒人の血が混じっていることを知って捨てた報いにより、築き上げた家庭は内部から崩壊していく。小説表現の限界に挑みながら20世紀文学の最先端を歩み続けたフォークナーの渾身の大作。

魯庵日記
講談社文芸文庫
小説、評論、翻訳と明治文壇にあって幅広く活躍した魯庵は、終生社会的関心を失わず、特に旺盛な好奇心は、随筆においてその面白さを発揮した。本書は魯庵の日記の明治27年から44年までの抜き書きであり、コラージュ的に新聞記事をそのまま貼りつけたり、実物大の名刺があったり、当時の生活風俗万般がそのまま記載され、いまでいう文化人類学的厚みをもった日記となっている。

アブサロム、アブサロム!(上)
講談社文芸文庫
南北戦争が始まる頃、ヨクナパトーファ郡ジェファソンに飄然と現れた得体の知れない男トマス・サトペンは、インディアンから百平方マイルの土地を手に入れ、大いなる家系を創始するべく、町の商人コールドフィールドの娘と結婚する。サトペン家の興隆と崩壊を物語りつつ、アメリカ南部の過去と現在の宿命的な交わりを描いた迫力ある長篇。

私の上に降る雪は
講談社文芸文庫
《私はあの子のことを、よくわかってやろうとしませんでした。……中也が詩を作るのに反対しながら、私は一方でお茶ばかり熱中していたんです。》
明治40年、医者の長男として山口県湯田温泉に生まれ、生涯仕事に就くことなく30歳で天逝した詩人の姿を94歳になった母が悔恨と愛惜の情を込めて話す。中也を知る必須の資料であり、美しい感動を伝える書。

日本浪曼派批判序説
講談社文芸文庫
「日本浪曼派」は神保光太郎、亀井勝一郎、中島栄次郎、中谷孝雄、緒方隆士、保田与重郎ら6人で創刊した雑誌名であるが、戦前、大日本帝国の侵略的アジア主義、満州国の擁立から第2次大戦の流れのなかで文学運動をこえて、青少年に思想的に多大な影響を与えた。本書は、日本浪曼派の中心人物たる保田与重郎らの近代批判、古代賛歌的日本主義などを初めて精細に批判、検証したもの。

日本文壇史22 明治文壇の残照
講談社文芸文庫
大正元年、舟木重雄・広津和郎・葛西善蔵ら「奇蹟」創刊。堺利彦の売り文社にいた大杉栄・荒畑寒村「近代思想」創刊。小山内薫が欧州へ演劇修業に出発。大正2年、こま子との関係に苦悩、藤村パリへ出発。斎藤茂吉の「赤光」が広く文豪の称賛の得る。花袋・藤村・秋声・白鳥・泡鳴ら自然主義文学大家の変化と去就、明治文豪を背負いつつも明確な大正文学の胎動を、思潮と人間交流の中に鮮やかに描く。
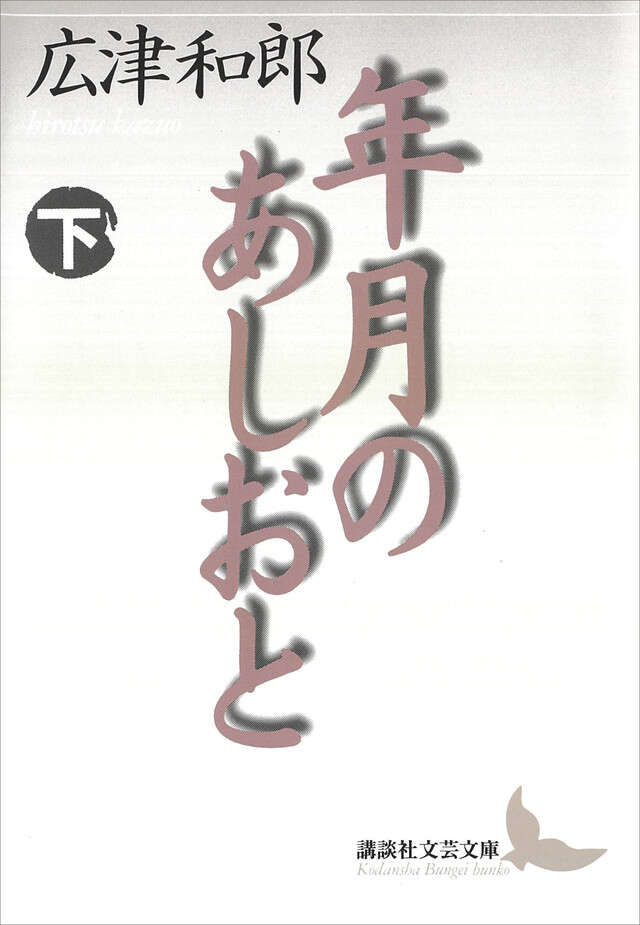
年月のあしおと(下)
講談社文芸文庫
文芸評論家となる切っかけとなった「洪水以後」入社前後から、小説を書き始めた頃の滝田樗陰との出会い、尾崎士郎、宇野千代との大森馬込時代、関東大震災後の市井の不穏、プロレタリア文学抬頭期の本郷菊富士ホテル周辺、畏友・宇野浩二の病、芥川龍之介の自殺、葛西善蔵の死、父・柳浪の他界など、自伝的要素を加えた屈指の文壇回想録。野間文芸賞、毎日出版文化賞受賞作品。正篇上下2巻完結。
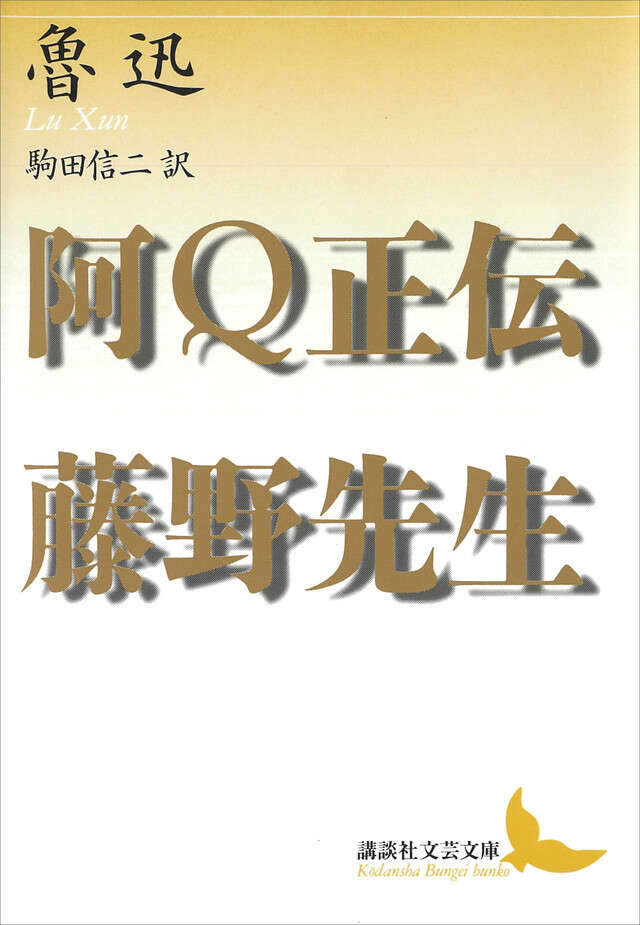
阿Q正伝・藤野先生
講談社文芸文庫
「人が人を食う」ことを恐怖する主人公の、「子供を救え」の叫びとともに、封建制度・儒教道徳の暗黒を描く「狂人日記」。革命のどさくさの中の阿Qの死と悲喜劇を通して、「革命と民衆」を鋭くつく「阿Q正伝」。ほかに、「孔乙己」「酒楼にて」など。辛亥革命前後の混乱期に、敢然とペンを執って立ち上がり、中国近代文学を切り拓いた魯迅が、時代の苦悩と不屈の精神を伝える13篇の名作。魯迅を読まずして中国を知ることはできない。
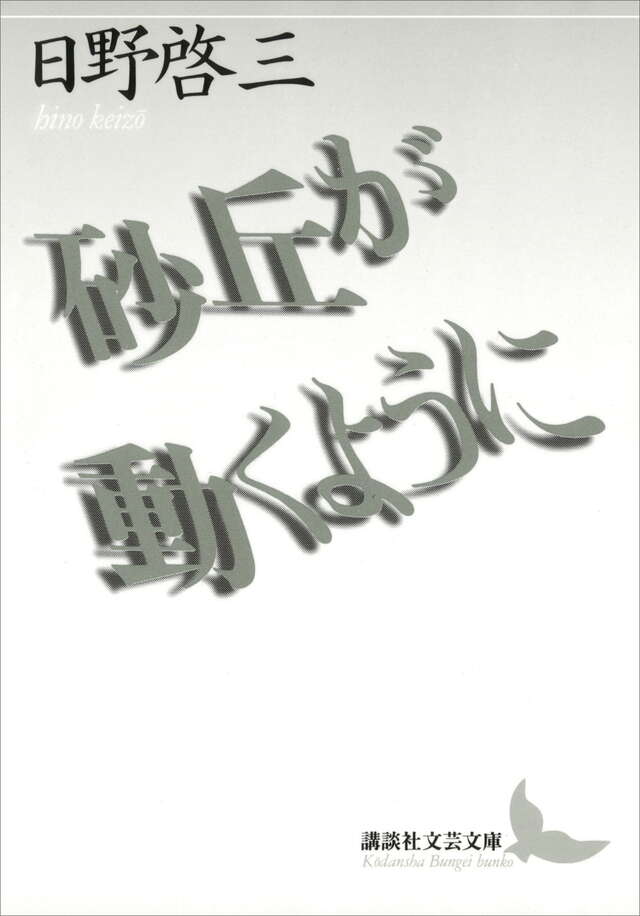
砂丘が動くように
講談社文芸文庫
海沿いの砂丘のある町にやってきたルポライターの男が、少年に誘われ迷い込んでゆく奇妙な町の夜と昼の光景。超能力を持つ少年と盲目のその姉。女装する美しい若者。夜の闇に異常発生する正体不明の無数の小動物キンチ。刻々に変化して砂防林にも拘らず死滅へと向かう砂丘。現代人の意識の変容を砂丘の物質のイメージに托しつつ未来宇宙への甦りを象徴させる。第22回谷崎潤一郎賞。