講談社文芸文庫作品一覧

愛のごとく
講談社文芸文庫
自己中心的な生き方に固執する青年の下宿に土曜日ごとに現われる、かつて恋人だった人妻との異様な情事を通して孤独な青年の荒寥とした精神風土を描いた「愛のこどく」ほか、「演技の果て」「その一年」「海岸公園」「クリスマスの贈物」「最初の秋」を収録。戦後の変転の中で青春を生き、交通事故で早世した山川方夫の傑作選。

招魂の賦
講談社文芸文庫
梶井基次郎らと刊行した雑誌、「青空」、そして保田與重郎、亀井勝一郎らと創刊した「日本浪曼派」はとくに戦前の風潮とあいまって一世を風靡した感がある。本書は文学的僚友のあいだで、地味ではあるが兄貴分の場所にいた中谷孝雄が、いまだ文学的雰囲気の濃密な時代と友人たち、彼らの死を親情あふるる抑制をもって描く。収録作品中、「桂子」は主人公の孫の早逝を悲しんで哀切きわまりない。

挾み撃ち
講談社文芸文庫
20年前に北九州から上京した時に着ていた旧陸軍の外套の行方を求めて、昔の下宿先を訪ねる1日の間に、主人公の心中には、生まれ育った朝鮮北部で迎えた敗戦、九州の親の郷里への帰還、学生時代の下宿生活などが、脱線をくり返しながら次々に展開する。
他者との関係の中に自己存在の根拠を見出そうとする思考の運動を、独特の饒舌体で綴った傑作長篇。

日本文壇史21 「新しき女」の群
講談社文芸文庫
平塚らいてう、尾竹紅吉、神近市子、伊藤野枝ら「青鞜」の活動、“吉原登楼”など「新しい女」達は激しい批判を呼ぶと共に“現代の婦人問題”の端緒を拓いた。晶子はロンドンで婦人運動に目を瞠る。白樺派の作家、谷崎、荷風と三田派の青年、白秋、露風等の交遊と多感な生活。啄木の死。『一握の砂』刊。明治天皇崩御。乃木希典夫妻殉死の衝撃と鴎外の『興津弥五右衛門の遺書』。坩堝の如き文壇、社会を抱き時代は大正へ。

エヴゲ-ニイ・オネ-ギン
講談社文芸文庫
《もはや疑う余地はない。いたましや!エヴゲーニイはタチヤーナに子供のような恋をしたのだ。》
19世紀初頭のロシア社交界、可憐な少女の愛を拒んだ青年オネーギンは、後年魅力溢れる人妻に変貌していた彼女を見、衝撃を受け、求愛する。しかし、時遅く……。愁いをたたえ、心の美しい公爵夫人タチヤーナをめぐって人間の真実の愛を謳う近代ロシア最高の韻文小説の名訳。

年月のあしおと(上)
講談社文芸文庫
明治・大正・昭和の文学的追想。ことに大正から昭和の時代風俗、文壇の裏面史をぎっしりと埋め込み、芥川龍之介をはじめ同時代の作家の風貌をいきいきと捉えた、自伝的文壇回想録。正篇を上下二巻に編集、上巻には大正4年終生の友人・宇野浩二との親交を深めた三保松原の旅行、父・柳浪が病気療養のため東京から知多半島師崎に転ずる前後までを収録。野間文芸賞、毎日出版文化賞受賞作品。<上下巻>

晩年の父犀星
講談社文芸文庫
昭和36年夏、軽井沢滞在中の犀星は、軽い胸痛を覚え帰京後入院。翌年春、詩「老いたるえびのうた」を遺して肺癌で逝去。本書は、病臥の父の姿を克明に綴り、最期まで作家の想いを共に生きた娘の鎮魂の書。犀星が晩年に身近に隠し置いた女性2人の存在を明かし、微妙に揺れる娘としての心情を書く「三人の女ひと」併録。

使徒教父文書
講談社文芸文庫
教会史上、正典につぐ地位を占めてきた諸文書。古代キリスト教会で評価の高かった「十二使徒の教訓」、黙示文学の形式で書かれた「ヘルマスの牧者」の他、「バルナバの手紙」「クレメンスの手紙」「イグナティオスの手紙」「ポリュカルポスの殉教」など10篇を学問的に原典から訳した、新約聖書の世界の全体像を把握するために必読の書。

中世・剣
講談社文芸文庫
著者が出征に際し、遺書代りに書いたという「中世」は、25歳にして夭折した足利義尚を悼んでの父義政の嘆きとこの世ならぬ魂の招来を美文で綴る三島文学の美への基調を窺わせる。また、「剣」は剣道部員を主人公に、思想を鍛える如くに修練に励み、そして部員の裏切りにも自死を以て諫める知行合一的世界を展開、後年の死をも含めた作品群を暗示する。他に4篇収録。

謡曲平家物語
講談社文芸文庫
幼い頃自ら能の舞台にも立った経験を持つ著者が、平家物語と謡曲との違い、読むもの、聞くものから見るものへの展開、その魅力の深まりを跡づける。幽霊能の世界を極めた「花伝書」の世阿弥に共感しつつ、能が醸す夢うつつの至福の境へと読者を誘う。平家物語と能への導きとなる27章。

日本文壇史20 漱石門下の文人たち
講談社文芸文庫
帝国劇場完成後、岡本綺堂ら近代劇の脚本家が輩出。無名の谷崎潤一郎は荷風の大讃辞を得、明治44年12月第1創作集「刺青」刊、一躍文壇に登場。漱石の「彼岸過迄」。晶川の死、小山内薫、泡鳴、秋江、牧水、夕暮、中里介山の動静。のちの漱石門下三羽烏鈴木三重吉、寺田寅彦、中勘助や小宮豊隆、和辻哲郎、阿部次郎等々。新思潮が競い咲く明治末年、多岐多様な文学ジャンルを担う若者たちの青春群像。
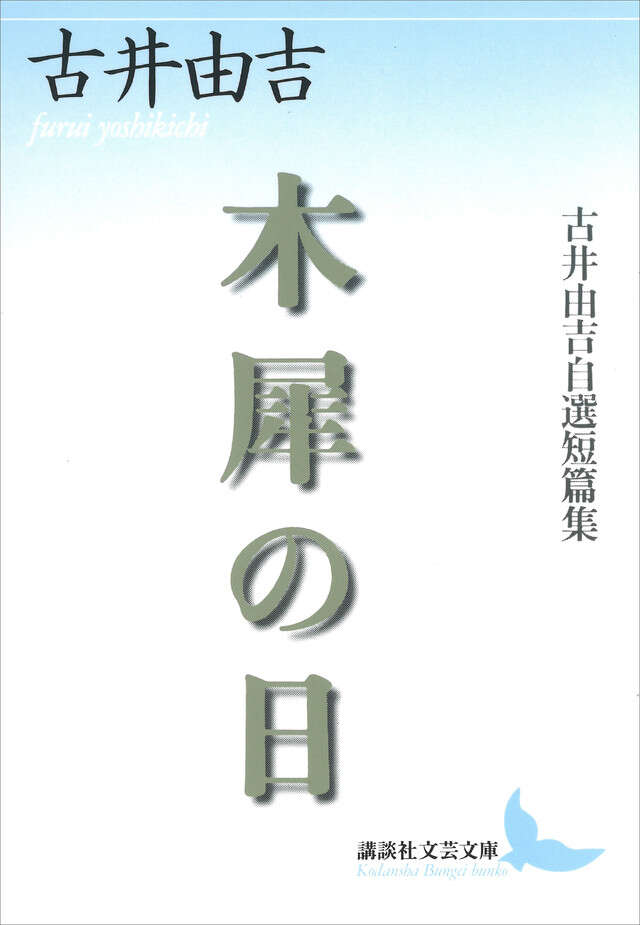
木犀の日
講談社文芸文庫
「都会とは恐ろしいところだ」……5年間、地方で暮らし、都会に戻った私は、毎朝のラッシュに呆然とする。奇妙に保たれた〈秩序〉、神秘を鎮めた〈個と群れ〉の対比、生の深層を描出する「先導獣の話」のほか、表題作「木犀の日」、「椋鳥」「陽気な夜まわり」「夜はいま」「眉雨」「秋の日」「風邪の日」「髭の子」「背中ばかりが暮れ残る」の10篇。内向の世代の旗頭・古井由吉の傑作自選短篇集。

迷路のなかで
講談社文芸文庫
おなじ外観の家が続く雪に塗りこめられた街の迷路をさまよう敗残兵の姿と、「ライフェンヘルスの敗戦」と題された絵の場面とが交錯し、物語は複雑な軌跡を描きながら展開回帰をくり返す。兵士は銃撃をうけ、居合わせた医者に介抱されながら死ぬが、意表をつく結末が控えている。執拗なまでに幾何学的な描写によって独特の世界を構築し、ヌーボー・ロマンの旗手となったロブ・グリエの代表作。

儀式
講談社文芸文庫
戦争後遺症のラグーナ・プエブロ族の混血の青年テイヨの心身は軍の病院でも治療できない。頼みは部族伝統の儀式。メディシン・マンのベトニー老人は治癒への“新しい儀式”と砂絵を示す。自然の知恵、愛、自己の認識。口承文学の香り高き寓話と詩を自在にとり入れつつ、第2次世界大戦後の“アメリカ・インディアン”の若者達の厳しい現実を描出。ネイティヴ・アメリカン文学の旗手シルコウの物語世界。

近代日本の批評3 明治・大正篇
講談社文芸文庫
野口武彦「煩悶、高揚、そして悲哀近代日本の『批評』の発見」、蓮實重彦「『大正的』言説と批評」の2論文を機軸に徹底討議。近代国家成立から帝国主義へと移行する明治・大正期の思想批評の諸問題、言文一致、キリスト教、自然主義、白樺派、私小説等を詳細に分析。浅田彰、柄谷、野口、蓮實、三浦雅士によるシリーズ第3弾。『近代日本の批評』全3巻完結。各巻に批評史略年表、人名・書名索引を付す。

何処へ・入江のほとり
講談社文芸文庫
栄達出世を夢みつつ、人生への懐疑にゆれる悩める青年健次の魂の行方を追う「何処へ」。瀬戸内海沿いの旧家に集まる兄弟姉妹らの心の翳と哀感を描く「入江のほとり」。父の死を綴る「今年の春」、母の死を書く「今年の初夏」。生涯基督教の神を求めながら棄教し、晩年に回心した“懐疑しつつ信仰を求めた求道者”正宗白鳥の代表作8篇。
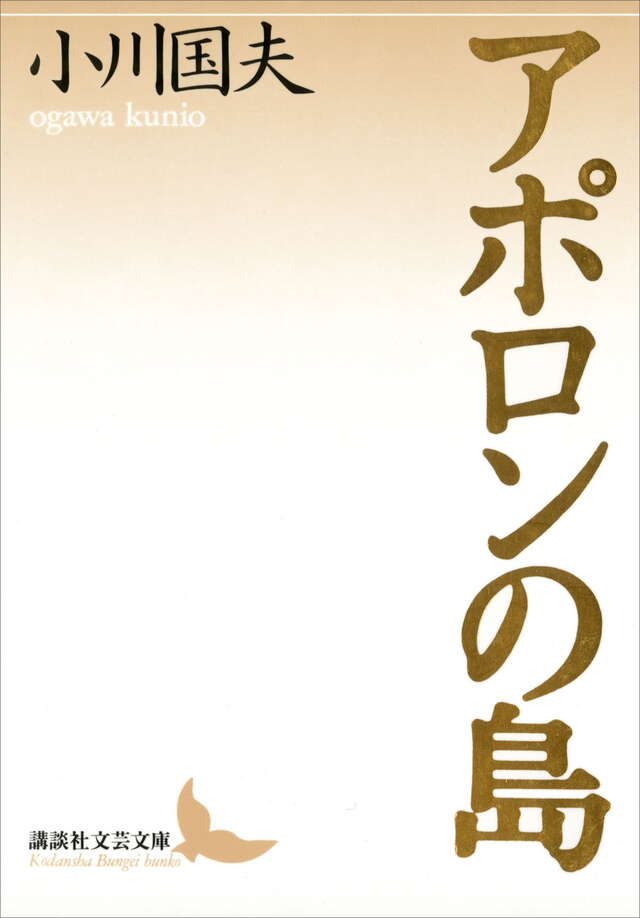
アポロンの島
講談社文芸文庫

新約聖書外典
講談社文芸文庫
「新約聖書外典」とは、現行の新約聖書の27の文書が正典として成立する過程において、「アポクリファ」として排除され、正典として採用されなかった諸文書をいう。古代におけるキリスト教大衆文学とグノーシス的異端文学の間に位置するこれらの文書は、当時の大衆によって、正典よりもむしろ好んで読まれ、しばしば古代・中世から近代に至る西欧の芸術作品のモチーフともなってきた。
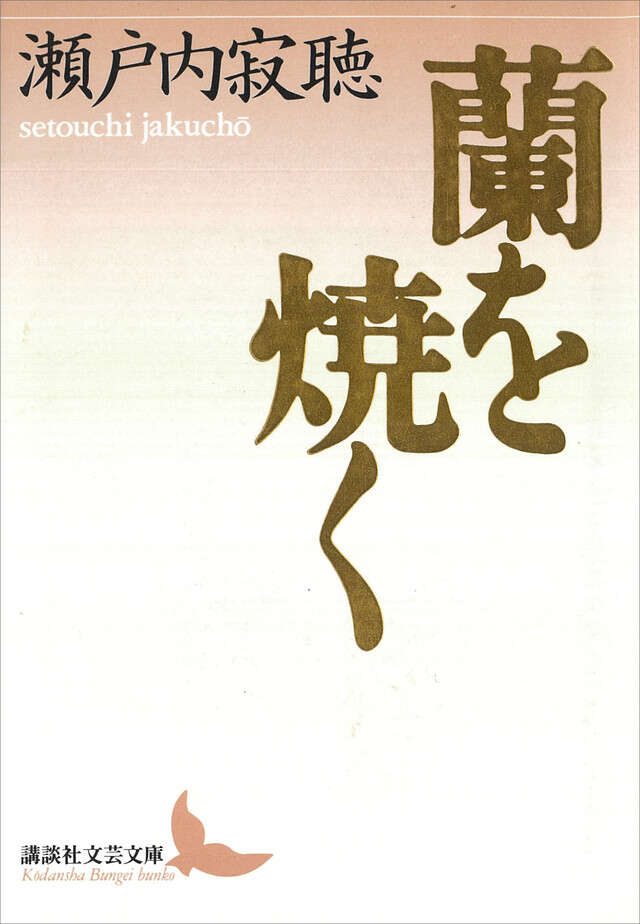
蘭を焼く
講談社文芸文庫
著者の50年に及ぶ文業のうちでも、第一の傑作短篇集ーー男女の関係性の善悪は、つねに社会の規範の中にあるが、ここに登場するヒロインたちは、もっとも女性的に生きることで、社会への反逆者となり、そこには満ちあふるるエロティシズムと頽廃とが生と死を越えて、抽象にまで至る愛のリアリティをもって存在する。表題作のほか「公園にて」「予兆」など、8篇を収録。
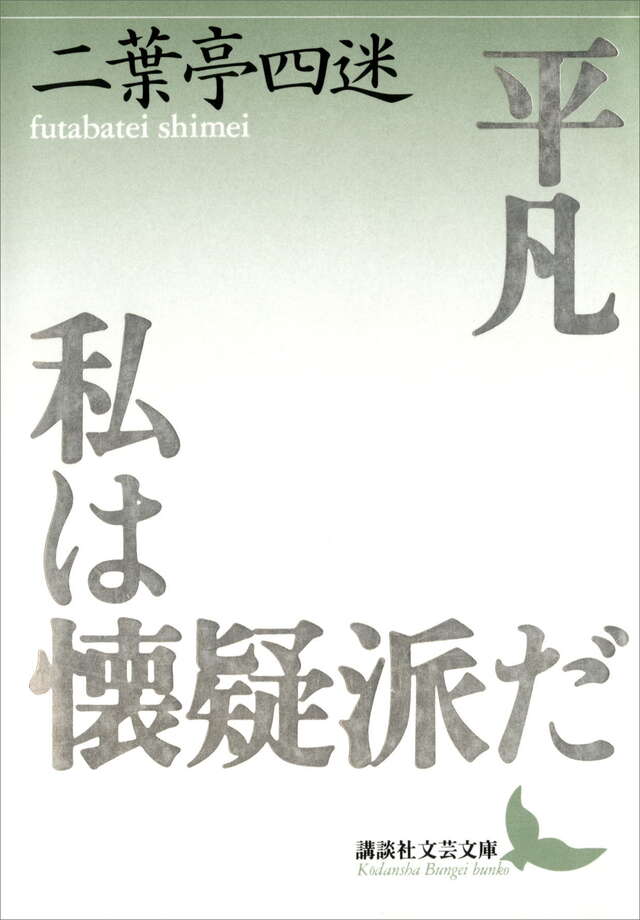
平凡・私は懐疑派だ
講談社文芸文庫
明治文学の黎明を告げる名作「浮雲」を執筆しながらも人生への懐疑より一時筆を断ち、晩年はロシヤに渡って、病に倒れ、帰途ベンガル湾洋上にて、45歳で客死。終生、、人間いかに生くべきかを自問し、明治の激動期を生き急いだ先覚者四迷の小説、翻訳、評論を1冊に集成。自伝体小説「平凡」、翻訳「あいびき」、「狂人日記」他、評論「私は懐疑派だ」「予が半生の懺悔」「遺言書」等収録。