講談社文芸文庫作品一覧

日本文壇史14 反自然主義の人たち
講談社文芸文庫
若い詩人達が新詩運動に熱中していた明治42年3月、近代詩を画す白秋『邪宗門』刊行。荷風『ふらんす物語』発禁。臨風、宙外ら反自然主義の文芸革新会発足。5月、ベンガル湾船中で二葉亭客死。7月、鴎外「ヰタ・セクスアリス」発表、月末に発禁。9月、露風、詩集『廃園』刊。10月、花袋は名作『田舎教師』刊行。鴎外等その立場を異とする人々の中からも自然主義文学の影響のもと香気溢れる文学作品続々誕生!

蕁麻の家
講談社文芸文庫
著名な詩人である洋之介の長女に生まれた嫩(ふたば)は、8歳の時母が男と去り、知能障害の妹と父の実家で、祖母の虐待を受けつつ成長した。家庭的不幸の“救いようのない陥穽”。親族は身心憔悴の「私」の除籍を死の床の父に迫る。『父・萩原朔太郎』で文壇的出発をした著者が、青春の日の孤独と挫折の暗部を凄絶な苦闘の果てに毅然と描き切った自伝的長篇小説、3部作の第1作。女流文学賞受賞。

空想家とシナリオ・汽車の罐焚き
講談社文芸文庫
「労働者が何かを要求することは天皇に叛逆することだ、という思想が強まろうとしてきた時代」に、中野重治は区役所の戸籍係の文学青年に自身の鬱屈した夢を託し、汽車の罐焚きの男に熱い想いを込めて創作をした。1932年、重治は治安維持法違反で逮捕拘禁された。弾圧の戦時下を真摯に生きて抵抗した小説家の時代を超えていま深まる感銘。中篇小説の秀作2篇。
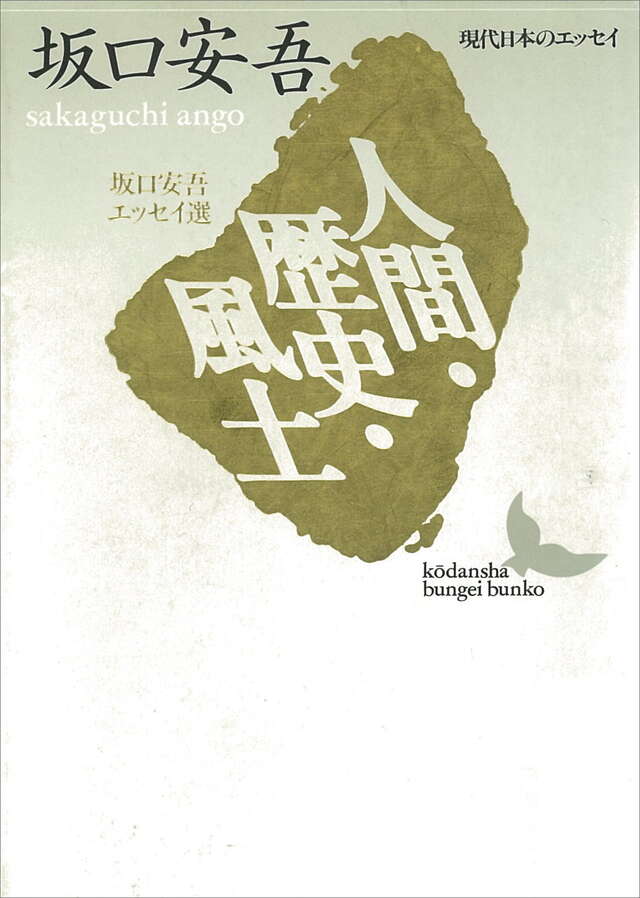
人間・歴史・風土
講談社文芸文庫
自然の風土の中で生きる人間をとおして作られるのが真実の歴史であるとする安吾独得の歴史観を背景に、自ら現地に足を運び、卓抜した洞察力を働かせてものした歴史紀行の中から「天草四郎」「安吾・伊勢神宮にゆく」「飛騨・高山の抹殺」など10篇を収録。司馬遼太郎の「街道をゆく」や松本清張の「古代探究」などの紀行文学のさきがけとなった画期的エッセイ。

妖・花食い姥
講談社文芸文庫
深い怒りと悲しみに培われて女の内部に居据わる〈業〉を凄絶に描いた「ひもじい月日」(女流文学者賞受賞)、『春雨物語』を踏まえた鬼気迫る傑作「二世の縁 拾遺」、夢幻と現実が見事に融合する「花食い姥」、ほかに「黝い紫陽花」「妖」「猫の草子」「川波抄」を収録。伝統的優美と豊かな知性が研きあげた隠微な官能、妖気を漂わせる特異の世界、円地文子傑作短篇集・7篇。

放浪時代・アパアトの女たちと僕と
講談社文芸文庫
昭和初期のモダニズム文学の旗手として一世を風靡しながら、突然文壇から消えた竜胆寺雄の代表作3篇。消費生活がアメリカ風に変化してゆく大都会の片隅でショーウインドーの飾り付けなどをしながら気儘に生きる若者たちを、淡いペーソスを交えて軽妙に描いた表題作、及び、文壇の派閥性を攻撃してその地位を失うきっかけとなった「M・子への遺書」を収録。

ものみな歌でおわる・爆裂弾記
講談社文芸文庫
『復興期の精神』の著者の代表的戯曲3篇を収録ーー虚実交錯する二元的批判構図を持ち、特異な発想と構想で、常に戦後文学に先鋭な問題を提起し続けた『復興期の精神』の著者・花田清輝の、代表的戯曲3篇。明治18年、自由民権運動を背景に、女壮士・新聞記者・講釈師・演歌師などを配して、その過激な運動の壊滅までの顛末を描いた諷刺喜劇「爆裂弾記」のほか、「ものみな歌でおわる」「首が飛んでも――眉間尺」を収録。

浅草紅団・浅草祭
講談社文芸文庫
昭和はじめの浅草を舞台にした川端康成の都市小説。不良集団「浅草紅団」の女首領・弓子に案内されつつ、“私”は浅草の路地に生きる人々の歓び哀感を探訪する。カジノ・フォウリイの出し物と踊子達。浮浪者と娼婦。関東大震災以降の変貌する都会風俗と、昭和恐慌の影さす終末的な不安と喧騒の世情をルポタージュ風に描出した昭和モダニズム文学の名篇。続篇「浅草祭」併録。

日本文壇史13頽唐派の人たち
講談社文芸文庫
青春を謳歌する吉井勇、白秋らとの交遊の一方、生活面全てを金田一京助らの友情で過す啄木は挫折と焦燥に襲われた。その明治41年7月欧米のデカダンスに耽けた荷風帰国、8月『あめりか物語』刊。9月、漱石『三四郎』連載。11月、「明星」終刊。12月パンの会発足。42年1月新浪漫派の一拠点「スバル」創刊、鴎外、白秋、啄木、敏、光太郎ら参加。自然主義最盛期に多彩な個性の萌芽と躍動の源を読む。
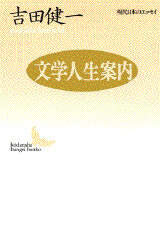
文学人生案内
講談社文芸文庫
「暗夜行路」「雪国」など日本の名作7篇、および「赤と黒」「罪と罰」「チャタレイ夫人の恋人」などヨーロッパの名作9篇を取りあげて、文学の本質である「詩と真実」は、俗世間の道徳や知恵を超越しながらも、同時にそれらの源泉ともなっている消息を、独特の語り口で明らかにする。

世阿弥
講談社文芸文庫
役者・作者・演出家・批評家をも兼ね、利休、芭蕉に比すべき、天才世阿弥が残した16部集の“言葉の真実の価値”と“秘伝”の意味を、「花伝書」「花の発見」「初心について」「幽玄について」「仮面の芸術」「序破急」等々で心新たに語る。著者の古典文学の素養と幼少から親しんだ能の舞台体験が、世阿弥が語りかける無言の表現・豊潤の世界を、幾世紀の刻を超えて、現代人に鮮やかに説き明かす。

角帯兵児帯・わが半生記
講談社文芸文庫
長い文学的不遇をさか手にとり、さりげない日常の世界に、暖かく優しい眼をふりそそぎ続けた、木山捷平の飄飄人生。けちくさい世間の眼や、つまらぬ栄誉から離れた自由世界。小動物や生き物、草花や木、身辺な物から見出す美事な詩。天衣無縫で無防備で、いつも傍にいてくれる“日本の親爺”、木山捷平の、主として晩年に書かれた秀逸なエッセイ集。

オレゴン夢十夜
講談社文芸文庫
小説家の日記には素顔の魅力が覗くと言う。『オレゴン夢十夜』は、一見、日本文学を講ずる為にオレゴン州に滞在した“私”の日記という形を装う。滞在中の瑣事を書き、あらゆる感懐を述べながら、これまでの外国体験が物語られて時に夢とうつつが交錯し、そして幼時、両親、先祖への懐古へと遡ってゆく。小説家、詩人大庭みな子の底深い精神の原風景の幻。
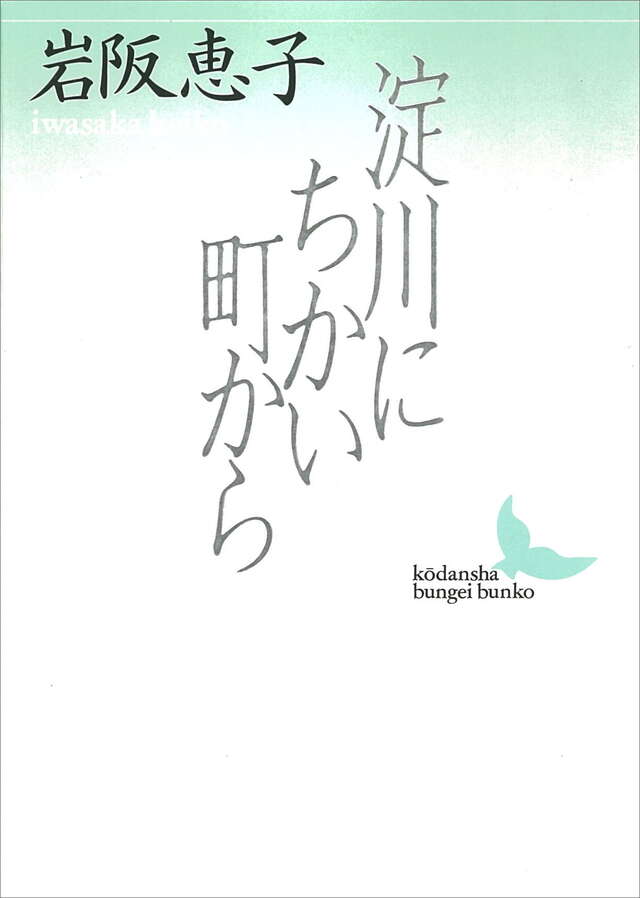
淀川にちかい町から
講談社文芸文庫
清冽な抒情と透明な詩心を持つ新進女流詩人として出発。昭和61年『ミモザの林を』で野間文芸新人賞、次いで平成4年評伝『画家小出楢重の肖像』で平林たい子賞受賞。人生の機微を深く鮮やかに彫り彩る独自の散文世界を構築、『淀川にちかい町から』で芸術選奨・紫式部文学賞両賞受賞。こころ暖かく、こころ鎮まる、爽やかな散文の小説世界。

日本文壇史12 自然主義の最盛期
講談社文芸文庫
鴎外が観潮楼歌会を開いた翌年明治41年、1月白秋ら7人が脱退し「明星」は衰退。4月、文壇注目の渾身の力作花袋『生』、藤村『春』の新聞連載開始。花袋らが病床の独歩に贈った『二十八人集』が文壇の主流・自然主義の宣言書となる。啄木が3年振りに北海道から上京。6月、独歩死す。二葉亭宿願のロシアへ向う。漱石、宙外、白鳥、眉山、長江、青果、抱月等々と新文壇の流れに日本近代文学の特性を読む!
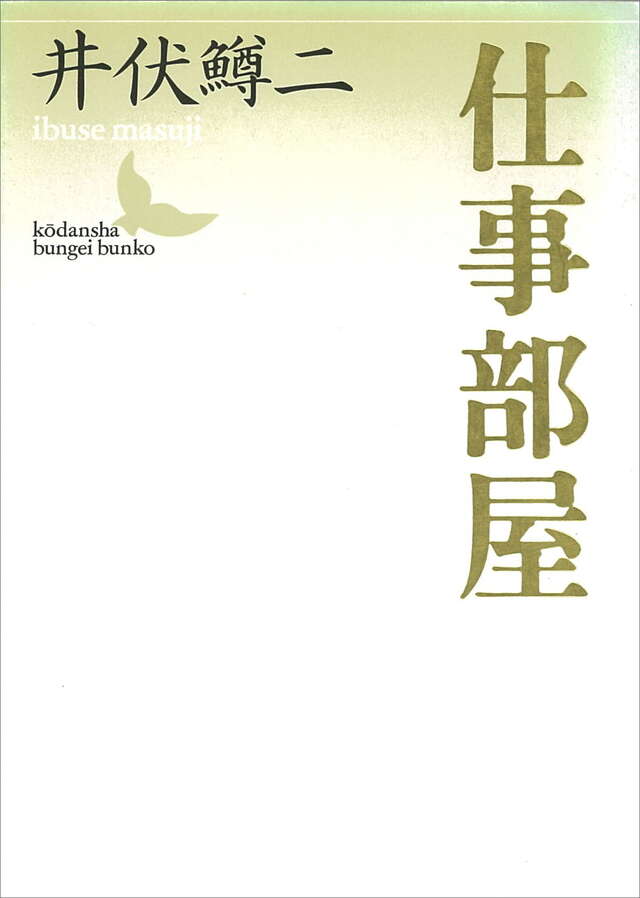
仕事部屋
講談社文芸文庫
《芸術の友よ。御身に捧ぐるに今この美しい言葉の花束を以てする。是こそ新興芸術派の巨匠・井伏鱒二の心の贈物である》(春陽堂、昭和6年刊『仕事部屋』広告文)。全集等未収録の幻の名作というべき「仕事部屋」を始め、「丹下氏邸」他初刊本の全14篇をそのままに収録。昭和初年代のモダニズム、都市小説の新風俗が描かれて、井伏鱒二の文学に新たな光を当てる真の芸術の友への贈物。

常陸坊海尊・かさぶた式部考
講談社文芸文庫
海尊と名乗る法師が村々を懺悔し流浪するという東北の貴人伝説を背景に、学童疎開し孤児となった啓太の罪の生涯を描く田村俊子賞、芸術祭賞受賞「常陸坊海尊」、和泉式部に纒る伝説を題材に、九州の炭坑事故で冒された豊市、その母と嫁に、式部の後裔という魔性の尼僧を絡め社会の底辺に生きる人々の深い哀しみを描く毎日芸術賞受賞「かさぶた式部考」、方言を駆使し民衆の苦悩に迫る戯曲2篇。
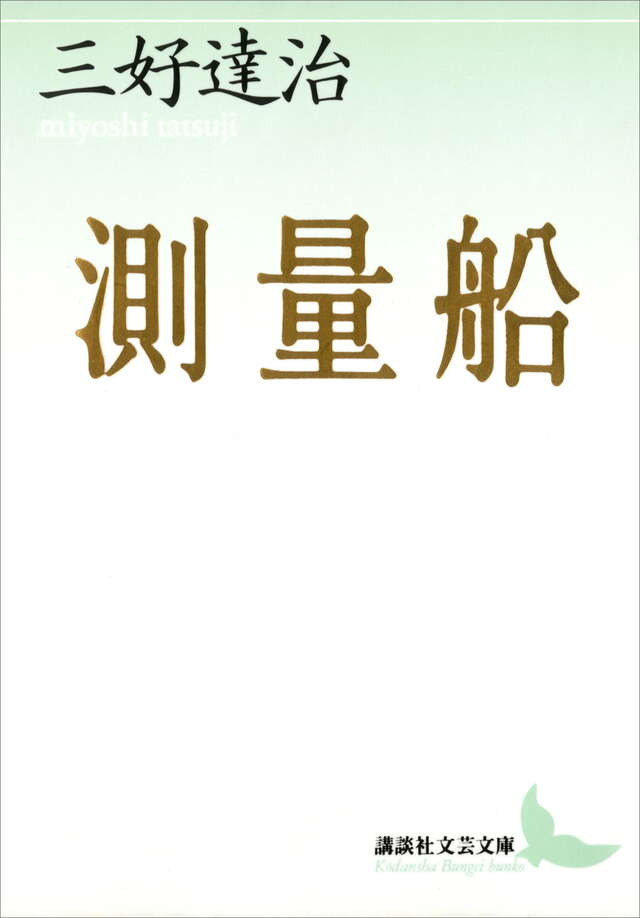
測量船
講談社文芸文庫
太郎を眠らせ、太郎の屋根に雪ふりつむ。次郎を眠らせ、次郎の屋根に雪ふりつむ。無限のイメージを喚起するわずか二行の詩「雪」他を収録の第1詩集『測量船』。「乳母車」「甃のうえ」「鳥語」「獅子」等、日本古典の詩風と西欧象徴詩風が混然と融合し、魅了する全92篇(「測量船拾遺」を含む)。新詩の可能性を追究する若き詩人・達治が“現代抒情詩”を展開させた画期的詩集。

蛇淫
講談社文芸文庫
重い血の記憶がよどむ南紀の風土のなかで原始的な本性に衝き動かされるままに荒々しい生をいとなむ男の姿を、緊迫感溢れる文体で描く短篇集。若い女との気ままで怠惰な生活をなじられ、衝動的に両親を殺すに至る表題作の他、「荒くれ」「水の家」「路地」「雲山」「荒神」の6篇を収録。

下駄にふる雨・月桂樹・赤い靴下
講談社文芸文庫
父が果たせなかった文学の道を、子・木山捷平もまた、志した。世に容れられぬ苦節の日々、あろうことか、捷平は敗戦直前の満州へ渡った。1年が100年に値するような辛酸の日々。故郷笠岡へ痩せさらばえて帰り、貧乏・不幸何でもやって来いの覚悟がすわる。そして、暖かな人生声援の文学が始まる。市井人として生涯を貫いた文士・木山捷平晩年の短篇秀作。