講談社学術文庫作品一覧

森のバロック
講談社学術文庫
生物学・民俗学から神話・宗教学に精通、あらゆる不思議に挑んだ南方熊楠。那智の森の中に、粘菌の生態の奥に、直観された「流れるもの」とは何か。自然や人間精神の研究の末織り上げられた南方マンダラの可能性とは?後継者のいない南方熊楠の思想、「旧石器的」な思考の中に、著者は未来の怪物的な子供を見出す。対称性理論への出発点となった記念碑的著作。
南方熊楠から取り出す 思想の新しい子供
「対称性」理論への出発点
生物学・民俗学から神話・宗教学に精通、あらゆる
不思議に挑んだ南方熊楠。那智の森の中に、粘菌の生態の奥に、直観された「流れるもの」とは何か。自然や人間精神の研究の末織り上げられた南方マンダラの
可能性とは?後継者のいない南方熊楠の思想、「旧石
器的」な思考の中に、著者は未来の怪物的な子供を
見出す。対称性理論への出発点となった記念碑的著作。

日本後紀(中)
講談社学術文庫
勅撰の正史、「六国史」の第三
初の現代語訳(付・原文)
『日本後紀』は平安時代初期の歴史を扱った国史であり、朝廷中枢の重要な出来事を網羅した貴重な史料でもある。全巻のうち10巻のみが現存、散佚した部分の修復補完が江戸時代から多くの学者の手により試みられてきた。本書では、『類聚国史』『日本紀略』等から集めた逸文を加えて復元された全40巻に、初めて現代語訳を施す。歴史の曲がり角、平安初期の様子が間近に蘇ってくる。
『日本後紀』は古代国家が編纂した六国史の1つで、桓武朝の後半から平城・嵯峨・淳和朝に至る4代、年号で言えば延暦11年から天長10年に至る40年余の歴史を記述している。都が「咲く花の匂ふがごとく」と栄華を謳歌した奈良京から長岡京へ遷り、それも束の間、平安京への遷都が行われ1000年の都城建設がすすめられる一方で、律令国家は大きな曲がり角を迎え、政治改革が模索される時代であった。――<本書上巻「まえがき」より>

おかあさんになったアイ
講談社学術文庫
アイとアユムの最新情報を加筆
チンパンジーの育児、教育、文化
漢字や数字を理解するチンパンジーとして名高いアイ。彼女が息子アユムを産んで6年が経過した。はたして子育ては順調に進んだのか。また、親が獲得した知識や技能は、世代を超えて息子に伝えられるのか。アイ母子を軸に、野生下における観察・研究をも踏まえ、チンパンジーの親子関係、教育、文化の諸相を探る。「その後のアユム」最新情報を加筆。
ゲノムの外側にある文化的な蓄積を親の世代から子の世代へ伝えるのは、人間だけかというと、そうではありません。……人間だけではなくて、チンパンジーもある程度そうだということがわかってきました。……「進化の隣人」と呼べるチンパンジーで、いま述べたような知識や技術の獲得と世代を超えた伝播というのは、どういうふうになっているのでしょうか。それが、この本を通じてのテーマになると思います。――<本書「はじめに」より>

主君「押込」の構造
講談社学術文庫
近世大名家の君臣秩序と御家
悪主・暴君に対抗する強制的隠居という実力行使
「御身持宜しからず御慎しみあるべし」――主君の悪政・不行跡に対して家臣団が執る最後の手段「押込(おしこめ)」。君臣間の上下秩序が絶対の近世武家社会において、遊蕩・大酒あるいは専制に走る主君は、家臣にとって憂慮すべき存在であった。御家の永遠性への忠義からなされる主君強制隠居の内談、実行、幕府側の処置の論理など、主君廃立の隠された慣行を明らかにする。
それは家老・重臣たちが主君を幽閉し、強制的に隠居――廃位させる行為である。それ故にこれはまた「押込隠居」とも呼ばれていた。(中略)主君「押込」は家臣団の手で、主君を強制的に隠居させるものであるから、その本性において主君廃立行為としての性格をもち、近世の国制を考察するにはやはり避けて通れぬ問題である。――<「はしがき」より>

日本後紀(上)
講談社学術文庫
『日本書紀』『続日本紀』に次ぐ勅撰史書 待望の現代語訳
六国史は漢文編年体で書かれた勅撰の正史である。
『日本書紀』『続日本紀』に続く『日本後紀』では、延暦11年から天長10年の40年余が扱われ、平安時代初期、歴史の変革期の面白さが描かれる。残存する10巻分に逸文を加え、復元された原文に、分かりやすい現代語訳を施し、懇切な注を付す。本書は日本歴史の貴重な文献が身近に読める待望の書である。

紫禁城の栄光
講談社学術文庫
偉容を誇る中華皇帝の王城=紫禁城は、モンゴル人が建設し、満洲人が遺したものである。遊牧帝国と農耕帝国の合体が生み出した巨大な多民族国家・中国。漢人たちが漢文化を育んだ2大河の流域「シナ」は、満洲・モンゴル・チベット・新疆の周辺をどのように統一したのか?14世紀後半の元の北帰と明の興起から、清の落日が始まる19世紀初頭まで、アジア激動の450年を描く。
14世紀後半から19世紀初頭、アジア大編成時代を描く
「農耕帝国」と「遊牧帝国」が融合して、多民族・巨大国家「中国」が誕生した
偉容を誇る中華皇帝の王城=紫禁城は、モンゴル人が建設し、満洲人が遺したものである。遊牧帝国と農耕帝国の合体が生み出した巨大な多民族国家・中国。漢人たちが漢文化を育んだ2大河の流域「シナ」は、満洲・モンゴル・チベット・新疆の周辺をどのように統一したのか?14世紀後半の元の北帰と明の興起から、清の落日が始まる19世紀初頭まで、アジア激動の450年を描く。
数多ある類書の中で際立つ本書の特徴は、その視点・論理の明晰さと独創性とにある。本書の基本的視座は、漢人が主に住まい漢文化を育んできた「シナ」と、それとは別の歩みをたどってきた満洲・モンゴル・チベット・新疆をも包含する「中国」とを自覚的に区別し、この時代の歴史を「シナから中国へ」の展開として捉えるという、ユニークかつ核心を衝いたものである。このために、シナ史中心の類書とは一線を劃する一方、独立した民族史・地域史としてのモンゴル史・チベット史などとも異なって、これらを1つに融合した脈絡ある歴史として叙述することに成功している。――<「学術文庫版まえがき」より>

出雲神話の誕生
講談社学術文庫
記紀と『風土記』の記述の相違
神話に隠された秘密を明かす
記紀神話の3分の1以上を占める出雲神話。しかしその出典たる『出雲国風土記』には、記紀とは異なる舞台、神々の美しく雄大な詩が綴られていた。それらを抹殺し、出雲国を強大な国であるかのように仕立てあげた大和朝廷の策略とは、どのようなものだったのか。国引き説話や大神の麗しい物語が、支配者によってねじまげられ、被支配者たちに受け入れられていく過程を解き明かす。
出雲の弱小国がどういう理由で神代巻の3分の1も占めるとともに、それに基づいて起こった錯覚によって、1000年もの長い間、大和朝廷に対立する強大な出雲国を、われわれに想像させてきたのであろうか。まず読者のすべての方に申したいが、これまでの出雲観のすべてを完全に拭い去って、白紙の立場で新しく出雲を見直す心がまえを持っていただきたいと思う。――<本書より>

みちの辺の花
講談社学術文庫
カラー版 花への恋情あふれる画文集
春、夏、秋、冬、日本の四季のうつろいを彩る花々、
みちの辺でふと出会う野の花、山の花。蕗の薹(ふきのとう)、蛍袋、藤袴、吾亦紅(われもこう)など可憐に咲く草の花。山茱萸(さんしゅゆ)、梅花空木(ばいかうつぎ)、黒芽柳など野趣に富む木の花。季ごとに届けられる花を美しい色彩で詩情豊かに描き、また、愛する花へのあふれる思いを綿々と綴ってゆく。身近で秘やかに咲く花への恋情こもる画文集。
山野の路傍にこの花を見つけて、「しばらく」と声をかけても、しょんぼりうつむいてだまっている。思いのほか無愛想だから、長く立ちどまって見とれるほど気を惹かない。名のおかげで、ずいぶん得をしている。一抹の幼ごころをよみがえらせ、ほんの一時にせよ、人をいわば詩人に変える魔法が、ほたるぶくろという呼び名にはひそんでいる。――<本書「蛍袋」より>

善の研究
講談社学術文庫
日本最初の本格的な哲学書『善の研究』。深い思索とたゆまぬ探究心、西洋思想との厳しい対決。西田幾多郎は、人間の意識を深く掘り下げ、心の最深部にある真実の心は何かを探究し続けた。本書では、難解な本文を平易に噛み砕きやさしく読み解き、詳細で懇切な注釈と的確な解説を施し、論旨を纏め示す。2編の補論も収載、西田の代表作理解のための最善の書。(講談社学術文庫)
丁寧な注釈と的確な解説
日本哲学の名著を読む
日本最初の本格的な哲学書『善の研究』。深い思索とたゆまぬ探究心、西洋思想との厳しい対決。西田幾多郎は、人間の意識を深く掘り下げ、心の最深部にある真実の心は何かを探究し続けた。本書では、難解な本文を平易に噛み砕きやさしく読み解き、詳細で懇切な注釈と的確な解説を施し、論旨を纏め示す。2編の補論も収載、西田の代表作理解のための最善の書。
本書は、西田幾多郎の代表作『善の研究』に注釈と解説を試みたものである。『善の研究』で用いられている難解な哲学用語をわかりやすく説明し、本文中に引用されている哲学者の思想やその著作を簡明に解説した。また、意味のとりにくい難解な文章をできるだけ平易に、くだいた形で表現し直し、各章ごとに、その全体の論旨をまとめ、それと同時に、個々の主張の背後にある根本の精神を明らかにするよう努めた。――<本書「まえがき」より>

十二世紀ルネサンス
講談社学術文庫
中世の真っ只中、閉ざされた一文化圏であったヨーロッパが、突如として「離陸」を開始する12世紀。東方からシチリアへ、イベリア半島へ、ギリシア・アラビアの学術がもたらされる。ユークリッド、プトレマイオス、アル=フワーリズミーなどが次々とラテン訳され、飛躍的に充実する西欧の知的基盤。先進的アラビアとの遭遇が生んだ一大転換期を読む。
アラビア世界から西欧へ
中世の眠りを覚ます 創造的文明移転の時代
中世の真っ只中、閉ざされた一文化圏であったヨーロッパが、突如として「離陸」を開始する12世紀。東方からシチリアへ、イベリア半島へ、ギリシア・アラビアの学術がもたらされる。ユークリッド、プトレマイオス、アル=フワーリズミーなどが次々とラテン訳され、飛躍的に充実する西欧の知的基盤。先進的アラビアとの遭遇が生んだ一大転換期を読む。

民藝とは何か
講談社学術文庫
「民藝」とは、民衆が日常に使う工藝品である。民家、民具、民画を総称して「民藝」と呼ぶ。「民藝品たること」と「美しく作りたること」には、固い結縁があり、質素こそが慕わしい徳である。このように清貧の美を説いた筆者の理念とは? 昭和の初頭に創始され、現在にまで受けつがれる「民藝運動」の精髄を知るための格好の入門書。(講談社学術文庫)
民家、民具、民画、民器……
日常生活の中にある「下手(げて)の美」の発見
「民藝」とは、民衆が日常に使う工藝品である。民家、民具、民画を総称して「民藝」と呼ぶ。「民藝品たること」と「美しく作りたること」には、固い結縁があり、質素こそが慕わしい徳である。このように清貧の美を説いた筆者の理念とは?昭和の初頭に創始され、現在にまで受けつがれる「民藝運動」の精髄を知るための格好の入門書。
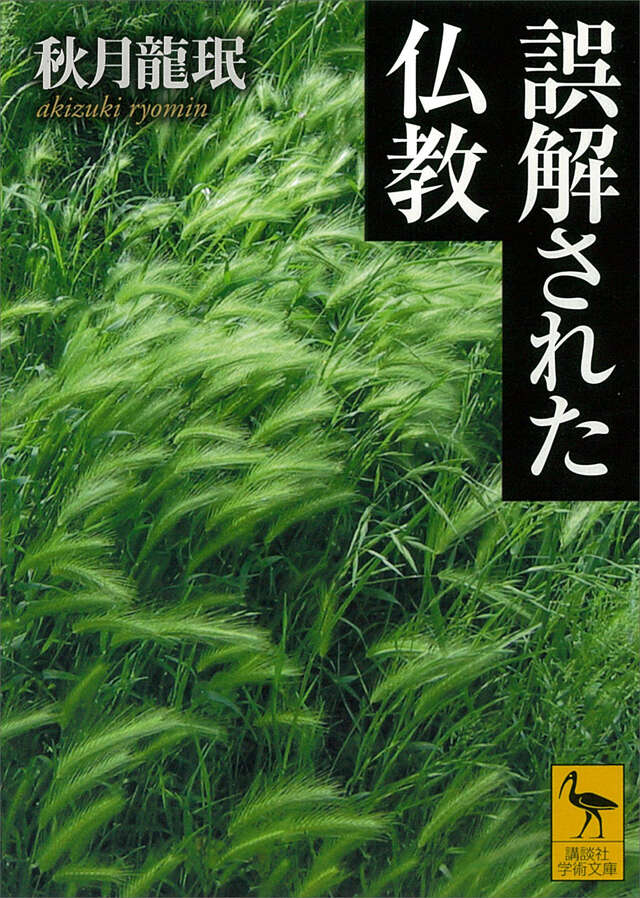
誤解された仏教
講談社学術文庫
インドに発した仏教は、長い時間をかけてわが国へと到達したが、伝播の道筋で土着の思想と習合し、本来の思想から大きく変容した。この結果、「死者儀礼」「死者に対する〈仏〉という呼称」「霊魂の存在」など、現代に通じる誤った仏教理解が生じる。こうした誤解に塗れた日本人の仏教観を叱り、「仏教=無神論・無霊魂論」の主張を軸に、正伝の仏法を説く。(講談社学術文庫)
死者を仏と呼んではならぬ! 霊魂は無い! 霊魂や輪廻転生、神、死者儀礼等をめぐる問題を軸に、日本人の仏教に対する様々な誤解を龍ミン師が喝破。仏教についての正しい理解のあり方を説いた刺激的論考。

後白河法皇
講談社学術文庫
彼は〈日本一の大天狗〉だったのか?
中世胎動期に屹立する政治的巨人が透視したもの
源頼朝に対抗し、守旧勢力を巧妙に操った老獪な〈大天狗〉。はたまた『梁塵秘抄』を編纂した粋狂な男。後白河がいなければ、天皇制は存続しなかったかもしれない。古代王権を中世王権へと再生させるために、法皇は何を考えていたのか? 王権の機能を再編成し、文化情報の収集・独占と操作の意味を透視した天才の精神に迫る。

脳と人間
講談社学術文庫
現実に「躓く」とは?「ズレ」とは?
精神科医が明らかにする 分裂病と脳の活動の関係
世界・現実との関係において躓き、ズレていく統合失調症=精神分裂病。「今」と「今から」を意図することの困難、身近な事物がもつ意味の突如たる凶変はなぜ起こるのか。脳の働きのどのような不具合が関係しているのか。精神科医療の最前線に立ち膨大なエビデンスを有する著者が、脳科学の最新の成果を動員して練り上げた、脳と精神に関する総合理論。

中世ヨーロッパの都市の生活
講談社学術文庫
賑わうシャンパーニュの大市
今も変わらぬ主婦の生活
1250年、トロワを描く
中世、城壁が築かれ、都市があちこちで誕生した。
異民族の侵寇や農業・商業の発達はそれに拍車をかけた。1250年、シャンパーニュ伯領の中心都市、トロワ。そこに住む人々はどのような生活を送っていたのか。主婦や子供たちの1日、結婚や葬儀、教会や学校の役割、医療や市(いち)の様子などを豊富なエピソードを盛り込み描く。活気に満ち繁栄した中世都市の実像が生き生きと蘇る。
西ヨーロッパにおいて、現在へとつながる都市が成立したのは、中世のことである。1250年には、古代から栄えた地中海沿岸地域だけでなく、北西ヨーロッパにおいても都市は活気に満ち、繁栄していた。本書では、この時期に新たに花開いた都市の一つであるトロワを選び、13世紀の折り返し点、1250年におけるトロワの人々の生活を追ってみようと思う。――<本書「プロローグ」より>

麺の文化史
講談社学術文庫
そば、うどん、ラーメン、スパゲッティ…
広範な実地調査の成果をもとに問う 麺の起源とその伝播
そば、うどん、冷麺、ラーメン、スパゲッティ……。これらに当代の即席麺まで加えれば、今や麺文化は世界を覆っているといっても過言ではない。そもそも麺とはいったい何か。麺はいつ頃、どこに生まれ、どのように波及したのか。厖大な文献を渉猟するとともに、精力的に積み重ねた広範なフィールドワークの成果をもとに綴る、世界で初の「文化麺類学」。

太閤の手紙
講談社学術文庫
道義を好み不義を憎み、仲間と敵を愛し、
親孝行で子煩悩、女好きな恐妻家――
日本人に最も愛された英雄の素顔
数多の「太閤記」が振りまいた誇大と虚妄に満ちた英雄伝説の数々。しかるに、本当の秀吉はいかなる男だったのか? 喜・怒・哀・楽が発露する手紙。読めば読むほど面白い信書を、丹念に読み味わおう。「つゆとおちつゆときえにしわがみかな難波の事もゆめの又ゆめ」と辞世を詠んだ英雄の生きざまと本心が、まざまざとよみがえる。
秀頼事、成りたち候やうに、此の書付の衆として、たのみ申し候。なに事も、此のほかには、おもひのこす事なく候。
ここに掲げた末期の文は(中略)、「秀頼事、たのみ申し候。」の連発で、「なごりおしく候。」と結んでいるところなど、(中略)英雄の最期の言葉とは、どうしても思えない。忍び泣く女性の繰りごとにも似ている。鳥のまさに死なんとするや、その声よし…という古語があるが、これが人間太閤の本音であったと、私は思うのである。――<本書「19 末期の文」より>

金属と日本人の歴史
講談社学術文庫
草薙剣、奈良の大仏、日本刀、火縄銃――
人は金属器を造り 金属器は歴史を創った
人間と金属が織りなす壮大なロマン。西洋に例のない独特の音色をもつ梵鐘はどのように生まれたか。完成まで28年を要した奈良の大仏はどうやって作られたか。鋭さと美をあわせもつ日本刀の秘密、また時代を変えた火縄銃、その兵器革命はいかに展開したか――。歴史を創った日本人と冶金技術の興味深い関係を、金属学の泰斗が平易な文章で綴る。

ウィーン物語
講談社学術文庫
ハプスブルク家の支配のもと、血と力で600年の長きにわたり政治・経済・文化の要として欧州に君臨した、神聖ローマ帝国の都ウィーン。その都市と文化の調和はパリを羨望させた。芸術や学問にモーツァルト、クリムト、フロイト等々、数多の巨星を生んだウィーン文化の真髄を、聖堂、美術館、環状道路、カフェ、家具など都市空間に潜む感性に探る。

続・絵で見る幕末日本
講談社学術文庫
<好評続編> 異国人の目から見た 幕末の江戸の町とその生活
該博な知識、卓越した識見、犀利な慧眼。また人間味も豊かなスイス人の目に、日本はどのように映ったか。風雲急、激動する世情の中、日本の実情をつぶさに観察。大君の居城、正月や節句の行事、浅草の祭りや市など、江戸の町とその生活を見たままありのままに描写する。日本調査研究の記事も盛り込む興味深い幕末見聞録。味わい深い挿画を多数収録、日本翻訳文化賞受賞作品。
アンベールは余暇あるごとに日本の実情を調べ、歴史、地理、宗教、社会制度、政治機構、風俗習慣等を観察し、文筆の才のある彼は「世界一周」誌に、「日本」と題する記事を掲げたが、これよりいっそう精密な見聞記を書いた。これが本書である。筆を長崎入港に起こしているが、単なる旅行記ではなく、むしろ、アンベールの日本研究及び観察の成果というべきもので、雑然とした記述がかえって興味ある読み物となっている。――<本書「訳者のことば」より>