講談社現代新書作品一覧
映画の創造
講談社現代新書
現場の名人たちの情熱と技を生き生きと描くシナリオ決定から試写まで,美術,照明,撮影,スチ-ル,ネガ編集等,多くのプロが全力をそそぐ.光と影の総合芸術の創造現場の熱気と肉声を伝えるレポ-ト.
読むことからの出発
講談社現代新書

リーダーシップの心理学
講談社現代新書
個人を生かし組織を活性化するリーダーのあり方とは?集団目標達成のためにメンバーの調和を図りながら能力発揮をうながすのが、リーダーの役割である。円滑な機能と目的遂行のためには、決断力と強さが、和のためには、全体を見わたすことのできる冷静な眼が、個々人への心くばりのためには、やさしさが要求される。目標の設定から役割分担、メンバーの興味や感情への配慮、指示のし方、意見のきき方など具体的着眼点を示しつつ、豊かなコミュニケーションと開かれた人間関係にもとづいた柔軟で効果的なリーダーシップのスタイルを考察する。
ひとつの世界をつくる――リーダーシップを発揮するとは、自・他一体感の回復ということになろうかと思う。多分今までに偉大なリーダーといわれた人たちは、無我無心で「グループが自分、自分がグループ」という境地を味わっていたのではないかと思う。そうなるためには、自分を空しくして相手の世界に入り、自分と相手がひとつの世界をつくることである。リーダーシップとは、けっして相手を意のままに動かす技法ではない。いうなれば、グループ全員がひとつの世界をつくるための技法といったほうがよい。あるいは、相互に自己拡大しあう技法といってもよい。――本書より

「知」のソフトウェア
講談社現代新書
●雑念を捨て去り、ひたすら精神を集中せよ。
●読む価値のないものは読むな。
●無意識の巨大な潜在能力を活用せよ。
●ことさらにレトリックを弄するな。
●オリジナル情報にできるだけ近づけ……。
新聞・雑誌・書物から個人や組織にいたるまで、多様なメディアが発信する膨大な情報を、いかに収集・整理・活用するか。情報の真偽を吟味・加工し、ゆたかな知的生産を行うには、何が必要か。ジャーナリズムの最前線で活躍をつづける著者が、体験から編みだした考え方と技法の数々を公開する。
情報の意味を読む。──コンピュータは自分が処理する情報の意味を知っている必要はない。インプットされた情報を数値化し、それを与えられた演算法則に従って計算し、その結果をアウトプットする。インプットされる情報とアウトプットされる情報の意味は、人間が解読するが、両者の間のプロセスは、意味抜きの演算である。それに対して、人間という情報系では、情報は常に意味付きでなければならない。人間の思考は意味と切り離すことができない。従って、インプット能力は、目や耳の生理的情報受容能力以上に、情報の意味を理解していく能力に左右されることになる。──本書より

天才
講談社現代新書
〈天才〉はなぜ私たちをひきつけるのだろう?モーツァルト、ダ・ヴィンチ、ニュートン、アインシュタイン、空海、ゲーテ、ヘルダーリン、賢治、カフカ――。だれでも一度は、その豊かですばらしい世界にしたしみ、よろこびと活力を与えられたにちがいない。そこには、なにか神秘的で謎めいた狂気もあり、凡人には近づきがたい魅力とおそれをも感じさせる。本書は、彼らの創造の秘密をさぐり、生まれた環境や背景まで、考察をすすめた天才の精神分析である。天才には、生まれながら早熟な知性や語学能力を示した人も多いが、晩塾型の人も数多い。もしかするとあなたも天才になれるかもしれない。
天才への道――夢や躁状態など、異常な状態に対する天才たちの態度を見ていると、自分のうえに起こったこと、眼の前にあらわれた事象に対して、ひじょうに素直に心を開き、身を委ねて、自然であることがわかる。いままで見知らなかったもの――夢や狂気や幻想――をも、自分の一部として受容し、自己の領域を広く豊かにしてゆくことが、天才と狂気の別れ道である。このような柔軟で自然な態度が、未知の領域から、より多くの贈り物を受けとるのに適切な態度であることはいうまでもない。しかもこれは、躁うつ圏ないし、日本の天才たちに特徴的ともいえる態度である。これに対して、西欧の天才たち、とくに分裂病圏の作家たちは、病的体験や世界に対して対決的な態度をとり、自我と異質なものと自我とのあいだの緊張・葛藤が創造の動因となることが多いように見える。このばあいには、自我の柔軟性というよりは、自己主張の強さ・激しさが天才の条件となるであろう。天才への道は、一つではない。――本文より
現代米語慣用句コーパス辞典
講談社現代新書
核戦略ゲーム
講談社現代新書

集団の心理学
講談社現代新書
集団を円滑に機能させ、積極的に関わっていくために……肩書きで仕事をするな。自分の能力と地位・役割を混同してはいないか。無駄話や挨拶がコミュニケーションを豊かにする。とにかく声を出せ。異端者になるな。どんな立派な正論を吐こうと、無視され、相手にされなくなる。人は、なぜ群れ、そのなかでどう行動するのか。本書は、集団のまとまりから、お互いの同調・非同調、リーダーシップの条件まで、集団行動のダイナミズムを解剖し、集団に溶けこみつつ、個性的に生きる道を提示する。
たった一人の反乱――異端者のレッテルをいちど貼られてしまうと、どんなに正確を吐こうが、それは無視される。多数が正義なのである。異端者は変わり者としてあつかわれ、多数者はもはや相手にしなくなる。流れは低きにつくとよくいうけれど、仕事をなまけてもさぼっても、自分に実害がないとなれば、そしてそういう仲間の多いところでは、いきおいそれが大勢を占めていくことになるだろう。よほどおおがかりな配置転換でもして、職場の雰囲気を変えていかなければならない。たぶん、「たった一人の反乱」ではどうにもならないだろう。――本書より

性格分析
講談社現代新書
神経質な人は、きちょうめんで思慮深いが、小心で苦労性、くよくよ考えこみがちである。いわゆる外向的な人は、明朗活発で行動力にあふれているが、短慮軽率とも評される。性格は一面的にとらえることはできない。態度や行動からレッテルをはるだけでなくその人らしさを形づくっている、内なる心のはたらきを把握しなければならない。自己愛傾向、強迫傾向、自閉傾向、パラノイド傾向など、他者理解と自己分析の手がかりを、臨床例をもとに幼児体験、母子関係の深層まで踏みこんで解き明かし、自分への違和感や悩み、挫折こそが自己理解と内面の成長をうながし、信頼と愛の人間関係をもたらす契機であると説く。
心のバランス――挫折や失敗や症状や問題行動というものが、人間の内的成長の節目、節目に現われてくることから、こうした事柄は、人間がその人本来のあり方からはずれた内的な状態、いってみれば「自己疎外」の状態から真の自己を回復しようとする無意識の作用ですらないかと思われてくる。人間の心は深いところでも、バランスや調和を保とうとする機能をもっているのではなかろうか。であるから、とんでもないことをしでかしたり、症状や問題行動などでみずから悩まねばならなくなった人は、性格傾向も含め、今までの自分自身のあり方を深く検討し、自分に何が必要か、分析してみることが大切であろう。――本書より
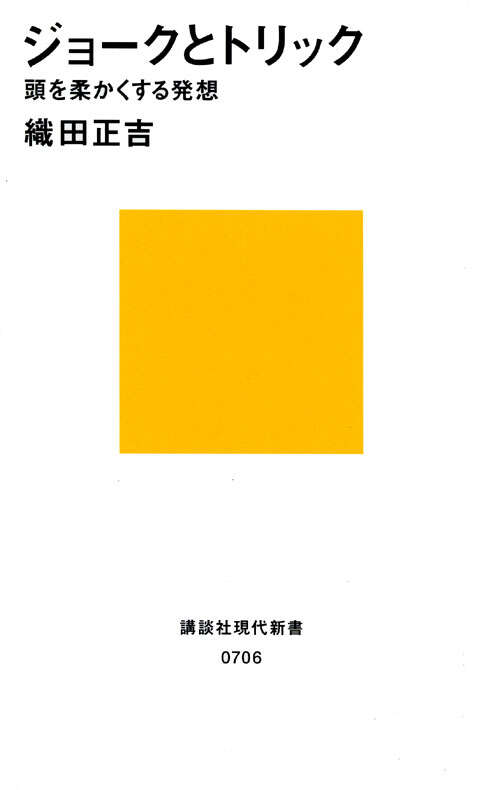
ジョークとトリック
講談社現代新書
――一日に二度出てくるのに一年に一度しか出ないものは?
――小林一茶と「月ハ東ニ日ハ西ニ」の関係は?〈解答は本書中〉すぐ答えられなければ本書必読、あなたは先入観にとらわれている!?ジョークは、笑いによって固定観念のワクを心地よくこわし、知性を刺戟するアイディアにみちた、古今東西の知恵の結晶だ。イソップからシェークスピアやアリスのしゃれ、ポオやホームズの推理、物名や折句、謎句などをとおして、伸縮自在の自由な発想法を教えてくれる本書で、頭の柔軟体操(ブレイン・トレーニング)をはじめよう!
バーはいつ開けるか――あるホテルのボーイが、泊り客からホテルのバーはいつ開けるか問い合わせの電話を受けた。「午前十時でございます。」一時間後、またおなじ客がバーはいつ開けるか電話でたずねてくる。返事はおなじ。二時間後、またおなじ電話がかかった。ボーイは我慢の限界に達し、「十時までお客さまをバーにお入れすることはできません!」すると電話の声が、「バーへ入る? おれは出たいんだ。――本文より

自分らしく生きる
講談社現代新書
君はいま、本当に心の充足を感じながら生きているか? 道具や機械、組織や制度に支配されず、本当に自律的な人生を生きているか?あり余るほどの“モノ”に囲まれ、情報や娯楽が氾濫する日常生活。過剰な生産=消費のサイクルの中で、自分らしさを失わずに生きるには、人はいったい何を必要とし、何を必要としないのか。現代を真摯に見つめてきた著者が、迷える若い世代に呼びかける熱い魂のメッセージ。
自分の道を選ぶには?――君が自分の人生にたいして高い要求をいだき、自分の本当にしたいことをして生きようと決意したとき、君はどういう問題につきあたるだろうか。《他律的に管理された生き方で満足するか、自律的な活動の生を選ぶか。その二者択一の決定をたえず自分でしなければならない》これが、君のつきあたる困難の第一だ。そして君が後者を選ぶ勇気をもつならば、君は、《自分の行為にたいする責任を自分でひきうけ、それによって生じるありとある危険をみずから担わなければならない》――本書より

タバコ
講談社現代新書
ケムリくゆらす至福と悲惨
タバコとガンによる死亡率の関係が強調され、公共的な場所での嫌煙運動がすすめられている。たしかに、煙は空気を汚すし、栄養にもならない。人間にとってタバコは、害のみをもたらし、益するところはないと、言いきれるのだろうか。作業能率や注意力にどんな作用を及ぼすのか。精神的なストレスを解消しているのではないか。ニコチンは体内でどんなはたらきをしているのか。体質や性格、吸い方や量、喫煙の条件と禁煙の必要な場合など、多面的に考察し、個人にとって社会にとっての喫煙の知恵を説く。

神と仏
講談社現代新書
人は古来、神秘という名の不思議や不安、恐怖にとらわれ、見えない神に祈願を捧げた。6世紀半ば、仏教とともに仏像がもたらされた時、日本人はそこに人間を見、来世を信じた。以来、神と仏は、陰に陽に、いつもわれわれの生活とともにある。肉体から霊魂を救済することをめざす神道、心身一如の状態を理想とする仏教。対照的な2つの宗教と、日本人はどのようにかかわってきたのだろうか。協調、融和、統合の関係を6つの側面からさぐり、日本人のアイデンティティに迫った。
さまざまの場所にいるカミ、ホトケ――古代の人間は、カミやホトケのような存在が、この宇宙空間のさまざまの場所に生息し生活しているのだと考えたとき、ようやく心の平安をえ、自分たちの生活の指針をうちたてることができると感じたのではないだろうか。現世を超越する怒りのカミやホトケ、あるいは山や川や樹木のように、われわれの身辺によりそって加護の手をさしのべてくれる慈愛にみちたカミやホトケが、しだいに一つのまとまりのある世界を形成するようになった。つまり、遠いところに超然としている天空のカミもいれば、近いところに寄りそって立つ地蔵菩薩のようなホトケもいる。そこから、さまざまな性格や属性をもつカミやホトケとわれわれ人間とを結ぶ、多様な遠近感覚が生みだされ、育てられていった。――本書より

自閉症
講談社現代新書
学校へ行かず、自分の部屋に閉じこもってしまう登校拒否の子、学校へ行っても、おし黙ってしまう緘黙(かんもく)の子……。他人との関係をもつことを避ける彼らは、けっして自閉症ではない。基本的に関係のもてない自閉児の世界ははるかに遠い。どこまでが自分の領域で、どこからが相手の領域か理解できないからこそ、会話は成立しない。と同時に、情の部分が欠如して、論理だけの世界に住む彼らは、何重にも絡み合わされた複雑な人間関係も苦手である。本書は、オウム返しやクレーン現象、パニックや自傷など、自閉児のことばや行動から、彼らの心の中に光をあて、関係をもつための、狭いながら確かな通路を模索する。
自閉の世界に入りこむ試み――ついに10日目になって教師の忍耐もつきた。まさに頭にきたのである。そして、切りきざんだ紙をさらに裁断機で細かくし、部屋の中に放りあげ、まきちらした。半ばやけ気味になって、「雪やこんこ」を歌った。紙片が子どもの頭にふりかかった。子どもはそれを払いのけようとして手を伸ばした。その瞬間、二人の目が本当に合ったという。目が合ったという表現は、それ以外のいいようがない。……そして子どもは声もあげずに教師の背中にまわって、おんぶの姿勢になったのである。――本書より

人はなぜ悩むのか
講談社現代新書
孤独と不安、病気や死への恐れ、劣等感、挫折感、複雑な人間関係のなかでの葛藤、親と子の確執、愛にまつわる苦しみ……。人は誰でも心の底に、さまざまな悩みをかこちながら生きている。神経症や心身症などの原因ともなる悩みを、逆に、よりよく生きるためのバネとするには、どう対処すればよいのか。本書は、苦悩の本態をさぐり出し、それを正しくうけとめ克服する方途を、豊富な臨床例にもとづきアドバイスする。
愛の悩み――神経症の人が結婚相手を選ぶことに不安を感じるのは、それによって、相手をひきうけるという重荷に耐えなければならなくなるからである。そして将来に対しての予期不安に悩まされるからである。だが、人間の営みにおいて、悩みを伴わない喜びはほとんど存在しない。したがって、愛の完結を求めようとするならば、同時に苦しみをもひきうける覚悟が必要になるのである。その決意と行動があってこそ“おとなの愛”が求められる。その苦悩の行く手に真の悦びが待っているのである。――本書より

小説―いかに読み、いかに書くか
講談社現代新書
人は、さまざまな体験や感動をもっている。それを小説にまとめあげられたら、どんなにうれしいことだろう。小説を読むのも、そこに共感する自己の投影をみるからであり、同時に、書く方法がわかれば、小説にしてみたいと、だれしも思う。本書は、日本の名作をとりあげ、読むことを通して、心理描写、文章表現のコツをつかみ、小説の発想を汲みあげる。
小説を書くために──小説は最終的には、あくまでも個人的なものだ。実際、才能や個性は一般化できない。たとえばドストエフスキーの才能、個性は普遍化できない。しかし、ここにそのドストエフスキーの次のような言葉がある。「われわれは皆ゴーゴリの『外套』から出てきた」つまり文学修業において、西欧先進国の文学に読みふけった彼が、いざ自分で小説を書こうとしたときには、やはりゴーゴリから、出発せざるを得なかったのである。自分たちの先輩によって書かれた作品の方法を、読みとると同時に、それを、いかに自分流に「変形」「発展」させるか、そこに、ドストエフスキーの小説家としての正統な文学的戦いがあった。──本文より

ユングの心理学
講談社現代新書
「魂の医師」としてユングは、自己内部を深く凝視し、心の深奥、広大な無意識の領域へ踏みこんでいった。そこは、人間の喜怒哀楽の感情を生みだす源泉であり、心のあやういバランスを保つ力も存在している。忘れられたの断片〈影〉、内なる異性像〈アニマ・アニムス〉、母なるものの根源にある〈グレート・マザー〉、そして〈老賢人〉などのイメージは壮大な神話やファンタジーを創りだしつつ、日常のささやかな幸福や人間関係のドラマにも密接に関わっている。ユングの心理学は、生の根底、自己の未知なる内面への旅である。
ファンタジーの創造社――ユングの心理学では、病的な症状はただ治療しなければならない、過去の悪い思い出とつながるだけのものではない。そこにはすでに、これから生まれるべき、別の姿が、一つのヴィジョンとして含まれているはずなのである。病的な状態が生みだす妄想さえも、ユングは決して否定的なものとはとらなかった。あらゆる人間のファンタジーは、心の奥から生まれてくる想像力が形作ったものなのである。その背景には、揺れ動く人間の創造性があって、現実化されるのを待っているというのが、彼の考えである。――本書より

酒の話
講談社現代新書
人類誕生以来ずっと、ひとは酒とともにかなしみ、よろこび、怒り、笑い、泣いてきた。一杯のビールから、一壜のワインから文化や芸術、政治が動き、歴史は変わっていった。まさに酒はわれわれの最良・最高の友である。いや、もしかすると悪魔の発明品かもしれない。風土や気候によって、世界の国々は特有の自分たちだけの酒を楽しんでいる。飲み方、うまさの秘密、早飲み、大酒飲みコンテスト、酔う酔わないの生理学まで、豊富なサカナを提供し、明日からのイッパイをさらに楽しくするおもしろ酒読本。
「酒はすべて悪徳のもと」――禁酒法が実施される前には、ニューヨークを例にしても、1万5000もの酒場が合法的にあったが、禁酒時代に入るとこれがなんと倍以上の3万2000もの地下もぐり酒場を生むことになる。また、禁酒時代に入るや、ハードリカー(ウィスキーのようなアルコール度の高い酒)が1年間に2億ガロン、ビールのようなソフトリカーになると6億8000万ガロン、ワインも1億1800万ガロン飲まれたと推測され、禁酒法以前に比べ10パーセントも増加している。禁酒法下でいかに酒が飲まれていたかを物語る好例に、摘発された飲酒運転の数があげられる。1920年の禁酒法最初の1年間に比べ、1927年1年間の酔っ払い運転の逮捕者は、実に467パーセントの増加となり、7年間で5倍近くもの逮捕者数となったのである。――本書より

〈自立〉の心理学
講談社現代新書
人生はプロセスである。過去のつまずきにとらわれることなく、はかり知れない結果を思いわずらうことなく、自らの人生の主人公として、納得できる自分の生き方を工夫するのが、自立した人間である。自立をうながす場としての家庭、親のあり方を軸に信頼と拒否、依存、現実直視、分離、反抗、グループ・マインド、自由など、自立への条件と着眼点を豊富なカウンセリング体験から提示する。あやまちをおそれず自分を生きよ、と説く自己回復のためのガイド・ブック。
ひとりの自分――人生とは愛の対象からの分離の連続である。つねにさびしさがつきまとうものである。しかし、考えてみれば、このさびしさがあるゆえに、人恋しさもおこるし、人と相和して生きるありがたさもわかるのである。分離の体験がなく、いつまでも母子一体感・親子一体感が続くと、ある日、突然分離せざるをえなくなったとき、パニックに陥る。そこでふだんから、人なかにまじり、人に和しているときでも、自分ひとりの自分を意識する必要がある。孤独を味わう必要がある。しかし、孤独(loneliness)は孤立(isolation)ではない。孤立には日から拒否されている感じがあるが、孤独にはそれがない。孤独とは自立の意識である。――本書より

生命あるすべてのものに
講談社現代新書
永遠に伝えたいマザー・テレサ。心にひびく愛のことば。
マザー・テレサは語りかける。力強くシンプルな言葉で、微笑みを絶やすことなく。一片のパンも、ひとかけらの愛もなく、飢え、死んでゆく人びと。生まれる前に愛をはぎとられ、死んでゆく多くの胎児たち。マザーは、この世界にみちみちている貧しさと心の飢えに、身を挺して愛を注ぎこむ、現代の聖母マリアである。自身の祈りの言葉を織りまぜつつ、母と子、学生を中心に、全世代の人びとに生命の尊さを訴えた来日講演録。英文原文付載、10ポ活字使用。
傷つくまで愛せよ――私たちは傷つくまで愛さねばなりません。
あるヒンズー教徒の4歳の子どもが、マザー・テレサは自分の子どもたちに与える砂糖を切らしていることを聞きました。カルカッタで一時砂糖がなくて困ったことがあったのです。その子どもは、これを聞くと両親に話しました。「3日間、お砂糖を食べないよ。ぼくのお砂糖をマザー・テレサにあげるの。」この幼い子どもは大きな愛で愛したのです。なぜなら傷つくまで愛したからです。そして、この子は私にどのように愛するかも教えてくれました。いくら与えたかではなく、与えることにどれだけの愛を注いだか、であると。――本文より