講談社現代新書作品一覧

経済学はむずかしくない(第2版)
講談社現代新書
もっとも身近な活動でありながらも、複雑、難解に見える現代経済学。
ミクロ経済学、マクロ経済学、ケインズ理論はどのようにして生まれたのか?
基本に立ち返り、平明に経済の構造を解き明かした名著が待望の復刊!

二十世紀の世界 新書西洋史(8)
講談社現代新書
社会主義国家の誕生、アメリカの躍進、民主主義の勃興と植民地の相つぐ独立――第1次世界大戦の終結は、同時に欧州中心の歴史の終焉でもあり、全地球規模での多極化と激動の時代の開幕でもあった。本書は、米ソ対立の二極構造をこえて多極化し、イデオロギーと国益が複雑にからみ合い、急速に微妙に流動する現代世界の動向に新しい光をあてた意欲作である。
現代史の構造――ヴァスコ・ダ・ガマ、コロンブス、マジェランらの航海が行なわれてから後には、世界を区分けしたのは常に欧州であり、19世紀末までに、地球全体の支配という世界史上例のない事業を、ごく少数の欧州諸国がやってのけた。こうした欧州の世界支配を打ち砕いたのが2つの世界大戦であり、ワシントンとモスクワが世界を支配するようになった。しかし、それも10年か20年しかもたなかった。世界史の構造がかくも短期間に変容したということは、そのテンポがいかに早められたかを証明している。今日、科学と技術の発達で世界は一体化した反面、世界勢力は分散化しつつある。分散化という点だけに限ってみれば、世界は、ガマやコロンブスやマジェラン以前の世界に似てきたのである。――本書より

帝国主義の展開 新書西洋史(7)
講談社現代新書
科学技術の驚異的発達・超大企業の出現、資本主義の爛熟にともなう帝国主義的進出、そして、はじめての世界戦争、さらには革命……。ドイツ帝国の興亡によって特徴づけられるこの時代は、ヨーロッパ的価値観が世界を征服し、いまわれわれの生きている〈現代〉のあり方を決定した時代でもあった。本書は、揺れ動く歴史的世界の構造をグローバルな目でとらえなおし、現代史理解のための新たな視座を提供した意欲作である。
-今日の世界を理解する鍵-本署の叙述は、19世紀以来おこなわれてきた一国単位の歴史叙述の集約ではない。筆者の念頭にあるのは、全地表的規模の歴史的世界とその構造の問題である。とくに、19世紀的世界から20世紀的世界への構造的転換の問題である。というのは、グローバルな歴史的世界はまさにこの半世紀間の「帝国主義の展開」を通じて形成されたものにほかならないからである。この時期の歴史を知ることは、今日の世界を理解することなのである。――本書より

ノイローゼ
講談社現代新書
ノイローゼは、脳の生理的な病ではなく、健康な精神が社会への適応につまづいたときに起る精神の病である。ストレス、欲求不満、強迫観念など、集団生活が強いる精神的緊張が、自我の日常的なリズムを狂わせるところにノイローゼが生じる。本書は、競争社会であるがゆえに増加するノイローゼの精神病理を解明し、このおとし穴におちいらぬための自己コントロールの方法をさぐる。
隣組ノイローゼ――住居の近代化によって、日本人も、団地やアパートに住むようになってきました。ところが、このような生活には、個人主義の発達が必要なのです。他人の生活に干渉しないことや、他人の迷惑にならないようにすることは、欠くことのできないことなのです。それができない人たちが、共同生活をするとき、どうしても緊張が生じてきます。私はかつて、これを隣組ノイローゼとよんだことがありましたが、今日では、団地ノイローゼとかアパートノイローゼというべきものが多くなっているといえましょう。――本書より

絶対王政の時代 新書西洋史(5)
講談社現代新書
太陽王ルイ14世が、はなばなしく活躍した時代は、近代社会へと、歴史が転換する激動の時代であった。僧侶・貴族から、その権力を奪い、絶対的統治権を手にした国王は、16-18世紀の300年間に、内に外にと勢力を膨張させ、植民地を通しての東西貿易によって、近代国家への発展の基礎をつくりあげた。また、哲学、文学、美術、音楽、自然科学などの分野で文化の花が開いた。この躍動する時代を、“ヨーロッパとは何か”という視点で把らえ、「転換期の歴史」の鼓動をつかむ。
統一と分裂の中のヨーロッパ――ヨーロッパの歴史は、政治的にみれば統一と分裂の2つの対極のあいだを揺れ動いているともいえる。ここに述べる絶対王政の展開は、まさにそのようなヨーロッパ的分裂化の端的な表現である。諸国家は自国の独自性と独立主権を強く主張し、すべてを自国の利害において計算し行動する。他国の富と繁栄は、自国の貧と衰退と考える。このような極端なヨーロッパの政治的分裂化にもかかわらず、実は、その内部では、絶対王政という政治形態をとって、1国の優位に対して、他国家が同盟して、その専横を阻止するという勢力均衡の原則が働いていた。――本書より

須弥山と極楽 -仏教の宇宙観-
講談社現代新書
須弥山とは高さ56万キロ、33人の天神が住む想像上の高峰である。紀元5世紀、インドで集大成された『倶舎論』は、この須弥山にはじまり、人間が宇宙をどう把えていたかを、詳細に描写している。本書は、この『倶舎論』を基礎に、仏教の宇宙観の変遷をさぐり、輪廻と解脱の2つの思想の誕生・発展の経緯を明らかにし、その現代的意味を説く。
輪廻と解脱の思想――仏教にはさまざまな経典や言葉があるけれど、結局は輪廻と解脱の2つの思想に帰するといえよう。仏教者はこうした輪廻的宇宙と解脱への道との両方を、それぞれ吟味し、研究し、やがてそれらを1つの壮大な体系にしたてあげた。そのような体系を示す書物の1つに、インド5世紀の仏僧ヴァスバンドゥの『倶舎論』がある。この中に須弥山説と呼ばれる仏教宇宙観が示されている。これが、後に“地獄と極楽”にまつわるさまざまな考え、描写へと発展し、日本にも大きな影響をあたえた。一見、過去のもの、われわれとは無縁のものと思われる仏教宇宙観も、実は、いまや新しい世界観を樹立する上で、重要な役割をになおうとしている。――本書より

異常の構造
講談社現代新書
精神異常の世界では、「正常」な人間が、ごくあたりまえに思っていることが、特別な意味を帯びて立ち現われてくる。そこには、安易なヒューマニズムに基づく「治療」などは寄せつけぬ人間精神の複雑さがある。著者は、道元や西田幾多郎の人間観を行きづまった西洋流の精神医学に導入し、異常の世界を真に理解する道を探ってきた。本書は現代人の素朴な合理信仰や常識が、いかに脆い仮構の上に成り立っているかを解明し、生きるということのほんとうの意味を根源から問い直している。
「全」と「一」の弁証法――赤ん坊が徐々に母親を自己ならざる他人として識別し、いろいろな人物や事物を認知し、それにともなって自分自身をも1個の存在として自覚するようになるにつれて、赤ん坊は「全」としての存在から「一」としての存在に移るようになる。幼児における社会性の発達は、「全」と「一」との弁証法的展開として、とらえてもよいのではないかと私は考えている。分裂病とよばれる精神の異常が、このような「一」の不成立、自己が自己であることの不成立にもとづいているのだとすれば、私たちはこのような「異常」な事態がどのようにして生じてきたのかを考えてみなくてはならない。――本書より

考える技術・書く技術
講談社現代新書
「情報過多の時代だから情報処理の技術を心得ておかないと翻弄されることになる」とは、
1973年刊行の本書に書かれていること。
さらに情報に振り回される現代こそ、本書の価値は高まっています。
学生・新社会人も必読!
「頭がいいとか悪いとか、ふだんよく使われる表現だが、もともとどういう意味があるのだろうか? (中略)
わたくしも教師生活を二十年近くは経験しているけれども、九十五点の学生と八十三点の学生の間に、
頭のよしあしの差があると思ったことは、いちどもない。
試験とはせいぜい、怠けているかどうかを知るのと、勉強をはげます程度にしか役立たないように思う。
学校の成績や入学試験にいたっては、競馬の勝ち負けより少しましだといったくらいのものだ。
とにかく信じられているほどには頭のよしあしとは関係がなさそうだ」
「独創とか創造とかについて、わたくしは日米あわせて五十冊くらいは参考書を読んだが、
(中略)すべてに共通することは、型にはまった考え方から離脱するために心身を訓練することであった。(中略)わたくしは、この態度をバンカラと呼んでいる」(本文より)
○脳は刺激を与えないと悪くなる
○「いつも」「みんな」という言葉は使うな
○朝は新聞を読むな
○ときどき、ふだん自分が興味のないジャンルを含め、あらゆる雑誌をまとめて眺め通すと、
頭のしこりがほぐれる(ブレーン・ストーミング読書)。
○精読するときは、黄色のダーマト鉛筆を使って気になる部分に線を引く
○読み返しのときは、しばらく時間をおく
○日本語はピラミッド型、英語は逆ピラミッド型。だから英語を聞き取るためには、文の 最初に注目する。
○自分に必要な情報を保存するとき、見出しをつけるときは「名詞」ではなく「動詞」を 使う
○保存する引用、要約に自分の見解を加えるときは、色を変えて書く
○アイデアを妨げるのは、「自分にはできない」という否定的な自己暗示
○相手に理解し、同調してもらうためには、「仲間意識」をつくりあげる
○読み手を味方にするには、私小説的アプローチを入れる
○数量化は大切
○自分の説と他人の説の区別は重要

美について
講談社現代新書
山河の美しさ、芸術の美しさ、人格の美……美は、さまざまな位相をとって人間の前に立ち現われ、より高い価値へとひとをいざなう。では、ひとはいかにして「美」を発見し、どのようにこれを受け入れてきたのか。最高の美とはいかなるものなのか。本書は、美についての理念の変遷や芸術の展開と関連づけながら、その存在論的意味を解明した美についての形而上学である。
美は人間の希望である――真と善と美とは人間の文化活動を保証し、かつ、刺戟してやまない価値理念である。真が存在の意味であり、善が存在の機能であるとすれば、美は、存在の恵みないし愛なのではなかろうか。われわれは美しい山河を眺めただけですら、救われた思いに浸る。卓越した芸術作品の美に接すれば、人間の偉大さにうたれ、自分が人間に属することを誇りに思うであろう。美は、たしかに、挫折し苦しむことの多いわれわれに差し出された存在の光りのようにも思われるではないか。美はこのようにして、人間の希望である。この輝かしい経験内容である美を反省しないでいることは、人間の栄光と喜びとについて考えずにおくことになる。――本書より

文明のあけぼの 新書西洋史(1)
講談社現代新書
石器や象形文字が語る古代人の奔放な活動の足跡――。本書は文明の発祥から、豊穰な文化遺産を残したエジプト・オリエントまで、連綿たる西洋文明の基礎となる古代人たちの知恵と信仰、さらには戦いと平和の歴史を、いきいきとよみがえらせた。ロゼッタストーンの解読、遺跡の発掘などにまつわる興味深いエピソードなどもまじえながら、西洋古代文化の構造と特質を平易に解明した好著である。
新たな時代区分――本書では古代を、始原、古拙、古典の3時代に分けて、文化を総体的にとらえ、歴史の主要な動向をたどってみたいと思う。ここで、歴史のはじめを「原始」といわず、「始原」と呼んだのは、それなりに理由があるからである。「原始」という語は、一般に低級な文化を示すために早くから使用され、遠古の文化に対しても、また、現今の未開文化に対しても適用されてきたため、そこには救いがたい混乱が見られるのである。ひとしく低級ではあっても、この2つの異質の文化を明確に区別することが必要であり、そのためには、しかるべき術語を用意しなければならない。――本書より

適応の条件
講談社現代新書
異なる文化に接した場合の〈カルチュア・ショック〉は、日本人において特に大きい。そこには、日本社会の〈タテ〉の原理による人間関係と、ウチからソトへの〈連続〉の思考が作用している。本書は、欧米・インド・東南アジアなど、ソトの場での日本人の適応と、そこに投影された〈ウチ〉意識の構造を分析し、〈強制〉と〈逃避〉という2つの顕著な傾きを指摘する。(講談社現代新書)
異なる文化に接した場合の〈カルチュア・ショック〉は、日本人において特に大きい。そこには、日本社会の〈タテ〉の原理による人間関係と、ウチからソトへの〈連続〉の思考が作用している。本書は、欧米・インド・東南アジアなど、ソトの場での日本人の適応と、そこに投影された〈ウチ〉意識の構造を分析し、〈強制〉と〈逃避〉という2つの顕著な傾きを指摘する。著者のゆたかなフィールド・ワークをもとに、国際化時代の日本人の適応条件を考察する本書は、ベストセラー『タテ社会の人間関係』につづく必読の好著である。
システムの発見――ゴムの産地として名高いマレーシアでは、英国統治時代からいわれてきた「ラバー・タイム」というのがある。ゴムのように伸びる時間の感覚である。熱帯ではどの国でも多少こうした傾向があるのがつねである。これに対して、約束した日時を守らないといって2年間も憤慨しつづけて過す日本人などがある。何度か同じように日時が守られなかった経験をもった場合には、怒るよりも、まず「なぜだろう」と考えるべきである。必ず何か理由があり、そのおくれ方自体に一定のシステムがみつかるものである。たとえば、1ヵ月といった場合はだいたい2ヵ月を意味するとか。表現というものは必ずしも実際の数を意味しないということは、どこの文化にもあることである。――本書より

本はどう読むか
講談社現代新書
本書は、本の選び方、読み方から、メモのとり方、整理の仕方、外国書の読み方まで、著者が豊富な読書経験からあみだした、本とつきあう上で欠かすことのできない知恵や工夫の数々をあまさず明かし、あわせて、マス・メディア時代における読書の意義を考察した読んで楽しい知的実用の書である。そして同時に、ここには、読書というフィルターを通して写し出された1つの卓越した精神の歴史がある。(講談社現代新書)
昭和を代表する知識人の体験的読書論 待望の復刊
本の選び方、読み方、メモのとり方、整理の仕方、外国書の読み方――。
豊富な読書経験からあみだした知恵や工夫の数々を紹介する、
読んで楽しい知的実用の書。
【目次】
1 私の読書経験から
2 教養のための読書
3 忘れない工夫
4 本とどうつきあうか
5 外国書に慣れる法
6 マスコミ時代の読書

バロック音楽
講談社現代新書
バロック音楽は、ある意味でもっとも現代的な音楽である。いっさいの先入観を必要とせず、虚心に音の美しさにひたりきらせる純粋さ。楽譜は見取り図にすぎず、ジャズにも似て即興演奏が重視され、聞く者の心に応じた多様な接近が可能となる。バッハやヴィヴァルディに象徴されるようにロック・ファン、ポビュラー・ファンにまで幅広く愛されている理由であろう。本書は、バロック音楽に関する最良の解説書であり、ファン待望の書である。
現代に生きるバッハ――最近おもしろいレコードを聞いた。バージル・フォックスという教会オルガニストがロックの会場で、何万というロック・ファンの若者たちにバッハのオルガン曲を聞かせている実況録音レコードである。まともなバッハである。正統的な演奏といってしまってさしつかえないだろう。多少リズムを鋭くし、テンポをいくぶん速目にとっているが、バッハの音楽には何の変形も加えていない。ところが、若者たちはフォックスの演奏を口笛をもって迎え、バッハの音楽の展開につれ、だんだん興奮し、あげくのはては手拍子までとって熱狂してゆくあり様である。わたくし自身、彼の演奏を生で聞いているが、バッハの音楽との違和感を覚えないばかりか、むしろバッハの音楽の普遍性というか、包容性というものにあらためて感嘆してしまったのである。――本書より
書評再録(本書より)
●バロック音楽と、どこかで、ふと偶然に出会った人に、さらにこの世界にふみ入るための手引きとして、本書は書かれている。一応、歴史的な概説を軸としているが、固苦しい学問臭はほとんど感じさせず、著者の個人的体験をまじえながら、バロック音楽の現代人への問いかけの意味を、一緒に考えて行こうとする姿勢に貫かれている。――-読売新聞-
●氏は、音楽にたいしてつねに開かれた態度で接しようとしている音楽学者であり、バロック音楽のすばらしさを説きながらも、それをべつの時代やべつの民族の音楽に対する優越性とすりかえようとはしない。また宗教音楽についても、「日本人には真の理解は難しい」式の俗論とは破綻委に、バッハが教会のためにも世俗のためにも、いかに人間くさい音楽を書いたかを力説する。――-朝日新聞-
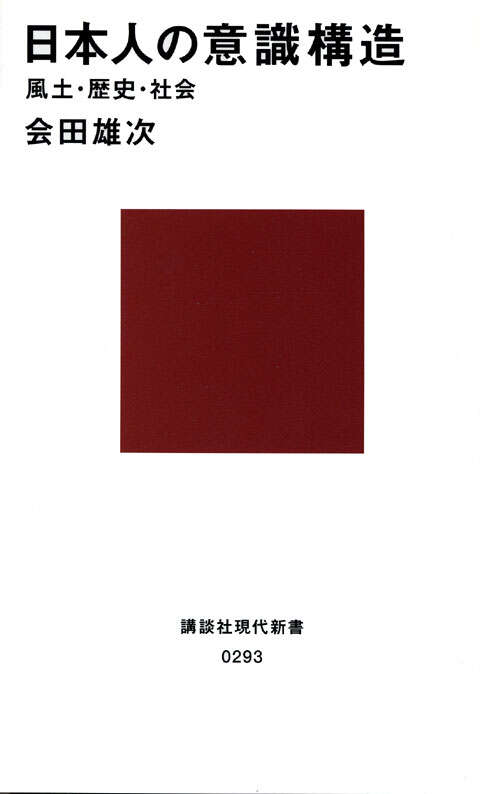
日本人の意識構造
講談社現代新書
子どもを危険から守るとき、日本人はかならず前に抱きかかえる。それはなぜか――。日常の何気ない動作や人間関係に表われる意識下の民族的特質に注目しつつ、ユニークな視点から日本人像をあざやかに浮かび上がらせ、独特の歯切れのいい会田史観を展開した快著。話題のロングセラーの新書版である。
短距離とマラソン――わたしたちはかならず、ひじょうに短い目標を定める。10日間がんばれ、20日間がんばれ、せいぜい1年間がんばれということになり、そういうときにはエネルギーが集中する。背中で対象を感得できる程度に短期目標であり、想像力でも把握できるように具体的な競争相手を明確に設定するとき、はじめて、その達成にひじょうな努力を払うということになる。突貫工事とか、追いつけ追いこせ、という形にするときひじょうにうまくいく。これは、内側を向いている人間の心理、内側を向いている精神的姿勢の特徴であろう。それは、ひじょうな長所であるかもしれない。一方、ヨーロッパ人に対して、3日間だけ、1年間だけがんばれといっても効果はすくない。壮大な長期目標がないと元気が出ないというのがヨーロッパ人、つまり外側に向いている人間の弱さである。――本書より
書評再録(本書より)
●日本人とは、どういう民族なのか、その特質はどこにあるのか、いまほど問題にされているときはない。国際的にもそうである。本書は、日本人の意識構造の特質を、独自の発想法でみごとにえぐり出している。――-毎日新聞-
●だれもが知っていること、逆に、だれもが見のがしていたことを手がかりに、日本人の長所や短所が、アメリカやヨーロッパと対比のうえで描き出されてゆく。……実にみごとな料理ぶりというほかない。――鯖田豊之氏-読売新聞-
●学問の通常のワクを越えた発想をしながら、それが単なる思いつくではなく、ユニークな体系にまで発展し、それが文化や時務の解明、批判の武器として活用されている……氏のものはいつも独自であり、新鮮である。――尾鍋輝彦氏-サンケイ新聞-

正しく考えるために
講談社現代新書
人間は「考える」ことなしには生きてゆけない。よりよく生きるとはよりよく考えることである。よりよく考えるにはどうしたらいいか。論理的に誤りのない「正しい」判断ができるだけの心構えと論理を身につけることである。本書は、ともすれば陥りやすい論理や判断の落し穴を具体例に即して教えた、考えるための手引書である。

愛すること信ずること
講談社現代新書
夫婦とはいったい何であろうか。人を愛するとは? 信仰に生きるとは?この人間に根本の問題を、著者は自らの生活を卒直に語りながら考える。ユーモアあふれる語り口で、深く、きびしく人生の機微をみごとにとらえた本書は、また、心あたたまる夫婦愛の記録でもある。
〈夫の歌を聞く〉――結婚して以来、わたしは心の底ででも、夫を軽べつしたことは一度もない。むしろ、わたしの口は「ハッキリ」とものを言うために、「ハッキリ」とほめてきたかもしれない。「うちにはテレビがないけれど、三浦が、歌が上手なものですから、テレビなどいらないんですよ」などと、ぬけぬけとわたしは言う。そして、三浦がうたってくれると、ウットリと三浦の顔を眺め、悲しい歌は涙を流して聞いてしまう。人から見ると、いい年をして馬鹿な女と笑われるかもしれない。だが、夫の歌がこの上なく楽しいことは、べつだん他人様の迷惑にはなるまい。夫婦なんて、それでいいんじゃないかと思う。聖書にも、人のことをあれこれ言うなと書いてある。「さばくな」と。――本書より
きらめくような鋭さ 田中澄江
仕合わせが満ち溢れているような本である。しかし、仕合わせをつかむことは、いつの時代でもむずかしい。三浦さんは、けっして、大げさでものものしい表現をとらず、日常生活の中から、ひととひととの結びつきのもろさと可能性を見つめつづけてこられた。その口あたりのよい文章には、一語一語に、きらめくような鋭さで仕合わせの意味があたたかく語られている。

失われた文明
講談社現代新書
かつて1万2千年前の地球上には、想像を絶するような高度に発達した文明が、花を開かせていた。重さ2千トンもあるような石の建築物、青銅の精錬技術を駆使した工芸品、空を飛ぶ器機などが作られていた。しかし、その文明は“大洪水”という世界的大異変によって、突然地球上から姿を消してしまった。本書は、この“失われた文明”を、沈黙の世界から、たぐり出し、ファンタジーの翼をひろげて、古代史の謎を系統的に総合的に追究する。
大異変はほんとうに起り得るか――この書物で述べられている1万2千年前の世界現在の世界地図に見られる海洋のうすい色のところは、すべて陸地であった。そこに栄えた高度な文明は、いかに想像を絶するものであったか、さまざまな神話や伝承、古文書が立証している。とはいえ、一旦栄えた文明が、途中で断絶することがあり得るだろうか。人間社会を全滅させるような大異変が、ほんとうに起り得るだろうか。こういった疑問を抱かれる読者は多いことと思う。しかし、今日の文明社会においてもまた、起り得るのである。たとえば、南極大陸をおおっている氷が、もし全部とけてしまったら、地球の多くの都市や土地はたちまち海底に没してしまうだろう。それは地軸が少し角度を変えたら、起り得るのである。このようなことを念頭に入れながら、読者は本書の内容を考えねばならない――著訳者のことばより
『失われた文明』に寄せて――東京大学教授 増田義郎
人間の文明史には、現代の科学や最高の学問をもってしても、まだ説明し得ない不可思議な伝説が、たくさん存在している。本書でも述べられているような世界各地にある“大洪水”の物語や高度に発達した文明に関する言い伝えなどがそうである。本書は、まだ解明されていない1万2千年前の空間的世界に入りこみ、多くの謎に満ちた現象に系統的な説明を加えている。さらに文明の発生への大胆な仮説をも提起している。大胆な発想は、しばしば歴史の解釈に新しいヒントを、与えることがある。本書もまた読者に、歴史の背後にある“沈黙の世界”を解明するヒントを与えてくれるであろう。

日本人はどこから来たか
講談社現代新書
日本人の起源は永遠の謎である。日本は古来文化のルツボであった、流れこむばかりでそこから出て行くことのない――。このルツボのうちそとの謎に、多くの先人が、果敢に挑み、先住民説・原人説・混血説などを説いた。本書は発掘物・言語など豊なデータをもとに、精密な推理を進め、江南要素を重視する。
〈日本人の起源に関する諸説〉歴史的にみると、まず、日本島には日本人以前に先住民がいたという、先住民論があり、その先住民がいかなるものであったかをめぐって、アイヌ説・プレアイヌ説・コロボックル説などがあらわれた。さらに日本人混血説をへて、ナショナリズムとのからみあいもあって、日本島には最初から日本人がいたとする日本原人論があらわれた。最近になって騎馬民族征服説なども出されたが、もちろんこの世界には、確たる定説はない。化石人骨・血液型・言語・石器・土器・各種の道具、そして稲作の問題など複雑なファクターを比較検討しながら、本書では、日本人の祖型には江南要素が濃厚であると結論する。

日本人の論理構造
講談社現代新書
どうせ、せめて、さすが、しみじみ・・・。
これらのことばが、どのような文化の中に生まれ、私たちをどのように性格づけてきたのか?
長年アメリカで日本語や日本文学を教え続けてきた著者が、身近なことばから日本人独特の心理を探りだしたユニークな文化論。
いまこそ読まれるべき名著の復刊。

文化人類学の世界 人間の鏡
講談社現代新書
文化人類学は人間諸科学を統合する新しい〈人間学〉として注目されている。しかし、未開社会の奇妙な習慣や親族関係や古ぼけた陶片などを調べて、人間に関するどんな新しいことがわかるというのだろうか。本書は、アメリカ人類学界の第一人者が、そんな疑問に豊富な実例をもって答えながら、人間を写す鏡としての人類学の魅力と考え方を楽しくかつあますところなく描きだした定評ある入門書である。