講談社現代新書作品一覧

「関係の空気」「場の空気」
講談社現代新書
なぜ上司と部下は話が通じないのか。キレる若者・息苦しい教室・無意味な会議・くだらない標語・リストラと自殺・女性の雇用と少子化問題・女子アナ人気・小泉劇場……、「なんか変だ」。
なぜ上司と部下は話が通じないのか
キレる若者・息苦しい教室・無意味な会議・くだらない標語・リストラと自殺・女性の雇用と少子化問題・女子アナ人気・小泉劇場……、「なんか変だ」
村上龍氏推薦!!
「日本語は、日本社会を映す鏡であり、駆動させる燃料でもある。NY在住の著者は『空気』というキーワードで『流通する日本語』を正確に検証している」
「空気」がすべてを決めていく……国際関係、少子化、高齢化、若年層の雇用、教育、財政赤字、消費税率、年金……。論点のそれぞれは深刻なのに、激しい対立もなければ現実的な妥協もない、それでいて何となく何かが決まっていく、あるいは先送りされていく、それが日本社会のようだ。そこでは「空気」がすべてを支配しているといってもよいだろう。論理や事実ではなく、「空気」が意思決定の主役になり、またその「空気」が風向きの変化によってよく変わるのだ。(中略)「空気」が支配しているのは、一国レベルの「世論」だけではない。個々の企業における「社内世論」や、学校のクラスにおける「先生ムカツク」とか「○○ちゃんウザい」というようなものも「空気」に他ならず、それぞれの小社会であたかも絶対権力を握っているかのようである。そして、この「空気」に対して、日本人の一人一人は無力である。「何ごともその場の空気によって決まる、というのは良いことではない。だが、その場の空気が濃くなればそれに対抗するのは難しいし何よりも損だろう」そんな感覚が日本の社会の隅々までを満たしている。――<「はじめに」より>

愛国者は信用できるか
講談社現代新書
愛国者は偉いか? 愛国者は信用できるか!? 三島由紀夫が「愛国心は嫌いだ」といった意味は何だったのか? そして意外にも女帝賛成論だったという事実! 新右翼の大物が書き下ろす全く新しい天皇制と国家論! (講談社現代新書)
愛国者は偉いか? 愛国者は信用できるか!? 三島由紀夫が「愛国心は嫌いだ」といった意味は何だったのか? そして意外にも女帝賛成論だったという事実! 新右翼の大物が書き下ろす全く新しい天皇制と国家論!

感動!ブラジルサッカー
講談社現代新書
わが友ロナウジーニョ「セレソン」の本音
外国人として唯一、密着取材を許された筆者が描く選手たちの素顔と、世界最強チームの秘密!

知ってる古文の知らない魅力
講談社現代新書
「つれづれなるままに、日ぐらし、硯にむかひて……」徒然草の有名な書き出しは、実は兼好法師のオリジナルじゃなかった!? 「つれづれなりし折……」(和泉式部)、「つれづれに侍るままに……」(堤中納言物語)、「つれづれのままに……」(讃岐典侍日記)など、平安時代の定番フレーズがその源にあった。古典文学の大河の間にまに掬い上げられる名句から、新たに生まれる流れを辿ってゆく。
「つれづれなるままに、日ぐらし、硯にむかひて……」徒然草の有名な書き出し。実は兼好法師のオリジナルじゃない!?
「つれづれなりし折……」(和泉式部)
「つれづれに侍るままに……」(堤中納言物語)
「つれづれのままに……」(讃岐典侍日記)
平安時代の定番フレーズをいただきました。

算数・数学が得意になる本
講談社現代新書
つまずいても大丈夫!
マイナスかけるマイナスはなぜプラス?
本当の力がつく『数学的思考法』のレッスン
「くり上がり・くり下がりがわかるコツ」から微分積分まで、「つまずき」を乗り越えるヒントが満載!

読む哲学事典
講談社現代新書
軽妙な文章で見せる、哲学的思考のパノラマ本質と時間、愛と暴力、ここと私……対にした項目から見える、日常の言葉と哲学用語が織りなす、概念のネットワーク。一流の哲学思考のエッセンスを「読む」事典。1人の哲学者がすべてを書いた!
1人の哲学者がすべてを書いた。
項目を対にすることで、日常の言葉と哲学用語が織りなす概念のネットワークが見えてくる。軽妙な文章で味わう、本格的な哲学思考の神髄!
哲学事典を引く人が、「存在」とか「記憶」とかの意味をまったく知らない、などということは考えにくい。求められているのは日常では一見自明な言葉に哲学者が見出す亀裂であり、それを通して見えてくる思いがけない意味連関ではなかろうか?概念間の連関が重要なのだ。ゆえに、哲学事典は一貫した視点で、1人が全項目を書くべきなのだ。これは、すべてを網羅するという事ではない。多くの知識を蓄える事が問題ではない。問題は、越境的な精神の自由を確保する事なのである。本書では、諸概念の連関を強調するため、事項を単独で説明するのではなく、一対の概念に対して説明をした。読者は、関連する事項説明をたどることによって、梁と梁が大きなドームをなすイスラム建築のように、あるいはたがいに連関して図形を構成する夜の星空のように広がる、概念の天蓋が見渡せよう。我々は、少なくとも千年の持続に耐え得るような伝統の基礎を築きたいと考えたものである。そして、その主要な部分はある程度の持続に耐えるはずだ。その大部分は、すでに2千年以上の時間の試練に耐えて受け継がれたものだから。
さあ、哲学をはじめよう。

モナ・リザの罠
講談社現代新書
ダ・ヴィンチの「仕掛け」を知的に読み解く
人気番組「世界一受けたい授業!!」で話題の美術案内人(ナビゲーター)が誘う“芸術=興奮”ワールド!!

北朝鮮に潜入せよ
講談社現代新書
歴史から消された秘密工作員たちの悲劇!
スカウト、訓練から拉致、爆破まで韓国 vs.北朝鮮の暗闘を描く

スラスラ書ける!ビジネス文書
講談社現代新書
仕事力は文書が決める!
よく通る企画書、誠意が伝わる依頼状、個性が光る挨拶状、一目置かれる報告書……
「大人の作法」から「プレゼンの裏技」まで、ビジネスを成功させる書き方の極意、教えます。

若者殺しの時代
講談社現代新書
ずんずん調査のホリイ博士が80年代と対峙。クリスマス・ファシズムの勃興、回転ベッドの衰退、浮遊する月9ドラマ、宮崎勤事件、バブル絶頂期の「一杯のかけそば」騒動……あの時なにが葬られたのか? (講談社現代新書)
ずんずん調査のホリイ博士が80年代と対峙。クリスマス・ファシズムの勃興、回転ベッドの衰退、浮遊する月9ドラマ、宮崎勤事件、バブル絶頂期の「一杯のかけそば」騒動……あの時なにが葬られたのか?

こんにゃくの中の日本史
講談社現代新書
桜田門外の変の資金源はこんにゃくだった!
松尾芭蕉に愛され、アメリカが恐れた「風船爆弾」を生み、ペニシリンの国産を助け、昭和天皇にも一目置かれた――その軟体には日本史の激動が刻まれている!
維新回天の陰に、こんにゃくがいた!
しかし、幕末に水戸藩が広めたのは尊王攘夷だけではなく、こんにゃくもしかりであった。かたや日本を維新回天に導いた多くの志士に影響を与えた誇り高き思想であり、こなた、あってもなくてもさしあたり人は困らぬこんにゃくであるが、このふたつはほぼ同じ時期に、水戸藩から全国に広まっている。(中略)尊王攘夷とこんにゃくは袋田を舞台に密接に結びつき、やがて幕府を激震させる大事件をひきおこすのである。(中略)いわゆる桜田門外の変だが、この襲撃事件の現場指揮をとったのが関鉄之介である。その日の朝、愛宕山で鉄之介が受けとった金は襲撃後の同志たちの逃亡資金で、その額200両といわれているが、これは根拠のたしかな数字ではない。こまかなことをいえば、金を運んだのは重箱ではなく、薬缶だったとする説もある。ディテールのちがいはともかく、はっきりしているのは、この資金を出し、使いの男にとどけさせたのが、袋田の蒟蒻会所を取り仕切っていた桜岡源次衛門だったことだ。――<本書より>

「イスラムvs.西欧」の近代
講談社現代新書
イスラムの<嫌西欧>はどこで生まれたのか
イスラムへの<違和感>の核心にあるものは何か
この時代は、中東が「近代化」された時代である。と同時に、ヨーロッパ列強に「植民地化」された時代でもある。この時期、イスラム世界はヨーロッパと本格的に邂逅し、それとの格闘のなかで、自らを近代化するも、結果的には、その支配下に置かれるようになる。この時代に、中東における「ヨーロッパとイスラム」の原型がつくられた。
なぜイスラム教徒は近代文明に反発するのか?
現在、毎日のように、イスラム教徒の過激な政治行動が報道されている。かれらは近代文明を拒否しているかにみえる。もちろん、近代文明を戦闘的に拒否しているのは、一部の過激なイスラム教徒である。圧倒的多くのイスラム教徒は、かれらの過激な政治行動を苦々しく思い、近代文明における生活スタイルにあこがれてさえいる。しかし、そのかれらも、過激なイスラム教徒の主張に相通じる怒りと反発を秘めている。一部の過激なイスラム教徒を例外とし、一般のイスラム教徒と切り離しては、問題の解決にはならない。一体、かれらは近代文明の何に反発しているのか。どうして近代文明に反発するようになったのか。本書は、その答えを、イスラム知識人における近代観の変化に探り、かれらのアイデンティティ危機の深化の過程として描くことを目的とする。それは、近代がかれらの意識下においてトラウマ化する過程であった。――<本書より>

知的な大人の勉強法 英語を制する「ライティング」
講談社現代新書
会話重視の学習よ、さらば!
本物の英語力を育てる「5パラグラフ・ライティング」とは何か?トリリンガルの著者による最強の英語習得戦略。日本人よ自信を持とう!
●日本の「費用対効果」が低すぎる理由
●「楽しくおしゃべり」では上手になれない
●「読み・書き偏重」という学校英語批判は的はずれ
●英語に「浸す」授業法の罠
●留学で伸びる本当の理由
●読んで書いて議論する
●エッセイを直すことに意味がある
●パラグラフ・ライティングで論理的思考を養おう
英語教育にまつわる「偽りの救い」
たしかに学校の英語教育を6年間受けたところで、たいていの日本人は英語があまりしゃべれない。書けない。聞けない。読めない。それにもかかわらず、1100時間の授業が無駄な努力であったというのは真っ赤なウソである。なぜなら、学校教育は英語を学ぶにおいて欠かせない土台、つまり「ボキャブラリー」と「グラマー」を教え込むからだ。(中略)将来ちゃんと英語を使いこなそうと思えば必ず役に立つであろう、基本中の基本をしっかりと教えていると言えるのではないだろうか。そもそも日本の学校英語教育が「読み・書き」中心という言い方自体、相当に的外れであると言わざるをえない。「読み」はともかく、「書き」は皆無に等しいのである。――<本書より>

江戸時代の設計者
講談社現代新書
伊予藩主・藤堂高虎は外様大名としては異例の信頼を幕府から得た。それは彼が日本で初めて「藩」を構想しえた政治家だったからだ。司馬遼太郎に「世渡り上手」と酷評された藤堂は、身長190cmの偉丈夫にして、きめ細かな築城術にたけたテクノクラートだった。しかし、彼がもっとも評価されるべきは、豊臣時代の中央集権に限界を見出し、地方分権国家を構想して近世の扉を開いたことにある。近世の成立を新史観で明かす。
徳川家康に天下を取らせ 城を、藩をつくった近世のプロデューサー
司馬遼太郎に「世渡り上手」と酷評された戦国武将、藤堂高虎は、身長190cmの偉丈夫にして、きめ細かな築城術にたけたテクノクラートだった。しかし、彼がもっとも評価されるべきは、豊臣時代の中央集権に限界を見出し、地方分権国家を構想して近世の扉を開いたことにある。
日本に「藩」を創った男
20世紀を造形した「中央集権」「官僚制」の限界に直面し、「市民」の願いが直接反映される合理的な国づくりがめざされるようになった。かかる動向のなかで、現在「地方分権」が注目され、分権国家への様々な模索がなされているのである。そのような今日、藤堂高虎(1556~1630年、藤堂藩三十二万石の初代藩主)が家康の参謀として取り組んだ改革、とりわけ藩≪くに≫づくりには学ぶべきことが多い。――<本書より>

日本人はなぜ狐を信仰するのか
講談社現代新書
お稲荷さんの謎を解く鍵は、エジプト・インドにある!
稲荷の鳥居はなぜ赤いのか?豊川稲荷はなぜダキニを祀るのか?「こっくりさん」の起源は何か?狐とエジプトのアヌビスの関係とは?タロットカードで見る狐の役割とは?新羅の伝説が示す稲荷縁起が持つ意味とは?
江戸時代から「伊勢屋、稲荷に犬の糞」とどこにでもあるものの代名詞として謳われ、いまでも日本中にあるお稲荷さん。しかし、そもそもなぜ稲荷は日本中に存在するのか?なぜ稲荷と言えば狐なのか?そして稲荷は何を祀っているのか?古代エジプトからインド、そして中国から新羅、日本。時間と空間を超え、稲荷信仰の謎に迫る。

解剖男
講談社現代新書
24時間戦う遺体科学者 動物進化の神秘へ迫る
動物の進化はいまなお謎だらけ
疾駆する山手線の車内では、私の目の前に、バイカルアザラシの眼球がある。アザラシがこんな大きな目をもったら、顔の大半が目に置き換えられてしまうではないか。今日はアメ横脇の曲線に揺さぶられながら、この大きな目をどうすれば頭蓋骨に収めることができるか、私の指に握られたピンセットが明らかにしていく。動物進化学の足跡を振り返ると、ホモ・サピエンスが神の創り出した粘土細工とされたキリスト教万能の時代から、容赦なきダーウィンの進化論がヒトの祖先をサルの身体に求めるようになるまで、けっして長い時間を要したわけではない。そして現在も、動物の形が何億年もの進化の歴史の中でどのように変わってきたかという科学の議論は、答えが確定されるどころか、日々猛スピードで書き換えられているのである。――<本書より>

スペイン巡礼史
講談社現代新書
聖地サンティアゴへようこそ!
巡礼に現世利益と魂の救済を求め、人びとは「奇跡」に何を託したか?
中近世ヨーロッパ人「信仰の社会史」
●海を渡った「3つの一神教」の巡礼者たち
●異教の聖所と連続する聖地
●「地の果て」(フィニス・テラーエ)の聖地
●聖地サンティアゴと聖ヤコブ
●聖ヤコブとカール大帝
●捏造される奇跡
●レコンキスタとサンティアゴ巡礼
●大航海時代とサンティアゴ巡礼
●フランコとサンティアゴ巡礼
●帆立貝と巡礼杖の意味とは?
●巡礼講と「苦難の長旅」
●帰路の意味するものとは?
●外国人旅行者の見た観光資源
●「聖なる都市」の誕生
●慈善サービスと「権力」の関係
●サンティアゴ巡礼と四国巡礼の「近さ」
サンティアゴ巡礼への誘い
本書は、巡礼と密接に関わる民衆信仰、シンクレティズム、「観光」、都市開発、慈善をキーワードに、中近世を中心にスペインの巡礼を全体的に読み解いたものである。巡礼というプリズムを通して見た、中近世スペイン史と言い換えることもできる。考察の中心はサンティアゴ巡礼であるが、3つの一神教を意識して、スペインのイスラム教徒とユダヤ人の巡礼についても言及することにする。ヨーロッパ史と宗教との関わりの一端なりとも、ここから汲みとっていただければ幸いである。――<本書より>

他人を見下す若者たち
講談社現代新書
現代人は自分の体面を保つために、周囲の見知らぬ他者の能力や実力を、いとも簡単に否定する。世間の連中はつまらない奴らだ、とるに足らぬ奴らだという感覚を、いつのまにか自分の身に染み込ませているように思われる。……このように若者を中心として、現代人の多くが他者を否定したり軽視することで、無意識的に自分の価値や能力を保持したり、高めようとしている――<本文より>
「自分以外はバカ」の時代!
●自分に甘く、他人に厳しい
●すぐにいらつき、キレる
●「悪い」と思っても謝らない
●泣けるドラマや小説は大好き
●無気力、鬱になりやすい
若者の感情とやる気が変化している!
現代人は自分の体面を保つために、周囲の見知らぬ他者の能力や実力を、いとも簡単に否定する。世間の連中はつまらない奴らだ、とるに足らぬ奴らだという感覚を、いつのまにか自分の身に染み込ませているように思われる。……このように若者を中心として、現代人の多くが他者を否定したり軽視することで、無意識的に自分の価値や能力を保持したり、高めようとしている――<本文より>
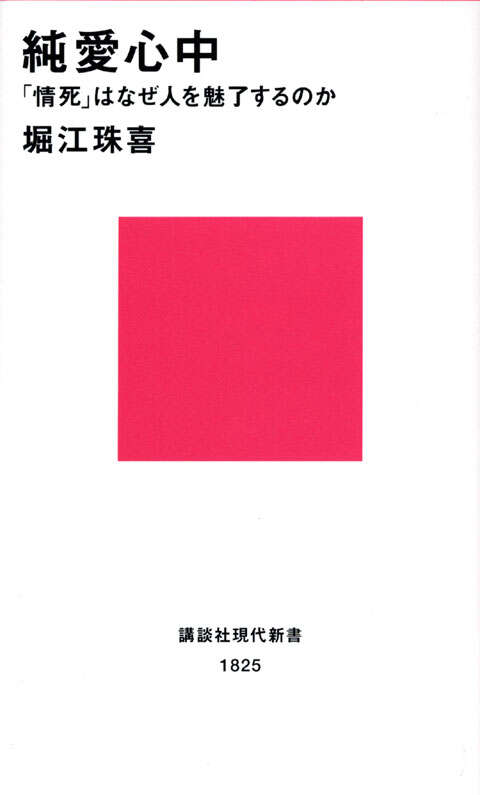
純愛心中
講談社現代新書
男と女「究極の愛のかたち」
物語では近松門左衛門の『曾根崎心中』、三島由紀夫の『憂国』、渡辺淳一の『失楽園』『愛の流刑地』、『ロミオとジュリエット』、『トリスタンとイゾルデ』……史実では乃木大将夫妻、天城山心中、皇太子ルドルフ、ダイアナ妃……
三島由紀夫の心中美学
三島は「心中論」を書いた12年後に市ケ谷で割腹自殺をすることになるのだが、本人もそのような未来が予見できるわけもなく、「若い人同士の心中はいい」とか、「太宰治などの中年者の心中の不潔さ」などと書いているのだ。皮肉なことに太宰が心中したのは38歳、三島が森田必勝と死んだのは45歳であった。(中略)さらに「心中論」として、当然ながら近松に言及されるのだが、心中に性的な意味を見つけ出す次の議論は興味深い。「大人の心中では、必ず心中の直前に性の営みが行はれるさうであるが、近松の心中物の道行の文章はつねにこれを暗示してゐる。文辞の上ではそれに類した文句はないけれど、あの永い道行の美文は、死の直前の性的陶酔そのままである。(中略)心中といふ言葉にはどうしても性的陶酔の極致といふ幻影がつきまとふので、男女の性行為は本質的に疑似心中的要素を持つてゐる。これは少くとも性的経験のある人間なら誰でも知つてゐる秘密である」。――<本書より>

漢詩のこころ 日本名作選
講談社現代新書
詩が生まれた風景を旅する
空海、謙信と信玄、良寛、西郷、乃木、漱石…21人の感慨を追体験!
空海との別れを惜しむ嵯峨天皇の「海公と茶を飲み、帰山を送る」
薔薇の花をこよなく愛した武田信玄の「薔薇」
藩の武力革命を決意した高杉晋作の「二十五日鴻城、井上聞多を訪ね、主人の韻に次す」
沖永良部島に流された西郷隆盛の「獄中所感」
江戸城無血開城を実現させた勝海舟の「江戸城明渡」
対露戦の多大な犠牲を恥じる乃木希典の「凱旋に感有り」
大病を患い死線をさまよう夏目漱石の「無題 明治四十三年九月二十日」
漢詩が生まれた「現場」を訪ねる
中国の広大な天地では、なかなかそうはいかないが、日本の漢詩人の場合は、良寛の詩にかぎらず、その詩人がある時期すごした場所を訪ねようと思えば、それができる。たしかに手間、暇のかかる作業であったが、それだけ日本の漢詩人と共有する時間を持つことができたのは楽しいことであった。他にもたとえば、菅原道真でいえば、大宰府遷謫(せんたく)期の漢詩数篇を、日本のボードレールといわれた柏木如亭の漢詩は、京の真如堂の草庵で詠まれた数篇を、下関長府の功山寺で維新回天の事業を出発させた高杉晋作の漢詩は、その前後の時期の数篇を、夏目漱石の場合は、起死回生の大患に遭った修善寺病臥の漢詩数篇をとりあげてみた。――<本書より>