講談社現代新書作品一覧

サバがトロより高くなる日
講談社現代新書
「豊かな食卓」を支える驚きの実態!!
漁獲量が147万トンから2万トンになったサバ
100万トンから26トンになったイカ
トロ90%のマグロを「生産」する
日本人の食べるウナギの70%がヨーロッパ生まれの中国育ち
貝の不当表示は業界の常識!?
「白身魚」は深海魚からアフリカの淡水魚の時代へ
「本物のシシャモ」は全体の5%以下
日本は世界一の魚消費国。しかし生産量(漁獲+養殖)ではすでに世界第6位まで落ちている。乱獲が進み、養殖も環境破壊など問題山積。私たちはいつまで魚を食べ続けることができるのか。身近な話題でありながら、知られてこなかった現実を明らかにする。
トロ90%のマグロを作る
畜養されるマグロは、数ヵ月から半年の間にイワシやサバ、イカなどを粉末にした濃厚な飼料を大量に与えられ、丸々と太り、脂が乗った体になる。(中略)天然のマグロは、寒い時でないと脂が乗らず、いいトロが取れる時期も海域も限られるが、畜養は違う。濃厚な飼料を与えることで、霜降りの松阪牛のように全身に脂が乗ったトロを「生産」することができる。天然物では体重の20%もトロがある魚はそうはいないのだが、畜養だと90%近くがトロかトロに近い状態というマグロも作れるそうだ。最近では、飼育期間を長くしてさらに太らせたマグロを作ろうとの試みも進んでいる。餌はイワシやサバなど脂の多い魚を与えてトロの多いマグロに育てるというのが一般的らしく、赤い色を付けるためにサクラエビのようなエビを餌に混ぜることもあるという。あまり大量にイワシなどを与えると魚肉が生臭くなってしまうので、与える餌の量や出荷時期と餌の加減などに業者は工夫を凝らしているらしい。――<本書より>

性愛奥義
講談社現代新書
われわれはなんと貧困な性愛しか知らなかったか!
誘惑の作法から爪と歯の使い方まで いまこそ学ぶ、古代の智恵
卓抜な比喩と精緻な分類から豊穣なカーマの世界が浮かび上がる!
●男のなすべき行為(9段階)
……/摩擦/圧迫/一撃/猪の一撃/牡牛の一撃/雀のたわむれ
●抱擁(12種類)
接触/媚態/摩擦/圧迫/蔓草の纏わり/木登り/……
●爪のたて方(8種類)
……/半月/環状/線状/虎の爪/孔雀の脚/兎の跳躍/蓮の葉
●女性からの愛情表現の見抜き方
愛の技術
インドの愛の指南書『カーマ・スートラ』は、有名なわりに意外と読まれていない。一般には性愛の体位を集めたいわゆる四十八手の指南書のように誤解されているが、その論ずるところはもっとはるかに深い。『カーマ・スートラ』が西欧に紹介されてから100年ちょっと経つわけだが、いまだに誤解されたままであり、ポルノグラフィーなみに扱われることが多いのが現状だ。しかし、まず最初にお断りしておかなければならないが、『カーマ・スートラ』で語られているのは「愛の技術」である。人間同士が出会って、お互いに言葉を交わし、魅かれ合い、愛し合うための手引書とでもいうべきものなのである。――<本書より>

日本語の森を歩いて
講談社現代新書
日本で暮らして4半世紀のフランス人言語学者フランス・ドルヌ。彼女の目には「行ってきます」「痛っ!」「助けて!」なにげない普通の日本語の背後に深い働きが見える。2つの言語を合わせ鏡に、夫・小林康夫との対話からうまれた日↔仏往復言語学。
水ではなく「お湯を沸かす」のはなぜ?
「よく来たね」の「よく」は何が良いの?
「ねぇ、貸して」の「ねぇ」って何?
「すごいよな」はOKで「すごいねな」はNG?
「しまった!」「ちょっと待った!」は過去形?
発話からはじめて……
あるひとつの個別言語は、それを学ぼうとする外国人にとっては、未知の規則によって支配された不思議な現象として現れます。(中略)どの日本人にとっても、あまりにもあたりまえで、いかなる不思議からも遠そうな「行ってきます」という表現が、とても不思議なものと映ります。自分の母語による関係網の形成の枠のなかにうまくおさまらないものがあると感じる。そこに日本語固有のローカルな表現があると見るのではなく、そこには自分の母語にはそのままの形で現れてはいないが、しかし別の回路を通ってつながっているような一般化可能な関係設定が現れているのではないか――それが探究の出発点なのです。――<本書より>

子の世話にならずに死にたい
講談社現代新書
介護、葬式、そして墓…「娘だけ」の家ではどうするか?自由葬を行うには?夫側の墓に入りたくない!継承者のいらない墓とは?老後と死後の自立のために
「子が世話して当然」から「子の世話になりたくない」へ
人が老いて死んでいくためには、精神的な「安心」と「安全」なシステムの両方の要素が必要である。かつての「家」には、子や孫に精神的に支えられる「安心」と、家の内部で介護や死者祭祀を担っていくという「安全」なシステムの両方が備わっていた。現在は後者が社会化し、家族の役割は精神的な「安心」を与える方に、より力が注がれている。(中略)「死後」の死者祭祀にも「子の世話にならない」という同様な意識が見受けられるようになってきた。死者本人には、自分の遺体の処理はできない。それを担ってきたのは「遺族」と呼ばれる人たちである。しかしこの「死者と遺族」の関係が刻々と変化を見せている。――<本書より>
実行のための関係団体連絡先リスト付き!
●樹木葬
●桜葬
●散骨
●墓のリフォーム・引越し
●遺骨の手元供養(器/アクセサリー)
●生前契約

昭和零年
講談社現代新書
20歳になった 日本が敗けた
戦争から平和へ 貧困から飽食へ 「ふたつの国」を生き抜いた1925年=昭和零年生まれの30人が戦後60年に贈る痛切の証言!

和田の一三0キロ台はなぜ打ちにくいか
講談社現代新書
打たれないストレートを投げよ!
こうすれば、あなたも速くなる?!これが和田毅の秘密だ!
(特別付録)卒業論文全文掲載!
甲子園ベスト8投手として早稲田大学進学。入学時には130キロも出なかった左腕は、学生トレーナー・土橋恵秀と運命的に出会う。2人3脚のハードトレーニングで、球速は半年で140キロを超えた。江川卓氏の持つ東京6大学の奪三振記録を更新して、プロ入り。多くの打者が「なぜ打てないのか」と首をかしげる独特の球質の正体とは何か。「まだ、本当に納得できる1球を投げたことがない」という高い志の向かう先には何があるのか。野球の現場の息づかいが聞こえてくる、野球好きによる野球好きのための力作!
バットの上を通るボール
しかしながら、彼の球速は、たまに140キロを超えることはあっても、そのほとんどが130キロ台の後半にすぎない。野茂英雄や佐々木主浩のようなものすごいフォークボールがあるわけでもない。同い年のライバルである松坂大輔(西武ライオンズ)が150キロ台の豪速球で三振の山を築いているのとは、あまりに対照的なピッチングスタイルなのである。しかも、プロ入り1年目は14勝で新人王、2年目もアテネ五輪に参加したことで約1ヵ月間ペナントレースを欠場しながら10勝をあげた。2004年の被安打率2割2分8厘はパ・リーグの最小――。つまり、リーグでもっとも打ちにくいピッチャーだったということだ。「あの130キロ台のボールで、なぜ?」――<本書より>

「身の丈起業」のすすめ
講談社現代新書
それでも独立したい人へ
「自分に合った仕事」へのAtoZ
自分の「身の丈」に合ったリスクを取る
取れるリスクのレベルは人それぞれです。人にはそれぞれ「リスク許容度」というものがあります。体力の衰えている人に強い薬を打ってはいけないように、リスクを取る懐が浅い人は大きなリスクを背負ってはいけません。最初はローリスク・ローリターンから始めればよいのです。(中略)最近は、「中小企業挑戦支援法」とかなんとかいって、資本金1円でも会社が作れてしまい、銀行も中小企業育成とかなんとかいってお金を貸してくれますが、借金をすると、事業を畳むことができなくなりますから、実力からいって許されるリスク許容度以上の負債を背負い込んでしまうことになります。日本の起業家が、アメリカと比較してどうも軽やかでなく、悲壮感が漂うのは、実力以上にお金を借りることができてしまう日本の金融風土によるところ大でしょう。――<本書より>
起業なんてうまくいくわけないと思っているあなたに
●自分にとって「嫌なこと」は何なのかを見つめる
●いいこと貯金をする
●会計の勉強をしておく
●スローなモードに染まらない
●(起業直後は)理不尽を許容する
●(最初は)法人化にこだわらない
●「人・モノ・金」ではない
●頭の中身を現金主義にする
●「バズワード」に逃げこまない
●たとえば、毎日掃除しましょう
●「飽き」に負けない
などなど、リスクを減らして成功するヒントが満載!

女帝の古代史
講談社現代新書
画期的論考!「女性天皇」はなぜ必要だったか
女帝の本質
古代日本における女性統治者の歴史的変遷をふまえて、女帝(王)の本質を考えねばならない。すると、通説のように女帝(王)を単なる中継ぎとしてはとらえ切れないことが了解できるだろう。なかでも、記紀に最初の女王として明記された推古は、むしろ彼女自身の資質が評価されて大王に推戴されたわけである。また、皇極の場合もその子の中大兄王子が次に即位するとは、必ずしも約束されていたわけではなかった。単なる中継ぎとしての女帝は、持統天皇が律令天皇制下の皇位継承ルールとして嫡系継承を実現して以降の、元明・元正の2女帝のみに限定されるのではないだろうか。――<本書より>

「特攻」と日本人
講談社現代新書
7000名に及ぶ特攻戦没者。長い間、政治的なバイアスがかかり、彼らの真意は伝えられなかった。志願か、命令か。英霊か、犬死にか。主導したのは海軍か、陸軍か――昭和史研究の第一人者が、残された遺書・日記を丹念に読み解き、特攻隊員の真意に迫る。
昭和史最大の「悲劇」を問う!
7000名に及ぶ特攻戦没者。長い間、政治的なバイアスがかかり、彼らの真意は伝えられなかった。昭和史研究の第一人者が、遺書・日記を新しい視点から読み解く
志願か、命令か。英霊か、犬死にか。主導したのは海軍か、陸軍か。
――昭和史研究の第一人者が、残された遺書・日記を丹念に読み解き、特攻隊員の真意に迫る。

自我の哲学史
講談社現代新書
デカルト、カント、ライプニッツからハイデッガー、レヴィナスまで…宮沢賢治や西田幾多郎の自我論とは?
日本人に自我はいらない!
重荷になった自我
あらかじめ見通しをいえば、われわれが通常、社会生活で是とする自我概念は、基本的には西洋近世の自我概念の上に成り立っており、日本人は近代化においてそれを受容したのである。しかし元々それは体型に合わないスーツみたいなものではなかったか。それが露わになりだしたのが、今日の思想的・社会的・文化的状況なのではないだろうか。自我が主体として、自由と責任の担い手たらんと意識することが、かならずしも人間の自己解放を意味するとは断定できまい。もしかしたら自我の確立は幸福のための絶対的な条件ではないかもしれないのだ。――<本書より>

現代小説のレッスン
講談社現代新書
村上龍、村上春樹、高橋源一郎、保坂和志、阿部和重、舞城王太郎、いしいしんじ、佐川光晴、水村美苗…
ブンガクはこう読め!

反米の世界史
講談社現代新書
ハワイ革命からソヴィエト、キューバ、ベトナム、イラン、イラクそして安保闘争まで
アメリカの大義の裏側!
世界の実像に迫る「郵便学宣言」
良くも悪くも、われわれ日本人は、基本的に、アメリカを中心とした西側経由で世界の情報を得ている。したがって、その是非善悪は別として“反米国家”(ないしは反西側国家)の主義主張に情報として接する機会は、アメリカの“大義”を見聞きするのと比べると、きわめて限られているというのが実情だ。それゆえ、われわれの日常生活に身近な切手や郵便物を通じて、彼らの側から見た“アメリカ”の歴史を、具体的なモノの手触りをもって示すことができれば、それは、読者の視野を広げる上でも有用な結果をもたらすことになるだろう。同時に、郵便学者である筆者としては、切手というフィルターを通じて、新事実の発見や歴史的事実の新解釈という点でのオリジナリティはともかく、いささかなりとも従来とは異なった視点からの歴史絵巻を展開することができれば、これに勝る喜びはない。――<本書より>

トヨタモデル
講談社現代新書
世界を制した「哲学」の全貌
不死鳥のような再起
トヨタ自動車がこのように、いったんは倒産の危機に追い込まれながら、不死鳥のように立ち直り世界一になろうとしている一番の秘訣は、いつも危機感を社員に与えて改善に取り組んでいることである。奥田碩会長の「変えないことは一番悪いことである」という言葉であらわされているように、いつも前進するという意識が7万人の社員に叩き込まれている。また、「車を作ることは人作りをすることである」という張富士夫副会長の考え方もこの危機感から来ている。――<本書より>

テレビアニメ魂
講談社現代新書
あの感動と笑いには理由があった!
●星飛雄馬は、最終回で死ぬはずだった。
●『オバケのQ太郎』は人気絶頂のときに打ち切られた。
●苦しくったって…の歌詞は二日酔いの男が作った。
●消える魔球の謎を考えるための合宿が行われた。
●『天才バカボン』は再放送のほうが視聴率が高かった。
●宮崎アニメの秘密は「動画枚数」にある。
●『ベルサイユのばら』監督は声優に交代させられた。
●素人が描いた顔1枚だけが原作のアニメがある。
テレビアニメの「へぇ」満載!
ゼロから作る苦しみ
なぜそんなに悩むことがあるのか?読者はそう思うかもしれない。原作に忠実に作ればいいだけじゃないか、と。たしかに、皆さんご存じのとおり『巨人の星』には原作がある。『週刊少年マガジン』連載、原作・梶原一騎、作画・川崎のぼるによる劇画『巨人の星』は、これも劇画史上に残る不朽の名作である。なにもわれわれが苦悶しながら別のストーリーをひねり出さなくても、原作を忠実にシナリオにすればいいに決まっている。だが、ないのである。忠実にシナリオにしようにも、その原作が……。――<本書より>

道路の経済学
講談社現代新書
アクアラインは800円でよい!
「必要な道路」「ムダな道路」はどう見分けるのか?よくわかる公共投資分析
日本の公共事業を「民営化」するために
道路公団が保有・管理してきた高速道路には、「ネットワーク型」と「バイパス型」があります。まずはバイパス型の道路資産の一部について、改良・維持管理・料金徴収などの運営事業を、民間企業に売却するのです。たとえば、東京―名古屋間は東名と中央高速が並行していますが、どちらかを(バイパスとみなして)民間に売却し、官と民の競争を促進させるのです。そのとき、私はDBFOやBOTの考え方を採り入れることを提案します。一定の契約期間ののちに国に無償で返還させ、以後は無料道路とするわけです。ネットワーク型の場合も、工夫次第で売却は可能でしょう。――<本書より>
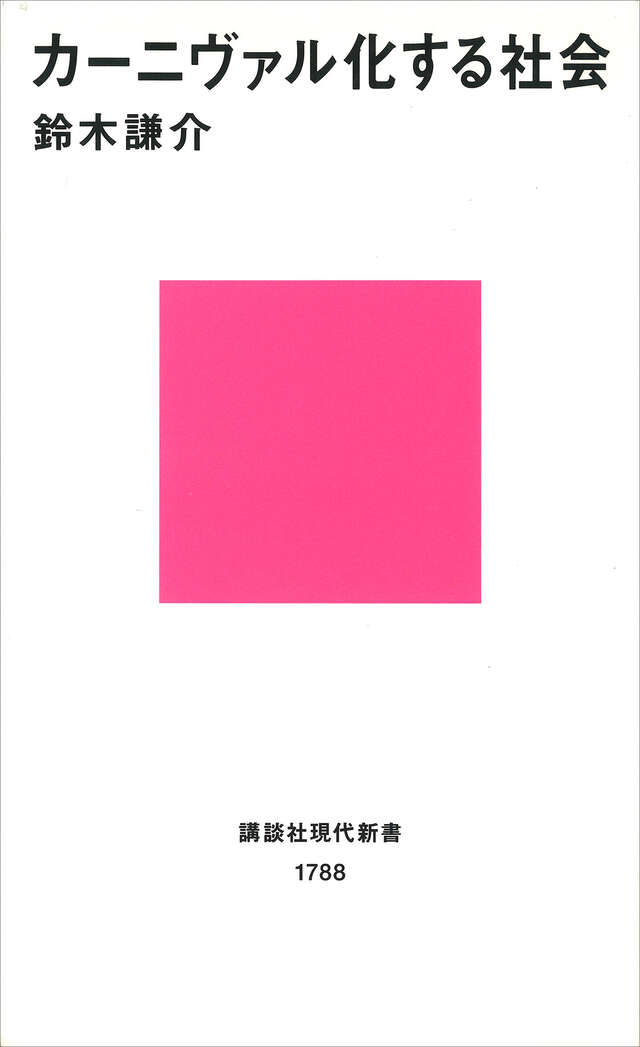
カーニヴァル化する社会
講談社現代新書
2000年代の若者達のリアルを鮮かに斬る。「やりたいこと」を探し続けるニートたち、自己確認をするデータベースとしての監視社会、そして「ケータイ依存」。これらを支える社会のメカニズムを分析する。
分断される自己イメージ、データベース化する人間関係…
ネット世代の論客が解き明かす「僕たちの日常」
「日常の祝祭化」の中を生きる
私たちの生きる社会は、上述してきたような「祭り」を駆動原理にし始めているのではないか、と私は考えている。本書では、そうした祭りのメカニズムについて、様々な事例に分け入りながら明らかにしていきたい。祭りといっても、季節とともに訪れる、伝統的な祝祭のことではない。21世紀に入って以降の我が国で、そしておそらく欧米では20世紀の終わり頃から顕在化し始めた、日常生活の中に突如として訪れる、歴史も本質的な理由も欠いた、ある種、度を過ぎた祝祭について、それはいったい何なのか、なぜ今になってそうした祭りが頻発するのか、といった問題を、様々な角度から論じたのが、この本である。結論を先取りして述べることになるが、私が本書で論じる「日常の祝祭化」は、近代化と、そしてその徹底として生じる「後期近代」に特有な現象として説明することのできるものだ。また、そうした「日常の祝祭化」の中を生きる私たちのライフスタイルも、これまで近代のシステムが前提にしてきた、確固たる自己像とはまったく異なった種類の自己モデルを要請し始めている。本書で取り扱うのは、こうした、日常に祝祭がビルトインされることによって可能になる、社会や自己の仕組みや、その要因についてなのだ。――<本書より>

人生に意味はあるか
講談社現代新書
本気で考え始めると、抜け出られなくなってしまいそうで、何となく、怖い。そんな気がして、あまり考えないようにしてきた、という方も、少なくないようです。……そんなあなたがこの問題について真剣に考え抜き、そして、心の底から納得できる「人生のほんとうの意味と目的」を探し求める旅に出るための、ガイドブックのような本です。――<本文より>
文学、心理学、哲学からスピリチュアリティまで
これが「答え」だ!
人生の「目的と意味」は何か?
本気で考え始めると、抜け出られなくなってしまいそうで、何となく、怖い。そんな気がして、あまり考えないようにしてきた、という方も、少なくないようです。……そんなあなたがこの問題について真剣に考え抜き、そして、心の底から納得できる「人生のほんとうの意味と目的」を探し求める旅に出るための、ガイドブックのような本です。――<本文より>

自民党と戦後
講談社現代新書
「50年」の意味を問う
政治部記者の目で描く長期政権の成功と限界
自民党は日本人そのものの姿
敗戦から立ち上がるときのたくましさ、高度経済成長を支える勤勉さ、冷戦構造の枠内で、できることなら血を流したくないという平和志向。その一方で、冷戦とバブル経済が崩壊した後の激動に十分対応しきれない保守性。自民党は、日本人そのものといってもよい特性を持っている。その自民党も、結党から半世紀を経て多くの点で限界を見せるようになってきた。それは、戦後半世紀余にわたり成功体験を重ねてきた日本の限界とも重なる。この機会に自民党という巨象を、さまざまな角度から眺めてみようというのが本書の狙いである。――<本書より>

はじめての金融工学
講談社現代新書
天候デリバティブって何?経済物理学とは?
これならわかる金融工学の基本理論
正直に告白しますと、私は文科系の出身ということもあり、ある時期までは、経済や金融の勉強をしていて、難しげな数式を伴った理論に出くわすと、どうしても「引いて」しまいがちでした。それだけに、かつての私のような人が、一見難しそうなイメージのせいで金融工学に近づこうとしないことは、容易に想像できます。しかし金融工学は、順を追って学んでいけば、決して難解なものでも、取っつきにくいものでもありません。世界のさまざまな動きに直接結びつくと同時に、知的な好奇心も満足させる、実にスケールが大きくて刺激的な考え方、それが金融工学なのです。――<本書より>
金融工学はこう考える/1+1<2の不思議な世界/都合のよい前提条件/タダ飯はない?/わかりやすい統計と確率の話/人間は本当に合理的か/リスクって何だ?/正規分布を疑う

数学的思考法
講談社現代新書
数学で学ぶ考え方のなかには、経済やビジネスだけでなく、社会問題であれ政治的問題であれ、身のまわりのさまざまな問題を考えるときにヒントになるものがたくさんある。そして「説明力」においても、算数や数学で学んだ論理性が大いに役立つはずだ。数学者の立場から、そうした思考と説明の技術やヒントをふんだんに紹介しようというのが本書の主眼である。
もっと試行錯誤を!!本当に考えるためのレッスン
試行錯誤のすすめ
数学で学ぶ考え方のなかには、経済やビジネスだけでなく、社会問題であれ政治的問題であれ、身のまわりのさまざまな問題を考えるときにヒントになるものがたくさんある。そして「説明力」においても、算数や数学で学んだ論理性が大いに役立つはずだ。数学者の立場から、そうした思考と説明の技術やヒントをふんだんに紹介しようというのが本書の主眼である。ただ、その入り口として、現在の算数・数学教育の抱えている大きな問題を是非とも指摘しておかなければならない。考える力を養い、論理的な説明力をはぐくむために必要なことが、そこではまったくなおざりにされているからである。――<本書より>