講談社現代新書作品一覧

ソシュールと言語学
講談社現代新書
現代思想の原点がここにある
コトバの本質を問う「ソシュール以後」の軌跡
ソシュールが挑んだコトバの謎
深く考えてみるまでもなく、音声と概念とはまったく性質が違うものです。音声は波ですから見たり触ったりすることはできないにしても、とにかく物理的な実体であるのに対し、概念は決して物理的な実体とは言えません。それなのに、私たち人間がコトバを使う時には、その似ても似つかない2つのものを対応させています。しかも、その対応のさせ方は、同じ言語を使う人々であればまったく同じなのです。もちろんだからこそコトバを使って意味の伝達ができるようになっているのですが、これほど性質の異なる2つの要素を、同じ言語を使う人々がどうして正しく結びつけることができるのかは、考えてみれば不思議なことです。――<本書より>

中国文明の歴史
講談社現代新書
もっとも平易でコンパクトな中国史の入門書。中国とはどんな意味か、そしていつ誕生したのか? 民族の変遷、王朝の栄枯盛衰や領土拡大を軸に、中国の歴史をわかりやすく教える。まったく新しい中国史の登場。(講談社現代新書)
もっとも平易でコンパクトな中国史の入門書。中国とはどんな意味か、そしていつ誕生したのか? 民族の変遷、王朝の栄枯盛衰や領土拡大を軸に、中国の歴史をわかりやすく教える。まったく新しい中国史の登場。
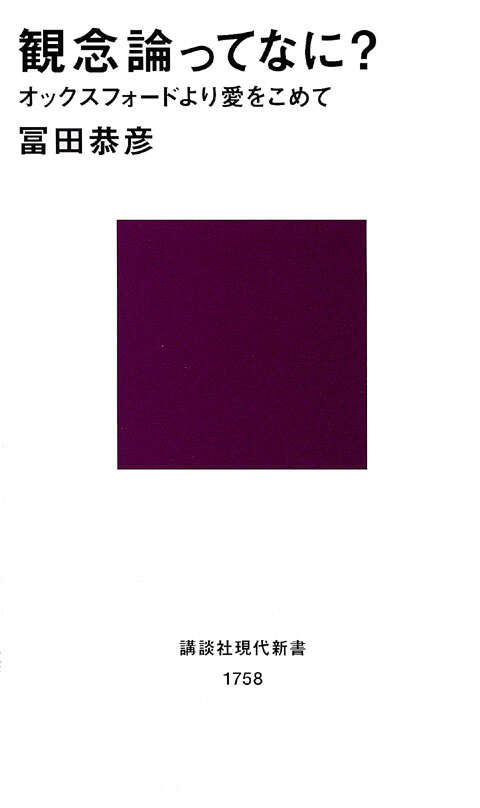
観念論ってなに?
講談社現代新書
バークリやロックの議論を現代的問題に接続するゆかいな哲学対話
この世界はすべて心の中の観念からなる?!
はじめに
いまどき、なぜ観念論なのかとお思いの方もおいででしょう。観念論?それって、この世界は心の中の観念からなるっていう考えだったかな?そういえば、バークリとか、フィヒテとか、ショーペンハウアーとか、なんとなくそんな名前は連想するけど……。もしかして、その昔、唯物論者がとことん排除しようとした立場じゃない?でも、バークリは、マッハやアインシュタインの先駆者だって話も、どこかで聞いたことがあるような……。確かに、観念論というのは、なんとなく知的興味をかき立てられはするものの、そもそもそれがどういうものなのか、なぜそんなものができあがったのか、また、それがなぜいまどき持ち出されるのか、どうもよくわからない。そう思われる方が、多いのではないでしょうか。――<本書より>
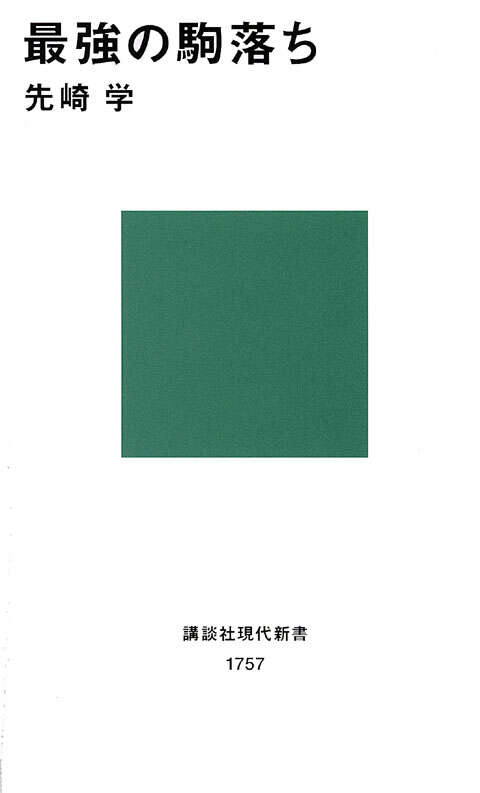
最強の駒落ち
講談社現代新書
駒落ちは自由だ!
すべてのファンの願いをかなえる新手・奇手満載
絶対勝ちたい下手に
●六枚落ち四間飛車戦法
●四枚落ち先崎流弱いふり向かい飛車
楽しく指したい上手に
●八枚落ち灘流必勝定跡
●二枚落ち金銀逆形作戦
ほか21世紀の駒落ち新戦法がズラリ!

経済学のことば
講談社現代新書
経済学の歴史がこれ1冊で見渡せる!
本書に登場する経済学者
ペティ/ステュアート/カンティロン/ケネー/スミス/マルサス/リカード/ミル/マルクス/ジェヴォンズ/メンガー/ワルラス/マーシャル/ヴィクセル/ヴェブレン/ヴェーバー/シュンペーター/ケインズ/ハイエク/ロビンズ/ヒックス/ロビンソン/サムエルソン/カレツキ/ハロッド/ガルブレイス/フリードマン/カルドア/コース/ボワイエ/セン/ベッカー/スティグリッツ/クルーグマン
経済学史は「宝の山」
以前、(中略)私は、経済学史を「宝の山」にたとえたが、世の中の経済学に関する言説を一瞥すると、その「宝の山」をいまだに活かしきっていないような感想を抱いてきた。そこで、改めて古今の経済学の名著を頭の中に浮かべながら、それらの面白さを読者に伝えられないものかと思い、本書の執筆を決意した。――<本書より>

うつ病をなおす
講談社現代新書
分かってきたことは、うつ病の本質は絶望にあるのではないことである。絶望は病気ゆえに感じる「症状」であって、症状である以上、医学的な治療が解決の切り札になる。そしてまた、うつ病の治療態勢はここ10年で見違えるほど整備されてきているのだ――<本文より>(講談社現代新書)
もっとも信頼される名医が教える最新治療法。うつ病の治療体制はこの10年で目覚ましく進歩した。さまざまなケーススタディを基に、うつ病の種類・治療薬・病気のメカニズム・性格改善法をやさしく教える。

タブーの漢字学
講談社現代新書
性の話、トイレの話……
はばかりながら読む漢字の文化史!
「性」にまつわる漢字
かりに私たちがまだ文字のない時代に暮らしているとして、王様から文字を作る仕事をあたえられた、と仮定してみよう。(中略)王様から作成を命じられたのが、もしも「一人前の立派な男」という意味を表す文字だったら、あなたはいったいどうするだろうか。男の子が成長し、一人前の立派な男性になったことを文字で示すには、いったい何で表現すればいいだろう。なにを使うかは、人によってまちまちである。現代人ならば、それをスーツにネクタイという姿で表現する人もいるだろうし、引きしまったたくましい肉体のイメージで、一人前の男をとらえる人もいるだろう。そして中には、そんなの「男のシンボル」でしか表現できないじゃないか、とニヤニヤしながら考える人もいるにちがいない。――<本書より>

「家計破綻」に負けない経済学
講談社現代新書
年収100万円台が急増 賃金デフレが止まらない
人生の備えありますか!?
●景気回復の分配は受けられない
●強者に都合のよい「改革」
●量産される低所得者層
●退職金税制見直しの狙いとは
●ハゲタカのビジネスモデル
●ダイエー「処理」の不可解さ
●「借金鬱」に陥らないために
●これからの運用・投資の鉄則
●小さなところから始めるビジネス
●年金改悪で老後が崩壊する
●消費税アップは不要だ
●働くという選択肢
中流層の家計が破壊される
家計の危機を過剰に恐れることはむしろ危険ですから、私は不安を煽ろうとは毛頭考えていません。ただ、深刻なデフレ不況が続くなか、私たち国民の家計にどんなリスクがあるのかを冷静に見つめ、備えをしておくことはどうしても不可欠です。また、おいおい説明していきますが、現在進行している「構造改革」が国民をどんな経済社会へ導こうとしているかということも、考えておかなければなりません。政府が打ち出す政策は、とくに中所得層の家計に直結するものだからです。――<本書より>

文系のための数学教室
講談社現代新書
数式は「眺め方」さえわかればこわくない! 数学アレルギーはもったいない。微分積分や確率統計の「読み方」から、経済学、政治学、論理学、哲学がもっとおもしろくなる数学的思考をわかりやすく伝授します。

仏教発見!
講談社現代新書
奈良の唐招提寺に伝わる鎌倉時代の釈迦如来像の像内には、心ひかれる文書が納められている。「必ず必ず、これらの衆生より始めて、一切衆生、皆々、仏となさせ給へ」とあり、その左に多数の名前が列記されているのだが、人の名前に交じり、クモ・ノミ・シラミ・ムカデ・ミミズ・カエル・トンボ・カなどの名も書かれている。――<本書より>
思わず誰かに話したくなる仏教の真髄
知っているようで知らない……これが仏教だ!
●お釈迦さまは何をさとったのか?
●さとればそれでよいのか?
●「縁起」とは?「慈悲」とは?
●ノミもシラミもみな仏?
●なぜ大仏はつくられたのか?
●仏教は「真理」を主張しない?
人間と塵を平等とする思想
奈良の唐招提寺に伝わる鎌倉時代の釈迦如来像の像内には、心ひかれる文書が納められている。「必ず必ず、これらの衆生より始めて、一切衆生、皆々、仏となさせ給へ」とあり、その左に多数の名前が列記されているのだが、人の名前に交じり、クモ・ノミ・シラミ・ムカデ・ミミズ・カエル・トンボ・カなどの名も書かれている。自分たちと同じく、ノミやシラミも仏になることを願った人が、かつて日本にいたのである。(中略)ノミもシラミも仏になれという発想は、仏教によらなければ決して生まれてこないと私は思っている。――<本書より>

中国語はおもしろい
講談社現代新書
中国語作家として活躍する著者が、中国語の魅力を語る。中国語を知ることは、世界中に伸びる華人ネットワークへのパスポートを手にすることだ。豊富な経験をもとに上達のコツ、言葉を知ることで広がる世界をガイドする。
実践的上達法から複眼思考の身に付け方まで中国語を知るとこんなに世界が広がります
中国語世界の広がり
中国人の世界にあっては、みんな普通話で何とか渡りきろうとし、実際に渡りきるのである。(中略)訛りなんてあって当然、なかったらかえって怪しまれる。日本語のことわざにも「訛りは国の手形」というではないか。手形といったら証明書、パスポートである。それで東は東シナ海から西はシルクロード・チベットまで、北はロシアとの国境から南はベトナム国境まで。サンフランシスコのチャイナタウンからボルネオの熱帯雨林まで。どこでも大丈夫、何とか渡りきれるのが中国語の世界というものなのである。(中略)広い中国、お互いの方言ではまったく通じない。だからこそ、必死に標準語で伝えようとする。その結果、訛りがあっても、間違っても、たいていは通じる。理解しあえる。なぜなら、わかろうという意志が強く働くからなのだ。――<本書より>

自由とは何か
講談社現代新書
「自由に倦んだ」時代に問う、渾身の論考! 自己責任や援助交際、殺人を巡る議論など、自由にまつわる問題に様々な角度から切り込み、現代社会・思想が陥っている「自由のジレンマ」を乗り越える方法を探る。(講談社現代新書)
「自由に倦んだ」時代に問う、渾身の論考! 自己責任や援助交際、殺人を巡る議論など、自由にまつわる問題に様々な角度から切り込み、現代社会・思想が陥っている「自由のジレンマ」を乗り越える方法を探る。

公会計革命
講談社現代新書
政治家よ、官僚よ、目を覚ませ!
日本を破綻から救う革命的意思決定システム!
●国民は政府の「顧客」ではなく「主権者」だ
●将来世代へのツケ回しをどう減らす?
●20XX年の内閣総理大臣の仕事
●日本は財政破綻するのか
●あの公共事業官庁の予算をシミュレーション!
●公会計は世界の経済と歴史を変える
国ナビとは何か
まず、「国家とは誰のものか。国家というシステムは、誰のためにあらねばならないのか」という問いを立ててみよう。言うまでもなく、その回答は「国民」以外にはないはずだ。(中略)つまり、国家の実質的所有者である国民がその経営を政治家にゆだねても、政治家が自分勝手な経営をしたり、私腹を肥やしたりしないようチェックするシステムが必要になるのだ。それが国ナビであり、民間企業において、会社の実質的所有者である株主が、経営を委任している経営者をチェックするために企業会計を利用する姿に重なるだろう。――<本文より>

生きづらい<私>たち
講談社現代新書
もはや一億総「心に穴が空いている」状態。若者どころか現代の日本を広く被う「生きづらさ」、心が安直に悲鳴をあげてしまうメカニズムとその裏にあるものに切り込み、それでも現実と折り合う道を模索する。(講談社現代新書)
もはや一億総「心に穴が空いている」状態。若者どころか現代の日本を広く被う「生きづらさ」、心が安直に悲鳴をあげてしまうメカニズムとその裏にあるものに切り込み、それでも現実と折り合う道を模索する。

中国の大盗賊・完全版
講談社現代新書
秘かに待望されてきた幻の完全版ついに刊行。名著のほまれ高い『中国の大盗賊』で割愛されていた150枚を完全収録。陳勝や高祖から毛沢東まで、縦横無尽に活躍する「盗賊」の姿を活写する中国史の決定版! (講談社現代新書)
秘かに待望されてきた幻の完全版ついに刊行名著のほまれ高い『中国の大盗賊』で割愛されていた150枚を完全収録。陳勝や高祖から毛沢東まで、縦横無尽に活躍する「盗賊」の姿を活写する中国史の決定版!

私・今・そして神
講談社現代新書
私はなぜ「今ここにいる、この私」なのか。古来より数多くの哲学者が最大の関心を寄せてきた「神、私、今」の問題について、まったく独自の考察を展開。自分の言葉だけでとことん哲学する、永井均の新境地。(講談社現代新書)
私はなぜ「今ここにいる、この私」なのか。古来より数多くの哲学者が最大の関心を寄せてきた「神、私、今」の問題について、まったく独自の考察を展開。自分の言葉だけでとことん哲学する、永井均の新境地

幸福論
講談社現代新書
生きていく辛さから逃れ得たら幸福だろうか? 停滞した時間、閉じた世界にある「充足に似たもの」は脆く表面的なものだ。世界と自分と現実とをリンクさせ、ささやかな日常を味わって生きる、大人な人生論。 第1章 幸福の1ダース 第2章 不幸の中の幸福 第3章 幸福と不幸との間 第4章 断片としての幸福 第5章 散歩者の視線
「風邪をひいたわたし」がなぜいいか
幸福の断片を味わう生き方!

漱石と三人の読者
講談社現代新書
漱石がわかる。小説がわかる。近代がわかる――画期的な文学入門書の登場! 漱石の作家活動とは読者との闘争だった! 新聞小説の読者である大衆をどう喜ばせるか。本郷文化人に自らの小説観をいかに伝えるか。漱石は作品ごとに大胆な実験を次々と行なった──。
小説は実験である!
あなたは漱石のたくらみを知っているか
漱石がわかる。小説がわかる。近代がわかる。――画期的な入門書の登場!
漱石の読者体験
まず、デビュー作の『吾輩は猫である』では自らを戯画化して書いているが、まだ素人作家だった漱石にも、自分が抱えていた鬱憤をそのまま吐き出しても読者には受け容れられないことぐらいはわかっていたのである。しかし、これはごく素朴な読者意識でしかなく、この時の漱石はまだごく身近な「顔の見える存在」に向けてしか書いてはいない。(中略)朝日新聞社の専属作家となった漱石は、入社第1作『虞美人草』によって手痛い失敗を体験した。読者は、漱石が「殺す」つもりで書き込んだ藤尾というヒロインを熱烈に支持したのである。――<本文より>

教育と国家
講談社現代新書
「愛国心」教育のウソを衝く!
戦後教育悪玉論
教育基本法を改正すれば教育がよくなると言う論者は、学校教育の意味をまったく問い直さず、かつてうまく機能していた(と彼らが思っている)学校制度をそのまま復活させれば子どもがよくなる、と思いこんでいる。しかし、今日ではむしろ近代の学校制度そのものが新たな社会環境、メディア環境によって問い直されているのです。そこにかつてなかった学校現場の現象も生じてきているのですから、教育基本法は学校教育制度を自明の前提としているという面では問い直されるべきですが、それは現在の改正論とはまったくレベルの違う問題なのです。――<本文より>

武士道の逆襲
講談社現代新書
武士道とは本当はどんな思想なのだろうか。ブームのようになっている武士道は、実は明治以降に作られたイメージにすぎない。「甲陽軍鑑」「葉隠」など重要文献を読みなおし、日本思想としての武士道を解明。(講談社現代新書)
武士道とは本当はどんな思想なのだろうか。ブームのようになっている武士道は、実は明治以降に作られたイメージにすぎない。「甲陽軍鑑」「葉隠」など重要文献を読みなおし、日本思想としての武士道を解明。