講談社現代新書作品一覧

スピノザの世界
講談社現代新書
スピノザの思想史的評価については多くのことが言われてきた。デカルト主義との関係、ユダヤ的伝統との関係。国家論におけるホッブズとの関係。初期啓蒙主義におけるスピノザの位置。ドイツ観念論とスピノザ。現代では、アルチュセール、ドゥルーズ、ネグリ、レヴィナスといった名前がスピノザの名とともに語られる。スピノザはいたるところにいる。が、すべては微妙だ。――<本書より>
神は制作者ではない。神にも人間にも自由な意志は存在しない。
すべての事物を必然ととらえたスピノザ哲学の魅力!
スピノザの思想史的評価については多くのことが言われてきた。デカルト主義との関係、ユダヤ的伝統との関係。国家論におけるホッブズとの関係。初期啓蒙主義におけるスピノザの位置。ドイツ観念論とスピノザ。現代では、アルチュセール、ドゥルーズ、ネグリ、レヴィナスといった名前がスピノザの名とともに語られる。スピノザはいたるところにいる。が、すべては微妙だ。たしかにスピノザについてはたくさん言うべきことがある。そのためにはスピノザの知的背景と時代背景、後代への影響、現代のスピノザ受容の状況を勉強する必要がある。けれども、まずはスピノザ自身の言っていることを知らなければどうしようもない。そのためには、スピノザがどこまで行ったのか、彼の世界を果てまで歩いてみるほかない。彼が望んだようにミニマリズムに与し、彼の理解したように事物の愛を学ぶほかないのである。――<本書より>

受験勉強の技術
講談社現代新書
生涯役立つ「ノウハウ学力」を身につける 脳を鍛える勉強法!
●覚えた内容(コンテンツ)よりも、覚える能力(ノウハウ)を伸ばせ!
●「受験戦争は心に悪い」のウソ!
●目標に特化した勉強法とは?
●出力トレーニングのすすめ
●暗記と理解のバランス
●記憶力を高め、記憶を残す方法
●やる気をどう維持するか?

世界のイスラーム建築
講談社現代新書
煌めく宮殿から発掘遺構まで イスラーム建築で世界一周!
イスラーム建築に魅せられて
このとき、私を強く捉えたのは……外からは想像さえつかない、今まで体験したことのないような空間であった。仰ぎ見れば、天井には連なるアーチの列が交差し、頭上に架かるドームを導いていた。どうしたらこんな形ができるのかと、アーチの数を数え、幾何学と建築の関係の深さにため息をついた。……イスラーム教を信ずる人々は、7世紀から今日まで、ユーラシア大陸のスペインから東南アジア、さらには日本やアメリカまで、長い時代にわたって、そして広い地域に、その足跡たる建物を残している。茫漠たるイスラームの広がりのなかで、私が垣間見た建造物はごくわずかな片鱗にすぎない。とはいえ、なるべく私が自分で実際に訪れたことのあるものを主軸にして、イスラーム建築の秀作を紹介したい。――<本書より>
イスラームの歴史と美学が結実した名建築
カーバ神殿/預言者のモスク/アル・ハンブラ宮殿/フェズの旧市街/岩のドーム/ガーワーン学院/トプ・カプ宮殿/ヤサヴィー廟/王の広場/西安の清真寺/イスファハーンのバーザール/クアラルンプールのモスク/ウマイヤ・モスク/東京ジャーミ/サーマーン廟

鉄理論=地球と生命の奇跡
講談社現代新書
生命誕生は鉄のおかげ!? 鉄が進化を演出した!? 地球温暖化は鉄で解決できる!?
鉄の奇跡
人類が金属の鉄を使いだしたのは、たかだか5000年前のことにすぎない。しかし元素としての鉄は、40億年前に生命が誕生したときから、生命になくてはならないものであり、その後の生命の発展を陰で演出してきた、と言ったらみなさんは驚かれるだろうか。(中略)このいずれの鉄のはたらきも、1つの奇跡的な偶然から生み出された。鉄はすべての元素のなかでもっとも安定な原子核を持ち、その1つの帰結として、地球では質量比でもっとも多い元素である。その鉄が、その持っている電子の数のために、生命にとっても、現代文明にとっても、かけがえない機能を持つ元素となった、という偶然である。このことが、生命の誕生と発展のなかで、またさらに人類文明の展開のなかで、数々の奇跡を起こしてきた。――<本書より>

ほめるな
講談社現代新書
大流行!「ほめる教育」が子どもをつぶす!!!
「ほめる教育」がなぜダメかを指摘し、コミュニケーション重視のインタラクティヴ型支援を提唱する!
人生にとりきわめて貴重な「アモーレ情熱」(内発的動機づけ)をこわす「ほめる教育」
「ほめる教育」では、とにかくすこしでもいいところを見つけてほめるということをするわけです。これを子どもの活動のあらゆる面にたいして行ったら、いったいどういうことになるでしょうか?ほめるという心理的な報酬を、来る日も来る日も繰り返しあたえ続ける。(中略)おまけに、現在の日本では、それに物的報酬や評価が加わります。学校の成績が上がったらなにかを買ってやるなど、子どもにほうびをあたえる家庭のなんと多いことか。そして学校では……「意欲・関心・態度」などという、本来、評価など不可能な、そしてすべきではない面までをも評価の対象にしています。(中略)「ほめる」「ほうびをあたえる」そして「評価する」。この報酬の3点セットに長期間さらされ続けたら、子どもたちのアモーレ情熱はどうなるかは火を見るよりも明らかです。――<本書より>

「日本」とは何か
講談社現代新書
『古事記』に「日本」はない!「倭」「やまと」との関係は?
わたしたちは自己をどうとらえてきたか
日本、日本人、日本語、日本文学等々、当たり前のように、わたしたちは「日本」といい、自分たちをあらわす国の名(国号)として何ら疑わずにいる。しかし、その名がどういう意味をもつかということについて、共通の認識をもっているであろうか。小学校や中学校で、「日本」という名の意味を教えられた(あるいは、いま教えられている)であろうか。……この国は古代から変わることなく「日本」としてあり続けてきた。わたしたち自身のために、わたしたちが自己をあらわす「日本」について考えねばならない。それがどのような意味をもって設定されたのか(古代の「日本」)、どのような歴史をたどってきたのか(歴史のなかの「日本」)ということについて、きちんと見届けることがもとめられる。――<本書より>

『史記』の人間学
講談社現代新書
始皇帝、劉邦、太公望、孔子ら総登場!
不滅の人間ドラマに学ぼう
不滅の歴史書から「人間」を読み解く
『史記』が二千余年を隔てた今日、中国でも日本でも愛読されているのは、文学性とともにこの大衆性に負うところが大きい。いや『史記』の文学性とは、ほとんど大衆性である、といっても過言ではあるまい。日本中世の軍記物語、『保元物語』『平治物語』『平家物語』などには『史記』からの引用、とくに呉越の興亡と漢楚の争覇からの引用が非常に多い。軍記物の読者は日本史の上の興亡と、中国史の主な出来事を重ねあわせて学んだわけであり、それが当時の身分ある人々の教養となっていた。(中略)だが『史記』の注釈書や解説書は非常に多いが、半面『史記』が人間をどう描こうとしたかについての研究書は、武田泰淳氏の労作以外には案外少ないのではないか。あえて蛮勇を奮って「人間学」に取り組んだ次第である。――<本書より>

アメリカ外交
講談社現代新書
超大国の外交政策を見通すための最良の一冊。ブッシュ外交などと言われるが、外交はもちろん時の大統領の性格だけに負うものではない。建国以来、今日にいたるまでの政策を様々な視点から徹底的に分析する。(講談社現代新書)
超大国の外交政策を見通すための最良の一冊。ブッシュ外交などと言われるが、外交はもちろん時の大統領の性格だけに負うものではない。建国以来、今日にいたるまでの政策を様々な視点から徹底的に分析する。

グラフの表現術
講談社現代新書
基本からビジネス分析まで完全対応!
レポート・論文・プレゼンテーション・企画書…これが決め手だ!
なぜグラフを作成するのか
そもそも、なぜ私たちはグラフを作成するのでしょうか。その答えは、どんなときにグラフを作るのか、どんなところでグラフを目にするかを思い出すと、自然にわかるはずです。大まかに言ってしまえば、他人にデータの特徴をわかりやすく伝えるためと、グラフ表現を用いて自分がデータについて理解を深めるためと言えるでしょう(後者については忘れられがちですが、非常に重要です)。これを言い換えると、グラフ表現は、データをさまざまな角度で観察することができたり、多種多様な方法で説明や自分の主張を裏づけたり理解を促したりできるようになるためのものと言えるのです。――<本書より>

西田幾多郎の生命哲学
講談社現代新書
ベルクソン、ドゥルーズとどのようにつながっているか?
純粋経験、自覚、場所、叡智的世界、絶対無、絶対矛盾的自己同一…
西田とは「生命の哲学」である!
西田が論じたひとつのこと
西田の哲学の特徴は、彼が同じことをめぐってさまざまな仕方で議論を展開したことにある。さまざまなテーマを経るといっても、それは、原理的に、ひとつの問題をめぐって、接近する方法を執拗に変更していったことにほかならない。ではそこで、西田が論じたひとつの問題とは、率直にいって何であるのか。それは簡単にいえば、「行為」という方向からこの世界に存在する「私」を考えることであるといえる。そしてそのことは、「生成する世界」とは何かという問いと、必ず表裏一体をなすことになる。「行為する私」と「生成する世界」、それら両者が結びつく地点に、西田が見てとる「現実」が定位される。(中略)生命論としての西田という姿が浮かびあがるのは、こうした視角からである。そこで、生きているこの私と、生成しゆくこの世界とは何であるのかという、生命を論じる根幹のような主題が開かれていくことになる。――<本書より>

微生物VS.人類
講談社現代新書
感染症との戦いの現在・過去・未来
ウイルス性肝炎/エボラ出血熱/炭疽/AIDS/鳥インフルエンザ/O157/レジオネラ症/クロイツフェルト・ヤコブ病/SARS

俳句とエロス
講談社現代新書
草城、子規、漱石から楸邨、ちづこまで
これがエロティシズム俳句だ!
連作俳句「赤い月」
赤い月にんげんしろき足そらす 富澤赤黄男
句集『魚の骨』(『現代俳句三』所収)の中の句です。「赤い月」と題する連作俳句五句中の一句。(中略)赤黄男句は、行為の瞬間の「女」の「足」の動きを描写していますので、一句から受ける印象が、大変エロティックになっています。ただし、不思議に猥褻感は、まったくありません。一句を読んだ後で読者に残るのは、「女」の白い「足」のエロティシズム。この一句は、もちろんのこと、五句全体、時にメタファーを用いながらの、朧化表現によって形象化されていることが、文芸作品としての質を保つことになったのだと思います。――<本書より>

まんが パレスチナ問題
講談社現代新書
なぜ、アラブとイスラエルは争うの?
アリとニッシムが世界の難問をやさしくガイド
旧約聖書の時代から、現代まで。宗教や民族についてもよくわかる!!
いつも「複雑な」と言われる「パレスチナ問題」。宗教や民族という日本人にはなじみにくい概念が問題のベースになっているし、昨日までの味方同士が突然戦争を始めたりして、たしかに、わかりにくいのはたしかです。だからこそ、本書では少しでもわかりやすいように、ユダヤの少年ニッシムとパレスチナの少年アリ、そしてエルサレムのねこ、2人と1匹が、旧約聖書の時代から21世紀のいままでの「パレスチナ問題」をガイドします。日本から少し距離のある国のお話ですが、すべてがつながっている現代では、けっして遠い世界のお話ではないのです。

男と女の法律戦略
講談社現代新書
不倫、離婚、慰謝料、婚約詐欺… テレビが絶対に教えない「男女関係と法律」の鉄則!
孫子の兵法に「勝算なきは戦わず」とあるように、勝つ見込みがなければ戦争を始めてはいけません。俗に言う「負ける喧嘩はするな」ということです。男女間の法律問題にも、これはよく当てはまります。(中略) 敵の中には、常軌を逸するほど強靱な相手がいます。(中略)「マザコン男性とその母親」などがいい例です。彼らは深い愛情で結ばれており、一般的に、他者からの攻撃に対して非常に強く反撃します。そういう相手と戦って勝つのは容易ではないし、仮に勝ったところでこちらの消耗も大きくなります。そういう相手に対しては、戦わずに兵を引いて、こちらの資源を温存するのです。そして、将来向こうが自滅するのを待つのです。これを私は「不敗戦略」と呼んでいます。――<本書より>
屈指の経験を持つ弁護士の「戦わずして勝つ」考え方
●離婚してくれない相手との別れ方
●「不倫すると慰謝料を取られる」と思え
●「弁護士殺しの必殺技」とは?
●リスクを減らす「不敗戦略」
●「子供の親権だけは確保する」場合
●裁判官は何に弱いか
●孫子とクラウゼヴィッツの教訓
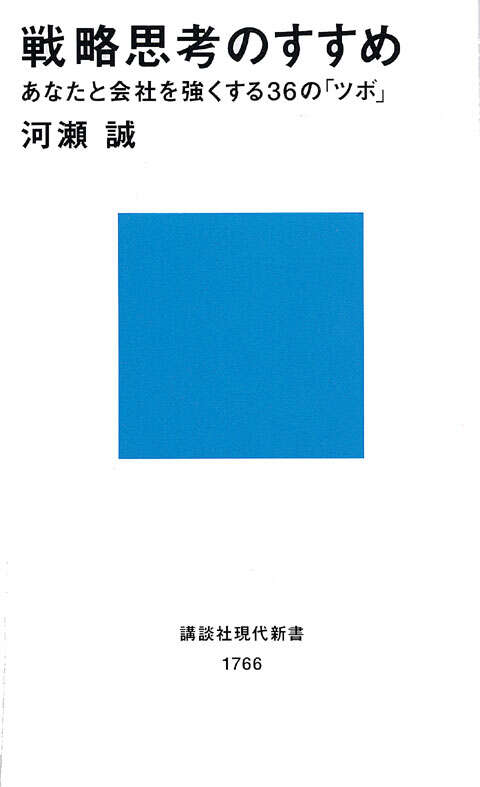
戦略思考のすすめ
講談社現代新書
英語もMBAも関係ない!これがビジネスのツボだ
会社員の価値は「英語ができます」とか「ケーススタディが解けます」といったことにあるわけではありません。会社員の価値とは、あくまで組織と社会に貢献すること、つまり「仕事を通じて会社を強くする力」にあります。それができる人こそが、まさに“できる人”であり、大きな市場価値のある人です。仕事を通じて会社を強くするには、押さえるべきいくつかの「ツボ」があります。この本では、ビジネスの基本として押さえたい「36個のツボ」を紹介していきます。(中略)どうせ仕事をするならば、ワクワクする楽しい仕事、自分を活かす仕事をしたいですよね。ツボを押さえれば、仕事はもっと楽しくなります。どんな組織にいても、面白い仕事は“できる人”に回ってくるからです。――<本書より>
●ビジネスを強くする4つの戦略とは?
●競争とは自分の棲み場所を見つけること
●自分の強みを生かして競争するために
●お客を見ない会社は亡びる
●全員がハッピーになるビジネスモデルの作り方
●何が「知識型組織」を動かすのか
●あなたの動機に合った仕事をしよう
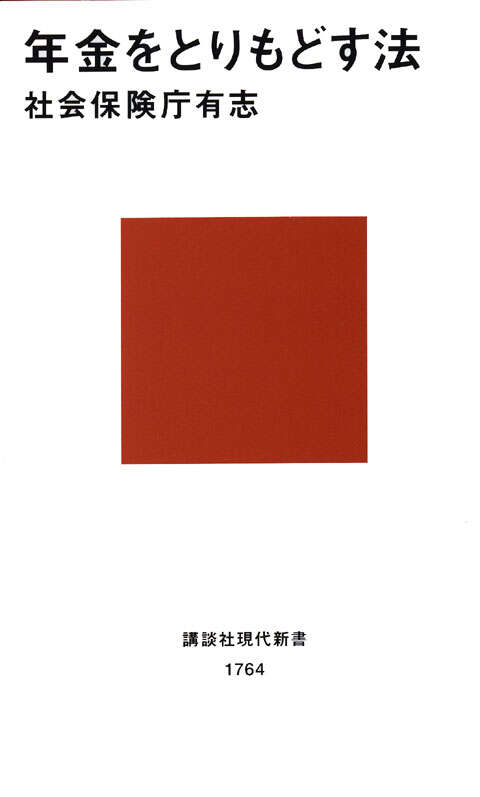
年金をとりもどす法
講談社現代新書
現役官僚が授ける誰も知らない裏ワザ
矛盾した制度に負けない「理論武装」を
こうしたお粗末きわまりない公的年金を放置してきた責任は、政治家と、厚生労働省や社会保険庁の役人にある。ネズミのように逃げ出す前に、みずからが責任を全うできない制度を国民に押しつけてきたために深刻なところにまで立ち至ってしまった矛盾を解決することが、先決のはずではないか。このような無責任な連中に対抗するためには、理論武装が必要である。本書は、読者がいままで汗水垂らして働いて得た給料から強制的に天引きされた「年金掛金」を、年金官僚の手から少しでもとりもどす戦術を授ける指南書である。(中略) そして逃亡をはかる年金役人たちに、制度の矛盾に泣く国民の叫びを、筆者が代弁して少しでも訴えたいと思っている。――<本書より>
●愛人の子も遺族年金を請求すべし
●59歳で退社、再就職で年金をふやせ
●離婚するなら平成19年4月以降に
●あまりにずさんな障害年金の「認定」
●役人たちの「年金術」を盗め!

性の用語集
講談社現代新書
「性の言葉」の起源と変遷!「性」はいつからセックス的意味になった?なぜ陰毛が「ヘア」なのか?どうして「風俗」は「フーゾク」に?
「性」という言葉を見ると、日本語文化圏で生まれ育った人たちは、たいてい「セックス」や「セックスに関連する事柄」をさしている、と思うようだ。(中略)しかし、「セックス」や「セックス的事柄」は、「性」のもともとの意味ではない。白川静著『字通』(1996年)を見ると、「性」は「それぞれの持つ本質や属性」をいい、また「ものが固有するもの」を指すとしている。つまり、「さが、たち、うまれつき、もちまえ」などをいうのである。世界や世界にあるものの本質・属性が「性」である。(中略)つまり、どこかの時点で、また、どこかの地点で、「性」という漢字、あるいは、言葉・記号に、「セックス」という意味が加わったのである。――<本書より>
<本書でとりあげた用語(一部)>
性/エロ・エロス/エッチとエスエム/変態‐H/童貞/処女/ヘア/フーゾク・風俗/ママ/ホステス/おかま/女装/巨乳/――専/コンドーム/セックスレス/カーセックス/のぞき/立小便/アベックはカップルか?/ニューハーフ/Mr.レディ・Miss.ダンディ/援助交際/社交/ノンケ/フリーセックス/不能/ブルー……
愉快に(でも真剣に)エッチな言葉を考えてみた!

経済論戦の読み方
講談社現代新書
明解!大混乱の経済論戦シーンをあざやかに読み解く!
辛口ブックレビュー付き
近年の日本では、「21世紀型グローバリズムでは従来の経済学は通用しない」とか「デフレ対策をやりすぎるとハイパーインフレが起こり、市場経済は崩壊する」などという安易な説が唱えられている。そのような、どこからともなく(おそらく主張している人の直観や経験からだろうか?)湧いて出てきた新種の「理論」で、しばしば従来の経済学の遺産が完全否定されてもいる。こんなことは、過去の経済思想の歴史を見てもほとんどありえない現象だった。しかし、このように経済学の世界では考えられないような主張がしばしば世をにぎわせるのが、いまの日本の経済論戦の主要なシーンなのである。――<本書より>
●エコノミストは役に立たないのか
●「流動性の罠」に陥った日本経済
●「構造改革主義」という幻想
●「1940年体制テーゼ」の呪縛
●間違いだらけのハイパーインフレ論
●日本の財政破綻はありうるのか
●「万年危機論者」たちの終わらない宴

武装解除
講談社現代新書
むき出しの暴力、軍閥ボスのエゴ、戦争が日常の子どもたち……。泥沼の紛争地でいかに銃を捨てさせるか? 東チモールからアフガンまで現場を指揮した男が明かす真実。真の平和論はこの一冊から。(講談社現代新書)
職業:「紛争屋」
職務内容:多国籍の軍人・警官を部下に従え、軍閥の間に立ち、あらゆる手段を駆使して武器を取り上げる。
紛争解決の究極の処方箋?――DDR
ハンマーがひとつ、ふたつと、古びたAK47オートマティック・ライフルに打ち下ろされる。やっと銃身が曲がり始めたところで、涙を拭い、また打ち下ろす。ハンマーを握るのは、歳の頃は18くらい。まだ顔にあどけなさが残る、同じ年恰好の少年たちで構成されるゲリラ小隊を率いてきた“隊長(コマンダー)”だ。(中略)何人の子供たち、婦女子に手をかけ、そして、何人の同朋、家族の死を見てきたのだろうか。長年使い慣れた武器に止めを刺すこの瞬間、この少年の頭によぎるのはどういう光景であろうか。通称DDR(Disarmament,Demobilization&Reintegration:武装解除、動員解除、社会再統合)の現場である。――<本書より>
机上の空論はもういらない 現場で考えた紛争屋の平和論!
●魑魅魍魎の日本のNGO業界
●政治家なんて恫喝させておけ
●紛争屋という危ない業界
●後方支援は人道支援ではない
●米国が醸し出す究極のダブル・スタンダード
●テロを封じ込める決定的解決法
●和解という暴力
●紛争解決の究極の処方箋?――DDR
●多国籍軍の体たらく
●戦争利権としての人道援助
●日本の血税で買ったトラックが大砲を牽引する
●改憲論者が護憲論者になるとき

科学する麻雀
講談社現代新書
「数理の力」があなたの麻雀を変える!
裏スジは危険ではない/回し打ちは無意味だ/ベタオリには法則がある/「読み」など必要ない
「麻雀の答え」を明らかにする
従来の戦術書は、「読み」や「総合的な判断」や「ツキの操り方」といった一般化が不可能な、個人レベルでしか身につけることが出来ない“技術”だけで麻雀を論じています。そして、それらこそが高度な技術であると、麻雀を打つ人たちの間では長く信じられてきました。(中略)本書では、こうした曖昧な記述をできるだけ排し、「どんな場合に、何を基準に、どう考えるか」といった「麻雀の答え」を明示していきます。たとえば「リーチすべきか、ダマにすべきか」という判断に対して、きちんと「どういう場合にリーチすべきである」と具体的に示します。それらの「答え」は理論的、数理的、あるいは統計的な根拠にもとづいています。根拠のない不明確な考え方はいっさい出てきません。――<本書より>
●ピンフのみテンパイはリーチすべきか?
●役牌が持ち持ちになっている確率は?
●チートイツは全和了の何%を占めるか?
●他家リーチに安全牌がないときどうする?
すべての「答え」がここにある!