講談社現代新書作品一覧

哲学の歴史
講談社現代新書
現代思想の鋭く根底的な問いは、西欧の厖大な知の集積から生まれた。私は何か? 他者というアポリア、言語と世界の迷路をどう切り拓くか? 哲学が2500年にわたって問い続けた主題を、現代哲学の開かれた地点から捉えかえす。
哲学的伝統の魔力――近代初頭において、人間の認識の視点への拘束性が発見されていたにもかかわらず、反面では人間は、神と同様に、世界を全体として認識できる脱世界化された視点をもつ主観として構想されてくる。近代の認識論はこの両面を背負っている。……今日こうした形而上学の伝説から脱却がはかられているといっても、ことはそう簡単に運ばないのである。というのは、さまざまな概念の装置に浸透している伝統の魔力、思想の論理を貫く「原型的理論(モデル)」の威力がわれわれの経験に深く沈んですべてを制約してくるからである。かつての啓蒙の哲学者たちも、徹底的に先入見の解体につとめた。現代の哲学者たちもまたそうした努力なしに思惟をすすめることはできない。――本書より
ダンディ ある男たちの美学
講談社現代新書
画一の時代に反逆する差異崇拝の生き方とはダンディズムは,多数に対して単独を,過剰に対して希少を,労働に対して余暇を対置する.進歩と平均の時勢に異を唱え,徹底して自分自身にこだわる生き様の美学

百人一首の謎
講談社現代新書
なぜ、百人一首とよぶのだろうか。「紅葉」「白菊」「舟」「濡れる袖」……繰り返されるシンボリック・ワードに密かに隠されたメッセージとは何か。定家の組みたてた暗号を解き「百人一首」撰歌の謎に迫る。
撰歌の疑問――中世依頼の伝承では、『百人一首』は定家が撰び、小倉山の山荘に書きおいた色紙の和歌であると伝えられてきた。どういう基準で歌人を選んだのかということについて、「百人一首抄」は「不審のこと」とし、定家もその撰に加わった『新古今集』が定家の本意に適わなかったので、「『百人一首』は定家が実を根本に花を加えるという歌の理想を示したものである」と述べている。表現は抽象的だが、『百人一首』が通常の秀歌撰ではないということは、はっきりと述べている。――本書より
先端医療 診断・治療の最前線
講談社現代新書
医療現場の最前線でいま何が起きているか?コンピュータ技術を駆使したCTスキャンや超音波による診断面の進歩、ICUの登場やレーザーメス開発など治療面での技術革新。最先端の医学情報を平易に解説。
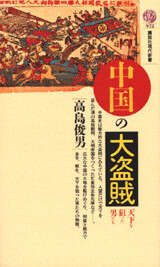
中国の大盗賊
講談社現代新書
中国史は魅力的な大盗賊にみちている。人望だけで天下を盗んだ漢の高祖劉邦、大明帝国をつくった乞食坊主朱元璋など――。広大な中国の大地を駆けめぐり、知謀と腕力で金を、都を、天下を狙った男たちの物語。
「盗賊」だらけの中国史――昔、中国に「盗賊」というものがいた。いつでもいたし、どこにでもいた。日本のどろぼうとはちょっとちがう。中国の「盗賊」は必ず集団である。これが力をたのんで村や町を襲い、食糧や金や女を奪う。へんぴな田舎のほうでコソコソやっているようなのは、めんどうだから当局もほうっておく。ところがそのうちに大きくなって、都市を一つ占拠して居坐ったりすると、なかなか手がつけられなくなる。さらに大きくなって、一地方、日本のいくつかの県をあわせたくらいの地域を支配したなんてのは史上いくらでも例がある。しまいには国都を狙い、天下を狙う。実際に天下を取ってしまったというのも、また例にとぼしくないのである。――本書より

文化大革命
講談社現代新書
天安門広場に毛語録の波が揺れる。「造反有理」から「批林批孔」「四人組」まで、当時の中国はまさに混乱のるつぼであった。社会主義における変革とは何か。毛沢東のかかげた夢と、現実を膨大な資料の中から検証しつつ現代中国の起点といえる文化大革命の真相を、具体的かつ、実証的に抉り出した待望の書。(講談社現代新書)
現代中国に傷痕を残す文化大革命を振り返る。現代中国に大きな傷痕を残してしまった文化大革命とはいったい何であったのだろうか。豊富な文献をとおし、その意味と事実経過を辿り、中国の苦難史を解明する。
パズルとパラドックス
講談社現代新書
パズル・なぞなぞ・逆説で読む楽しい論理学20世紀論理学の展開にヒントを与えたルイス・キャロル「アリス」物語。クワイン、スマリヤン、ゲーデル等が好んだアリスの世界を題材に現代論理学の問題を解説

日本語をみがく小辞典<形容詞・副詞篇>
講談社現代新書
「えぐい」言葉より「まろやか」な表現で、「けざやか」に語りたい。形容詞や副詞を「とりどり」に使い、「こまやか」な日本語生活を!
女房と畳の鮮度――新しいものは、それだけで価値を持つ。古代日本語にあっては「あたらし」は「惜し」で、“立派だ”“すばらしい”の意味であった。……これとは別に、「あらた」なる語があって、……これを形容詞化させた「あらたし」、これが今日の“新しい”の意味だった。さらに音韻転倒を起こして「あらたし」が「あたらし」となったのだから、芸が込んでいる。ちょうど「腹鼓(つづみ)」が「腹づつみ」と発音されたり、「さんざか」が「山茶花(さざんか)」から変じたように。――本書より

ロ-マはなぜ滅んだか
講談社現代新書
全世界から巨富を集め、繁栄の限りをつくしたローマ帝国。食卓をにぎわす珍鳥・珍魚、文学に、スポーツに進出する「自由な女」、文化となった愛欲――。「永遠」をうたわれた巨大文明の興亡の中に現代の超大国・日本の姿を透し見る。
ローマ人たちの胃――ローマ人は全世界からあらゆる珍味を集めたが、放恣に疲れ切った彼らの胃は、それを受容れることができなくなったのである。ローマ人は、「食べるために吐き、吐くために食べているのだ」というセネカの非難は、単に過食の贅沢に向けられたものではなかった。全世界からかき集められた富を、奢侈と浪費に蕩尽している不健康な悪徳に対する文明批判なのである。吐いた汚物は、便所か路傍の小便壺に捨てられるか、あるいは道端に投げ捨てられる。不正によってかき集められた富は、こうして無駄に浪費されてゆく。――本書より
英語パズル
講談社現代新書
英語で笑い、英語で考え、英語で遊ぶ快著 スフィンクス以来のリドルから、ポーの愛したサイファー、パズルの王クロスワードまで、興味つきない英語パズルの数々を豊富な実例とエピソードで楽しむ知的一冊
物質の究極は何だろうか
講談社現代新書
究極物質を求めた物理学が示す驚くべき世界原子→原子核→素粒子→クォークと続く階層は無限に続くのだろうか? 物質の究極と宇宙の始まりが「無」から誕生したとする最新理論から、不変なるモノを追う。

はじめてのオペラ
講談社現代新書
ウィーンミラノにパリ、ニューヨーク。世界中のオペラ劇場を股にかけ、魅惑のアリアにブラボーする。四夜続けて、「ニーベルンクの指環」。スペクタルなら「アイーダ」。作品、歴史から歌手、劇場まで、“いけない楽しみ”オペラの全て、こっそり、あなたに教えます。
オペラは危険だ――江戸のころには芝居見物して切腹させられた武士がいたというが、いまオペラを聴いて命にかかわることはない。誰からも責められない。それどころか、まだ成人にも達していない女の子がオペラを好んだとしても、世間は大目に見ている。これは多分、オペラがいけない楽しみであると、まだ知られていないからではないか。少なくとも、私の両親には知られていなかった。「今度外国からオペラが来るんだけど……」と頼めば、ちゃんと小遣いを引き出せた……「マリファナを手に入れるので援助を……」というわけにはいかなかった。どちらが危ないかは、いまならはっきり言える。オペラだ。――本書より
日本銀行 知られざる“円の司祭”
講談社現代新書
日本国の“金庫番”=日銀の知られざる全貌金融市場の自由化、為替相場の変動、景気や物価の浮沈のなかで日銀はどんな役割を果たしているのか? 巨大な力をもつ「円の司祭」の組織・機能・政策を解明する
超人の哲学
講談社現代新書
語り継がれる超人になぜ憧れるのであろうか不敗の神話、肉体の超越……人間は常に超人に憧れつづけてきた。家族や社会のあり方から、超人が必然的に析出される意味を、豊富な素材をもとに明快に解き明す。
「戦国策」の知恵
講談社現代新書
中国の大変動期を生きた個性の魅力を探る。後進国秦を一挙に超先進国にした商君、舌先三寸に命をかける大策士たち、反「孔孟」的人物・政商呂不韋など、戦国時代を生きた群像を通して人間性の本質に迫る。

進化を忘れた動物たち
講談社現代新書
古代大陸生まれの原始猿や絶滅した恐龍族の血をひくドラゴン。地球に残された貴重な密林に高山に深海にひっそり生き続ける「進化の生き証人」たちをたずねる。
手抜き子育ては天下一[ツパイ]――飼育下の母親は、自分のとは別の巣で子どもを産むと、二日に一度しか授乳に訪れない。……しかも5~10分もするとサッサと帰ってしまう。掃除もしていかない。排泄物の世話をしないのだ。子どもは巣に1ヶ月もいるのだからたまらない。赤ん坊が尿と糞にまみれ、しかも飢えているのを想像すると忍びない。……子どもが巣立つまでの間に、母と子が一緒にいるのは、合計してもせいぜい1時間半である。スキンシップが霊長類の特徴の一つならば、「ツパイよ、それでもサルか」と言いたくなる。――本書より

自己表現上達法
講談社現代新書
気持ちをうまく伝えたい。初対面で好感をあたえるには? 説得力のある話し方をするには? など対人心理学の実験を通して効果的な自己表現を考える。
セイリエンス効果――心理学の実験で、二人の討議を聞き、どちらがその討議に大きな影響力をもっていたかまたどちらの人に好意をもてるかを調べた研究があります……その結果、同じ討議を聞き、観察したにもかかわらず、観察者は各々自分の向かいがわに坐っていた顔の見える人を、影響力があり、また好感がもてると判定しました……面接者との位置関係は非常に重要になります。せっかく、よい意見をのべても、面接者の視野の中心を占めてないと、その発言も過小評価されてしまうとのことです。逆に面接者の視線の方向に位置しているとそれだけで目立ち、好印象をあたえることができます。――本文より
使いこなすパソコン通信
講談社現代新書
パソコン通信のシステムと初心者入門ガイド電話とファクシミリの便利さをかねそなえたパソコン通信。ワープロを使える人なら大丈夫。データベース、電子メール、草の根ネットワークの活用法を200%紹介

東インド会社 巨大商業資本の盛衰
講談社現代新書
東方の夢、胡椒がシナモンが茶が、ロンドン庶民の食卓に到達した。「楽園」の物資を運ぶ東インド会社は、世界をヨーロッパに収斂させる。貿易を牛耳り、インドの支配者となった一大海商企業の盛衰とその時代を読む。
商業革命――家屋の新築は都会でも田舎でも相次いだ。造船も盛んだったし、農業面の改良もすすんだ。オランダとの戦争やロンドン大火、ペストの流行といった災害もみられたけれども、このころの英国は全体として生活水準が向上した時代であった。物質的繁栄の時代であった。1665年から1688年までの間に、国民所得は8パーセント上昇し、全体として国富は23パーセント増加したと、当時の人は計算している。しかしこのような経済的発展は何によってもたらされたかというと、何よりも外国貿易の拡大によっていた。外国貿易こそが、当時イギリスの経済発展を支えたリーディング・セクターだといってよかった。一人当たりの年収をひき上げる上で、大商人と海上貿易業者の果たした役割が大きかったと、経済通であったグレゴリー・キング(1648――1712)も述べている。――本書より
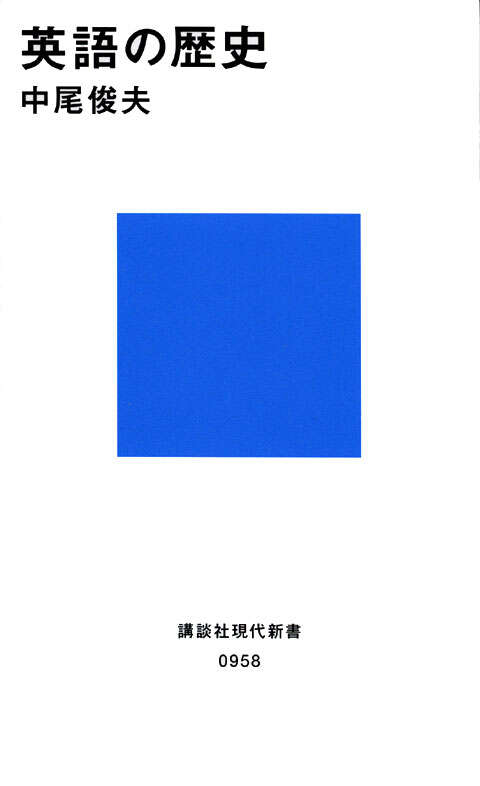
英語の歴史
講談社現代新書
一人称を「I」と書くのはなぜ?ノルマンの征服とフランス語の流入、18世紀の学校文法の完成など、文法・発音・語形・語彙がいかに変化してきたかを豊富な例とともに解説する。
It is me.とIt is I.――今日の口語では「私です」というとき、it is I.の代わりにIt is me. という。しかし14世紀を境にして、それ以前と以後ではまったく違った構造をしていた。すなわち、それ以前ではIt am I.といった。この文の主語は明らかにItではなくIである。しかも「補語+動詞+主語」という奇妙な語順をとっている。この文の主語がIであるというのは古英語以来の構文を受け継いだ結果で、古英語ではI it am.といっていた。つまり中英語期のIt am I.は古英語の主語Iを動詞の後ろに移動してできた構文なのである。It am I.は語源の確立とともに動詞の前は主語の領域と感じられてきて、だんだんItが主語と解されamがisに変わった。同じように動詞の後ろは目的格の領域と感じられてきたために、isがbe動詞であるにもかかわらず、他動詞であるかのようにIはmeへ変化した。――本書より