創文社オンデマンド叢書作品一覧

キリスト教古典叢書12:祈りについて・殉教の勧め
創文社オンデマンド叢書
キリスト者としてのオリゲネスの熱烈な信仰が躍如として行間にあふれる本書は、その「キリスト教的人格を知る上できわめて重要な資料」であり、古代から現代に至るまで愛読され続けている。
古代キリスト教の卓越した思想家オリゲネスの著作のなかでもこれほど美しい思想に満ちているものはないと評される「珠玉の小品」。
【目次】
序言 P・ネメシェギ
緒言
オリゲネスにおける「祈り」と「殉教」
教父時代における「主の祈り」
『祈りについて』
『殉教の勧め』
引用箇所の注
解説の注
文献

オッカム『大論理学』註解V 第III部―3 全46章・第III部―4 全18章
創文社オンデマンド叢書
中世から近世への転換期を生きたオッカム(1285‐1349)は、今日に至るまで、哲学・論理学に多大な影響を及ぼしてきた。しかし彼の思想のみならず論理学に関する本格的研究は殆どなされていない。アリストテレスの論理学を批判的に継承し中世論理学を集大成したオッカムの主著SUMMA LOGICAEはポルピュリオス『イサゴゲー』やアリストテレスのオルガノン全般に関する興味深い注釈とともに、現代論理学や言語哲学と類似した多くのアイデアを展開した。
中世哲学研究のみならず現代哲学や古代哲学研究にとっても第一級の原典を、正確な訳文にくわえ古代哲学とスコラ哲学、同時代の影響関係などを踏まえた詳細な註を付して、世界でも初めての完全な現代語訳として提供する。本巻の第3部‐3はアリストテレス『トピカ』に対応し、推論の区分、討論における拘束に関する諸規則、解決困難な命題いわゆる嘘つきのパラドックスについて論じられる。また第3部‐4は『詭弁論駁論』に対応する。とくに世界初訳の本巻は、国内外で待望の刊行である。
【目次】
第3部‐3 推論について(三段論法の形式を持たない推論や論証による議論の仕方について。第一に、推論ということは、どれほど多くの意味で言われるのか;内的な媒介によって行なわれ、その結論が全称命題である推論が成立するための一般的な規則について;或る特定の述語において、全称肯定命題が結論として導かれるための規則について;全称否定命題を結論として導く推論が成立するための規則について ほか)
第3部‐4 誤謬推理について(誤謬の種類について;同名異議の第一の様式について;同名異議の第二の様式について;同名異議の第三の様式について ほか)

オッカム『大論理学』註解IV 第III部―1 全68章・第III部―2 全41章
創文社オンデマンド叢書
アリストテレスの論理学を批判的に継承し中世論理学を集大成したオッカムの主著『SUMMA LOGICAE』はポルピュリオス『イサゴゲー』やアリストテレスのオルガノン全般に関する興味深い注釈とともに、現代論理学や言語哲学と類似した多くのアイデアを展開した。
中世哲学研究のみならず現代哲学や古代哲学研究にとっても第一級の原典を、正確な訳文にくわえ古代哲学とスコラ哲学、同時代の影響関係などを踏まえた詳細な註を付して、世界でも初めての完全な現代語訳として提供する。本巻の第3部―1、2はアリストテレスの『分析論前書』『分析論後書』に対応し、第3部―1では三段論法全般について、第3部―2では厳密な意味での知を生じさせる論証的三段論法について論じられる。中世哲学の場から古代へ更には現代へと新たな光を放つ画期的訳業。
【目次】
三段論法について(三段論法の区分と定義について;論題に入るに先立って、前もって述べられるべき前置きについて;第一格でなされる三段論法について;前章において述べられたことは、如何にして証明されるのか ほか)
論証的三段論法について(「論証」という語によって何が理解されるか。「知る」ということはどれだけ多くの意味で言われるか;どのような語が論証の中に入るのか;論証を行なう者は前もって何を知らなければならないか;論証に必要とされる諸命題の区分について ほか)

オッカム『大論理学』註解II 第I部 第44章~第77章
創文社オンデマンド叢書
中世哲学研究のみならず現代哲学や古代哲学研究にとっても第一級の原典を、正確な訳文にくわえ古代哲学とスコラ哲学、同時代の影響関係などを踏まえた詳細な註を付して、世界でも初めての完全な現代語訳として提供する。中世哲学の場から古代へ更には現代へと新たな光を放つ画期的訳業の第2巻は、実体や質および量といった範疇の問題(第44―62章)、さらに中世論理学独自の分野である代示の理論(第63―77章)を収め、ここに第1部「語について」が完結した。
【目次】
範疇―アリストテレス『範疇論』の註解(量という範疇について;前述の見解に対する反論;量という類のうちに措定されるものについて;量の特性について ほか)
代示の理論(命題における語の代示について;代示の区分;語は命題のなかにおいて、どんな場合に個体代示、あるいは単純代示や資料代示を持つことが可能なのか;これまで述べられた事柄に対してなされうる、諸々の反論について ほか)

オッカム『大論理学』註解I 第I部 第1章~第43章
創文社オンデマンド叢書
中世哲学研究のみならず現代哲学や古代哲学研究にとっても第一級の原典を、正確な訳文にくわえ古代哲学とスコラ哲学、同時代の影響関係などを踏まえた詳細な註を付して、世界でも初めての完全な現代語訳として提供する。中世哲学の場から古代へ更には現代へと新たな光を放つ画期的訳業の冒頭を飾る本巻は、具象語と抽象語、概念、類と種、実体と質量など言葉・普遍・範疇について論じる第1部43章までを収める。
【目次】
語の区分(語の定義とその区分(総論)
語の区分。「語」という名前は、様々な仕方で解されうる(各論) ほか)
普遍は心の外のものではない―スコトゥスに対する反駁(互いに対立する、「普遍」と「個」という普通名辞について;普遍は心の外のものではない ほか)
五つの普遍―ポルピュリオス『イサゴゲー』の註解(五つの普遍。それらで充分であることについて;普遍のもとに含まれる個について ほか)
論理学者の用いる語(定義について。定義は、幾通りの仕方で言われるのか;「記述句」という名前について ほか)
範疇―アリストテレス『範疇論』の註解(「範疇」という語について;範疇の数 ほか)
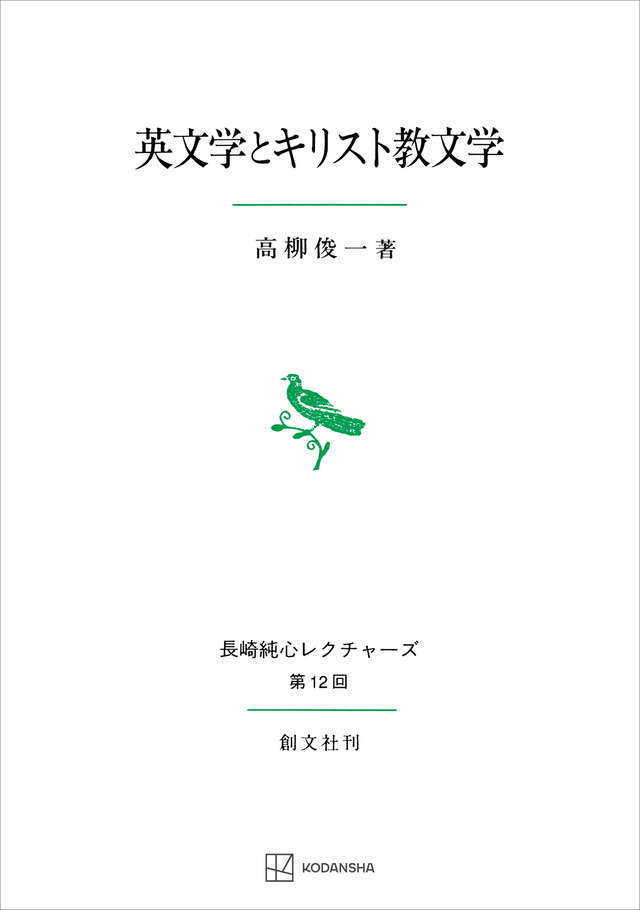
英文学とキリスト教文学(長崎純心レクチャーズ)
創文社オンデマンド叢書
近現代のキリスト教作家に焦点を当て、わが国では分かりにくい国教会諸派やカトリックの文芸運動との関連を解説、世俗化する社会や国際政治の変化も踏まえて作品を位置づけ、英文学におけるキリスト教文学の展開を論じる。さらには聖書学の成果を用いて福音書のイエス伝と小説のイエス像との関係を考察するとともに、批評理論の動向を見すえつつ、互いに影響し合う聖書と文学理論の深い関係を明らかにする。大きな物語、すなわち聖書に基づいた物語は終焉したとしたリオタールの主張を斥け、今日における文学の使命を示唆する、稀有なイギリス文学史。
【目次】
「長崎純心レクチャーズ」について 片岡千鶴子
序論
一 「キリスト教文学」の背景
二 ニューマンと「カトリック文芸復興」
I ホプキンズとR・S・トマス 聖職者詩人
一 イエズス会詩人ジェラード・マンリー・ホプキンズ
二 ウェールズ教会詩人R・S・トマス
II エリオットとオーデン 国教会詩人
一 アングロ・カトリック詩人T・S・エリオット
二 ハイチャーチ詩人W・H・オーデン
三 エリオットとオーデン以後のキリスト教詩人
III 第二次大戦後のカトリック小説家
一 冷戦とカトリック小説
二 恩寵と罪 グレアム・グリーンの世界
三 伝統への回帰 イーヴィリン・ウォーの復古主義
IV 中流化とカトリック小説
一 イギリス小説 大衆読み物から文学へ
二 哲学的小説の世界 ミューリエル・スパーク
三 中流カトリック信徒の生き方 デイヴィッド・ロッジ
四 後続カトリック小説家とキリスト教作家
V イエスの生涯の小説化
一 聖書外典文学と小説
二 外典文学と第五福音書
三 新しい写本の発見とユダの福音
VI 聖書と最近の批評理論
一 批評理論と聖書批判
二 解釈学の契機への注目
三 オーサーの死と「本」の枠組みの崩壊
結び
一 聖書の代わりとしての文学作品
二 ポストモダンの状況とキリスト教文学
文献表
あとがき

近世初期実学思想の研究
創文社オンデマンド叢書

キリスト教古典叢書15:聖霊論
創文社オンデマンド叢書
アレイオスによって生じた4世紀前半のイエス・キリストの理解をめぐる論争は、4世紀後半になると聖霊の神性をめぐる論争に進展し、多くの教父が論陣を張る。
「キリスト教正統信仰の父」と称せられるアタナシオスは激しい文体の中に、アレキサンドリア教理学校の校長を務めたディデュモスは穏やかな文体で、それぞれの聖霊の神性を弁証する。ここにギリシア教会の伝承となる豊かな聖霊論が展開される。
ディデュモスの聖霊論は、世界初の現代語訳となる。
【目次】
序言 ペトロ・ネメシェギ
緒言
アタナシオス―セラピオン―ディデュモス
四世紀後半における聖霊の理解
アタナシオス『セラピオンへの手紙』
第一の手紙
第二・第三の手紙
第四の手紙
ディデュモス『聖霊論』
聖書引用箇所の注
解説の注

キリスト教古典叢書14:ローマの信徒への手紙注解
創文社オンデマンド叢書
古代教会最大の神学者オリゲネスによる、キリスト教史上最大のローマ書注解。文字による律法と霊的な律法、心に刻み込まれた法と罪の法、肉体の割礼と心の割礼、内なる人と外なる人、異邦人の召命、救いの歴史、キリスト者の新しい生き方を論じ、善なる神の愛の勝利を高らかに謳う。
「序言」より
「古代教会の最大の神学者のひとりであったオリゲネスのローマ書注解が今度日本語訳で出版される運びとなったことは、きわめて喜ばしいことである。確かに、オリゲネスの性格も神学思想も、パウロのそれとは大いに異なっている。しかもオリゲネスの神学的確信は非常に強いもので、それとは違った傾向の発言を自分の考えに合わせて解釈するように彼を駆り立てたのである。そこでかれは、パウロの逆説的で、論争的な論述を、バランスの取れた思想体系に変えようとしたのである。その結果、オリゲネスの解釈がパウロの本来の思想とかなり異なったものになったところも決して少なくない。しかし、その時でも、全力を尽くして聖書を「善い方であられる神にふさわしく」説明しようとする彼の誠実な意気込みがよく感じられる。しかも、彼のて天分のひらめきが現れる箇所はまれではない。」
【目次】
序言 ペトロ・ネメシェギ
『ローマの信徒への手紙注解』解説
内容区分
『ローマの信徒への手紙注解』
ルフィヌスの序文
第一部
序章
第一巻
第二巻
第三巻
第四巻
第五巻
第六巻
第七巻
第二部
第七巻(続き)
第八巻
第九巻
第十巻
ルフィヌスの結語
訳者あとがき
文献

キリスト教古典叢書11:ヨハネによる福音注解
創文社オンデマンド叢書
「序言」より
「古代教会が正統信仰として宣言し、キリスト教の主流が今日に至るまで承認してきたキリスト論に決定的な影響を及ぼしたのは、まさに、このヨハネ福音書である。後の時代になると、西欧のキリスト教界においては、特に宗教改革以来、パウロの思想が影響力を増したが、ヨハネの思想を優先的に扱い続けてきたのは、東方教会である・・・
ヨハネ福音書をあれほど高く評価した古代教会の神学者の手によるヨハネ福音書注解の翻訳を日本語で読者に提供することは、確かに重大な意義がある。小高毅氏が、三年かかって完成したこの翻訳は、学問的に高いレベルを保っている正確な訳でありながら、一般読者にも読みやすい文書になっている・・・
オリゲネスの原作の大部分が紛失し、一部分しか保存されていないことは、もちろんきわめて残念なことであるが、現存しているその一部分によっても、オリゲネスの解釈方法や神学的理解は、現代の聖書学者や神学者のそれとは大いに異なっているが、きわめて興味深いのである。・・・
オリゲネスのヨハネ理解には、プラトン哲学によって形作られた彼の思想体系に由来し、永久的な妥当性を有していない諸点があるにしても、彼の説明に、人間の永遠の根本問題をいつの時代の人々とともに考えざるを得ない現代人にとっても、有効な点が多く見いだされるのである」
【目次】
序言 ペテロ・ネメシェギ
『ヨハネによる福音注解』解説
内容区分
『ヨハネによる福音注解』
第一巻
第二巻
第四巻(断片)
第五巻(断片)
第六巻
第十巻
第十三巻
第十九巻
第二十巻
第二十八巻
第三十二巻
断片
引用箇所の注
本文批判
ギリシア語翻訳凡例
文献

キリスト教古典叢書10:雅歌注解・講話
創文社オンデマンド叢書
「序言」より
「オリゲネス自身、人間関係の基礎となっている……神との関係を常に追い求める人であった.民数記講話において、彼は次のように言っている。
『神の知恵には、限界があるでしょうか。人は、それに近づけば近づくほど、そのうちに深遠を見いだし、それを探求すればするほど、神の知恵が名状し難く、理解し難く、評価し難いものであることを発見します……知識の火によって燃えている魂が、ゆっくり休むことができるときは、いつまでも来ません。魂は常に、善からいっそう善いことは、いっそう善いことからさらに超える高いところへ進むように刺激されています」(17・4)
このような歩みの到達点は、神との完全な統合である。オリゲネスはさらに述べている。
『神が個々のものにおいてすべてとなられるのは次のようなことである。即ち、あらゆる悪徳のかすを清められ、あらゆる悪意の霧を取り払われて、理性的精神が考えたり、理解したり、思惟したりすることのすべてが神であり、神以外の何ものをも考えず、神を思惟し、神を見、神に固着し、神がそのすべての動きの基準および規範であるということである。』」(諸原理について』3・6・3)
……
敵にさえ及ぶすべての人に対する愛を生み出す神との一致―これはオリゲネスが一生涯追求した理想であり、すべての著作、特に雅歌についての著作において彼が教えることである」
【目次】
序言 P・ネメシェギ
緒言
オリゲネスの聖書解釈
『雅歌注解』
序文
第一巻
第二巻
第三巻
〔第四巻〕
『雅歌講話』
〔ヒエロニムスの〕序文
第一の講話
第二の講話
引用箇所の注
解説の注
参考文献

比較芸術学
創文社オンデマンド叢書
哲学の1ジャンルでもある比較芸術学の古典。芸術作品は「”人間性”という絶対的な価値尺度に従ってはかられるとき、その絶対的な価値を獲得」し、”限界状況”の体験と関係するとする。芸術の究極は、「歴史的創造行為をあるいは絶対的な中心に関係づけんと試みることなどによって、あるいは形而上学的な性格を持つに至る」ということになる。
身体表現/空間表現、身体感情/空間感情、直立モチーフ/運動モチーフ、目標モチーフ/進路モチーフ、静止/運動などの範疇に分けけて、考察する。
「芸術とは何か」を考えるための必読書でもある。
【目次】
一 問題設定
比較芸術学の課題/空間及び時間の諸範疇/人体表現の根本モチーフ・直立モチーフと運動モチーフ/構築的形成の根本モチーフ・目標モチーフと進路モチーフほか
二 直立モチーフ
エジプト
西アジア
ギリシア
西欧
東欧
印度
東亜
三 運動モチーフ
エジプト
西アジア
ギリシア
西欧
東欧
印度
東亜
四 目標モチーフ
エジプト
西アジア
ギリシア
西欧
東欧
印度
東亜
五 進路モチーフ
エジプト
西アジア
ギリシア
西欧
東欧
印度
東亜
六 結び
空間及び時間の観念は意志的態度に基づく/世界肯定と世界逃避の両極性/より包括的なる文化諸連関/超地域的超民族的超時代的な根本形式/根源象徴/C・ハソルド及びF・S・C・ノースロップへの態度
補遺 時間(E・パノフスキー、図像の研究) 時間の比喩的表現
訳註・主要著作目録
訳者あとがき
索引

エドガア・ポオ論考 芥川龍之介とエドガア・ポオ
創文社オンデマンド叢書
エドガア・アラン・ポー(1809ー1849)は、アメリカの詩人・小説家で、文筆活動で生計を立てた初期の著名な人物のひとりでもあります。
ゴシック風の恐怖小説「アッシャー家の崩壊」「黒猫」やはよく知られています。また、詩では「大鴉」がよく知られ、アメリカよりもむしろヨーロッパでの評判が高く、ボードレールの翻訳によって、紹介されました。後の象徴派に大きな影響を与えました。「モルグ街の殺人」は世界初の推理小説と目され、登場人物のオーギュスト・デュパンはその後の探偵の原型となりました。また、暗号小説の草分け「黄金虫」などの短編作品を多く発表しました。また、出版社を渡り歩き、編集者としても活動をした異才でした。しかし、人間関係でトラブルを引き起こすことが多かったとされています。
芥川竜之介(1892ー1927)とこの作家を比較することで、文学とはなにか? 日米の相違点、時代背景による文学のあり方などを読み解いていきます。
【目次】
序説
一 近代文学の創始者としてのポオ
二 アメリカ文学の疎外者としてのポオ観
三 ポオ観修正のこころみとその着眼点
四 世界の文学のなかに生きるポオ
第一部 二十世紀から見たエドガア・ポオの意義
第一章 ポオ評価の変遷
一 アメリカにおけるポオ評価の概観
二 ポオと同時代の人々の評価
三 十九世紀後半から二十世紀にかけてのポオの評価
第二章 ポオとその社会的環境
一 ポオの南部人気質について
二 社会批評家としてのポオ
三 文芸批評家としてのポオ
第三章 ポオとその文学的環境
一 ポオと「南方文学通信」
二 十九世紀前半の南部の文学趣味
三 南部におけるローマン作家の流行とポオ
四 当時の雑誌文芸とポオとの関係
第二部 芥川龍之介とエドガア・ポオ
第一章 芸術観と意識的制作
一 芸術家の肖像
二 芥川におよぼしたポオの影響
三 作家の資質 理知と情熱
四 芸術観 美の創造
五 意識的制作
六 芥川の回心
第二章 短篇小説の技法
一 短篇小説家としてのポオと芥川
二 虚構の文学 芸術と生活
三 制作の手法
1 芸術的効果
2 背景
3 事件又は題材
4 迫真性 リアリズムの手法
第三章 鬼趣と鬼気について
一 〈鬼趣〉と〈鬼気〉
二 神秘と怪異への関心
三 芥川の作品における怪異性
四 ポオの作品における〈魂の怪異〉
五 晩年の芥川の鬼気
結語 ふたたびポオについて
エドガア・ポオ年譜
註
あとがき
文献書目
索引

十七世紀危機論争
創文社オンデマンド叢書
イングランドの清教徒革命、フランスのフロンドの乱、ネーデルランドの宮廷革命、スペイン帝国のカタロニア反乱、ポルポルトガルの反乱、イタリアのマサニエロの反乱(ナポリの反乱)・・・
17世紀の革命の嵐はヨーロッパ・ルネサンスの陽気な気候を一気に吹き飛ばしてしまった。本書は、この危機を〈ルネサンス国家〉の社会に対する諸関係の全般的危機であるとする。そして、大胆な17世紀ヨーロッパ像を展開するトレヴァ=ローパーの独創的論文を中心に、最大の批判者ボブズボームの論文と世界の著名な歴史家6名の討論を編纂し、新しいヨーロッパ像の再構築を試みる。
【目次】
凡例
十七世紀におけるヨーロッパ経済の全般的危機(E・J・ホブズボーム)
十七世紀の全般的危機(H・R・トレヴァ=ローパー)
H・R・トレヴァ=ローパーの「十七世紀の全般的危機」をめぐる討論
一 E・H・コスマン
二 E・J・ホブズボーム
三 J・H・ヘクスター
四 ローラン・ムーニエ
五 J・H・エリオット
六 ローレンス・ストーン
七 トレヴァ=ローパー教授の解答
訳者あとがき
人名索引

ニーチェ 解放されたプロメテウス
創文社オンデマンド叢書
圓増治之「ニーチェ 解放されたプロメテウス ―ニーチェ哲学に於ける 解放力としての『音楽』」より
――思い起せば、ニーチェはその処女作 『悲劇の誕生』ですでに、後のニーチェ自身の言うとろによれば「差し当っては学者の頭巾で身を隠し、ドイツ人の重苦しさと弁証法的無味乾燥 さで身を隠し、 ワーグナー主義者のまずい流儀でもってまでも身を隠して」ではあるが、暗々裡に生そのものの心臓の通暁者として、 「力への意志」の通暁者として、語っているのであった。
すなわち、 『悲劇の誕生』第 1版刊行から16年後の第3版で新たに付加された序文 『自己批判の試み』の第4節の冒頭でこう言っている。すなわち、 「そうだ、ではディオニュソス的とは何であるか?-この本のなかにその答えが記されている-ここで語っているのは一人の『通暁者』である、すなわち、その神の秘密祭祀参入者にして使徒である」 と。
「それほど独自な見解と冒険に対してやはり独自な言葉で語ることをすべての点で 自分に許すだけの勇気」を当時ニーチェは未だ持っていなかったとはいえ、それ故末だ暖味にであるとはいえ、『悲劇の誕生』は秘かにすでに生の最も内奥の心臓から、すなわち 「力の意志」の次元から、我々に語りかけているのであった――。
【目次】
まえがき
第一部 ニーチェの立場へ
第一章 「真理への意志」 近世哲学に於けるその内的変動
第二章 ニーチェ・コントゥラ・パスカル
第一節 パスカルの「理性の論理」と「心情の論理」
第二節 パスカルの「心情」とニーチェの「心胸」
第三節 パスカルからニーチェに至る哲学に於ける「畏敬の心胸」
第四節 ニーチェに於ける「畏敬の心胸」の破棄
第五節 「心胸のメタモルフォロギー」への序論
第二部 ニーチェの場合
第一章 ニーチェに於ける「イロニー」
第二章 ニーチェに於ける「勇気」
第一節 「永劫回帰」の思想と「勇気」
第二節 ニーチェ・コントゥラ・ヘーゲル
第三章 ニーチェに於ける「メランコリー」
第四章 ニーチェに於ける「最後の神」 ニーチェ・コントゥラ・ハイデッガー
第五章 ニーチェ哲学に於ける解放力としての「音楽」
第三部 ニーチェの立場から
第一章 生の「メタモルフォロギー」的形式としての遠近法 テクノロジーの時代の超克のために
第二章 「力への意志」の一形態としてのテクノロジー
第一節 「テクノロジカルな自然支配」と「テクノロジーの自然本性」
第二節 「自然の人間化」と「人間の自然化」
注
後記
索引(人名著作名・事項)

インド正統派哲学思想の始源
創文社オンデマンド叢書
哲学者にしてヨーガの実践者でもあった著者が、インド古代思想の流れをわかりやすく説く。ヴェーダ思想、ブルシャ思想、ウパニシャッド思想、中期ウパニシャッド思想、ヨーガ思想、一神教的信仰と思想の流れを追跡し、解説する。
宗教的な思想と哲学的思考が融合したインドの古代にあって、その正統的なながれを一冊で紹介する入門書でもある。
【目次】
第一章 ヴェーダ思想展開の図式
第二章 ヴェーダに於ける密儀思想
第一節 ヴェーダ思想展開の内面過程
第二節 リグ・ヴェーダに於ける密儀的宗教思想
第三節 アタハルヴァ・ヴェーダに於ける咒法密儀的精神
第三章 プルシャ思想の展開
第一節 プルシャの語義について
第二節 リグ・ヴェーダに現われたプルシャ思想
第三節 後期ヴェーダ本集及び梵書に現われたプルシャ思想
第四節 ウパニシャッドに於けるプルシャ思想の諸相
(一) クシャトリヤのプルシャ思想
(二) プルシャと他の諸原理との関係
第四章 ウパニシャッド哲学の根本構造
第一節 ウパニシャッド哲学思想の起原
第二節 ウパニシャッド哲学と王族階級
第三節 ウダーラカの実在論哲学
第四節 ヤージナヴァルキアの観念論哲学
第五章 中期ウパニシャッドとバハガヴァッド・ギーターに於けるヨーガ思想
第一節 カタハ・ウパニシャッドに於けるヨーガ思想
第二節 カタハ以後の中期ウパニシャッドとギーターとに於けるヨーガ思想
第六章 古代インドの一神教的信仰
索引
英文概説

シュンペーターの経済学
創文社オンデマンド叢書
20世紀の最重要経済学者の1人であるシュンペーター(1883~1950)は、起業家精神によるイノヴェーションを、経済発展の原動力と見なした。これがシュンペーター経済学の中心にある。
イノヴェーションは、新しい財貨、新しい生産方法、新しい販売先、原料あるいは半製品の新しい供給源、新しい組織などによって引き起こされる。そしてインヴェーションが、景気循環を生むと主張した。
イノヴェーション理論以外にも、一般均衡理論、資本主義・社会主義、信用創造などの分野についても、研究をした。
シュンペーターの経済学を総合的に知るための必読書です。
【目次】
まえがき
序章 シュンペーター二元論の特有性について シュンペーターのcircular flowとフリッシュ=サミュエルソン流のstationary state
第I部 基礎工事としての経済循環の理論
第1章 シュンペーター利子論への若干の反省 ロビンズ,サミュエルソン,ハーバラー等の諸見解の吟味を通じて
第2章 シュンペーターの均衡の近傍の概念について
第II部 経済発展の理論の本質
第1章 シュンペーター経済発展理論の特徴
第2章 ポースト・ケインジアンの循環的成長理論 ハロッド,ヒックスの循環的成長論を中心に
第3章 シュンペーターの循環理論とヒックス型循環理論(I) 両理論の比較検討
第4章 シュンペーターの循環理論とヒックス型循環理論(II) 両理論の統合への試み
第III部 資本主義の長期的動向観
第1章 リカードの分配理論と資本主義動向観
第2章 マルクスの資本主義の長期的動向観
第3章 ケインズおよびケインジアンの資本主義の長期的動向観
第4章 シュンペーターの資本主義の長期的動向観
終章 シュンペーターの経済学と現代
索引

法の一般理論(新版)
創文社オンデマンド叢書
ベルギーの法学者である著者は、自然法論者であった。「組織された社会の規範」を法概念の根底に据え、法律的自然法の存在を否定したが、倫理的自然法の存在は肯定した。
第二次大戦後に「自然法論」の再生に尽力した著者は、法の根源を問い、法はどうあるべきかの法哲学を展開した。
自然法をめぐる考えを知るための必読書。
【目次】
はしがき
序論
第一部 法規範の形式的定義
序説
第一章 法規範を他から分かつ諸特徴
第一節 法=政治的社会の規範
第二節 政治権力=法規範の至高の淵源
第三節 法と公的強制
第四節 この定義への異論
第二章 法規範の性格
第一節 法=定言的掟を課す規範
第二節 法=一般的規範
第三節 体系的規範としての法=法律制度
第三章 法により規律される素材
第一節 内心の活動の除外 対神的義務および対自己的義務
第二節 社会的諸関係と法関係観念
第三節 社会的諸関係の種々の種類に応ずる法の諸部門
第四節 素材の本性に応じた法規範支配の度合
第二部 法の方法
第一章 法は「所与」か「所造」か、「学」の対象か「技術」の対象か?
第一節 問題のありかと今日の所説
第二節 「所与」説(デュギー、ジェニーなど)の吟味
第三節 法は「思慮」であり、したがって「所造」である
第二章 法形成の諸指導原理
序論
第一 法的規定の目的=世俗的公共善
第一節 世俗的公共善の観念と性格
第二節 世俗的公共善=法の積極的内容の規矩
第三節 世俗的公共善=法の消極的内容の規矩
第二 諸手段=法の技術的道具だて
序説
第一節 定義あるいは法概念論
第二節 規範に服する諸事実の立証適合性
第三節 法素材の集中
結論 法の方法についての結論およびその系論
第一節 法における技術の対象の二重性
第二節 法の相対的確実性と可変性
第三部 自然法、正義および法規範
序論
第一章 自然法の観念
第一節 伝統的概念
第二節 法律的自然法ありや?
第二章 正義の観念
第一節 現時の概念規定、ことにアリストテレスおよび聖トマスの概念規定
第二節 正義の種類
第三節 自然的正義と実定的正義
第三章 法形成における自然法および正義の「所与」
第一節 道徳と世俗的公共善
第二節 正義=法規範の通常の素材
第三節 法規範と自然法および正義の「所与」とのあいだに矛盾がある場合
訳者あとがき

国家とは何か 「政治的なもの」の探求
創文社オンデマンド叢書
「最大多数の最大幸福」の実現を是と考える功利主義によれば、人権の不可侵性は認められない。つまり、多数の幸福のために、少数の人間が犠牲になることを容認する。ロールズの「正義論」は、功利主義批判の書としてもある。
さて、著者が依拠するのは、「トミスム」である。トミスムとは、中世の大神学者トマス・アクィナスに立ち戻り、カトリック哲学による新しい価値観の立て直しをする考え方である。トミスム法哲学を継承しつつ、「組織された社会の規範」を法の根源とした。
法を制定・執行する国家とは、どのような存在であるのかを、法哲学的に解き明かした重要著作である。
【目次】
はしがき
序論
第一章 国家の予備的な諸要素
第一節 人口を構成するもろもろの人間
A 民族性
B 階級国家
第二節 領土
第二章 国家の構成的な諸要素
予備的考察
第一項 国家の目的=世俗的公共善
第一節 用語および方法の問題
第二節 公共善の主体=公衆
第三節 公共善の形式的対象=公衆がその善益として求めるもの
第四節 公共善の質料的対象あるいは素材
国家と経済
国家と人格の諸価値
もっぱら政治的な諸価値
第五節 世俗的なものと宗教的なもの
第二項 権威あるいは政治的権力
第一節 国家における権威の必要
第二節 政治的「権力」の活動対象
A 固有の意味でいう統治
B 行政
第三節 統治者の諸権利および諸特権の職分的性格
第三項 国家観念についての若干の学説の吟味
第四項 国家の起源の哲学的問題
第一節 国家=自然的社会
第二節 国家の法律的根拠についての論争
第三章 国家の諸性格
第一項 法人としての国家
第二項 主権的社会としての国家
第三項 法に服するものとしての国家
訳者あとがき

権利論
創文社オンデマンド叢書
法哲学者による「権利本質論」の重要著作を読む。人権、倫理において、人間存在に不可侵の権利があるということを法学的に問い直す著作。
「最大多数の最大幸福」の実現を是と考える功利主義によれば、人権の不可侵性は認められない。つまり、多数の幸福のために、少数の人間が犠牲になることを容認する。ロールズの「正義論」は、功利主義批判の書としてもある。
さて、著者が依拠するのは、「トミスム」である。トミスムとは、中世の大神学者トマス・アクィナスに立ち戻り、カトリック哲学による新しい価値観の立て直しをする考え方である。
本書で言うところの法は、哲学者やモラリストの「法」ではなく、法律家のいうところの法である。つまり、「実定法」である。
現代においては、「動物の権利」が、取り沙汰されることが増えてきた。
不可侵の権利とはなにか? 不可侵の権利と法の関係とは? 不可侵の権利の根源にはなにがあるのか?
あらためて、法の根源に迫る法哲学の高著である。
【目次】
序論
問題の位置
用語論=客観法と主観法
本書のプラン
第一章 権利の存在の問題
第一 否認論の叙述
第二 否認論への批判と権利の弁護
第二章 権利の定義
第一 通説的定義の叙述と批判
第二 新しい定義の提示、権利=依属-支配
第三章 権利の主体と「法人的人格性」
問題の位置
第一 自然人
第二 「法人的人格性」
第一節 社団(広義)の場合
第四章 権利の分類
分類の方法
第一 客体による分類
第二 個人間の権利と団体的権利
第三 自己中心的目的の権利と職分権
第五章 権利の利用
問題の位置
第一 職分権のコントロール
第二 自己中心的権利のコントロール(権利濫用論)
訳者あとがき