新刊書籍
レーベルで絞り込む :
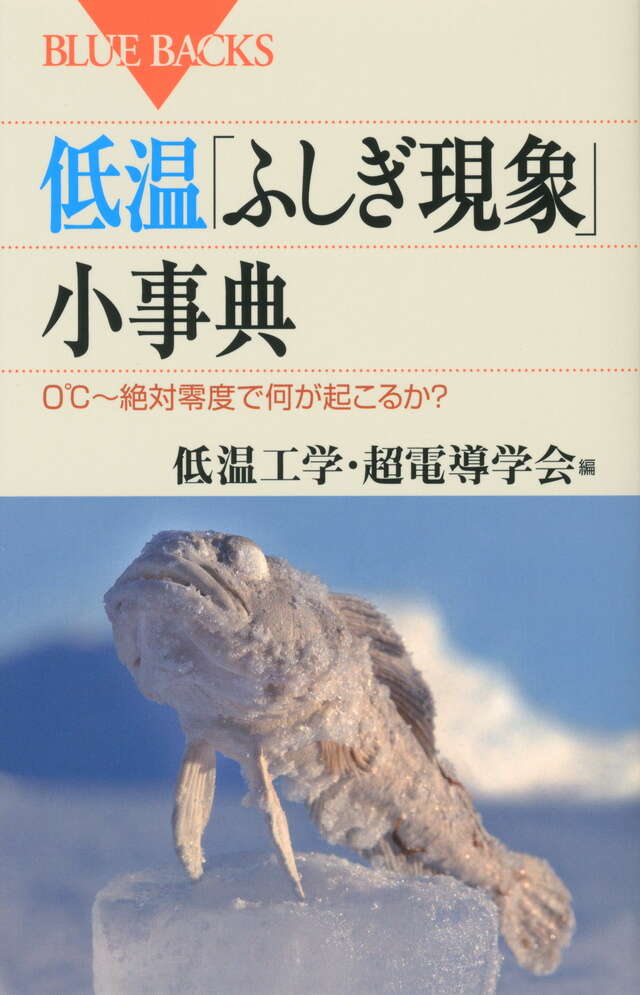
2014.11.21発売
低温「ふしぎ現象」小事典
ブルーバックス
凍った魚が蘇る「生体冷凍保存術」。最高の美味を極める「冷凍と解凍の科学」。本当は恐ろしい「低体温症」の話。無風なのに真横に煙がたなびく南極大陸の怪奇。ダークマターを捉える超ヘビー級の低温液体。電気抵抗がゼロになる「超電導」や、壁を這い上がる忍者液体「超流動」。氷点下をはるかに下回る世界で、なぜ「ふしぎ現象」が生じるのか、低温技術で何ができるかを網羅した「温度別」読む事典。
「温度の底」に向かうエレベーターに乗って
私たちがふだん生活している環境の温度は、「室温」と呼ばれています。寒い日も暑い日もありますが、絶対温度(ケルビン=K)という単位できりのいい300K程度、すなわち約27℃あたりを指す言葉です。
0℃で水が氷になることは、みなさんご存じのとおりです。ところが、氷点下を超えてどんどん温度を下げていくと、室温ではまずお目にかかることのできない「ふしぎ現象」が続々と姿を現します。いったい何が起こるのでしょうか? 極めて低い温度に到達するには、どんな技術が必要でしょうか? 果たして「温度の底」は存在するのでしょうか?
この本は、私たちが生活している温度から出発して低温の世界を探求する、好奇心あふれる旅への案内書です。みなさんは今、室温から温度の底へと向かうエレベーターに乗っていると想像してください。外の温度が下がっても凍りつくことのないように、エレベーターの壁面は断熱ガラス張りになっていますので、どうぞご安心を。私たちは、エレベーターが下がっていくそれぞれの温度で、ふしぎで面白い現象を見ることができます。
0℃(273K)から少し下がったあたりでは、一度凍った魚が生き返って泳ぎ出しています。音を使って温度を下げている人の姿もありますね。
この地球上で自然に得られる最も低い温度はマイナス89℃(184K)、極寒の大陸・南極で経験できます。南極では、コップのお湯を空中にまくと、瞬時に氷の花火が咲きます。
エレベーターがさらに下がっていくと、周囲の空気が冷えて液体へと変化します。温度はマイナス183℃(90K)。電気抵抗がゼロになる「超電導」現象が生じています。
2・177K、実にマイナス273℃以下という低温では、奇妙な液体ヘリウムの世界が登場します。忍者のように壁を這い上がり、わずかな隙間をもすり抜ける超流動液体です。極低温ならではの、超電導磁石を駆使する高エネルギー物理学者、あるいは宇宙からの赤外線天体観測を行う人たちにも出会うことでしょう。
「温度の底」へと向かうエレベーターは、果たして目標の地点に到達できるのでしょうか?

2014.11.21発売
人はなぜだまされるのか
ブルーバックス
心の機能は遺伝し、進化する! 壁のシミが幽霊に見えたり、噂話を信じやすかったり、記憶力はチンパンジーに劣ったり……。そんな人間の「愚かさ」は、高度に進化した認知機能ゆえの副作用だった。心の動きを生物進化に基づいて考える今注目の進化心理学の最新知見から、人間特有の心の本質を解き明かす。(ブルーバックス・2011年7月刊)
心の機能は遺伝し、進化する!
壁のシミが幽霊に見えたり、噂話を信じやすかったり、記憶力はチンパンジーに劣ったり……。そんな人間の「愚かさ」は、高度に進化した認知機能ゆえの副作用だった。心の動きを生物進化に基づいて考える今注目の進化心理学の最新知見から、人間特有の心の本質を解き明かす。
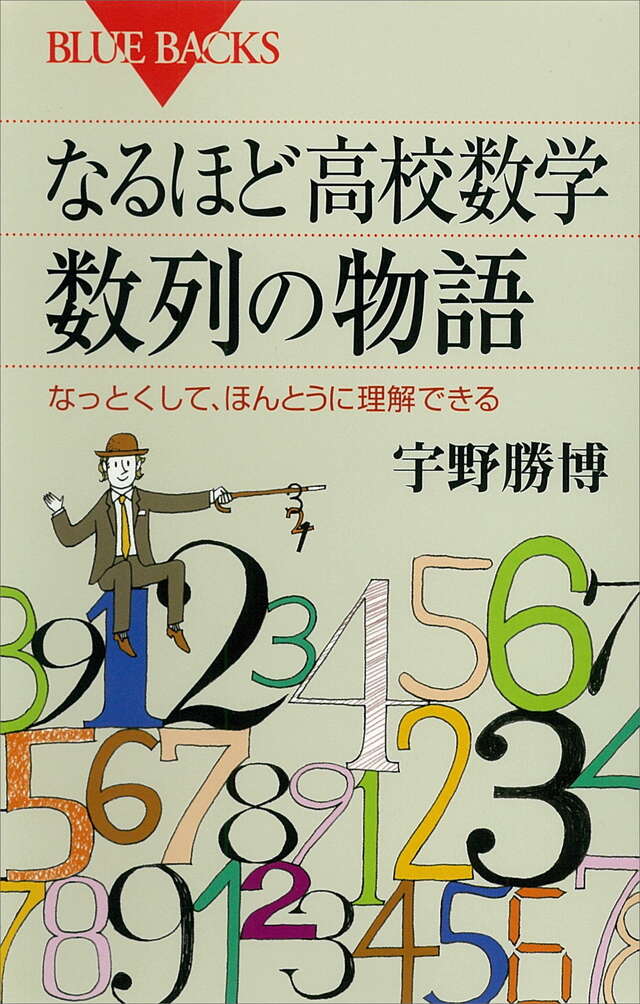
2014.11.21発売
なるほど高校数学 数列の物語
ブルーバックス
数字の並び方に秘められた謎を解く これが数列の面白さ。高校で学ぶ数学を、テーマ別に「わかりやすく、自由に、広がりを実感できる」ように語る、数学入門シリーズ。数列の表し方から、等差数列、等比数列、数列の和、パズルを解くように推理する漸化式、頭を悩ます数学的帰納法までを、ゆっくりと説明します。数列の向こう側には、無限が見えてくる! (ブルーバックス・2011年1月刊)
数字の並び方に秘められた謎を解く!
数字の並び方に秘められた謎を解く これが数列の面白さ
高校で学ぶ数学を、テーマ別に「わかりやすく、自由に、広がりを実感できる」ように語る、数学入門シリーズ。数列の表し方から、等差数列、等比数列、数列の和、パズルを解くように推理する漸化式、頭を悩ます数学的帰納法までを、ゆっくりと説明します。数列の向こう側には、無限が見えてくる!
1,4,7,10,□,16,19 □に入るのは、いくつでしょう?
数字が並んでいるものを、そのものズバリ、数列といいます。その数字の並び方の性質を調べるのが、数学の教科書に出てくる「数列」です。しかし、数字は7個しか並んでいるとは限りません。100個かもしれないし、1000個かもしれません。もしかしたら無限個並んでいるかもしれません。どうしますか? 数列の向こう側には無限が広がっています。

2014.11.21発売
光と色彩の科学
ブルーバックス
なぜわれわれに色が見えるのか? 同じ赤でも自ら光を発する赤と光の反射によって見える赤は違って見えるのか? 色を認識する視覚と脳の関係、色と光の物理的・化学的関係、色と心の関係、光を使った最先端技術まで光と色彩のさまざまな話題が満載。(ブルーバックス・2010年10月刊)
バラの赤とネオンの赤は同じ赤なのか?
光の反射と発光の違い、染色法のさまざま、漂泊の魔術、構造色の“美”の秘密、液晶テレビ、有機ELの超技術
なぜわれわれに色が見えるのか?
同じ赤でも自ら光を発する赤と光の反射によって見える赤は違って見えるのか? 色を認識する視覚と脳の関係、色と光の物理的・化学的関係、色と心の関係、光を使った最先端技術まで光と色彩のさまざまな話題が満載。

2014.11.21発売
量子重力理論とはなにか
ブルーバックス
最先端の「時空の物理学」にチャレンジしよう。時空と重力の基本原理である相対性理論と、素粒子と原子を記述する量子力学。この2つの原理を満たす時空の理論(=量子重力理論)は、はたして可能なのか? そもそも「時空を量子化する」とは、どんなことなのか? 物理学最先端の研究とその雰囲気をあえて数式を使って解説する。(ブルーバックス・2010年3月刊)
量子化される時空
最先端の「時空の物理学」にチャレンジしよう
時空と重力の基本原理である相対性理論と、素粒子と原子を記述する量子力学。この2つの原理を満たす時空の理論(=量子重力理論)は、はたして可能なのか?そもそも「時空を量子化する」とは、どんなことなのか?物理学最先端の研究とその雰囲気をあえて数式を使って解説する。
物理学最大の問題の1つ、それは時空構造の追究、つまり空間と時間の構造の数理モデルを作ることです。その条件は、時空と重力の原理である「相対性理論」と素粒子・原子などのミクロな理論「量子力学」が共に成り立つことです。では、「相対論と量子力学が共に成り立つ」とはどういうことでしょうか?それが「時空の量子化」です。
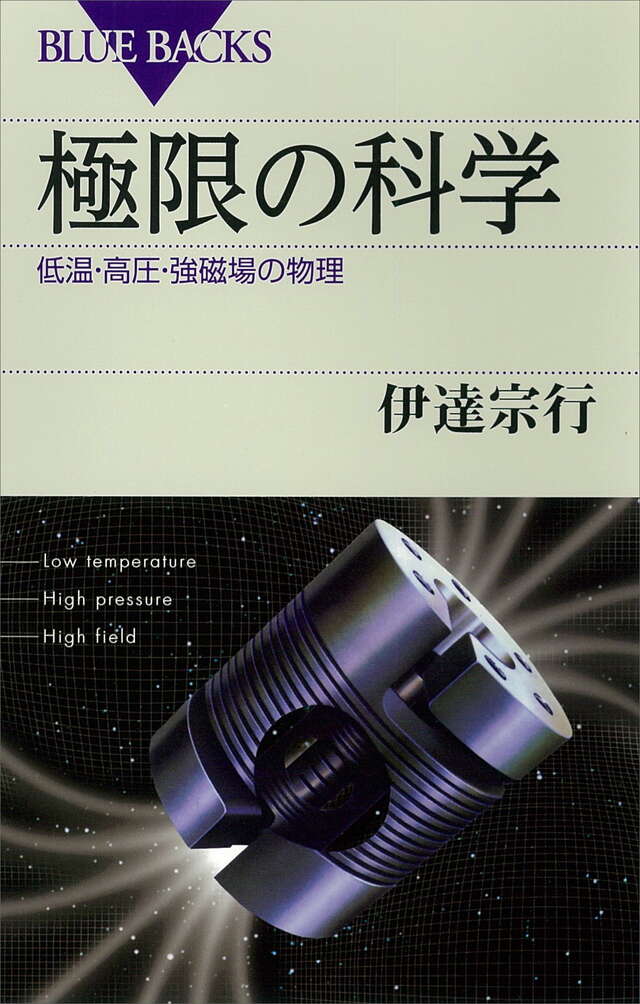
2014.11.21発売
極限の科学
ブルーバックス
ナノテクノロジーの次にやってくる極限技術の最前線に迫る。未経験な極限的世界に一歩踏み込んで物質が置かれている環境を深くゆさぶってみると、物質は思いもよらぬ新しい顔を見せてくれる。気体が金属になったり、超伝導体になったり、鉄の磁気が消えてしまったり、新しい機能の発現の画期的なヒントが満載。(ブルーバックス・2010年2月刊)
常識を覆す不思議な物質の世界
●超低温下では、原子と光が絡み合ってねばねばになる
●超高圧下では、原子核から中性子がドロドロに溶け出す
●強磁場下では、丸い原子が針状に尖ってくる
ナノテクノロジーの次にやってくる極限技術の最前線に迫る
未経験な極限的世界に一歩踏み込んで物質が置かれている環境を深くゆさぶってみると、物質は思いもよらぬ新しい顔を見せてくれる。気体が金属になったり、超伝導体になったり、鉄の磁気が消えてしまったり、新しい機能の発現の画期的なヒントが満載。
極限世界で起こるさまざまな現象
●高圧で消える鉄の磁気
●酸素が超伝導体に
●水素やシリコンが金属に
●粘性ゼロの超流動ベアリング
●電気抵抗ゼロの超伝導マグネット

2014.11.21発売
地球環境を映す鏡 南極の科学
ブルーバックス
地球上の90.6パーセントの氷が南極には存在している。巨大な氷の塊である「氷床」の厚さは富士山の高さを超え、隕石が大量に見つかるポイントがあったり、氷の下には“幻の巨大湖”が存在していたりする。温暖化の懸念から南極への注目度はますます高まるなか、オゾンホールが南極に現れる仕組みから基地における最新の観測方法やその生活内容まで、“現在の南極”にまつわるエピソードを網羅した1冊。
観測船「新しらせ」就航!
知っているようで知らない南極のスケール
●富士山より厚い氷が大陸を覆う!
●観測史上の最低気温マイナス89.2℃!
●最大瞬間風速100メートル/秒を記録!
●氷の下には琵琶湖の22倍の面積を持つ巨大湖!
知っているようで知らない南極大陸のふしぎ
地球上の90.6パーセントの氷が南極には存在している。巨大な氷の塊である「氷床」の厚さは富士山の高さを超え、隕石が大量に見つかるポイントがあったり、氷の下には“幻の巨大湖”が存在していたりする。温暖化の懸念から南極への注目度はますます高まるなか、オゾンホールが南極に現れる仕組みから基地における最新の観測方法やその生活内容まで、“現在の南極”にまつわるエピソードを網羅した1冊。
南極観測史上の3大発見
●オゾンホールの発見が環境問題への警鐘に
●1万6000個を超える南極隕石を発見
●氷の下には巨大な氷底湖が眠る
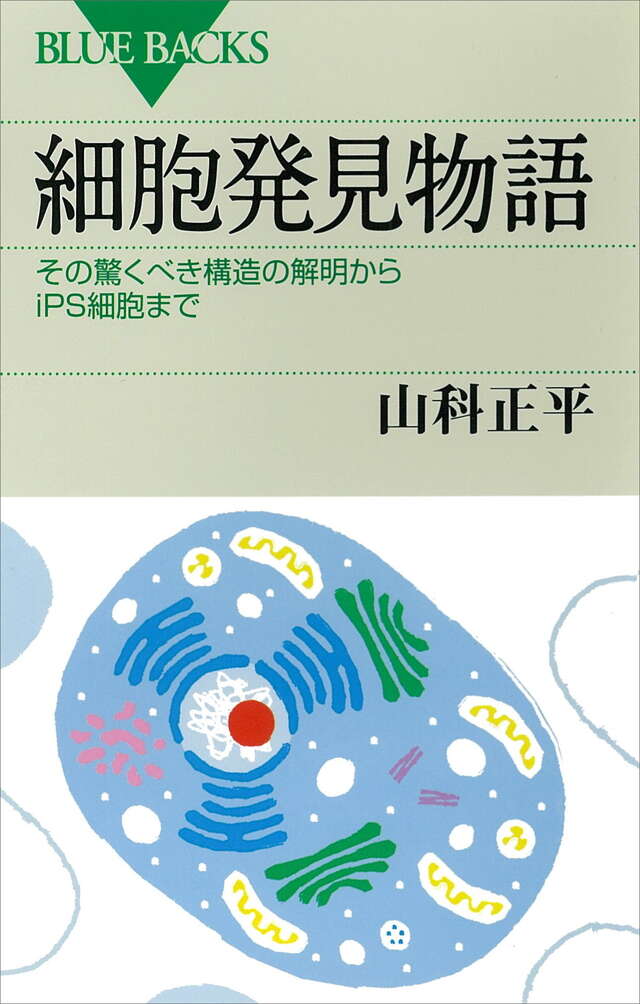
2014.11.21発売
細胞発見物語
ブルーバックス
細胞の中にも骨があるってホント!? 「生命の最小単位」=細胞がよくわかる。私たちの体を形作る60兆個の細胞。その微小世界に魅入られた研究者たちによって、生命の謎は今や分子レベルで解き明かされつつある。世界で最初の細胞図からiPS細胞の誕生まで、発見の歴史をたどりながら生命の不思議に迫る。(ブルーバックス・2009年10月刊)
物語で楽しく学ぶ細胞生物学
細胞の発見から細胞生物学の誕生、最新の研究までを、オムニバス形式で分かりやすく解説。全12話の物語を通して細胞生物学の歴史と概要が自然に理解できる。
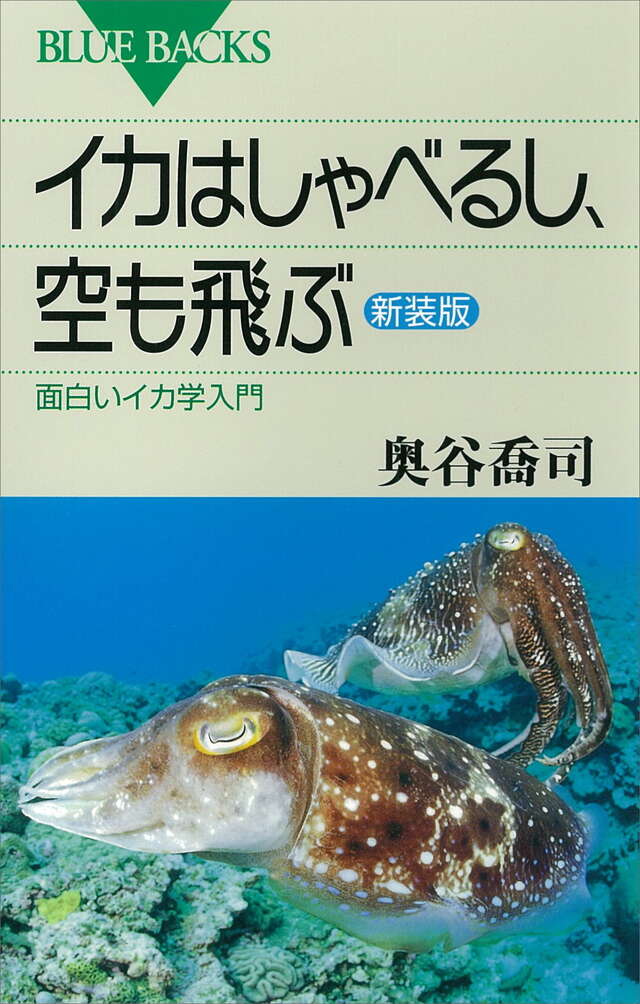
2014.11.21発売
イカはしゃべるし、空も飛ぶ〈新装版〉
ブルーバックス
知れば知るほど味わい深いイカたちの不思議な生態。古くから日本の食卓で愛されてきたイカの消費量は、サケやマグロに匹敵する。そもそも「イカ」の語源をたどれば、「食べ物そのもの」を意味しているという。トビウオのように海面上を飛ぶイカもいれば、体色の七変化で熱烈に求愛するイカもいる。さまざまなイカの魅力的な生態を余すところなく伝える“イカ学入門書”。(ブルーバックス・2009年8月刊)
イカのイカした話が満載! 読んでビックリ! 面白い!
知れば知るほど味わい深いイカたちの不思議な生態
古くから日本の食卓で愛されてきたイカの消費量は、サケやマグロに匹敵する。そもそも「イカ」の語源をたどれば、「食べ物そのもの」を意味しているという。トビウオのように海面上を飛ぶイカもいれば、体色の七変化で熱烈に求愛するイカもいる。さまざまなイカの魅力的な生態を余すところなく伝える“イカ学入門書”。
イカたちの面白いエピソードが満載!
●ヤリイカは集団結婚をする
●ホタルイカはなぜ光る?
●“おしゃべり”なイカもいる
●イカには心臓が3つもある
●イカの神経は動物で最も太い
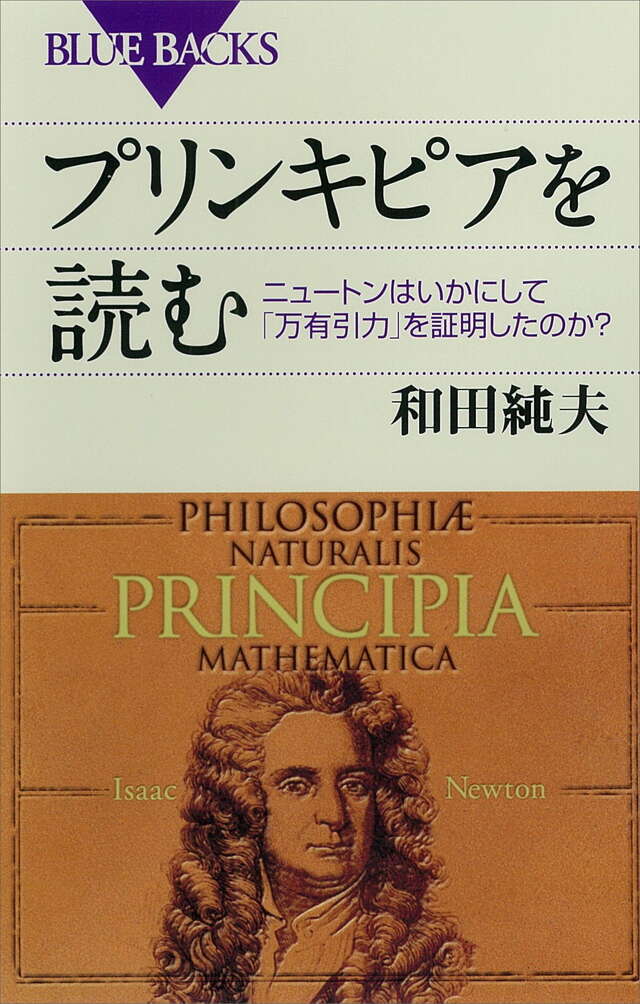
2014.11.21発売
プリンキピアを読む
ブルーバックス
ニュートンが17世紀に著した『プリンキピア』は、運動の法則や万有引力を基に自然界の仕組みを明らかにし、近代科学の出発点となった。図形を使った幾何学的な手法で力学の様々な難問を証明したニュートンのアプローチは、現代人が読んでも素晴らしく、その天才ぶりに驚嘆させられることだろう。科学史上、最も有名な本のひとつである『プリンキピア』の醍醐味を味わう1冊。(ブルーバックス・2009年5月刊)
人類の世界観を変えた科学史上最も有名なニュートンの名著を読み解く
ニュートンが遺した金字塔『プリンキピア』を丁寧に解説
ニュートンが17世紀に著した『プリンキピア』は、運動の法則や万有引力を基に自然界の仕組みを明らかにし、近代科学の出発点となった。図形を使った幾何学的な手法で力学の様々な難問を証明したニュートンのアプローチは、現代人が読んでも素晴らしく、その天才ぶりに驚嘆させられることだろう。科学史上、最も有名な本のひとつである『プリンキピア』の醍醐味を味わう1冊。
重力とは何か? 惑星はなぜ楕円運動をしているのか? 発表当時、「誰も理解できない」とさえ噂された『プリンキピア』。ニュートンが後世に多大なる影響を与えたその名著を読み解く。
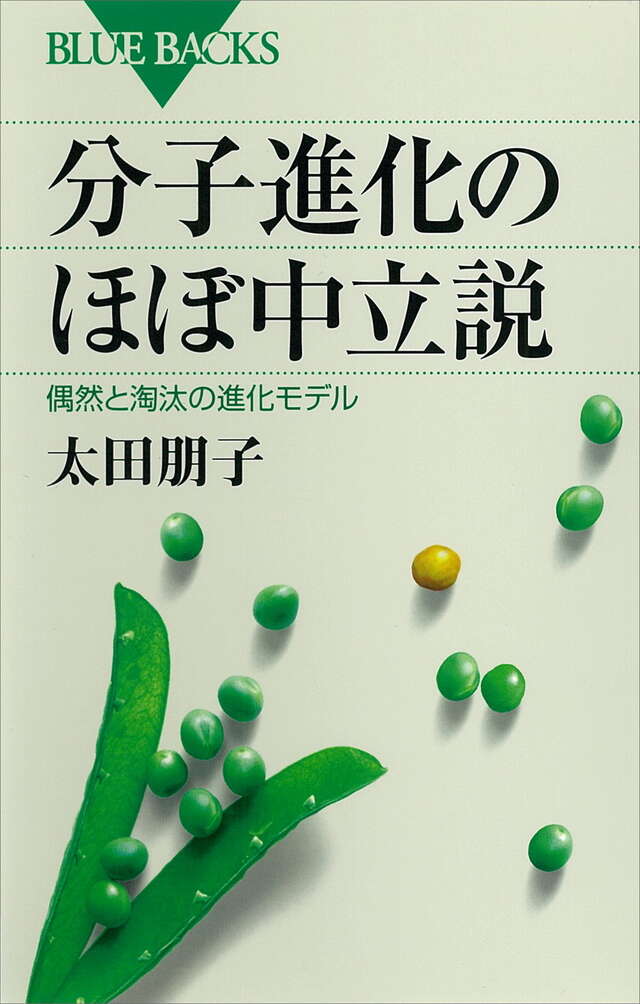
2014.11.21発売
分子進化のほぼ中立説
ブルーバックス
遺伝子から、生物進化を考える。自然淘汰だけで、進化は語れるだろうか? どんなに優れた形質でも、子に受け継がれなくては、その形質は絶えてしまう。受け継がれるかどうかは、確率が支配する。集団遺伝学の第一人者が提唱する偶然と淘汰の新しい進化モデルを解説する(ブルーバックス・2009年5月刊)
生物が進化するということは、遺伝子が変化するということだ。遺伝子は偶然と必然の微妙なバランスで進化してきた。
遺伝子から、生物進化を考える
自然淘汰だけで、進化は語れるだろうか? どんなに優れた形質でも、子に受け継がれなくては、その形質は絶えてしまう。受け継がれるかどうかは、確率が支配する。集団遺伝学の第一人者が提唱する偶然と淘汰の新しい進化モデルを解説する
1968年、国立遺伝学研究所の木村資生博士によって提唱された「中立説」は、自然選択説を信奉していた進化の研究者たちにたいへん大きな衝撃を与えました。その共同研究者で、中立説の理論的発展に貢献した著者が、実際の生物進化に即してさらに理論的に推し進めた仮説が、現在は国際的にも高く評価されている「ほぼ中立説」です。
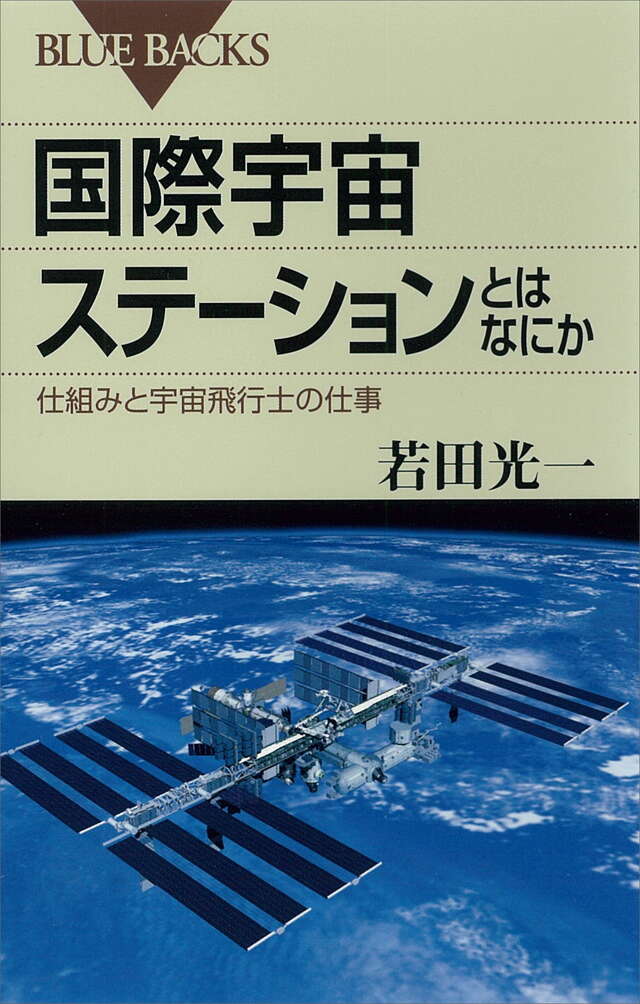
2014.11.21発売
国際宇宙ステーションとはなにか
ブルーバックス
地上400kmの宇宙に浮かぶサッカー場と同じサイズの巨大な駅(ステーション)。2010年に完成予定の国際宇宙ステーション(ISS)は、6名の宇宙飛行士が長期滞在しながら実験や観測ができる、人類初の巨大な宇宙実験施設です。日本人で初めて長期滞在する若田宇宙飛行士が、ISSの仕組み、宇宙飛行士の衣食住、訓練などを、自らの体験を通して興味深く語ります。(ブルーバックス・2009年2月刊)
若田宇宙飛行士が語る宇宙ステーションとミッション
地上400kmの宇宙に浮かぶサッカー場と同じサイズの巨大な駅(ステーション)。
2010年に完成予定の国際宇宙ステーション(ISS)は、6名の宇宙飛行士が長期滞在しながら実験や観測ができる、人類初の巨大な宇宙実験施設です。日本人で初めて長期滞在する若田宇宙飛行士が、ISSの仕組み、宇宙飛行士の衣食住、訓練などを、自らの体験を通して興味深く語ります。
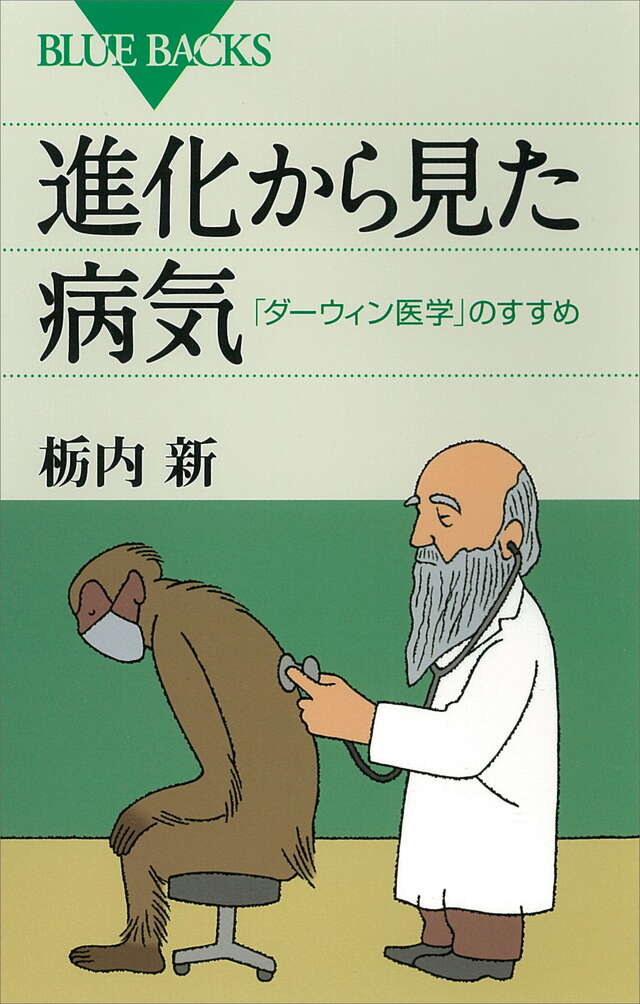
2014.11.21発売
進化から見た病気
ブルーバックス
ヒトが病気になるのは、進化による必然だった! 感染症、遺伝的疾患、生活習慣病……。「病気」はヒトにとって不都合であるように思えるが、その症状の多くは身体を守るための防御反応であるということ、また、病気の原因遺伝子にはヒトが生き延びるために有益なものがあったということがわかってきた。進化論をもとにした「ダーウィン医学」によって明らかになりつつある、病気があることの意味を豊富な例とともに平易に解説。
風邪を薬で治そうとすると、「ぶり返し」が起こりやすい!
新しい「病気とのつきあい方」を身につけよう
ヒトが病気になるのは、進化による必然だった!
感染症、遺伝的疾患、生活習慣病……。「病気」はヒトにとって不都合であるように思えるが、その症状の多くは身体を守るための防御反応であるということ、また、病気の原因遺伝子にはヒトが生き延びるために有益なものがあったということがわかってきた。進化論をもとにした「ダーウィン医学」によって明らかになりつつある、病気があることの意味を豊富な例とともに平易に解説。
「ダーウィン医学」は、医師のネシーと進化生物学者のウィリアムズによって1991年に提唱された。進化論をもとに、病気を中心とした、ヒトの身体に起こる不都合の意味を探り、治療・解決法の手がかりとすることをめざしている。ダーウィン医学が示す、ヒトの自然治癒力を生かすことの必要性や現代の医療が抱える問題点から、新しい「病気とのつきあい方」が見えてくる。
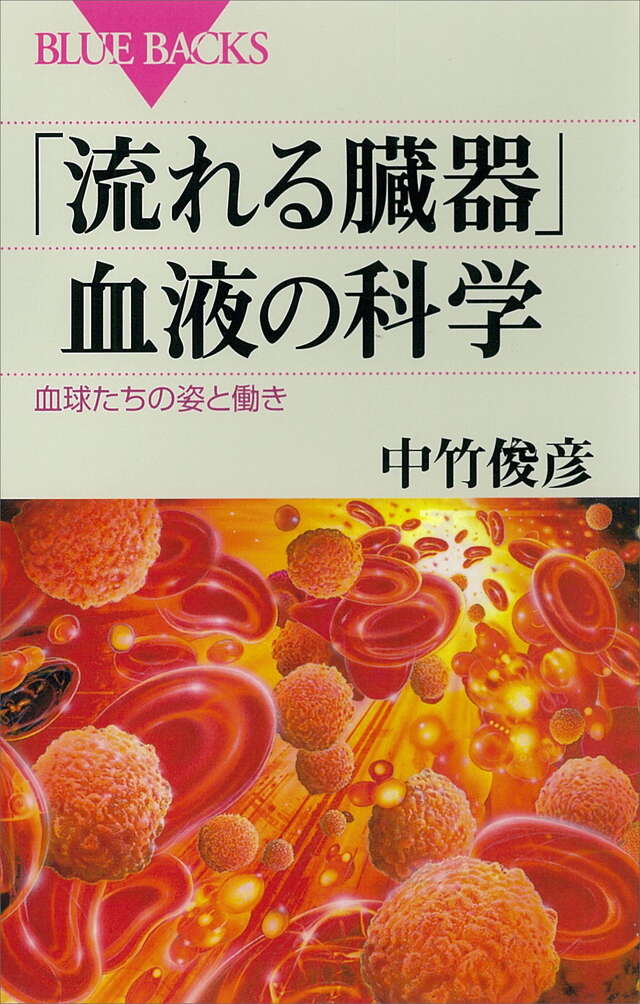
2014.11.21発売
「流れる臓器」血液の科学
ブルーバックス
血液についての「真っ赤なホント」の話! ミクロの細胞たちの驚くべきシステム。血液は固まらないから流れ、流れるから固まらない!? ヘモグロビンは酸素を運ぶが、炭酸ガスは回収しない!? 血液の凝固と止血とは似て非なるシステム!? 血液型性格診断のウソを見破った実験とは!? (ブルーバックス・2009年2月刊)
いちばん重い「臓器」の知られざる姿と働き。血液は固まらないから流れ、流れるから固まらない。ヘモグロビンは酸素を運ぶが炭酸ガスは回収しない。血液型性格判断を覆す実験結果とは? など血液の新常識。
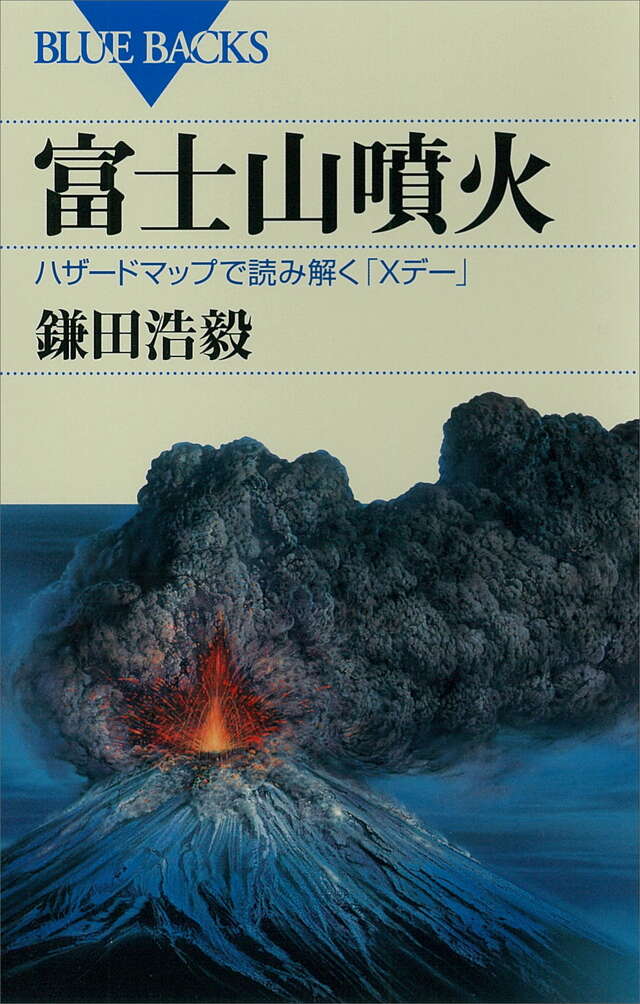
2014.11.21発売
富士山噴火
ブルーバックス
宝永噴火から300年、いま「その日」が来たら? 江戸時代以降、不気味な沈黙を続ける日本最大の活火山、富士山。もしも現代のハイテク社会が噴火に見舞われたら? 新幹線は? コンピュータは? 人体への影響は? 火山灰、溶岩流、火砕流、山体崩壊など猛威の全貌を予測して防災に役立てる「ハザードマップ」の解読法とともに、知られざる富士山の「正体」もわかる決定版! (ブルーバックス・2007年11月刊)
富士山噴火! 何が起こる? 何をすれば? 富士山は死んでいない。いつ噴火するかわからない活火山なのだ。もしXデーが来たら、どんな被害が出るのか、どう防げばよいのかを「火山の権威」が緊急提言!
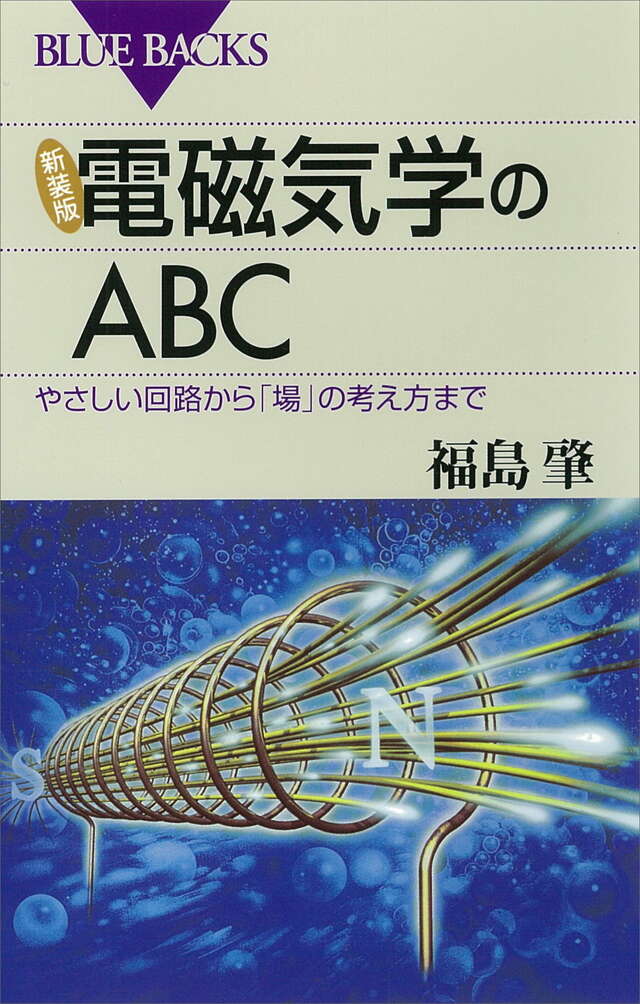
2014.11.21発売
新装版 電磁気学のABC
ブルーバックス
中高生から読める電磁気学の入門書。推理小説を読むように電磁場の本性を探る。電場と磁場 自然界に存在する2つの「場」とは、本当のところどんなものなのか? どうしてそんなものを科学者が考えたのか? 電磁気のさまざまな現象を調べながら、電場と磁場を徹底追究!(ブルーバックス・2007年9月刊)
推理小説を読むように電磁場の本性をさぐる。やさしい回路の話から始めて、「場」の考え方を徹底追究! 電場と磁場が本当のところどんなものか、どうしてそんなものを科学者が考えたのか、初めてナットク。
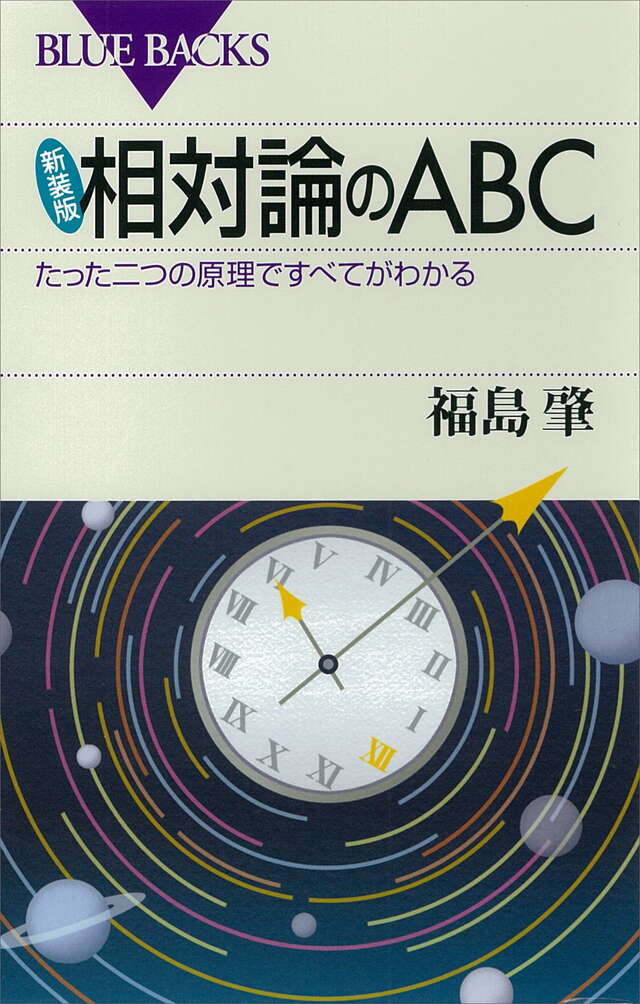
2014.11.21発売
新装版 相対論のABC
ブルーバックス
中高生から読める相対論の入門書。なぜ、時間・空間の考え方を変えなければならなかったのか? 相対論を理解するための基本原理は、たった2つ。相対性原理と、光速度不変の原理。この2つの原理の核心をつかめば、相対論は難しくない! 常識の壁を打ち破ったアインシュタインと相対論の世界へようこそ。(ブルーバックス・2007年7月刊)
中高生から読める相対論の入門書
なぜ、時間・空間の考え方を変えなければならなかったのか?
相対論を理解するための基本原理は、たった2つ。相対性原理と、光速度不変の原理。この2つの原理の核心をつかめば、相対論は難しくない!
常識の壁を打ち破ったアインシュタインと相対論の世界へようこそ。
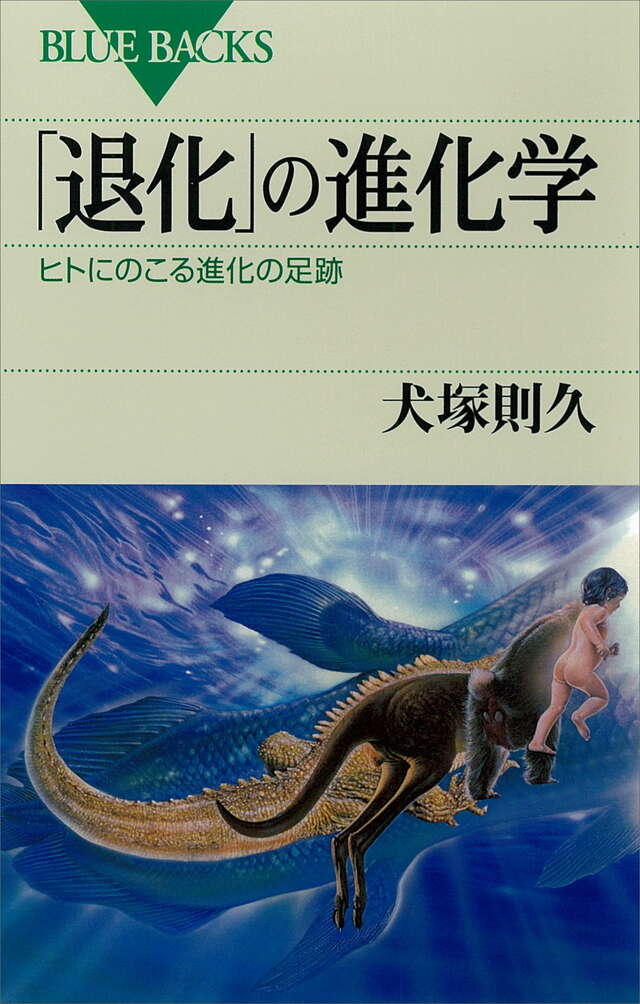
2014.11.21発売
「退化」の進化学
ブルーバックス
サメの顎が退化した耳小骨、トカゲの眼のなごりの松果体、舌にのこる「二枚舌」の痕跡、男にもある「子宮」、サメ肌から生まれた歯など、祖先とは機能を変えたり、失ったりした器官をみれば、ヒトの進化の道をたどることができる。人体には「ユネスコ世界遺産」に負けない「自然遺産」がある。さあ、このガイドブック片手に、人体遺跡めぐりの旅に出よう! (ブルーバックス・2006年12月刊)
退化器官でたどるヒト4億年の歴史
耳の中にサメの顎がのこっている!?
頭の中にはトカゲの眼のなごりが!?
男にも「子宮」がある!?
昔は「二枚舌」だった!?
口の中のサメ肌って!?
サメの顎が退化した耳小骨、トカゲの眼のなごりの松果体、舌にのこる「二枚舌」の痕跡、男にもある「子宮」、サメ肌から生まれた歯など、祖先とは機能を変えたり、失ったりした器官をみれば、ヒトの進化の道をたどることができる。
人体には「ユネスコ世界遺産」に負けない「自然遺産」がある。さあ、このガイドブック片手に、人体遺跡めぐりの旅に出よう!
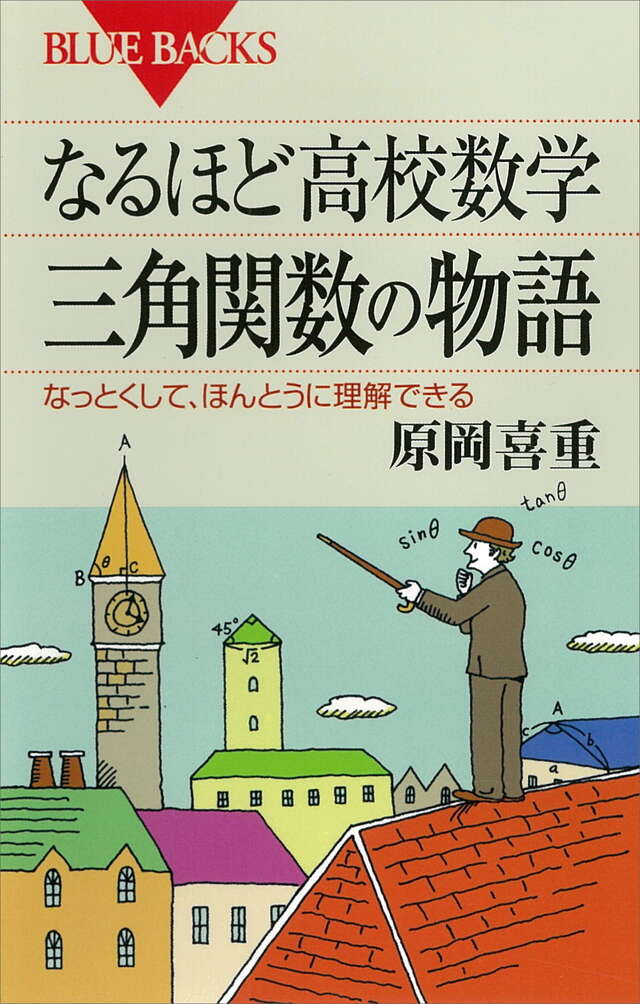
2014.11.21発売
なるほど高校数学 三角関数の物語
ブルーバックス
高校の数学って、こんなにやさしかったんだ! 「相似」さえ知っていれば大丈夫。三角関数が「まるごと」わかる。高校で学ぶ数学を、テーマ別に「わかりやすく、自由に、広がりを実感できる」ように語る、新シリーズ。意欲的な中学生から社会人まで、教科書にはない、ほんとうの数学のおもしろさを味わおう。(ブルーバックス・2005年5月刊)
高校の数学って、こんなにやさしかったんだ!
「相似」さえ知っていれば大丈夫 三角関数が「まるごと」わかる
高校で学ぶ数学を、テーマ別に「わかりやすく、自由に、広がりを実感できる」ように語る、新シリーズ。意欲的な中学生から社会人まで、教科書にはない、ほんとうの数学のおもしろさを味わおう。

2014.11.21発売
新装版 数学・まだこんなことがわからない
ブルーバックス
【講談社出版文化賞「科学出版賞」受賞作】 なにが解けない? どうして解けない? 古代ギリシアに端を発する「完全数」や「素数」の探究問題から100万ドルの賞金がかけられた「リーマン予想」「3次元ポアンカレ予想」「P=NP問題」まで世界の数学者が挑みつづけてきた未解決の難問を中学生にもわかるようにやさしく解説。予備知識がなくても現代数学の醍醐味が味わえる。(ブルーバックス・2004年9月刊)
名著復活!
講談社出版文化賞「科学出版賞」受賞作!
なにが解けない? どうして解けない?
古代ギリシアに端を発する「完全数」や「素数」の探究問題から100万ドルの賞金がかけられた「リーマン予想」「3次元ポアンカレ予想」「P=NP問題」まで世界の数学者が挑みつづけてきた未解決の難問を中学生にもわかるようにやさしく解説。予備知識がなくても現代数学の醍醐味が味わえる。
証明できるか?――ゴールドバッハの予想
(1) 2より大きなすべての偶数は2個の素数の和である
(2) 7より大きな奇数はすべて3個の奇素数の和である
(3) 5より大きな整数はすべて3個の素数の和である