新刊書籍
レーベルで絞り込む :

2024.09.30発売
パスカル
創文社オンデマンド叢書
「人間はかんがえる葦である」で知られる17世紀の哲学者・数学者・論理学者など万能の天才はジャンセニストでもあった。偉大なる哲学者のキリスト教的意識の実態を探究する。
【目次】
著者のまえがき
第一章 メモリアル パスカルの生涯における宗教的危機
第二章 人間とその現実界における位置
第三章 自然と人工
第四章 かくれた神と心情
第五章 賭けの論証 一つの歴史的関連
第六章 パスカルの論争
訳者のあとがき

2024.09.30発売
ドストエーフスキイ
創文社オンデマンド叢書
19世紀ロシアの文豪の5大作品『罪と罰』『白痴』「悪霊』『未成年』『カラマーゾフの兄弟』を宗教哲学者が読み解く。
【目次】
まえがき ドストエフスキーの世界における宗教的なるもの
第一章 民衆、および民衆の聖なるものへの道
民衆/敬虔な女たち/異教
第二章 静かな人々と偉大な受容
民衆と個人/ソーニャ・アンドレーヴナ/ソーニャ・セミョーノヴナ
第三章 宗教的な男たち
民衆と宗教的な男たち/巡礼者マカール/ゾシマ長老とその兄マルケル
第四章 智天使(ケルビム)
これまでとの関連/アリョーシャ・カラマーゾフ/真理と天使
第五章 反抗
大審問官の説話とその作者/イワン・カラマーゾフ/説話と、それに関連する問題
第六章 無神
まえがき/キリーロフ/有限性と無/スタヴローギン
第七章 キリストの象徴
設問/ムイシュキンの人格/人物の意味
あとがき
訳者あとがき

2024.09.30発売
文化への発言(フォルミカ選書)
創文社オンデマンド叢書
「第二芸術論」で知られる思想家は、戦後の京都学派の中心人物として、さまざまな文化活動に関係した。また、フランス文学・フランス文化への造詣が深く、独自の思想でも知られる。その著者が、文化をどう捉えていたのかを示す好著である。
【目次】
ナショナリズムと文化
今日における歌舞伎
文化遺産のうけつぎ
伝承問答
伝統と民族性
地方文化私見
日本インテリの弱さ
素朴ヒューマニズム
西洋文学研究者の自戒的反省
人間性の試金石
文学者と酒
日本映画の成長
漢文必修などと
みんなの日本語
子の名づけの問題
南方熊楠の学問
桑原隲蔵小伝
あとがき

2024.09.30発売
夜明けのランプ
創文社オンデマンド叢書
ほのかにゆらぐランプの灯の下で遠い日の愛の思い出は悲しみの花びらを綴る。清冽な抒情をたたえた草原に輝く愛の姿を、敬虔な祈りをこめて描く。寡作な純文学作家の珠玉の小品集。
【目次】
星の聲
夜明けのランプ
羽衣
湖尻の芒
西瓜
ハンカチーフ
深雪
霜細道
樹林の中
あとがき

2024.09.30発売
鶴の書
創文社オンデマンド叢書
寡作な作家の短編集。美しくも恐ろしい夜明けの蒼さに震える表題作「鶴の書」他を収録したもの。
【目次】
山吹
鶴の書
炎晝
ともしび
黄落
あとがき

2024.09.30発売
古い中国と新しい中国
創文社オンデマンド叢書
古代中国学の泰斗による、中国をめぐる学術的随想。日中国交がまだ正常化される前の中国訪問で、古代中国と現代の中国に何を思ったのか。
【目次】
古い中国と新しい中国
民族の復活
東洋における学問の自由
中国の伝統
中共の歴史的背景
古支那学者の回顧と反省
一 現実の革命と学者の革命
二 民主主義の挫折と内藤博士の予言
中国人の考え方
中国古代都市における民会の制度
礼
ウェーバーの儒教観
書後

2024.09.30発売
ヨルダンの此岸に立ちて
創文社オンデマンド叢書
1960年代、日本の大学を吹き荒れた“大学紛争”の嵐の中で学問への志半ばにして、その解決に邁進し逝った若き学者。その真摯な姿はヨルダン河を渡らずして別れたヨシュア記のモーゼを思わせる。大学紛争の記録としても重要な史料である。
【目次】
第一部 法の精神と大学の理念
大学改革への断想
大学格差論 国・公・私立大学の格差を是正する途
法とは何か 法に対する懐疑と憧憬
秋灯対談 大臣と学長
ある戦い アレクサンダー博士のこと
プロイセン一般ラント法と良心の自由
靖国神社法案反対の思想的根拠は何か
塵のにおい
第二部 学園紛争の嵐の中で
闘うキリスト者同盟の諸君に答えかつ問う
一九六九年明治学院大学文学部入学式式辞
学長代行声明 (一)~(十二)
父兄に訴える
明学大改革の基本姿勢
大学改革実現への具体策 クラス制への問題提起
大学に秩序と平和を
ご父兄保証人各位への報告
講義
大学の自由と平和のために 無法との闘い
教職員各位へ
遠い家
近い家
個々の目覚め必要 アンケートに答える
自由で平和な大学を
大学の現状を語りかつ訴える(対談)
座談会 学長を囲んで
新春クリスマス対談
明治学院大学卒業式式辞(一九七四・三)
第三部 教会と共に歩んで
通信
総会に臨んで
近隣の救い
チュービンゲンのクリスマス
”救われる者は誰か” マタイによる福音書一九章一六~三〇節
人格神と人格的交わり
修養会の印象
聖書研究「ピリピ人への手紙」(二章一九~三〇節)(対談)
信仰と職業 工藤英一氏著『職業と社会』から
現代日本と美竹教会 浅野順一先生との対談
前進か後退か 信音二〇〇号編集の歩み
戦争の問題について 終戦記念懇談会報告
ドイツの教会について
なぜ美竹の教勢は減ってゆくか!?
主を恐れることは知識のはじめである 箴言一・七
エルサレムを救う者
いちぢくの木の下のナタナエル
知識のはじめ
主の復活の証人 使徒行伝一・一五~二六より
エテロ 豊かなる人格 出エジプト記一八章より
道標
夏休みを終えるに当って
終末の日と新しき世 出エジプト記一三・二二
解説
故 和田昌衛氏略年譜
追想(和田和子)
明治学院大学紛争事実経過

2024.09.30発売
リルケの墓
創文社オンデマンド叢書
詩人リルケがその美しい風光を愛し、幾多の名作を産んだスイスの高原地帯・ヴァレーを、詩人の墓地、詩人が晩年をおくったミュゾットの館、そしてアルプスの主峰モン・ブランへと辿った旅の記録。
「しかし今、夏の午後の明るい光の中で、私の眼はこの岩山に荒寥としたスペインの風景とは全く違ったもの、人間を拒むというよりはむしろ人間を包むような、人間を遙かに高く超えてはいるが深く人間的であるような、いわば精神の秩序に精妙に調和する天界の風景を観照する。この明るさ、優しさ、親しみ深さ。」(「ミュゾットの館」の章より)
【目次】
ブリッグにて
リルケの墓
ミュゾットの館
モン・ブラン
あとがき

2024.09.30発売
日本史概説
創文社オンデマンド叢書
日本の法制史の泰斗がその該博な知識をもって、日本の歴史の流れを大きくつかんで紹介する。政治史の大きな動きが捉えられる入門書。
【目次】
序説
第一篇 原始時代(原始社会)
第二篇 上代(氏族的古代社会・前期古代社会)
序説 一 上代の発展概要 二 氏族的古代社会 三 史料
第一章 弥生文化の成立と氏族社会の発達(初期氏族社会 上代前期)
第二章 統合的氏族国家の成立及び発展と氏族社会(統合的氏族社会 上代中期)
第三章 氏姓国家とその文化(氏姓社会 上代後期)
第三篇 上世(律令的古代社会・後期古代社会)
第一章 大化改新(広義、上世前期)
第二章 律令社会(狭義、上世中期)
第三章 律令社会の衰頽(上世後期 格式社会)
第四篇 中世(古代的封建社会・庄園的封建社会)
序説 一 中世の発展概要 二 庄(荘)園的封建社会
第一章 貴族社会(中世前期 平安時代後半期)
第二章 庄園的封建社会(中世中期 鎌倉時代)
第三章 庄園的封建社会の衰頽(中世後期 室町時代)
第五篇 近世(封建社会・藩村的封建社会)
序説 一 近世の発展概要 二 藩村的封建社会
第一章 戦国時代(近世前期)
第二章 藩村的封建社会(近世中期 桃山時代及び江戸時代前半期)
第三章 藩村的封建社会の衰頽(近世後期 江戸時代後半期)
第六篇 近代(半封建的資本主義社会)
序説 一 近代の発展概要 二 半封建的近代社会
第一章 明治維新(近代前期)
第二章 君主立憲政治時代(近代中期)
第三章 君主立憲政治の衰頽と太平洋戦爭(近代後期)
第七篇 現代(民主立憲政治時代・資本主義社会)
結び
跋
索引
年表
一 上代 二 上世 三 中世 四 近世 五 近代 六 現代
附 皇統略図・藤原氏略系図・平氏略系図・源氏略系図・北条氏略系図・足利氏略系図・徳川氏略系図・歴代内閣総理大臣一覧・国と都府県対照表

2024.09.30発売
貿易利益と国際収支(数量経済学選書)
創文社オンデマンド叢書
競争の最適化、内部経済、外部経済、不完全競争、次善問題、安定条件、二分法などの問題を国際経済の具体的な諸問題にそくして、議論を展開をしたもの。一般均衡理論をツールとして、分析を行う。
【目次】
目次
はしがき
I ヘクシャー・オリーン理論
はしがき
1 閉鎖経済の二部門分析
2 開放経済の二部門モデル
3 ヘクシャー・オリーンの定理
II 貿易均衡の存在と最適性
はしがき
1 ミル・チップマンのケース
2 二国二財二要素の一般的ケース
3 輸送費の導入
III 収穫逓増による国際分業 1 マーシャルの外部経済
はしがき
1 貿易利益の部分均衡分析
2 貿易利益の一般均衡分析
3 完全特化の可能性
IV 収穫逓増による国際分業 2 不完全競争
はしがき
1 貿易論と立地論
2 貿易の不完全競争モデル
3 貿易利益の論証
V 国内経済のゆがみと次善的関税
はしがき
1 バグワティ・ラマスワミの所論
2 産業間賃金格差によるゆがみ
3 潜在的失業のゆがみ
VI 関税同盟の次善理論
はしがき
1 先行する諸理論
2 同盟国の利害
3 世界全体の利害
VII 幼稚産業の保護育成
はしがき
1 産業保護の諸基準
2 産業保護の部分均衡分析
3 産業保護の一般均衡分析
VIII 最適資本移動の動学的分析
はしがき
1 最適資本移動の静学的分析
2 純粋資本移動の長期的モデル
3 貿易と資本移動の二期間モデル
IX 為替市場の安定条件
はしがき
1 安定分析
2 ヒックス安定と国際収支
3 金融政策と国際収支
X 国際経済学の二分法 実物的分析と貨幣的分析
はしがき
1 対象の二分法と方法の二分法
2 分離性と貿易収支均衡
3 マーシャル・ラーナー安定条件
XI 経済成長と国際収支
はしがき
1 マクロ分析
2 交易条件と国際収支
3 物価安定と国際収支
索引
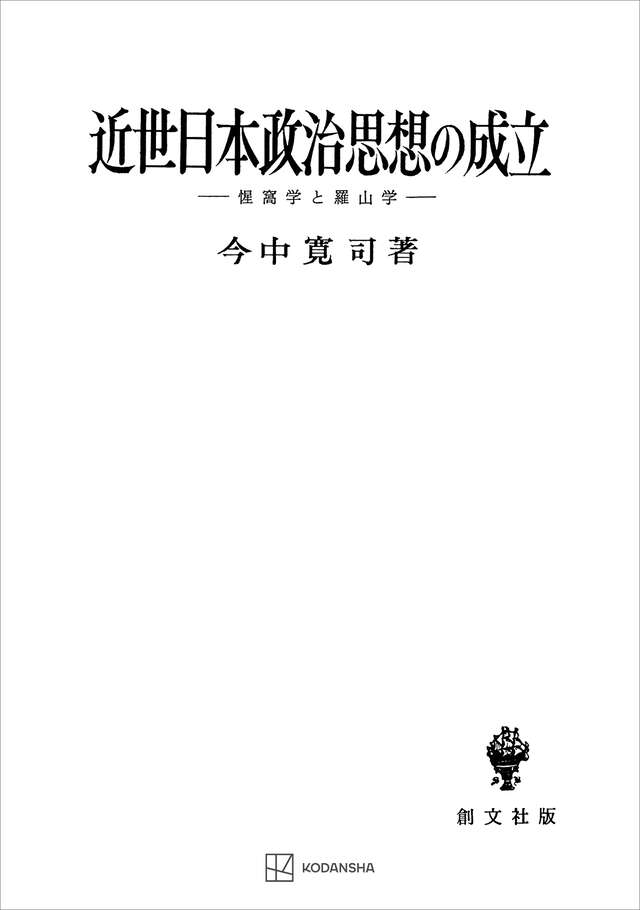
2024.09.30発売
近世日本政治思想の成立
創文社オンデマンド叢書
江戸時代を代表する儒学者・藤原惺窩(1561~1619)と朱子学者・林羅山(1583-1657)における、政治的思想を検討し、江戸期における政治思想の成立の実態を解き明かす。
【目次】
序章 中国及びわが国儒学の概略
第一章 惺窩の学風と学統
第一節 藤原惺窩の経歴
第二節 惺窩の『四書五経倭訓』と姜〓
(一)『四書五経倭訓』
(二)姜〓との関係
第三節 惺窩学の成立
第二章 惺窩の職能
第一節 惺窩の「友社」とその生活
第二節 御伽衆藤原惺窩
(一)御伽衆
(二)近世的職能
第三節 排仏帰儒
第四節 惺窩学の歴史的評価
第三章 羅山学の成立
第一節 林羅山の経歴と建仁寺の学問
第二節 『心学五倫書』をめぐる近世思想史上の諸問題
(一)『心学五倫書』の著作者問題
(二)羅山との関係
第三節 「心学」的思想形態の伝統
(一)『心学五倫書』の歴史的背景
(二)羅山と心学
第四節 羅山の理当心地神道
(一)清原宣賢の『日本紀神代抄』
(二)羅山の理当心地神道
第四章 羅山学とその学統
第一節 羅山の教訓仮名抄
(一)江戸時代初頭の教訓仮名抄
(二)羅山抄
第二節 四書仮名抄と羅山学
(一)清原宣賢の『孟子抄』
(二)羅山抄の思想
第三節 羅山の政治思想
第四節 羅山学の学統と清家学の伝統
索引

2024.09.30発売
場所的論理と呼応の原理
創文社オンデマンド叢書
京都学派の哲学者高山岩男が、自身の哲学の二つの根本原理とした場所的論理と呼応の原理についてものした画期的な著作である。1976年創文社により刊行された本書は、1951年に刊行された弘文堂版を改訂したものになる。 師の田邊元は、本書を一部認め、一部不十分と批評した。
構成
【目次】
前篇 場所的論理と呼応の原理
第一章 序説 種々の論理(一―二)
第二章 論理の根本原理(三―七)
第三章 呼応の原理と場所的論理(八―一〇)
第四章 呼応的論理の段階(一一―一六)
第一節 技術と科学(一一―一二)
第二節 社会と歴史(一三―一六)
第五章 宗教と呼応的論理(一七―二〇)
後篇 所の倫理
第一章 所の倫理の概念について
第二章 所の倫理と秩序の理念
第三章 欲望と自然的均衡秩序
第四章 理性的人格と法的秩序
第五章 場と所と個と
第六章 文化の所と創造性
第七章 無我の道義性と創造的世界観

2024.09.30発売
道徳の危機と新倫理
創文社オンデマンド叢書
第二次大戦終戦後7年目に書かれた本書は、戦後になって失われつつあった戦前の「道徳」教育を、あらためて問い直すともに、新時代に相応しい新たな「倫理」のあり方を模索する。
【目次】
序
道徳の頽廃 戦後頽廃の諸相
一 戦後の犯罪と不道徳
二 道徳感覚の磨滅
三 虚無的頽廃
四 道徳的原理の無政府
道徳の危機 新倫理とは何ぞや
一 倫理の革新とは何か
二 新倫理の在所
三 十九世紀的観念の崩壊
四 現代文明の倫理的危機
五 現代世界の倫理的危機
六 新倫理の方向
新しき社会
一 封建社会と市民社会
二 近代社会の倫理
三 近代経済の危機
四 近代政治の危機
五 封建意識の再生
六 共産主義と全体主義
倫理の永遠性と創造性
一 倫理の変化と不変
二 進歩するものとせざるもの
三 道徳的人格
四 文明の創造と文化の創造
五 倫理の創造性
六 道徳意志の普遍性
倫理の権威と限界
一 倫理の有限性の問題
二 倫理至上主義の誤謬
三 真の宗教と擬似宗教
四 倫理と宗教
倫理教育の反省
一 新倫理教育への疑問 その一
二 新倫理教育への疑問 その二
三 道徳教育の意味
四 道徳的判断力の育成
職業倫理の問題
一 教師の倫理
二 職業倫理の本質
三 階級倫理の問題
国民道徳の問題
一 国民道徳の意味
二 日本の国民道徳 その一
三 日本の国民道徳 その二

2024.09.30発売
宗教はなぜ必要か(フォルミカ選書)
創文社オンデマンド叢書
京都学派の哲学者である著者が、宗教の必要性についてさまざまな角度から検討を加え、考察した。人間にとって宗教(的なるもの)がなくならないわけを探究する。
【目次】
目次
第一 宗教への懐疑
一 現代的知性の宗教への懐疑
二 延命長壽・願望滿足の宗教、祈祷宗教
三 造物神、審判者、惡神、靈魂不滅
四 眞實の宗教と似而非宗教
五 科學と宗教
六 自然宗教と髙等宗教
七 知性の限界と道徳の限界
八 總括
第二 宗教の本質
一 宗教的要求、宗教心、無常
二 宗教的疑惑、宗教的絶望
三 宗教的世界と宗教的課題
四 人間的價値の超越、生死からの死
五 自力・他力の呼應的關係
六 神の人格性、人格的宗教
七 空・無、哲學的宗教
第三 宗教と生活
一 日常の淨化、道徳的淨化と宗教的淨化
二 目的・手段の超越、永遠、死後の救濟
三 宗教と文化、宗教と社會革命
四 現代文化と純粹宗教性
五 技術文明と宗教、神の創造
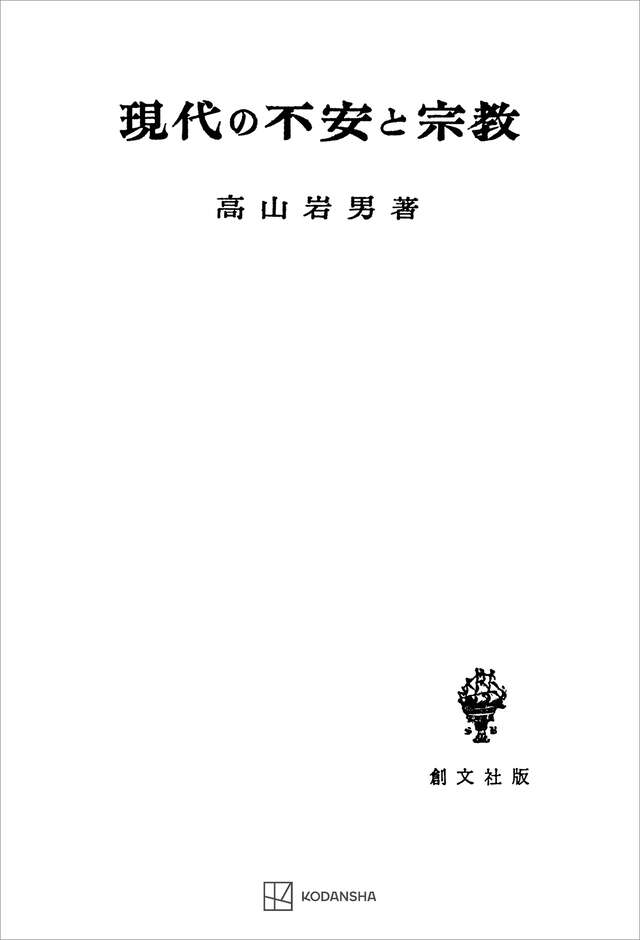
2024.09.30発売
現代の不安と宗教
創文社オンデマンド叢書
科学が発達した現在においても、なぜ宗教はなくならないのか? 現代特有の不安の感覚と現代における宗教の役割を解き明かす。
【目次】
現代の不安と宗教の問題
一 世界不安の由つて来るところ
二 民主主義の直面せる逆説的矛盾
三 現代倫理の直面せる逆説的矛盾
四 人間至上主義の解体 精神革命
五 現代の要求する宗教性
現代の神話と現代的迷信
一 科学に対する現代人の迷信
二 技術に対する現代人の迷信
三 経済力に対する現代人の信仰
四 現代に於ける革命神話
五 現代に神話と迷信の発生する理由
宗教の世界 科学に対して
一 宗教の言葉と科学の言葉
二 人間的現実と宗教心の在所
三 価値は無価値だという体験
四 一切の相対を超える世界
五 科学と宗教との平和的共存
宗教の世界 道徳に対して
一 宗教と道徳との間の断絶性
二 道徳の世界に救済はない
三 苦悩・安心・生死脱落
四 無明・無我・復活・新生
五 自由の自己矛盾・絶望・罪
六 信仰・懺悔・愛・慈悲
七 二つの道 有神論と無神論
宗教の世界 文明に対して
一 人類愛の実現としての文明
二 技術は宗教と結びつくか
三 技術・発明・創造の神秘性
四 技術の創造的世界観
五 文化の創造と創造の精神
宗教の世界 歴史に対して
一 歴史的課題と宗教的課題
二 末法の宗教的歴史意識(一)
三 末法の宗教的歴史意識(二)
四 現代の末法性の自覚

2024.09.30発売
教育と倫理
創文社オンデマンド叢書
京都学派の哲学者による、教育における「倫理」のあり方をめぐる考察。戦前と戦後の教育をめぐる変化への興味深い解析がある。また、軍隊の考え方、道徳教育、保守と革新の違いなどを徹底的に論ずる。
【目次】
序
教育の前提となる人間観
教育勅語と教育基本法
道徳教育の本質とその前提
社会科と社会科的思考法
現代の政治・社会に関する思想 社会科的思考法育成のため
緒言
第一章 民主主義とその問題点
第二章 自由主義とその問題点
第三章 社会主義・共産主義とその問題点
第四章 中立主義とその問題点
民主政治と立憲的独裁
保守と革新 保守主義の哲学
歴史教育について
社会科教科書雑感
協同社会の理念
教育の政治的中立性
日教組の「教師の倫理綱領」批判
教師の新倫理綱領を提唱する
旧日本軍隊の軍人精神と精神教育
序論 軍人精神の固有性と歴史性
第一章 精神教育の方針
第二章 将校の精神教育の問題
第三章 軍事と政治 軍人精神の破綻
軍人倫理
序説
第一章 職業倫理
第二章 国民倫理
第三章 軍人倫理
附録
一 教育に関する勅語 二 教育基本法 三 教師の倫理綱領

2024.09.30発売
西田幾多郎先生の生涯と思想
創文社オンデマンド叢書
京都学派四天王の一人である著者が、京都学派の創始者である西田幾多郎の生涯とその思想を、謦咳に触れた経験をもとに論じきったもの。
【目次】
序
序章 『善の研究』の生まれるまで
第一節 先生の回顧
第二節 先生の日記
第一章 純粋経験の立場
第一節 若き日の体験
第二節 善の研究
I 純粋経験の性格
II 実在の真景
III 純粋経験と善
第二章 自覚の立場
第一節 純粋経験から自覚へ
I 学の哲学と生の哲学
II 純粋経験の二義性
III 『思索と体験』
第二節 自覚の体系
I 自覚の構造
II 純粋思惟の体系から経験体系へ
III 物質・生命・精神
第三章 場所の立場
第一節 自覚から場所へ
I 先生の講義
II 直観主義と論理主義の結合
第二節 三つの場所
I 場所の論理
II 三つの場所
III 叡智的世界
第四章 弁証法的世界の立場
第一節 その頃の先生
第二節 『無の自覚的限定』の有つ二つの意味
I 場所から世界への過渡的意味
II 我と汝
第三節 哲学体系の試み
I 弁証法的世界の図式
II 一即多、多即一
III 外即内、内即外
第五章 矛盾的自己同一の立場
第一節 晩年の先生
第二節 行為的直観の構造
I 身体・道具・言語
II 種の問題
第三節 大患・表現的体系の深化
第四節 絶対矛盾的自己同一の体系
I 物質的世界
II 生命的世界
III 歴史的世界
第五節 先生と宗教
I 先生の宗教観
II 先生の死
再刊にあたって(久山康)

2024.09.30発売
詩と哲学
創文社オンデマンド叢書
古来より、詩と哲学の関連については、多くの議論がなされてきた。この議論は、つきつめれば「芸術」と「真理」との関係に通じるのである。京都学派四天王の一人である著者による、詩と哲学の関係を探究したもの。
【目次】
ハイデッガーとヘルダーリン
ドストエーフスキイの「大審問官」と現代
ゲーテとカント
デカルトと実存
実存主義の真理性とその限界

2024.09.30発売
あたりまえのこと
創文社オンデマンド叢書
ドイツ哲学とくに実存哲学者であった著者が、日々の出来事について、さまざまに思い巡らせた随想をまとめたものである。
【目次】
あたりまえのこと
忘れる
自由について
批評について
ソクラテスの反語
永遠の女性
実存と死
言葉の魔力
神の不在
西洋的ものの考え方
あたりまえのことは忘れられる
現代への一提言
私の歩んだ道
坂のある町
三途の川
教育のむずかしさ
お粗末な「美談」
郷里のこと
麦笛
郷愁食
郷里の正月
友あり遠方より……
教師
私の仕事部屋
いつもおそすぎる人生
新しい旅をもとめて
出会い
野球談義
早稲田祭によせて
考えない人達
就職ブームの明暗
人間の限界
汚れた人生
方丈記
拈華微笑
自然を守れ
仕方がない
貝になりたい
仏教と庶民の間
出会い
見るということ
見るということ
「ひとり」と「ひと」
自殺について
逸民
神話は生きている
健忘症
せっかちな文明
哲学は主張する
もて扱いかねる「自由」
告発の相手
この孤独感
心なき人生
歴史の深さ
随想
良き人と良き社会
人づくり
学問知識の氾濫
自分の言葉
学問について
思いつくまま
あとがきにかえて(岡田幸一)

2024.09.30発売
ヨーロッパの歴史
創文社オンデマンド叢書
「マホメットなくしてシャルルマーニュなし」のテーゼで知られるベルギーの歴史家による、1500年にわたる西欧の歴史の大きな流れを描く。アンリ・ピレンヌの代表作。歴史の原動力を商業と工業と捉え、理念よりも事実に即した歴史記述で知られる。
【目次】
序文 ジャック・ピレンヌ
序
第一編 西方におけるローマ世界の終末(回教徒の侵入まで)
第一章 ローマ帝国内の蛮族諸王国
第二章 ユスティニアーヌス ランゴバルド族
第三章 回教徒の侵入
第二編 カーロリンガ時代
第一章 教会
第二章 フランク王国
第三章 西方における帝国の復興
第四章 経済と社会の組織
第三編 封建ヨーロッパ
第一章 帝国の解体
第二章 ヨーロッパの分裂
第三章 封建制
第四編 叙任権闘争と十字軍
第一章 教会
第二章 叙任権闘争
第三章 十字軍
第五編 市民の成立
第一章 商業の復活
第二章 都市の成立
第三章 都市の伝播とその諸結果
第六編 西ヨーロッパ諸国の登場
第一章 イギリス
第二章 フランス
第三章 帝国
第七編 一三世紀における教皇権の主導権とフランスの主導権
第一章 教皇権と教会
第二章 教皇権、イタリア、及びドイツ
第三章 フランス
第四章 フィリップ美男王とボニファティウス八世
第八編 ヨーロッパの危機(一三〇〇―一四五〇年) アヴィニョンの教皇権と教会大分裂と百年戦争との時代
第一章 時代の一般的諸特徴
第二章 百年戦争
第三章 帝国。 スラヴ諸国家とハンガリー。
第四章 スペイン。ポルトガル。 トルコ人。
第九編 ルネサンスと宗教改革
序論
第一章 一五世紀中葉以降の社会生活の変化
第二章 宗教改革
第三章 一五世紀中葉から一六世紀中葉までのヨーロッパ諸国家
原注及び訳注
訳後贅言
人名索引