講談社文芸文庫作品一覧
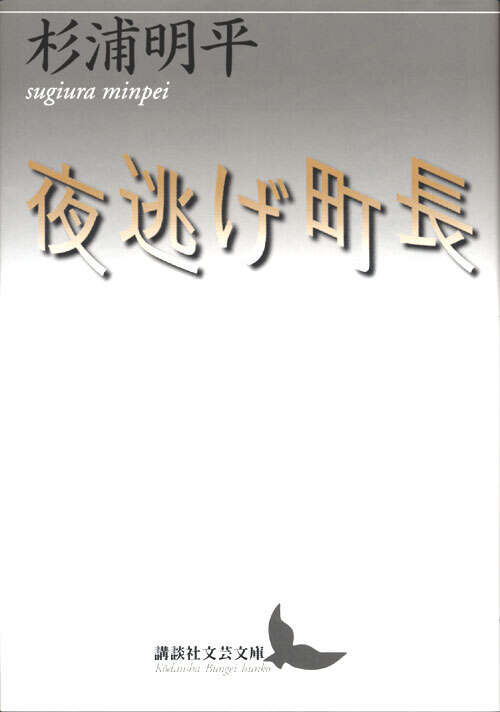
夜逃げ町長
講談社文芸文庫
出馬予定の県会議員選挙の前夜、町長が行方をくらました。地方の平和な田園風景の中にくりひろげられる滑稽な人間模様の数々! 事実に基づく題材を、鋭利で、しかも軽妙な文体で活写した、記録文学の傑作。他に不可抗力として著者を襲った「落第について」、「幻、夢、うつつ。」など8つの作品集。哄笑・傑作小説集。
〇小嵐九八郎 実際のことは1979年から1983年にかけてで、米ソ対立があった中で日本は自民党の下で割あい“安泰”だったけれど、主役の町長の悪人ぶりには腹の肉がおかしくなるほど“哄笑”せざるを得ぬ。――<「解説」より>

へっぽこ先生その他
講談社文芸文庫
東京下町の思い出、四季折々変化する鎌倉の風物、昭和文士たちとの友情、懐かしさ溢れる名随筆の数々ーー作家としての早熟な才能を示した東京・神田育ちの青年は、菊池寛に誘われ文藝春秋社で編集者となった。しかし敗戦後は社を去り、以後筆一本の暮らしに入る……。人生の断片を印象鮮やかに描き出す短篇小説の達人が、横光利一、小林秀雄、井伏鱒二ら文学者との深い交流や、さりげなくも捨てがたい日常・身辺の雑事を、透徹した視線と達意の文章で綴った、珠玉の名随筆59篇。
◎「自分の小さかった時のことを思い出してみて、夜なべに針仕事をする母のすぐ脇に、寝床を寄せて眼をつむっていると、なに一つ言葉を交わすのでもないのに、うれしくてうれしくて、眠ったふりをしながら、いつまでも眠らずにこうしていたいと思ったことがあったし、銭湯の帰り道、父と二人並んで歩いていると、まっくらな中で、これが自分と父なのだという、きわめて自然な血のつながりを感じたこともあった。」
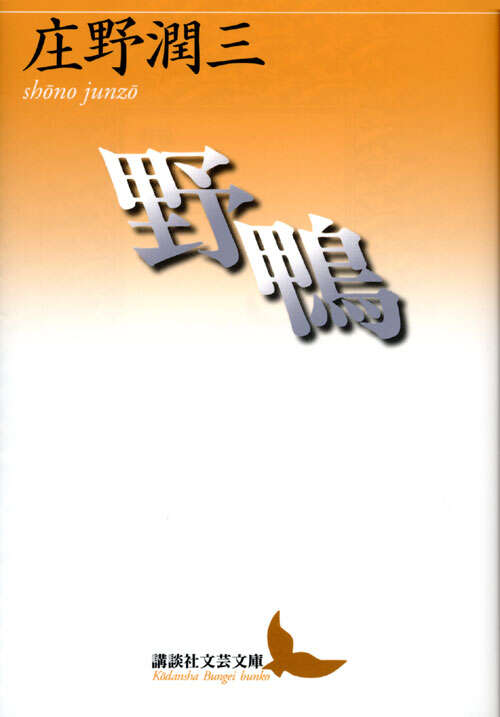
野鴨
講談社文芸文庫
はかなく取りとめない日常の中に現代の至福を描き出す長篇小説。家族を愛し人生を慈しむーー丘の上に住む作家一家。息子たちは高校生・大学生になり、嫁いだ娘も赤ん坊を背負ってしばしばやってくる。ある時から作家は机の前に視点を定め、外に向いては木、花、野鳥など身近な自然の日々の移ろいを、内では、家族に生起する悲喜交々の小事件を、揺るぎない観察眼と無限の愛情を以て、時の流れの中に描き留めた。名作『夕べの雲』『絵合せ』に続く充実期の作家が、大いなる実験精神で取り組んだ長篇。
◎庭に来る鳥や、庭の樹木から書き起こされる章が多いが、人の心が自然現象のなかに融け、照らし出されているように感じられる。八章には、「四十雀が飛び立ったあと、水盤の水に映った空が揺れている。」という小景描写があった。水面が揺れているのではなく空が揺れている。こんなところを読むと、今、見ているような気がする。昭和の小説には、このような豊かさがあった。<小池昌代「解説」より>

正宗白鳥――その底にあるもの――
講談社文芸文庫
生と死、神の存在を問い続けた、クリスチャン正宗白鳥の信仰の真実に迫る!
自然主義の代表的作家として、人生虚妄を唱えた冷徹なニヒリスト・正宗白鳥の死を契機に、彼が青年時代に棄教したキリスト教に復帰したのかどうかが、人々の関心を集めた。文芸評論に幅広い活躍をした著者が、「白鳥は終始クリスチャンだった」という観点で、白鳥の小説や深い影響力をもった内村鑑三、トルストイの作品等を読み解き、白鳥文学の深層に潜む、信仰と魂の問題、作家の人生を探った独自の作家論。
富岡幸一郎
一見するとこの白鳥論は、白鳥のキリスト教への「入信」と「棄教」そして「信仰復活」(白鳥は自らの葬儀を自分の意志でキリスト教会において行なった)という、一人の文学者の内面の変遷と信仰への葛藤を辿り描いており、事実その通りなのだが、その背後には正宗白鳥という個性的な作家の問題をこえた、より広く深い「魂」についての問いがあったのではないだろうか。――<「解説」より>
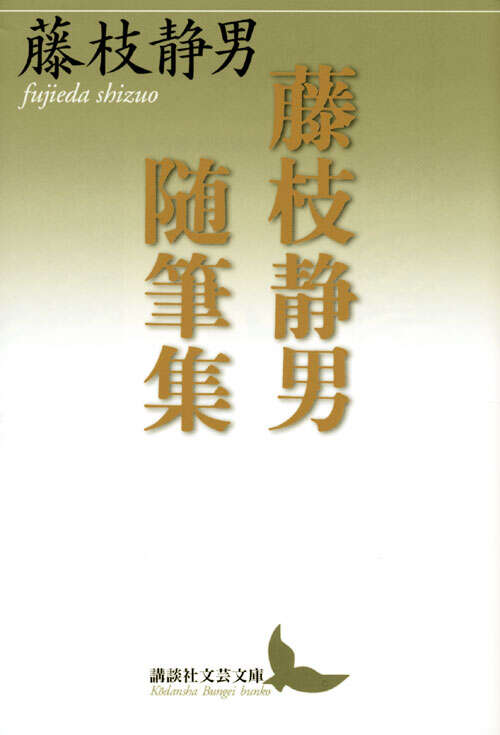
藤枝静男随筆集
講談社文芸文庫
自伝的随筆から骨董論まで、創作と人生の全てを語るーー旧制八高時代からの親友、平野謙、本多秋五との交友、生涯の師となる志賀直哉を訪ねた奈良旅行、最初の作品を「近代文学」に発表する経緯など……小説家・藤枝静男の誕生から、医師であり作家であることの心構え、骨董へのこだわり、晩年の心境まで――私小説に特異な新境地を切り開いた藤枝文学のエッセンスとともに、剛毅木訥なるひとがらとその人生を知るための精選随筆集。
◎堀江敏幸 どの頁にも、彼の小説に直結する「不合理な逆遠近法」の、残酷で滑稽な悲しみがあふれている。最後の一篇「妻の遺骨」で、妻の骨と石をまちがえて掘り出す場面は、自叙伝的な記述の性質とはまたべつの意味で遠近の狂った、しかも正しい眼の紡ぎ出したものとして、あるいは「鼻紙にくるんで胸ポケットにしまった」小さな骨のようなものとして、ながく読者の心に刻まれるだろう。――<「解説」より>
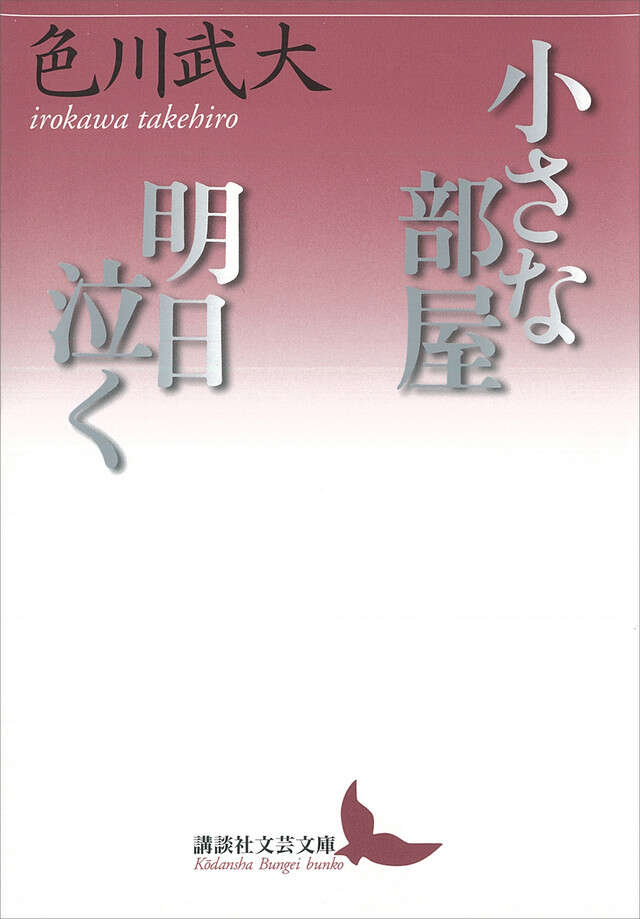
小さな部屋・明日泣く
講談社文芸文庫
朽ちかけた貸部屋に我物顔に出入りする猫、鼠、虫たち。いつしか青年は、凄まじい〈部屋〉を自分と同じ細胞をもつ存在と感じ熱愛し始める――没後10年目に発見された色川武大名義の幻の処女作「小さな部屋」、名曲「アイル・クライ・トゥモロウ」そのままの流転の人生を辿る女を陰影深く描く「明日泣く」など12篇。戦後の巷を常に無頼として生きながら、文学への志を性根にすえて書いた色川武大の原質とその変貌を示す精選集。
心優しき無頼派・色川武大。幻の処女作から没年作まで秀作12を精選。
朽ちかけた貸部屋に、わがもの顔に出入りする猫、鼠、虫たち。いつしか青年は、凄まじい<部屋>を自分と同じ細胞をもつ存在と感じ熱愛し始める――没後10年目に発見された色川武大名義の幻の処女作「小さな部屋」、名曲「アイル・クライ・トゥモロウ」そのままの流転の人生を辿る女を陰影深く描く「明日泣く」など12篇。戦後の巷を常に無頼として生きながら、文学への志を性根にすえて書いた色川武大の原質とその変貌を示す精選集。
内藤誠(映画監督)
高度成長とバブルのばか騒ぎも体験したあとで、あらためて色川武大が書いたものを読んでいると、いまさらながら、彼の作品に出てくる異能の登場人物たちになんとも言えぬ懐かしさをおぼえる。(略)人生の大半を大学生として過ごしてきたという友人だとか、さしたる理由もないのに平然と作家宅に居候をきめこむ人物などを、彼らのあるがままに受け入れて、魅力的な存在にしてしまう、色川文学のスケールに、わたしたちは虚実をこえて読みふけるのである。――<「解説」より>
※本書に収録した作品のうち、「小さな部屋」は「文学界」(1999年5月号)を、その他の作品は、福武書店刊『色川武大 阿佐田哲也全集』第1巻、第3巻、第5巻(1991年11月、12月、1992年7月)を底本として使用しました。

銀色の鈴
講談社文芸文庫
身辺の移り変わりをユーモアとペーソスで綴った名短篇集
前妻の死から再婚までを淡々と綴った表題作、戦時下、疎開先での教員体験をユーモラスに描いた「古い編上靴」――これら世評の高い<大寺さん>シリーズほか、伯母の家の凋落に時代の変遷を重ねる「小径」、戦前の良き時代の交友を哀惜の情をもって語る「昔の仲間」など、7作品を収録。滋味あふれる洗練された筆致で、ほのぼのと温かい独特の世界を創り出した「小沼文学」中期の代表的作品集。
清水良典
小沼の小説においては、「可笑しい」をはじめとする「驚いた」「吃驚した」「閉口した」といった心的印象の結語は、心理の簡潔な表示というよりも、ほとんど「心理」を封印している。同時にそれはまったく別の経路から、心があふれ出す出口なのである。ことに「可笑しい」は、小沼らしさを象徴している言葉である。――<「解説」より>
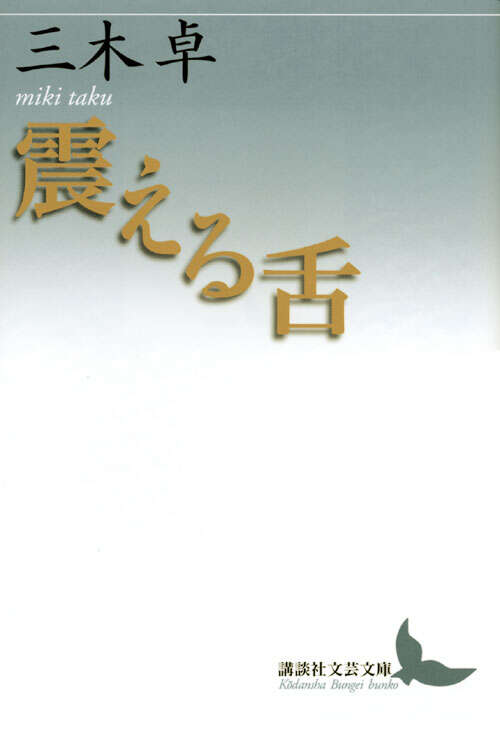
震える舌
講談社文芸文庫
その予感は娘の発作で始まった。極限の恐怖に誘われる衝撃の作品ーー平和な家庭での、いつもの風景の中に忍び込む、ある予兆。それは、幼い娘の、いつもと違う行動だった。やがて、その予感は、激しい発作として表れる。<破傷風>に罹った娘の想像を絶する病いと、疲労困憊し感染への恐怖に取りつかれる夫婦。平穏な日常から不条理な災厄に襲われた崇高な人間ドラマを、見事に描いた衝撃作。
◎距離が伸びる時には父親として病気に向き合い、距離が縮む時、一人の人間として感染症の恐怖に怯える中で語られる心の葛藤は、医学小説のそれではなく、もちろん恐怖小説のものでもなく、強いて言うなら、極めて純粋な戦記文学を読んでいる印象です。確かに、今まで読んだ全ての小説の中で、病棟という「戦場」の真実がここまで正確に描かれた作品を知りません。<石黒達昌「解説」より>

暗い絵・顔の中の赤い月
講談社文芸文庫
新人・野間宏、戦後日本に颯爽と登場――初期作品6篇収録のオリジナル作品集
1946年、すべてを失い混乱の極みにある敗戦後の日本に、野間宏が「暗い絵」を携え衝撃的に登場――第一次戦後派として、その第一歩を記す。戦場で戦争を体験し、根本的に存在を揺さぶられた人間が、戦後の時間をいかに生きられるかを問う「顔の中の赤い月」。ほかに「残像」「崩解感覚」「第三十六号」「哀れな歓楽」を収録する、実験精神に満ちた初期短篇集。
ーー草もなく木もなく実りもなく吹きすさぶ雪風が荒涼として吹き過ぎる。はるか高い丘の辺りは雲にかくれた黒い日に焦げ、暗く輝く地平線をつけた大地のところどころに黒い漏斗形の穴がぽつりぽつりと開いている。その穴の口の辺りは生命の過度に充ちた唇のような光沢を放ち、堆い土饅頭の真中に開いているその穴が、繰り返される、鈍重で淫らな触感を待ち受けて、まるで軟体動物に属する生きもののように幾つも大地に口を開けている。
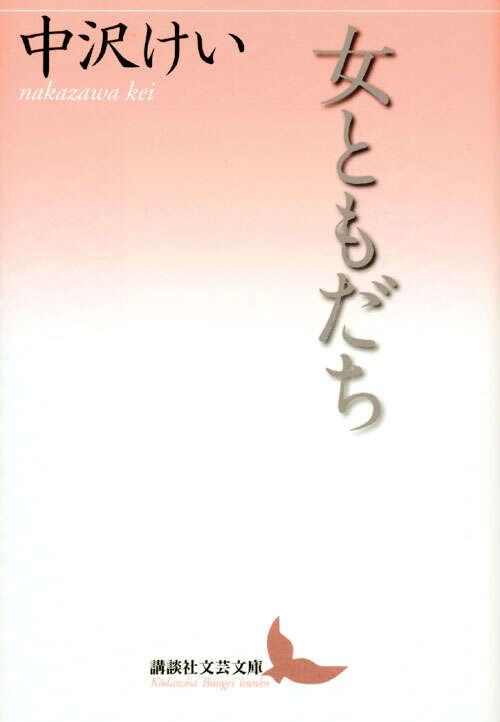
女ともだち
講談社文芸文庫
二十歳前後の3人の女性たちが織りなす日常の風景ーー大学夜間部に通う主人公と、二人の女ともだち。私は、10代で書いた小説で賞を受け、嘘のような生活をしていたが、そこに高校の後輩・隆子が転がりこむ。若い女性たちの生々とした光と影を見事に描ききり、「海を感じる時」で衝撃的なデビューを飾った著者の豊かな感性が弾けた中篇小説。短篇「アジアンタム」も収録。
◎角田光代「旧友に会うまでは、話すことがいくらでもありそうだと思っていたのに、いざ会ってみると、相手に興味も持てず、接点も見つけられないと気づくことは、よくある。この場面の、空気の白々した感じが痛いほどわかる。私はずっとそれを、友だちは変わるものだからだと思っていた。成長すれば嗜好も趣味も自身の器も変わる。友人もそれにともなって変化しないはずがない。けれど友人のなかには、この感覚を薄情だと言う人もいる。」(「解説」より)

聖ヨハネ病院にて・大懺悔
講談社文芸文庫
半身不随の病苦の中で一字一字刻みつけた魂の言葉。「私小説」の佳品10篇
文学への純粋な情熱を胸底に78年の生涯を私小説一筋に生きた上林暁。脳溢血で半身不随、言語障害を患った晩年も、左手と口述で一字一句、彫心鏤骨の作品を生みつづけた。川端康成に賞賛された出世作「薔薇盗人」、心を病む妻を看取った痛切な体験を曇りない目で描く「聖ヨハネ病院にて」、生と死のあわいを辿る幻想譚「白い屋形船」(読売文学賞)等、人生の苦悩の底から清冽な魂の言葉を響かせる珠玉短篇集。
富岡幸一郎
作家の「眼の誠実」と川端がいったのは、上林暁が、描かれる対象にたいするいたわりを内に含み、そのことにおいて人がそこで生きている真実の姿を浮き彫りにしている点であろう。(略)上林暁の「私小説」はつねに他者を包含し許容することで、また自然をはじめとする森羅万象を受け容れる姿勢を保つことで、描くべき存在に生命の息吹を注入し活力を回復させるのである。――<「解説」より>

錨のない船 下
講談社文芸文庫
外交官来島平三郎とアメリカ出身のアリスの長男である健は母の容貌をより濃く受け継いだがゆえ、日本陸軍飛行兵として戦争に深く関わっていくことを自ら選んでいた。日本の敗色濃厚な1945年春、来島健は戦闘機疾風を操り米軍のB29を撃墜するも、結局無惨な死を迎える。敗戦。息子に先立たれた平三郎は、戦犯の疑いをかけられ――歴史に翻弄された一家の運命を描く歴史長篇完結。
大きな戦争が、男も女も激流に巻き込み、突き進む。感動の歴史長篇完結!
人々は竹槍を構えた。1人が健の左胸をぐいと突いた。鋭い槍先が肉を貫き体の芯へと抜けていく。2番目の老人は首をぐさり突き刺した。何ごとがおこったのか。これはどういうことだ、健は、3番目の竹槍を受ける前に、「違ウ、違ウ、ボクハ日本人ダ」と叫んだが、それは首の傷口から笛のように漏れただけであった。
外交官来島平三郎とアメリカ出身のアリスの長男である健は母の容貌をより濃く受け継いだがゆえ、日本陸軍飛行兵として戦争に深く関わっていくことを自ら選んでいた。日本の敗色濃厚な1945年春、来島健は戦闘機疾風を操り米軍のB29を撃墜するも、結局無惨な死を迎える。敗戦。息子に先立たれた平三郎は、戦犯の疑いをかけられ――歴史に翻弄された一家の運命を描く歴史長篇の新装版完結。

わんぱく時代
講談社文芸文庫
初恋、喧嘩、反逆心――。文豪佐藤春夫の知られざる名作!
野ゆき山ゆき海辺ゆき/真ひるの丘べ花を敷き/つぶら瞳の君ゆゑに/うれひは青し空よりも(『殉情詩集』より)
明治25年、和歌山県新宮に生を享けた佐藤春夫は、故郷の自然と人への熱い想いを若き日の詩に詠い、老年に至ってこの生命感迸る少年文学に結実させた。敵味方、智略を尽すわんぱく戦争、薄倖の少女との初恋、大逆事件に向う社会への反逆と覚醒。少年時代を描き浪漫的詩情があふれる傑作長篇。
佐藤洋二郎
この作品には少年たちの生きようとする苦悩や苦労があり、それでも伸びやかに生きる彼らの姿がある。真の教育は、おとなが宛がうのではなく、こどもたちがそれぞれに育みながら手にするものだと改めてかんじさせられた。(略)この作品はたんなる教養小説とは違い、おとなの心にも深く届いてくるものとなっている。そこには春夫の人間やものを見る透徹した目があるからだろう。――<「解説」より>

一日 夢の柵
講談社文芸文庫
日常の内奥にひそむ光と闇。――人々が暮らしてゆく、生々しい奇妙な現実。生きることの本質と豊穣。著者60代半ばから70代半ばにかけて書かれた短篇群、野間文芸賞受賞の12の人生の断片。「夢の柵」「影の家」「眼」「浅いつきあい」「電車の中で」「隣家」「丸の内」「記録」「一日」「危うい日」「久介の歳」「要蔵の夜」収録。
日常にひそむ光と闇 生々しい現実 豊穣の文学。人生の断片、12の短篇。
日常の内奥にひそむ光と闇。――人々が暮らしてゆく、生々しい奇妙な現実。生きることの本質と豊穣。著者60代半ばから70代半ばにかけて書かれた短篇群、野間文芸賞受賞の12の人生の断片。「夢の柵」「影の家」「眼」「浅いつきあい」「電車の中で」「隣家」「丸の内」「記録」「一日」「危うい日」「久介の歳」「要蔵の夜」収録。
三浦雅士
たとえば『一日 夢の柵』の登場人物の誰ひとり生々しくないものはない。「夢の柵」の滝口内科医院の先客3人にしてもそうだ。ほんの一瞬、登場するだけでも生々しい。だが、生々しいと同時に、こいうい人っているよな、と思わせてしまうのである。「影の家」の老女の現実感にいたっては驚くばかりである。しかも、家の近所にも確かにいる、と思わせてしまうのだ。――<「解説」より>

錨のない船 上
講談社文芸文庫
1941年、アメリカの厳しい経済制裁で資源確保が困難化、進退窮まる日本。武力解決を訴える勢力の圧迫を受けつつも、ワシントンに飛んだ来島平三郎特命全権大使は、妻の故郷アメリカとの開戦回避の道を懸命に模索していた。だが、ルーズヴェルト大統領、ハル国務長官を相手の交渉は難航、だましうちのように真珠湾攻撃が敢行されてしまう――。戦争に翻弄される外交官一家の肖像をつぶさに描く傑作長篇。
世の中には空しい職業がいろいろあるが、この外交官ほど空しい文字を記さねばならぬ職業もないだろう。いくら条約を作っても親善を結んでも、国と国との利害が衝突する大波が打寄せてくれば跡形もなく消えてしまう。そんな話を、一昨年息子の健に話したことがある。すると健は、自分はそんなはかない仕事よりも、橋一つ機械一つでも、世に永く残るものを作ることに一生をかけたいと言った。
1941年初冬 妻の故国アメリカとの戦争回避に全力を尽くした外交官がいた――歴史に翻弄された一家の物語
1941年、アメリカの厳しい経済制裁で資源確保が困難化、進退窮まる日本。武力解決を訴える勢力の圧迫を受けつつも、ワシントンに飛んだ来島平三郎特命全権大使は、妻の故郷アメリカとの開戦回避の道を懸命に模索していた。だが、ルーズヴェルト大統領、ハル国務長官を相手の交渉は難航、だましうちのように真珠湾攻撃が敢行されてしまう――。戦争に翻弄される外交官一家の肖像をつぶさに描く傑作長篇。

三田文学短篇選
講談社文芸文庫
三田文学創刊以来の名作から選びぬいた13の短篇
創刊100周年の文芸誌「三田文学」に掲載の短篇小説を精選。森鷗外「普請中」 久保田万太郎「朝顔」 水上瀧太郎「山の手の子」 石坂洋次郎「海をみに行く」 坂口安吾「村のひと騒ぎ」 原民喜「夏の花」 松本清張「記憶」 吉行淳之介「谷間」 安岡章太郎「逆立」 伊藤桂一「形と影」 坂上弘「バンド・ボーイ」 津島佑子「粒子」 立松和平「ともに帰るもの」
田中和生
文芸雑誌「三田文学」は、1910年5月に創刊された。初代の編集長は永井荷風、発行所は慶応義塾内の三田文学会である。(略)永井荷風が示した方針は、学校当局が望んだような早稲田に対抗して慶応の名を上げるという、世俗の利害に囚われたものではなかった。自らも慶応の外部から呼ばれた文学者であることに示されるように、それはまず「公」に向かって誌面を開き、なにより読者のための雑誌を作ることだった。そのことは、当時の文芸雑誌としては異例なほど創作が充実しているという、誌面の構成によく表われている。――<「解説」より>

われらにとって美は存在するか
講談社文芸文庫
第三の新人と伴走した悲劇の批評家の精選評論集
「第三の新人」が文壇に登場し、注目を浴びていた時、彼らと歩を合わせるかのように、ひとりの新しき批評家が誕生する。それまでのマルクス主義的批評でもなく、また作家の生理によりかかる作家論的アプローチでもなく、作品それ自体の内部に<美>を見出す審美的批評を提唱し、その原理を探究する途に赴くも、中絶。新世代批評家として嘱望されながらも、33歳で自死した服部達の代表的作品を精選。
勝又浩
33歳の彼が、自分の32歳のときの文章を指して「若気の至り」だと言っている。思うに、この頃、文芸評論を書き始めた服部達はこんなふうに、まるで竹の子が育つように急成長していたのだ。竹は芽の出たその年の内に一生分の成長を果たしてしまうが、彼のあまりにも早すぎた死を思うとき、私はそんなイメージを思い浮かべずにはいられない。批評家としての服部達は、そんな軌跡を見せている。ずば抜けた秀才の悲劇ではなかったろうか。――<「解説」より>

夢屑
講談社文芸文庫
夢と現実、実在と不在、「死」を見た作家の、名作短篇集。
『死の棘』の最後の章ののち発表された8つの短篇。島尾敏雄が、執拗に描き続けてきた“夢”。何故、彼は、これほどまで“夢”にこだわったのか……。夢の中に現実の関係を投影し、人の心の微妙な揺らめきにしなやかな文学的感受性を示した、野間文芸賞受賞作家の名作短篇集。
富岡幸一郎
本書に収められている「夢屑」「過程」「痣」は夢を題材にして書かれた作品である。しかし、「幼女」「マホを辿って」「水郷へ」「亡命人」も作家の家族や過去の体験に基づいて書かれてはいるが、その現実のうちには夢の世界といってもいい気配が色濃く漂っている。そもそも夢と現を画然と分けることができるのだろうか。――<「解説」より>
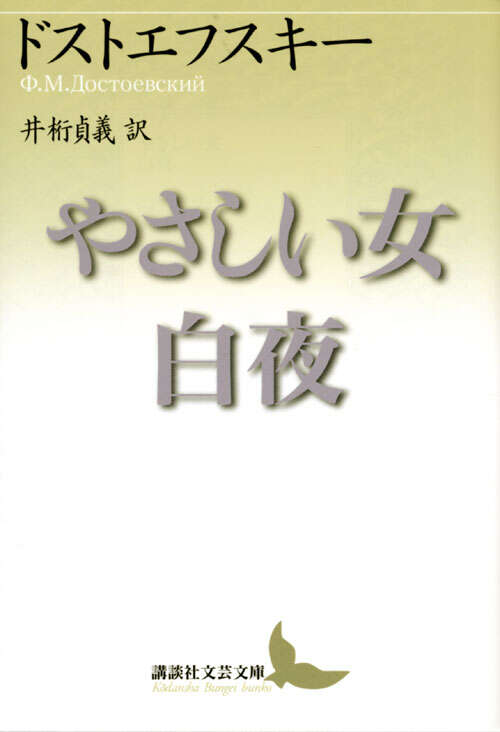
やさしい女・白夜
講談社文芸文庫
小金にものを言わせ若い女を娶った質屋がその妻に窓から身投げされ、テーブルの上に安置された遺体を前に苦渋に満ちた結婚生活を回想する――。人を愛すること、その愛を持続することの困難さを描いたドストエフスキー後期の傑作「やさしい女」とヴィスコンティによる映画化で知られる初期の佳品「白夜」を読みやすい新訳で収録。
ロシア文学の実験精神が到達した高み 新訳による中篇2作収録
小金にものを言わせ若い女を娶った質屋がその妻に窓から身投げされ、テーブルの上に安置された遺体を前に苦渋に満ちた結婚生活を回想する――。人を愛すること、その愛を持続することの困難さを描いたドストエフスキー後期の傑作「やさしい女」とヴィスコンティによる映画化で知られる初期の佳品「白夜」を読みやすい新訳で収録。
井桁貞義
長篇小説で知られるドストエフスキーだが、同時に中篇小説の名手でもあった。そしてその文学的背景に、1840年代から1870年代にかけてのロシア文学全体に共通する表現方法(フォルム、ポエチカ)の真剣な模索があった。(略)ロシアの作家たちは人間そのものをとらえ、その心の動きを運動のまっただなかで表現することに向かっていた。(略)ここに訳出した2つの「愛をめぐる」中篇小説『白夜』(1848年)と『やさしい女』(1876年)も、そうしたロシア文学の模索の到達点を、それぞれに示したものと言える。――<「解説」より>

文林通言
講談社文芸文庫
新人古井、金井登場。大江、大岡、吉行が書き、三島が突然去った――。夷斎文芸論の粋!
1970年を挟む2年間、騒然とした世情を映す新聞紙上で、「事の雅俗を問わず……勝手気ままに」連載された文芸時評集。文学、哲学、史学と境界なき“文林”を逍遥し、読む者を精神の躍動に誘うアミュージングを求めて、時には峻烈に、時にはユーモアを交えた絶妙な文体で批評を展開した。三島事件の前にその予兆を、事件後に追懐を述べた珠玉の2篇始め、時評でありつつ時代を超える夷斎文芸論の白眉。
池内紀
あらためて石川淳の炯眼をいうべきだろうか? 触れれば血のほとばしるような抜き身の刃をかかげての時評なのだ。捨てるべきものはさっさと捨てられ、ひたすら語るに足るだけのものが語られた。ふつう時評家は他人の布を借りて即席の服をつくるが、石川淳はカイコが腹中から糸を出すようにして月々の服をつくった。――<「解説」より>