講談社文芸文庫作品一覧

閉ざされた海 中納言秀家夫人の生涯
講談社文芸文庫
戦国に生きた男女の運命を哀切に描いた名作 関ヶ原の戦いに敗れ、八丈島に流人として生きた宇喜多秀家と、故郷加賀に孤独の生を終えた奥方お豪。二人の生涯を通して、真の幸福の意味を追求した長篇歴史小説

完訳グリム童話集 3
講談社文芸文庫
二世紀を超えて読まれる不滅のメルヒェン集 近代の黎明期、グリムは普通の人々の魂に新生ドイツの根拠を求め、フォルク(民衆)の言語文学の華であるメルヒェン集を編んだ。「星の銀貨」「寿命」など九二篇

槐多の歌へる 村山槐多詩文集
講談社文芸文庫
夭折した天才画家の〈詩魂〉をたどる詩文集 生まれた時から詩人であり画家であった槐多。放浪、デカダンス、酩酊のうちに肺患に苦しみ、短い生を駆け抜けた生涯に残された、詩、短歌、小説、日記を精選収録

完訳グリム童話集 2
講談社文芸文庫
大人を魅了する豊饒なメルヒェンを全三巻で 古代から同時代までの神話、英雄叙事詩を渉猟する一方、農民や職人といったふつうの庶民の喜怒哀楽を映しす無数の話を記録整理して成ったグリム童話。完訳決定版
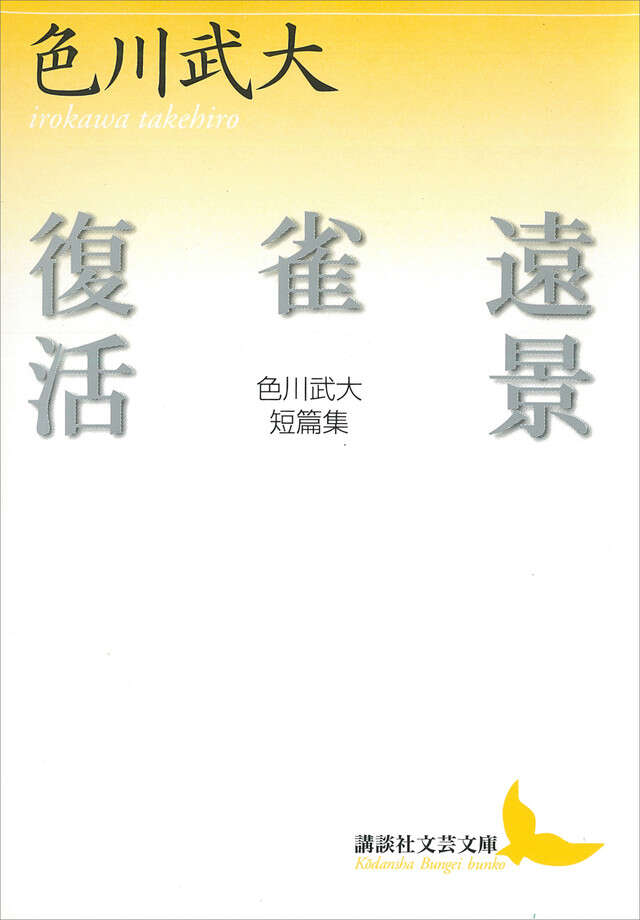
遠景・雀・復活 色川武大短篇集
講談社文芸文庫
父の末弟で、受験に何度も失敗し、自らの生を決めかね、悲しい結末を迎える若き叔父・御年。彼の書き残した父宛の手紙で構成した「遠景」をはじめとし、夢の手法をまじえて綴った「復活」ほか、生家をめぐる人々をモチーフとした作品を中心に、ギャンブル仲間であった一人の男の意外な出世と悲惨な転落を追った「虫喰仙次」など、全9篇を収録。戦後最後の無頼派作家の描く、はぐれ者たちの生と死、そして原点としての父と生家。
戦後最後の「無頼派」色川武大の傑作短篇集 入試に失敗し挫折する若い叔父・御年さん、床下に巨大な穴を掘り続ける元海軍司令の父、博打ゆえに自滅する友など、はぐれ者達の生と死に深い共感を綴る秀作七篇

完訳グリム童話集 1
講談社文芸文庫
古典中の古典に新鮮な名訳で挑む(全3巻) グリム兄弟によって蒐集され一言一句無駄のない名文で「世界で最も面白い本」とされるメルヒェン211篇を、生きのいい日本語で現代に甦らせた完訳を3巻で編む
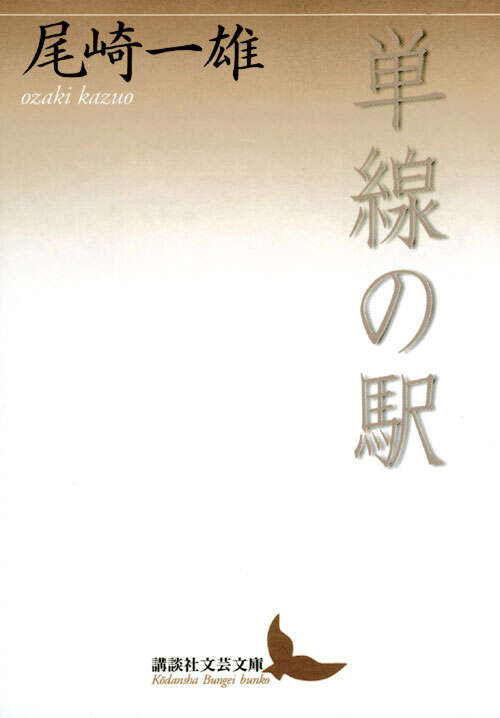
単線の駅
講談社文芸文庫
昭和50年、野間文芸賞を受賞した回想記『あの日この日』に収めることのできなかった、とっておきのエピソードをまとめた「こぼれ話」を中心に、小田原・下曾我の自宅周辺の草木の観察から、公害問題や文明観への言及、また、尾崎士郎、檀一雄、浅見淵、大岡昇平、木山捷平ら文学者の思い出など、随筆57篇を収録。身近な自然を愛し、老いの日々を淡々と生きる著者晩年の、深い人生観照にもとづく滋味深い一冊。
深い人生観照にもとづく、著者晩年の随筆集 小田原下曽我で暮らす日々の雑感から、若き日の回想、志賀直哉、武者小路実篤、木山捷平ら文学者の思い出、自作についてなど、ユーモアただよう珠玉の随筆58篇

文学概論
講談社文芸文庫
言葉とは何か。吉田文学の成熟を示す名評論 言葉のはたらきは、精神を解放する。文学とは何かをめぐって、古今東西、はるかな時空を超えて自在に説く、吉田文学晩年の豊饒を告げる知られざる傑作評論集。
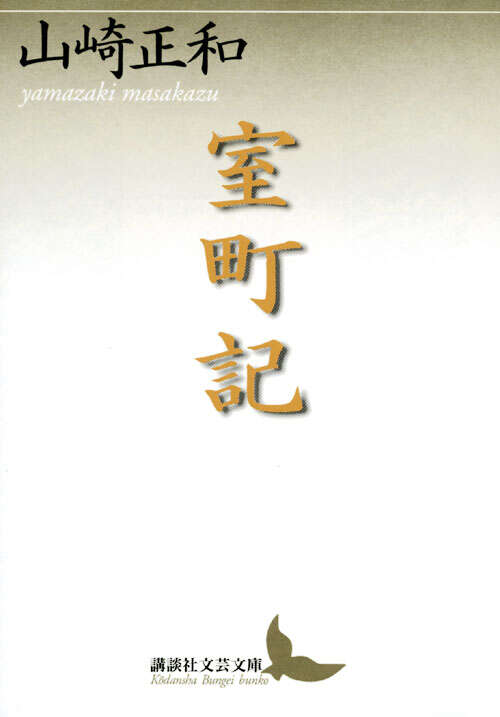
室町記
講談社文芸文庫
日本文化の核を育み、社会の階層をかき回した、渾沌と沸騰の200年! 豊かな乱世の絢爛たる文化ーー
日本の歴史の中でも室町時代の200年ほど、混乱の極みを見せた時代はなかった。が、一方では、その「豊かな乱世」は、生け花、茶の湯、連歌、水墨画、能・狂言、作庭など、今日の日本文化の核をなす偉大な趣味が創造された時代でもあり、まさに日本のルネサンスというべき様相を呈していた。史上に際立つ輝かしい乱世を、足利尊氏や織田信長らの多彩な人物像を活写しつつ、独自の視点で鮮やかに照射する。
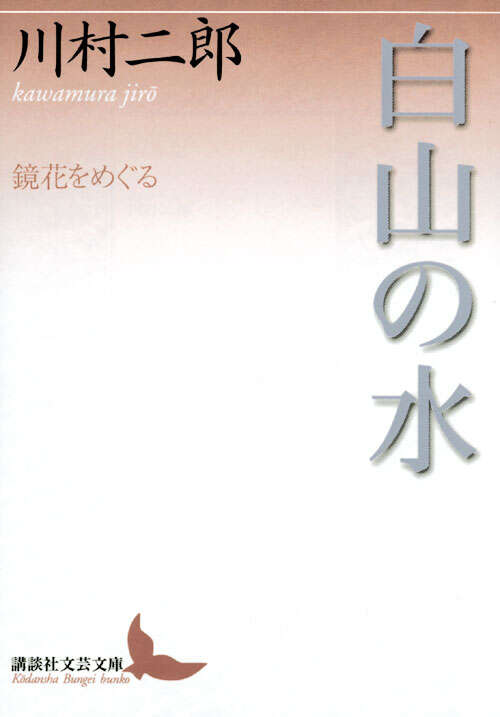
白山の水 鏡花をめぐる
講談社文芸文庫
著者少年期の金沢体験を出発点に、また、その後の土地の精霊を訪ねる旅での見聞をもとに、泉鏡花の作品世界を、地誌的・民俗学的に読み解いた長篇エッセイ。「川」「峠」「水神」「蛇」「化物」「白神」等のキー・タームから、鏡花作品の幻想性に入りこみ、その深奥にある北陸の山と水、それらを宰領する精霊たちのうごめきを感じとる。鏡花をめぐるセンチメンタル・ジャーニー、巡歴の記録。
幻想の深奥にうごめく地霊たち
著者少年期の金沢体験を出発点に、また、その後の土地の精霊を訪ねる旅での見聞をもとに、泉鏡花の作品世界を、地誌的・民俗学的に読み解いた長篇エッセイ。「川」「峠」「水神」「蛇」「化物」「白神」等のキー・タームから、鏡花作品の幻想性に入りこみ、その深奥にある北陸の山と水、それらを宰領する精霊たちのうごめきを感じとる。鏡花をめぐるセンチメンタル・ジャーニー、巡歴の記録。
日和聡子
本書の中心には地誌的な視座が据えられ、単なる作家論、作品論とは異なる相を見せる。泉鏡花の文学に通暁した著者による、つかずはなれず、絶妙な距離とバランスを保った泉鏡花論としての側面をもちながらも、著者自身の調査旅行をはじめとする紀行文や、自伝的回想をも基調とした、ときに小説のような表情も見せるものである。そして、ドイツ文学者であり日本神話の古層にも造詣の深い著者ならではの、比較文学の視点もふんだんに盛り込まれており、多岐にわたる多様な魅力と含蓄に富んだ、重厚な書物である。――<「解説」より>
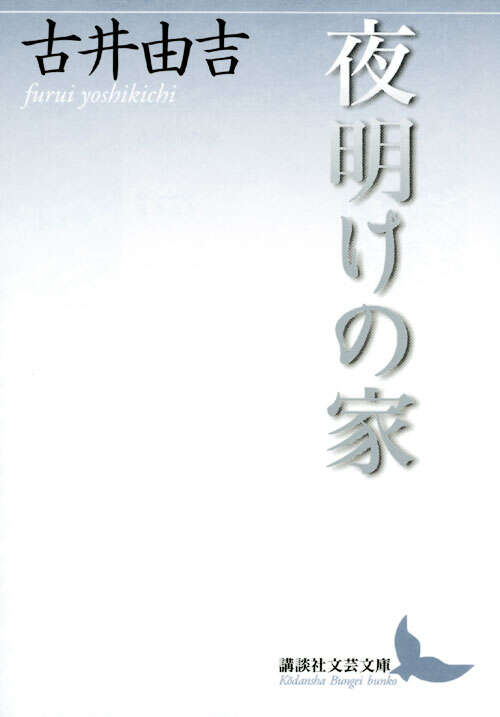
夜明けの家
講談社文芸文庫
「老耄が人の自然なら、長年の死者が日々に生者となってもどるのも、老耄の自然ではないか。」――主人公の「私」が、未明の池の端での老人との出会いの記憶に、病、戦争、夢、近親者の死への想いを絡ませ、生死の境が緩む夜明けの幻想を語った表題作をはじめ、「祈りのように」「島の日」「不軽」「山の日」など「老い」を自覚した人間の脆さや哀しみと、深まる生への執着を「日常」の中に見据えた連作短篇集。
生と死の間に人生の孤独を描く連作短篇12 「老い」を自覚することで、生命の脆さと、深まる生への執着を、「日常」の中に見据えた表題作を始め、「祈りのように」「島の日」「不軽」など古井文学の一頂点

高級な友情 小林秀雄と青山二郎
講談社文芸文庫
文圃堂主人が綴る文士たちの壮絶な“友情”ドラマ
昭和6年、本郷東大正門前に開業した古書店兼出版社・文圃堂。売り場面積3坪余り、主人は21歳になったばかりの青年。中原中也の『山羊の歌』、最初の『宮沢賢治全集』を出版、第2次「文學界」の発行所となったが、僅か6年にして廃業。しかし、若者は昭和文学史を彩る多くの文学者達に愛された。小林秀雄、青山二郎、河上徹太郎、そして吉田健一。昭和の知的青春に揉まれ成長した、個性際立つ一出版人の貴重な証言。
長谷川郁夫
小林秀雄、河上徹太郎、そして青山二郎。――かれらが全身を賭して護り育てたのは、創造としての批評の成熟であった。その壮絶なまでの“友情”のドラマは、批評もまた、小説と同じように、肉体をもつものであることを示すものであった。その現場の証言者として選ばれたのが、野々上さんだった。いや、もしかすると、野々上慶一こそが、かれら3人が見事に造型した作品であったのかも知れない。今にして、そのことにようやく気付くのである。――<「解説」より>

長篇小説 芥川龍之介
講談社文芸文庫
芥川の人と文学の秘密を赤裸に暴く
若き日に師事した芥川龍之介の姿を活写した、著者晩年の作。芥川文学の、漢文脈による洗練された修辞をはじめとした教養主義は、「私」を語ることのできない「物語作家」に彼をおしとどめ、「小説家」へと転身をはかろうとした試みの不可能性に悲劇を読み解く。芥川の作品の持つ窮屈さは、養子・龍之介の養家への気兼ねの表れだとも喝破する。身近に接した芥川を、老成した小説家の眼で捉えた快作。
出久根達郎
芥川は、面白い話をつづる一流の「物語作家」ではあるが、人生の諸相をえぐりだし、人の生き方を示す「小説家」ではない。小島はそのような結論を下す。極論かどうかは、問題ではない。読者の私たちが、そうかも知れないなあ、と共鳴したなら、小島の思う壺にまんまとはまったのである。なぜなら、本書は、「小説」だからである。「長篇小説 芥川龍之介」だからである。評論ではない。評論めかした小説なのである。――<「解説」より>

「アボジ」を踏む 小田実短篇集
講談社文芸文庫
時代の最前線で行動し書いた著者の半世紀を刻する珠玉短篇集
「ぼくは生(な)まで帰る」――食うために朝鮮から移民、激しい肉体労働の60年を送った「アボジ」の望みは、生まの遺体で故郷の済州島に還ることだった。著者自身の義父を通して歴史の軛に喘ぎながら逞しく生きる人間像を見事に彫琢した表題作(川端康成文学賞受賞)他6篇。戦争の世紀の只中にあって、常に「殺される側」の庶民の目と感性で行動し、書き、自ら時代の語り部たらんとした小田実の40年に亘る珠玉短篇集。
川村湊
『オモニ太平記』や『「アボジ」を踏む』を読んだ時、初めて小説家オダ・マコトの本領を見たような気がした。そこには、オダさんの妻の両親である在日朝鮮人の「オモニ」と「アボジ」の姿が、ユーモアとペーソスをまじえて、とても生き生きと描かれていたからである。(略)日本で散々に“踏み付け”にされてきた「アボジ」を、日本人のオダさんが踏む。この笑えないギャグ的光景を想像するたびに、ぼくはオダさんが、「ひどい国」の国民として、「アボジ」の国と人に、真剣に和解と贖罪を求めていたと考えるのである。――<「解説」より>

インド酔夢行
講談社文芸文庫
軽妙洒脱かつ深遠なるインド旅行記の決定版 紀元前と紀元後がうず巻くインドの混沌のなかをウィスキー片手に旅する詩人。ユーモア溢れ、詩人らしい鋭い切れ味の言葉でインドの奥深さを語る紀行文学の白眉。

『徒然草』を読む
講談社文芸文庫
京の町衆の家に生まれ育ち、当代きっての文人学者として、東西文学を自在に往還し続ける著者が、随筆史上、最大の古典『徒然草』を読み解く――。鎌倉時代末の乱世を出家遁世し、歌人であることを隠れ蓑に、反時代的に生きた兼好のざわめく心、色好み、もののあはれ、無常の世の処し方、有職故実の世界への思いなど、その人間性の複雑さと心の深層からの言葉を探る。兼好の筆触に迫る随筆仕立ての名著。
人生とは何かを問う「徒然草」味読の醍醐味 随筆史上、最大の古典「徒然草」を、フランス文学者にして、名随筆家の著者が読み解く。無常の世の処し方、人間の楽欲、色欲等、兼好の心の深層からの言葉を探る。
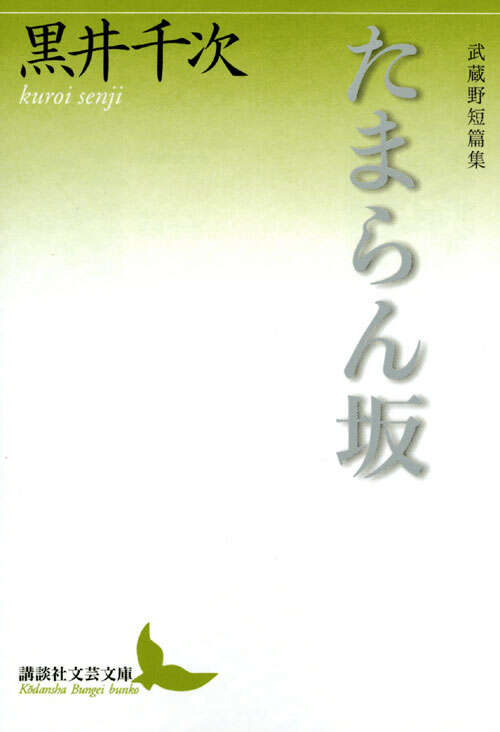
たまらん坂 武蔵野短篇集
講談社文芸文庫
土地の名が呼びさます昔の幻影。連作短篇集 たまらん坂、おたかの道……武蔵野に実在する不思議な土地の名が初老期の男達に垣間見せる青春の残像。時間と空間の交点に人生を映し出す黒井文学の豊かな収穫。
土地の名が呼びさます昔の幻影。連作短篇集 たまらん坂、おたかの道・・・武蔵野に実在する不思議な土地の名が初老期の男達に垣間見せる青春の残像。時間と空間の交点に人生を映し出す黒井文学の豊かな収穫。

ひとつの文壇史
講談社文芸文庫
一葉研究の第一人者であり、晩年『接木の台』『暗い流れ』など、人間の業を見つめ、味わい深い世界を描いた作家・和田芳恵の出発は、編集者であった。昭和6年、新潮社に入社、大衆雑誌「日の出」の編集に携わり、菊池寛、吉川英治、尾崎士郎、小島政二郎ら多くの作家とつき合い、小説の純化のために奔走した。「その時の目撃者として、生き証人になることを心がけ」綴った回想録は、当時の貴重な文壇人物誌となった。
ひとりの編集者として綴った珠玉の文壇回想 『一葉の日記』『暗い流れ』の著者は昭和の初頭から大衆雑誌の編集に携わった。その現場の生き証人として当時を回顧した現代文学の貴重な資料となる文壇人物誌。
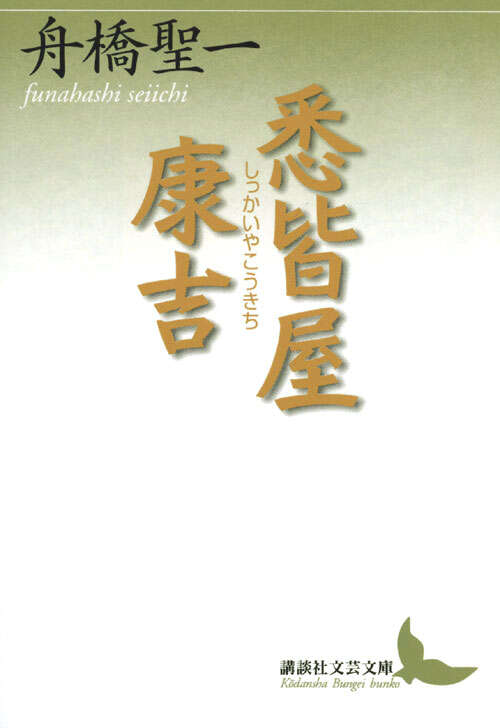
悉皆屋康吉
講談社文芸文庫
呉服についての便利屋であり、染色の仲介業者でもある「悉皆屋」の康吉は、職人としての良心に徹することで、自らを芸術家と恃むようになる。大衆の消費生活が拡大する大正モダニズム期には、華美で軽佻な嗜好を嫌い、ニ・ニ六事件の近づく昭和前期には、時代の黒い影を誰よりも逸早く捉える男でもあった。著者が戦時下に書き継ぎ、芸術的良心を守った昭和文学史上の金字塔と評される名作。

百句燦燦 現代俳諧頌
講談社文芸文庫
ありうべき最高の美学は虚無――生涯徹底した反リアリズム芸術至上の立場を貫いた塚本邦雄。藤原定家等中世の歌人を理想とする塚本にとり俳諧は、近世という暗黒時代に咲く「異次元の巨花」であった。その輝かしい裔である現代俳人、石田波郷、西東三鬼、下村槐太、寺山修司、飯田蛇笏等、69人の秀句100を選び、斬新かつ創造的評釈を展開。稀代のアンソロジストによって招喚された現代俳諧頌!
短歌の鬼才が最愛の敵に捧げた俳諧頌、百! 近世は和歌の暗黒時代と見る前衛歌人が異次元の巨花と愛でる俳諧。その輝かしい裔・現代俳人を奔放に論じる。西東三鬼、寺山修司、飯田龍太等の魅惑の百句精選。