講談社文芸文庫作品一覧

鰐 ドストエフスキー ユーモア小説集 沼野充義編
講談社文芸文庫
ドストエフスキーは最初から「ユーモア作家」だった!
怪しい色男を巡る、2人の紳士の空疎な手紙のやり取り。寝取られた亭主の滑稽かつ珍奇で懸命なドタバタ喜劇。小心者で人目を気にする閣下の無様で哀しい失態の物語。鰐に呑み込まれた男を取り巻く人々の不条理な論理と会話。19世紀半ばのロシア社会への鋭い批評と、ペテルブルグの街のゴシップを種にした、都会派作家ドストエフスキーの真骨頂、初期・中期のヴォードヴィル的ユーモア小説4篇を収録。
沼野充義
ここに収められた初期から中期のドストエフスキー作品の基調ともいうべきものは、延々と続く形而上的議論の底知れぬ深みに下りていく手前で踏みとどまり(いったん呑み込まれたら這い出すことができないような深みがあることはすでに予感されるとはいえ)、あえて表層で戯れ続けているような感じさえ与える過剰な言葉と自意識のドタバタ劇場であって、ドストエフスキーは明らかにユーモア作家でもあった。――<「解説」より>

この三つのもの
講談社文芸文庫
まことの恋と友情と智恵の石
主人公・赤木清吉は、友人・北村荘一郎にないがしろにされている夫人・お八重に同情するうちに、永遠の恋に陥ちてしまう――。かつてスキャンダラスな「細君譲渡事件」として世に知られた佐藤春夫と谷崎潤一郎および千代夫人との三角関係を題材に、自らの愛憎の葛藤を吐露した未完の表題作と、「一情景」「僕らの結婚」を収録。10年におよぶ愛の軌跡の全貌を辿る。作品は、愛を貫く文学者の誠実を示すものとなった。
千葉俊二
時間的にはわずか4日間の出来事が記されているのみであるが、その場面々々に応じて過去の回想や述懐が挟まれ、時間が重層的に組み合わされる。あたかも絵の具を丹念に何度も塗りかさねるようにして画いた油絵の大作をみるように、描写の密度は細かく、登場人物の人間関係や心理の交錯が、それこそバルザック風の本格的なリアリズムの手法によって重厚に描きだされる。――<「解説」より>
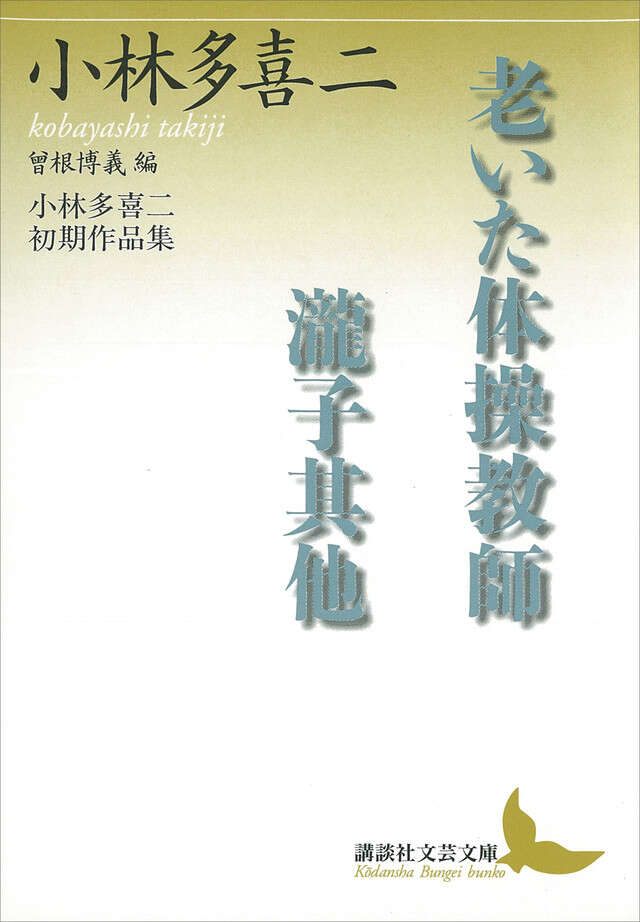
老いた体操教師・瀧子其他 小林多喜二初期作品集 曾根博義編
講談社文芸文庫
大正から昭和初め、働きつつ学ぶ青年・多喜二は、文学への熱情、人間を抑圧する社会への怒り、知り初めた恋の苦しみを、ノートに書きつけ雑誌に投稿した。虐げられる弱き者への優しい眼差しと、苦の根源への鋭い問いを秘めた、これら初期作品群こそは、29歳で権力に虐殺されたプロレタリア作家の多感な青春の碑である。86年ぶりに発掘された最初期の「老いた体操教師」、秀作「瀧子其他」を含む16篇を精選。
革命、恋。短くも激しく燃えた青春の碑
大正から昭和初め、働きつつ学ぶ青年・多喜二は、文学への熱情、人間を抑圧する社会への怒り、知り初めた恋の苦しみを、ノートに書きつけ雑誌に投稿した。虐げられる弱き者への優しい眼差しと、苦の根源への鋭い問いを秘めた、これら初期作品群こそは、29歳で権力に虐殺されたプロレタリア作家の多感な青春の碑である。86年ぶりに発掘された最初期の「老いた体操教師」、秀作「瀧子其他」を含む16篇を精選。
曾根博義
「瀧子もの」……など、昭和に入ってからの短篇に、多喜二のリアリズムが個人的にも社会的にも登りつめ、磨きをかけられた末に、「救い」や「理想」を求めて闘い、個人を超えるぎりぎりの地点にまで達した、その最高の成果が見られる。(略)また「人を殺す犬」の残酷さは個人の内面を無視した表現の残酷さではなくて事実の残酷さであるにもかかわらず、言葉によるリアリズムの極限の恐ろしいまでの力を感じさせて、2年後の「蟹工船」を想起させずにはおかない。――<「解説」より>

世俗の詩・民衆の歌 池田彌三郎エッセイ選
講談社文芸文庫
懐かしの童謡、唱歌の世界。歌でたどる都市の風俗ーー折口信夫の高弟にして、日本芸能研究の重鎮である著者の歌と言葉をめぐる軽妙なエッセイの数々。小学生時代と重なる大正期、その時、口ずさんだ童謡や唱歌を記憶のなかから甦らせ、都市の風俗と言語生活の変遷をたどり、宝塚少女歌劇から戦後の歌謡曲まで、そこに息づく庶民の心を読み解く。軍歌の一方的排斥に異を唱え、歌詞のなかの言葉遣いへの辛辣な評言も著者ならでは。
◎「文学の歴史の叙述にも、文学作品そのもの、あるいは作者の歴史に対して、読者の歴史が書かれなければならないように、歌の場合にも、それを聴き、習い、歌った、つまり与えられた側の歴史が書かれてもいいと、わたしはかねて思っていた。わたし達のまわりにあるものは、それを制作して与えてきた側の記述が多く、それを聴き、習い、歌った側の記述がほとんどないからである。それには、わたしはかなり不満であった。」<「あとがき」より>
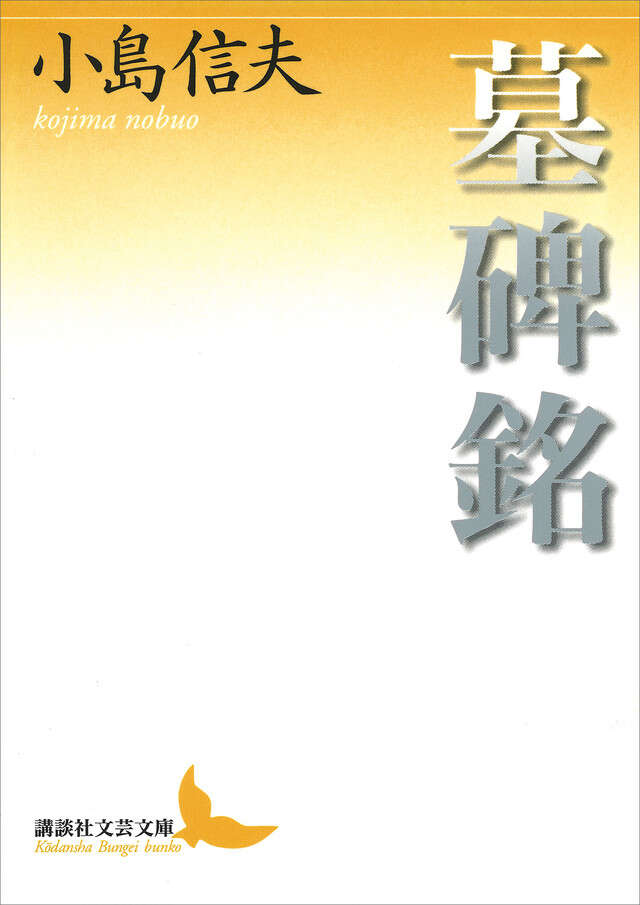
墓碑銘
講談社文芸文庫
アメリカ人の父親と日本人の母親の許に生まれた、トーマス・アンダーソンこと浜仲富夫。日米開戦を機に、日本人として生きることを強いられる。坊主頭で国民服を着て、剣道を習い、国策映画では悪役アメリカ人を演ずる。そして入営。青い眼の初年兵は、異父妹への想いを支えに、軍隊生活のつらさに耐える。だが、山西省から米兵と対峙するレイテ島に転進。極限状況の中でアイデンティティを問う、戦争文学の白眉。異色の戦争文学……日米混血の日本兵、その壮絶な自己喪失の過程を描く。
〇千石英世 『墓碑銘』はちがう。(略)これは総論ではなく各論なのだ。極私的各論、戦争を極私の次元で、あるいは極私の日常性の次元で捉えようとする小説、しかもその「私」がいつしか消滅する小説、総論としての日本論や政策論へと傾きがちな戦後文学の対極に位置して異次元を開く小説に徹した小説、言語芸術の不思議を具現する小説なのである。(略)それを審美的異物としての小説と呼んでもよい。――<「解説」より>

ザ・ダルマ・バムズ
講談社文芸文庫
物質文明を否定し、人間性の回復を願った若者達の、精神的放浪を描いたビートニク文学の傑作。
1950年代のアメリカに擡頭した<ビート・ジェネレーション>の旗手ジャック・ケルアックとゲリー・スナイダー。2人を投影したレイ・スミスとジェフィ・ライダーの出会い、友情、禅的至福を求めた精神的放浪、そして離別までを描いた自伝的青春物語。「あらゆる個性が失われ、あらゆる驚異が死んでしまったこの現代社会を離れて、文明の源流に溯り、その暗黒の奥底にひそむ神秘を探り出さんがために」元祖ヒッピー達が行く!
中井義幸
一世を風靡した「ビート」という言葉は、ケルアックの造語であった。これは、朝鮮戦争後、50年代に入ったアイク=ニクソン体制下のアメリカの、清潔で、空虚で、欺瞞に満ちた中産階級(ミドルクラス)文化に反逆し、雨風に打ちたたかれてしたたかに鍛え抜かれ、ジャズのビートの如くに生命に溢れた新文化を築いて行こうという真摯な青年達の運動であった。――<「解説」より>

内部の人間の犯罪 秋山駿評論集
講談社文芸文庫
「犯罪」とは――。都市の空虚なビル、そのコンクリートの壁の上に、簡単な1本の線で描かれる「人間」の形である。少年による「理由なき殺人」の嚆矢、小松川女高生殺人事件。犯人の少年の獄中書簡に強く心を衝たれた著者は、動機の周りを低回する世間の言説に抗し、爆発的な自己表現を求めた内部の「私」の犯罪であるとする文学の言葉を屹立させた。他、永山則夫、金嬉老など、犯罪を論じた評論17篇を精選。

贋・久坂葉子伝
講談社文芸文庫
愛に殉じた若き伝説の女性作家、その可憐で熾烈な生涯。
昭和27年の大晦日、21歳で列車に身を投じた伝説の女性作家・久坂葉子。名門家庭の重圧に抗いつつ、敗戦後の自由と倦怠の空気の中で、自らの芸術を追い求め、愛と性に殉じた可憐で強烈な生涯。3人の男性の間で激しく揺れ動く自分を「罪深き女」と断罪し、本当のことのみを書くと、死の当日まで綴った作品を残して逝った、その死に至る過程を、師の温かい眼差しで見事に描破した力作長篇。
山田稔
愛惜と悔恨の情は、すでに久坂の通夜でつぎのような疑問をいだかせていた。「本当にあの棺桶の中に久坂が入っているのかな」。(中略)この、久坂生存・転生のテーマというか願望は重要で、後々まで富士正晴のうちに生きつづける。(中略)自殺をうまく「すり抜け」たにせの久坂葉子が両性具有者(彼女には男の子じみたところがあった)として転生し、この世のどこかに生きつづける、いわば富士版『オーランド』が書かれたかもしれない。――<「解説」より>

柿二つ
講談社文芸文庫
死に往く子規と、見つめる虚子。写生文の白眉と称される長篇小説。
「余りの苦しさに天地も忘れ……野心も色気も忘れてしもうて、もとの生れた儘の裸体にかえりかけているのだな。」K(虚子)は……尊い心持で其話を聞いていた。(第十八回「介抱」)正岡子規と高浜虚子――無二の友でありかつ火花を散らす二つの個性。病床に臥す子規の日常、死を所有する内奥の恐怖と孤独を凝視、写実に徹した写生文の白眉と評された長篇小説。題名は「三千の俳句を閲し柿二つ」(子規)による。
山下一海
子規と虚子の間のさまざまな交渉や葛藤が、子規を主としながら、とくに感情的、心理的な側面から、赤裸々に描きだされている。素材的な意味だけでも、興味津々たる小説である。表題は、子規が京の禅僧で歌人の愚庵から贈られた好物の柿が二つ残っていて<三千の俳句を閲し柿二つ>の句を作ったことによるものであろうが、小説の全体を読むと、子規と虚子というたぐいまれな存在が、二つの艶やかな柿のように思われてくる。――<「解説」より>

私の戦旅歌
講談社文芸文庫
昭和14年、騎兵として中国山西省に出動した若き兵士は、果てしない黄土高原の風景、生死を一瞬に分かつ戦の実状と兵士の死生観、帰還しなかった軍馬達への哀惜を歌に詠んだ。旅嚢の底に秘め辛々持ち帰った手帖に記された歌に回想を加えた本書には、戦争体験者の真情と詩心が溢れ返っている。
戦旅にあってなお歌は生まれた
陣地占りてようやく心しずまりぬ曳光弾を美しと思う
茫茫とわれを越えゆく歳月を堰くすべもなきいくさなりしか
昭和14年、騎兵として中国山西省に出動した若き兵士は、果てしない黄土高原の風景、生死を一瞬に分かつ戦の実状と兵士の死生観、帰還しなかった軍馬達への哀惜を歌に詠んだ。旅嚢の底に秘め辛々持ち帰った手帖に記された歌に回想を加えた本書には、戦争体験者の真情と詩心が溢れ返っている。
大河内昭爾
この情感の豊かさが『私の戦旅歌』1冊の基調である。また「大自然の風光というのは、人間を、基本的に魅了してしまう力がある」といい、「一種の虚脱感、放心に陥れてしまう。」と著者はしるしているが、かかる放心が『私の戦旅歌』と一連の文章の底にあって、反戦などという戦記物につきまとう、おきまりの観念の入り込む余地はない。――<「解説」より>
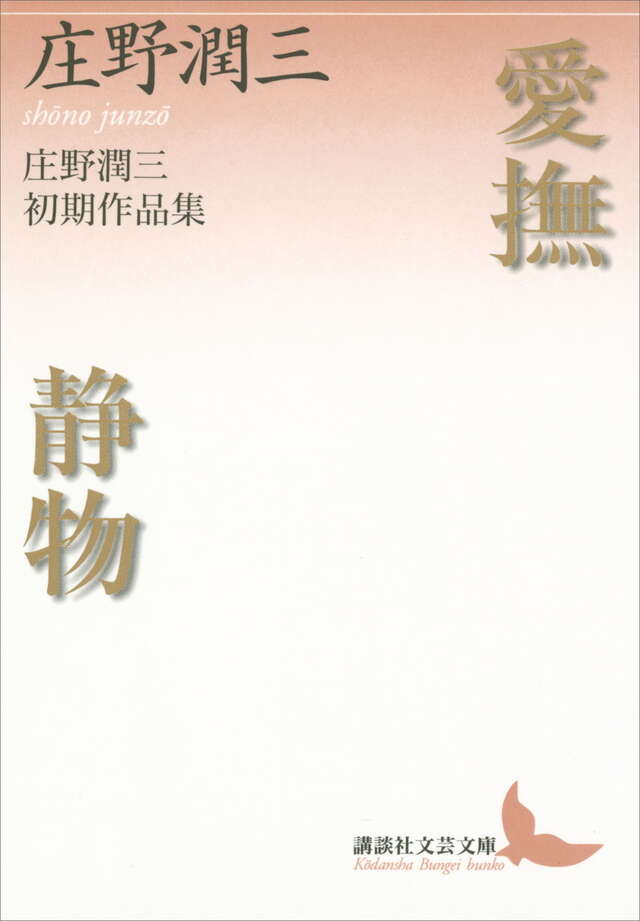
愛撫・静物 庄野潤三初期作品集
講談社文芸文庫
妻の小さな過去の秘密を執拗に問い質す夫と、夫の影の如き存在になってしまった自分を心許なく思う妻。結婚3年目の若い夫婦の心理の翳りを瑞々しく鮮烈に描いた「愛撫」。幼い子供達との牧歌的な生活のディテールを繊細な手付きで切り取りつつ、人生の光陰を一幅の絵に定着させた「静物」。実質的な文壇へのデビュー作「愛撫」から、出世作「静物」まで、庄野文学の静かなる成熟の道程を明かす秀作7篇。
日常という画布(カンバス)を一閃する人生の真実
妻の小さな過去の秘密を執拗に問い質す夫と、夫の影の如き存在になってしまった自分を心許なく思う妻。結婚3年目の若い夫婦の心理の翳りを瑞々しく鮮烈に描いた「愛撫」。幼い子供達との牧歌的な生活のディテールを繊細な手付きで切り取りつつ、人生の光陰を一幅の絵に定着させた「静物」。実質的な文壇へのデビュー作「愛撫」から、出世作「静物」まで、庄野文学の静かなる成熟の道程を明かす秀作7篇。
高橋英夫
それら短篇群のあとに、中篇とも見なしうる大きな作品「静物」が来る。それがこの1冊の要であり、あらゆる初期作品はそこへと収斂してゆくことになったのだと観じ、感嘆するほかはない名作「静物」である。遠い山中に発した水源が、少しずつ水量を増しながら長い水の旅を続けて、ついに河口に達し、海に流れ入ったような感銘がこの作品にはある。そしてそのとき読者は、あきらかにそれまでの熱い感触の人間図絵とは異る、不思議に鎮静されたトーンがくまなくこの作品に行き亘っていることに気付かされるだろう。――<「解説」より>
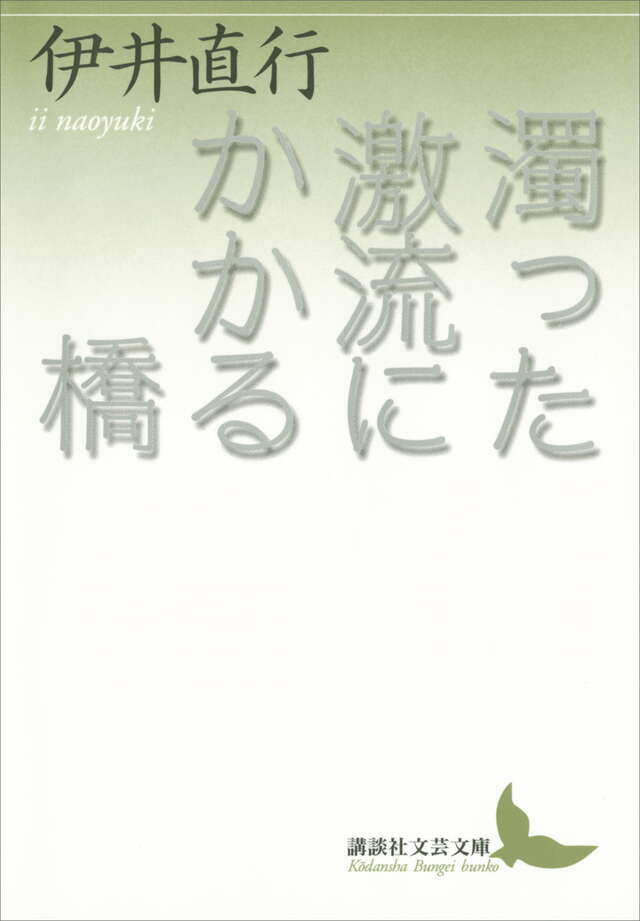
濁った激流にかかる橋
講談社文芸文庫
激流によって分断された町の右岸と左岸。それをつなぐ唯一の異形の橋。かつての小川は氾濫をくり返し、川幅は百倍にもなり、唯一の橋は拡張に拡張を重ね、その全貌を把握できぬほどの複雑怪奇さを示す。そして右岸と左岸にはまったく気質の異なる人々が住む。この寓話的世界の不思議な住民たちの語る9つの物語。諧謔的かつ魔術的なリアリズムで現代の増殖する都市の構造を剔抉した読売文学賞受賞作。
寓話的都市の崩壊と再生。
激流によって分断された町の右岸と左岸。それをつなぐ唯一の異形の橋。かつての小川は氾濫をくり返し、川幅は百倍にもなり、唯一の橋は拡張に拡張を重ね、その全貌を把握できぬほどの複雑怪奇さを示す。そして右岸と左岸にはまったく気質の異なる人々が住む。この寓話的世界の不思議な住民たちの語る9つの物語。諧謔的かつ魔術的なリアリズムで現代の増殖する都市の構造を剔抉した読売文学賞受賞作。
笙野頼子
壊れているのだけれど形は元のまま。生きた本当の人間を渡さない橋。新しい文学や時代意識を阻む、分かりやすいけれど嘘だらけの、改良しようとすると抑圧される、そんな橋であった。それは「上から見た国家視点で書く現実世界」とか「マジョリティのためにある真実」を渡すための「マスコミ言語的」愚民橋である。渡れるのはマッチ棒大の人形のみ。格差社会を繋ぎ、難解で恨みに満ちた現実の激流を越えて渡れるような、そんな新しい橋は、まだまだ遠い。――<「解説」より>

ロンドンの味 吉田健一未収録エッセイ
講談社文芸文庫
詩心が響映する吉田文学40年の遺珠68篇。
古今東西の文学に通暁し、言葉による表現の重要性を唱え、独自の豊かな文学世界を構築した天性の文人・吉田健一。その軽妙洒脱な食味随筆、紀行文、イギリス滞在記を始め、最初期のラフォルグ論、ボードレール論、鴎外論、また、後年の文学的開花に密接に繋がる厖大な翻訳の「解説」、さらには、最晩年の中島敦論まで、精緻な調査によって発見された新資料を含む、単行本未収録エッセイ68篇。
島内裕子
没後30年が過ぎようとしている今、未収録作品も含めて、吉田健一の全貌をわがものとし、不断にその清新な感情と感覚に触れることは、かけがえのない生きる喜びとなって、わたしたちの心を潤わせてくれる。吉田健一の文学世界はすべて、彼の詩心が響映した精緻繊細であると同時に、のびやかでのどかな稀に見る別天地である。しかし、その別天地は、彼の言葉によって実在がわたしたちに保証されている現実世界でもあるのだ。――<「解説」より>

糞尿譚・河童曼陀羅(抄)
講談社文芸文庫
人は地を這い、河童は天翔ける 火野文学の「聖」と「俗」
出征前日まで書き継がれ、前線の玉井(火野)伍長に芥川賞の栄誉をもたらすと共に、国家の命による従軍報道、戦後の追放という、苛酷な道を強いた運命の1冊「糞尿譚」。郷里若松の自然と人への郷愁を、愛してやまない河童に託し夢とうつつの境を軽やかに飛翔させる火野版ファンタジー、「河童曼陀羅」。激動の昭和を生き抜く庶民的現実と芸術の至高性への憧憬――聖俗併せもつ火野文学の独自の魅力に迫る。
井口時男
火野の河童たちには、どれも、弱者、敗者の哀れと滑稽がにじんでいる。そもそも敗者の落魄は、零落した神としての河童の本性に属するものだが、それだけではあるまい。「河童は、詩と小説との間を彷徨した私が、ほっとためいきをついたような場所」なのだ、と解説で火野はいう。そのとおりなのだろう。戦中戦後と猛烈な勢いで原稿を書きつづけた火野葦平の、これは「ためいき」のような世界なのかもしれない。――<「解説」より>

私の詩と真実
講談社文芸文庫
評論の形で描く精神形成の自画像
小林秀雄とともにわが国の近代文芸批評を文学として確立させた河上徹太郎。「純粋」という観念に憑かれた一青年は、中原中也、また青山二郎らとの深い交流のなかで精神の自己形成を図った。音楽を愛し、ヴェルレーヌ、ジッド、ヴァレリーらフランス象徴主義の思考により、エピキュリアンにしてストイックな精神性を身につけた、日本文学最高のアマトゥールによる自伝的連作エッセイ11篇。
長谷川郁夫
「私の詩と真実」はやがて訪れる晩年の豊饒を約束する一書となった。虚無の豊饒、とは本書中にみられる一つの観念(イデー)だが、それが見事に花開くのだった。(中略) 批評というものが、なんとも「贅沢」な文学形式であることを、河上徹太郎は実践をもって示した。そして、それは「完璧」なものであった。――<「解説」より>

アメリカと私
講談社文芸文庫
著者20代最後の年、1962年より2年間のプリンストン滞在記。この間、公民権運動の高揚、キューバ危機、ケネディ暗殺など、激動期を迎えていたアメリカ社会の深部を見つめ、そこに横たわる自他の文化の異質性を身をもって体験する。アメリカという他者と向き合うことで、自らのアイデンティティの危機を乗り越え、その後の「国家」への関心、敗戦・占領期研究への契機ともなった、日本文化論の歴史的名著。
60年代の激動するアメリカで戦後日本のありうべき姿を模索する
著者20代最後の年、1962年より2年間のプリンストン滞在記。この間、公民権運動の高揚、キューバ危機、ケネディ暗殺など、激動期を迎えていたアメリカ社会の深部を見つめ、そこに横たわる自他の文化の異質性を身をもって体験する。アメリカという他者と向き合うことで、自らのアイデンティティの危機を乗り越え、その後の「国家」への関心、敗戦・占領期研究への契機ともなった歴史的名著。
加藤典洋
大日本帝国という極東の新興国からロンドンという世界の中心地に来た留学生夏目漱石には「自己本位」というあり方を発見させるが、ほぼ60年後、日本という敗戦国からプリンストンという米国発祥に関わりの深い大学町に来た客員研究員の江藤淳には、日本人たる自分というアイデンティティ、つまり「自国本位」というあり方を、発見させる。――<「解説」より>

随筆三国志
講談社文芸文庫
流行りの梁父吟(ロカビリー)が大好きな諸葛孔明は当時のアプレ・ゲール! 強靱なレトリックと博覧強記で縦横に古典を論じ、同じく乱世の修羅にある現代の貌を浮き彫りにする花田流三国志論。戦争中に書かれた比類なき抵抗の書『復興期の精神』から最後の著作『日本のルネッサンス人』まで首尾一貫、転形期の人間像を描き続けた花田清輝が、三国志に託して今の世界を、さらに歴史の未来を透視する知的興奮に満ちた1冊。
諸葛孔明はロカビリアンだった!?
破天荒な花田流三国志論
流行りの梁父吟(ロカビリー)が大好きな諸葛孔明は当時のアプレ・ゲール! 強靱なレトリックと博覧強記で縦横に古典を論じ、同じく乱世の修羅にある現代の貌を浮き彫りにする花田流三国志論。戦争中に書かれた比類なき抵抗の書『復興期の精神』から最後の著作『日本のルネッサンス人』まで首尾一貫、転形期の人間像を描き続けた花田清輝が、三国志に託して今の世界を、さらに歴史の未来を透視する知的興奮に満ちた1冊。
井波律子
60年代末の激動の季節(中略)揺れ動く時間帯のまっただなかで書かれたこの作品は、今、読み返して見ても、時の流れを超えていきいきと読者に語りかけてくる躍動性にみちあふれている。いかにも花田清輝らしく、思いつくままアトランダムに書きすすめているようでありながら、その実、本書は「三国志」世界の開幕から終幕に至るまで、ユニークな問題意識を以て要所要所を掘り下げながら追跡しきっており、みごとというほかない。――<「解説」より>

ロダンの言葉 現代日本の翻訳
講談社文芸文庫
「私はロダンによって救われ、ロダンによって励まされた。」
その詩業において不可欠である智恵子の存在と同様、光雲の嗣子として生まれ彫刻家の運命を定められた高村光太郎にとって巨匠オーギュスト・ロダンとの出会いは、天啓にもひとしいものだったにちがいない。「ランスの本寺」に始まり手稿、聞書を翻訳編纂することは自らの芸術観を確立するための必然的な作業でもあった。そして本書は若い芸術家たちに歓呼で迎えられた。
湯原かの子
光太郎は30代の働き盛りの大半をロダンの訳業にあてた。その後も、評伝「オオギュスト・ロダン」(1927)を著したり、美術書に作品解説をしたりと、ロダンに関わり続ける。こうした訳業を通して、西洋彫刻の技術的な知識や専門的な概念を学んだのはもちろんのこと、ロダンの自然主義と生命の芸術論から大きな影響を受けるのである。――<「解説」より>
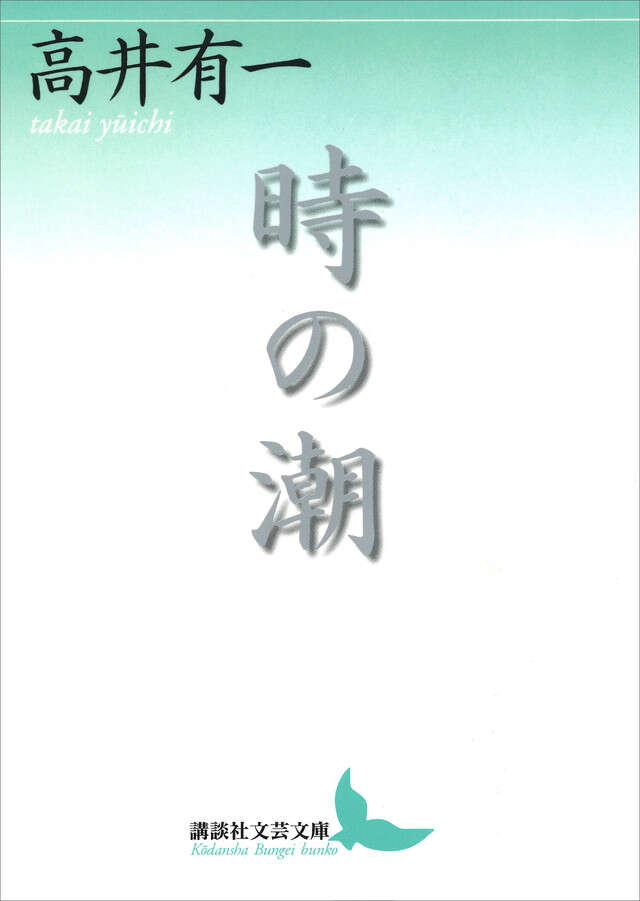
時の潮
講談社文芸文庫
今日、昭和が終った。天皇崩御のニュースをきいて、近くの御用邸に記帳に出かけた。昭和に生まれた私は、私の時代が終わってしまったような気がした。元新聞記者の私は、10歳年下の共同生活者・真子と葉山に暮らし、四季を楽しんでいる。しかし、さまざまに形をかえて潮だまりが出現するように、二人の間にわだかまりがないわけではない。戦時下に生まれ、戦後を生きる男と女を静かに描く、野間文芸賞受賞作。
〇松田哲夫 戦争と天皇にまつわる思い出が、時には烈しく、時には静かに、登場人物に押し寄せてくる。高井さんは、決して声高に歴史や政治にもの申すわけではない。しかし、ここに刻み込まれた言葉は、ぼくたち読者の心にズシリと重くのしかかってくる。そういう意味では、戦争の時代をとらえた、優れた歴史小説だと言ってもさしつかえないだろう。――<「解説」より>

偶像再興・面とペルソナ 和辻哲郎感想集
講談社文芸文庫
時代に共鳴する
荒漠たる秋の野に立つ。星は月の御座を囲み月は清らかに地の花を輝らす。――と書き出される「霊的本能主義」。18歳、一高校友会雑誌に発表されたこの論考に始まり、『古寺巡礼』と同時期に刊行されながら著者自らによって封印された『偶像再興』、芸術への深い造詣を示す名随筆『面とペルソナ』に至る知の巨人の感性溢れる文章世界を厳選して再読する。
和辻哲郎
予はただ「古きものの復活」を目ざしているのではない。古きものもよみがえらされた時には古い殻をぬいで新しい生命に輝いている。そこにはもはや時間の制約はない。それは永遠に若く永遠に新しい。予の目ざすのはかくのごとき永遠に現在なる生命の顕揚である。――<本文より>