講談社文芸文庫作品一覧

男
講談社文芸文庫
男は黙ってよく働いている
だいじにしなければなあと思う
歿後30年。
「男」をめぐる初の随筆選。
羅臼の鮭漁、森林伐採、ごみ収集、救急医療、下水処理、少年院、橋脚工事ーー
日常の暮らしを支える現場で働く男性たちに注ぐ、やわらかく細やかな眼差し。
現場に分け入り、プロフェッショナルたちと語らい、自身の目で見て体感したことのみを凜とした文章で描き出す、行動する作家・幸田文の随筆の粋。
(収録作品)
男(濡れた男/確認する/切除/火の人/傾斜に伐る/都会の静脈/まずかった/ちりんちりんの車/救急のかけはし/並んで坐る/橋)
ちどりがけ
当世床屋譚
植える
出合いもの
いい男
男のひと
素朴な山の男
男のせんたく
男へ

野川
講談社文芸文庫
大空襲から戦後の涯へ、時空を貫く生涯の道。現代文学の最高峰、古井文学の原景をたどる名篇。
急逝した友人が抱え続けた空襲の夜の母子の秘密。狂気をはらむ年上の女との情事に囚われた学生時代の友人。そして防空壕の底で爆音に怯えた幼時の自分。生涯の記憶は歳月を経て自他の境を超え、老年の男の身の内で響きあう。戦後の時空間にひしめく死者たちの声とエロス、現代の生の実相を重層的な文体で描いた傑作長篇小説。解説・佐伯一麦。

村上春樹の世界
講談社文芸文庫
著者の文芸評論家としてのキャリアのなかで一貫してつづいた村上春樹作品への強い関心。世界的な人気作家を相手に遠慮も手加減もなく長篇も短篇も読むたびごとに全力で受け止め、刺戟的な批評の言葉を対置して向き合ってきた。肯定も否定も超え真価を問う営みがここにある。没後発表された遺稿「第二部の深淵」を収録。

テクストから遠く離れて
講談社文芸文庫
いま小説に何が起きているのか?現場の思考を貫いた著者が、同時代の文学・批評と格闘してつかんだ、共に生きるための思想。
『テクストから遠く離れて』は、一見、難しそうに見える本だ。けれども、難しいのには理由がある。それは、ほんとうに大切なことだけれど、それをきちんと理解するためには、ぼくたちがふだん考えているような、「適当な」、あるいは、「みんなが考えているのでそうだと思いこんでいる」やり方では、ダメだ、という場合があるからだ。ときには、「堅い」ものを噛まなきゃならない必要がある。ぼくたちのからだに必要な「栄養」を与えてくれるものを、摂取するためには。
―ー高橋源一郎(「解説」より)
ポストモダン思想とともに80年代以降、日本の文学理論を席巻した「テクスト論」批評。その淵源をバルト、デリダ、フーコーらの論にたどりつつ、大江健三郎、高橋源一郎、村上春樹、阿部和重ら、同時代作家による先端的な作品の読解を通して、小説の内部からテクスト論の限界を超える新たな方法論を開示した、著者の文芸批評の主著。批評のダイナミズムを伝える、桑原武夫学芸賞受賞作。

一人と千三百人/二人の中尉 平沢計七先駆作品集
講談社文芸文庫
関東大震災の混乱のなか亀戸事件で惨殺された若き労働運動家は瑞々しくも鮮烈な先駆的文芸作品を遺していた。
知られざる作家、再発見
関東大震災の混乱のなか亀戸事件によってわずか三十四歳で非業の死を遂げた労働運動家・平沢計七。
彼は少年時から鉄道会社の大工場で労働現場に立ち、やがて労働組合活動に入っていったが、その短い生涯で、瑞々しくも鮮烈な文芸作品を遺していた。
短篇小説十三篇、戯曲七篇と評論・エッセイ七篇を精選し、知られざる先駆的作家に再び光をあてる。
祖国の手で打砕かるゝか、
民衆の手で打砕かるゝか
死を予想しえた若き労働運動家、
その知られざる文学的航跡。
大和田 茂
平沢は日々の労働運動や社会運動の中で、数々の軋轢、暗闘、分裂をいやというほど味わってきた。なぜ、人々は階級的憎悪をもってテロリズムに走るのか、なぜ思想のちがいや意見対立、すなわち小異を捨てて大同団結できないのか。彼にとって、革命は遼遠の彼方であった。(中略)平沢はさらに労働者の意識に下降しようとしていた。彼は指導者意識が強かったが、一方では小説、戯曲、講談などで人々の内面にわかりやすく訴えかけていこうとした。「解説」より

稲垣足穂詩文集
講談社文芸文庫
「さあこれから管を吹きます、何が出るか消えぬうちに御覧下さい」
――理屈つぽく夢想的な人々のための小品
日本文学の異才、その“詩性”を捉え直す
「詩的要素は多い」と認めつつ、「詩人」のレッテルを否定していた稲垣足穂。
それでも、詩やコントというべき独創的な作品群が数多く大正期の前衛詩誌に発表され、若い詩人たちに多様な影響を与えた。
一九二〇~三〇年代を中心に晩年まで並べられた稀有な作品集に、大正期から戦後を経て晩年に至るまでの詩論やエッセイを併載し、日本文学の異才の“詩性”を剔出する。
「大正期の前衛詩誌に発表された稲垣足穂の初期作品にはじまり、一九二〇~三〇年代を中心に晩年まで並べられた作品集はほかにない。(中略)そして、編者である中野嘉一は自身、足穂と同じく、詩の形式が根底から問い直されていた詩論の時代に生き、「モダニズム詩」の可能性を追い求めた当事者でもあった。彼の「前衛詩運動史」という歴史的観点から稲垣足穂の「詩」を捉え直そうとする意志にこそ、本書のもう一つの特色はある」(高橋孝次「序文」より)

つげ義春日記
講談社文芸文庫
伝説の漫画家が私生活の苦闘を描いた幻の日記、待望の初文庫化。
昭和50年代、結婚し長男も誕生して一家をかまえた漫画家つげ義春は、寡作ながらも「ねじ式」「紅い花」など評価の高い作品群が次々と文庫化され、人気を博す。生活上の安定こそ得たが、新作の執筆は思うように進まず、将来への不安、育児の苦労、妻の闘病と自身の心身の不調など人生の尽きぬ悩みに向き合う日々を、私小説さながら赤裸々に、真率かつユーモア漂う筆致で描いた日記文学の名篇。解説・松田哲夫。

庭の山の木
講談社文芸文庫
田舎風のばらずしをこしらえるのに、ちょっと似ている――
七十編に及ぶ随筆を一冊にまとめる工程を、著者はあとがきでそんなふうに表現した。
家庭でのできごと、世相への思い、愛する文学作品、敬慕する作家たち――
それぞれの「具材」が渾然一体となり、著者のやわらかな視点、ゆるぎない文学観が浮かび上がる。
充実期に書かれた随筆群を集成した、味わい深い一書。

乳母車・最後の女 石坂洋次郎傑作短編選
講談社文芸文庫
戦後、一世を風靡した大流行作家・石坂洋次郎。小説『青い山脈』は映画化され、1949(昭和24)年に封切られると同時に大ヒットし、その主題歌とともにほとんど戦後民主主義の代名詞と見なされるにいたりました。以後、石坂原作の映画が封切られない年は、1960年代後半までありませんでした。それほどの流行作家だったのです。しかし、70年代に入るやいなや、その流行はあっという間に衰えてしまいました。かつて『青い山脈』を明朗健全であるがゆえに評価し、暗くなりがちな戦後に爽やかな風を送ったとして称賛した読者が、こんどはその明朗健全さに飽きてしまったのでしょうか? いずれにせよ、石坂は「忘れられた作家」のひとりとなりました。しかし、石坂には、明朗健全以上に重要な特徴があると編者の三浦雅士さんは言います。それは「女を主体として描く」という特徴です。主人公と言わずに主体と言うのは、女は主人公であるのみならず、必ず、主体的に男を選び主体的に行動する存在として描かれているからです。女は見られ選ばれる客体である以上に、自ら進んで男を選び、男に結婚を促し、自分自身の事業を展開する主体なのです。明朗健全な爽やかさはこの主体的な女性が結果的に醸し出すのであって、逆ではありません。この特徴に誰も気づかずにいたのは驚くべきこと、「明朗健全なるがゆえに売れっ子となり、またそれゆえに忘れられた作家」などというのがいかに浅薄な見方であったか、いまや思い知るべき時が来たと三浦さんは説きます。かくして選び出された「女性の主体的な生き方の最終的な姿を示してほとんど常識を覆す域に達している」短編9編。いまこそふたたび石坂作品の魅力を多くの読者に知ってほしいとの思いから選ばれた傑作です。

詩への小路 ドゥイノの悲歌
講談社文芸文庫
ライナー・マリア・リルケ「ドゥイノの悲歌」全訳をはじめ、長年親しんだドイツ、フランスの詩人からギリシャ悲劇まで、還暦の年から九年にわたり書き継がれた詩をめぐる自在な随想と、自らの手による翻訳。徹底した思索と比類なきエッセイズムが結晶した名篇。
「詩はもとより私の領分ではない。外国文学の分野からも、離れてからもう久しい。それでも還暦の今ならぎりぎり、青年期への「お礼奉公」をささやかながら済ませるような気持もあった。/小説は相変わらず苦渋の連続だったが、この詩についての随想のほうは、わずかずつ思い出すにまかせているうちに、いつか私としては楽な筆の運びとなっていた。こんなことは、「山躁賦」の時のほかは知らない。自分は小説と随想の間に生息する者かと思った。」――古井由吉

深淵と浮遊 現代作家自己ベストセレクション
講談社文芸文庫
アンソロジスト高原英理の呼びかけで実現した、未だかつてない「作家自己ベスト作品集」。
「そう来たか!」と意表を突くセレクトから納得の王道的傑作まで。
短編小説、随筆、短歌、経典の評釈――
現代文学の最前線を牽引する文学者たちが挙げた「自己ベスト作品」を集成した豪華アンソロジー。
「編者が作品を選ばない」
この編纂方法でなければ一堂に会することはなかった、それぞれの作家固有の文学観と達成を示す煌びやかな収録作品群の妙を堪能できる、奇跡の一書!
「これまでいくつかアンソロジーを編んできて、ほぼどれもありがたい反響をいただき、よい仕事をしたと自負もしているが、ただ、ときに内心忸怩たる思いがないではなかった。どこまでいってもこの自分の視点からしか見られないことの無念である。自分のまるで考えもしなかった視界を開く方法はないか。
こうして当アンソロジーのプランは生まれた。参加していただける個々の作家自身の決定にお任せする。それは私などの狭い先入観を裏切って思いもよらない豊饒な結果を生むだろう。ご覧いただきたい」
(編者・高原英理氏解説より)
〈収録作品〉
伊藤比呂美「読み解き「懺悔文」女がひとり、海千山千になるまで」
小川洋子「愛犬ベネディクト」
高原英理「ブルトンの遺言」
多和田葉子「胞子」
筒井康隆「ペニスに命中」
古井由吉「瓦礫の陰に」
穂村弘「いろいろ」
堀江敏幸「のぼりとのスナフキン」
町田康「逆水戸」
山田詠美「間食」
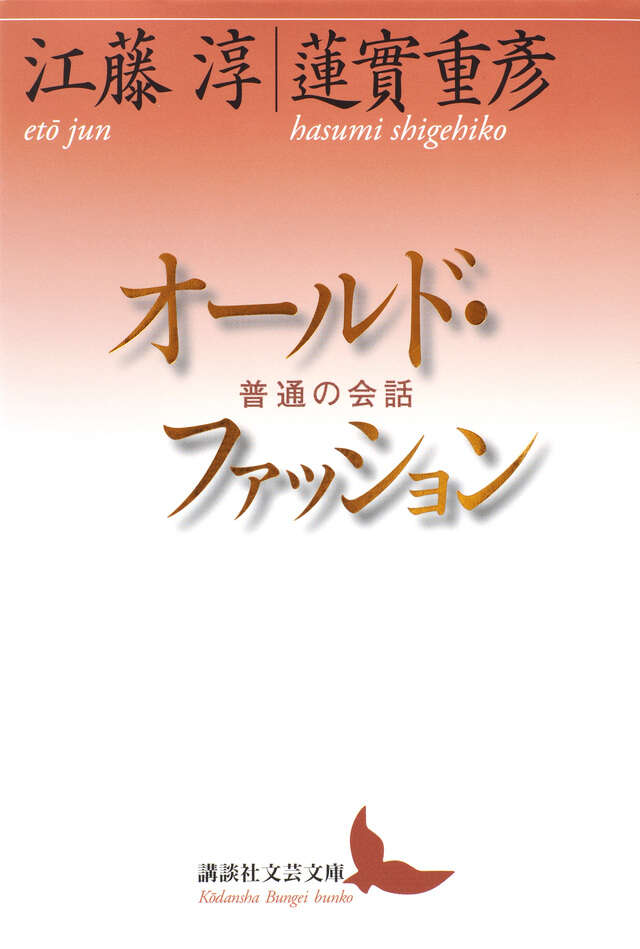
オールド・ファッション 普通の会話
講談社文芸文庫
一九八五年四月八日。東京ステーションホテルにて、
日本を代表する批評家が初対峙する。夕食とともに開幕した
「普通の会話」ならぬ前代未聞の「知の饗宴」は、
食後のブランデー、チョコレートを愉しみつつ一日目を終了、
翌朝も食堂、客室と舞台を移しつつ、正午近くに及ぶ。
文学、映画、歴史、政治から、私生活に人生論まで。
ユーモアとイロニー、深い洞察に満ちた、歴史的対話篇。

茂吉秀歌『赤光』百首
講談社文芸文庫
前衛歌人で稀代の批評家、そして剛腕アンソロジストでもある塚本邦雄が、斎藤茂吉の秀歌に対して「弟子、一門の徒」とは別角度から真摯に迫り、批評・鑑賞を施した歴史的名著。茂吉の歌を照射し、その秘密に肉薄しつつ、短歌を含めた日本詩歌のあるべき姿を追究する、茂吉ファン、塚本ファン、短歌ファンのみならず、日本文学に関心のあるすべての人へ。言語芸術の粋がここにある。

ヒューマニズム考 人間であること
講談社文芸文庫
「それは人間であることとなんの関係があるのか。」
フランス・ルネサンス文学の泰斗が、宗教改革をはじめさまざまな価値の転換に翻弄されながらも、その思想を貫いたユマニスト(ヒューマニスト)たち――エラスムス、ラブレー、モンテーニュらを通して、「人間らしく生きようとする心根と、そのために必要な、時代を見透す眼をもつこと」の尊さを平易な文章で伝える名著。
●大江健三郎氏による、本書の底本(講談社現代新書版、1973年)への推薦の言葉より
〈この平易な小冊子にこめられているのは、先生が生涯深められてきた思想である。「人類は所詮滅びるものかもしれない。しかし、抵抗しながら滅びよう。」という言葉を見つめながら、先生はその抵抗の根本の力を明らかにしてゆかれる。〉
【目次】
1 ヒューマニズムということば
2 ユマニスムの発生
3 宗教改革とユマニスム
4 ラブレーとカルヴァン(一)
5 ラブレーとカルヴァン(二)
6 ユマニスムとカルヴィニスム
7 宗教戦争とモンテーニュ
8 新大陸発見とモンテーニュ
9 現代人とユマニスム

柄谷行人浅田彰全対話
講談社文芸文庫
1985年になされた最初の対談「オリエンタリズムとアジア」で、柄谷行人は「政治と離れた言説などはありえないということを、もう一度強調すべき時期にきて」いると言う。本書では、思想や芸術など多様な話題を次々繰り出しつつ、かならず世界そして日本はいかにあるべきかという問いかけに戻っていく。二人の知識人は縦横無尽に語り合うことを通して、読む者に思考と発言を続けることの重要性を訴えているのである。日本を代表する知識人二人が、自在に語りあった諸問題ーー解決にはほど遠くさらなる混迷に突き進む世界の現在を予見した、奇跡の対話集。
目次
オリエンタリズムとアジア
昭和の終焉に
冷戦の終焉に
「ホンネ」の共同体を超えて
歴史の終焉の終焉
再びマルクスの可能性の中心を問う
あとがき 浅田彰と私(柄谷行人)

珍饌会 露伴の食
講談社文芸文庫
博覧強記の文豪が描く、奇奇妙妙の「食」尽くし。露伴とその周辺の好事家たちをモデルに描く抱腹絶倒の戯曲「珍饌会」、河豚を愛した文人たちの漢詩を読み解く「桃花と河豚」、故事来歴から料理法まで網羅した「鱸」など随筆六篇を収録。稀代の碩学・露伴の「食」をめぐる蘊蓄と諧謔を味わう名篇集。南條竹則・編。
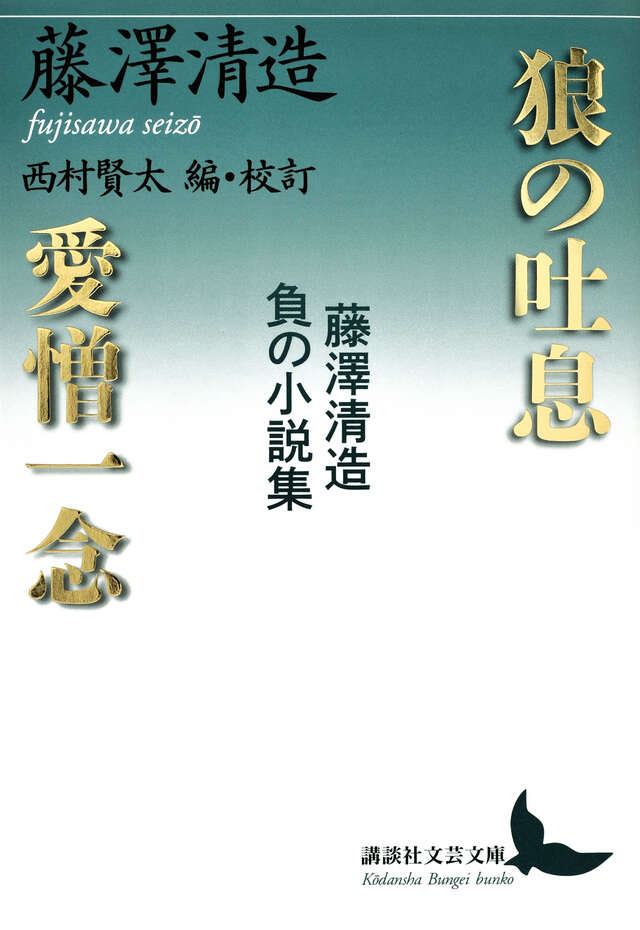
狼の吐息/愛憎一念 藤澤清造 負の小説集
講談社文芸文庫
蘇える木枯しの文士
“どうで死ぬ身の一踊り”を実践し、
自ら破滅へと向かった大正・昭和初期の私小説家。
その生涯を賭した、不屈の「負」の結晶。
藤澤清造生誕一三〇周年
貧苦と怨嗟を戯作精神で彩った作品群から歿後弟子・西村賢太が精選し、校訂を施す。
新発見原稿を併せ、不屈を貫いた私小説家の“負”の意地の真髄を照射する。
芝公園で狂凍死するまでの、藤澤清造の創作活動は十年に及んだ。
貧苦と怨嗟を戯作精神で彩ったその作品群から歿後弟子・西村賢太が十九篇を精選、校訂を施す。
不遇作家の意地と矜恃のあわいの諦観を描く「狼の吐息」、内妻への暴力に至る過程が遣る瀬ない「愛憎一念」、新発見原稿「乳首を見る」、関東大震災直後の惨状のルポルタージュ等、不屈を貫いた私小説作家の“負”の真髄を照射する。
西村賢太
登場時すでにして古めかしいと評され、冷笑視されてもいたその文体だが、当然、小説が日記やレポートの類と違うのは、それが読者に読ませるものでなければならない点にある。その上では何んと云っても文体がモノを言ってくるわけだが、清造の場合、自らの古風、かつ独自の文体をより強固に支えるに戯作者の精神を持ってきた。そこが良くも悪くも、凡百の自然主義作品とは大きく異なるところである。
「解説」より

子午線を求めて
講談社文芸文庫
フランスで長らく経度の基準とされてきた、パリ子午線。敬愛する詩人ジャック・レダの文章に導かれて、その痕跡をたどりながら、「私」は街をさまよい歩く。パリの郊外が抱え込む闇を抉り出したセリーヌやロマン・ノワールの書き手たちへの眼差し。断章で鮮やかに綴るエルヴェ・ギベールの肖像……。著者の作家としての原点を映し出す、初期傑作散文集。

異邦の香り ネルヴァル『東方紀行』論
講談社文芸文庫
ウィーン、カイロ、シリアを経てコンスタンチノープルへ。『東方紀行』は異国への憧憬と幻想に彩られながら、オリエンタリズムの批判者サイードにさえ愛された、遊歩者(フラヌール)ネルヴァルの面目躍如たる旅行記であった。四十代で縊死、時を経てプルースト、ブルトンらにより再評価された十九世紀ロマン派詩人ネルヴァルの魅力をみずみずしい筆致で描く傑作評論。読売文学賞(研究・翻訳賞)受賞作。
巻末に、東京大学文学部での最終講義「ネルヴァルと夢の書物」を収録。

モナリザの微笑 ハクスレー傑作選
講談社文芸文庫
機械文明の発達により便利になった世界がかえって人間性の喪失につながるという、まさに21世紀の世界が直面する問題を描いたディストピア小説『すばらしい新世界』のハクスレーによる、傑作短篇集。モームやヘンリー・ジェイムズの名訳者として知られる行方昭夫氏が、作風の異なる5つの短篇を精選し、訳し下ろしました。科学、数学から美術、音楽、哲学にいたるまで、博学で知られるハクスレーの面目躍如たる作品集です。収録作:「モナリザの微笑」「天才児」「小さなメキシコ帽」「半休日」「チョードロン」