講談社文芸文庫作品一覧

乞食王子
講談社文芸文庫
“その積りでいれば”世の中随分おもしろく眺められる“結構な御身分”のその時々を自由自在に生きる“乞食王子”。ロンドン、パリ、上海、カルカッタ、世界各地を歩き、古今東西の文明・文化の何たるかを知り尽した著者の、感性豊かな視線とウイットに溢れた独創の世界。「銀座界隈」「東京」「人の親切」「宮廷」「文士」「海坊主」等々、虚実入り混った79篇収録の限りなく優雅なエッセイ集。

雉子日記
講談社文芸文庫
『風たちぬ』の最終章「死のかげの谷」完結までの数年、軽井沢滞在等の中で祈り祈りに綴られたエッセイ集。浅間の高原の四季への想い。読書の日々。生涯にわたって最も深く影響をうけたリルケをめぐる「リルケ雑記」。療養しつつ清冽なリリシズム漂う作品を残した堀辰雄の死に立ち向う健康的で強靱な精神の持続が生んだ名品。
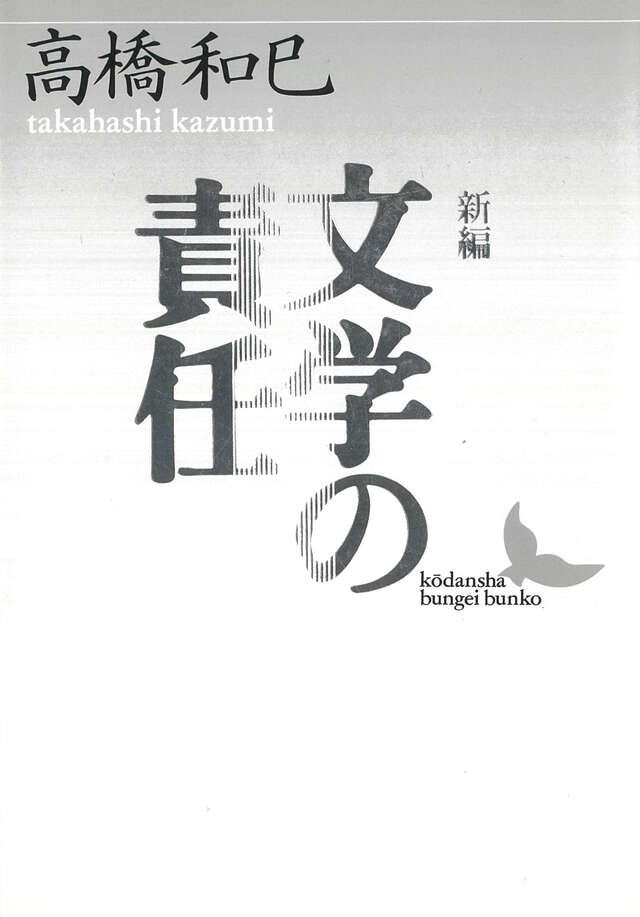
新編 文学の責任
講談社文芸文庫
碩学・吉川幸次郎の中国文学の高弟であり、戦後日本文学の思想を根源的に、果敢に継承しようとして早逝した著者。『悲の器』で圧倒的な出発を果たし、『邪宗門』『散華』等々、70年代までの現代日本を代表する文学・思想者、高橋和巳の文壇的出発前を含めた初期の思想を凝集した「志」エッセイ。
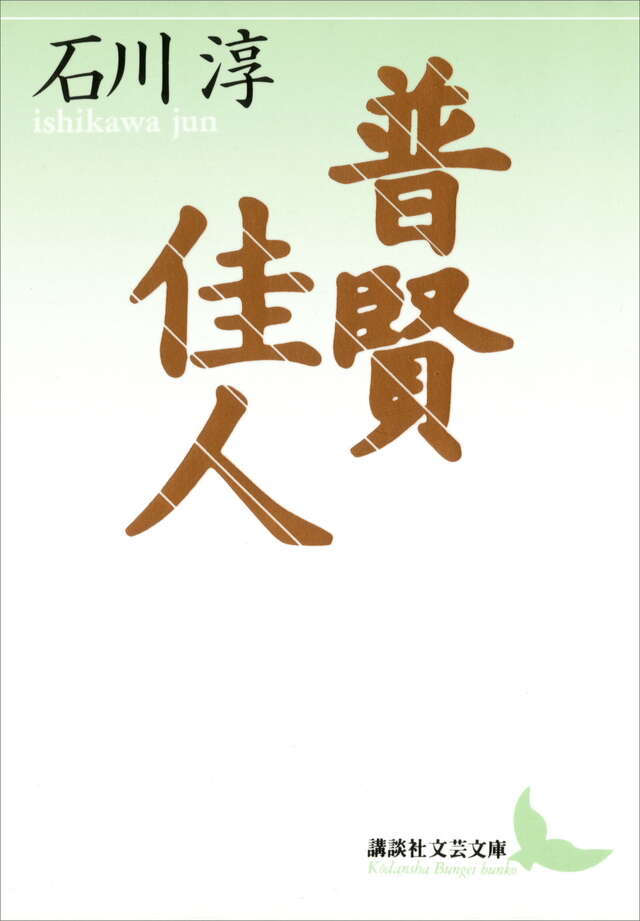
普賢・佳人
講談社文芸文庫
中世フランスの女流詩人の伝記を書く主人公〈わたし〉。友人庵文蔵、非合法の運動をする文蔵の妹ユカリ――日常の様々な事件に捲込まれ、その只中に身を置く〈わたし〉の現実を、饒舌自在に描く芥川賞受賞作「普賢」のほか処女作「佳人」、「貧窮問答」など。和漢洋の比類ない学識と絶妙の文体、鋭い批評眼で知られた石川淳の文学原理を鮮明に表出する初期作品群4篇。

うず潮・盲目の詩
講談社文芸文庫
《私はいったい何を怖れているのだろうか……月の光を溶かして、うず潮は昏く流れている。》幼い子を抱え料理屋で働く戦争未亡人の高浜千代子は、ジャワから復員して妻をなくした男杉本晃吉を知って荒涼とした敗戦直後の東京で3人共に生きようとする。1947(昭和22)年、戦後初の新聞小説として執筆、戦争で傷ついた庶民を温かく描いた家庭小説の名篇。

森と湖のまつり
講談社文芸文庫
北海道の広大な自然を舞台に滅びゆく民族の苦悩と解放を主題に展開する一大ロマン。アイヌの風俗を画く画家佐伯雪子、アイヌ統一委員会会長農学者池博士、その弟子風森一太郎、キリスト者の姉ミツ、カバフト軒マダム鶴子など多彩な登場人物を配し、委員会と反対派の抗争の中で混沌とした人々の生々しい美醜を、周密な取材と透徹した視点で鮮烈に描く長篇大作。

榛の畦みち・海辺の熔岩
講談社文芸文庫
世にこれほど美しい友情の文章を書き得たものがいたか!美校首席入学の後、世に出る事なく逝った若き日の友人へのこの上なく深く優しく暖かいレクイエム「榛の畦みち」。風景画を志し、師友を愛し、清貧を生きた反骨の芸術家魂。77歳で失明、なお精進怠らず、“へなぶり”や随筆を書く101歳までの晩年。エッセイスト・クラブ賞受賞の表題作他。

日本文壇史3 悩める若人の群
講談社文芸文庫
明治24年「早稲田文学」創刊。「しがらみ草紙」と2誌を舞台に展開した鴎外・逍遙の没理想論争は、文学青年達に新鮮な感動を与えた。露伴『五重塔』発表。「文学界」創刊。「帝国文学」創刊、一葉『たけくらべ』等発表の28年まで。新しい文学機運の中で透谷、藤村、子規、漱石、独歩、蘆花ら、20代の若き彼らは、文学、恋に苦悩しつつ、自らの人生を生き抜いていた。青春の香り溢れる明治20年代文壇群像。
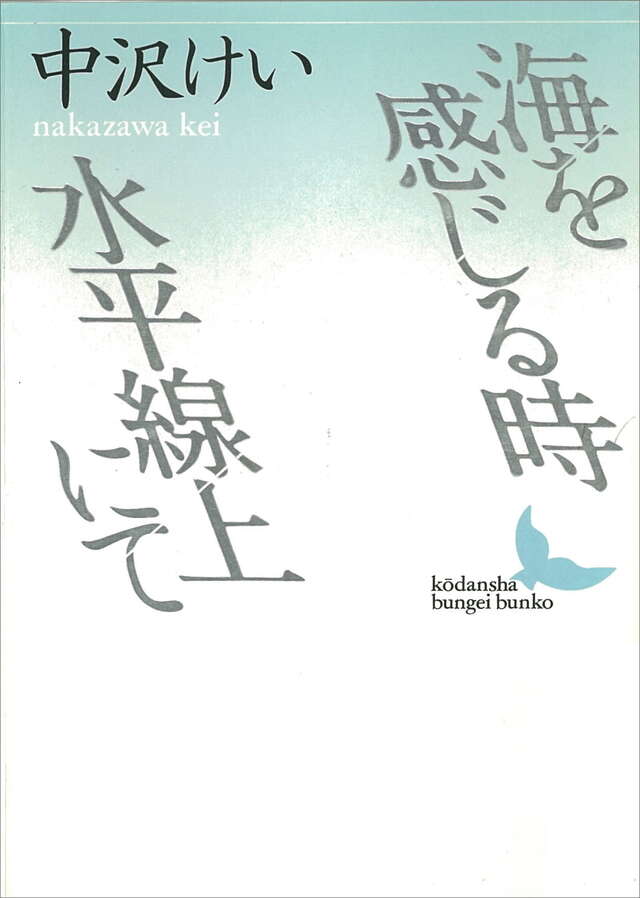
海を感じる時・水平線上にて
講談社文芸文庫
《海は暗く深い女たちの血にみちている。私は身体の一部として海を感じている。……》年上の男子生徒とのセックスの体験を鋭利な感覚で捉えて、身体の芯が震える程の鮮烈な感銘を与えた秀作。作家の出発を告げた群像新人賞受賞「海を感じる時」と、大学生となった、その後の性意識と体験を描き深めた野間文芸新人賞「水平線上にて」。力作2篇収録。

語源をさぐる
講談社文芸文庫
〈ごまかす〉は文化文政江戸の胡麻菓子。国語音韻史、中世、近世の国語研究に多大な業績を残した『広辞苑』の編者・新村出の語源探索セット。「天と地」「日と月」「しぐれ」「風の名」「霞と霧」「鶴」「松竹梅」「毒だみ」「香と臭」「本の語源」「家庭という語」「馬鹿考」「胡麻菓子」など、多角的論証と平易な文章で説く興味尽きない語源談、48歳。

美の世界・愛の世界
講談社文芸文庫
深く傾倒した与謝野晶子の短歌をはじめとして、蘇テイの「汾上驚秋」からベルレーヌの「落葉」へと想いを馳せ、白秋、朔太郎、芭蕉、蕪村、白居易、ラディゲ等々、愛誦の古今東西の詩歌を心に浮かぶままとりあげ評釈する。平易、融通無礙に詩歌のエッセンスを説き明かし、著者の美意識と稟質の漲る卓越した“詩歌入門書”。表題作に「童心の世界」を加えた最晩年の円熟の3部作。
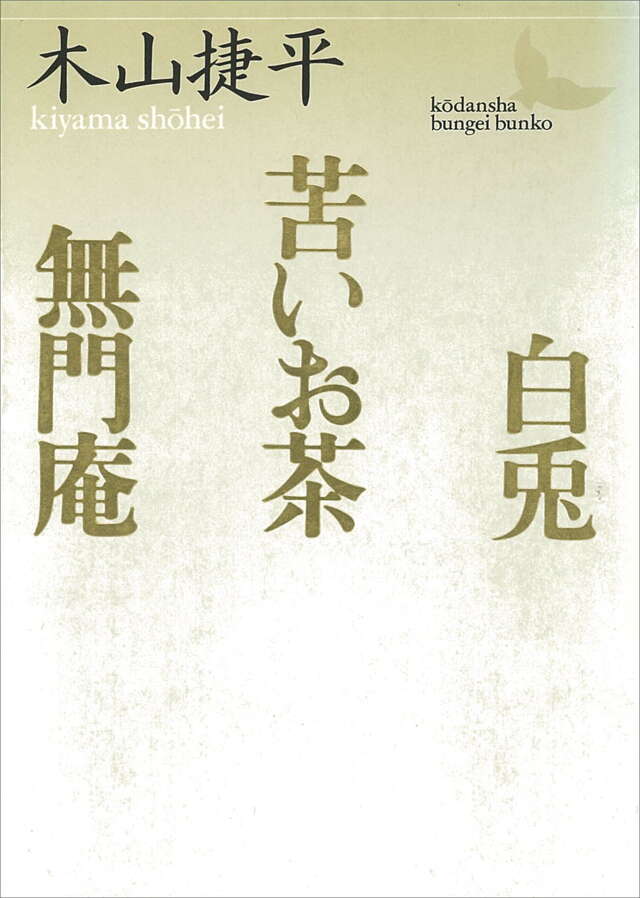
白兎・苦いお茶・無門庵
講談社文芸文庫
敵の戦車に人間爆弾となって廃兵が飛込む訓練を繰返す。そんな理不尽きわまる敗けいくさ。夫たちが徴兵され、著者がいみじくも名付けた半後家たちとの置き去りにされた生活。“一年が百年にも感じられる”流謫の生活の中でも、市井に生き続ける“在野”の精神を飄々たる詩魂で支え、正に“人生の歌”を歌った木山捷平、中期・晩年の代表的短篇。

遠くにありて
講談社文芸文庫
上田敏の薫陶を受け、詩的資質を認められ森鴎外・永井荷風の文章に親しんだ仏文学者山内義雄。ジッド『狭き門』の名訳、マルタン=デュ=ガール『チボー家の人々』の完訳、ポール=クローデルとの親交、日仏文化交流に多大な功績を残し、芳醇流麗な筆致の翻訳で知られた著者の唯一の随想集。「まぼろしの京都」「『ふらんす物語』の思い出」「二人の文豪」ほか54篇。

ポオ詩集・サロメ
講談社文芸文庫
“あたかも衆俗の安易な理解を拒むかのように”、また、“佶屈を以つて武装し、晦渋を以て身を護る”と評された、自己の美学を貫ぬき通した詩人にして、碩学、秀抜な批評家・日夏耿之介のE・ポオの訳詩と、O・ワイルドの詩劇の名訳。前人未踏の独創的な視覚と聴覚の綜合美の世界。

旅人かへらず
講談社文芸文庫
1933(昭和8)年、英国留学後に上梓、幾多の詩人達に衝撃的影響を与えた日本語第1詩集『Ambarvalia』(『アムバルワリア』)。「旅人は待てよ/このかすかな泉に/……」ではじまる東洋的幽玄漂う長篇詩、1947年刊『旅人かへらず』。対照的な2冊に時に耀き時に沈潜する西脇順三郎の奔放自在、華麗な詩想とことばの生誕の源泉を見る。日本の現代詩最高の偉業2作を完全収録の文庫版。

日本文壇史2 新文学の創始者たち
講談社文芸文庫
明治19年1月、21歳の二葉亭四迷は、不審紙を付けた『小説神髄』を持ち、本郷真砂町に未知の坪内逍遙を訪ねた。その翌年、幼な友達だった二葉亭と山田美妙は奇しくも、時を同じくして日本最初の口語体小説を発表した。紅葉、忍月、露伴、透谷、鴎外等による画期的文学の創造。漱石と子規の出会い。一葉の半井桃水への入門。独歩の受洗。新文学への熱気をはらむ若き群像と文壇人間模様。
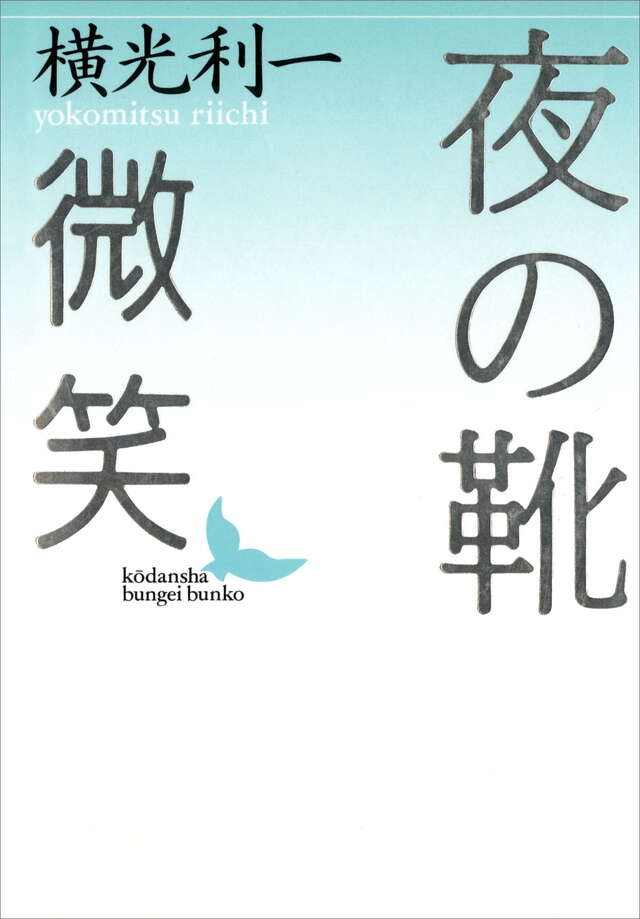
夜の靴・微笑
講談社文芸文庫
戦時下、畢生の大作『旅愁』を書いて東北地方の僻村に疎開していた横光利一は、そこで日本の敗戦を知る。国敗れた山河を叙し、身辺を語り、困難な己れの精神の再生を祈念しつつ綴った日記体長篇小説『夜の靴』。数学の天才の一青年に静かな共感をよせる『微笑』。時代と誠実に格闘しつつ逝った横光利一最晩年の2篇。

わが文学半生記
講談社文芸文庫
大学生の時、初めて接した師・夏目漱石。その後の日々と葬儀までを、瑞々しく捉えた「夏目漱石とその弟子たち」「漱石山房夜話」「夏目漱石の死」「漱石死後の漱石山房」。上野・清凌亭での芥川と佐多稲子、谷崎潤一郎らとの才気溢れる交遊を通して語られる「その頃の芥川龍之介」。菊池寛、久米正雄、宇野浩二、佐藤春夫等の作家群像と、その時代の断面を鮮やかに切り取った、自伝的大正文壇回想。

終りし道の標べに
講談社文芸文庫
幻の処女作。ここに新しいリアリティーがあった。異民族の中で培った確固とした他者。埴谷雄高は何かの予感を禁じ得ず雑誌「個性」に持ち込んだ。青年公房の生身の思索は17年後書き換えられ、もはや読むことはできなくなった処女作。読者の期待に応え甦った処女長篇小説真善美出版。

大川の水・追憶・本所両国
講談社文芸文庫
昭和2年7月24日、芥川龍之介自殺。「ぼんやりした不安」を抱え、歪みの只中に向って移行する激動の〈時〉をうけとめた死は、大正文学の終焉を印した。初期「大川の水」「松江印象記」、遺稿「機関車を見ながら」の他「漱石山房の冬」「追憶」「本所両国」「江口渙氏のこと」「学校友だち」「身のまわり」など、知の作家芥川龍之介の内奥の柔らかな心を抽出したエッセイ59篇。