講談社文芸文庫作品一覧

大川の水・追憶・本所両国
講談社文芸文庫
昭和2年7月24日、芥川龍之介自殺。「ぼんやりした不安」を抱え、歪みの只中に向って移行する激動の〈時〉をうけとめた死は、大正文学の終焉を印した。初期「大川の水」「松江印象記」、遺稿「機関車を見ながら」の他「漱石山房の冬」「追憶」「本所両国」「江口渙氏のこと」「学校友だち」「身のまわり」など、知の作家芥川龍之介の内奥の柔らかな心を抽出したエッセイ59篇。

新編 沓掛筆記
講談社文芸文庫
戦前・戦中・戦後の日本を最も誠実に生き抜いた文学者・中野重治の“遺書”とも評される晩年のエッセイ。雑誌「文芸」に連載され、単行本となった『沓掛筆記』を軸に、言い遺しておきたいこと、思いつづけてきたこと、友人達のこと、長、短いりまじった随筆を新しく編集したエッセイ集。
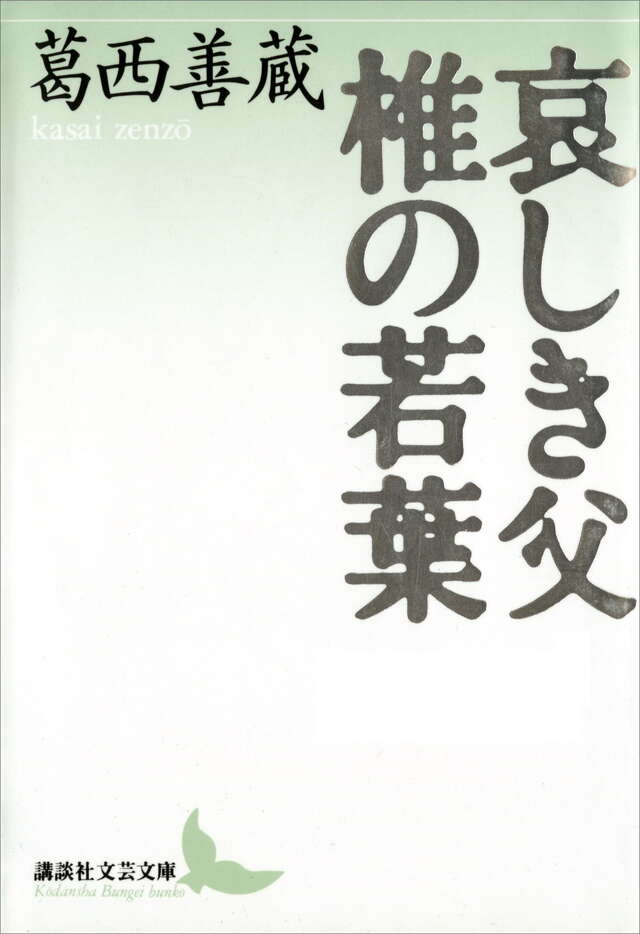
哀しき父 椎の若葉
講談社文芸文庫
「生活の破産、人間の破産、そこから僕の芸術生活が始まる」と記した葛西善蔵は、大正末期から昭和初年へかけての純文学の象徴であった。文学の為にはすべてを犠牲にする特異無類の生活態度で、哀愁と飄逸を漂わせた凄絶苛烈な作品を描いた。処女作「哀しき父」、出世作「子をつれて」、絶筆「忌明」のほか「馬糞石」「蠢く者」「湖畔手記」など代表作15篇。

「最後の小説」
講談社文芸文庫
人は死に向って年をとる、というしみじみした自己認識をもつに至った小説家が、いま自分はこのように生きている、という真撃な現場報告を提示して、1冊の濃密な本とした。「国外で日本人作家たること」「僕自身のなかの死」等、全5章の評論に、戯曲・シナリオ草稿「革命女性」200枚。長篇3部作「燃えあがる緑の木」を構想しつつある作家の“現在”の心の内奥と作家的パフォーマンスの全体像。

日本文壇史1 開化期の人々
講談社文芸文庫
同時代の文士や思想家、政治家の行動、「そのつながりや関係や影響を明らかにすることに全力をつくした」という菊地寛賞受賞の伊藤整畢生の明治文壇史・全18巻の“1”。仮名垣魯文、福沢諭吉、鴎外、柳北、新島襄、犬養毅ら、各界のジャーナリズム動かした人々。坪内逍遙の出現と、まだ自己の仕事や運命も知らずに行き合う紅葉、漱石等々を厖大な資料を渉猟しつつ生き生きと描写する人間物語!

辰雄・朔太郎・犀星
講談社文芸文庫
作家としての福永武彦が、現代にふさわしい小説を書こうと意図したとき、たくまずその脳裏に浮かんだ先達ともいうべき作家たち――彼らへの「感謝の現れ」、オマージュとして捧げたのが『意中の文士たち』である。本書はその下巻であり、福永が最も親炙し敬愛した堀辰雄、その魂の内面の表現に深く共感を寄せた萩原朔太郎・室生犀星についての、こよなく優れたエッセイを収めた。
作家としての福永武彦が、現代にふさわしい小説を書こうと意図したとき、たくまずその脳裏に浮かんだ先達ともいうべき作家たち──彼らへの「感謝の現れ」、オマージュとして捧げたのが「意中の文人たち」である。本書にはその下巻──福永が最も親炙し敬愛した堀辰雄、その魂の内面の表現に深く共感を寄せた萩原朔太郎・室生犀星についてのこよなく優れたエッセイを収めた。

石蕗の花網野菊さんと私
講談社文芸文庫
祖父広津柳浪、父和郎、そして桃子。1人きりの兄が病没し、嫁がず、孕まず、“家”が消滅する宿命を担う湘南での日々。名作『一期一会』を残し、孤独な老齢を靭く生きる網野菊へのひとかたならぬ親愛と深い交響の中で生まれる静謐な感動。文学者3代の末、広津桃子の女流文学賞受賞の名品。

古典の細道
講談社文芸文庫
記紀の記述の相違から倭建命に深くかかわる精神、能「大原御幸」の演者の一瞬の間に隠れた真実を感得する魂。芸術・文学に造詣深い著者が、誘われるごとく、業平、小町、世阿弥、蝉丸、継体天皇、惟喬親王等、12人の縁りの地を訪ね歩き、正史に載らぬもう一つの姿を鮮やかに描き出す。伝承・伝説を語り継いだ名もない人々“語り部”、その心に、共鳴し、慈しむ、白洲正子の独創的古典へのエッセイ。

ゆれる葦
講談社文芸文庫
6歳で実母と生き別れ、16歳で女子大に仮入学する旅立ちまでの精神の遍歴をたどった自伝的長篇。終生志賀直哉を文学の師と仰ぎ精進した女流作家が、3代にわたる一族と、自己の人間形成を冷静に見据える。他に短篇「教母」「イワーノワさん」等6作を収録し、網野菊の感銘深い文学世界の精髄を凝縮する。

ヨオロッパの人間
講談社文芸文庫
ヨオロッパ世界はその精神の故郷が地中海にあってその文明の円熟の頂点は18世紀に極まるとみる著者は、人間が人間であることの限界を認め、その人間らしさを重視しつつ、エリザベス1世、ヴォルテエル等の魅力からランボオ、ヴァレリイ他の鮮かな人間像へと説き及ぶ。18世紀の優雅と哀愁を回顧し、諦念から出発した人生のそれ故の喜びと楽しみを、芳純な文体で語る歴史随筆。
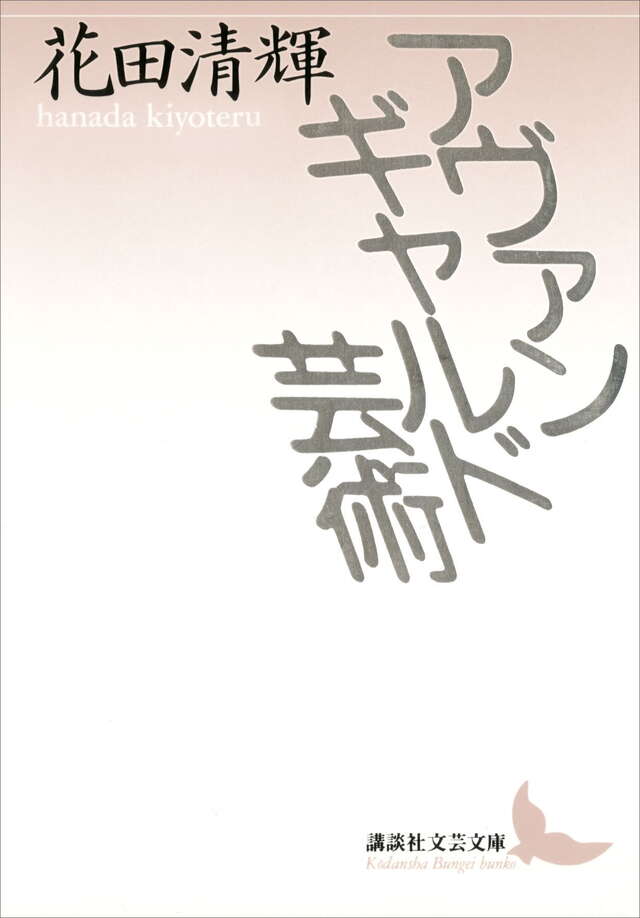
アヴァンギャルド芸術
講談社文芸文庫
常に時代を“転形期”として捉え、前近代的なもの、B級の芸術を否定的媒介にして“モダニズム”を超える思考の提出。世界の秀れた前衛の思想をラジカルに踏んだ強力な視座、常にダイナミックな“変革”を志す世界的発信性の獲得。思想の追尋者・花田清輝の代表作。

河岸の古本屋
講談社文芸文庫
古本屋のない町は文化の低い町とみる著者が、パリのセーヌ河岸の古本屋(ブキニスト)の盛衰を心情込めて語る『河岸の古本屋』。「誤訳の楽しみ」など12章に綴る魅力溢れる読書論「本とつき合う法」。日本人の人生観、パリでの青春の日の見聞、日本の文壇人の想い出、大学教育の危機等。血肉を通してフランスのモラリストを深く研究した著者の多彩な文学活動を示す、滋味豊かなエッセイ集。

マルドロオルの歌
講談社文芸文庫
「筆名ロオトレアモン伯爵、本名イジドル・デュカス。1846年に生れ、1870年に死す。」これ以外、その生涯が全く不明の詩人が残した「歌」は、奇跡的に今世紀に伝わり、現代文学の新たな脱皮、革命の起爆装置として日々作用しつづけている。『マルドロオルの歌』の初訳者として、戦中・戦後の熱烈な読者の詩魂を震盪せしめた青柳瑞穂の名訳を収める。

魯迅
講談社文芸文庫
“絶望の虚妄なることは正に希望と相同じい”と魯迅を引用し「絶望も虚妄ならば、人は何をすればよいか。……何者にも頼らず、何者も自己の支えとしないことによって、すべてを我がものにしなければならぬ。」と魯迅を追尋しつつ論及、昭和18年遺書を書く想いで脱稿。そして応召。僚友武田泰淳の『司馬遷』とともに、戦時下での代表的名著。

あにいもうと・詩人の別れ
講談社文芸文庫
長い沈潜の後、自らの抒情を封じ、野性の愛を描いて見事に第2の昴揚期を開いた「あにいもうと」(文芸懇話会賞)。深い愛で妻の発病と命の揺らぎを見つめた「死のいざない」。親しい詩人達の友誼と理非を超えたその死を語る「信濃」「詩人の別れ」ほか、「つくしこいしの歌」「庭」「虫寺抄」等。逞しい作家魂とひたむきに追う犀星の美意識が展開する多彩な中期作品群より8篇を収録。
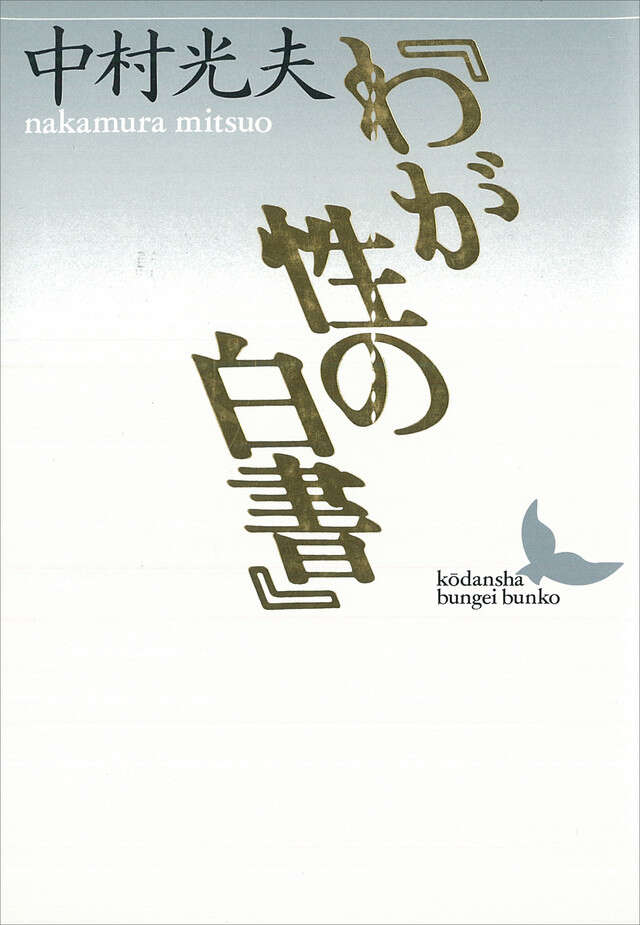
『わが性の白書』
講談社文芸文庫
癌で死んだ或る作家の遺書『わが性の白書』の出版をめぐる、関係者たちの思惑とその「真相」。逆手にとりつつ、文壇・マスコミに登場する女流作家の放胆な軌跡。現代という時代の「世界の空虚さ」の真只中で演じられる、真摯に生きようとする者たちの喜劇的なドラマ。文芸評論家・中村光夫が、初めて50代で執筆発表した、痛撃な批評と苦いユーモアの漂う、意欲的長篇小説。現代風俗を取り込んで描く、果敢な挑戦作。

新編 琅 記
講談社文芸文庫
『広辞苑』の編者新村出博士の名著と名高い語源探索の書『琅かん記(ろうかんき)』全61編の随筆から、令孫新村徹氏が30余編を選んで「新編」とした。「更紗」「キセル」の語源を尋ねて南蛮の情緒にひたり、「亜刺比亜馬と波斯馬」を語って「魏志」「後漢書」の倭国の記述に始まり、秀吉を経て将軍吉宗の馬匹改良の話に達す。興趣尽きぬ、琅かんの玉にも比すべき随筆集。

戦艦大和ノ最期
講談社文芸文庫
昭和20年3月29日、世界最大の不沈戦艦と誇った「大和」は、必敗の作戦へと呉軍港を出港した。吉田満は前年東大法科を繰り上げ卒業、海軍少尉、副電測士として「大和」に乗り組んでいた。「徳之島ノ北西洋上、「大和」轟沈シテ巨体四裂ス 今ナオ埋没スル三千の骸(ムクロ) 彼ラ終焉ノ胸中果シテ如何」戦後半世紀、いよいよ光芒を放つ名作の「決定稿」。
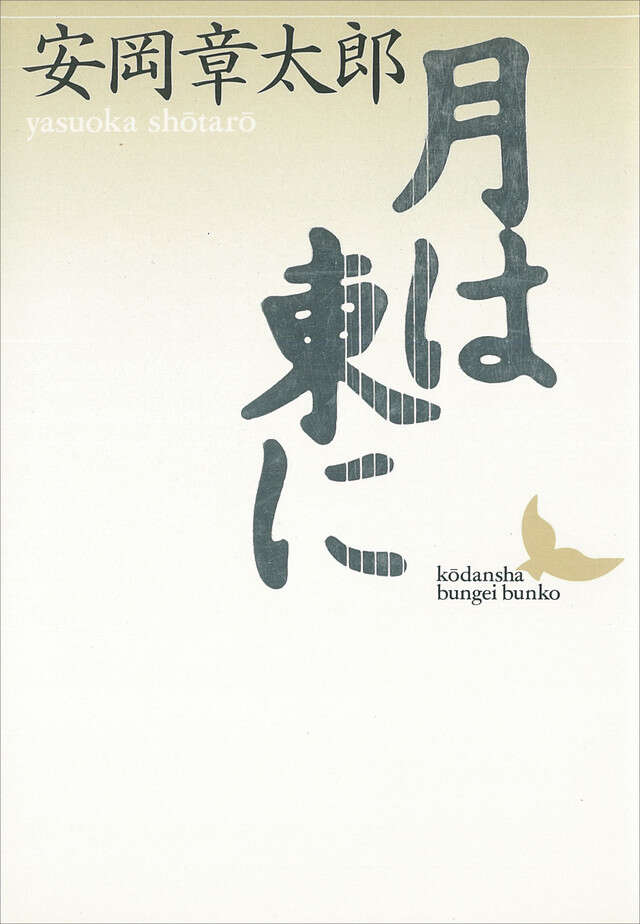
月は東に
講談社文芸文庫
起きてしまった知人の配偶者との「関係」の事実を、男は謝罪し弁明するほどに、ますます窮地に陥ってゆく。露呈する主人公の心の「やましさ」を、作家の眼が凝視する。救いを願う個我の微妙な感情と心理を描いた、意欲的長篇。夏目漱石、志賀直哉らと日本の近代小説が探求し続けてきた、人間の「倫理とエゴ」の重く切実な主題を共有する、『幕が下りてから』に続く著者中期の代表作。

夢の力
講談社文芸文庫
芥川賞受賞前後から『枯木灘』『紀州木の国・根の国物語』の達成、熊野大学の開校、『化粧』を編み、『鳳仙花』へと書き継ぐ3年間の、その時を語る若き中上健次のエネルギーの“渦”。「風景の貌」「緋の花」「戦争を欲する子供たち」「一本の草」「坂口安吾」「野性の青春」「路上のジャズ」「私の文章修業」等。挑戦して止まぬ若者と物語世界を繋ぐ第二文芸エッセイ集。「この『夢の力』は、木箱をこじあけるように開けて欲しい」