講談社文芸文庫作品一覧

鴎外・漱石・龍之介 意中の文士たち(上)
講談社文芸文庫
作家としてのみならず学究・評者として非凡であった福永武彦が、深く心の裡に愛した文学者について自ら記した文章を蒐めて、「意中の文士たち」と名づけたエッセイ集上下巻のうち、上巻を収める。鴎外・漱石・芥川・荷風・谷崎・梶井基次郎・中島敦、そして川端康成への、いわば福永武彦の「感謝の現れ」をオマージュとして捧げた文章である。
作家としてのみならず学究・評者として非凡であった福永武彦が、深く心の裡に愛した文学者に就て自ら記した文章を蒐めて「意中の文士たち」と名づけたエッセイ集上下巻のうち、上巻を収める。鴎外・漱石・芥川・荷風・谷崎・梶井基次郎・中島敦、そして川端康成への、いわば福永武彦の「感謝の現れ」をオマージュとして捧げた文章である。

再婚者・弓浦市
講談社文芸文庫
幼い娘をもつ若い女性と結婚した中年の“私”が、“官能の烈しさ”を秘めた過去の日々を回想する「再婚者」。30年ほど前にお会いし求婚されました、という婦人の突然の来訪に戸惑う小説家の奇妙な体験「弓浦市」。作家の日常の虚実を淡々と語る「夢がつくった小説」。川端康成最晩年に至る心境のにじむ短篇11篇収録。

詩人 金子光晴自伝
講談社文芸文庫
あまりに刺激的な幼少期の環境と気弱な反面の劇しい性格。詩と放埒の青春と人生を決定した最初のヨーロッパ旅行。『鮫』『マレー蘭印紀行』等の芳醇、厖大な詩と散文を生んだ破天荒な2度目のヨーロッパ行き。戦後の“解体”と“出発”。人間尊重と自我意識で、独りファシズムに抗し、常に現代詩に独自の輝きを放った詩魂の遍歴の道筋を平易淡々と自ら語った波瀾・流浪の“人生記録”。
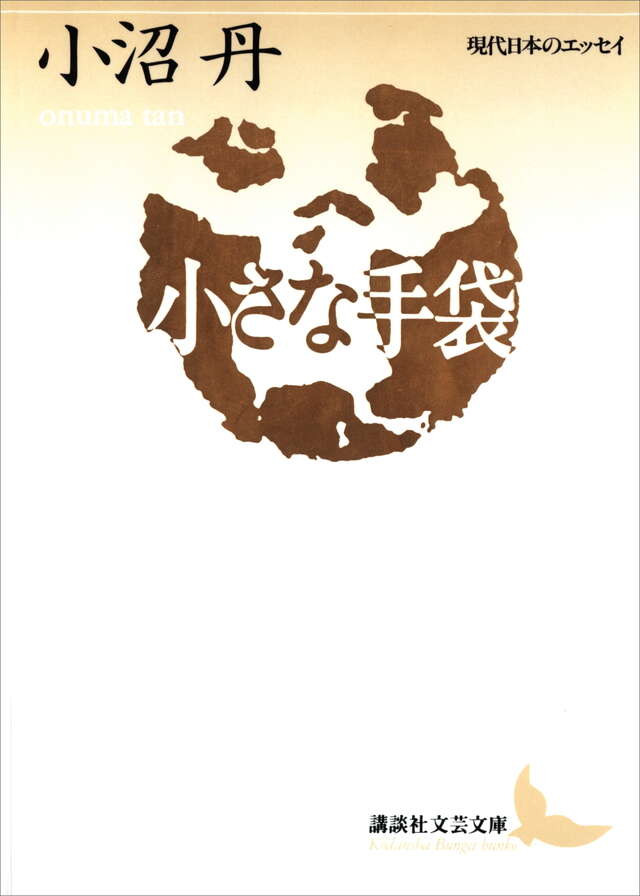
小さな手袋
講談社文芸文庫
日々のささやかな移ろいの中で、眼にした草花、小鳥、樹木、そして井伏鱒二、木山捷平、庄野潤三、西条八十、チェホフら親しんだ先輩、知己たちについてのこの上ない鮮やかな素描。端正、精妙な、香り高い文章で綴られた自然と人をめぐる、比類なく優しい独得のユーモアに満ちた秀抜なエッセイ。

厄除け詩集 特装版
講談社文芸文庫
文庫版初の『厄除け詩集』愛蔵特装版刊行。
“ハナニアラシノタトエモアルゾ 「サヨナラ」ダケガ人生ダ”の名訳で知られる「勧酒」等々、井伏鱒二の詩精神溢れ、永く読み継がれて来た名著の愛蔵決定版。

詩集 野の娘
講談社文芸文庫
大正10年、有島武郎の推薦により刊行された第1詩集『見なれざる人』。改版、再改版を経て、「昔の友」「自負」「黙つている蝉」など7篇を加え再編改題した第2詩集『野の娘』。2詩集の重複と「見なれざる人」所収の短歌3篇を除き、全詩業を収録。簡素・高潔・強靱、深い感情に支えられた品位と雅趣を湛える中川一政の初期詩作61篇。

木乃伊の口紅・破壊する前
講談社文芸文庫
田村俊子は、雑誌「青鞜」創刊号に耽美的な小説を書き官能的な資質と近代的自我の意識の間で揺れ動く、自立しようとする女の自画像を濃密、多彩な作品に残して数奇な遍歴の果て戦時下中国・上海の陋巷で客死した。その先駆的な生涯、作品共に再評価高まる女性作家の表題作と「生血」「女作者」「彼女の生活」「山道」等の代表作9篇を以って編成。新しい田村俊子像の再誕。

ビリチスの歌
講談社文芸文庫
フランス世紀末の象徴派詩人ピエエル・ルイスが、紀元前のギリシャに女流詩人ビリチスを想定して、その愛怨の生を艶麗に歌わしめた長篇詩『ビリチスの歌』。絢爛たる才に恵まれた早熟の詩人ルイスが24歳の時、古代ギリシャ語から翻訳といつわって発表したしたたるような官能と華麗な詩篇の鈴木信太郎による名訳。ファスケル版挿画160点を入れて贈る。

氏神さま・春雨・耳学問
講談社文芸文庫
井伏鱒二の色紙にある“捷平はげん人(げんじん)なり”のように、つつしみ深く、含羞のある、飄々たるユーモアに遊ぶ精神。掘り返された土に陽があたる田園や、父母や妻子の風景を、いわば“魂の故郷”を、都市の文明に決して汚されぬ眼で、こよなく暖かく描き続けた、作家・木山捷平の自由なる詩心。正に“人生を短篇で読む”絶好の初・中期珠玉の飄々短篇集。
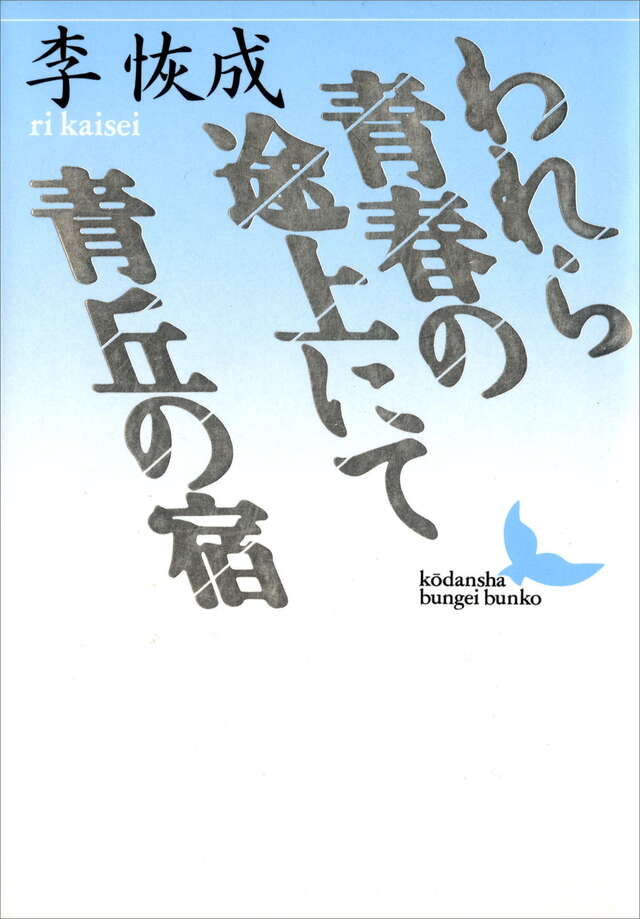
われら青春の途上にて・青丘の宿
講談社文芸文庫
祖国が分断され、まだ多くある差別の中で、若い青春を、本当の生きかたとは何か、を真摯に問いながら生きる群像。李恢成の初期中篇「われら青春の途上にて」「青丘の宿」ほか父親の死を契機に、対立し、相反する2つの組織が手を結ぶ、僅かに残された“黄金風景”を描く「死者の遺したもの」収録。
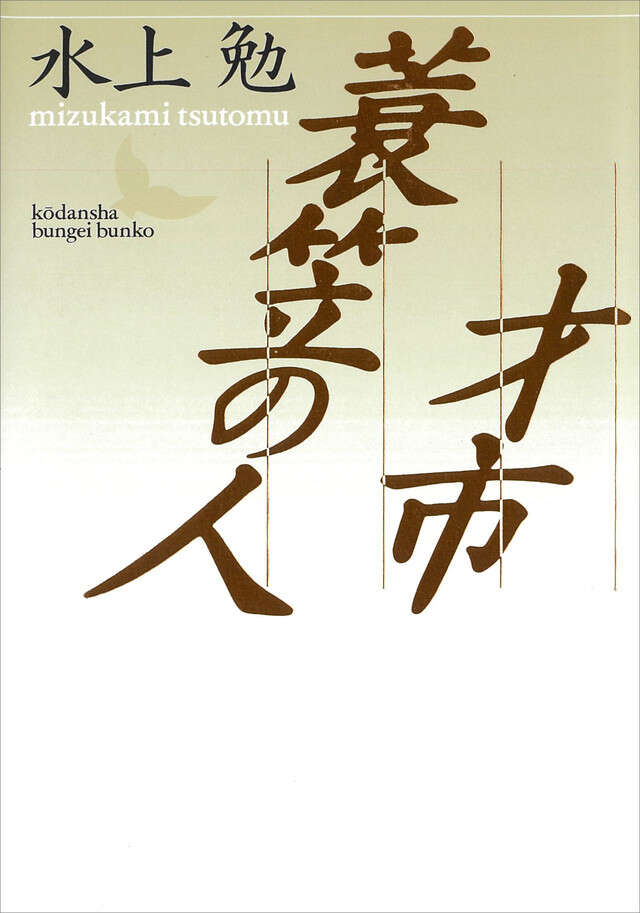
才市・簑笠の人
講談社文芸文庫
念仏に生き、83歳で一生を終えた、下駄職人・浅原才市。下駄作りの際に出るかんな屑に書き残した、1万首に及ぶ信仰の歌……。「わしのこころわ わやわやで/くもともとれの/きりともとれの/かぜともとれの」……無名の庶民の営為に心惹かれて、その謎めく生涯を深く追究した、伝記小説「才市」。一所不住・清貧孤独に徹した良寛の境涯に迫る「蓑笠の人」。信仰を主題の力作2篇。

わが文芸談
講談社文芸文庫
慶応義塾長、経済学者小泉信三は、かつて塾卒業直後、「三田文学」の創刊に際会し、親友水上滝太郎と文科教授永井荷風の講筵に列なった文学好きな青年でもあった。本書は、水上や久保田万太郎と生涯の友であった小泉が、歿前年、慶応大学学生を前に座談風に語った9回の講義をのちに単行本として刊行したもの。鴎外・漱石・露伴・荷風・鏡花らを、愛惜と創見に満ちた語り口で論ずる。

包む
講談社文芸文庫
季節と詩情が常に添う父・露伴の酒、その忘れられぬ興趣をなつかしむ「蜜柑の花まで」。命のもろさ、哀しさをさらりと綴る「鱸」、「紹介状」「包む」「結婚雑談」「歩く」「ち」「花」など、著者の細やかさと勁さが交錯する29篇。「何をお包みいたしましょう」。子供心にも浸みいったゆかしい言葉を思い出しつつ、包みきれない「わが心」を清々しく1冊に包む、珠玉のエッセイ集『包む』。
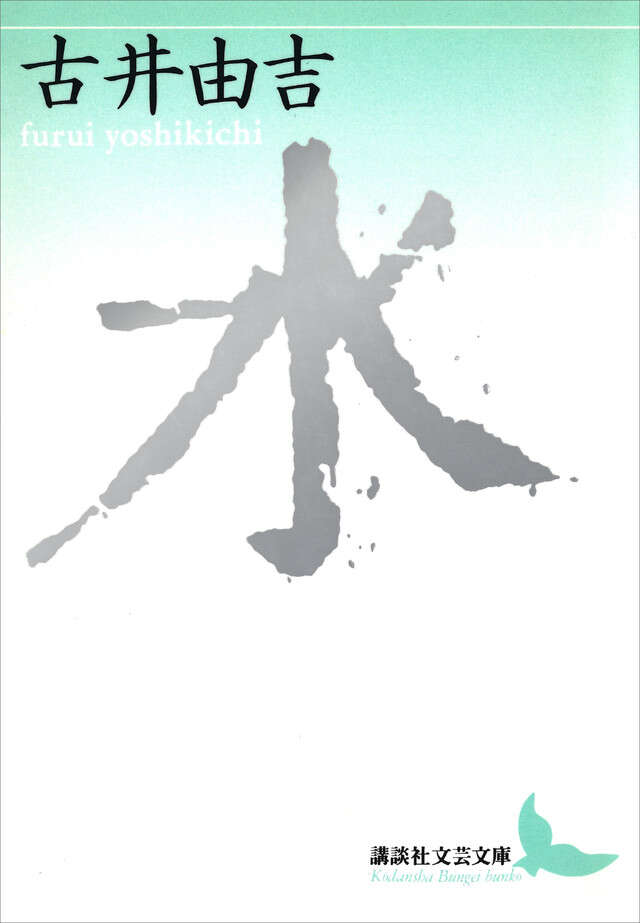
水
講談社文芸文庫
鋭敏細緻な文体で描出した、古井由吉初期作品世界ーー水差しから救いの水を飲んだ直後、息絶えた病床の母(「水」)。「死にたくない、俺ひとり」と、妻の胸で叫ぶ癌を病む夫(「谷」)。生と死のきわどさ、戦き、微かな命の甦りの感覚を、生理と意識の内部に深く分け入っていく鋭敏な文体で描出した、「影」「水」「狐」「衣」「弟」「谷」の6作による、初期連作短篇集。

箱の話・ここだけの話
講談社文芸文庫
混迷を生き貫く思考の発条。花田清輝の秀抜の遺著ーー『乱世今昔談』をどうしても『ここだけの話』と改題希望した著者の遺志を実現し、遺著『箱の話』と合わせ、花田清輝の常にインターナショナルな、発見的思考の持続を顕彰し、混迷する思想・時代状況を生き、貫いて行く根源力を提示。今日さらに重要な意味を加え続ける、花田清輝の貴重な1冊。

日本の紙・紙漉村旅日記 現代日本のエッセイ
講談社文芸文庫
寿岳文章は、その高い志具現のために一生を生きた。強烈な個性をもち、真の美を究極まで追い求める。それを書物という形に実現するために真撃に全身全霊を傾ける。寿岳文章の確かな業績は、しかし、妻しづの夫、文章への愛にみちた理解なしには考えられない。この希有な夫妻の共同作業の代表作『紙漉村旅日記』『向日庵消息』ほか、和紙をめぐるエッセイを収めた。

厄除け詩集
講談社文芸文庫
そこはかとなきおかしみに幽愁を秘めた「なだれ」「つくだ煮の小魚」「歳末閑居」「寒夜母を思ふ」等の初期詩篇。“ハナニアラシノタトヘモアルゾ「サヨナラ」ダケガ人生ダ”の名訳で知られる「勧酒」、「復愁」「静夜思」「田舎春望」等闊達自在、有情に充ちた漢詩訳。深遠な詩魂溢れる「黒い蝶」「蟻地獄(コンコンの唄)」等、魅了してやまぬ井伏鱒二の詩精神。4部構成の『厄除け詩集』。
そこはかとなきおかしみに幽愁を秘めた「なだれ」「つくだ煮の小魚」「歳末閑居」「寒夜母を思ふ」等の初期詩篇。“ハナニアラシノタトヘモアルゾ「サヨナラ」ダケガ人生ダ”の名訳で知られる「勧酒」、「復愁」「静夜思」「田舎春望」等闊達自在、有情に充ちた漢詩訳。深遠な詩魂溢れる「黒い蝶」「蟻地獄(コンコンの唄)」等、魅了してやまぬ井伏鱒二の詩精神。4部構成の初の文庫版『厄除け詩集』。

おまんが紅・接木の台・雪女
講談社文芸文庫
片隅に生きる職人の密かな誇りと覚悟を顕彰する「冬の声」。不作のため娼妓となった女への暖かな眼差し「おまんが紅」。一葉研究史の画期的労作『一葉の日記』の著者和田芳恵の晩年の読売文学賞受賞作「接木の台」、著者の名品中の名品・川端康成賞受賞の短篇「雪女」など代表作14篇を収録。

村の家・おじさんの話・歌のわかれ
講談社文芸文庫
1934年5月、中野重治転向、即日出所。――志を貫き筆を折れという純朴な昔気質の老いた父親と書くことにより“転向”を引受け闘いぬくと自らに誓い課す息子。その対立をとおし転向の内的課程を強く深く追究した「村の家」をはじめ、四高時代の鬱屈した青春を描き、抒情と訣別し変革への道を暗示した三部作。「歌のわかれ」、ほかに「春さきの風」などを収録。

近江山河抄
講談社文芸文庫
逢坂、大津、比良山、竹生島、沖の島、鈴鹿、伊吹等の琵琶湖を中心とした日本文化の発生の地、近江。かつて“えたいの知れぬ魅力”にとりつかれた近江の地を、深々と自らの足で訪ね歩き、古代からの息吹を感得する。王朝の盛衰、世阿弥の能の源流、神仏混こうのパターン等々、日本文化の姿、歴史観、自然観の源泉への想いを飛翔させ、鮮やかに現代から古代への山河を巡る紀行エッセイ。