講談社学術文庫作品一覧

東と西の語る日本の歴史
講談社学術文庫
日本人は同じ言語・人種からなるという単一民族説にとらわれすぎていないか。本書は、日本列島の東と西に生きた人々の生活や文化に見られる差異が歴史にどんな作用を及ぼしてきたかを考察し、考古学をはじめ社会・民俗・文化人類等の諸学に拠りながら、通説化した日本史像を根本から見直した野心的な論考である。魅力的な中世像を提示して日本の歴史学界に新風を吹き込んだ網野史学の代表作の1つ。

戦争論
講談社学術文庫
第1次・第2次大戦から湾岸戦争まで
20世紀の世界戦争は現代思想をどう変えたか
20世紀の戦争は地球を覆う全面戦争と化し、世界を1つの運命共同体とした。冷戦終結後も湾岸戦争に見られたように、戦争は従来の国家の枠を超えて世界化する。一地域の抗争があらゆる国の利害を絡め、いかなる国をもその局外に立たせないのである。クラウゼヴィッツからバタイユ、レヴィナスへと戦争の思考をたどり、臨界に達した西欧近代の〈黙示録後〉の世界を現代史の時間軸に沿って考察する。

新装版 解体新書
講談社学術文庫
日本の遅れた医学を改革しようと、杉田玄白、前野良沢らは西洋の「解剖図」の翻訳に挑戦する。3年半の年月を経て、1774年オランダ語版『ターヘル・アナトミア』は『解体新書』として完成をみた。辞書のない時代、〈門脈〉〈神経〉など現代も使われている用語を造りながらの難事業であった。本書は、医学会のみならず、その後の蘭学の隆盛に貢献し、日本文化が大きく変容する契機となったのである。
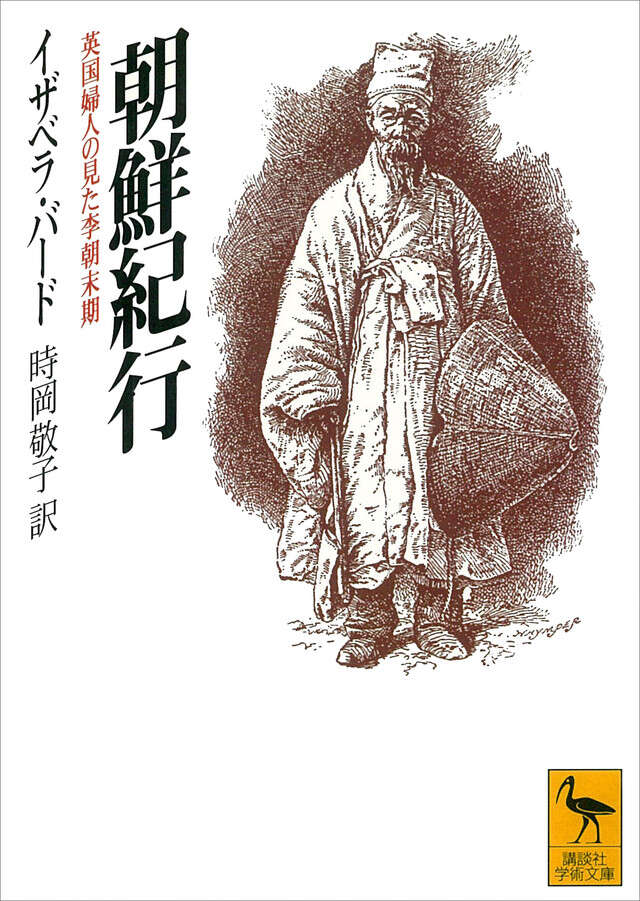
朝鮮紀行
講談社学術文庫
英国人女性旅行家イザベラ・バードが朝鮮を訪れたのは、1894年、62歳の時のことである。以後3年余、バードは4度にわたり朝鮮各地を旅した。折りしも朝鮮内外には、日清戦争、東学党の反乱、閔妃(びんひ)暗殺等の歴史的事件が続発する。国際情勢に翻弄される李朝末期の不穏な政情や、開国間もない朝鮮に色濃く残る伝統的風土・民俗・文化等々、バードの眼に映った朝鮮の素顔を忠実に伝える名紀行。
英人女性旅行家イザベラ・バードが描く19世紀末の朝鮮の素顔。
英国人女性旅行家イザベラ・バードが朝鮮を訪れたのは、1894年、62歳の時のことである。以後3年余、バードは4度にわたり朝鮮各地を旅した。折りしも朝鮮内外には、日清戦争、東学党の反乱、閔妃(びんひ)暗殺等の歴史的事件が続発する。国際情勢に翻弄される李朝末期の不穏な政情や、開国間もない朝鮮に色濃く残る伝統的風土・民俗・文化等々、バードの眼に映った朝鮮の素顔を忠実に伝える名紀行。

マックス・ヴェ-バ-とアジアの近代化
講談社学術文庫
近代化を探究したマックス・ヴェーバーは、宗教改革を経た禁欲的なプロテスタンティズムが、勤勉に働き資本形成に励む企業家精神を養い資本主義を生んだとした。一方、アジアの神秘主義的な儒教や現世逃避的な仏教は、合理化を求める近代化とは相いれず、日本のみが西欧的な封建制をもったため容易に資本主義を受けいれることができたとする。ヴェーバーの理論でアジアの近代化の問題点を指摘する。

日本の狂気誌
講談社学術文庫
日本人にとって狂気とは何か。古来、狂気はどのようにあらわれ、どのように受けとめられてきたか。『日本霊異記』『今昔物語』『百箇条調書』『遠野物語』等々、文学や説話、裁判例、民俗学的資料等に見出される狂気を剔出。古代──中古・中世──近世──近代の各時代の狂気の現象や狂気観、狂気への社会的対応を解き明かし、それらを通時的に積み重ねることにより日本の狂気の特性を探った陰刻の日本精神史。

幻想の都市
講談社学術文庫
ヨーロッパ文化の深層を探るロマンあふれる古都歴訪
フランドルの宝石とも呼ばれる中世都市・ブリュージュやルネサンスの花開いたフィレンツェなど、ヨーロッパの古都を歴訪。重層する文化の集約点であり、象徴である都市の独自の文化を観察して、共時的で多様な西欧の歴史を読む。また古代ローマの遺跡を残すパリから、ブルターニュやアイルランドなどケルトの故郷を訪ねて、ヨーロッパの基層をも考察。西欧文化の実像を描いた旅情豊かな歴史紀行。

ロシア
講談社学術文庫
共産主義的ユートピアの夢は消滅し、21世紀のロシアはどこへ行こうとしているのか。著者は、好感・反感のいずれからにせよ、イデオロギー的に特別視する旧来の一面的なロシア観を斥け、文学・芸術の歴史から、都市と農村、民族・宗教・女性の問題まで、政治を決定してきたロシアの文化的風土を多角的に詳説する。日本にとって益々重要度を増す謎に包まれた隣国ロシアを知るための必携の好著。

エックハルト
講談社学術文庫
「マイスター・エックハルトというのは偉大な名である。……我々はエックハルトを知っている。同時に我々はエックハルトを知らない」と語られる中世ドイツの神秘主義思想の創始者エックハルト。本書は、思想家エックハルトの生涯と思想の形成を第一人者が精魂を込めて叙述。さらに「脱却して自由」「神との合一」等を説いた論述、及び説教集を平易に紹介、広範にわたる彼の思想の本質に迫る意欲作。

玄奘三蔵
講談社学術文庫
天竺にこそ仏法がある!7世紀、唐の都・長安からひとり中央アジアの砂漠を征き、天に至る山巓を越えて聖地インドを目ざした三蔵法師。数々の苦難を乗りこえ、各地の大徳を訪ねて仏教の奥義を極め多くの仏典を携えて帰国した。小説『西遊記』はこの旅行から取材したもの。帰国後は勅許を得て経典翻訳の大事業を成しとげた。本書は、求法の生涯を貫いた名僧玄奘三蔵の最も信頼すべき伝記である。

漂流思考
講談社学術文庫
軟体動物のようにおいしくて仕方がない人、私にとってベルクソンとはそのような存在にほかならない。だが不幸なことに、この軟体動物、ベルクソンのテクストの中では進化の袋小路に入り込んだものとして、いわば出来そこない扱いされている。本書は、この軟体動物が袋小路から出て、思想や芸術の世界をさまよってみせた漂流譚のようなものである──現代の思想・芸術世界への豊かで大胆な思索の試み。

構造主義科学論の冒険
講談社学術文庫
科学とは、客観的に実在する外部世界の真理を究めていく学問であるとされてきた。その理論を唯一の真理として現代科学はとめどなく巨大化し、環境破壊などの破壊的状況をもたらした。本書で著者は、これまで科学的真理とされてきた理論を根底から問い直すために、フッサールの認識論やソシュールの言語論を踏まえ、多様性を重んじる構造主義科学論を提唱する。あるべき科学の未来を説く必読の書。

フィレンツェ名門貴族の処世術
講談社学術文庫
波乱のルネサンスを生きたイタリア貴族の知恵
メディチ家とも親交があり、有能な政治家や大使を輩出した名門に生れたグィッチャルディーニ。28歳でフィレンツェ共和国のスペイン大使になり、共和国崩壊後はメディチ家出身の教皇に仕えて教会領行政官として活躍。動乱のルネサンス・イタリアを常に敵に囲まれながら生き抜き、その体験を子孫に書き残した。冷静な眼で人間の真実を赤裸に描いた本書は、現代に通ずる貴重な処世の書といえる。
君の気がすすまないなにごとかを申し入れられた場合、できうるかぎりひき延ばすように努力するがよい。四六時中見てのとおり、このようなやっかいから逃れさせてくれるような突発事がおこってくるものだ。──(「リコルディ」B76)

現代人の仏教
講談社学術文庫
無相とは、この世の中にあるすべてのものは無常なるものであることを明確に透徹した目で観ることから成り立つ。この現世は永遠であり、絶対だと思うところから出発する有相の価値観に比し、この現世は仮の宿に過ぎないと考える無相の価値観。日本人の精神生活に大きな影響を与えたこの仏教のこころ「無相の価値観」を見直し、いまこそ混迷の時代を生きるわれわれ現代人の指針とすべきだと説く好著。

アルプス登攀記
講談社学術文庫
魔物の棲む山と恐れられ、有史以来人間を拒み続けてきたアルプスの名峰マッターホルンは、1865年、ウィンパー隊によりついに征服された。初めての挑戦から足かけ5年、9度目のトライでつかんだ栄光であった。しかしそれもつかの間、登頂直後の下山中に思わぬ悲劇がメンバーを襲う……。精緻な木版画多数をちりばめ、アルプス登山史を彩る最大のドラマを克明に綴った山岳文学の記念碑的作品。

白旗伝説
講談社学術文庫
紅白戦で知られるように日本では源氏の旗であり、また弔いの旗でもあった白旗。日本人がその降伏の意味を知ったのは、1853年に来航したペリーが、交戦となって降伏したければこれを掲げよと幕府に白旗を送りつけた時であった。日清・日露戦争までは、戦場において白旗の国際ルールを尊重した日本が、太平洋戦争ではそれを無視して野蛮な戦争を敢行した。日本人が忘却した白旗の歴史を語る力作。

庭園の世界史
講談社学術文庫
アルハンブラやヴェルサイユなど、世界の名園を歴史家として著名な筆者が歴訪。庭の創造は、人間の自己表現への欲求の最高の段階であるとし、ヨーロッパだけでなく、イスラム、日本、中国の庭の理想と精神をも明快に考察。バラの咲き乱れるバビロンの架空園を追慕し、トスカーナではメディチ家のロレンツォが構想した幻の大庭園を紙上に再現して、その魅力を語る。地上の楽園=庭の3千年の歴史。
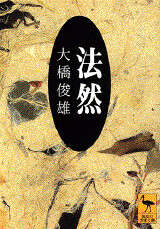
法然
講談社学術文庫
13歳で叡山に登り30年に及ぶ南都北嶺での修行の後、無知な人びとをも救いたいという思いから、難行を捨て阿弥陀仏の本願に救いを求める称名だけを選びとった浄土宗の祖・法然上人。専修念仏により善人、悪人にかかわりなく往生できるとする法然思想の形成過程や浄土宗の成立・発展、鎌倉新興仏教の先駆者ゆえの苦難にみちた80年の生涯を鮮やかに描出。法然研究の第一人者による書き下ろし。

シュリーマン旅行記 清国・日本
講談社学術文庫
トロイア遺跡の発掘で知られるハインリッヒ・シュリーマン。彼はその発掘に先立つ6年前、世界旅行の途中、中国につづいて幕末の日本を訪れている。3ヵ月という短期間の滞在にもかかわらず、江戸を中心とした当時の日本の様子を、なんの偏見にも捉われず、清新かつ客観的に観察した。執拗なまでの探究心と旺盛な情熱で、転換期日本の実像を生き生きと活写したシュリーマンの興味つきない見聞記。
これまで方々の国でいろいろな旅行者にであったが、彼らはみな感激した面持ちで日本について語ってくれた。私はかねてから、この国を訪れたいという思いに身を焦がしていたのである。──(第4章 江戸上陸より)

漱石とあたたかな科学
講談社学術文庫
夏目漱石は当時の文人としては異例な科学好きであった。『三四郎』で野々宮理学士が行う「光線の圧力測定」の実験などには、手作りの装置でこつこつと自然の謎を解明しようとする科学者の純朴な姿がある。現代科学には失われてしまった人肌のぬくもりを持つ1世紀前の科学は、漱石の作品に味わい深さと膨らみを与えた。科学をこよなく愛した文豪を、同時代の科学史的背景と共に描いた異色の漱石論。