講談社現代新書作品一覧
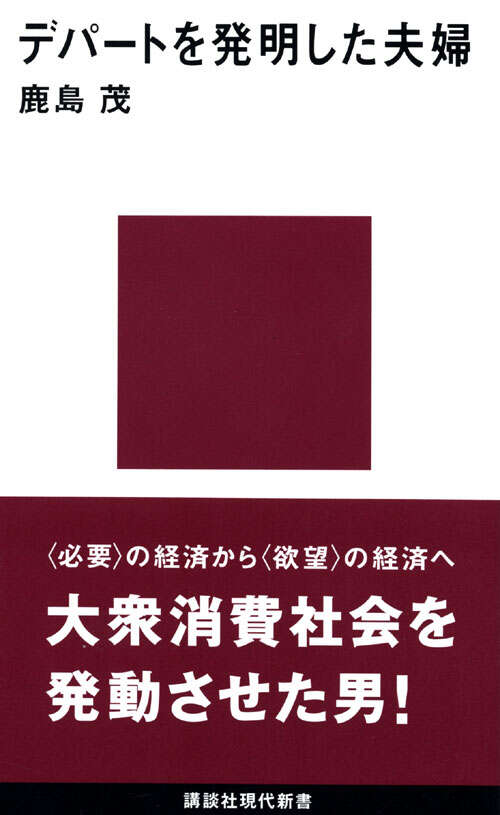
デパ-トを発明した夫婦
講談社現代新書
19世紀半ば、パリに産声をあげた、世界初のデパート〈ボン・マルシェ〉。衝動買いを誘うウィンドウ・ディスプレイ。演奏会、バーゲンなど集客戦術。〈必要〉から〈欲望〉へと、消費のキイワードを一変させた天才商人、ブシコーとその夫人の足跡を追う。
「白」の展覧会――大売出しの始まり――バーゲンの終わった1月下旬のある寒い日、売上げの落ち込みを回避する方法はないものかと思案しながら窓の外の冬景色をぼんやりと見つめていたブシコーは、空から降ってくる粉雪に目をとめた。その瞬間、「白」という言葉が頭にひらめいた。業界用語では、白(ブラン)とは、リンネルや綿布などの白生地を使ったワイシャツ、ブラウス、下着、シーツ、タオル、テーブル・クロスなどのことを指す。ブシコーは、暮れの大売り出しと年頭のバーゲンのあと、春物を売り出すにはまだ寒いこの時期に、季節商品とは関係の薄いこの「白物」を集中的に売り出すことを思いついた。かくして、2月の初め「エクスポジシオン・ド・ブラン」と銘打った「白物」の大売出しが始まった。それは、エクスポジシオン(展覧会)というにふさわしい、ありとあらゆる白生地商品のオンパレードで、店内の多くの売り場がこの商品の展示のために使われ、店内はまさに白一色の銀世界と化した。――本書より

精神病理からみる現代思想
講談社現代新書
離人症における自明性の解体、分裂病が示す自他認識のエポケー、失語症にみられるシニフィアンの交錯など、精神病理を題材に、現象学、フロイトから、ラカン、デリダへと至る、現代哲学にアプローチ。
意味=ロゴスを疑う――フロイトが自我に対して無意識をもち出してきたとき、すでにそれは、「純粋自我」とか「純粋な私」といった近代特有の思想的前提が、いかに疑わしいものであったかを告発しているのだ。同様にわれわれはまた、純粋な「現在」とか純粋な「意味」というものの存在根拠をも、根本から疑ってみる必要があるのではないか。……意味の純化はすでにひとつの暴力にほかならない。それはフーコーが見事にあばいて見せたように、いつか必ず「ヒューマニズム」の名のもとに、そのテリトリーに属さぬものを「病者」として抑圧監禁する、暴力的本性を露わにしてくることだろう。繰り返し言っておこう。われわれはハイデッガーやデリダやラカンのために近代批判や形而上学批判をするのではない。たんにその必要があるからそうするのだ。――本書より

故事成語
講談社現代新書
人生禍福のとらえがたさを示す「塞翁が馬」、滅びゆく美しきものを惜しむ「佳人薄命」、政治的心理の恐ろしさを表わす「狡兎死して良狗烹らる」、恋人同志を結ぶ“赤い糸”の出典「月下氷人」。悠久の中国が生んだ風格ある言葉の森を歩き、人生の底知れぬ奥行を読み味わう。
故事成語の国、中国――中国は文字の国といわれているが、ある面ではそれを、故事成語の国といいかえることができるであろう。三千年の久しきにわたって、中国の人々は絶ゆることなく厖大な文籍の山を築いてきたが、それとともにおびただしい故事成語をも生んできた。旧時代の知識人は、文字通り故事成語の洪水の中を泳ぎまわるような生活を送っていたといっていいが、その伝統は今日でもなお脈々と生きており、知識人の条件の一つに、成語を自在にあやつることができるかどうかをあげてもいいほどである。故事成語こそ、まさに中国語の中の精華であり、またおそらく世界の多くの言語の中でも独特の風格をもった、中国語特有のものといえよう。故事成語はまた、いにしえの人々が悩み、苦しみ、喜び、悲しみ、愛し、争った実際生活の中から生まれたものであり、長い歴史の試煉にたえ、無数の人々の共感を得て生き残った中国人の霊魂ともいうベきものである。――本書より

はじめてのドイツ語
講談社現代新書
ドイツ語は明快な詞。綴りと発音のシステム、名詞・冠詞・形容詞の対応、単語や文章のもつ、堅固で自在な「枠構造」。ほどよい文法秩序に示される、ドイツ語の正性格構造的に理解する。
集合名詞Volkの力――1989年12月のベルリンの壁崩壊のわずか2ヶ月前のことですが、ライプツィッヒで民主化を要求する大規模なデモ行進が起きました。このとき掲げられたスローガンが、Wir sind das Volk.(我々が人民だ)でした。……Wir sind~という表現は、官憲が威嚇的にみずからの所属や権威を明らかにするときに使われるものです。かつて旧東ドイツを車で旅したとき、突然、何人かの警官に取り囲まれて、Wir sind die Volkspolizei.「人民警察の者だが」という言葉を突きつけられたことがあります。単に運転免許証の提示を求められたにすぎないのですが、これはこれで、相当に恐ろしい体験でした。民主化要求デモのWir sind dos Volk.は、その言い方を逆手にとったものです。それだけに、この表現には想像以上の迫力があったのです。――本書より
ハンガリー狂騒曲
講談社現代新書
改革に揺れるブダペストからの現場レポ-ト社会主義体制崩壊という歴史的転換を,ハンガリ-はどう受けとめたか? 自由化・民主化の進むブダペストで2年間過ごした女性の,生活に密着したドキュメント.
ヴァルタ-・ベンヤミン
講談社現代新書
越境する思想家の思考運動の核にある物は?「文の人」ベンヤミンが読みとろうとする「みえないもの」としての表現の根源.“亀裂”“不連続点”を手がかりに目覚めを待つ真理内容に迫る彼の思考の跡を追う

毛沢東と周恩来
講談社現代新書
厳格なる父・毛沢東、寛容なる母・周恩来。最新の資料から、田舎っぺ皇帝と気配り宰相の素顔に迫り、二つの巨星が作りげた中国の社会主義を検証。『天安門』以後を占う。
田舎っぺ毛沢東――毛沢東はなによりも農民の子であった。その生活習慣には、「田舎っぺ」(土包子)くささがあふれていた。たとえば医者ぎらい、栄養剤ぎらい、質素な食事と衣生活などは、青年時代から保持した習慣である。権力をとってからも、毛沢東の生活は非常に質素だった。毛沢東は許可なしに新しい衣服をつくることを許さなかった。現に53年から62年末まで、彼は新しい衣服をつくっていない。いつも水で顔を洗い、化粧石鹸は用いなかった。墨汁や油で手を汚したときは、洗濯用石鹸で洗った。顔クリームなど化粧品もつかわず、いや練り歯みがきさえ用いず、安物の粉歯みがきを用いていた。タオルケットや寝巻はつぎはぎだらけであった。北京入城のさいも、葬式のさいもそうだった。彼の下着やパンツ、それに靴下もつぎはぎだらけであり、ちょっと不注意に足を伸ばすと靴下のつぎはぎがあらわれた。客をむかえるとき、李銀橋らはよくこう注意したものだ。「家の恥を外に見せないようにしなくては」――本書より

英語表現をみがく―動詞編
講談社現代新書
動詞こそ英語の心臓部(キーポイント)。頻出する基本16動詞(give make ……)生命力あふれる2語動詞(go on put out ……)微妙なトーンを作る助動詞(can must ……)など、動詞をその基本から理解し、英語感覚をみがく。
基本16動詞とは――「ベイシック英語」の動詞として提案されたのは次の16語である。come go put take give get make keep let do say see send be seem have。
名詞400語および形容詞150 語にくらべても、16という基本動詞の語数はきわめて限定されている。その理由としては、enter はcome in 、returnはcome back look はgive a lookのように「基本動詞+副詞」あるいは「基本動詞+名詞」でその代用ができるという事実があげられよう。さしあたって、ここに示されているような基本動詞を身につけておけば、最低限のコミケュニケーションは保証される。――本書より
インサイダー取引 証券市場と日本人
講談社現代新書
インサイダー取引をめぐる日米文化比較論。なぜ日本では内部者取引が処罰されないか?情報社会における企業倫理とは?日米の商取引の慣習や法意識の比較を通して、投資者保護はどうあるべきかを考える。
バルセロナ
講談社現代新書
自由と独立の風が吹く、地中海都市を訪ねて1888年万博から1992年オリンピックに至るカタルーニヤ・ルネサンスの道のり。ピカソ、ミロ、ダリ、ガウディやアナーキストたちを生んだ風土の魅力を探る

マンダラは何を語っているか
講談社現代新書
密教思想が説く「悟りの世界」「聖なる空間」の絢爛華麗なイメージ。マンダラに秘められたほとけの智慧に近づくことは、いかにして可能か。
空海の意図と演出――当時、密教を受け入れた一般の姿勢は、その「加持祈祷」にもっぱら期待するものであった。難解な教養を理解しようとするのは限られた知識階級のみで、朝廷も民衆も、空海に望んだのは祈祷による現世利益的効験であったろうことは、密教の性格からいって当然だった。即身成仏論の魅力も、そうした実地の効験と結びつかなければ大衆の心を惹きつけることは困難だったと考えられる。空海はこのことをよく知っていた。そのために、修法の場をいかに構成し、演出するかを、綿密に計画し、それを実現した。「秘密荘厳心」を具体的な実在として示すための密教儀式こそ、空海が肝胆を砕いて創り上げた造型の、劇的な綜合芸術なのである。――本書より

MBA―アメリカのビジネス・エリ-ト
講談社現代新書
アメリカのワールド・ビジネスを支配する若き経営専門家はいかに養成されるのか? 磨きぬかれたカリキュラム、苛酷なワーク・ロード、激論とびかう授業。ハーバード、ミシガンなど経営大学院の実態を詳細に紹介しつつ、21世紀のビジネス社会を展望する。
約束された将来――アメリカ社会では、大学を出てそのまま就職しても、先はせいぜい熱練セールスマンである。MBAを取得して大手企業に就職すれば、アメリカの平均世帯所得が三万ドルちょっとという状況のなかで、初任給でも五万ドルはもらえる。ましてや、トップ・テンのビジネス・スクールの卒業生ともなれば、ビジネス・パーソンとしての将来は約束されたも同様である。アイアコッカのように、年収何億円という世界も夢ではない。アメリカのビジネス界で力を発揮し、出世するためには、もはやMBAは必須の条件となっているのである。このようなアメリカにおけるMBAの存在は、わが国で近年よく知られるようになり、アメリカのビジネス・スクールへ入学する人たち、あるいは入学を希望する人たちも年々増加の傾向にある。――本書より
物見遊山と日本人
講談社現代新書
日本人の好奇心の源である物見遊山を解剖.桜に酔いしれる江戸庶民,お伊勢参りにブ-ム……日本人は季節に応じ,名所旧跡に事つけ,物見遊山をたのしんだ.エネルギ-の源である物見遊山を文化史的に解剖
SISは企業を変える
講談社現代新書
圧倒的競争優位をめざす<SIS>革命とはサ-ビスを差別化,仕入れ先から顧客までを囲い込んで市場を制する.デ-タベ-ス資源と通信ネットワ-クを活用する注目の経営戦略を実例をまじえつつ紹介.
女たちのアメリカ~フェミニズムは何を変えたか
講談社現代新書
女性革命が引き出した家族の変容をえがく.見えざる男性優位の壁に悩むス-パ-ウ-マンと女性兵士たち.家族へ回帰する新伝統主義と繁栄する「生殖産業」アメリカの家族と女性のルポから未来社会を考える
コナン・ドイル―ホ-ムズ・SF・心霊主義
講談社現代新書
ホ-ムズを生んだ唯物主義者の世紀末的変容医師として出発しながら,ベストセラ-探偵小説家として世に容れられたコナン・ドイル.意に染まぬ肩書を捨てるため心霊主義へと傾いていった彼の軌跡を追う.
ロビイスト―アメリカ政治を動かすもの
講談社現代新書
アメリカ政治を動かす代理人たちの実態は?ワシントン最大の産業であるロビイング.米国の中東政策を決定するイスラエルロビ-,経済摩擦をめぐる日米ロビイング合戦等,米国政治を影で動かす仕掛人の実態

脳はどこまでわかったか
講談社現代新書
人体最後の秘境。宇宙でもっとも複雑なシステム。脳研究は「こころ」の過程を考えるまでになった。概念の形成や思考は、いかになされるのか?長期記憶と短期記憶は、どうちがうのか?最先端の知見からやさしく解説する。
インテリアの近代
講談社現代新書
都市と建築の近代精神をインテリアに探る.壁を本で織り上げたような図書館.聴衆を照らす音楽堂の光天井.ガウディやオルタの住宅に見る「芸術空間に棲む」営為.ヨ-ロッパのモダンインテリアを訪ねる.

客家
講談社現代新書
辛亥革命はなぜ成功したのか? 共産党の長征はなぜ可能だったか? トウ小平、朱徳、葉剣英など、多くの革命家を生み、中国を支配する客家の「血のネットワーク」。太平天国からニクソン訪中、華南経済圏まで、宋代文化を現在に残す小数民俗に、もうひとつの中国史を読む。(講談社現代新書)
東洋のユダヤ・客家族から中国の政治を読む孫文,葉剣英、トウ小平、リークアンコー…。中国、東南アジアの政治を影から動かす少数民族・客家族。「中国人の中の中国人」と呼ばれる彼らのネットワークに迫る。