講談社選書メチエ作品一覧
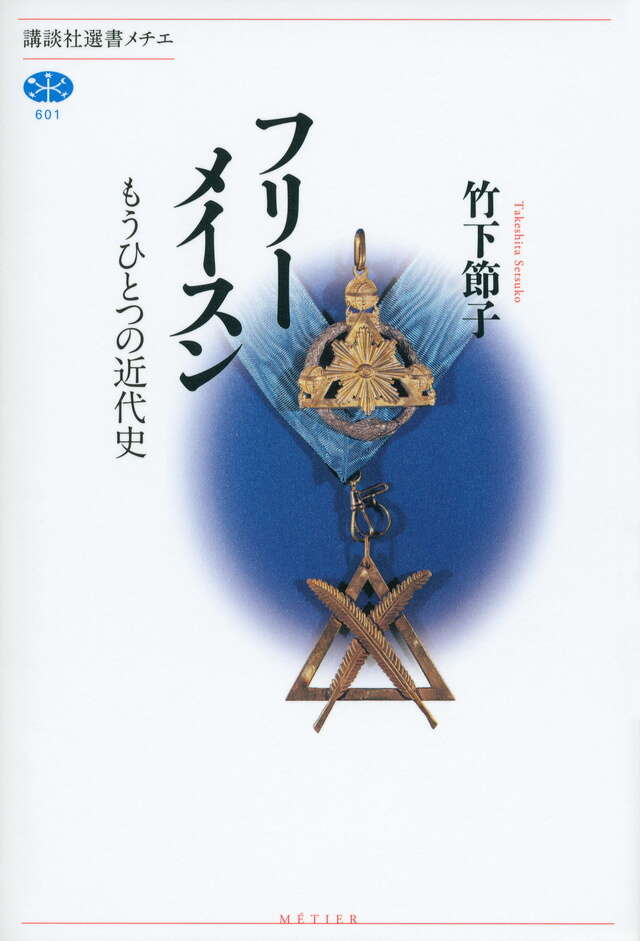
フリーメイスン もうひとつの近代史
講談社選書メチエ
謎めいた存在ゆえに、陰謀論の格好の対象となるフリーメイスン。秘密に包まれたイニシエーションの実態とは? 「自由、平等、兄弟愛」などキリスト教ルーツの価値観を政治から切り離し、「普遍価値」として復権させることが彼らの使命である。アメリカ独立戦争、フランス革命から『シャルリー・エブド』事件まで、フリーメイスンの誕生と変容を辿りながら、西洋近代をもうひとつの視点からとらえなおす。(講談社選書メチエ)
謎めいた存在ゆえに、陰謀論の格好の対象となるフリーメイスン。
秘密に包まれたイニシエーションの実態とは?
「自由、平等、兄弟愛」などキリスト教ルーツの価値観を政治から切り離し、
「普遍価値」として復権させることが彼らの使命である。
アメリカ独立戦争、フランス革命から『シャルリー・エブド』事件まで、フリーメイスンの誕生と変容を辿りながら、西洋近代をもうひとつの視点からとらえなおす。

知の教科書 ライプニッツ
講談社選書メチエ
17世紀中葉のドイツに生まれたゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツ(1646-1716年)は、哲学、論理学、倫理学のみならず、歴史学、政治学、経済学から、数学をはじめとする自然科学に至るまで、まさに知の全領域を横断した知の巨人である。ルネ・デカルト(1596-1650年)、バールーフ・デ・スピノザ(1632-77年)と並んで近代哲学の礎を築いたこの巨人が与えた影響は狭義の哲学のみならず、数学や文化交流にまで及ぶが、残念ながらライプニッツはみずからの思想を分かりやすい形では決して示さなかった。
ライプニッツが提示した概念はしばしば奇妙で抽象的である上、異なる見方を統合する傾向があるため、読者は常に困惑させられ、その思想の全容を理解するのは決して容易ではない。そこで、本書は専門的な議論や影響史についての記述を割愛し、大切なことだけを取り上げる。しかも、それをわれわれの経験から実感できるように描くことで、明快にして徹底的な内容をもちながら最良の手引きにもなる、という稀有な書物が実現されている。ライプニッツ思想の全領域をカバーし、要となる分野については重点的に検証しながら、形而上学、認識論、倫理学、政治思想の交わる領域を概観した末には、それらの基盤となる世界がモナドで構成されるという著名な説はわれわれ自身の生きることと深く結びつきながら理解されることになるだろう。
生きるための、生きることを理解するための哲学のリアルな姿がここにある。
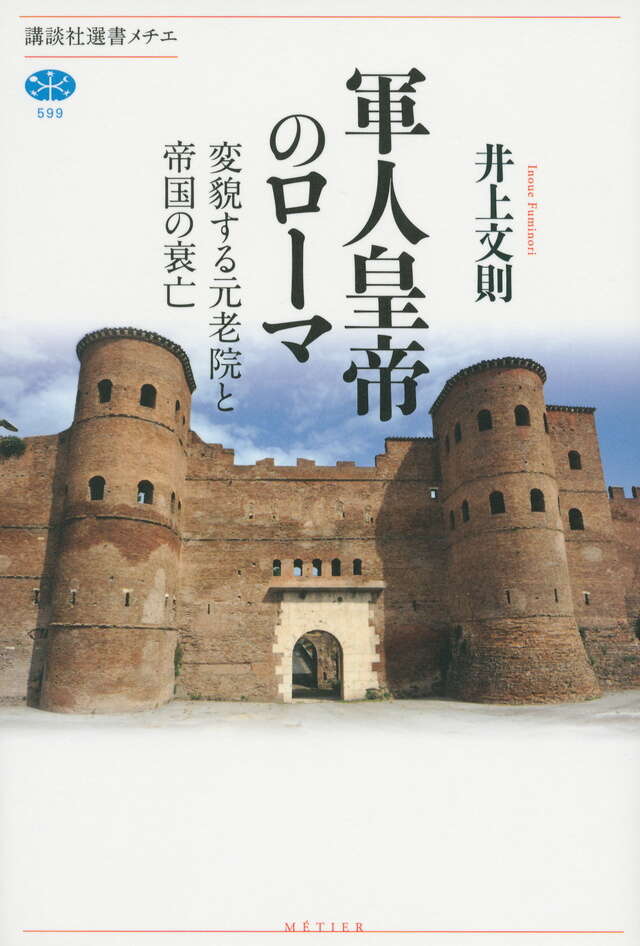
軍人皇帝のローマ 変貌する元老院と帝国の衰亡
講談社選書メチエ
共和政期以来、ローマ帝国を支えてきた元老院。しかし、軍事情勢が悪化し、貧富の差が拡大した三世紀以降、支配権はバルカン半島出身で下層民からのぼりつめた軍人皇帝の手に移る。アウレリアヌス帝、ディオクレティアヌス帝、コンスタンティヌス帝など、七七人中二四人が、バルカン半島出身の軍人皇帝である。ローマ文明を担うエリートの元老院の失墜と武人支配への変化を描き、ローマ帝国衰亡の世界史的意味をとらえなおす。
共和政期以来、七〇〇年にわたり、ローマ帝国を支えてきた元老院。
しかし、軍事情勢が悪化し、貧富の差が拡大した三世紀以降、
支配権はバルカン半島出身で下層民からのぼりつめた軍人皇帝の手に移る。
アウレリアヌス帝、ディオクレティアヌス帝、コンスタンティヌス帝など、
じつに七七人中二四人が、バルカン半島出身の軍人皇帝である。
ローマ文明を担うエリートの元老院の失墜と武人支配への変化を描き、
ローマ帝国衰亡の世界史的意味をとらえなおす。

地図入門
講談社選書メチエ
地図とは地形や道路、建物などの現実を記号化すること。そのためには、さまざまな省略があります。地図の制作者はどのように現実を記号化するのでしょうか。「総描」「転位」とはどのような作業なのか? また、基準を決めるのも重要です。たとえば、海抜0メートルの決め方とは? 地形図と海図の基準の違いとは?日本の近代以降の地図を中心に、読み方から楽しみ方まで紹介する入門書の登場です。

権力の空間/空間の権力 個人と国家の〈あいだ〉を設計せよ
講談社選書メチエ
古代ギリシア都市に見られる領域「ノー・マンズ・ランド」とは何か? ハンナ・アレントが重視したこの領域は、現代の都市から完全に失われた。世界的建築家がアレントの主著を読み解きながら、われわれが暮らす住居と都市が抱える問題を浮かび上がらせ、未来を生き抜くための都市計画を展望する。人が幸せに生きるためには、来たるべき建築家が、公的なものと私的なものの〈あいだ〉を設計しなければならない。
ハンナ・アレントは『人間の条件』の中で、古代ギリシアの都市に触れて「私的なるものと公的なるものとの間にある一種の無人地帯」という奇妙な表現を使っている。ここで言われる「無人地帯」とは「ノー・マンズ・ランド(no man’s land)」の訳語である。そして、このノー・マンズ・ランドこそ、都市に暮らす人間にとっては決定的に重要だ、とアレントは言う。
本書は、この表現に注目した世界的建築家が、アレントの主著を読み解きながら、現代の都市と人々の生活が抱える問題をあぶり出し、われわれが未来を生き抜くために必要な都市の姿を提示する書である。
ノー・マンズ・ランドとは、日本家屋で喩えるなら、空間的な広がりをもった「敷居」のようなものだと著者は言う。古代の都市では、異なる機能をもつ複数の部屋を隔てたり、家の内と外を隔てたり、私的な領域と公的な領域を隔てたりする「敷居」そのものが場所として成立していた。しかし、そのような場所は現代の都市からは完全に失われている。
それこそが人々の閉塞感を生み、人と人のつながりを破壊した原因であることに気づいた著者は、敢然と異議を唱える。その打開策として打ち出されるのが、インフラのレベルから構築される「地域社会圏」というヴィジョンである。そこでは、国家の官僚制的支配から自由になった人々が、それぞれの能力と条件に応じて協同し、住民の転入・転出があっても確固として存在し続ける都市が実現される。
誰も有効な処方箋を書けずにいる困難な日本で、幾多の都市にまなざしを向けてきた建築家が回答を示す必読の書。

女たちの平安宮廷 『栄花物語』によむ権力と性
講談社選書メチエ
本書は、平安時代の摂関政治がどのように権力を生み出していったか、そのしくみについて女たちの後宮世界からみていくものです。その恰好の例として『栄花物語』を取り上げます。作者は歴史的事実をあえて無視したり操作することで、女であること・生むこと・母となることの連なりに走る裂け目こそが、男たちの世界をつくってはやがて掘り崩し、そうした変化が新しい権力構造を生みだしていくことをはからずも明らかにするのです。
本書は、平安時代の摂関政治がどのように権力を生み出していったか、そのしくみについて女たちの後宮世界からみていくものです。
平安時代の宮廷サロンが生み出した文学作品に、「歴史物語」とよばれるジャンルがあります。男たちが漢文で記す「正史」にたいして、女たちの使う仮名であらわしたものです。できごとを羅列する無味乾燥な「記録」にたいして、できごとを活き活きと語る「物語」です。
平安宮廷の表舞台は摂関政治に代表される男の世界ですが、周知のようにその根底を支えているのは男と女の性の営み、天皇の閨房にありました。摂政関白という地位は、天皇の外祖父が後見役になることで得られるものですから、大臣たちは次々と娘を天皇に嫁入りさせ、親族関係を築くことに必死でした。
そうした要請から、摂関政治は結果として一夫多妻婚を必然としました。後宮に集う女たちは、天皇の寵愛を得るために、そして天皇の子、とりわけ次代の天皇となる第一皇子を身ごもるために競いあいました。
天皇の後見と称して、その権限を乗っ取るようにして発揮する最大の権力が、天皇と女たちの情事に賭けられていたというのは、ずいぶんと滑稽な話ですが、「歴史」はそういうことをあからさまにしたりはしません。あくまで男同士の権力闘争として書くわけで、むしろその本質であるはずの、いくつものサロンの抗争や女たちの闘争は「物語」にこそ明らかになるのです。
その恰好の例が『栄花物語』です。作者は歴史的事実をあえて無視したり操作することで、女であること・生むこと・母となることの連なりに走る裂け目こそが、男たちの世界をつくってはやがて掘り崩し、そうした変化が新しい権力構造を生みだしていくことをはからずも明らかにします。
【目次】
はじめに なぜ『栄花物語』なのか
第一章 「オモテ」の権力と「ウラ」の権力
第二章 後宮からの出発
第三章 花山帝という存在
第四章 生む政治
第五章 女房・召人・乳母
第六章 システムの揺らぎを語る
むすびに 院政期のはじまりへ
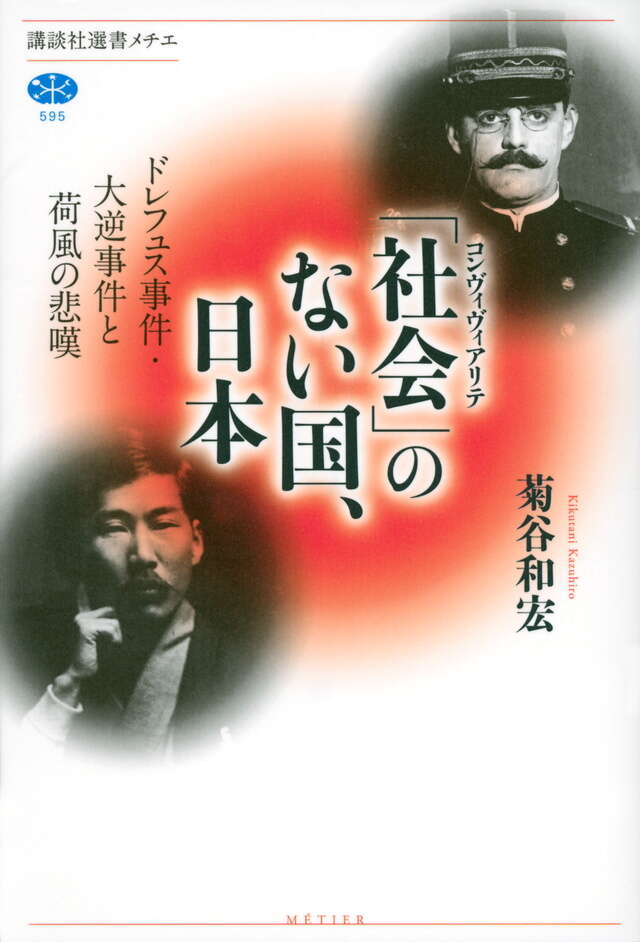
「社会」のない国、日本 ドレフュス事件・大逆事件と荷風の悲嘆
講談社選書メチエ
20世紀初頭に日仏両国に勃発した二つの事件。冤罪被害者は、なぜフランスでは救われるのに、日本では救われないのか? 二大事件とそこに関わった人々のドラマを比較し、日本に潜む深刻な問題が白日の下にさらされる。「日本」という国家はなくても、日本という「社会」は存在できる。永井荷風の悲嘆を受けて、「共に生きること(コンヴィヴィアリテ)」を実現するための処方箋を示す、日本の未来に向けられた希望の書。
本書は、国家による冤罪事件として知られるフランスのドレフュス事件(1894-1906年)と日本の大逆事件(1910年)を取り上げ、日仏両国の比較を通して、日本に見出される問題が今日もなお深刻なまま続いていることを明らかにする。
スパイの嫌疑を受けて終身刑に処せられたユダヤ系の陸軍大尉アルフレッド・ドレフュスは、軍部や右翼との闘いの末、最終的に無罪になった。その背景に作家エミール・ゾラをはじめとする知識人の擁護があったことはよく知られている。一方、天皇暗殺計画を理由に起訴された24名が死刑宣告を受けた大逆事件では、幸徳秋水をはじめとする12名が実際に処刑されるに至った。
二つの事件に強く反応した永井荷風は、ゾラと自分を比較し、自分の情けなさを痛感した、と告白している。そこで刻み込まれた悲嘆の深さは、荷風に戯作者として隠遁生活を送ることを余儀なくさせるほどだった。
ここに見られる違いは、どうして生まれたのか。本書は、両事件を詳しく分析することで、その理由が日本には「社会」がないという事実にあることを突きとめる。「日本」というのは国家の名称に尽きるものではない。国家が存在しなかったとしても、社会は存在しうる。そして、国家が個人に牙を剥いてきたとき、社会は個人を救う力をもっている。しかし、この国には、国家はあっても社会はない。それが、ドレフュスは無罪になったのに、幸徳らは見殺しにされた理由である。
今日も何ら変わっていないこの事実に抗い、「共に生きること(コンヴィヴィアリテ)」を実現するための処方箋を示す、日本の未来に向けられた希望の書。

ある豪農一家の近代 幕末・明治・大正を生きた杉田家
講談社選書メチエ
幕末期、仁政イデオロギーのもと大庄屋として地域を指導していた仙十郎。彼はなぜ「万機公論」「四民平等」の新政府に期待し、そして失望したのか。自由民権運動に身を投じ、第一回衆議院選挙で国会議員となった定一を支えた杉田家の困窮。英学の修得に情熱を燃やし、新島襄・八重夫婦との交流を深めた鈴が体現する新しい女性像。従来の教科書的理解では、決してわからない日本の近代化の多面的な実相を描き出す。
越前一の豪農として知られた杉田家の父・仙十郎、息子・定一とその妻・鈴。
幕末期、仁政イデオロギーのもと大庄屋として地域を指導していた仙十郎。彼はなぜ「万機公論」「四民平等」の新政府に期待し、そして失望したのか。
自由民権運動に身を投じ、第一回衆議院選挙で国会議員となった定一を支えた杉田家の困窮。
英学の修得に情熱を燃やし、新島襄・八重夫婦との交流を深めた鈴が体現する新しい女性像。
従来の教科書的理解では、決してわからない日本の近代化の多面的な実相を描き出す。
【目次】
はじめに
第一章 幕末期の杉田家
第二章 明治期の杉田家
第三章 大正・昭和期の杉田家
おわりに
主要参考文献一覧
杉田仙十郎・定一・鈴関連年表
あとがき

マーケット・デザイン オークションとマッチングの経済学
講談社選書メチエ
マーケット・デザインとは、より良い制度・ルールの設計・改革を行う経済学の最先端分野である。結婚、就職、学校選択、臓器移植……。この世界には市場メカニズムが利用できない問題が数多くある。基礎となる市場理論やゲーム理論などを解説したうえで、グーグルなどもその研究と実践に取り組むマーケット・デザインの最新成果をその課題とともに具体的に紹介する。

知の教科書 スピノザ
講談社選書メチエ
17世紀のオランダの生んだ大哲学者・神学者スピノザの著作は、その進歩的思想により、刊行当時禁書とされました。
18世紀後半になると、「汎神論論争」が起こり、スピノザの評価が大きく変化します。ヘーゲルは、スピノザがあらゆる哲学の出発点となったと宣言し、ニーチェはスピノザに先駆者の姿を見出しています。二〇世紀、フロイトやラッセル、アインシュタインもスピノザを評価しています。二〇世紀後半には、スピノザ・リバイバルが起こります。これはフロイデンタール、ゲプハルトらによる初期の歴史研究、原典研究に依っています。バリバール、ネグリ、ドゥルーズなどの現代思想家たちも影響を受けています。スピノザの思想の重要性は、現代において増大しています。
しかし、スピノザの思想は、ハードルの高いものです。というのもスピノザの思想は、形而上学、精神哲学、認識論、倫理学、政治哲学といった哲学的主題から、宇宙論や心理学、物理学までと幅広いこと。そして主著『エチカ』は、中世後期のスコラ哲学の語彙で書かれ、「幾何学的な秩序で」提示されることからも、大変難解です。
本書では、スピノザの生涯と思想形成をたどり、『エチカ』『神学政治論』『国家論』といった主要著作の概要がつかめるように、おおきくまとめて語られます。スピノザ入門(初級・中級)の決定版です。

民俗学・台湾・国際連盟 柳田國男と新渡戸稲造
講談社選書メチエ
植民地台湾における新渡戸稲造の「治者」の視線。それに触発されて新たな学問を構想した柳田國男だったが、国際連盟委員としてジュネーブでおおきな挫折を経験する。反転した視線は「常民」へと向かう……。近代化への応答としての日本民俗学誕生の過程を追う。
柳田國男については、これまでさまざまな論究が蓄積されてきました。また、柳田に比べれば数は少ないものの、新渡戸稲造についても同様です。しかし、両者の関係、とくに思想的連関とその社会的背景に関するまとまった論考は今まで、ほとんど書かれていないません。
しかしながら、二人はともに東京帝国大学で農政学を修めた同窓であり、学問的な領域は近いのです。柳田は内務官僚として、のちには朝日新聞社の論説委員として従事するかたわら、ほぼ独力で民俗学の研究者としての地位を築いていったために、民俗学における「師」と呼ぶような存在をもちませんでしたが、その柳田にとって新渡戸はただひとり「師」に当たる人物であったともいえます。柳田の、ひいては日本における民俗学の成立を考えるうえで、新渡戸と関係を丁寧にみていくことが不可欠だと著者は考えます。
二人の関係が急速に接近したきっかけは、1907(明治40)年2月14日、台湾総督府の任を終えて帰国した新渡戸の講演「地方(じかた)の研究」を柳田が聴いたことであることは、ほぼ、まちがいありません。柳田はこの講演に大きな感銘を受け、その後1910(明治43)年12月、新渡戸邸を会場とした「郷土会」が発足します。この会は新渡戸を世話人とし、柳田を幹事役とした研究会で、地方文化に興味をもった農政官僚や研究者、知識人らが集い、自由で活発な議論がおこなわれました。この郷土会は新渡戸が国際連盟の事務次長としてスイスに赴任する1919(大正8)年まで60回以上続くことになります。この期間に柳田はみずからの学問の基礎をつくっていくのです。
やがて柳田は、新渡戸の推挙によって国際連盟の委任統治委員に就任しますが、わずか2年あまりで辞任しています。その後、両者の関係は希薄になっていったものと思われますが、それでもこの関係こそが日本民俗学誕生の決定的契機だと見なせます。
本書では柳田が確立した「民俗学」(一国民俗学)が、植民地における「治者」の視線に胚胎し、やがてそれが反転して「常民」の学となっていく過程を追います。また、それがある種の──文化人類学とはちがった意味での──文化相対主義の産物であり、それは国際連盟における新渡戸との経験の反映であったことを明らかにします。

原敬 外交と政治の理想(下)
講談社選書メチエ
「平民宰相」原敬の初の本格的評伝。新聞記者・外交官・企業経営者など多彩な顔を持ち、一貫して「公利」という概念を重視して第一次世界大戦後の世界を見通した、ポスト「元勲世代」の偉大な政治家の生涯。下巻は、大隈重信、山県有朋、桂太郎らとの確執を経て、首相として初の政党内閣を成立させながら、東京駅で凶刃に倒れるまでの後半生を描き、この暗殺によって失われたその後の可能性と、原が日本の歴史に遺したものを考察。
厖大な史料を歴史研究者としての確かな眼で読み込み、伊藤博文や山県有朋、昭和天皇など近代日本をつくってきた人々の評伝を著して高い評価を得てきた著者による、渾身の書き下ろし新作。「平民宰相」として知られる原敬の65年の生涯を描く、本格的評伝。上下全2巻のうちの下巻。
原敬といえば、おもに初の本格的政党内閣を実現し、薩長藩閥政治の克服に努めた東北出身の政治家としてのみ語られることが多いが、著者によれば、原の政治家としての特色は、外交や内政に高い理想を持ち、それが当時の状況に合致していたこと、またそれらを実現するための手法やタイミングを知り尽くしていたこと、にあるという。また、新聞記者・外交官・企業経営者など多彩な顔を持ち、そこで吸収した見識を元に一貫して「公利」という概念を重視し、第一次世界大戦後の世界を見通して新たな日本政治の道筋をつけた、ポスト「元勲世代」のもっとも偉大な政治家だったのである。
下巻では、大隈重信、山県有朋、桂太郎らとの確執を経て、首相として初の政党内閣を成立させながら、東京駅で凶刃に倒れるまでの後半生を描き、この暗殺によって失われた日本政治のその後の可能性と、原が日本の歴史に遺したものについて考察する。

原敬 外交と政治の理想(上)
講談社選書メチエ
「平民宰相」原敬の初の本格的評伝。新聞記者・外交官・企業経営者など多彩な顔を持ち、一貫して「公利」という概念を重視し、第一次世界大戦後の世界を見通して新たな日本政治の道筋をつけた、ポスト「元勲世代」のもっとも偉大な政治家の65年の生涯を描く。上巻では、原の誕生から、フランス語を学び、ジャーナリストとして見聞を広めたのちに外交官として活躍し、陸奥宗光の知己を得て政治の世界へと進むまでの前半生を描く。
厖大な史料を歴史研究者としての確かな眼で読み込み、伊藤博文や山県有朋、昭和天皇など近代日本をつくってきた人々の評伝を著して高い評価を得てきた著者による、渾身の書き下ろし新作。「平民宰相」として知られる原敬の65年の生涯を描く、本格的評伝。上下全2巻のうちの上巻。
原敬といえば、おもに初の本格的政党内閣を実現し、薩長藩閥政治の克服に努めた東北出身の政治家としてのみ語られることが多いが、著者によれば、原の政治家としての特色は、外交や内政に高い理想を持ち、それが当時の状況に合致していたこと、またそれらを実現するための手法やタイミングを知り尽くしていたこと、にあるという。また、ジャーナリスト・外交官・企業経営者など多彩な顔を持ち、そこで吸収した見識を元に一貫して「公利」という概念を重視し、第一次世界大戦後の世界を見通して新たな日本政治の道筋をつけた、ポスト「元勲世代」のもっとも偉大な政治家だったのである。
上巻では、盛岡での誕生から、フランス語を学び、新聞記者として見聞を広めたのちに外交官として、さらに大阪毎日新聞社長として活躍し、陸奥宗光の知己を得て政治の世界へと進むまでの前半生を描く。

平泉 北方王国の夢
講談社選書メチエ
奥州藤原氏の政庁平泉館跡で発見された儀式・宴会用の大量のかわらけ。金、馬、鷲羽の交易で得られた巨富。紛争の調停者として所領支配を保障し、平和の実現をもって家臣団を統合する独自の安全保障体制――。中国大陸までつながる交易網を築き、一宮二十二社制や真言密教など中央の神仏体系を拒否した奥州藤原氏は、列島に第三の勢力として君臨した。ヤマトともアズマとも異なるもうひとつの世界を明らかにし、歴史のなかの「東北」を問い直す。
北緯三十九度以北に華開いた、ヤマトともアズマとも異なるもうひとつの世界を明らかにし、歴史のなかの「東北」を問い直す。
【目次】
はじめに――「平泉」とは何か
序章 北方王国の夢
第一章 一〇・一一世紀の北方世界――平泉前史
1 初代清衡――父母と系譜
2 鎮守府と奥六郡――北方政策の転換
3 北緯四〇度の北――躍動する蝦夷社会
第二章 奥州藤原氏誕生
1 前九年合戦勃発
2 清衡誕生と安倍氏滅亡
3 延久合戦と諸勢力の抗争
4 後三年合戦
5 奥州藤原氏誕生――新たな時代の到来
第三章 平泉開府と北方王国
1 平泉開府――奥六郡から衣川の南へ
2 平泉・奥大道と津軽・外浜
3 「えぞが千島」と「奥の御館」の誕生
4 「平泉の富」の三点セット――平泉政権の支配領域
5 蝦夷ヶ島の交易拠点厚真
6 北方王国の夢
第四章 仏教都市平泉と平泉仏教
1 仏教都市平泉
2 「寺塔已下注文」が語るもの
3 多宝寺落慶――中尊寺造営の開始
4 初期中尊寺伽藍の完成
5 金色堂・供養願文伽藍(鎮護国家大伽藍一区)
6 平泉仏教と日本国・東アジア
7 北の辺境の宗教世界
第五章 「北方王国の都」平泉
1 清衡から基衡・秀衡へ
2 都市平泉の発展
3 「北方王国の都」平泉の完成
4 都市平泉の副都心・水陸交通の要衝、衣川
5 「大平泉」と都市平泉のネットワーク
6 京都・九州・大陸とのネットワーク――海のシルクロードの東の終点平泉
終 章 未完の北方王国
1 「天下三分」から自治王国としての「奥州幕府」構想へ――秀衡最後の政治構想
2 最後の「征夷」戦争

海洋帝国興隆史 ヨーロッパ・海・近代世界システム
講談社選書メチエ
近代黎明期、困難な海上ルートを通じて、世界へと乗り出したヨーロッパ諸国が築いた海洋帝国。ポルトガル海洋帝国が形成した異文化間交易ネットワーク。商業資本主義の時代、海運国家として繁栄を謳歌したオランダ。イギリスの電信網が生んだ世界の一体化――。ウォーラーステインの「近代世界システム」を海と商人の視点から捉え直し、ヨーロッパによる世界支配の本質に迫る。
近代黎明期、困難な海上ルートを通じて、世界へと乗り出したヨーロッパ諸国が築いた海洋帝国。ポルトガル海洋帝国が形成した異文化間交易のネットワーク。商業資本主義の時代、海運国家として繁栄を謳歌したオランダ。イギリスの電信網が生んだ世界の一体化――。
ウォーラーステインの「近代世界システム」を海と商人の視点から捉え直し、ヨーロッパによる世界支配の本質に迫る。まったく新しい海事史(Maritime History)入門。

〈階級〉の日本近代史 政治的平等と社会的不平等
講談社選書メチエ
武士の革命としての明治維新。農村地主の運動としての自由民権運動。男子普通選挙制を生んだ大正の都市中間層……。しかし、社会的格差の是正は、自由主義体制下ではなく、日中戦争後の総力戦体制下で進んだというジレンマをどうとらえればよいのか。「階級」という観点から、明治維新から日中戦争勃発前夜までの七〇年の歴史を、日本近代史の碩学が描き出す。(講談社選書メチエ)
武士の革命としての明治維新。農村地主の運動としての自由民権運動。男子普通選挙制を生んだ大正の都市中間層……。しかし、社会的格差の是正は、自由主義体制下ではなく、日中戦争後の総力戦体制下で進んだというジレンマをどうとらえればよいのか。
「階級」という観点から、明治維新から日中戦争勃発前夜までの七〇年の歴史を、日本近代史の碩学が描き出す。

パンの世界 基本から最前線まで
講談社選書メチエ
多加水・低温長時間発酵でパンづくりの常識を変えた、世界的なトップランナー。パリのパン職人の技術をも更新、三ツ星レストランの「narisawa」などにオリジナルのパンを卸し、多くのシェフやブーランジェから高く評価されている。本書では世界と日本のパンの歴史をふりかえり、発酵の科学的なメカニズムを説明しながら、酵母種の使い分け、小麦粉・ライ麦粉の扱い方なども具体的に明かす。パンづくりの最前線に案内!
多加水、低温・長時間発酵でパンづくりの常識を変えた、世界的なトップランナーが日本にいます。世田谷の「シニフィアン・シニフィエ」では、フランスやドイツのパン職人の技術をも更新し、世界から顧客が来店しています。また、三ツ星レストランの「narisawa」などにオリジナルのパンを卸しており、一流のシェフから高く評価されています。
本書では、世界と日本のパンの歴史をふりかえり、発酵・成形・焼成の科学的なメカニズムを説明しながら、酵母種の使い分け、小麦粉・ライ麦粉の扱い方、発酵のポイントなども具体的に明かします。パンのカリスマが最前線に案内する、はじめての「パン入門」です。
1章──パンの歴史
2章──日本のパンの可能性
3章──小麦粉を考える
4章──発酵種とは何か
5章──水と塩の役割
6章──パンを作る

知の教科書 カバラー
講談社選書メチエ
ユダヤ教は基本的に「現世」志向の宗教です。戒律に則った生活をすることが美徳であると考えられています。カバラーとはユダヤ教公認の形而上学とも言えるものです。
ユダヤ教自体が扱わない霊魂、死後の生、天と黄泉(よみ)の構造、世界の創造、終末の出来事といったことがカバラーのテーマになります。
カバラーは、二千年以上前から、何千もの書物とたくさんの運動、神秘主義者たちを生み出してきました。その間、ユダヤ教徒の意識的滋養の源泉だったのです。
カバラーとは、ヘブライ語のle-kabel(受け取る)に由来しています。カバラーの伝統のすべては、太古の源泉から来たものと考えられています。
歴史としてのカバラーではなく、ユダヤ教的な神秘的実在についての思想としてのカバラーを分かりやすく解説する待望の一冊です。
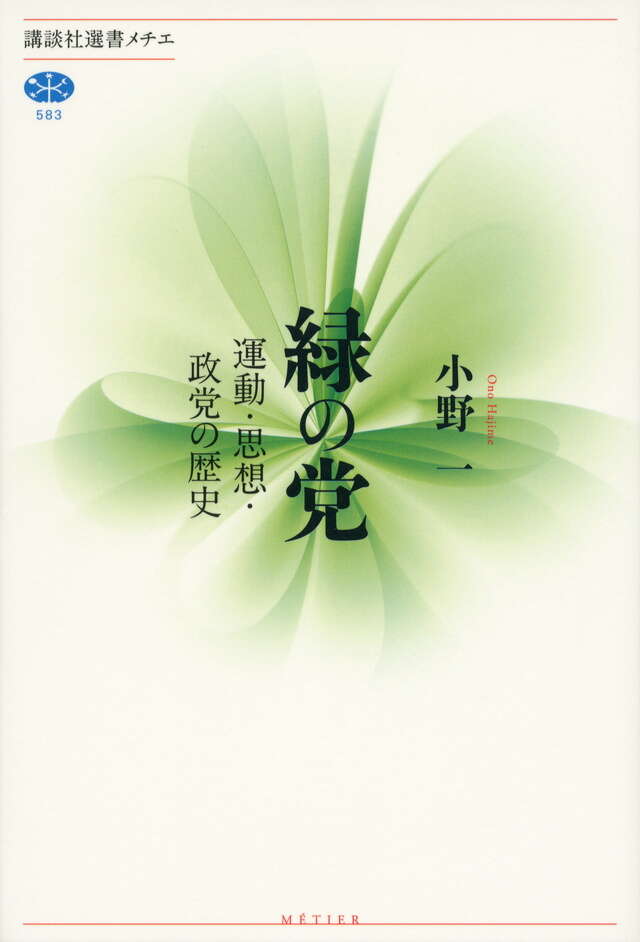
緑の党 運動・思想・政党の歴史
講談社選書メチエ
一九六〇年代末~七〇年代初頭、先進国で高揚した「新しい社会運動」。そこから出発した緑の党は、役割を変化させながら現在に至っている。ドイツをはじめとした諸外国のケースを検討しながら、運動・思想・体制(政権党)の三つの側面を分析する。私たちはどのような社会を望むのか。緑の党はその選択肢になりうるのか。いま改めて考え直す。
【目次】
序章 なぜいま緑の党か
第1章 世界に広がる緑の党
1.欧州諸国
2.ドイツ
3.フランス
4.アングロサクソン諸国
5.グローバル・グリーンズ
第2章 運動としての緑の党
1.転換点としての一九六八年
2.多様なテーマ
3.社会運動から政権党へ
第3章 思想としての緑の党
1.エコロジー思想は左翼か
2.環境思想│源流からエコロジー的近代化まで
3.新しい生き方・働き方を求めて
第4章 体制(政権党)としての緑の党
1.シュレーダー政権の軌跡と緑の党
2.焦点としての脱原発問題
3.政権参加と緑の党のアイデンティティ
4.ポスト赤緑時代の政党連立問題
終章 緑の党と私たち
1.戦後日本政治と革新勢力の脆弱性
2.緑の党研究から私たちは何を学ぶか
3.私たちはどのような社会を望むのか
注釈
あとがき
索引
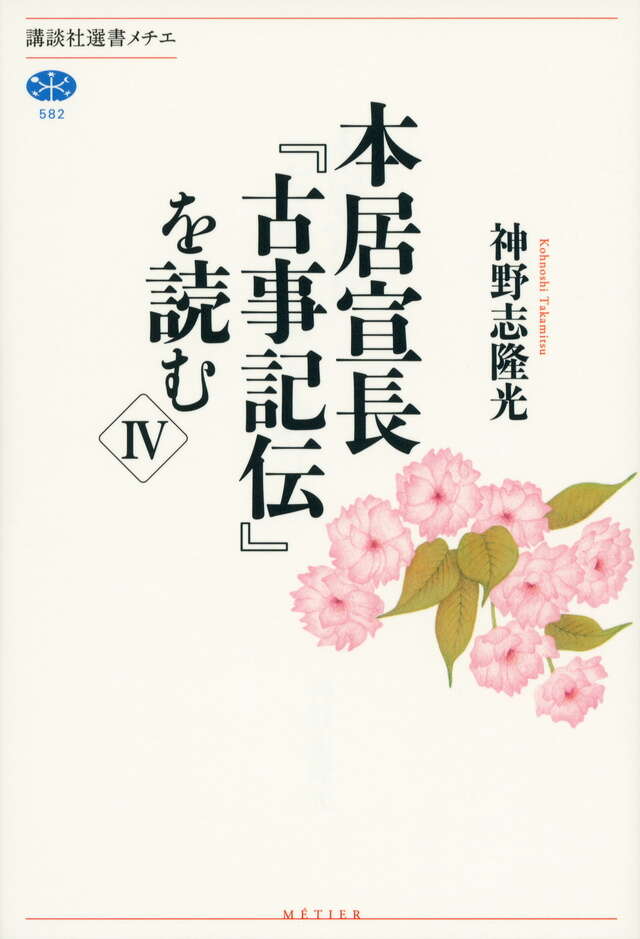
本居宣長『古事記伝』を読む 4
講談社選書メチエ
日本史上に名を残す名高い著作でありながら、あまりに厖大で誰も読み通せない本居宣長の『古事記伝』。その全44巻を細部まで詳細に、丁寧にわかりやすく、解説し尽くした未曾有のシリーズ、ついに完結! 第4巻は、「聖帝」仁徳天皇と大后石之日売命の嫉妬、軽太子・軽大郎女の禁じられた恋など、歌物語を中心に展開する。宣長が読み、現しだした古事記の世界とは。
応神天皇の三人の御子の皇位継承争い。継承した大雀命(仁徳天皇)が寵愛する八田若郎女と大后石之日売命の嫉妬。軽太子・軽大郎女の恋。――第4巻は、応神天皇から推古天皇までをあつかうが、その中心は、歌物語による、嫉妬や争いのうずまく古代世界です。そこで宣長が示す読みとは?
本居宣長の主著『古事記伝』は、『古事記』を日本最古の書物として再評価し、日本史のありかたに決定的な影響を与えた、歴史的な名著です。しかしながら、全44巻あり、しかもその内容は厖大多岐にわたり、とても読み通せるものではありません。本当に全巻読み通した人は数えるほどしかいないのではないでしょうか。
ところが、よく読むと、じつは非常に面白いのです。まずは、なんでも実証しようとする態度。『古事記』本文のひとつひとつの言葉に注釈を与えようとするのですが、その解釈は、かならず 証拠を持ち出して行おうとします。そのためには、『日本書紀』だろうと『万葉集』だろうと、ありとあらゆる文献、資料を持ち出してくる。あくまで解釈であって、現代によくあるようなたんなる学者の感想ではありません。
ただ、たまには、いろいろな解釈の可能性と証拠をしめしたあとで、いきなり「まさりてきこゆる」(理由はないが、こっちがいいような気がする)と、おちゃめな結論を出したりもする。
宣長といえば、「漢意(からごころ)批判」です。『日本書紀』には、中国的なものが入っており、それを「漢意」として排す。『古事記』にこそ、本来の日本の古代が書かれている、と主張しました。それは、右翼的な、日本至上主義にも結びつきやすい一面をもっていました。
しかし、『古事記伝』の著者の本質は、そのようなたんなるイデオローグではないのです。とにかく、徹底的に解釈しきる。その先に、日本の古代のすがたが見えてくるはずだと考えたのでした。
本シリーズは、煩雑・厖大であるがゆえに、誰もが名のみ知り、ふれることのすくない『古事記伝』の世界を、全44巻すべて、読み、解説する、という画期的なシリーズです。
第4巻で、ついに完結。最後の推古天皇までたどりつきました。
『古事記』はイザナギ・イザナミ神話だけではありません。『古事記伝』があらわしだす『古事記』の世界を、最後まで楽しんでください。