星海社新書作品一覧

萌えを立体に!
星海社新書
この世で一番萌える立体、フィギュアの世界へようこそ!
かつては専門店に行かなければ手に入らなかった美少女フィギュア。近年オタクカルチャーが市民権を得たことで、美少女フィギュアは誰でも気軽に楽しめるアイテムとなりました。マンガやパソコンのディスプレイにしか存在しなかった〈平面〉(2D)のキャラクターが萌える〈立体〉(3D)となり、直に触れ、思う存分に愛でることができる時代が到来したのです。しかし、フィギュアを作る原型師について語られる機会はほとんどありません。本書では、爆発的な拡大を遂げたフィギュア業界と、その大黒柱として活躍する原型師たちの泥臭く血と汗と涙にまみれた最前線をお伝えします。これを読めば、あなたのフィギュアがもっと愛おしくなる!

日本語の活かし方
星海社新書
一生使える「日本語の技術」を学ぼう
私は横浜市で国語塾を開いています。言いたいことがまとまらない。相手の話を聞いていてもよく整理できない。文章を読むのに時間がかかる。まして、書くのにはもっと時間がかかる。こんな悩みを持つ一〇〇人の小・中・高校生を相手に日々「言語技術」を教えています。話す力・聞く力・読む力・書く力を高めるために必要なのは、センスではなく、技術です。本書は、生徒と同じ悩みを持つ「大人」に向けて書きました。授業の現場からしか生まれないノウハウは、大人にも新鮮に感じられるはずです。歴史上、現代ほど「言語」の力が求められる時代もありません。一生使える「日本語の技術」を、私と一緒に学んでいきましょう。

今、改めて「自衛隊のイラク派兵差止訴訟」判決文を読む
星海社新書
誰が憲法を「解釈」するのか
気鋭の弁護士、川口創が中心となり「イラク派兵」問題をめぐって起こした「自衛隊のイラク派兵差止訴訟」裁判に対して、名古屋高等裁判所が言い渡した歴史的な「違憲」判決。田母神俊雄元航空幕僚長が「そんなの、関係ねえ」と逆ギレし、福田康夫元首相が「傍論でしょ?」と冷笑した、「平和的生存権」をめぐるこの画期的な判決文は、年を重ねるごとにその重みを増している。原告のひとり、大塚英志を聞き手とした判決文全文の徹底レクチャーから、この国の未来が今こそ見えてくる!

整形した女は幸せになっているのか
星海社新書
顔さえ変えれば、うまくいく?
あっけらかんとした「公言」に留まらず、手術前後をブログで「実況」するモデルまで出現し、ますますカジュアルになっていく「美容整形」。ある調査によれば、18歳~39歳の日本人女性の実に11%が、整形経験者であるという。スマホで手軽に写真撮影・アップロードができ、これまで以上に「見た目」で判断される機会の増えた現代社会。時に美しさは、幸せになるための必要条件であるかのように語られる。美しく生まれた女が幸福に近いのであれば、美しさを「手に入れた」女もまたそうであると言えるのか。現代社会だからこそ出現したこのいびつな問いに、社会学の俊英が挑む。あなたのモラルは、どこまで許す?

いいデザイナーは、見ためのよさから考えない
星海社新書
経営学部出身のデザイナーが思考する、デザインの論理
「デザイン」は、「デザイナー」と呼ばれる人たちの専売特許ではありません。ロジカルシンキングやプレゼンテーションと同じ問題解決の「道具」であり、コツさえ学べば誰にでも使いこなすことのできるものなのです。本書では、書籍やアニメ、スマホアプリなどの身近な題材を元に、デザイナーの思考プロセスを分解。「デザインとは何か」を、一緒に考えていきます。著者の有馬トモユキは経営学部出身。デザインとビジネスをつなぐのには、おあつらえ向きの人材です。さあ、「センス」や「絵心」のせいにするのはやめにして、共に「デザインの論理」について学びましょう。あなたの仕事をよいものにするヒントが、たくさん見つかりますよ。

pixivエンジニアが教えるプログラミング入門
星海社新書
非エンジニアのための、短期集中講義
本書は、「画像投稿掲示板を作ってみる」というシンプルな目標に向かって実際にプログラミングを実施して頂く行程を、具体的かつ丁寧に、ゼロから解説した一冊です。
・エンジニアと仕事をする機会の多いWebディレクター
・プログラミングに興味を持っている方
・転職/就職を機に、未経験からシステムエンジニアになることになった方
このような状況にある「非エンジニア」の方々にとって、最適なテキストとなっています。わかりやすく解説していますので、ぜひ一緒に「プログラミング」を始めてみましょう。

声優魂
星海社新書
「みんながこれをやらないから、私に仕事が来る」
声優界に並び称される者のない唯一無二の存在、大塚明夫。その類い希なる演技力と個性ある声は、性別と世代を超えて愛され続けている。バトーへの共感、ライダーとの共鳴、黒ひげに思う血脈、そしてソリッド・スネークに込めた魂─誰よりも仕事を愛する男が、「声優だけはやめておけ」と発信し続けるのはなぜなのか? 「戦友」山寺宏一氏をはじめ、最前線で共闘する「一流」たちの流儀とは? 稀代の名声優がおくる、声優志望者と、全ての職業人に向けた仕事・人生・演技論であり、生存戦略指南書。これは大塚明夫ファンが読む本ではない。読んだ人が、大塚明夫ファンとなる一冊である。

内定童貞
星海社新書
本質を見極めれば「就活」はそこまで怖くない
学生は、就活への恐怖を肥大化させ過ぎている。インターンに行かなくても内定はとれるし、面接で話す内容は立派でなくてもいい。合否は能力ではなく、相性で決まる。第一志望に通らなくても、中途採用で入ればいい。面接官にもバカはいるし、人事は味方だ――。大切なのは、美辞麗句に隠れた「企業の本音」を知ることと、社会人と「普通に」話せるトレーニング(方法は本文にて紹介する)をしておくこと。そして、すぐバレるような「ウソをつかない」ことだ。これさえできれば、就活は怖くない。誰もが未経験(=童貞)であるがゆえ、不安まみれになる就活。キツイ数ヶ月になるが、本書を読んで気持ちを軽くし、乗り切ってもらいたい。

中国のインターネット史 ワールドワイドウェブからの独立
星海社新書
6億人のユーザーを抱える独立国が、ネット上に出現した!
2014年末、中国政府はGoogleを完全に遮断し、ワールドワイドウェブから独立を果たしました。Twitterなどの西側サービスを拒絶し、国外サイトへのアクセスを制限された世界は不気味にも思えます。しかし、そこでは6億人が、パクリ的な国内サービスを使ってインターネットを楽しんでいます。では、このネット上の独立国はいかにして成立したのでしょうか? その過程を探ると、いくつもの興味深い事実が明らかになりました。ネット導入は政府主導だったこと、パクリでも国産サービスが選ばれること、しかし国内のIT企業は常に世界を目指していたこと……。さあ、ネット上に国境線が引かれるまでの20年を、共に辿り直しましょう!
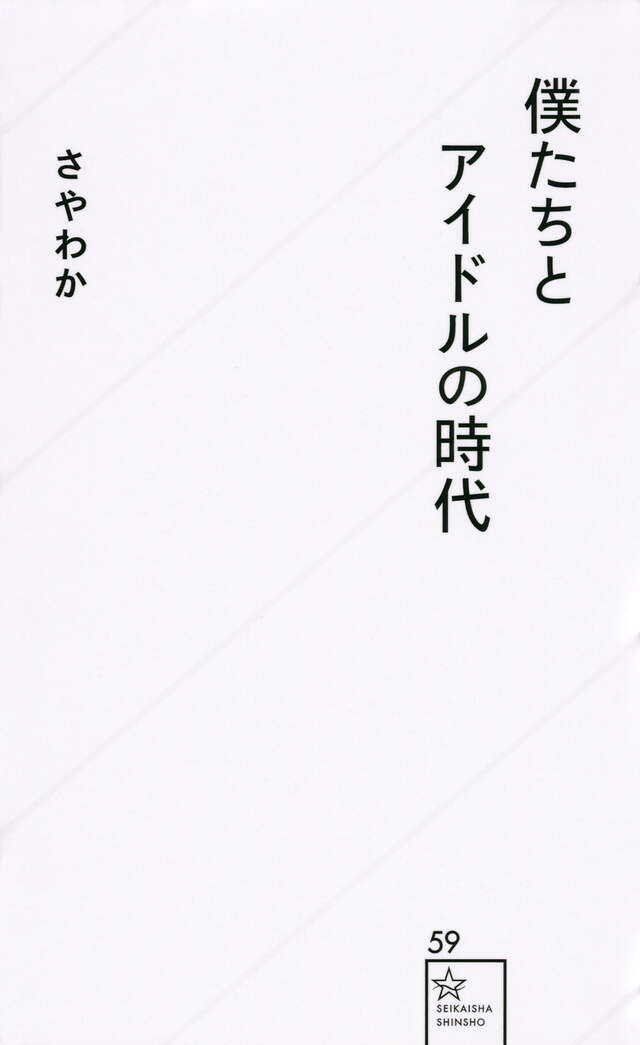
僕たちとアイドルの時代
星海社新書
批判の的になった「AKB商法」こそが、新時代の鍵だった!
「AKB商法」という言葉があります。CDを複数枚買ってもらうことを前提としたこのリリース形式は、AKB48を筆頭にグループアイドルの躍進をもたらすと同時に、激しい批判にさらされてもいます。はたして、彼女たちの人気はまがい物で、アイドルなど取るにたらない存在なのでしょうか? 本書ではそのような批判を念頭に置きつつ’70年代から現在までのヒットチャートに基づき、日本のポップミュージックの歴史を振り返っていきます。そこから見えてきたのは、アイドルと「AKB商法」こそが音楽産業を救ったという意外な事実でした。そう、今や「僕たちとアイドル」こそが、新たな時代をもたらしているのです。

ディズニープリンセスと幸せの法則
星海社新書
ディズニープリンセスがあなたに教える幸せの法則
あのディズニーが『白雪姫』を制作した1937年から現在に至るまで、一貫して使い続けてきた「夢見るプリンセスが幸せをつかむには?」という不変のテーマ。本書では未曾有のヒット作となった『アナと雪の女王』を中心に、移りゆく時代とともにプリンセスたちの「夢」や「幸せ」がどのように変化してきたかを読み解きます。誰もが知っている劇中歌や名台詞の分析を通じて、ディズニー映画の現在・過去・未来を見通し、作品に隠された「幸せの法則」を明らかにしてゆきます。それではさっそく、ディズニープリンセスにまつわる魅惑の歴史を紐解いてゆきましょう。

サマる技術
星海社新書
要約が、あなたの知にドライブをかける!
あなたは、先月読んだ本の内容を覚えていますか? 仕事の合間に読んで「ためになった!」と思ったネットの記事の内容を人に話すことができますか? 私はこれが、心底苦手でした。仕事柄、年間1000冊以上の本に目を通しますが、読んだそばから内容を忘れてしまい、頭に入れたはずの知識を活かすことができていなかったのです。しかし、ある時『認知科学』という学問分野に出会い、科学的なアプローチをもってこの課題の克服に成功します。キーワードは、要約(サマる)×クラウド。さあ、「使い捨ての知識」を頭に流しこむ日々に別れを告げ、「一生ものの知」をスマホに入れて持ち歩く、生産性の高い人生をスタートさせましょう!

白熱日本酒教室
星海社新書
古い知識はおさらば! 日本文化の最先端「日本酒」を味わおう!
今、世界一面白いお酒、それは間違いなく「日本酒」です。近年では、スペイン料理やフランス料理にあわせるための日本酒や、芳醇なワインを思わせる香り豊かな日本酒、ほんの少し温度を変えるだけでがらりとその味わいを変える日本酒……、お米だけで造られているとはとても考えられないほど様々な日本酒が登場しています。これらは、日本各地に存在する蔵元の伝統と創意工夫、そして最新の醸造技術の結晶です。今や日本酒は、世界から注目を集める面白いお酒に進化したといっても過言ではありません。「難易度が高いお酒」と思われがちな日本酒ですが、それはもはや昔の話。さぁ、今こそ日本酒の魅力を存分に味わいましょう!

あなたのプレゼンに「まくら」はあるか? 落語に学ぶ仕事のヒント
星海社新書
落語は、面白くて、ためになる!
この本は、落語の面白さについて語ると同時に、落語がいかに「役に立つか」について解説した本です。落語修業を経て私の中に芽生えたのは、「サラリーマン時代に落語を知っていれば、もう少しましな仕事ができたのに……」という思いでした。話し方はプレゼンの参考になりますし、噺の内容から人間関係のコツを学ぶこともできます。しかも予備知識が不要で、三千円も出せば一流の芸がみれて、グローバル社会で必須となる日本文化の知識まで得られる。そして、なんといってもべらぼうに面白い! 手前味噌ですが、こんなにいい趣味って他にないと思いませんか? 落語には、あなたの仕事を進化させるヒントが詰まっています。

知中論 理不尽な国の7つの論理
星海社新書
内在論理を知れば中国は怖くない──反中・嫌中の先へ
尖閣諸島への露骨な野心、反日デモにおける破壊行為、言論統制や少数民族の弾圧─。日本人の目から見た中国は、理不尽で横暴、人権も民主主義も認めない「悪い国」にほかなりません。しかし、中国を論じる視点を彼らが「バカ」で「悪」であることだけに求め、感情的な反中・嫌中に走るのは得策でしょうか? 中国には中国なりのそうならざるを得なかった事情もあるのではないか?本書ではそんな視点から、日中間に横たわる諸問題の背景にある文脈を丁寧に解きほぐしていきます。日本にとって中国は、二〇〇〇年近い交流と対峙の歴史を持つ隣国です。いま最も必要なのは、蔑視も理想論も捨ててリアルな中国と向き合う態度なのです。
中国人漫画・孫向文による漫画『中国のヤバくない日常』を併録!

テヅカ・イズ・デッド ひらかれたマンガ表現論へ
星海社新書
豊潤な「マンガの時代」は神の不在の上で花開いた
1989年、手塚治虫が死去した。その後に訪れた90年代、いつしか「マンガはつまらなくなった」という言説が一人歩きを始めた。手塚の死とともに、マンガの歴史は終わってしまったのか? いや、そのようなことは決してない。マンガ評論における歴史的空白のなかにあっても、新しいマンガたちが描かれ、読まれ、愛されているのだ。では、神の死後に生まれたマンガたちが見向きもされない現実は、マンガにとって不幸ではないのか? そして、なぜそのようなことが起きてしまったのか? 歴史的空白を「キャラとリアリティ」の観点からとらえ直すことで、マンガ表現論の新たな地平を切り開いた名著、ついに新書化。マンガ・イズ・ノット・デッド。

江戸しぐさの正体 教育をむしばむ偽りの伝統
星海社新書
「江戸しぐさ」とは、現実逃避から生まれた架空の伝統である
本書は、「江戸しぐさ」を徹底的に検証したものだ。「江戸しぐさ」は、そのネーミングとは裏腹に、一九八〇年代に芝三光という反骨の知識人によって生み出されたものである。そのため、そこで述べられるマナーは、実際の江戸時代の風俗からかけ離れたものとなっている。芝の没後に繰り広げられた越川禮子を中心とする普及活動、桐山勝の助力による「NPO法人設立」を経て、現在では教育現場で道徳教育の教材として用いられるまでになってしまった。しかし、「江戸しぐさ」は偽史であり、オカルトであり、現実逃避の産物として生み出されたものである。我々は、偽りを子供たちに教えないためにも、「江戸しぐさ」の正体を見極めねばならないのだ。

弁護士が勝つために考えていること
星海社新書
私たちは「訴訟」のことをなにも知らずに生きている
「訴えたい」と思ったことはありますか? もしくは「訴えられそう」になったことはありますか? ネットワークが発達し、LINEやツイッターなど、コミュニケーション手段が日々進化していく中、かつての生活からは想像もつかないトラブルが発生する世の中になってしまいました。そして、それがどんなに小さな火種でも、訴訟に発展しないとは言い切れません。だからこそ私たちは、紛争解決の最後の手段である「訴訟」を知らずに今を生きる訳にはいかないのです。本書では、訴訟のプロである弁護士が勝つために考えていることを通じて、民事訴訟の仕組みを明らかにするとともに、トラブルを未然に防ぐための思考を提示します。

夢、死ね! 若者を殺す「自己実現」という嘘
星海社新書
夢と自己実現の国、ニッポン
現在の日本は「夢」がやたらと優遇されすぎている。だが、夢を追い続けてきた結果、悲惨な目に遭った人々を私は散々見てきた。ミュージシャン、お笑い芸人、作家、司法浪人生、国家公務員試験受験生、学者、アーティスト、芸能人、起業したい人、フリーランスで自由に働きたい人―夢を簡単に煽って欲しくないのである。彼らがどんだけ「夢を持て」といったことばに騙されて悲惨な人生を送っているか! 本書で語るのは、そういったおとぎ話を真っ向から否定する、地に足の着いた仕事論である。さあ諸君、ワーク・ライフ・バランスに悩むのをやめ、「夢を諦める日付」を手帳に書き入れよう。仕事は元来、くだらないものなのだ。

「学問」はこんなにおもしろい! 憲法・経済・商い・ウナギ
星海社新書
この世で最も大学に行きたがっているのは、社会人だ!
星山英人は、中堅メーカーに勤める社会人1年生。やる気いっぱいで就職したものの、上司の「君は大学で何を学んで来たんだ?」という質問に答えられなかったことから、自らの教養および学術的素養の無さにコンプレックスを感じはじめる。そんな英人の相談を受けた同じく新卒の海野栞奈は、若手大学教官へのインタビューを提案。ふたりは、仕事の合間をぬって、4人の「ジセダイ教官」に会いにいくことになり……。現役若手大学教官から「知」を引き出しその社会的接点を聞く、星海社Webサイト『ジセダイ』の人気連載が新書化。「もっと勉強しておけばよかった」と思う全ての社会人に贈る、最先端の「学問入門」!