講談社文芸文庫作品一覧

東文彦作品集
講談社文芸文庫
若き三島由紀夫ガ愛した夭逝作家の世界 三島の『十代書簡集』が示すよう戦争中、文学的青春を共有、昭和18年、23歳で病に斃れた東文彦。病床で書かれた小説12編に覚書を収録。伝説の作家が甦る。
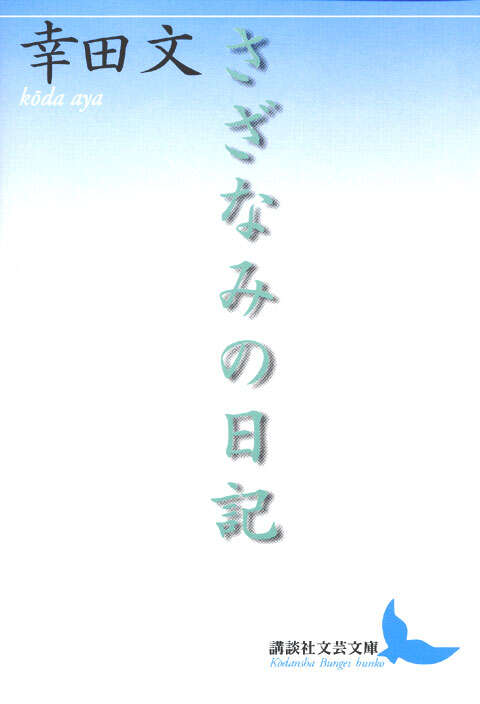
さざなみの日記
講談社文芸文庫
平凡にひそやかに生きる女たちの心のさざ波……「明るく晴れている海だって始終さざ波はあるもの、それだから海はきらきらと光っている。」――手習いの師匠を営む母と年頃の娘、そのひっそりと平凡な女所帯の哀歓を、洗練された東京言葉の文体で、ユーモアをまじえて描きあげた小説集。明治の文豪・幸田露伴の娘として、父の最晩年の日常を綴った文章で世に出た著者が、一旦の断筆宣言ののち、父の思い出から離れて、初めて本格的に取り組んだ記念碑的作品。
◎村松友視ーー濡れた和紙の束を一枚ずつていねいに剥がしてゆくような手さばきが、幸田文の文章の真骨頂だ。(中略)相手の生活を慮り、相手の気持を気遣ったあげく、その虚しさに落着したとしても、慮りや気遣いをまったく作動させずにいる人生より、一ミリほど贅沢だという余韻が、読後の私には強く残った。――<「解説」より>
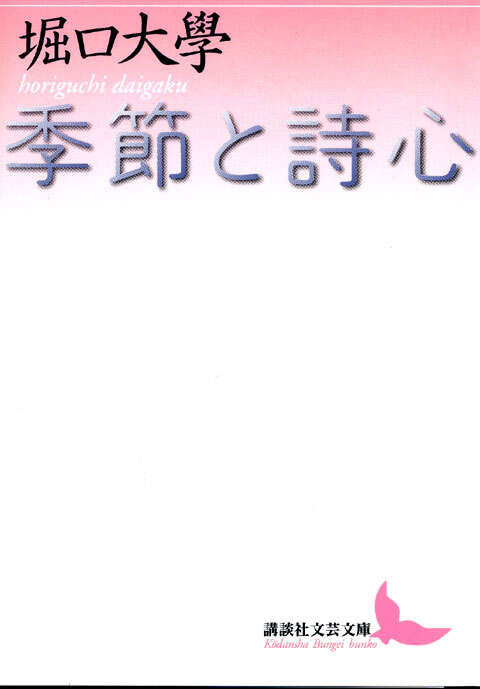
季節と詩心
講談社文芸文庫
外交官である父に伴われて、メキシコ、スペイン、ブラジルと大正期のほとんどを海外で過ごし、ベル・エポックの香気に触れた“雅び”の詩人・堀口大學。アポリネール、コクトーら、20世紀“新精神(エスプリ・ヌーヴォー)”詩人たちの息吹きを満載した訳詩集『月下の一群』は、洗練された機智と豊潤なエロスを薫風にのせて、わが国の湿潤な文学風土に送り込んだ。詩の子、恋の子、旅する子の面目躍如たる第一随想集。

うるわしきあさも 阪田寛夫短篇集
講談社文芸文庫
「サッちゃん」「ねこふんじゃった」などで、世代を超えて愛される童謡詩人・阪田寛夫は、また、片隅のささやかな人生をあえかな情感と上質のユーモアで描く稀有なる小説家でもあった。脳溢血で倒れた作曲家の叔父の滅びゆく肉体を凝視しつつ、その内で鳴り続ける最後の音楽を哀惜こめて書き留めた表題作、ほか9篇。初期作「平城山」から遺稿「鬱の髄から天井のぞく」まで、「含羞の詩人」の知られざるペーソス溢れる、デビュー作から遺稿まで50年に亘る名品を精選。

随筆 泥仏堂日録
講談社文芸文庫
昭和の光悦と称された陶芸家の雅趣と遊び心
「東の魯山人、西の半泥子」と並び称された一流の風流人――川喜田半泥子。伊勢の豪商の家に生まれ、銀行頭取、地方議員などの要職をこなしつつ、書画、茶の湯、写真、俳句と、その多芸ぶりを発揮。とりわけ陶芸では破格の才を示し、自由奔放ななかにも雅趣に富む造形世界を創造、「昭和の光悦」と声価を高める。数寄の作陶家・半泥子の陶芸論を中心とした、遊び心溢れる、貴重な随筆集。
川喜田半泥子
泥仏堂日録とは、住職無茶法師の泥に関する日記である。無茶法師とは其生れ星とやらが五黄で、干支が寅であるために、或るものが五黄の寅は無茶星だ、といったのから思いついて自ら無茶法師と名乗ったのである。禅宗でも浄土でもない。轆轤宗とでもいって置くか。――<「本文」より>
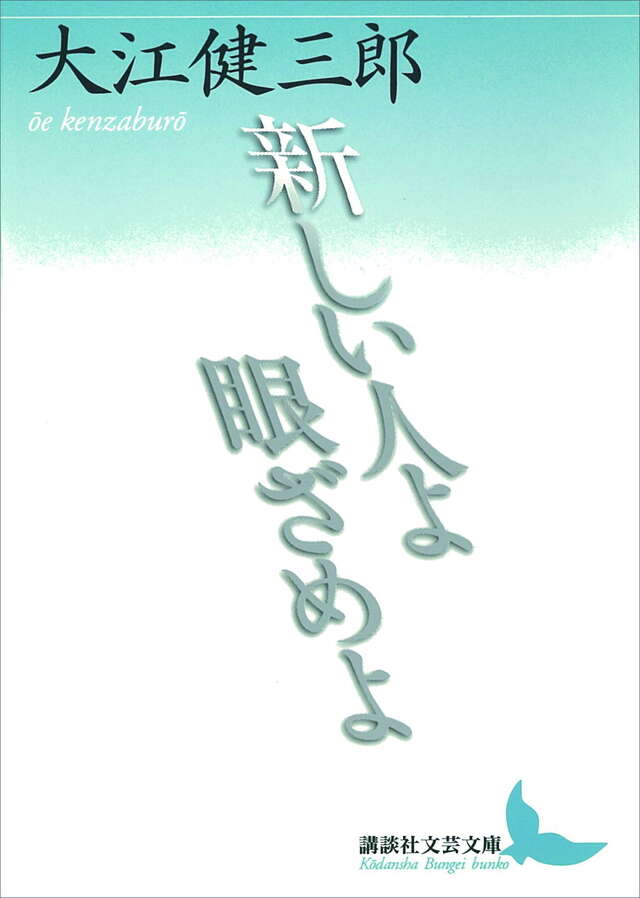
新しい人よ眼ざめよ
講談社文芸文庫
神秘主義詩人ウィリアム・ブレイクの預言詩(プロフェシー)に導かれ、障害を持って生まれた長男イーヨーとの共生の中で、真の幸福、家族の絆について深く思いを巡らす。無垢という魂の原質が問われ、やがて主人公である作家は、危機の時代の人間の<再生>を希求する。新しい人よ眼ざめよとは、来たるべき時代の若者たちへの作者による、心優しい魂の呼びかけである。大江文学の一到達点を示す、感動を呼ぶ連作短篇集。
<いま現在の僕とイーヨーの共生の意味があかるみに浮かびあがる。>
神秘主義詩人ウィリアム・ブレイクの預言詩(プロフェシー)に導かれ、障害を持って生まれた長男イーヨーとの共生の中で、真の幸福、家族の絆について深く思いを巡らす。無垢という魂の原質が問われ、やがて主人公である作家は、危機の時代の人間の<再生>を希求する。新しい人よ眼ざめよとは、来たるべき時代の若者たちへの作者による、心優しい魂の呼びかけである。大江文学の一到達点を示す、感動を呼ぶ連作短篇集。
リービ英雄
『新しい人よ眼ざめよ』は、innocence(無垢)の危機から始まる、ともいえる。(中略)ブレイクのinnocenceとexperience(経験)の歌が、おり交ぜている、という以上に、語りの言葉の一すじとなる、fatherとsonの詩が、「父親」たる語り手によって読まれている、だけでなく、読まれていること自体が物語の一主題となってゆく。このような「引用」のめざましい活かし方を一言で描ける文芸用語を、ぼくは知らない。――<「解説」より>

若い荒地
講談社文芸文庫
軍靴響く時代、詩の自由を求めた若き詩人たち
戦後詩を先導した「荒地」の詩人たち――鮎川信夫、中桐雅夫、田村隆一、三好豊一郎、北村太郎、さらには戦後を迎えることなく歿した牧野虚太郎、森川義信ら……。軍靴響く閉塞した時代のなかで、自由なる詩精神を堅持した、彼ら“若き荒地”の青春群像を、当時の詩誌「LUNA」「LE BAL」「詩集」等を綿密に辿ることで、鮮やかに再現。戦前・戦中の詩史に新たな光をあてた貴重で異色な試み。
田村隆一
(昭和16年)10月18日の夜、ぼくが新宿の『ナルシス』で、スコッチ・ウイスキーを飲んでいたことは絶対たしかだ。まだほんの宵の口で、客はだれもいなかった。所在なくひとりで飲んでいたとき、表を号外売りがけたたましい叫び声をあげながら通った。ぼくは小銭を出して号外を買った。「東条陸相に組閣の大命降下!」思わずぼくは、ガランとした酒場の中で叫んだ、むろん、声を出さずに心のなかで――「戦争だ!」――<「本文」より>

日本の童話名作選 戦後篇
講談社文芸文庫
戦争の傷跡と底抜けの希望が共に在った“戦後”名作童話21篇!
戦後、「少国民」は「子ども」にかえり、民主主義という新しい価値観のもと、童話も本来の明るさを取り戻した。子どもの視点に立つ成長物語、幼児の心を発見する幼年童話、異世界への扉をあけるファンタジーが一斉に花ひらくいっぽう、空襲、集団疎開等の記憶を語り継ぐ戦争童話も数多書かれた。そして草創期のテレビは童話を含めた子ども文化に大変化をもたらした。戦後すぐから60年代までを俯瞰する名品21篇。
●ノンちゃん雲に乗る 石井桃子
●原始林あらし 前川康男
●一つの花 今西祐行
●風信器 大石真
●おねえさんといっしょ 筒井敬介
●ぞうのたまごのたまごやき 寺村輝夫
●くじらとり 中川李枝子
●きばをなくすと 小沢正
●ちょうちょむすび 今江祥智
●神かくしの山 岩崎京子
●ちいさいモモちゃん 松谷みよ子
●ぐず伸のホームラン 山中恒
●ひょっこりひょうたん島 井上ひさし/山元護久
●そこなし森の話 佐藤さとる
●焼けあとの白鳥 長崎源之助
●夜のかげぼうし 宮川ひろ
●さんしょっ子 安房直子
●おにたのぼうし あまんきみこ
●ウーフは、おしっこでできてるか?? 神沢利子
●白い帆船 庄野英二
●花かんざし 立原えりか
――<「目次」より>
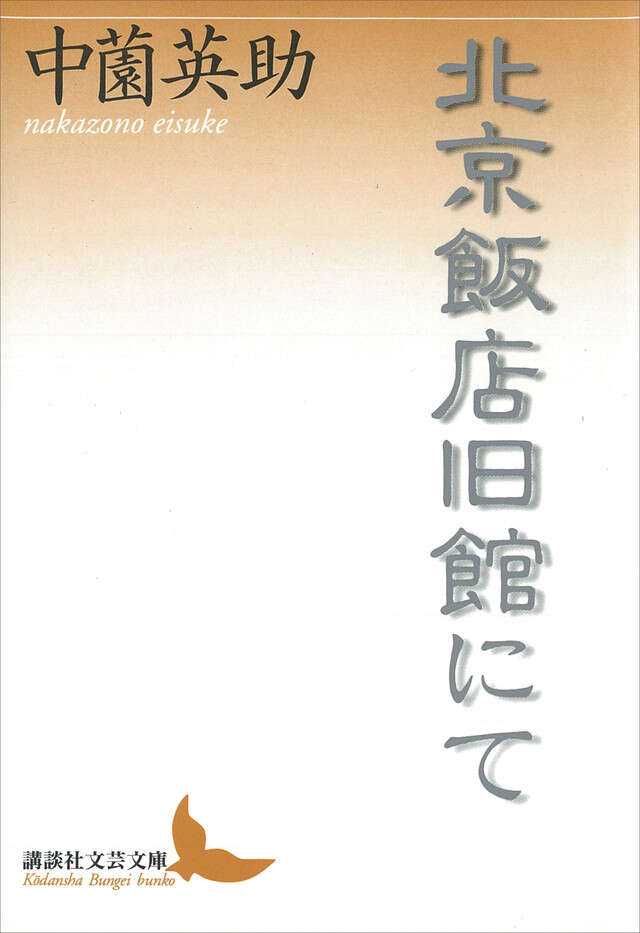
北京飯店旧館にて
講談社文芸文庫
「きみは、人類という立場に立てますか?」日本占領下の北京で出会った中国の友は、謎の問いを残し戦地に消えた。またある友は、文化大革命で迫害を受け窮死。41年の歳月を経て、青春の地・北京に還った作家は、彼我を隔てる深い歴史の暗渠に立ち竦みつつ、その底になお輝きを放つ人間の真実を探してやまない。日中の狭間に生き、書いた中薗の深い想いが結晶した代表作。読売文学賞受賞作。
北京、わが痛みと愛
「きみは、人類という立場に立てますか?」日本占領下の北京で出会った中国の友は、謎の問いを残し戦地に消えた。またある友は、文化大革命で迫害を受け窮死。41年の歳月を経て、青春の地・北京に還った作家は、彼我を隔てる深い歴史の暗渠に立ち竦みつつ、その底になお輝きを放つ人間の真実を探してやまない。日中の狭間に生き、書いた中薗の深い想いが結晶した代表作。読売文学賞受賞。
藤井省三
中薗英助一生のテーマは、越境者として歴史を語ることであった。1937年、17歳にして中国に渡って放浪語学生となり、40年に北京邦字紙の学芸記者となるかたわら同人誌で小説を書き始め、やがて45年の終戦を迎えて大陸二世の日本人女性と結婚、46年に東京へ引き揚げたという彼の青春は、日本の中国に対する全面侵略戦争とそのまま重なっており、中薗文学に国境を越えた視点から現代日中間の歴史の記憶を描くという生涯の課題を与えたのだった。――<「解説」より>

世の中へ・乳の匂い 加能作次郎作品集 荒川洋治編
講談社文芸文庫
大正期を代表する作家の人情味溢れた世界
郷里を出奔し、苦難に満ちた京都での丁稚時代をつぶさに描き、文壇的地位を確立した「世の中へ」、大正文壇に貢献した編集者でもあった著者が、その時代の痛切な一齣を活写した「羽織と時計」、郷里の海難に材をとった「屍を嘗めた話」、生涯の傑作と声価を高めた「乳の匂い」等8篇を収録。大正を代表する自然主義作家の、深く誠実な人生観照にもとづく、濃やかな人情味溢れた絶品集。
荒川洋治
若き日の生活が、文学への思いを深めさせるだけではなく、みずからの文章を励まし、支えたのではないか。故郷に心を向けながら、加能作次郎は新たな「世の中」へと向かっていた。よりひろい世界のなかに置かれる、文学の姿を夢見ていたのだ。(中略)ぼくは加能作次郎の作品を読むたびに、未知の光に顔を打たれるような、新鮮な感じにおそわれる。――<「解説」より>

ハムレット役者 芥川比呂志エッセイ選 丸谷才一編
講談社文芸文庫
諧謔愛好はハムレットの気質
快活、陽気な悲劇の主人公を演じる私もまたそれをたのしむ
シェイクスピア「ハムレット」のタイトルロールにはじまり俳優として、演出家として新風をまきおこしてきた偉大な演劇人は、名エッセイストでもあった。父・龍之介の手ほどきで演劇に目ざめたこと、母の思い出、友との交流、そして演劇への熱い思い。「ハムレット」の台詞にならう『決められた以外のせりふ』などから、その端正で洗錬された文章世界を厳選する。
芥川比呂志
芥川という姓は、多くはないが、とりわけ珍しい姓ではなさそうである。(中略)小学生の時、「アクタガワってのは、ゴミカワとも読めるな」と、つまらぬ発見をしたのは、級長の宮沢喜一で、それ以来、私にけんかを売ろうとする奴は、私のことを「ゴミカワ」と呼ぶだけで目的を達するようになった。気がとがめたと見えて、級長は、彼の発見した呼び名に見切りをつけ、その代りに「アク」という略称を用いるようになった。こっちも「ミヤ」と呼んでやった。あいこである。――<「本文」より>
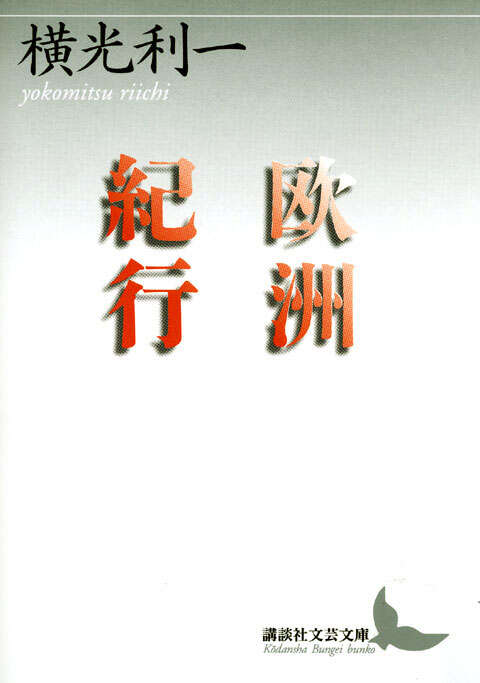
欧洲紀行
講談社文芸文庫
大戦前の激動のパリに立ち 日本精神の行方を憂う
昭和11年、ベルリン・オリンピック観戦のため、欧州へと旅立った横光利一。船上で2・26事件の報に接し、パリでは人民戦線派と右翼の激突――ゼネストに困惑する。スペインでのフランコ将軍の反乱、ドイツでのヒトラー支配の絶対化など、世界史の転換の最前線を直に知り、文明のあるべき姿を模索する赤裸で真摯な紀行文。戦時下に書かれた最後の大作『旅愁』を生み出す契機ともなった、時代精神の貴重なる軌跡。
大久保喬樹
これらの報告、感想は単なる時局的な発言といったものではない。時局から出発しながら、おのずとその背景に広がる文明史的問題にまで発展していくところが横光の真骨頂であり、(中略)この現代史の転換期に、その転換の最前線に立ち会って、横光は、この転換の世界史的意味とは何なのか、日本はこの転換にどう対応すべきか、どういう方向にむかって進むべきなのかをひたすら考えつづけていたのである。――<「解説」より>

どこか或る家 高橋たか子自選エッセイ集
講談社文芸文庫
すべて素顔の私。私らしい文章40篇を厳選ーー小説の中に表われる作家の分身……。自身そのように小説を書いてきたけれど、それは、<私>という人間そのものでは、決してない。おさない頃の京都の記憶、日々の生活を楽しんだ鎌倉、親しい友との旅、出会い、そしてパリでの霊的体験……。書きつづってきた文章の中から、40篇を選び出してみた、ほんとうの<私>をわかっていただくために。
◎高橋たか子「今、人生の最終段階にいる私は、私という者が大体どういう者であったかを、すくなくとも、すでに書いたエッセイをざっと並べる形において、わかっていただきたい、と思う。大体、と書いたが、全体は神のみぞ知る。<「著者から読者へ」より>

旅の時間
講談社文芸文庫
旅の時間に託した人生哲学。大人の小説
酒を愛で、食通として知られた著者は、気儘な旅を好み、名作『金沢』によって、月明かりの世界に、古都の漆のように艶やかな魅力を妖しく浮かび上がらせ、『時間』によって、独自な人生哲学を語った。自在な空想と想像力を駆使し、パリ、ロンドン、大阪、神戸、京都など親しく馴染んだ土地を舞台に、「生の意義」を思索した連作短篇集『旅の時間』によって、日本近代文学は確かな、ゆとりある大人の小説を得た。
清水徹
個々の作品の排列には特別の意図があったとは想像しにくいが、読んでゆくと一作ごとに≪時間≫の語られ方の気分がさらりと変えられていて、そうした短篇の排列具合から微妙に変化するリズム感が感じられる。≪旅の途中の時間≫と≪旅先での時間≫ではそれぞれに、時間の受けとめ方が、あるいは時間と空間の関係が、微妙に、しかし確実にちがう。その微妙な差異を吉田健一は独特のしなやかにうねる文章によってみごとに表出している。――<「解説」より>
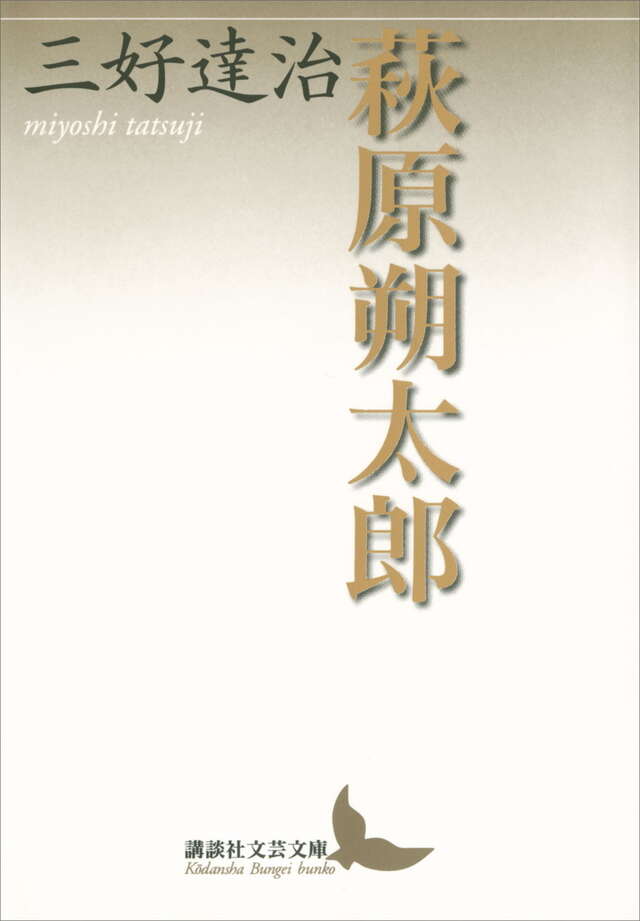
萩原朔太郎
講談社文芸文庫
昭和2年、萩原朔太郎の知遇を得て以来、昭和17年の死まで、常にその周辺にあり、さらには歿後、三度におよぶ全集の編集に携わるなど、三好達治にとって、朔太郎は生涯にわたる師であった。格調高い名文によって、朔太郎との交遊を振り返り、その面影をしのびつつ、同時に、作品の形成過程を緻密に辿る。朔太郎の詩の核心が、批評の美によって浮き上がるまさにライフワークとしての、師へのオマージュ。
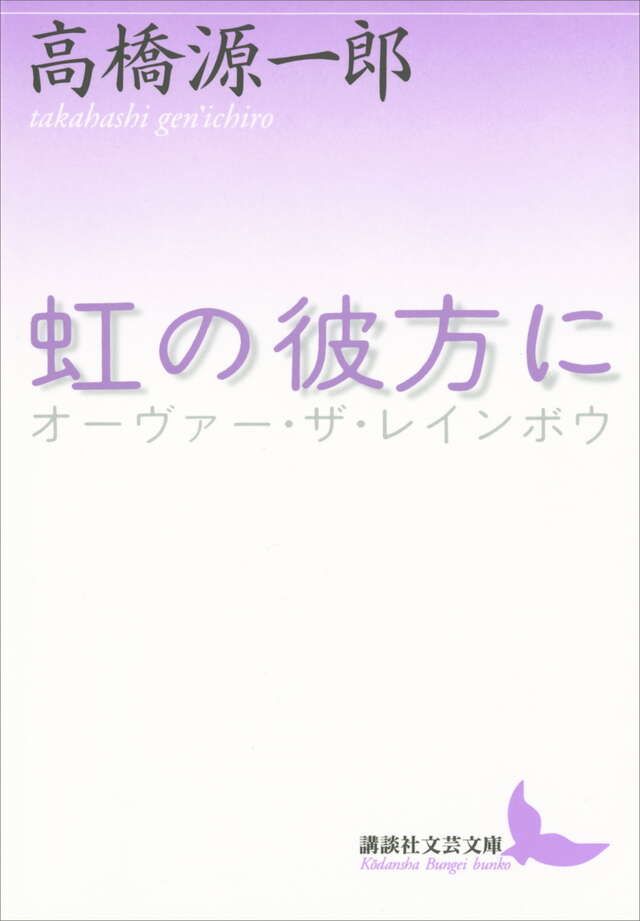
虹の彼方に
講談社文芸文庫
1973年夏、東京拘置所。『カール・マルクス』『ウルトラマン』等、夢見る囚人達と所長『ハンプティ・D』の間で演じられる可笑しくも悲痛な思想劇。『さようなら、ギャングたち』『ジョン・レノン対火星人』と並び著者の原点を示す秀作。
夢見る囚人達VS.所長ハンプティ・D(ダー)。
言葉と暴力が吹き荒れた時代への弔歌。
――この一切をはじめたのは、ほんとうは誰なんだよ!!
――だからおれの夢の中に出てくる『虹の彼方に(オーヴァー・ザ・レインボウ)』だって言ってるじゃねえか。
1973年夏、東京拘置所。『カール・マルクス』『ウルトラマン』等、夢見る囚人達と所長『ハンプティ・D』の間で演じられる可笑しくも悲痛な思想劇。『さようなら、ギャングたち』『ジョン・レノン対火星人』と並び著者の原点を示す秀作。
高橋源一郎
もし、あの時、雑誌が廃刊されなかったら。もし、あの時、他に発表のあてがあったら。もしかしたら、ぼくは、さらに『虹』を書き続けていたかもしれない。いまもなお、誰からも忘れられても、ひたすら、「全世界」を表現するはずの小説を書き続けていたかもしれない。いまのぼくには「それは間違いだ」といえる。しかし、同時に、不可能なことを可能であると信じた、その頃の自分が、そしてその頃書き続けていた作品が、眩しく見えるのである。――<「著者から読者へ」より>

焼跡のイエス・善財
講談社文芸文庫
敗戦直後、上野のガード下の闇市で、主人公の「わたし」が、浮浪児がキリストに変身する一瞬を目にする「焼跡のイエス」。少女の身に聖なる刻印が現われる「処女懐胎」。戦後無頼派と称された石川淳の超俗的な美学が結晶した代表作のほかに「山桜」「マルスの歌」「かよい小町」「善財」を収録し、戦前、戦中、そして戦後へ。徹底した虚構性に新たな幻想的光景を現出させた、精神の鮮やかな働きを示す佳作6篇。
戦前から戦後へ。
精神の運動の輝かしい軌跡を描く秀作6篇。
敗戦直後、上野のガード下の闇市で、主人公の「わたし」が、浮浪児がキリストに変身する一瞬を目にする「焼跡のイエス」。少女の身に聖なる刻印が現われる「処女懐胎」。戦後無頼派と称された石川淳の超俗的な美学が結晶した代表作のほかに「山桜」「マルスの歌」「かよい小町」「善財」を収録し、戦前、戦中、そして戦後へ。徹底した虚構性に新たな幻想的光景を現出させた、精神の鮮やかな働きを示す佳作6篇。
立石伯
石川淳の現実や時代と切り結び、闘いつづけた精神の軌跡は、一言でいえば、仮定から仮定へと飛翔するダイナミックな言葉の響きあう波動と延々とつづくその努力の線上にくっきりと刻印されている。原稿用紙にひとたび書きはじめられた言葉の力は精神の磁場を形成し、そこに生みだされた質量をバネにしながら、現実の闇のなかをペンが発明に向けて運動していくものにほかならない。――<「解説」より>

決壊
講談社文芸文庫
漂流する人々の心のわだかまり
優しさを押し売りする若者を痛烈に批判する中年のディスク・ジョッキイ、テディ・ベア(「金魚鉢の囚人」)、雨もよいの逗子のリゾート・ホテルを舞台に、抑制のきいた文章で綴る鬱屈した人々の一夜(「ビートルズの優しい夜」)、1960年代から80年代の<現実>を描き、漂うように生きる主人公たちの心に蟠(わだかま)っている信じきれぬものを抽出。ほかに表題作、「息をひそめて」、「パーティー」の傑作5篇。
小林信彦
「決壊」はとても愛着のある微妙な作品なので、今まで文庫に入れなかった。(略)「決壊」を今まで文庫に入れなかったのは、私小説というよりも、もっと私的ななにかを、他人の目に触れないところに隠しておきたかったからである。そうだとすると、活字にして発表することと矛盾するのだが、こうしたすれすれの作業が好きなのであり、なかなかやめられない。小説を書くという作業が、本来は、そういうものである気もする。――<「著者から読者へ」より>
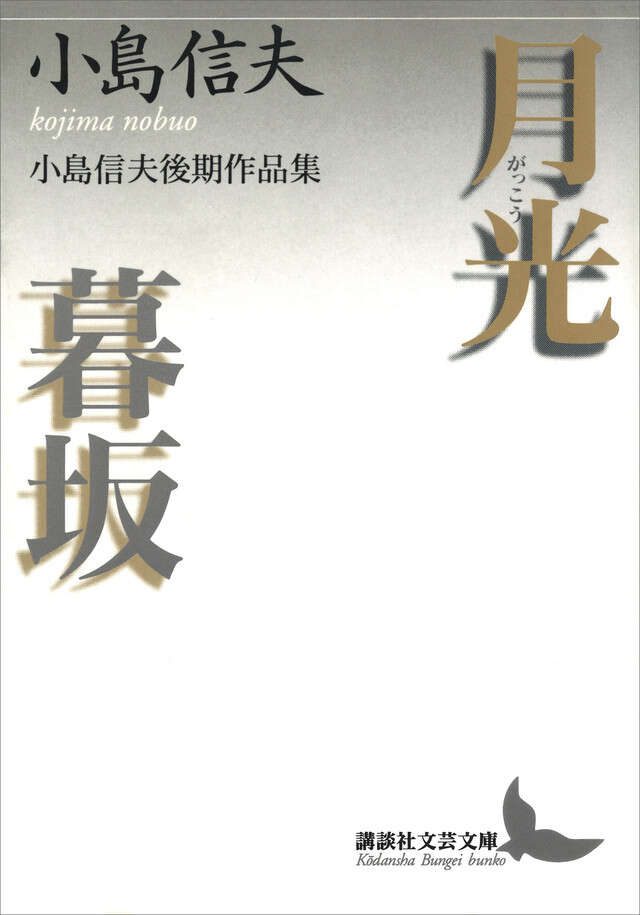
月光・暮坂
講談社文芸文庫
かつての作品の引用から、実在する家族や郷里の友人らとの関係のなかから、ひとつの物語が別の物語を生み出し、常に物語が増殖しつづける<開かれた>小説の世界。<思考の生理>によって形造られる作品は、自由闊達に動きながらも、完結することを拒み、いつしか混沌へと反転していく。メタ・フィクションともいえる実験的試み9篇を、『別れる理由』以降の作品を中心に自選した作品集。物語のあらゆるコードから逸脱し続ける作品世界!
〇小島信夫 私は、彼女がいなくなると、何か安心したように、いっきょに、たいへんな速さで娘時代から幼い頃へとさかのぼり、そのあたりのところに、自分が停滞するというか、そんな状態に見舞われた。その時代から、ゆっくりと先へ進みはじめ、不意に彼女がカチンと音を立てる。我に返ると、それがほかならぬこの私であった。――<「月光」より>

定家百首・雪月花(抄)
講談社文芸文庫
戦後、リアリズム至上の伝統歌壇に激震を起した前衛歌人の中でも歌と評論両輪の異才で光芒を放つカリスマ塚本邦雄。非在の境に虚の美を幻視する塚本は自らの詩的血脈を遡行、心灼かれた唯一の存在として宿敵・藤原定家を見出す。選び抜いた秀歌100首に逐語訳を排した散文詞と評釈を対置、言葉を刃に真剣勝負を挑む「定家百首」に加え、『雪月花』から藤原良経の項を抄録。塚本邦雄の真髄を表す2評論。
“愛しかつ憎んだ”宿敵定家に挑む
戦後、リアリズム至上の伝統歌壇に激震を起した前衛歌人の中でも歌と評論両輪の異才で光芒を放つカリスマ塚本邦雄。非在の境に虚の美を幻視する塚本は自らの詩的血脈を遡行、心灼かれた唯一の存在として宿敵・藤原定家を見出す。選び抜いた秀歌100首に逐語訳を排した散文詞と評釈を対置、言葉を刃に真剣勝負を挑む「定家百首」に加え、『雪月花』から藤原良経の項を抄録。塚本邦雄の真髄を表す2評論。
島内景二
繰り返し、言おう。邦雄の定家論は、由紀夫を含む滔々たる戦後文学の一大潮流の中で把握すべきである。龍彦もまた、然り。不可勝数の芸術家たちが群星のように燃えさかり、昼の太陽光線よりも赫く夜空を焦がした。彼らは異端・鬼才などと呼ばれたが、由紀夫という正統派の天才をマスコミの前面に押し立て、自分たちこそが芸術の正統だと高唱した。それが昭和40年代の空気だった。――<「解説」より>