講談社現代新書作品一覧

音楽のヨ-ロッパ史
講談社現代新書
古代の軍楽から国家まで音の力が歴史を変えた!
神を讃えるラッパ。声の魔力。戦場の太鼓。国歌の誕生。人心を癒し、時代を動かす力であった音楽を通して、歴史を読みなおす。

小さな農園主の日記
講談社現代新書
「旅する人」から「種まく人」へ。田園と都市を往復しながら、“五十三歳の早すぎる老境”を綴った、1年間の記録。

パソコンが野球を変える!
講談社現代新書
球種や打球の方向などをパソコンで処理する画期的システムがプロ野球を席捲している。その全貌をはじめて明かす。

銀行革命・勝ち残るのは誰か
講談社現代新書
みずほ、住友+さくら、三和+東海+あさひ、東京三菱 イトーヨーカ堂、ソニー……金融激変を読む!
巨大銀行は再生できるか。「コンビニ銀行」「ネット銀行」の成算は?気鋭のアナリストが読む金融の近未来図。

理想の病院
講談社現代新書
病院選びが生死を分けることもある!脳、心臓、がん治療の最前線から、老人医療、生活習慣病まで、全国の優良病院完全ガイド。
病院選びも医療のうち──「患者の寿命は医者次第」と言われるのに、とりあえず近所にあるクリニックや地元の病院へと駆けこむ。では、この場合で一体、何が第一の判断基準になるのだろう。世間の評判の高さ、知人の紹介、家族や親戚の勧める病院。あるいは、最初にかかった医師により別の病院を紹介してもらうケースだって珍しくない。ただ、がんや心臓病、脳の病気のような命にかかわる重い病気の場合は、うまくゆくとは限らない。そんなとき、どうしたらいいか。最近は、医療が多様化して、その病気に対する治療法も1つや2つではなくなってきた。この場合、だれに何を聞いてどう選べばいいか。自分や愛する家族の病状では、どの治療法がベストの選択なのか。そこで私はもう一歩踏みこんで、「自分がその病気にかかったら、どこまで最高の医療を受けられるか」という視点で、病院のリアルな現場を知ってみたいと思った。──本書より

セルフコントロールの心理学
講談社現代新書
悩み克服や目標達成のために心身をどう整えたらよいのか。思考、意識、イメージのはたらきをふまえつつ望ましい自己を実現するプロセスを考察。
下手な人──セルフコントロールの下手な人は、客観的には非常に限定された状況での失敗の繰り返しを、過度に一般化して解釈することが多く、そのために芳しくない自動化した反応もどんどん拡大していく。そしてこのような人は、たとえ成功を繰り返した場合でも、それを非常に幸運な特殊な状況として、過度に狭く解釈するために、望ましい自動化がなかなか起こらない。なるべく目的が達成しやすいように、状況を特定したいところである。しかし状況の特定は一定の思考であり、そのパターンは自動化する。もし状況の特定の仕方が望ましくなく、それを修正しようとするのであれば、多くの場合、反復練習によってその自動化のパターンを変える必要がある。──本書より
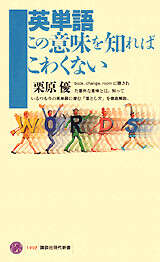
英単語この意味を知ればこわくない
講談社現代新書
book、change、roomに隠された意外な意味とは。知っているつもりの英単語に潜む「落とし穴」を徹底解説。
幹の部分の意味が大切──
availableという単語は色々なところで、色々な意味で使われています。……非常に大雑把にまとめていえば、要するにavailableは「OKだ」という意味だと覚えておけばよいでしょう。……多くの単語は(語源が異なるのに、現代の英語で結果的に同じ綴りになってしまったもの[同綴異義語]を除いて)、もとの1つの意味から段々と派生して一見異なった意味に分かれたものが多いのですから、結果的にさまざまな意味になった木の枝の部分を1つ1つ教えようとするよりも、そのもっとも太いとはいわないまでも(原義が失われている単語もありますから)、少なくともある程度の幹の部分の意味を教えた方が効果的であると思います。──本書より

謎の古代都市アレクサンドリア
講談社現代新書
『聖書』はなぜギリシア語に訳されたか?
アリストテレスの蔵書の謎とは?
ムーセイオンと幻の大図書館を擁し、地中海・東方の学者たちが集った国際学術都市。ギリシア文化を世界に伝えた知の都の実像に迫る。
アレクサンドリアの図書館長──アンティパトロスの子カッサンドロスのいわば傀儡(かいらい)としてアテナイの総督であった、先のデメトリオスは、「アリステアスの手紙」では王立図書館長として登場する。彼は、プトレマイオス2世を思わせる王から、創建された図書館の充実のため、世界中からありとあらゆる書物を、金に糸目をつけず蒐集するよう依頼される。彼は、書物を買い求め、場合によっては写本を借用して転写し、王の意図の達成に努める。そして蒐書の完璧を期すため、ユダヤ人の律法書、すなわち『聖書』をヘブライ語からギリシア語へと翻訳し、図書館に収蔵することを王に勧める。このデメトリオスの勧告が機縁となって、エルサレムから大祭司エレアザルより派遣された72人の翻訳者がアレクサンドリアに来ることになるのである。──本書より

テレビ・ドキュメンタリーの現場から
講談社現代新書
視聴率とは?良い番組とは?テレビ局で働く人々のホンネ
テレビ第一世代の女性ディレクターが語る番組制作者たちの発想と真実に迫る映像化の全プロセス。

マイルス・デイヴィス
講談社現代新書
20世紀を代表する天才音楽家は、40年以上にわたりシーンの最前線を走り続けた。残された膨大な音源から「必聴盤」を紹介し、“帝王”の魅力に迫る。
レコーディングから40年後にあたる1999年、「カインド・オブ・ブルー」にまつわる話題が内外の音楽シーンをにぎわせた……すでにピッチ(演奏の速度)が狂っていたことは数年前に解明され、現在は正規のピッチによる改訂版も発売されているが、それより注目すべきは、このアルバムが発売以来200万枚のセールスを記録し、その半数にあたる100万枚を最近の5年間で売り上げたこと──本書より

リストラと能力主義
講談社現代新書
リストラの「四つの誤り」とは何か。能力主義の致命的欠陥とは──。企業優先主義を排し、「自由と自己責任」の新雇用革命を提唱する。
暴走する日本企業──リストラの嵐が日本中を吹き荒れている。ブルーカラーもホワイトカラーも、中高年も若者も、昨日まで何ごともなく普通に仕事をしていた善良なサラリーマンに、突然リストラの魔の手が忍び寄る。一度リストラされたら、そう簡単には元の労働条件は取り戻せない。だから日本中のサラリーマンが、頭を低くしてこの嵐が過ぎ去るのをただじっと待ちつづけている。しかし、嵐はなかなかおさまりそうもない。なにしろ『経済白書』までが「雇用・設備・債務という3つの過剰の解消が重要」と「リストラのすすめ」を説いてしまうのだから、錦の御旗を手に入れた企業がリストラの手を緩めるはずなどないからである。(中略)「暴走」をしているのは、市場原理ではない。暴走しているのは、日本の企業、とりわけ人事部、企画部、役員会といった日本企業の「大本営」なのである。──本書より

日本の公安警察
講談社現代新書
オウム・革マル派との“隠された戦い”とは?
監視・尾行・盗聴・スパイ養成の実践法は?
誰にも書けなかった“治安活動”の真実!
公安警察の暗部──東京・中野のJR中野駅にほど近い一角。
コンサート会場や結婚式場として有名な中野サンプラザの裏手あたりに広大な敷地を有する警察大学校がある。
この敷地内にかつて、古びた木造の建物があった。
入り口には縦長の看板。
黒い字で「さくら寮」と記されていた。
こここそが戦後間もなくから日本の公安警察に存在する秘密部隊の本拠地だった。
その組織は「四係」と呼ばれていた。
地方分権を建て前としながら、中央集権的な機構を持つ公安警察の中枢として全国の公安警察官の活動を指揮・管理する裏組織。
いつしか警察内や関係者の間では「サクラ」の隠語を冠されて呼称されるようになる。
……戦後公安警察の暗部を辿っていくと、糸は全てが中野へと収斂されていく。
「サクラ」とはいったい何をなしてきた組織なのか。
(本書より──)

ゴシックとは何か
講談社現代新書
中世キリスト教信仰と自然崇拝が生んだ聖なるかたち。その思想をたどり、ヨーロッパを読み直す。
大聖堂はなぜ高いのか?
ヨーロッパの心を読む!
大聖堂はなぜ建てられたのか──過疎化の極にあり不活性の底に沈んでいた都市を興隆させたのは、彼ら農村からの移住者たちだった。……だがその彼らには聖性の体験の場が欠如していた。都市において財を成した者もそうでなかった者も一様に、失った巨木の聖林への思いは強く、母なる大地への憧憬を募らせるばかりだった。巨木の森と母なる大地にもう一度まみえたい。深い左極の聖性のなかで自分たち相互の、自分と自然との連帯を見出したい。このような宗教的感情を新都市住民が強く持っていたことにゴシック大聖堂の誕生の原因は求められる。他方で、裁きの神イエスの脅威も彼らに強力に作用していた。最後の審判で問われる罪は贖(あがな)っておかねばならない。免罪を求めて彼らは惜しみなく献金をした。また、天国行きを執り成してくれるマリアに聖所を築いて捧げる必要性、いや強迫観念にも彼ら新都市住民は駆られていた。だがゴシックの大聖堂が建った理由はこれだけではない。別な動機からその建設を望んでいた者たちがいた。大聖堂の主である司教、そして国王は、自分たちの権威の象徴として巨大な伽藍(がらん)の建設を欲していた。権威への意志、裏を返せば権威不足への恐れに彼らは呪縛されていた。──本書より

エリザベス一世
講談社現代新書
逆境に生まれ、大国スペインに勝ち、そして貴公子との恋……
イギリスの運命を変えた女王!
来襲する無敵艦隊を破り、華やかで冒険に満ちた時代を築いた処女王。その魅力的な実像と時代を鮮やかに描き出す。
華麗にして勇猛──ためらいや迷いは長かったが、いったん決断するとエリザベスの行動は常に素早かった。周囲の者は身を案じて止めようとしたが、エリザベスは敢然としてティルベリーの防衛軍を閲兵し、全将兵を前に演説した。「私はこの戦いのただ中で、あなた方と生死をともにする覚悟であり、また神と私の王国のため……塵の中へ命も投げ捨てる覚悟である。私は自分が女性として肉体が弱いことは知っているが、1人の国王として、またイングランド国王としての心と勇気とをもっている……ヨーロッパの君主側が王国の領土をあえて侵すようなことがあれば、それをこの上ない侮辱と考え、それを忍ぶよりは、自らも武器を取って自分があなた方の司令官となり、審判者となり、戦場におけるあなた方の働きに報奨を与える者になりたい」これを耳にした全軍の将兵も、伝え聞いた国民も奮い立ったことはいうまでもない。──本文より

知の編集術
講談社現代新書
考える力をみるみる引き出す実践レッスンとは?いいかえ要約法、箇条書き構成、らしさのショーアップなど情報の達人が明かす知の実用決定版。
私の好きな読書法──私はしばしば「目次読書法」という読み方をする。本をペラペラめくってしまう前に、比較的ゆっくり目次を眺めるのである。……そして目次をよみながら著者が書いていそうなことを想像する。むろん勝手な想像であるのだから、あたっていなくともよい。こうしておきながらやおらパラパラとページをめくり、自分の想定とのちがいを見る。そうすると、最初に想定したことが多少はあたっていたり、まったく予想はずれになることもあるのだが、その想定距離と実測距離との差異が読書を加速させ、立体化させるのである。……鉛筆やボールペンで本のページをマーキングすることも多い。……マーキングのしかたにはだいたいルールがあって、重要箇所を囲むばあいの線の種類や、固有名詞と概念名詞を区分けするマークや、あとでその1冊をさっと見て思い出せるようにしておくマーキングなど、いろいろ用意してある。──本書より

手足を持った魚たち
講談社現代新書
世界の第一人者が書きおろす「生命の歴史」シリーズ第3弾!
人類の祖先はなぜ大陸をめざしたのか
水から陸への冒険──今からおよそ3億7000万年前、不思議で重要な出来事が地球上で起こった。時はデボン紀と呼ばれる地球史上の一時代。もっとも、一般には「魚の時代」という呼び名のほうがなじみやすいだろう。ところで、なぜデボン紀は「魚の時代」なのか。それは、この時代に脊椎動物、すなわち背骨を持った動物たちのあいだで、不思議な出来事が起きたからだ。魚類型の動物が急増したのである。この動物たちは湖や川、沼地、入り江にすみついていた。そしてデボン紀の後半には、指の付いた四本の足=四肢を発達させたのだ。この「四肢動物」は、以後3億5000万年ほどのあいだに、水中生活を離れて、地上を歩き回る脊椎動物へと進化し、徐々に陸上を支配するに至った。四肢と指を持つ四肢動物には、もちろん私たちも人類も含まれる。だから、この事件は、地球にとっても私たち自身にとっても深い意味を持っている。──本書より

介護保険・何がどう変わるか
講談社現代新書
公的介護保険の「落とし穴」とは何か。「老い」をどう支えるか──。実体験から語る「介護の心得」。
介護の心得──大きな難病という爆弾を抱えて、要介護の身になって知ったあたりまえの幸せは、いまの私にとって最もいとおしく、ささやかだけれど、いちばん大切にしたいものです。老いを迎えたなかで訪れる「グッド・タイム」をいかに過ごすか、そして、それをいかに有意義なものとして継続させるか、私はいま、その実現に向かって必死にもがいている最中です。おそらく世の中の老いを迎えた多くの方々も、失ってはじめて知る幸せを身に沁みて感じながら、「グッド・タイム」を有意義なものとして過ごしたいという願望をだれもが持っているように思います。ただ、本来ならその実現をサポートするべき医療や福祉が、その役割をまったく果たしていないというのが日本の現状だと、私は自分の体験から実感しているのです。──本書より

迷う心の「整理学」
講談社現代新書
解消しにくい悩みや心の問題にどう対処すればいいのか。実行しやすく効果の大きい方法を提示。
問題との関係のあり方を変える──悩みや心の問題は死ぬまで起こり続けます。それは生きている限り変わりません。ただ心の問題に対する本人との関係のあり方は相当変わることができます。ないし、自然にずいぶん変わっていきます。ある意味で精神療法という仕事は、患者さんの問題への見方や考え方、とくに「感じ方」を変えることで問題と本人との関係のあり方を変える仕事だといえるかもしれません。……そしてこのモデルで大切にするのは常に、「今、ここの自分」です。人は「今、ここ」でしか生きていません。そして変えられるのも昔でなく「今、ここの自分」です。「今、ここ」の自分が変われば、昔の事実は変わらないけれど、昔を見る見方は変わっていきます。──本書より

「家族」と「幸福」の戦後史
講談社現代新書
家庭内でそれぞれ孤立する夫・妻・子供たち。アメリカ的豊かさの象徴であるはずの「郊外」生活が、戦後日本にもたらしたものは何か。
大量生産された家族──家族や郊外というものは、高度経済成長期の日本においていわば意図的につくりだされてきた一種の「装置」である。その家族は自然なものでもないし、伝統的なものでもない。少なくとも、今われわれが普通に思い描く家族は、戦後の高度経済成長期につくられた、きわめて特殊なものである。……家族は人々の欲望を充足させるだけでなく、同時に欲望を喚起する装置になった。すなわち、家族は大量生産されたのだ。団地や家電や自動車が大量生産されただけでなく、家族そのものが大量生産されたのだ。戦後の核家族とは大量生産された家族なのだ。そして家族はマスメディアを通して大量に広告され、大衆によって大量に消費されたのである。──本書より

日本の<地霊>
講談社現代新書
東京、大阪、神戸、広島──都市の伝説を掘り起こし、日本近代を捉え直す新しい試み。
国会議事堂は“伊藤博文の墓”だった!?
国会議事堂のピラミッド屋根──国会議事堂の屋根のかたちは、どう考えても不思議である。ふつうあのような左右対称でクラシックな建物は、中心にドームを戴く。アメリカの国会議事堂がそうであるし、ロンドンのナショナル・ギャラリー、ローマのサン・ピエトロ大聖堂など、そうした例は枚挙にいとまがない。……しかるにわが国会議事堂の屋根は、段々になったというか、階段状のピラミッドというか、じつにユニークな形態である。もともとわが国には、公共建築は左右対称に建物の構成をまとめ、その中央に塔を上げるという伝統がある。明治以来の官庁の建築、官立学校の本館(たとえば東大の安田講堂)などを思い浮かべれば、それは即座に納得されるだろう。……もっとも、左右対称式の建築は大正時代にはいると段々古くさくなってくる。大正には対称は流行らない。……しかしなぜ、遅れてきた左右対称式が国会議事堂の意匠を支配しているのか。──本書より