講談社+α新書作品一覧

日記力『日記』を書く生活のすすめ
講談社+α新書
テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、インターネット……。情報が氾濫する時代、逃してはいけない大切なことをメモにとる。日記を書くとみずみずしい感性を失わない。自分なりに、情報を自由に書く、新しい日記の書き方!
●日記を書き続けることで、変化してきたのはどんなことかというと、敏感になったことでしょう。それまでなら「まあ、たいしたことないや」と思っていたことが、「気にしたほうがいい」と感じるようになったこと。反対に、気にしていたことが「今日はこういうことがありました」でいいだろう、という考え方をするようになったのもあります。
僕が成熟することでの変化であったり、他の変化であったりします。それを隠そうとしても、毎日書き続けることで、それを見れば出てくる。だからといって、それが正解とはいえない。
日々の変化というのは、日記を書き続けることで、若返る、みずみずしい感性を保ち続けることであり、日記を読み返すことで、感性の衰えを感じることでもあります。
<日記力『日記』を書く生活のすすめ>
●インターネットでは拾えない情報
●訃報記事は過去の復活
●今日でなければ無意味なもの
●日記憲法5ヵ条
●時代を俯瞰する目
●アンテナの磨き方
●昨日と今日の微妙な変化
●日記の若返り効果
●120日坊主から始めよう
●遺言と自分史

異文化間コミュニケーションの技術―日米欧の言語表現
講談社+α新書
「next」は「今度」か、「次」なのか?表現技術の差はここにある!!
「本音と建て前」の日本語と「本音」文化の英語。
心と表現のギャップ、英語同士でも誤解や混乱を招く表現を具体例で紹介。
日米欧の表現の相違を知れば真の意思疎通が図れる!
近年、異文化理解のためのコミュニケーション研究が盛んである。しかし、多くは日英比較文化論や日米比較文化論でしかない。これでは異文化の文字が泣く。いまやアメリカとEU、そして日本の時代である。単一の国との比較文化論を論じているときではない。特にヨーロッパにおいては、EU主要国であるドイツ・フランスを論じることなしに文化を理解するのは不可能だ。ヨーロッパ文化を理解して初めて日本の活路が開かれる。
本書では、異文化間コミュニケーションの根本である言語表現を、わかりやすく例をあげて分析し、正確に把握する方法を説いた。日本語表現と比較しながら、英語を中心とした各種のヨーロッパ言語表現の神髄を理解し、彼らの考え方を探ろうというものである。個人が情報を正しく分析できて初めて、真のコミュニケーションが図れる。
<異文化間コミュニケーションの技術 日米欧の言語表現>
●欧米人から見た難解な日本語表現
●進化する日本語
●英語同士なのに意味が通じない
●英語だけでは英字新聞は読めない
●コミュニケーションを円滑にする
●心と表現のギャップ
●英語は本音、日本語は建て前
●褒(ほ)める文化、謙遜する文化
●「ASAP」は何のこと?
●ちょっと俗な言い回し

弱さを強さに変えるセルフコーチング
講談社+α新書
一流スポーツ選手を見ていると、多くのことを学ぶ。よい選手、勝てる選手ほど、自分のことをよく知っていて、よいところを伸ばす力がある。弱さに目を向けるより、よい部分をしっかり意識することで、どんどん強くなっていくのだ。この方法で、弱さを克服しようと努力することこそが、セルフコーチングであり、この手法を用いれば貴方の人生も見違えるように輝き出す!
ビジネス書を100冊読むより役に立つ「勝ち」への道!!
子どもの純粋な質問に答えることで見えてきた!
スポーツ医学の専門医が解き明かす、自分を変える考え方のコツ57。
単純明快! 自分のよさがわかれば強くなる!
子どもたちの質問に答えていると、自分が元気になってくる、そんな気がしました。それは、子どもの悩みが、じつは大人である自分の仕事や人生の悩みに重なっているからなのでしょう。
従来のコーチングの本に足りなかったのはこれだ! と感じました。よいコーチであるためには、まずはセルフコーチングができなければダメなんだ!
一流スポーツ選手を見ていると、多くのことを学びます。
よい選手、勝てる選手ほど、自分のことをよく知っていて、よいところを伸ばす力があります。弱さに目を向けるより、よい部分をしっかり意識することで、どんどん強くなっていくのです。この方法で、弱さを克服しようと努力することこそが、セルフコーチングだと思うのです。
<弱さを強さに変えるセルフコーチング>
●「勝つ」は自分の中にある
●負けたときこそ本当の力がわかる
●「コーチ力」が人を育てる
●人は誰でも聞いてほしい
●「ここ一番」に強くなる
●九割の人はネガティブ思考
●過去や未来を味方につける思考法
●元気度を数値化してみよう
●違いを受け入れる力を養う
●「可能性」は眠っている

一級建築家の知恵袋 マンションの価値107
講談社+α新書
価値が落ちない家はキッチン、トイレのつくり方でわかる!!
ベテラン設計士だから言える、財産価値が目減りしないマンション! 間取りから室内設備、構造、環境までを図版付きでポイント解説。
これで業者の力量も一目瞭然!
マンションを購入する前の下見の段階で(中略)物件を客観的に評価してくれる専門家に同行してもらうのがベストなのだが、身近にそういった専門家がいないことの方が多いだろう。
そこで、私の25年のマンション設計歴と、30社を超えるディベロッパーとのつき合いをもとに、読者にとって本当にいいマンションを見分けるポイントを解説したのが本書である。
マンション設計は経験工学といわれるほど経験がものをいう分野で、それまでにいかに多くのクレームと対峙してきたかが勝負といっていい。私自身はこの25年間に、ディベロッパーの意向に従ってユーザーに不利益を与えたこともあるが、設計責任者として数え切れないクレームを聞いてきたおかげで、今がある。

私だけの仏教 あなただけの仏教入門
講談社+α新書
「ヴァイキング」式仏教入門でわかりにくい仏教がわかる!!
各宗派の要素を自分の好みで組み合わせよう!
現役僧侶で芥川賞作家が書いた「現代仏教入門」!!
●あくまでも実践するための仏教
●仏教の発生とその基本
●「通仏教」という考え方
●対機説法と観音様の思想
●空腹の自覚
●ナイフ・フォークの用意
●一所懸命の危うさ
●食べる姿勢としての「四無量心(しむりょうしん)」
●食後のコーヒー
●求められる仏教的パラダイム
昔から日本人はヴァイキング形式で独自の文化を作ってきた。クリスマスや初詣やお盆の併存はその典型だろう。仏教各宗派の和合の状況も然り、である。ヴァイキングに並ぶ豊富な食料から自分の口や体に合ったものを選んでいただくこと。それがこの本の最終的な目標であることを、まず初めにお断りしておきたい。そうした食事形式に「ヴァイキング」と上手に命名したように、皆さんもお好きな名前をつけて「○○仏教」などと呼んでも面白いかもしれない。

LD(学習障害)とADHD(注意欠陥多動性障害)
講談社+α新書
6%はいるLD児、ADHD児を自立させる!!
子供の心がわかる話題の本!
LD児、ADHD児たちは「障害者」なのか!?
彼らが将来、社会で自立するために親や教師がすべき支援とは、障害者ではなく「個性的な人」と認められる教育を求めることだ!!
●LD・ADHDを理解する
●映画や小説のLDと仲間たち
●なぜLD・ADHDになるのか
●LDの判断と個人内差
●教育こそサービス業
●ADHDの示す困難と魅力
●行動修正は指導の基本
●よい理解者、サポーターとは
●本人への告知はいつすべきか
●社会自立のしやすや・しにくさ
学校も社会も人間関係をその基盤にしている。そのことは自分の周りにさまざまな人がおり、さまざまな個性があり、自分自身のその一員であることを、発達のなかでしっかり自覚しなければならないことの大切さを意味している。LDやADHDの存在は、これからの、個性を尊重する教育の在り方を考える貴重なモデルといえる。人が人として自信をもって生きていくには、その人らしさを失わずに、相手を受けとめ、相手に受けとめられる、そうした自然な接し方、つきあい方をお互いに学びあっていくことである。

サムライたちのプロ野球―すぐに面白くなる7つの条件
講談社+α新書
実名・実話で「野球界」のタブーを破る野球論!!
ナベツネ、広岡、コミッショナー、そして長嶋も斬る!!
「野球を知らない奴ら」からプロ野球を取り戻せ!!
大リーグより面白い「最強のプロ野球」はすぐに甦る!!
●ドジャース戦法の悲劇
●博多の夜のアポ取りに盗塁
●「長嶋式お手討ち」の実態
●パで残るのはダイエーだけ
●オリンピックに巨人軍参加の裏で
●日本進出を狙う大リーグの球団
●米コミッショナーが上原を調査
●月を使ったブロックサイン
●守備位置順に打たせた投手とは
●松井を恐れた長嶋
本来、日本の野球は野性味溢れる独特の活気に満ちていた。現在のアメリカ大リーグにも負けないほど個性溢れた選手が、右に左に走り回ってボールを追い、独特の打法を駆使してホームランをかっ飛ばしていた。
いや、なにも過去形にすることはない。いまだって、立派に大リーグに通用する選手がいるのと同じように、ほんのちょっとやり方を変えるだけで面白くなるプロ野球が、この東洋の島国にはしっかりと根づいているのである。
この本では、大リーグに決して引けを取らない日本のプロ野球の魅力、その楽しみ方をファンの諸氏に伝授するとともに、明日からでもすぐに変えられるプロ野球への提言を盛り込んだ。
いかにすれば大リーグにのみ込まれないですむか、それはただ運営のしかたいかんにかかっているのである。

娘は男親のどこを見ているか
講談社+α新書
娘の男運は父親次第だった!
娘の幸福の道へのヒント!!
なぜ娘は父を避けるのか?
なぜ恋愛や結婚がうまくいかないのか?
すべてのカギを握る男親の「父」としての能力!
お父さん、あなたは娘の「王子様」になれますか!?
●父と娘の不思議な関係
●お父さん、私の「騎士」になって
●女親はライバル!
●娘は父親にどうあってほしいか
●娘がもっともショックなこと
●性を超えた聖なる愛とは
●父親不信の女性が早い性体験を
●男性を宿命から解放する女性
●夫婦愛再生プログラム
●互いを親から解放できる夫婦
「娘のサイン」は、父親にとっての勲章なのです。自慢していい勲章です。
なぜなら、娘を愛して愛して愛し尽くしたからこそ、その信頼の証として娘が発行する「父親認定証」だからです。そして、1人の男性として、いえ、1人の人間としての立派さの証でもあるからです。
人は、どんな立派な大学を出て、どんな立派な職業に就いていても、娘から尊敬されるとは限りません。男性の智恵と勇気と愛こそ、女性を安心させ、リラックスさせる原動力なのです。
智恵と勇気は、知識の量や学歴とは無関係です。ですから、娘がお父さんのことが好き、というのは、自分を愛してくれたからということのほかに、人間として立派である、という意味も含まれるのです。
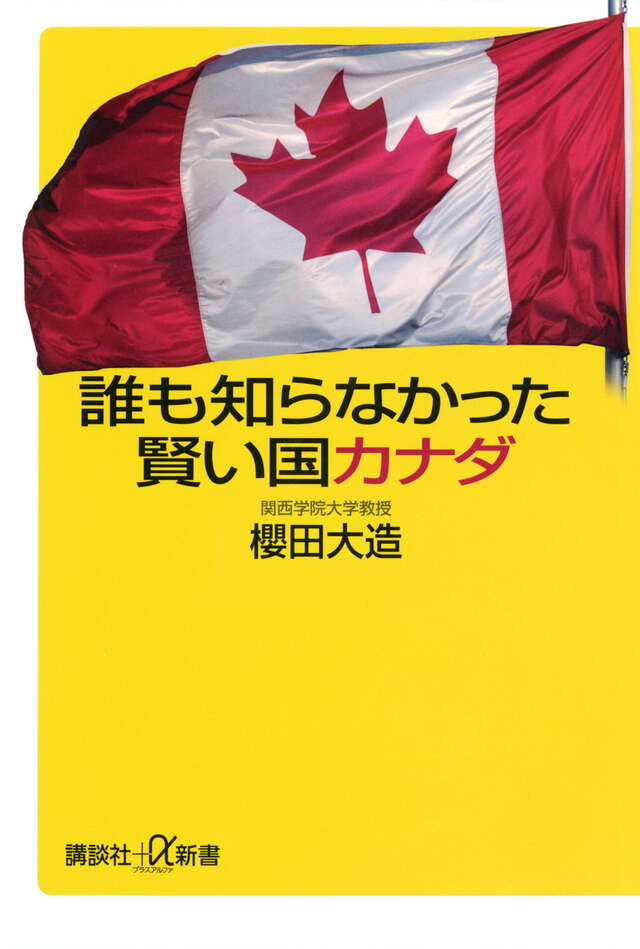
誰も知らなかった賢い国カナダ
講談社+α新書
超大国アメリカの陰に隠れて、カナダとアメリカの違いを説明できない人も多いことであろう。たしかに、両国とも主要言語が英語であったり、政治経済的には自由民主主義、資本主義であり、共通点は多い。しかし、カナダは米国とは別のアイデンティティを模索・樹立し、米国の「言いなり」にならない国だ。日本が、アメリカとは異なるカナダから学べる政策や教訓のようなものは、あまりにも多い。
米国の言いなりにならない知られざる「豊かな大国」!!
経済的規模は東京都レベルで対米貿易が8割。
しかし、対米従属ではない自主外交。政治、教育、医療……。
アメリカ属国・日本の手本はカナダにあった!
●カナダと日本の重要な関係
●少なすぎるカナダ情報
●行財政改革も大成功
●経済の泣き所=高い失業率
●自立の安全を誇るカナダ
●頭脳流出とカナダの「選択」
●「首相」が11人いる
●首相に集中する政治権限
●カナダ国王はエリザベス女王
●ケベック独立問題=分裂するか
超大国アメリカの陰に隠れて、カナダとアメリカの違いを説明できない人も多いことであろう。ふつうの日本人にとって、カナダとアメリカはほぼ同じようにみえるかもしれない。
日本人は、カナダ人というと、『赤毛のアン』くらしか知らないのがふつうだ。いや、「アン・シャーリー」さえ、アメリカ人と信じ込んでいる日本人も多いだろう。たしかに、両国とも主要言語が英語であったり、政治経済的には自由民主主義、資本主義であり、共通点は多い。しかし、カナダは米国とは別のアイデンティティを模索・樹立し、米国の「言いなり」にならない国だ。
日本が、アメリカとは異なるカナダから学べる政策や教訓のようなものは、あまりにも多い。

消えた街道・鉄道を歩く地図の旅
講談社+α新書
地図を読み、旅を創る!奥深い「地図の旅」!!
地形図片手に、道歩きそのものを楽しむ旅がある。
歩くのは廃線の鉄道跡、山中の古道、変哲もない路地。
旅行書には載らない、ちょっと冒険的で風情豊かな旅の案内。
●地形図を手に気ままな旅に出る
●か細く険しい暗越(くらがりごえ)・奈良街道
●熊野古道(くまのこどう)伊勢路・馬越峠(まごせとうげ)越え
●本州最北の廃鉄路。下北(しもきた)鉄道線
●東大雪(ひがしだいせつ)のふところ・士幌(しほろ)線跡
●古代官道名残の道・長尾街道
●閑静な家並みを貫く旧山陽道
●人吉(ひとよし)・えびのの紆余曲折の峠道
●中綱湖(なかつなこ)・青木湖間の塩の道
●小繋(こつなぎ)・御堂(みどう)間の旧奥州街道
「地図の旅」とは、(1)大勢の人が集まる盛り場・祭りの場、団体ツアーのバスが押し寄せるところ、ガイドブックに載っている名所、などは極力避け、(2)都市よりも、自然に心ゆくまでひたることのできる場所を志向し、(3)地形図で自分にとって魅力的で味わい深そうなところを探し出し、地形図を持ってそこへ行き、(4)現地では少なくとも数キロ、長ければ十数キロを足で歩き、(5)大勢ではなく1人で、または高々数人の志向を同じくする人たちだけで行き、(6)数人で行くさいにも、誰かが乗車券・宿泊などの世話をすることも、現地でガイドすることも一切せず、てんで勝手なスケジュールで現地へ行き、現地でもてんでに見たいものを見、てんでに発見し、それぞれのペースで、それぞれの興味に従って、自由に歩く、という旅です。

賢い医者のかかり方
講談社+α新書
明日の健康&フトコロに自信がありますか?
病気を正しく治すためには医者任せではダメ!
医療機関の選び方は? トクする薬の選び方は?
予防のために今できることは? 治療費のカラクリ満載!!
●日本の医療は悪くない?
●「薬漬け医療」といわれるが
●ジェネリック医薬品とは何?
●病院ごとに初診料が違う不思議
●真のセカンド・オピニオンとは?
●医師の技術をどう評価するか?
●病院によって治療費が違う!
●どんな病気が高くつく?
●どんどんふくらむ予防の費用
●自分の健康は自分で守る
「医療にかかる費用が高い」と、最近よくいわれるようになった。ここでいう「費用が高い」というのには2つの意味がある。ひとつは国全体の国民医療費が高い、ということで、もうひとつは自分の払う医療費が高い、ということだ。しかし、一般にはこの2つが一緒になって、あちらこちらで「医療費(用)が高い」との言葉が聞かれるようになった。しかし、本当に日本の医療費は高いのだろうか。後者の意味、つまり、我々の払う医療費が高いのかどうかということは、本書のテーマなので、みなさんと順に考えていくことにして、まず、国民医療費そのものが高いのかを考えてみよう。

ここまで「痛み」はとれる―ペインクリニックの最新医学
講談社+α新書
頭痛、腰痛、五十肩、がん、すべての痛みよ、サヨウナラ!!
麻酔専門医で、ペインクリニック認定医でもある著者が「痛み」の治療法を症例別に一挙紹介。鎮痛薬からモルヒネなどの麻薬まで、使われ方と副作用がわかる一冊。
●痛みに強い人・弱い人
●麻酔医と麻酔科医
●ペインクリニックと神経ブロック
●安全な頭痛・危険な頭痛
●腰痛の治療法
●術後の痛みはコントロールできる
●ストレスと痛み
●モルヒネ内服薬の副作用
●モルヒネの誤解をとく
●がんの痛みの治療 Q&A
痛みは脳で感じているが、脳は数多くの情報のうち、1000万分の1程度の、生命活動に重要なものを最優先で処理している。女性の約95%、男性の約90%が、なんらかの頭痛を経験している。現在、慢性頭痛患者は約3000万人いると推定され、その9割は医者にはかからず、市販薬での治療や、何もしないで我慢しているのが実情でる。また、人類が2本足歩行になり、私たちは、腰痛という病気から逃れられない宿命を負ったといえる。本書では誰もが経験する頭痛、現代病の代表でもある腰痛、五十肩や痛風、そしてがんの痛みなどについて解説し、薬物療法と、ペインクリニックの最新医学から、その治療法を紹介している。それが、痛みで苦しんでいる人や、今後、突然の痛みにおそわれた場合に、少しでも役立てられればと願っている。

日本語のうまい人は英語もうまい
講談社+α新書
TOEICと日本語能力テストの得点は比例する!!
英会話上達のポイントは文法でも構文でもなくキーワード。
舌がからまりそうな発音に四苦八苦するより、日本語で得意分野を強化して、コミュニケーションの達人に!!
●「キーワード式会話術」とは
●日本語能力とTOEICの関係
●実用英検1級の無残
●構文ではなく「キーワード」
●国語と外国語で違う文法の重要性
●TOEIC高得点者の構文
●日本語が下手な帰国子女の英語は
●日本文化に自信がある人の英語は
●中高年の話がわかりやすい理由
言葉は意志疎通の手段であるが、単位時間当たりの言葉の数が問題になるわけではない。むしろ、文脈と、その文脈を構成するキーワードを的確に選ぶ能力が問題になる。これは言語の種類とは、本質的に無関係である。
こんなことからも、「日本語のうまい人は英語もうまい」ということがわかる。これらの実験を通じて、日本語の確かな人が精進すれば、TOEICで高得点を望むことができる、との確信を持っている。母国語は慣れの問題ではないが、外国語は慣れの要素が大きいからである。

図解で考える40歳からのライフデザイン
講談社+α新書
会社一途でなく、好きなことでプロになる!!
人生50年から人生80年への転換の時、本業以外にもう1つ自分のテーマをライフデザインしよう。日航ビジネスマンから大学教授に転身した「凡人」の著者の人生後半30年計画!!
●やりたいことをやる
●後世に名を残す
●悟りを得る
●人生80年への組み直し
●著名人のライフプランを参考に
●三割打者を目指す
●凡人が仕事に成功する知恵
●本業以外に得意を持つ
●図解コミュニケーションを発見
●毎日の生活リズムを快適にする
昔の人は時間が短かったから、1つのことしかやれなかった。したがって1つのことに打ち込むのがよしとされた。しかし、これからは単一のことばかりやる生き方では危険です。もし時代が変ったら、新しい技術が登場したら、職場が変ったら、勤めていた会社が倒産したら、1本足で立っていたら、おしまいになります。ですから人生80年の時代は、長くなった分だけ問題や苦労も多くなり、危機管理が必要です。どっちに転んでもよい、2本足、3本足で立てる人生に組み替えなければなりません。
とりあえずは、1本足でいくけれども、並行して2本目の足を育てておく。定年になってからあわてて2本目を育てようとしても、間に合わないのです。

塀の内外 喰いしんぼ右往左往
講談社+α新書
健康はどうでもいい。「旨いもの」が喰べたい!!
刑務所のメシから世界中の有名無名レストランまで喰べ尽くし、「喰い意地が張っている」と自称する著者が、旨い店に感動し、まずい店に怒る!!
●脂がなくて旨いものか
●匂いこそ旨み
●塀の中の悲しい喰べもの
●あっちの塀の中
●魚と肴
●味なレストラン
●旨いもの屋に足が向く
●こんな店、つぶれてしまえ
●鍋、なべ、そして鍋
●旨いものにはわけがある
65歳という隠れもない爺様となった僕に、若い頃と同じかそれ以上に出来ること楽しめることは、書くことと、喋ること、それに喰べることの3つだけです。
書くことと、それに最近はちょっと舌足らずになってしまった喋ることは、暮らしを立てている仕事ですから、一生懸命努力してやっていますが、喰べることは何の苦労もありません。極く自然に、喰いしんぼがやっていられるのです。
この歳になって何でも旨いものは素材と、それに加えて料理するほうの心だ……ということを つくづく思い知りました。作る人の喰べる人への愛が籠もっていなければ、それは画竜点睛を欠きます。心の籠もっていない、愛の感じられない喰べものを喰べるのは苦痛で不快です。

ユダヤ人 復讐の行動原理
講談社+α新書
ユダヤ人の「受難と報復」は「選ばれた民」の思想にある!!
1967年の第三次中東戦争以後、エルサレム全都を支配下に置いたイスラエルの権利とは何か。
聖書の時代に「選民」の思想と「聖戦」の行動の歴史をたどる!
●ヨシュアの聖なる絶滅戦争
●神のためには許される殺戮
●ヤコブー族が復讐の大虐殺
●ソドミーとホロコースト
●人間を食人鬼に堕とす神の呪い
●イスラエル同族間の争い
●不倶戴天の異国人王妃と予言者
●ユダヤ人絶滅の企てとその報復
●反ヘレニズム闘士に残忍な弾圧
●イスラエル建国の権利とは何か
聖書のイスラエルの民は、紀元前六世紀、長年のバビロニア捕囚から父祖の地パレスチナに帰還した後、父祖たちの唯一の神を奉じるユダヤ人の宗教共同体として自覚を新たにした。このユダヤ人の子孫がふたたび亡国の民となり、中世、近世、現代と、苛酷な運命に翻弄された果てに、ついに自らの国家として回復したのが現在のイスラエルである。
彼ら、ユダヤ人の歴史という場合、起源は聖書の時代にさかのぼる。むろん、聖書は史実の忠実な記録ではない。伝承された神話や説話の要素をかなりふくんでいる。一方、聖書の中には、歴史を叙述した書がいくつもある。その歴史は、神が人間――とくに選ばれたイスラエルの民に対し、何をし、どう関わってきたかをたどり、これを伝える。本書が扱う歴史は、主としてこの聖書の記述が内容である。

究極のヨーグルト健康法
講談社+α新書
老化する腸を若返らせる乳酸菌の脅威の真実!!
腸内細菌の働きを初めて科学的に分析・検証した世界的研究者が明かす乳酸菌の秘密。
「万病の元は腸内細菌にあった」。
病気の症状別に機能性乳酸菌の効果的な利用法も公開!!
●老化する腸年齢
●増える便秘の危険性
●腸年齢チェック
●腸内細菌叢の全容がわかった
●寿命をコントロールする腸内細菌
●注目される新しい乳酸菌の機能
●がんのリスクを低減する
●アレルギー低減効果
●老人性痴呆症を予防する
●機能性ヨーグルトの選び方
私たちの体の中で、いちばん病気の種類が多いのは「大腸」だ。現代人の病気の原因の多くは、腸内環境にある。腸内細菌の種類は500種以上にもなり、そのバランスが崩れると、便秘や感染症、大腸がんや過敏性腸症候群、潰瘍性大腸炎など、さまざまな病気の原因となる。また、痴呆症や生活習慣病とも深い関係をもつ。
腸内細菌の全容がわかったことにより、これまでわからなかった乳酸菌の驚くべき機能も、あきらかにされきた。乳酸菌には、がんのリスクを低減する効果や、胃がんの原因といわれているヘリコバクター・ピロリの活性抑制効果、アレルギーを低減し、免疫活性を活発にする効果、コレステロールや血圧を下げる効果がある。本書では、ほとんどすべての機能性乳酸菌の種類と効果の最新情報を紹介している。

漱石のレシピ
講談社+α新書
胃弱だった漱石が作品にちりばめた食のかくし味!――『吾輩は猫である』の牛鍋屋、『坊っちゃん』で清がくれた金鍔(きんつば)。 作品の中に出てくる洋食と日本の家庭食の意味は? 明治から始まる日本人の激動期を、食文化の視点から考察する!
●『吾輩は猫である』の家庭食
●胃弱な漱石と苦沙彌(くしゃみ)先生
●『坊っちゃん』と天麩羅蕎麦
●博覧会と『虞美人草』
●三四郎が行かなかった食堂車
●明治家庭のカレーレシピ
●本格仏料理店、精養軒
●『明暗』のりんごは何県産か
●サンドイッチとビスケット
●漱石は最期に何を食べたのか
「漱石といえば胃が悪く、酒も弱い。ろくなもの、食べていなかったんじゃないのか?」
そんな疑問を抱かれる向きもあろう。
しかし、漱石だってやはり人間。食べてきたのである。彼が生まれたのは、まさに日本の夜明け。詳しくは本編と年譜を見ていただきたいのだが、江戸から東京に変化し、日本が西洋の料理をどんどん取り入れていく過渡期に彼は生きていた。そして小説のなかに、彼自身がつぎつぎと出合っていったさまざまな食べ物を書き込んでいったのである。
漱石を読むと、新しい食べ物を前にして、ときに驚き、喜び、ときに懐疑的に対峙した明治の日本人がみえてくる。それは、とても新鮮である。

国と会社の格付け 実像と虚像
講談社+α新書
日本を振りまわすムーディーズは何者?
格付けは正確なのか!!
ムーディーズの銀行財務格付けで、日本の銀行の多くは最低の「E」ランク評価。
この評価の基準何か、また格付けの問題点は?
格付け会社を格付けする!!
●高格付けが日本人をくすぐった
●社債の安全神話
●主要格付け会社の紹介
●格付け記号の体系
●格付けの原則
●格付けと会社の価値
●急激な格下げが招く企業の突然死
●格付けの格差はなぜ起きるのか
●日本国債と銀行の格付け
●格付けの評価は適正か
格付けという言葉が一般に知られるようになったのは、日本がバブル経済の頂点にあった1990年頃が最初だと思われます。当時は大手の邦銀には、軒並み才女右京の格付けであるAaaをつけていました。大多数の邦銀は大手の米銀よりはるかに競争力が強かったのです。もちろん、日本の国債の格付けも各社から最上級の評価が与えられていました。しかし、1998年から日本国債の格下げがはじまり、2001年12月のムーディーズによる引き下げでは、とうとうイタリアや、台湾などより低い格付けになってしまいました。
現在の格付けが妥当なものなのかということについては議論がありますが、強いものはますます高く評価されるが、いったん落ち目になれば容赦なく叩かれることは市場経済の宿命なのです。

平成名騎手名勝負
講談社+α新書
騎手は一瞬の判断に賭ける。
騎手自らが語るレース秘話!!
競馬は計算できないから面白い。
最高の大舞台G1レースで、武豊、岡部、四位、藤田らはどう戦ったのか。
関係者が著者だけに語った名勝負の真実!!
●平成競馬のキーワードとは
●なぜ、関西勢が強くなったのか
●不屈のファイティングスピリット
●最初から敵(かな)わないなんて思わない
●「ぼくの馬のほうがずっといい」
●抜け出すチャンスは必ずある
●最後の最後まで気を抜くな
●幸運に後押しされた!
●勝てなくても悲観しない
●名馬は騎手を育てる
名騎手、名勝負といっても、なにをもってそういうのか、実際に測定する客観的な基準はない。またこういうものは、ある熟成の時間を経過したあとに、いわず語らずにファンの間に定まるものだろう。その意味でいえば、まだ熟成前というおそれもないではない。
ここに書いた8つの名勝負は、クラシックレース、G1レースの中から、わたし個人がレースの(前後も)内容を見て、自身の琴線に触れた勝負と騎手を選んだ。しかし、これらは誰が見てもそれなりの輝きがあるレースだと、わたし自身は自負している。
平成年間の中央競馬の最大の特色は、関西の強さである。なぜかはまだ明確には解答は出せない。が、筆者はひそかに思っていることがある。関西の強さは、坂路(はんろ)などの物理的なものよりも、厩舎人の個性的な上昇志向である、と。