講談社+α新書作品一覧

実践「免疫革命」爪もみ療法
講談社+α新書
もむだけで治る 驚異の免疫療法!!
「福田=安保理論」実践の書!!
新潟に帰った私は、自律神経の動きを調べ、まずはアトピーやリウマチに悩まされている知人、友人数名を対象におそるおそる治療を始めたのである。治療というと何やら、大仰に聞こえるかもしれないが何のことはない。注射針を用いて頭や背中、それに手足の指の爪の生え際など自律神経のツボをチクチクと刺激するだけのことである。 するとどうだろう。それまで何年、病院に通っても効果らしい効果が現れなかった彼らの症状が、この簡単な治療をほんの数回、施すだけで、ほとんど1人の例外もなく目に見えて好転し始めたのである。「ほんとに効くんだ」――予想を上回る効果に患者も驚き、私自身も驚いた。 ――「まえがき」より
●奇跡の自律神経療法
●働きすぎるとがんになる
●がんが跡形もなく消えた
●免疫を高めればアトピーも治る
●ステロイドを使わなければ治る
●リウマチなど膠原病にも効果が
●深夜勤務でリンパ球が激減する
●病気は自律神経の異常サイン
●「リンパ球人間」と「顆粒球人間」
●両手足の爪の生え際を刺激する

強すぎた名馬たち
講談社+α新書
強さは罪か。強さに人が乱れる!馬主、厩舎、騎手が明かす真相!!
速くて強いがゆえに期待され才能をつぶされる。関係者だけが知る真実とは。トキノミノルからサイレンススズカまで、遺伝子を残さず逝った伝説の名馬が、今ここに蘇る!!
なにが歴史的名馬か、これは常に競馬界のテーマである。たぶんシンザン、シンボリルドルフ、ナリタブライアンなどの三冠馬を中心とした、いわゆる名馬になるのだろう。しかし、いま一度競馬の歴史を考えると、“スピード”という大きな潮流があることに気がつく。(中略)といった観点に立てば、それはサイレンススズカであり、ハマノパレードであり、トキノミノルである。事実トキノミノルは、明らかにスピードでシンザンをしのぎ、サイレンススズカの才能はシンボリルドルフに勝るものだった。それにもかかわらず、これらの馬は歴史的名馬にはなりえなかった。短い栄光の直後に世を去ったからである。したがって遺伝子を残さず、歴史もつくれない。その速さ、強さは語り草だが、やがてその名は、時代とともに忘れ去られていくのだろう。
●スピードの化身、神の嫉妬か
●逃げ切りとは無敵の独走なり
●自力勝負で勝つ能力はある
●小柄な体に宿る強靱な競争生命
●ダービーを勝つために生まれた
●巨体の「不沈艦」最後の真実
●スピードも能力も半端じゃない
●天才と狂気が同居した強烈な個性
●人に翻弄され才能を滅ぼす
●鬼神も避けよ、怒濤の追い込み

名人板前 日本料理の秘伝
講談社+α新書
おいしい味覚を極めた名人わざを家庭の料理に!!
毎日の料理がこんなに簡単に、おいしく変身する!和食の極意、味の「方程式」など、今日から役立つプロの手のうちを説き明かした「料理指南書」!!
日本の主食は米。その米をおいしく食べることが、和食の基本コンセプトです。日本人にとって毎日、一生食べ続けてもあきないおいしさ。米、そして水と空気。これを淡味というのは語弊があるかもしれませんが、ここに私は家庭で作る料理の真髄があると思うのです。なにげないけれど、人の心の底にスッと届く味です。 この本は、女性、男性を問わず、「おいしいものが好き」「自分の手でおいしい料理を作りたい」というすべての人に読んでもらいたいと考えて書きました。といっても、通常の料理本に出ているような形のレシピがのっているわけではありません。具体的な作り方を知ってもらう前に、レシピの奧に隠れた料理の仕組み、おいしく仕上げるために必要な手間や手順を、まずみなさんにお伝えしたいと考えたからです。
●庖丁わざは紳士の愉しみ
●刺身を引く、野菜を打つ
●「一期一会」のおいしいタイミング
●初がつおに新キャベツ
●田舎もんの口福
●プロの手のうち、味の「方程式」
●和の料理の極意は引き算
●ほとんどの煮物は「八・一出し」で
●赤身の魚はステーキでもいけます
●作りおきして使い回す卵のたれ

仏像でわかる仏教入門
講談社+α新書
仏像に手を合わせると、ほとけさまの声が聞こえてくる――如来像、菩薩像、明王像などの仏像を、どう拝めば祈りは通じるのか。さまざまな「仏像の約束事」を知り、仏像を拝むことから、仏教の教えに入っていけるようになる!
●野球で監督やコーチ、選手たちがさまざまなサインを出しているように、仏像もまた、さまざまなサインを出しています。仏像の手の指を見れば、「(略)説法をしておられるのだ」「坐禅をしておられる」(略)というようなことがわかります。手の指だけではありません。着ておられるもの、身につけておられる装身具のある・なしによって、そのほとけさまが出家された方であるか、在家の人間なのかがわかります。そうなんです、仏像にはさまざまな約束事があります。(略)仏像に手を合わせて拝むときにも、わたしたちは仏像の約束事を知っておいたほうがよいのです。仏像の約束事を知って仏像を拝んでいると、「仏像が語りかける声」が聞こえてきます。そしてその声を手がかり・足がかりにして、わたしたちは仏教の教えに入っていけるのです。
●仏像に関する1つの伝説
●原始仏教と大乗仏教の仏陀観
●偶像崇拝の禁止と仏像との関係
●仏像はほとけの最高の美を凍結
●請求書の祈り、領収書の祈り
●立体曼荼羅が持つエネルギー
●お寺が持っている3つの機能
●仏像の5分類
●お釈迦さまの3つの基本印相
●あなたのために語りかける説法

箱庭療法 こころが見えてくる方法
講談社+α新書
数多くの実証例。自分で自分のこころを開く治療法!!
なぜ箱庭をつくることで、こころの深層が動きだすのか?病んだこころが癒されるのか?実例を通して、こころの変わりゆく様子が手に取るようにわかってくる!
箱庭療法は、砂遊びの感覚があり、子どもに好まれる。不登校、情緒不安定、チック、夜尿、いじめ、抜毛など、さまざまな子どもたちが対象となっている。一方、子どもばかりでなく、思春期・青年期、さらに大人が箱庭制作に取り組むことが、心理的な問題の解決に有効であることがわかっている。対人恐怖症や抑うつ、摂食障害、職場不適応、中年期のこころの危機などにおいても、自らのこころの世界を表現し、深く体験することによって、内的な変容が促され、症状が解消したり、対人関係などの外的世界における変化が生じてくるのである。
●悲しみをこころに収めるまで
●痛みの体験が転回点
●こころの傷が癒されるきっかけ
●変化は向こう側からやってくる
●学習困難な16歳の箱庭と夢
●中年の危機の中でつかんだこと
●今までと違う「私」になるとき
●ユング少年の「偉大な秘密」
●イメージ療法から見た箱庭体験
●小さな変化が人生の質を変える

「がん」は予防できる
講談社+α新書
日本人のがん予防法を科学的に検証する!
予防効果が立証されていない食べ物に頼るより、禁煙、節酒、有効検診受診が最優先。矛盾だらけのがん予防常識を改善すれば「日本人のがんの多くは防げる」!!
次のことをまず確認しておくことは、とても重要です。
「日本人のがんの多くは、現在の知識や技術によって、すでに予防できる状態にある。医学が将来進歩するまで、手をこまねいて待つ必要はないし、待つべきではない」
意外な事実に、驚かれる方もあるかもしれません。私自身、この原稿を書くために資料をまとめながら、あらためてこう感じました。
「現在の知識や技術によって、すでに予防が可能なはずのがんで、いまも多くの人が亡くなっている。そのことが、がんを日本人の死因の第1位に留まらせていることにつながっている」
ですから、がん予防についての正確な知識を得ることは、私たちの生死にかかわる重大事なのです。最初にその点を強調しておきたいと思います。
●日本人に多いがんの共通点
●がん予防14ヵ条
●日本人の野菜・果物摂取量は十分!?
●緑茶にがん予防効果はある?
●「安全なはずの健康食品」の害
●アルコールは発がん物質と同じ扱い
●食事は重視、たばこは軽視の傾向
●がん検診は受けるべき?
●有効検診の受診率が低い日本
●がんの代替療法、4つの判定段階

野菜づくり名人の知恵袋
講談社+α新書
名人のコツを知れば野菜づくりはこんなに簡単!!
無農薬、低農薬も、小規模菜園やプランターだからこそ実現する。健康野菜に情熱を燃やす野菜づくり指導の第一人者が、初心者のための失敗しないコツを一挙公開!!
野菜づくりにはちょっとしたコツがある。そのコツを初心者が学ぶのはむずかしいかもしれない。そのポイントをわかりやすく教えているのが、私の体験農園だと自負している。農園に入園される方を指導していて感じることは、素人がおちいりやすい要点というか、つい誰でもがやってしまう失敗の決まりごとのようなことがあるということだ。無駄な失敗をしないでうまくいっている事例を、正しく表現すれば、それが「野菜づくり成功への道」になるだろう。
この本では、成功への道標となるべく、素人がついおかしてしまう失敗例、対比してプロの農家のやり方など、私の知りうるもろもろの新しい情報を織り込みながら、野菜づくりが上手になるポイントを記した。大地の自然の恵みをいっぱい受けた安全な健康野菜づくりに挑戦してほしい。
●苗はあわてて買わない
●トマトは足音で育つ
●「ママレモン」の驚くべき効果
●ピーマンは乾燥にご用心
●ナガネギは春まきがおすすめ
●ブロッコリーは立てて保存する
●ダイコン十耕
●覆土は野菜によって違う
●「元気丸」で元気な野菜を
●野菜の相性を知る

なぜ宗教は平和を妨げるのか
講談社+α新書
アメリカ教・キリスト教とイスラム教、終わりなき戦い!!
宗教・民族・領土・政治・経済の原理が世界を複雑にし、国家間や民族間対立の溝を深くする。歴史をひもとき、正義の仮面の下で宗教を歪める人間のエゴを衝く!
かねてからテロリストのゲリラ攻撃に悩まされているアメリカは、イスラム原理主義を「正義」に真っ向から対立する「邪悪」と決めつけている。だからこそテロリスト対策組織につけられた最初のコードネームは、「無限の正義」だったのである。後になって、イスラム教徒から批判を受けたため、引っ込めたものの、そこにあったのは「悪」を<対象化>させる構造であったことは明らかである。
しかし、イスラム原理主義をアメリカ自身が持つ世俗的原理主義の「投影」でないと、果たして言いきれるのだろうか。アメリカが中心となった市場原理主義が目覚ましい経済発展を遂げていく一方で、途上国の貧困がどんどん進んでいく。しかもその貧困国の大半がイスラム教圏にある。
●グローバリズムという大宣教命令
●世界貿易センターはカーバ神殿
●米大統領が失言した「十字軍」
●『コーラン』に記されている敵意
●何がイスラエルを怒らせるのか
●パレスチナは原理主義の交差点
●必ずしも平和愛好者でない仏教徒
●原理主義に走りやすいイスラム教
●紛争という家族の不幸
●人類は宗教を乗り越えられるか

プラハ歴史散策
講談社+α新書
歴史を彩る芸術家、壮麗な塔。黄金の古都をガイド!!
中欧チェコの美しい街並みを残す古都プラハ。その波乱に満ちた歴史と人物、記念的な建築物を辿り、歴史の余韻を体感する。プラハが身近になり訪れてみたくなる本!!
「黄金のプラハ」と、中世以来讃えられてきた、中欧の美しい古都。「百塔のプラハ」とも呼ばれ、塔が林立する独特の幻想的な景観を誇る町プラハ……。ヨーロッパのちょうど中央に位置するこの古都は、波乱に満ちた長い歴史を経てきた。ここでは、様々な劇的な歴史絵巻が繰り広げられ、様々な個性的な人物たちが歴史の舞台で活躍し、その記憶と記念が町のあちこちに残されている。(中略)
本書はプラハを歴史の劇場として捉え、第1部では「プラハ歴史劇場」で演じた主役と脇役にスポットライトを当てて、プラハに残る彼らの足跡と記念を訪ねながらプラハとチェコの歴史を再現し、第2部では歴史の舞台となった主要な場所を訪れて、プラハの町に刻まれた歴史の跡を辿るという意匠を凝らした。
●プラハっ子が愛したモーツァルト
●「3つの民族の町」の作家カフカ
●伝説上のプラハ創設者リブシェ
●独立運動の指導者マサリク
●ゲットーの大学者ラビ・レーフ
●最高権力の由緒ある象徴プラハ城
●「黄金の門」と聖ヴィート大聖堂
●「プラハ市」発祥の地旧市街広場
●聖像が演じる彫刻劇場カレル橋
●シナゴーグと旧ユダヤ人街

40歳からの人生を簡単にする99のコーチング
講談社+α新書
「お金」「健康」「家族」「遊び」……自分だけの最適な答えが見つかる!!
「何かと問題が多い」「だけど軌道修正は難しい」「限界を感じる」そんな40代に向けて、人生の10要素について99の質問を用意。具体例をもとにして、各人各様の答えを導き出す!!
自分だけの「答え」を見つけ出すための本。それが、この本の基本コンセプトです。このことは、コーチングの考え方にあてはまります。コーチングは「これが正解」という誰にでも共通する答えを提示するものではありません。テーマは、人生を構成する大きな10の要素に分けました。「お金」「人間関係」「時間管理」「学習」「健康」「家族」「未来」「遊び」「充実感」「老後」――です。各ページ冒頭の質問の答えを、まずは考えてみてください。本文の中では、その答えを違う角度から考え直したり、答えを深めたり、より具体化できるような考え方を示しています。20代や30代のように、一からやり直すことが難しい40代。先行きが見えない40代。そんな行き詰まり感に、ささやかな反旗を翻してみませんか。
●あといくら年収を増やしたいか
●あなたを消耗させるのは誰か
●未完了事項がどのくらいあるか
●学ぶために他の何を諦めるか
●10年前の理想体重は何キロか
●家族と共有したいものは何か
●20年前のあなたと何を話すか
●休日の終わる晩に虚しくなるか
●自分を好きな点がいくつあるか
●最期に残したい一言は何か

テレビパソコン革命の楽しみ方
講談社+α新書
ガラリと変わるパソコンとテレビの買い方使い方!!
今やパソコンはテレビチューナー内臓が当たり前。生活に革命的変化をもたらすテレビパソコン、さらには次世代テレビと次世代ビデオの全容が、この1冊でわかる!
テレビパソコンとは、パソコンにテレビチューナーを組み込んで、テレビがみられるようにしたものだ。加えて、番組の予約録画やDVDディスクへの記録もできる。これまではみるだけだったテレビの番組を情報として蓄積し、めいっぱい楽しむことができるようになった。テレビパソコンを手に入れたユーザーは、テレビ番組を簡単に録画し再生できるデジタルツールの便利さに驚き喜ぶに違いない。本書では、DVDレコーダーやハードディスクを総称して「次世代ビデオ」と呼び、解説した。同様に液晶テレビ、プラズマテレビの選び方も「次世代テレビ」として解説した。本書を読めば、テレビパソコン、次世代テレビ、次世代ビデオのすべてがわかる。テレビの新しい楽しみ方に挑戦していただきたい。
●「ネット」+「テレビ」の便利さ
●DVD再生はパソコンが簡単
●VHSをパソコンでデジタル化
●テレビパソコンの仕組み
●液晶画面を見極めるツボ
●メーカーによる違いを知ろう
●最新「ブランド」事情
●地上デジタルで何が変わる?
●入門「次世代テレビ」
●入門「次世代ビデオ」

すしの蘊蓄 旨さの秘密
講談社+α新書
奥が深い、すしの正体!!MRIで秘密に迫る!!
「旨いすしには理由(わけ)がある」を食品学の権威が科学的に実証。旨いすし飯、握り方の秘密とは?白身・赤身・魚介等ネタを見るポイントは?全国の絶品ずしも紹介!
おいしく出来上がった握りずしは、すし全体になんともいえない光沢があります。人差し指と中指でネタの上から押さえる技術によって、すし飯につやができるのだといいます。上手に押さえたすしはネタとすし飯が密着し、さらに、その間に適度の手からの体温が伝わり、握りずしの旨さが生まれるのだそうです。よく、すし職人が握ったすしは米が立っていると形容されます。確かにベテランのすし職人が握ったすし飯は、やわらかく、ほとんどの飯粒は一定の方向を向いています。しかも、すし飯を口の中に入れると、ふわぁっとして噛むと弾力があって旨いのです。
●これがプロの握り技
●上ネタ、並ネタ、頭ネタ
●初代華屋與兵衛がつくったすし
●すし職人はどの米を選ぶか
●ガリがかならずつくわけ
●大トロ、中トロのうま味成分比較
●すし店は二の切れを欲しがる
●マコガレイとホシガレイ、味の差
●タウリンが多いコウイカ
●全国の旨いすしを食べ歩く

ひきこもりと不登校
講談社+α新書
その子のもつ「特質」に根ざす心の病にどう対処するか!!
ひきこもり・不登校の状態は、苦しいものの、彼らのいまの状態は、社会的に巣立つために必要な時間。親や周囲の人で彼らの将来は決まる。対処法も解説!!
不登校の子どもは、手のかからない、素直な良い子が多いのです。やさしくて思いやりがあり、人を押しのけてまで自己主張するのが苦手という人たちは、学校という同世代の集団の中では、すごいストレスを感じてしまうのでしょう。そういう性格は、親や家庭環境や学校での教育によって影響されるものでもあるのでしょうが、やはりその人本来のもって生まれた特質の方が強く影響しています。思春期において巣立つために、彼らは、不登校という過程を通らなければいけなかったのです。しかし、その特質はけっして発達の障害や、人格的な欠陥ではありません。事実、大人になってからは、その思いやりに満ちたやさしい性格は、社会的に大きく役立っています。ひきこもりも、本人の特質に根ざす点で、不登校と一緒です。
●自律の問題としての不登校
●ひきこもりは病気か
●生きづらさをかかえた人たち
●個室化する身体と精神
●80年代におきたこと
●世界の居場所
●自律を強要する社会
●豊かな社会を生きる困難さ
●「行動する人」と「考える人」
●専門家はいないし、いらない

朝食抜き!ときどき断食!
講談社+α新書
これで万病が防げる、治る!!一日二食の「西医学」健康法!!
起きぬけの体は排泄モード。この時間に食べると、腸が汚れ免疫力が下がる。昭和初期に「暖衣飽食」の害を訴えた「西医学」の継承者の、体が根本から健康になる方法!!
今、健康のキーワードは「免疫力」です。免疫力を高める食事法をはじめ、サプリメントや健康法を紹介する本や雑誌が、飛ぶように売れていると聞きます。腸内環境を整えると、免疫力が高まることが、科学的にも実証されたそうです。それを聞いたとき、ようやく世間の動きが私に追いついてきた、と思いました。なぜなら、この免疫力こそが、私のいう自然治癒力だからです。朝食を抜くことが、腸内をきれいにして、自然治癒力を高める第一歩であると、私はもう半世紀近くも前から、訴え続けてきたのです。今こそ、再びはっきり申し上げたいと思います。健康を目指すなら、まずは朝食を抜きなさい、と。
●起きぬけの体は「排泄モード」
●「朝食を抜くと太る」はウソ
●朝食で胃潰瘍や胃がんの危険性?
●朝食を食べないほうが疲れにくい
●空腹で自然治癒力が高まる
●長生きしたければ腸を清くせよ
●脳出血の人は必ず宿便がある
●朝食抜きの生活で腸がきれいに
●ときどき断食で体内を浄化
●寒天と水でつらくない週末断食

「ムダな時間」の充電力「バカな時間」の開放力
講談社+α新書
ムダと思える時間、没頭する時間に大きな意味があった!!
スピードと効率だけでは新しいものは何も生まれない。成功者になるには柔軟な自己改革が必要。
自分の過去・現在・未来を見つめ、「時間」と「タイミング」を見失わない7つの時間術!!
1日は誰にとっても24時間なのに、時間を使いこなしている名人もいれば、時間に支配されている凡人もいる。 知識社会だから専門性が必要だとか、スピードや効率を上げないと勝ち残れないといった20世紀的な見方に縛られすぎると、自分の「時間」や自分の「タイミング」を見失う。これらを「時間病」といい、いくら情報収集や学習や資格取得をやってもムダ。体や頭や心をこわすだけだ。(中略)
時間について深く考え直すと、とてつもない変革につながる。思い切って「ムダな時間」や「バカな時間」をうまくつくることが、あなたの本来の能力を全開させるために必要である。いつも使っているものや、基準にしているものの目盛りをちょっと動かすことに成功すれば、あなたは変身できる。
●7つの時間術と時間病の治療法
●オンリーワンのとんがりをつくる
●ひらめきにはバカな時間が必要
●こつこつとムダな時間を蓄積する
●散らかり机は知的ワーカーの勲章
●コンピューターよりも紙がいい
●寿命を延ばす報酬、縮める報酬
●「過去」は「未来」の宝庫
●「現在」に意識を集中する術
●即席没頭術、スローウォーキング

「テロ」は日本でも確実に起きる
講談社+α新書
北朝鮮の核、アルカイダのテロ!!現実化する脅威!!
日本のテロ対策最前線で、世界の大量破壊兵器と向きあってきた著者が、何が起こるかわからないまま、自分で自分の身を守るために不可欠な「生きた知識・情報」を公開!
いま世界は非常に不安定な時期に突入している。北朝鮮とアメリカの核をめぐる「ゲーム」は今後、激しさを増すであろう。 私は自衛隊というミリタリー専門の組織で、核兵器、化学兵器、生物兵器というものを学んできた。そういう忌まわしい兵器による攻撃から、どう部隊を防護すればいいか、研究してきた。基本は「知識」であり、「情報」である。いかにその兵器というものを知っているか。知っていれば、対処ができる。知らなければ、逃げることすらできない。この本では、とかく無意味に隠されている核兵器、化学兵器、生物兵器、それからいま問題になりつつある放射能兵器について、私の知る情報をお伝えしたいと思っている。
●この先10年は非常に危険な理由
●アルカイダは「その機会」を狙う
●何が起こるか、3つのシナリオ
●「核は力」その冷厳なる現実
●北朝鮮、イラクの核のテロ
●北朝鮮の化学戦能力
●気になる「バイナリー」兵器
●生物兵器に立ち向かうには
●化学兵器によるパニックの回避法
●放射能兵器に対する防護法

「痛い」「だるい」は生活習慣病のサイン
講談社+α新書
だれもが感じる症状に病気が隠れている!!
身近な症状は思いがけない病気が原因だった!?自分ではよかれと思ってやっていた健康法が、じつは勘違い!?大学病院の診察室で内分泌科専門の医師がみた実例集!
「生活習慣病」という言葉をテレビやラジオなどで見聞きする機会は多いが、はたしてその意味はと問われると、なんとなく知っているだけというのが一般的で、はっきりした答えが出てこないものである。
生活習慣病というのは1つの疾患を指すのではなく、生活習慣が発症、進行に関与する一群の疾患を総称する行政用語であると、1996年の公衆衛生審議会成人病難病対策部会で明記されている。
肥満、糖尿病、高脂血症、高血圧、循環器病、大腸がん、アルコール性肝炎、骨粗しょう症、歯周病などがこの疾患群に含まれる。
このような疾患を生活習慣病というのなら、現代人はまさに「生活習慣病に脅かされる歴史上まれにみる人類」ということになる。
●「たかが」といえない身近な症状
●しびれ、けいれん
●のどの渇き
●頭痛、腹痛
●腰痛、ひざの痛み
●原因不明のだるさ
●年のせいだと思っていたら
●奇妙な症状
●症状はないけれど
●現代人の養生訓

100年住める家のつくり方
講談社+α新書
安心できる家と安心できない家のつくり方、ここが違う!!
第1に住み心地のよさ。第2に地震などの災害から家を守ること。第3に防犯。第4に住宅の欠陥保障。そして100年以上長持ちする家づくりが究極の安心につながる。
これまでに、いろいろな建築のデザインを手がけてきましたが、ぼくにとってもっとも興味深く、そして難しいのが住まいのデザインといえそうです。
21世紀にはいって、我が国の住まいづくりは、これまでのどちらかといえばつくり手、売り手主導から、住み手主導の時代へと展開しつつあります。住宅購入者の保護を目的として、住宅の品質と性能の向上をはかるため、2000年に制定された「品確法」は、まさに画期的な新法といえます。 このような新法をはじめ幅広い知識があってこそ、住み手主導の住まいづくりができるのではないでしょうか。 そこで、大げさにいえば、ビッグバンのように拡大した、住まいへの知識全般と住まいづくりについて、ぼく自身の体験も含めて、できるだけわかりやすく説明しました。
●住まいには「へそ」が必要です
●悪条件の敷地に、広く使える家
●安全な階段と危険な階段
●広さの目安は1人9坪
●天災は忘れたころにやってくる
●階段は左回りで火から逃げる
●災害に弱い危ない間取り
●泥棒もあきらめる10分間
●暖房費のいらない家づくり
●100年以上長持ちする家づくり
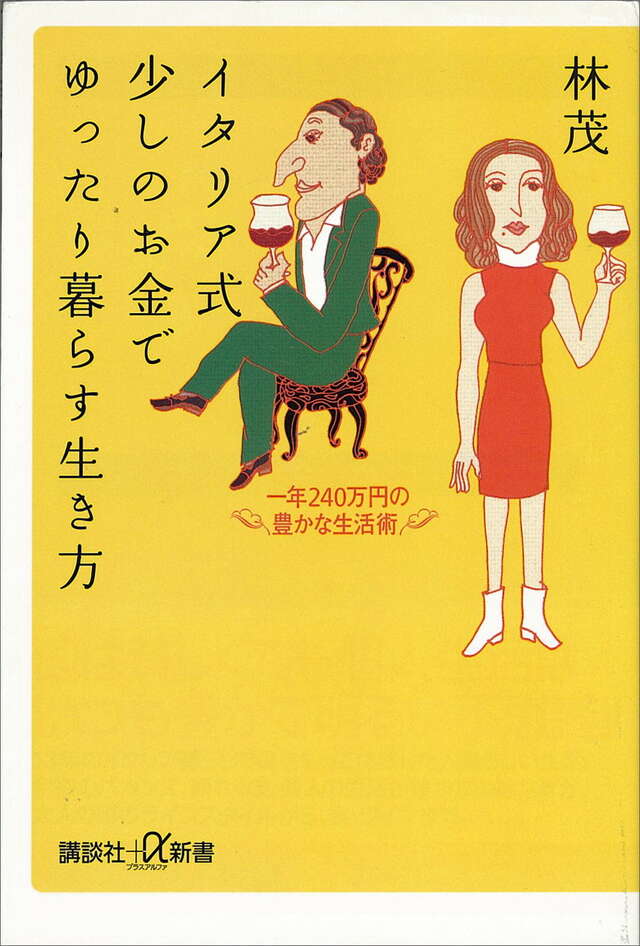
イタリア式 少しのお金でゆったり暮らす生き方
講談社+α新書
国は貧しくても個人生活はいつも豊かで明るい不思議!!
13年のイタリア暮らしで身をもって体験した人間らしい生活。余裕のバカンス、頼れる友、個人の生活が豊かなのはなぜか。大人の国のライフスタイルから、食・ワインまで。
イタリア人の年収は、平均400万円ほどだという。手取りで240万円ぐらいだろうか。(中略) 大都市や街の中心地でなければ、100平方メートルのアッパルタメント(マンション式の家)が1000万円程度で購入できる。 結婚を決めたカップルは、まず2人でためたお金と両親の助け、それにムトゥア(健康保険組合)からお金を借りて家を購入する。そして結婚式の当日には招待者をよんで新居のお披露目(ひろめ)をする。
やがて子どもが生まれ、多少の余裕ができると、今度は別荘の購入を考える。とにかく年間30日以上の休暇取得が義務づけられているので、しっかりと時間を過ごせる場所が必要だ。
●イタリア的発想の原点とは
●約束時間は「目標時間」
●「アミーコ」は一生の宝物
●年収400万円で別荘ライフ
●「貧しい国」の豊かな労働者
●イタリア式節約生活
●外食好きなイタリア人
●10歳からワインに親しむ国
●理想のイタリア料理店
●スローフードの国、イタリア

生ジュース・ダイエット健康法
講談社+α新書
体の中を簡単に解毒・浄化!ガン・痛風などに驚異の効果!!
葉も茎も、皮も種も全部使った濃厚な味。体脂肪の減少、血糖値や血圧の調整などにも抜群の効果が。
血液中のゴミを浄化し、体内の有毒物質を解毒する生ジュース絶食も紹介!
生ジュースの効用は欧米では古くから認知され、健康維持や疾病予防のためにはもちろん、あらゆる病気の治療にもとり入れられてきました。現代医学で手に負えない疾患に対しての奇跡的な治癒効果も数多く報告されています。私自身、生ジュース療法で完治した経験をもっています。それ以来、生ジュースは私の生活の一部になり、毎日グラスに最低3~4杯は飲んでいます。ハードスケジュールに追われながらも疲労を意識することなく、つねに最高の健康状態を維持しエネルギッシュに活動できるのは、まさに生ジュースのおかげです。私のアドバイスを守ってくれた人からは「3ヶ月で10キロ以上やせた」「血糖値が正常値になった」「痛風が治った」など、多くのうれしいご報告をいただきます。このような結果が出るのは、酵素栄養学ではあたりまえのことなのです。
●なぜ生ジュースは体にいいのか
●皮も種も、茎も葉も、全部使う
●フルーツジュースで活力をアップ
●朝の果物は老廃物を排泄する
●野菜ジュースで体内から若返る
●にんじんジュースで病気知らず
●生ジュース絶食でもっときれいになる
●解毒・浄化・排泄できれいになる
●生ジュース療法の処方箋
●多くの奇跡を生む生ジュース療法