講談社選書メチエ作品一覧

イスラムと近代化 共和国トルコの苦闘
講談社選書メチエ
「世俗化」=「近代化」、「イスラム」=「反動」では、ない。「共和国トルコの父」ケマル・アタテュルクによって否定されたはずのイスラムは、なぜその後も長く生き残ったのか。幾重にも複雑に絡まった糸を解きほぐし、イスラム世界における近代化の問題を「脱イスラム」のフロントランナー、トルコ共和国の歩みから読み解く。
【目次】
序章 オルハン・パムクと「東洋vs.西洋」
第一章 トルコ共和国成立前後における改革とイスラム
第二章 ポスト・アタテュルク時代のイスラム派知識人
第三章 一九五〇~七〇年代のイスラム──ヌルジュとトルコ‐イスラム総合論
第四章 第三共和政下のイスラム──ギュレン運動、公正発展党
終章 ふたたび「東洋vs.西洋」
引用出典一覧
関連文献
あとがき
執筆者紹介

ピアニストのノート
講談社選書メチエ
音楽とはなにか? 音楽をえんそうするというとはどういうことか? 沈黙と時間と音楽と、どのような関係を結ぶのか? 人間と音楽は、どのような関係を結ぶのか?
質問:あなたは翡翠で楮(こうぞ)の葉を彫刻した男のことをお話になっています。この作品が完成すると人々はそれを本物の葉と区別することができなくなりました。「演奏家の手によって、楽譜に書かれた音符が実際の音になる。この両者の変化には、どこか違いがあるのだろうか?」あなたはこの質問にどうお答えになりますか?
答え:岩壁にきざまれた仏典にならって、譜面を石の塊に刻むこともできるかもしれませんね。ピアニストは、これとは別の演奏=解釈の段階に至ります。絶えず音符を解読し、それらの音符の彼方へ行き、再び音符に戻ってきます。解釈=演奏の射程の方がはるかに大きいのです。というのも、音符の彼方への旅をする過程で、演奏家は自分自身の過去および人類全体の過去を訪れるからです。それだけでなく、遠い未来に冒険しなければならない場合さえ出てくるでしょう亜。しかしながら、演奏家が何をしようとも、音符から離れることはできませんし、繋がれ、音符に釘付けされたままです。この点においては、何にも繋がれていない、作曲の方法にすら繋がれていない作曲家とは異なっています。いざとなれば作曲家は、作曲の法則を自分で変更することもできるのですから。作曲家の人生(あるいは紙)だけが、彼のほとばしる創造の勢いを変更したり、切り詰めたりすることができるのです。
【本書においてめぐらせられる思考】
創造者=作曲家と解釈者=演奏家の違いについて
楽譜と演奏者の関係について
現代の芸術、および芸術家の堕落について
シューベルト最晩年のピアノソナタについて
愛・死など著者の個人的な生と音楽の関わりについて

ソシュール超入門
講談社選書メチエ
『一般言語学講義』。言語=システムの謎を巡る孤独な戦いの記録である。今なお輝きを失わない20世紀思想の源流を改めて問い直す。
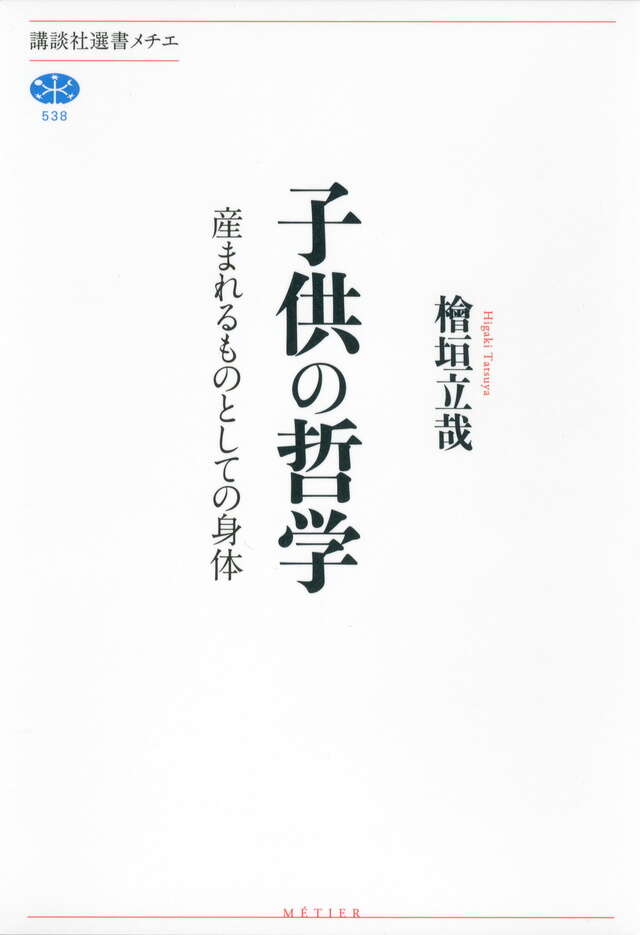
子供の哲学 産まれるものとしての身体
講談社選書メチエ
西田幾多郎、レヴィナス、ドゥルーズ……その思考のあらたな可能性これまでの哲学が再三にわたって論じてきた「私」という問題。しかしそこには、大きな見落としがあったのではないか? 産まれる、子をはらむ、産む、死んでいく、だけど誰かが残る。こうしたことを、それ自身として真正面からとらえる。そのための哲学が、ここからはじまる。
【目次】
序文 子供/妊娠の哲学のために
第1章 私と身体をめぐる伝統的議論
第2章 生命としての私へ
第3章 西田幾多郎の他者論と生殖論
第4章 レヴィナスの他者論と生殖論
第5章 私であることと「いのち」の遺伝
第6章 子供とは誰のことか――「自分の子供」概念の脱構築

昭和のドラマトゥルギー 戦後期昭和の時代精神
講談社選書メチエ
梶原一騎、ピンクレディー、阿久悠、三島由紀夫の自演映画『憂国』……戦後昭和期の時代精神の深部を〈サブカル〉から剔抉する本格評論。
【目次】
まえがき
第一章 梶原一騎 「英雄神話」としての劇画
第二章 ピンク・レディー 阿久悠と空虚な「主体」
第三章 少女ゲリラ 「ゲリラ」なき時代としての現代
第四章 『憂国』 小説、そして映画
第五章 「少年探偵団」 階級と隠された搾取の構造
あとがき

義経の冒険 英雄と異界をめぐる物語の文化史
講談社選書メチエ
「義経」の物語は、どのように生まれ、そして時代とともに変容していったか。大国主から鬼の国に至るまで、物語の基層を探る旅! 一篇の御伽草子『御曹子島渡』を手に携えて、英雄・義経の物語をめぐる旅が始まる──。『古事記』の大国主神話、吉備真備入唐譚、坂上田村麻呂と悪路王、鞍馬寺の毘沙門天信仰、陰陽道、蝦夷ヶ島などなど、古代から近世までを縦断する義経物語の遍歴を検証し、跡づける冒険的力作!
【目次】
はじめに
第一章 『御曹子島渡』の謎
第二章 鞍馬の山奥から
第三章 東北というトポス
第四章 兵法書の秘密
第五章 中世都市京都の周辺
第六章 吉備真備入唐譚をさかのぼる
第七章 蝦夷ヶ島へ
おわりに
参考文献
引用・参照資料

会社を支配するのは誰か 日本の企業統治
講談社選書メチエ
日本の企業風土にはびこる旧弊を乗りこえ、グローバル・スタンダードな企業統治(コーポレート・ガバナンス)を貫徹するべし──この通念は真なのか?
日本の企業を作りあげてきたものは何か。
“グローバル・スタンダード”礼賛の陰で見失われていた企業統治の多様なあり方を再評価する
同族経営、「物言わぬ」株主と取締役、御用組合。
日本の企業風土にはびこる旧弊を乗りこえ、グローバル・スタンダードな企業統治(コーポレート・ガバナンス)を貫徹するべし──この通念は真なのか?
大企業が果たしてきた危機克服──社長解任という統治行為の実態、この国の組織が育んできた伝統、そして「お手本」とされたアメリカの事例を検証し、企業統治論のオルタナティブを探る。
日本の会社を作りあげてきたもの、これから作りあげるものは、果たして何か?
【目次】
序章
第1章 企業統治の問題を生み出してきたもの ──株式会社制度に潜む本質的問題
第2章 日本の企業を作りあげてきたもの ──労働組合とミドルの力
第3章 日本の組織を作りあげてきたもの ──江戸期の商家・武家における統治
第4章 米国の企業を作りあげてきたもの ──ヘンリー・フォードの哲学
第5章 日本の企業を作りあげていくもの ──真の解決に向けて
注
参考文献

精神分析と自閉症 フロイトからヴィトゲンシュタインへ
講談社選書メチエ
フロイト、ウィトゲンシュタイン、自閉症理解の変更を迫る画期的試み!
永らく精神分析の「躓きの石」であった自閉症。両者の不幸な出会いを、フロイト思想の原点「心理学草案」に戻ることによって解消し、さらにはウィトゲンシュタインの思考を媒介に、新たな自閉症理論を構築する。
【目次】
はじめに──ミッシング・ピースを求めて
第一章 超自我とマゾヒズムと二人のフロイト 一九二〇年代の課題
第二章 あらかじめ失われた出発点へ帰る 初期フロイトの「心理学草案」
第三章 否定の論理・去勢の論理 二項対立と無限
第四章 自閉症を社会学へと開く 部分と全体
第五章 スペクトラム化したセカイ ライトノベルと自閉症
第六章 精神分析・隠喩・自閉症 ラカン的視点から
第七章 ヴィトゲンシュタインと嵐の中の歩行者 無意味と無価値
第八章 黄昏の風景から 私にとっての自閉症
おわりに──深夜の断想
引用文献
初出一覧

愛と欲望のナチズム
講談社選書メチエ
すべての性欲を解放せよ!!! 人間の欲望さえも動員するナチズムの〈性-政治〉。産めよ殖やせよ。強きゲルマン人の子を大量に得るために性の解放を謳うナチズム。従来の定説を覆し、欲望の禁止ではなく、解放により大衆を支配しようとしたナチズムの「性の政治」の実態に、豊富な原資料から光を当てる。(講談社選書メチエ)
すべての性欲を解放せよ!!!
人間の欲望さえも動員するナチズムの〈性-政治〉
産めよ殖やせよ。強きゲルマン人の子を大量に得るために性の解放を謳うナチズム。従来の定説を覆し、欲望の禁止ではなく、解放により大衆を支配しようとしたナチズムの生政治の実態に、豊富な原資料から光を当てる。
[本書の内容]1.性生活の効用 2.男性国家の悪疫 3.結婚を超えて 4.裸体への意志 5.ヌードの氾濫 6.道徳の解体

「イタリア」誕生の物語
講談社選書メチエ
一八世紀末、イタリア半島は小国の集合体だった。サルデーニャ王国、ジェノヴァ共和国、ヴェネツィア共和国、モデナ公国、パルマ公国、トスカーナ大公国、教会国家、ナポリ王国、ハプスブルク帝国領のミラノ公国……。フランス革命の風を受け、統一国家「イタリア」の実現を目指す「再興(リソルジメント)運動」の激しいうねり。大国フランスとオーストリアの狭間で、いかにして「想像の政治的共同体」は成立したのか?
【目次】
はじめに
地理的名称・イタリアを国家に/明治のイタリア史ブーム/イタリアへの親近感/『伊太利建國三傑』/中国と朝鮮でも
第一章 「自由の木の酸っぱいけれども甘い果実を味わった最初の国」──一七九六~一七九九年
イタリアとヨーロッパ/フランス革命とイタリア/「革命の三年間」(一七九六~一七九九年)/「姉妹共和国」の誕生/他
第二章 皇帝ナポレオンのイタリア支配──一八〇〇~一八一四年
統領ナポレオンの領土再編成/皇帝ナポレオンの領土再編成/ナポレオン支配の光と影/反ナポレオンの運動/ナポレオンの失墜
第三章 不安定な王政復古体制
ウィーン体制下のヨーロッパ/ウィーン会議によるイタリアの編成/秘密結社運動の活発化/ナポリとトリノの革命/
第四章 秘密結社運動から政党の運動へ
リソルジメント運動と亡命者たち/マッツィーニと「青年イタリア」/「青年」が意味するもの/「イタリア」の地理的定義/他
第五章 革命ではなく改革を目指した穏和派
穏和派とは/ジョベルティの『イタリア人の道徳的・文明的優位』/バルボの『イタリアの希望』/他
第六章 イタリアの長い「一八四八年革命」
一八四八年のイタリアとヨーロッパ/ミラノの煙草ストライキ/南から北へ連鎖する憲法発布/「一八四八年革命」の国際化/他
第七章 リソルジメントの国際化
第二次王政復古時代の特徴/憲章を堅持したサルデーニャ王国の動向/サルデーニャ王国に流入した亡命者/他
第八章 職人的なイタリア統一
第二次独立戦争の開始/中部イタリアにおける反乱とヴィッラフランカ休戦協定/サルデーニャ王国に併合された中部イタリア/ガリバルディの「千人隊」/他
第九章 半島の名前から民族の名前となったイタリア
統一に「洗礼」を授けた住民投票/イタリア王国の誕生/カヴールの急逝に対する反応/「歴史的右派」政権が取り組んだ諸問題/他
第十章 「クオー・ヴァディス、イタリア」──「おわりに」にかえて
「イタリアよ、何処に行きたもう?」/論争の二つの契機/近現代イタリアにおける三つの異なる政治体制/一九一一年の統一・五〇周年/他
あとがき
文献案内
年表

ドイツ観念論 カント・フィヒテ・シェリング・ヘーゲル
講談社選書メチエ
「いま」「ここで」、〈それでよい〉と語る勇気。近代的思考の基礎を作ったドイツ観念論の四人の代表的哲学者。彼らの思想の核心には、歴史の「これから」におのれの身一つで踏み出す勇気と決断があった。先達の思想を受け継ぎ、かつ乗り越えて行くダイナミックな思想の歩みを、これまでになく平易かつ明快に解説する。(講談社選書メチエ)
「いま」「ここで」、<それでよい>と語る勇気
近代的思考の基礎を作ったドイツ観念論の四人の代表的哲学者。彼らの思想の核心には、歴史の「これから」に、おのれの身一つで踏み出す勇気と決断があった。先達の思想を受け継ぎつつ、かつ乗り越えて行くダイナミックな思想の歩みを、これまでになく平易かつ明快に解説する。
[本書の内容 ]
●ドイツ観念論とは?
●カント『純粋理性批判』の「歴史哲学」
●フィヒテの『知識学』──フランス革命の哲学
●シェリング──自然史と共感の哲学
●ヘーゲル『精神現象学』──真理は「ことば」と「他者」のうちに住む

東シナ海文化圏 東の<地中海>の民俗世界
講談社選書メチエ
中国、朝鮮、琉球、台湾を一つの視野におさめ、「東の地中海」=東シナ海をめぐる地域に通底する基層文化を見通すための基軸を、多様な民俗現象から掘りおこす。
【目次】
はじめに
第一章 呉越文化の広がり
第二章 農、交易、生死
第三章 他界 魂は故郷をめざす
第四章 女の世界
第五章 『大長今』の世界から 一六世紀基層文化の事例研究
第六章 祭祀世界
おわりに まとめに代えて
あとがき
参考文献
関連サイト一覧
東方地中海地域文化関係略年表
索引

「三国志」の政治と思想 史実の英雄たち
講談社選書メチエ
「水魚の交わり」劉備と諸葛亮のあいだには、実は厳しい緊張関係があった!
曹操の「革新」とは何か?
孫呉の盛衰はどのような力学に動かされていたか?
三国志の英雄たちが活躍した舞台は、自らの権力を確固たるものにしたい君主たちと、儒教的思想と文化・名声を力とする「名士」がせめぎ合う、緊迫した政治空間であった。
中国史上の大転換点として、史実の三国時代を当代の第一人者が描ききる。
小説、漫画、ゲームで描かれる英傑たちの、「本当の闘い」がよくわかる画期的論考!
●主な内容
黄巾の乱と群雄割拠
文学の宣揚
孫氏の台頭
劉備と諸葛亮
君主と文化
孫呉政権の崩壊
魏晉革命と天下統一
中国史上における三国時代の位置

西洋哲学史 3 「ポスト・モダン」のまえに
講談社選書メチエ
大反響の「西洋哲学史」第3巻、刊行!
多様な中世哲学をあつかう第2巻をひきついで、近世そして近代へ。
近世によみがえるヘレニズム哲学。デカルト、ホッブズ、スピノザ。アリストテレス哲学の展開から、ヘーゲル、マルクス、ハイデガーへ。
近代哲学へと向かう哲学史の脈動を豊かな視点からとらえる!
【目次】
序論 アウグスティヌス主義の射程 熊野純彦
1.ヘレニズム復興 大西克智
2.近世スコラと宗教改革 楠川幸子(宮崎文典訳)
3.デカルトと近代形而上学 村上勝三
4.ホッブズとスピノザ 上野修
5.アリストテレスの子供たち――ヘーゲル、マルクス、ハイデガー 神崎繁
附録 人名・書名総索引

戦前昭和の国家構想
講談社選書メチエ
関東大震災の三年後に始まった戦前昭和とは、震災復興=国家再建の歴史だった。
社会主義、議会主義、農本主義、国家社会主義という四つの国家構想が、勃興しては次の構想に移っていく展開の過程として、戦前昭和を再構成する!
【目次】
プロローグ
I 社会主義
II 議会主義
III 農本主義
IV 国家社会主義
エピローグ
註
参考文献
あとがき

「ひとりではいられない」症候群 愛と孤独と依存症をめぐるエッセイ
講談社選書メチエ
絶対的な孤独感から自分を守るためあらゆるものに依存を余儀なくされる現代人の病理を豊富な臨床事例から解読、その処方箋を提示する

古代エジプト文明 世界史の源流
講談社選書メチエ
世界史の中で古代エジプト文明が果たした役割とは何か。ミノア、ヒクソス、アッシリア、ペルシア、ギリシア、ローマ……西洋世界の源流のひとつとしてエジプトを捉えたとき、まったく新たな歴史像が立ち上がる。最新の研究成果をふんだんに盛り込み、「外」とのインタラクションという視点の下にその興亡を描き直す、画期的試み! (講談社選書メチエ)
一神教の起源・「モーセ」と「アクエンアテン」、エジプト王国最後の象徴「クレオパトラ」、謎の民族「海の民」の正体、世界に広がる「エジプトの神々」と「来世信仰」、異民族「ヒクソス」の実像と「最古の戦争」カデシュの戦い
歴史の焦点がここにある!
世界史の中で古代エジプト文明が果たした役割とは何か。ミノア、ヒクソス、アッシリア、ペルシア、ギリシア、ローマ……西洋世界の源流のひとつとしてエジプトを捉えたとき、まったく新たな歴史像が立ち上がる。最新の研究成果をふんだんに盛り込み、「外」とのインタラクションという視点の下にその興亡を描き直す、画期的試み!

西洋哲学史 4 「哲学の現代」への回り道
講談社選書メチエ
オッカム、ロック、ヒュームの唯名論とパースやホワイトヘッドのの実在論。カントの弁証法とヘーゲルの弁証法。
ラベッソンとベルクソン・・・。
多様な視角から「哲学の現在」への道標を照射する。
【目次】
序論 ふたたび、哲学と哲学史をめぐって 熊野純彦
オッカムからヒュームへ 乗立雄輝
ライプニッツからバウムガルテンへ―美的=感性的人間の誕生 小田部胤久
ふたつのDialektikをめぐって―カントの弁証論とヘーゲルの弁証法 熊野純彦
同一哲学から積極哲学へ―シェリングの思索の軌跡 滝口清栄
思考と動くもの―「スランス・スピリチュアリムス」をめぐって 杉山直樹
あとがき 熊野純彦
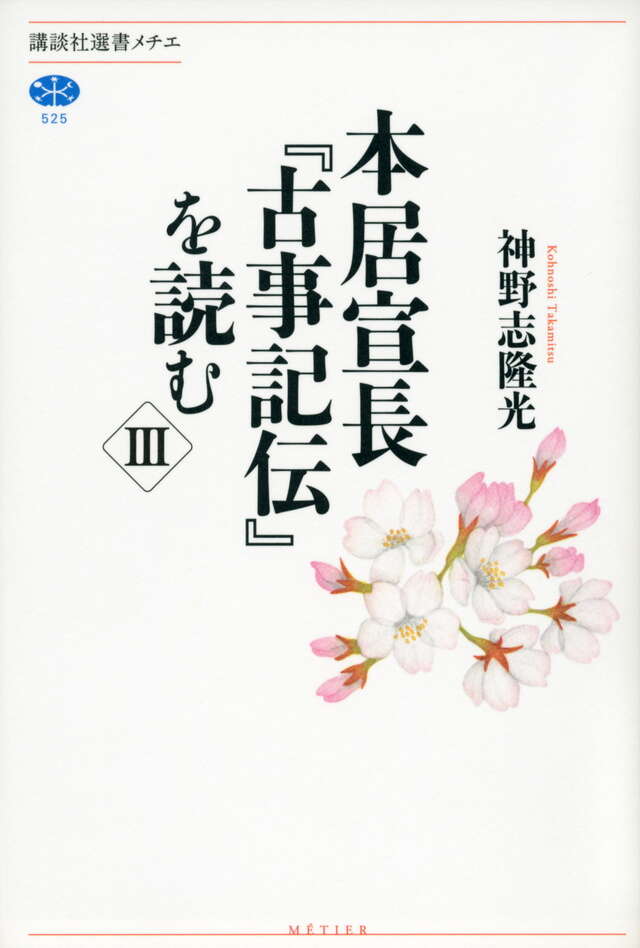
本居宣長『古事記伝』を読む 3
講談社選書メチエ
本居宣長の大著『古事記伝』──。厖大・多岐にわたるその注解を、全四十四巻すべて読み通す、画期的シリーズの第3巻、いよいよ登場。第3巻は、二十一之巻から三十一之巻まで、すなわち綏靖天皇から仲哀天皇の下巻まで。三輪山伝説、倭建命の西征東征、神功皇后の新羅征討などをあつかう。
三輪山伝説、倭建(ヤマトタケ)命の西征東征、神功皇后…
たゞ大らかなるぞ、真のありかたにはありける…
宣長は『古事記』になにを読み取ったか!?
本居宣長の大著『古事記伝』──。
厖大・多岐にわたるその注解を、全四十四巻すべて読み通す、画期的シリーズの第3巻、いよいよ登場。
第3巻は、二十一之巻から三十一之巻まで、すなわち綏靖天皇から仲哀天皇の下巻まで。三輪山伝説、倭建命の西征東征、神功皇后の新羅征討などをあつかう。
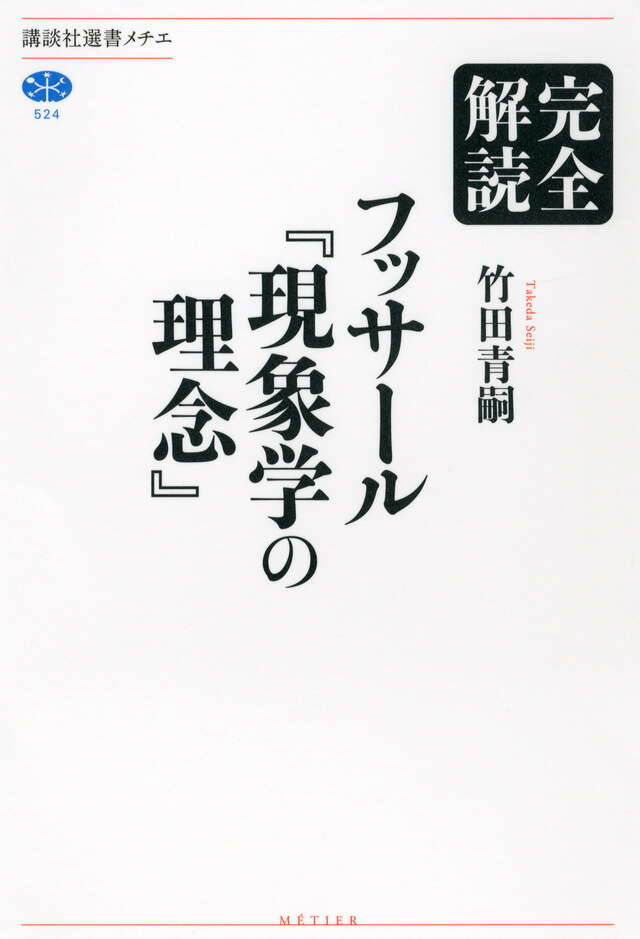
完全解読 フッサール『現象学の理念』
講談社選書メチエ
完全解読シリーズ第4弾は、現象学の祖フッサール前期の代表作。主-客問題を批判し認識問題に大転換をもたらした画期的著作を読む。さまざまな誤解にさらされてきた現象学の根本を、精緻な読みによって明快に解説する。