講談社選書メチエ作品一覧

漢字の魔力 漢字の国のアリス
講談社選書メチエ
漢字のワンダーランドへようこそ! 古代から現代まで、中国の多彩な資料を渉猟する著者がガイドする、摩訶不思議な文字の世界の冒険
【目次】
プロローグ 漢字の国へ
第一章 辞書にない漢字
第二章 文字の呪力
第三章 名前の秘密
第四章 漢字が語る未来
第五章 怪物のいない世界地図
第六章 漢字の博物学
第七章 絵のような漢字と漢字のような絵
第八章 浮遊する文字 漢字のトポグラフィー
第九章 漢字が創る宇宙
エピローグ
注
あとがき 十年と一夜の物語

ギリシア正教 東方の智
講談社選書メチエ
「東」のキリスト教――その深い智慧への誘い
カトリックともプロテスタントとも異なる「もう一つのキリスト教」。
東西教会分裂の原因となった「フィリオクェ」問題、アトス山などの修道生活で発展した独自の瞑想技法、華麗にして深遠なるイコンの世界など、「東」のキリスト教思想の奥義に迫る。

音楽とは何か ミューズの扉を開く七つの鍵
講談社選書メチエ
この不可思議な芸術が持つ“魔力”の根源への探究
空気の波動である音が、時に甘美に心を溶かし、時に激しく魂を揺さぶる魔法となる。この不可思議な音楽というものの正体を、クラシックをはじめ、ロック、民族音楽などの多彩な音と音楽学にとどまらない多様な視点から探究する。すべての音楽好きに贈る、あざやかでかろやかな論考。
【目次】
第1章 音楽は魔法である Music is magic?
第2章 音楽はシステムである Music is system?
第3章 音楽は表現である Music is expression?
第4章 音楽はリズムである Music is rhythm?
第5章 音楽は旋律である Music is melody?
第6章 音楽はハーモニーである Music is harmony?
第7章 音楽はコミュニケーションである Music is communication?
エピローグ──結語に代えて
注
あとがき

道教の世界
講談社選書メチエ
「道」とはなにか。高度な哲学的思弁と卑俗な民俗信仰の入り交じる、混沌と矛盾に充ち満ちた不可思議な思想。教団・経典の解説から「気」の思想、妖怪怪異の世界にいたるまで、複雑怪奇な道教の世界の神髄を縦横無尽に解き明かす。
【目次】
はじめに
第一章 しいたげられた心の救い
老子/宗教/自然観
第二章 転変する世界の肯定
教団/経典/神統譜
第三章 その喧騒のただなかで
山岳信仰/仙人/女神
第四章 陰気が陽気を犯すとき
文学/怪異/年中行事
第五章 体のなかは虫だらけ
民俗/医療/日本文化
第六章 十中八九でたらめでも
学術史/学者/現在
あとがき
参考文献
索引

記憶の歴史学 史料に見る戦国
講談社選書メチエ
「歴史」はどのようにして生まれるのか。本能寺の変、細川ガラシャ自害などの事件の記録を元に、記録が歴史となるプロセスを探る。
【目次】
はじめに
第一章 史料学と記憶
1 史料としての人間の記憶
2 日本前近代史のなかで集合的記憶を考える
第二章 記憶と史料と歴史のあいだ
1 史料と歴史的事実
2 史料同士のすれ違い
3 歴史が記憶にたどりつく
第三章 歴史をつくった記憶
1 太田牛一の視点
2 細川家の視点
3 史実の相対化と記憶
第四章 記録と記憶
1 記憶が日記になる瞬間
2 記録の改変と記憶(その一) 『断腸亭日乗』のばあい
3 記録の改変と記憶(その二) 『兼見卿記』のばあい
第五章 覚書と記憶
1 覚書の時代
2 上杉家の集合的記憶
3 上杉家・佐竹家と大坂の陣
第六章 文書と記憶
1 岩屋家と岩屋家文書
2 岩屋家相論と文書のゆくえ
3 文書から生まれる記憶
終章 歴史と記憶
注
引用史料
参考文献
あとがき
索引

魂と体、脳 計算機とドゥルーズで考える心身問題
講談社選書メチエ
本当に存在するものは何だろうか?
私の「今・ここでの体験」だろうか? それとも、他人からみた「物質としての脳」だろうか?
もちろん、両方だろう。
ところが、そう言った瞬間、「私の」体験と「他人からみた」脳を結ぶメカニズムが知りたくなる――
ライプニッツのモナドロジー、ドゥルーズの思考を、コンピュータ・シミュレーションで展開。
心身問題への新たなアプローチがはじまる!
【目次】
序:何が本当に存在するのか?
第I部 心身問題と中枢
「心身問題」から「支配的モナド」と「中枢」へ
「中枢」を作って展開する
第II部「閉鎖」としての「不確実性」の侵入
エージェントの閉鎖とモナド
第III部 不確実性の中心と中枢、そして意識
「不確実性の中心」とモナド的中枢
「中心」から「紐帯」へ
「紐帯」から「中心のない不確実性」へ
おわりに:心身問題への憎しみと、哲学の性急さについて

西洋哲学史 2 「知」の変貌・「信」の階梯
講談社選書メチエ
『西洋哲学史1』は、おかげさまで、たいへんな反響を呼び、また、各方面から高く評価されました。本書は、その第2巻です。(全4巻)
第2巻は、ヘレニズム哲学、中世の言語哲学、イスラーム哲学など、従来の「西洋哲学史」では、あまり重きをおかれてこなかったテーマにも、焦点をあてます。
ともすれば、暗黒の時代とみられがちだった中世を、「再生をくりかえした時代」として見直すという、本企画のひとつの大きな特徴が現れています。
また、「志向性」とか「様相」という、現代哲学につながるテーマについても丁寧に考える、期待にたがわぬ一冊です。
【目次】
序論 再開の哲学 鈴木泉
1.ヘレニズム哲学 近藤智彦
2.教父哲学 土橋茂樹
3.中世の言語哲学 永嶋哲也・周藤多紀
4.イスラーム哲学 山本芳久
5.盛期トマスとスコラ 上枝美典
6.中世における理性と信仰 加藤和哉
7.志向性概念の歴史 藤本温
8.様相概念 山内志朗

鎌倉仏教への道 実践と修学・信心の系譜
講談社選書メチエ
「旧仏教」を読み直し鎌倉新仏教のルーツを探る
鎌倉新仏教はゼロから生まれたのではなかった。偉大な祖師たちの思想が生まれる背景には、先行する有名無名の宗教者たちによる、さまざまな試みがあった。山林修行、戒律の問題、経典への信仰など「実践」をキーワードに、これまで見過ごされてきた、新仏教を準備したさまざまな運動に光を当てる。
【目次】
序章
第一章 優婆塞仏教の系譜
第二章 成熟と分裂──寺院社会の「出世」と「出世間」
第三章 実践と修学をつなぐモノ──経典信仰の諸相
第四章 信心の地平──夢想と観想
第五章 信心のゆくえ
終章
主要参考文献目録
図版出典
あとがき

分析哲学入門
講談社選書メチエ
英語圏の国々では現代哲学の主流であり続ける分析哲学。しかし、日本ではその存在感は薄い。その現状が「限りなく号泣状態に近いくらい悲しい」と嘆く著者による、渾身の入門書。「ある」とはどういうこと? 「知っている」とは? 「心」とは? 「物」とは? 分析という「理屈」を武器に、そしてユーモアを隠し味に、哲学的思考へとあなたをいざなう快著! (講談社選書メチエ)
現代哲学への最良の入門書、登場! 欧米では現代哲学の主潮流をなす分析哲学。その考え方の魅力を、専門用語を使わず、あくまでも日常的な話題に題材をとりながら、あますところなく語った快著。
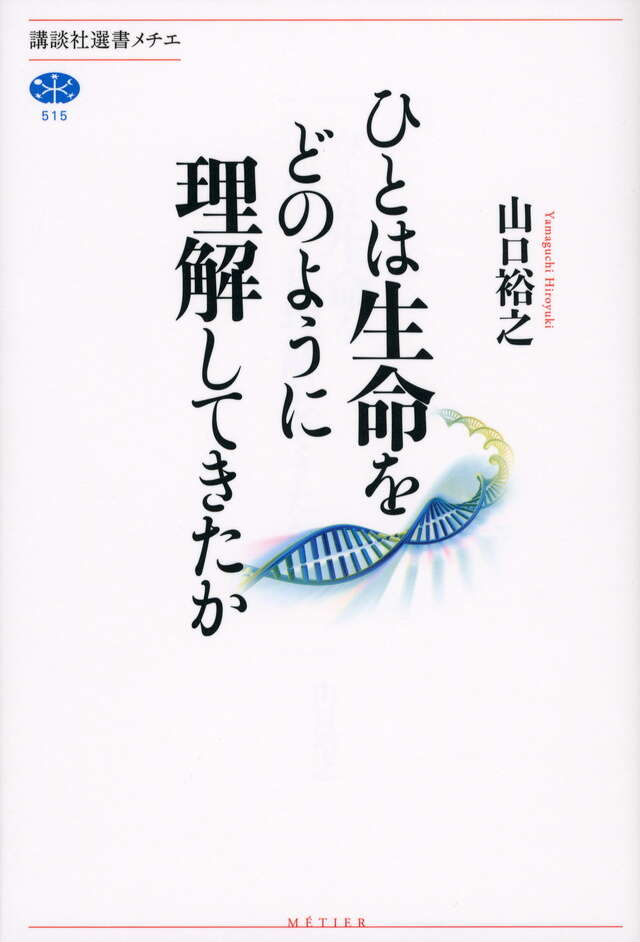
ひとは生命をどのように理解してきたか
講談社選書メチエ
「科学の見方」を問い直すエピステモロジー
DNAから何がどこまでわかるのか?
分子生物学や遺伝科学は「生命」をどう考えているか?
科学は、何を生命として捉え、分析してきたか?
現代生物学が拠って立つ論理と成立構造とは?
「遺伝子」概念が孕む揺らぎとは?
ダーウィン以前から、分子生物学や遺伝科学が急速発展するポスト・ゲノムの現代まで「生物学」の成立過程を辿り、「科学の見方」を哲学の視点から問い直す、生命のエピステモロジー。
【目次】
序章 生物学と哲学
第1章 生命科学の急発展と「遺伝子」概念の揺らぎ
第2章 生物学の成立構造
第3章 二つの遺伝子
第4章 機械としての生命
終章 「生命の存在論」へ向けて
注
引用文献一覧
あとがき

西洋哲学史 1 「ある」の衝撃からはじまる
講談社選書メチエ
哲学史の醍醐味がここに結集! 前ソクラテス期の哲学者パルメニデスの「存在」をめぐる考察にこそ西洋哲学の起点がある。その思考を読み解く論考に始まり、ニーチェ、ハイデガーに至る第1巻!
「西洋哲学史」と銘打つ書籍はたくさんある。しかし、それらは「哲学史」の知識の羅列になっていないだろうか。
「哲学史」は、どのような歴史観をもって、語られるべきか。
本シリーズは、哲学史に関して、現在、日本でもっとも信頼すべき知見を有する三人の編集委員による、「本気の哲学史」である。
全4巻で構成され、まずは、パルメメニデスの「存在」をめぐる思考に西洋哲学の起点があることを確認する。中世を暗黒の時代ではなく、再生をくりかえした時代として捉え直す。現代哲学は、未だ歴史に入らずと判断するが、古代キギリシアなど、まさに歴史の中に現代哲学の可能性を位置づける。
「これが哲学史だ」というべき渾身の企画である。
【目次】
序文 神崎繁
序論 哲学と哲学史をめぐって 熊野純彦
1.パルメニデス 納富信留
2.エンペドクレスとアナクサゴラス 木原志乃
3.古代ギリシアの数学 斎藤憲
4.ソクラテスそしてプラトン 中畑正志
5.アリストテレス 金子善彦
6.ニーチェとギリシア 丸橋裕
7.ハイデガーと前ソクラテス期の哲学者たち 村井則夫
8.哲学史の作り方 神崎繁

中華人民共和国誕生の社会史
講談社選書メチエ
「普通の人々」の現実から描く「革命前夜」。共産党の指導者の闘いや知識人たちの言説ではなく、貧困と暴力、腐敗の中で生きた街の人々のリアリティから、21世紀の大国となった「中華人民共和国」の誕生を描く。
【目次】
プロローグ
第1章 「〓勝」を生きる
1 戦後基層社会の出発点
2 退役兵士たちの戦後
第2章 繰り返される悪夢
1 戦時徴発の再開と抵抗
2 抵抗の屈折と内向化
3 社会のきしみと不信感
第3章 富裕者を一掃せよ
1 都市貧民の救済と管理
2 富裕者への厳しい視線
3 敵意のたどりつく場所
第4章 滅びゆく姿
1 社会秩序の崩壊へ
2 難民流入とその対策
3 末端行政の空洞化
第5章 革命後に引き継がれた遺産
1 食糧徴発の継続と強化
2 土地改革とその社会的条件
エピローグ
注
参照文献一覧
あとがき
索引

日米同盟はいかに作られたか 「安保体制」の転換点 1951-1964
講談社選書メチエ
池田勇人政権こそが、日米安保の岐路だった。アメリカから「貢献」「負担」を迫られ日本が応じる―「大国」に脱皮せんとする池田政権が強化し、現在まで日米関係の根底に据えられてきたこの構図の核心に迫る。
安保闘争の余韻が残る中、「大国日本」を志向する池田勇人政権は、日米安保体制の大きな岐路に立っていた。アメリカが「負担」の分担を求め、日本がそれを受け入れるという今日に至る構図を決定づけた外交プロセスとはいかなるものか。歴代首相と、外相・外務省の意図と動向、そして「天皇外交」の実相……。外交文書を緻密に読み込み、解明する!
【目次】
はじめに
第1章 「独立」の希求と日米安保体制 一九五〇年代
第1節 日米安保体制の形成
1 日米安保条約の調印と日本再軍備
2 警察予備隊から保安隊へ
3 自衛隊創設への道
第2節 安保改定の実現
1 鳩山一郎政権の挫折
2 安保改定に向けて
3 安保改定とその意義
第2章 日米「イコール・パートナーシップ」の形成
第1節 池田勇人政権の成立
1 池田政権の「新政策」
2 総選挙と日米関係の修復
第2節 池田=ケネディ会談の成果
1 ケネディ政権の対日政策
2 池田=ケネディ会談
3 「イコール・パートナーシップ」の演出
第3節 アメリカの「主要同盟国」へ 高まる日本への期待
1 池田政権の米欧日「三本柱」論
2 アメリカの期待と不満
第3章 防衛問題をめぐる日米関係
第1節 池田政権の防衛政策とアメリカ
1 第二次防衛力整備計画の策定
2 中国の脅威をめぐる相克
3 高まるアメリカの軍備増強要求
第2節 「核密約」と米原潜寄港
1 「核密約」の確認
2 米原潜寄稿の実現
第4章 池田政権のアジア反共外交と日米関係
第1節 池田政権の「ビルマ重視路線」とアメリカ
1 ケネディ政権の対日要求 韓国とインドへの支援
2 「ビルマ重視路線」の形成と展開
3 タイとラオスへの援助
4 日緬経済技術協力協定の締結
第2節 インドネシアへの積極的関与
1 池田のアジア大洋州諸国訪問
2 紛争の激化と日米の対応
第3節 ベトナム問題と日米関係
1 池田政権の対南ベトナム政策
2 対南ベトナム緊急援助の実施
おわりに
注
主要参考文献
あとがき
索引

中東戦記 ポスト9.11時代への政治的ガイド
講談社選書メチエ
9・11の直前と直後に、フランスの政治社会学者・イスラーム政治研究者ジル・ケペルはパレスチナ・イスラエルからエジプト、レバノン、シリアなど、中東の現地に頻繁に足を伸ばし、現地の反応や状況を微細に読み解いていく。
グローバル化の波の中で米国への憧れと敵意に揺れる若者たちを微細に描き、湾岸の繁栄の裏に潜む危機、ムスリム世界内部の分裂と闘争という最大の問題に言及していた本書は、9・11以後の10年とさらにその先を、鋭敏に見通していた。
訳者による詳細な注釈と独自の地図を多数盛り込んだ「中東の政治的ガイドブック」の決定版。
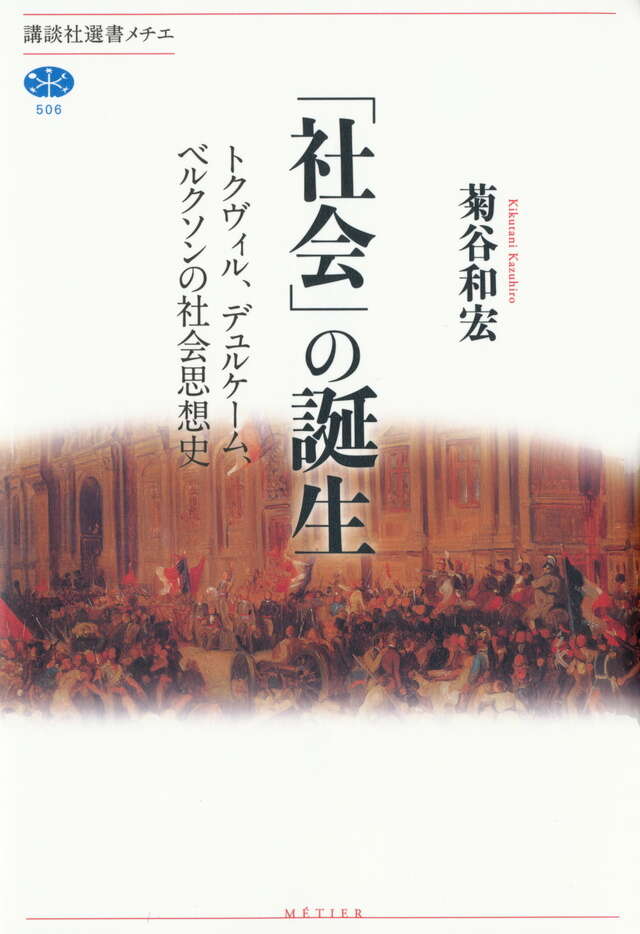
「社会」の誕生 トクヴィル、デュルケーム、ベルクソンの社会思想史
講談社選書メチエ
19世紀フランス、二月革命。
そこから人は、超越性に包まれた「世界」から「社会」という概念を生成した
神という超越性に包摂された世界から、社会という観念が切り離されたとき、「社会科学」が生まれた。
19世紀フランスに生まれたトクヴィル、デュルケーム、ベルクソンという三者を、ひとつの流れとして読み解く、これまでにない「ユニーク」な思想史!
【目次】
序 分解する現代社会──「社会」という表象
第1章 トクヴィル:懐疑
第2章 デュルケーム:格闘
第3章 ベルクソン:開展
終章 誕生した社会:絡繰──相互創造の網と人間的超越性
あとがき
参考文献
注
用語解説
年表

どのような教育が「よい」教育か
講談社選書メチエ
〈よい〉教育とは何か。根本から徹底的に考える。「ゆとり」か「つめこみ」か、「叱る」のか「ほめる」のか──教育の様々な理念の対立はなぜ起きるのか。教育問題を哲学問題として捉えなおし現代教育の行き詰まりを根本から解消する画期的著作! (講談社選書メチエ)
〈よい〉教育とは何か 根本から徹底的に考える
「ゆとり」か「つめこみ」か 「叱る」のか「ほめる」のか──
教育の様々な理念の対立はなぜ起きるのか。教育問題を哲学問題として捉えなおし現代教育の行き詰まりを根本から解消する画期的著作!

仏法僧とは何か 『三宝絵』の思想世界
講談社選書メチエ
源為憲が永観二年(九八四)、尊子内親王に献上した『三宝絵』。
三巻に分かれ、仏教説話によって構成されている。
釈迦は衆生を救うべく身を捨てて仏と成った。
上巻では、菩薩とよばれた前世での釈迦の実在する世界が、中巻では菩薩から僧に法が伝えられる様が、そして下巻では僧が行う仏教儀礼が語られる。現代社会にも深く浸透している日本仏教とは何なのか。
ここから、その本質が見えてくる!
【目次】
第一章 『三宝絵』の語る歴史
一 真理と慈悲
二 若き内親王の出家
三 神話的な歴史
四 平安時代の仏教における『三宝絵』
第二章 仏宝――施から孝養へ
一 釈迦の前世
二 尸〓王(しびおう)の行い
三 菩薩の願い
四 帝釈天のはたらき
五 天と地
六 孝養という行
第三章 法宝――音から物へ
一 仏の教え
二 聖徳太子
三 法の力
四 供養という行
第四章 僧宝――亡き釈迦と亡き母と
一 僧の役割
二 修正月
三 見えない釈迦
四 花をささげる
五 盂蘭盆会の由来
第五章 絶対的な幸福をめざして
一 ともに仏と成る
二 祈る子

アッティラ大王とフン族 「神の鞭」と呼ばれた男
講談社選書メチエ
ゲルマン民族を粉砕し、ゲルマン民族大移動を惹起してローマ帝国滅亡の引き金を引いたフン族。その最大の王アッティラとは何者か?
一五〇〇年以上にわたって積み重ねられた伝説のヴェイルを剥ぎ、歴史・考古資料のみにより、謎多き大遊牧帝国最強の王の実像を解明する。
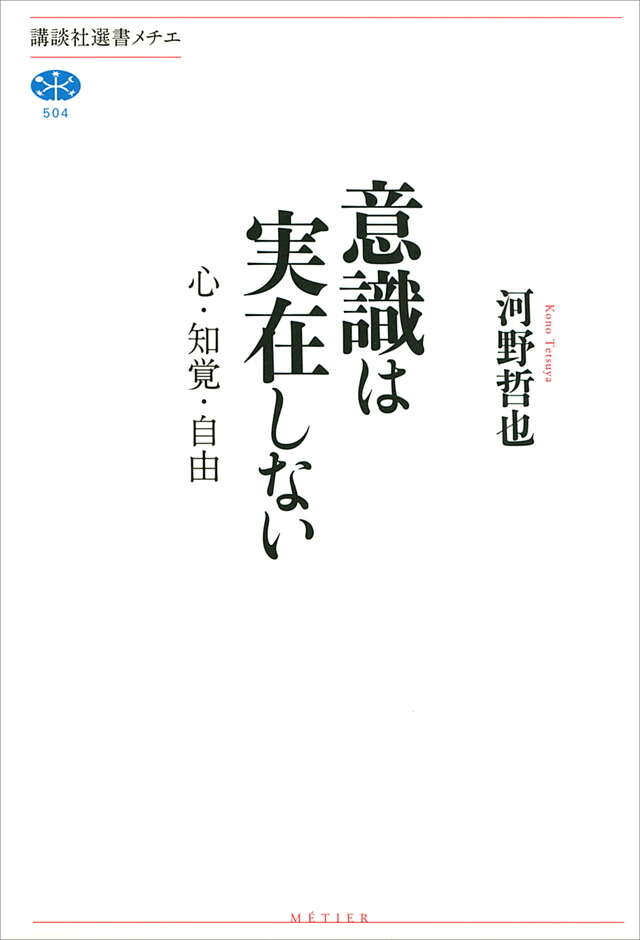
意識は実在しない 心・知覚・自由
講談社選書メチエ
近代的思考の限界を超える! “脳が世界を見ている”のではない! あなたの心は“環境”に広がっている!
心は身体の中に閉じ込められてはいない。知覚は脳に投影されるものではない。
そして、自由とは知覚する世界を探索することである──。
心の哲学やアフォーダンス理論、認知科学、脳性まひと自閉症の当事者研究などの最新の知見が、私たちの世界の見方を根本的に刷新する!
【目次】
序論 環境と心の問題
第1章 拡張した心
第2章 知覚とは何か――クオリアは存在しない
第3章 意図と自由の全体論――当事者研究とアフォーダンス
第4章 社会的アフォーダンスと生態学的記号論、そして、アクターネットワーク

株とは何か 市場・投資・企業を読み解く
講談社選書メチエ
市場と金融工学の暴走(リーマン・ショック)、企業再生(JAL再建)、CSRとSRI(社会的責任投資)……
株式は私たちに何をもたらしているのか? ファイナンスとガバナンスの相克
高度発達したファイナンス技術は、活発な企業活動を促すとともに、リーマン・ショックのような資本市場の暴走にも帰着する。
また、破綻した企業の再生やベンチャー育成、社会にとってよりよい企業を育てるSRI(社会的責任投資)を実現させられるのも株の力によるものである。
ファイナンス[企業の資金調達や投資]とガバナンス[企業をいかに統治するか]――株式の持つ相克する本質を掴み、市場社会の諸問題を基底から思考する!
【目次】
第1章 株とは何か
第2章 株式会社と資本市場の歴史的発展
第3章 現代ポートフォリオ理論の展開――デリバティブへの道
第4章 株式投資のメカニズム
第5章 資本市場は暴走する
第6章 社会のためのファイナンス