講談社選書メチエ作品一覧

中国が読んだ現代思想 サルトルからデリダ、シュミット、ロールズまで
講談社選書メチエ
日本の120年を30年で駆け抜ける! 貪欲な受容と激しい思考
サルトル、ハイデガー、フッサール、ウェーバー、レヴィ=ストロース、フーコー、デリダ、ハーバーマス、丸山眞男、ハイエク、ロールズ、シュミット、シュトラウス……
文化大革命の暗黒が晴れたそのときから、中国の猛烈な現代思想受容がはじまった! 日本のたどった道とよく似ているけれど、より切実で熱い思考にあふれたその現場と可能性を、自らも体感してきた中国人研究者が克明に描き出す。知られざる、そして知っておきたい中国がここにある。
【目次】
プロローグ
第1章 新しい啓蒙時代の幕開け――『読書』の創刊とヒューマニズムの復権
第2章 マックス・ウェーバーの再発見――「出土文物」の運命
第3章 異彩を放つ現代ドイツ哲学
第4章 西のマルキシズム「西馬」――フランクフルト学派を中心に
第5章 日本はいずこ?――一九八〇年代中国における福沢諭吉
第6章 遠のいていく新しい啓蒙時代――一九八〇年代の一つの総括
第7章 人気学問となった現象学
第8章 リクールとレヴィ=ストロース――フランス老大家の本格登場
第9章 フーコー受容の倒錯と可能性
第10章 脱構築と中国――デリダ訪中のインパクト
第11章 「西馬」再来――ハーバーマスと中国思想界
第12章 自由と正義への熱い思考――ハイエク、バーリン、ロールズ
第13章 合わせ鏡としての現代日本思想――丸山眞男の受容
第14章 注目される自由主義への批判者――カール・シュミットとレオ・シュトラウス
エピローグ――統括と展望

近代日本のナショナリズム
講談社選書メチエ
「日本」とは何か、今こそ考えなおす。近代日本をささえてきたものとはなにか。天皇制とナショナリズム、ファシズムとナショナリズムのかかわりとは……。いまこそ必読の論考。
戦前期のナショナリズムは、なぜ、ウルトラナショナリズムに向かったのか。「靖国問題」とはなにか。戦後社会とナショナリズムの相関とは……。「日本」を根本から考えなおすべき今、ナショナリズム研究に大きな足跡を残してきた社会学者が問う、日本のナショナリズムの本質!
【目次】
第1章 ナショナリズムという謎
第2章 ナショナリズムからウルトラナショナリズムへ
第3章 「靖国問題」と歴史認識
第4章 <山人>と<客人>
第5章 現代日本の若者の保守化?
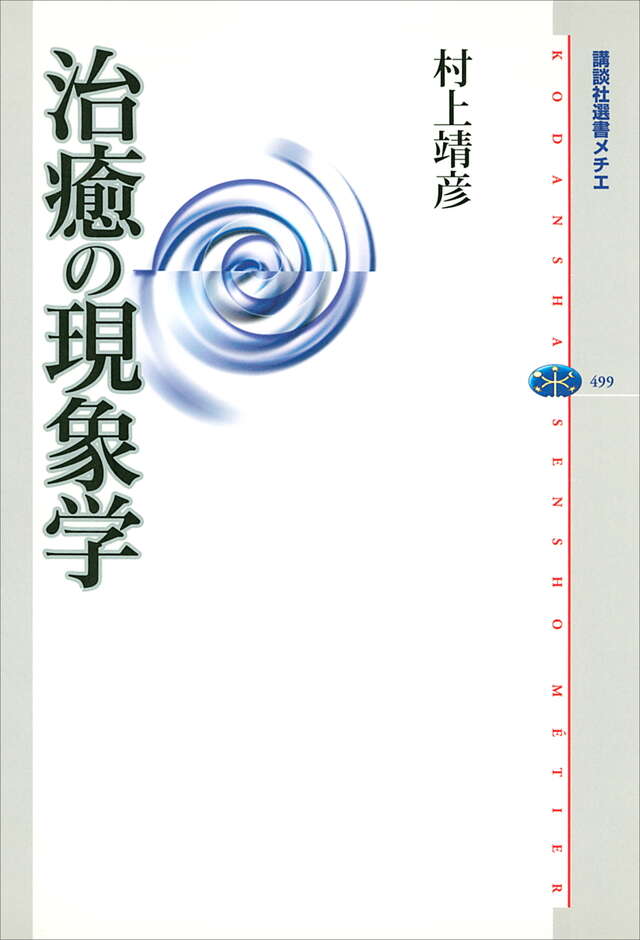
治癒の現象学
講談社選書メチエ
哲学と精神病理学、その交叉点で探究する「回復すること」の核心
人が「回復する」こと、とくに不安や精神の病から回復するとは、いったいどのような出来事なのか。
「治る」という不可思議な経験の意味と構造を求めて、フッサール以来の現象学が培ってきた「経験の構造」の探究を、精神病理学の臨床的知見と交叉させて、あらたな地平を切り拓く試み!
【目次】
序章
第1章 夢と自然治癒
──フロイトの「イルマの注射の夢」
第2章 芥川龍之介の不安
第3章 沈黙と夢
──空想身体の運動
第4章 超越論的テレパシー
──二人で作る創造性
第5章 椅子とうんちの物語
──行為の型と現実を囲い込む状況X
第6章 原ユートピア
──現実の反転について
終章 ジャン・ジュネの歌
──超越論的テレパシーに抗して
結語 空想身体の自由としての治癒
注
用語集
参考文献
索引

瞑想する脳科学
講談社選書メチエ
共感から慈悲へ
脳科学の知見から見通す 21世紀の人間の幸福!
「瞑想は、喜び、共感、直観、慈悲にかかわる脳の神経回路のネットワークを、かつて想像されたことのないような力強さで、生き生きと活動させる。そうした神経活動の変化は、脳の物理的構造の変化としても、あらわれてくる。人間の心や行動の変容のプロセスが、計測をつうじて、理解される道筋が開かれたのである。」(「はじめに」より)。脳科学の最前線を踏査し、瞑想宗教的行為と科学を結びつける可能性を探る。科学と宗教の両面からこれからの人間のありかたを問う。
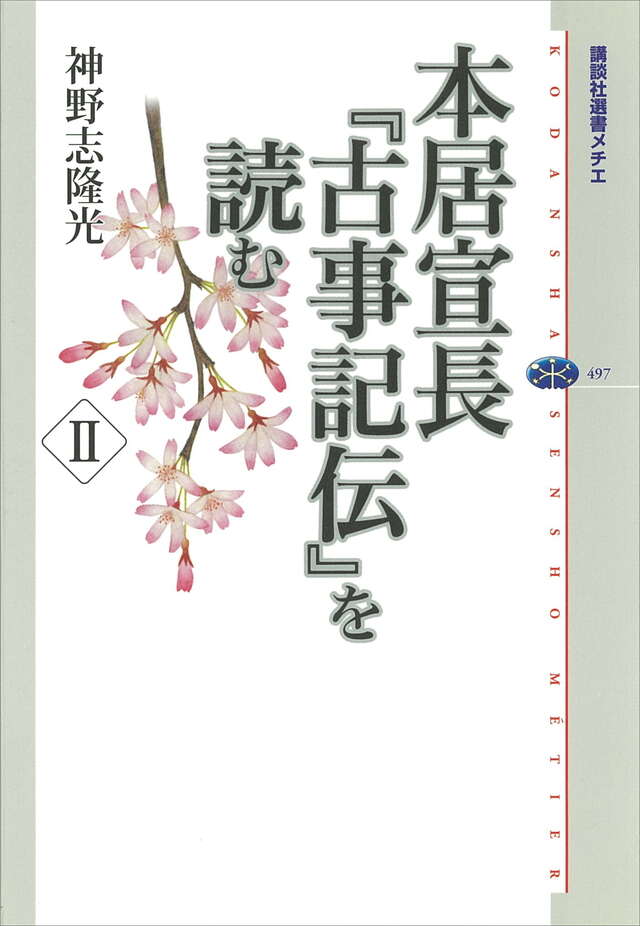
本居宣長『古事記伝』を読む 2
講談社選書メチエ
誰もがその名を知る本居宣長の大著『古事記伝』。しかし、全巻読み通した人はほとんどいないといっていい。本シリーズは、厖大・多岐にわたる宣長の注解を、全四十四巻、はじめから終わりまですべて読み尽くすという、画期的な試みである。第2巻は、十一之巻から二十之巻まで。八千矛神の歌物語、大国主神の国作り、天孫降臨、そして神武天皇の巻までをあつかう。
大国主神の国作り、天孫降臨、神武東征……
宣長があらわしだす「古事記」の世界!
誰もがその名を知る本居宣長の大著『古事記伝』。しかし、全巻読み通した人はほとんどいないといっていい。
本シリーズは、厖大・多岐にわたる宣長の注解を、全四十四巻、はじめから終わりまですべて読み尽くすという、画期的な試みである。
第2巻は、十一之巻から二十之巻まで。
八千矛神の歌物語、大国主神の国作り、天孫降臨、そして神武天皇の巻までをあつかう。
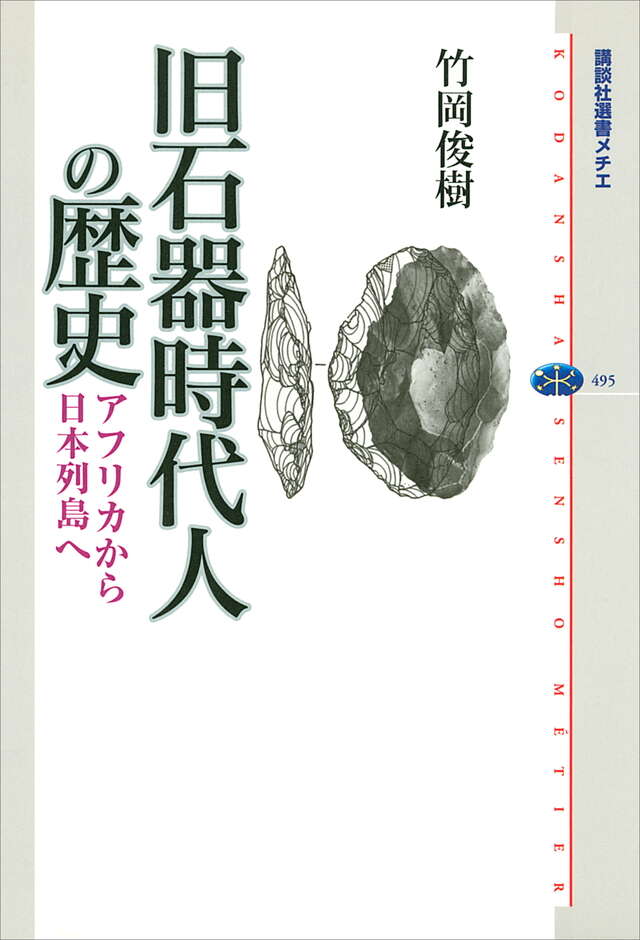
旧石器時代人の歴史 アフリカから日本列島へ
講談社選書メチエ
物言わぬ遺物=石器から旧石器時代の実像に迫る
石器しか資料がない中で、いかにして旧石器時代を知ることができるのか。
「捏造」事件の摘発にも深く関わった石器研究の第一人者が、石器の詳細な分析から、現代人とはまったく異質な旧石器時代人の文化を解明する。
【目次】
はじめに
第一章 私たちは何者か─人類の「進化」と人間の成立
1人類はどのようにして「進化」したのか
2人間はどのようにして成立したのか
第二章 岩宿遺跡の発掘から前期旧石器時代遺跡捏造事件へ
1文化の捉え方と文化の発展の論理の研究史
2前期旧石器時代研究の歴史
第三章 石器研究の方法
1研究方法の形成
2石器製作作業の分析方法
第四章 日本列島における旧石器時代の文化と歴史
1後期旧石器時代以前と後期旧石器時代初期の文化
2新石刃技法をもつ石器群
3国府系文化の変容
4文化の変容についての問題
第五章 遺跡はどのようにして形成されたのか
1環状ブロック群
2茂呂系文化のブロック群
3文化の荷い手はだれか
後記
引用文献
索引

アメリカ音楽史 ミンストレル・ショウ、ブルースからヒップホップまで
講談社選書メチエ
アメリカ音楽産業の殿堂・グラミー賞の歴代受賞者も多数登場。
偉大なるプレイヤーたちとそのサウンドの<歴史>をめぐる、エキサイティングな1冊!
ロック、ジャズ、ブルース、ファンク、ヒップホップ……音楽シーンの中心であり続けたそれらのサウンドは、19世紀以来の、他者を擬装するという欲望のもとに奏でられ、語られてきた。
アメリカ近現代における政治・社会・文化のダイナミズムのもと、その<歴史>をとらえなおし、白人/黒人という枠組みをも乗り越えようとする、真摯にして挑戦的な論考。
2011年サントリー学芸賞[芸術・文学部門]受賞
[目次]
はじめに
第1章 黒と白の弁証法 ――偽装するミンストレル・ショウ
第2章 憂鬱の正統性 ――ブルースの発掘
第3章 アメリカーナの政治学 ――ヒルビリー./カントリー・ミュージック
第4章 規格の創造性 ――ティンパン・アレーと都市音楽の黎明
第5章 音楽のデモクラシー ――スウィング・ジャズの速度
第6章 歴史の不可能性 ――ジャズのモダニズム
第7章 若者の誕生 ――リズム&ブルースとロックンロール
第8章 空間性と匿名性 ――ロック/ポップスのサウンド・デザイン
第9章 プラネタリー・トランスヴェスティズム ――ソウル/ファンクのフューチャリズム
第10章 音楽の標本化とポストモダニズム ――ディスコ、パンク、ヒップホップ
第11章 ヒスパニック・インヴェイジョン ――アメリカ音楽のラテン化
注
Bibliographical Essay │参考文献紹介
あとがき
索引

アイヌの世界
講談社選書メチエ
ダイナミックかつ多彩なアイヌの世界を活写する
アイヌは縄文人の子孫か?
クマ祭りの起源はイノシシ祭りだったのか?
阿倍比羅夫が戦ったのはアイヌか?
なぜマタギの言葉にアイヌ語があるのか?
中尊寺金色堂の金箔はアイヌが採った日高産か?──最新の知見をもとにアイヌをめぐる様々な問いに大胆に答えながら、伝統を守りつつもダイナミックに変貌し続けた、これまでになく多彩なアイヌ像を描き出す。

北条氏と鎌倉幕府
講談社選書メチエ
北条氏は、なぜ将軍にならなかったのか。なぜ鎌倉武士たちはあれほどに抗争を繰り返したのか。執権政治、得宗専制を成立せしめた論理と政治構造とは──。承久の乱を制し、執権への権力集中を成し遂げた義時と、蒙古侵略による危機の中、得宗による独裁体制を築いた時宗。この二人を軸にして、これまでになく明快に鎌倉幕府の政治史を見通す画期的論考! (講談社選書メチエ)
北条氏は、なぜ将軍にならなかったのか。
なぜ鎌倉武士たちはあれほどに抗争を繰り返したのか。
執権政治、得宗専制を成立せしめた論理と政治構造とは──。
承久の乱を制し、執権への権力集中を成し遂げた義時と、蒙古侵略による危機の中、得宗による独裁体制を築いた時宗。
この二人を軸にして、これまでになく明快に鎌倉幕府の政治史を見通す画期的論考!
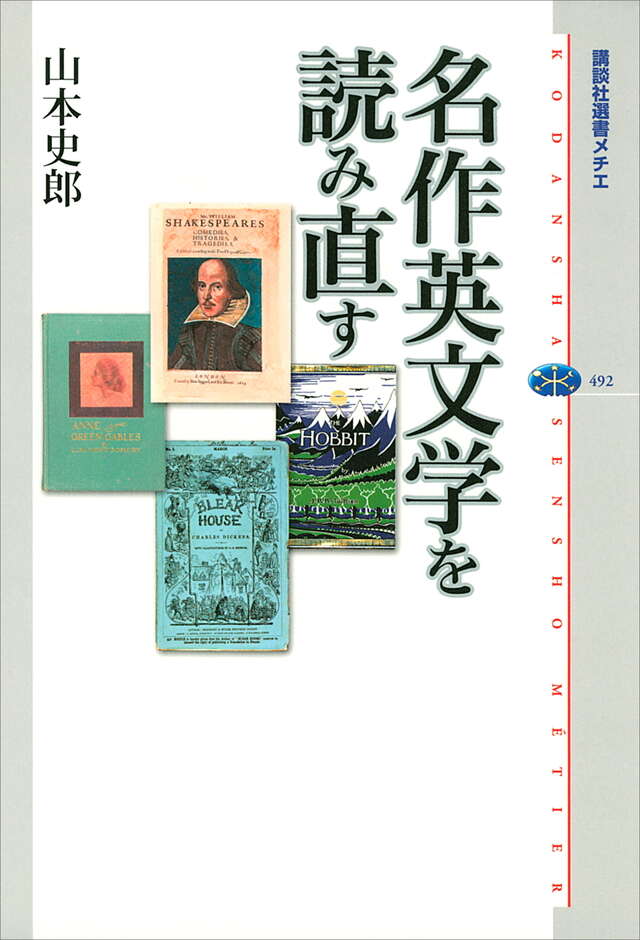
名作英文学を読み直す
講談社選書メチエ
秘密の花園、ロビンソン・クルーソー、アーサー王……
東大教授と一緒に英文学を遊ぼう
『秘密の花園』『赤毛のアン』=少女小説。
『ロビンソン・クルーソー』『ホビット』=冒険小説。
そう思い込んできたみなさん、慣れ親しんできたこうした作品には技アリ、しかけアリ、意外な意味がたくさん隠されているものです。「東大生だって、英文学に通暁しているわけじゃない。恥ずかしながら五十路になってやっと、そんな学生たちの微妙な空気を読み取っておもしろおかしい講義ができるようになった(はず)」とのたまう東大教授が、豊穣な英文学の世界にご案内いたします。
【目次】
はじめに
第1部 物語の中の「もう一つの物語」
第1章 隠されたテクスト
──『秘密の花園』にはどんな花が咲いているのだろう?
第2章 『ロビンソン・クルーソー』とモノモノモノ
──モノの饗宴と小説の誕生
第3章 ほんとうはこんなに笑えるトールキン
──ユーモアのレトリックを発掘する
第4章 『赤毛のアン』現象を読む
──ひそかに抹殺された「物語」
第2部 時代が生み出した「別の物語」
第5章 不倫千年
──アーサー王伝説を造り上げてきた三角形
第6章 つわものたちの夢
──マクベスの主題にもとづく変奏曲
第7章 変貌するテクスト
──『荒涼館』にはなぜ様々な花が咲くのだろう?
注
参考書目
あとがき

三人称の哲学 生の政治と非人称の思想
講談社選書メチエ
非――政治へ
非――人称へ
現代思想の最前線にたつ著者が挑む「人格」という装置の脱構築!
一見したところ正反対のようにみえる政治や思想、たとえば徹底して人格を破壊してきたナチズムの生政治=死政治と、逆に人格を金科玉条のように祭り上げる自由主義の人格尊重とが、実は同じような前提──生きるに値する生、生の生産的管理など──を共有している点にも、エスポジトはわたしたちの注意を喚起している。
生物学や人類学、言語学や社会学など、さまざまな観点から人間を解明しようとしてきた近代の諸科学を根底で突き動かしてきたもの、それがこの「ペルソナ」の装置であり、ナチズムとリベラリズムは、同じ装置によってもたらされた、たがいの反転像にほかならないのである。――<「訳者あとがき」 より>

交響曲入門
講談社選書メチエ
クラシック音楽の最高峰、交響曲のすべてがわかる!
おすすめディスクガイド付き
交響曲には「構造」と「論理」がある。「交響曲の父」ハイドンからモーツァルト、ベートーヴェンをへてブラームス、ブルックナー、マーラーへ。前代の課題を引きつぎつつ交響曲というジャンルに自らの個性を加えてゆく各作曲家の創意と工夫の跡を丹念にたどりながら名曲の高峰を経巡る、もう一歩深い鑑賞への誘い。
【目次】
目次
まえがき─クラシック音楽の聴き方
第一章 誕生
1 器楽の新しい波
2 交響曲への道
第二章 交響曲の雛形─ハイドン
1 ハイドンの交響曲創作の流れ
2 交響曲のプロトタイプ─交響曲第九五番ハ短調
第三章 交響曲の確立─モーツァルト
1 中期の創作
2 高峰への登攀
3 「深き淵より」─交響曲第四〇番ト短調
4 器楽の王=ジュピター
第四章 ベートーヴェン
1 《エロイカ》の飛躍
2 古典主義芸術の粋 ─交響曲第五番
3 《運命》以後
4 最後の境地 ─《第九交響曲》
第五章 ポスト《第九》─シューベルトとベルリオーズ
1 シンフォニスト、シューベルト
2 《グレート》
3 ベルリオーズの《幻想》
第六章 ロマン派交響曲
1 メンデルスゾーンとシューマン
2 歴史に堪える交響曲 ─ブラームス交響曲第一番
3 ロマン派交響曲
第七章 ブルックナーとマーラー
1 ブルックナー
2 達成点 ─交響曲第八番ハ短調
3 マーラー
4 否定への意志 ─マーラー交響曲第六番イ短調《悲劇的》
5 総合 ─交響曲第九番ニ長調
第八章 国民楽派のシンフォニストたち
1 ドイツ音楽の拡散
2 ドヴォルザーク
3 チャイコフスキー
第九章 二〇世紀と交響曲の未来
註
ディスクガイド
あとがき

中国「反日」の源流
講談社選書メチエ
倭寇の時代から現代まで
歴史が明かす「反日」の本質!
たんに「愛国」ということなら、日本人の多くも異存はない。日本にもナショナリズムはある。いわばおたがいさまのものである。自尊の意識なのだから、それがある程度の排外をともなうのも、常識の範囲内であろう。しかし中国の場合、現代日本人がわからないのは、まず日本がその排外の対象となり、それがいっこうに改まらないことにある。「愛国」が「反日」とイコールでむすびつき続ける中国人の心情と思考が、不可解かつ不気味なのである。――<本書プロローグより>

仏陀 南伝の旅
講談社選書メチエ
インド生まれの仏教は、まず、南へと旅立った。スリランカの石窟寺院と仏歯寺、黄金の仏塔の林立するミャンマーのパガン、タイの暁の寺……すべての故地を踏破した著者が、今なお生活の中に息づく仏陀の思想へと思いを馳せる思索の旅。
【目次】
はじまりは、ブッダ・ガヤー
第一章 仏陀の出現
1 ゴータマ・シッダルタの存在
2 ゴータマに先立つブッダの存在
3 ゴータマのさとり
4 如是我聞
5 仏教の成立
6 仏教の伝播
第二章 スリランカの仏教
1 光り輝く島
2 セイロン島への布教
3 仏陀の来島伝説
4 仏教王国・アヌラーダプラ
5 シーギリヤ遺跡への道
6 ポロンナールワへの遷都
7 キャンディの仏歯寺
第三章 ミャンマーの仏教
1 ビルマの竪琴
2 仏教の渡来伝説
3 黄金地への伝道
4 パガン王朝の宗教改革
5 ポパ山の精霊信仰
6 マンダレーのマハームニ仏
7 ミンドン王の第五回仏典結集
第四章 タイの仏教
1 黄金の地
2 仏教伝来
3 スコータイ王朝の仏教
4 アユタヤ王国の神と仏陀
5 時代はバンコク
6 仏教の現在
7 タイ仏教の行方
第五章 インドシナ三国の仏教
1 ラオスの仏教
2 メコン河とプーシー山
3 カンボジアの仏教
4 仏陀の化身
5 ヴェトナムの仏教
6 南伝と北伝の出会い
おわりも、ブッダ・ガヤー
あとがき

完全解読 カント『実践理性批判』
講談社選書メチエ
世界初のこころみ
超難解哲学書を徹底的に読みつくす
大好評、知の高峰を読み平らげるメチエ「完全解読」シリーズ第3弾。カント三批判書の第二書にして、「善」の根拠を論理的に証明し「倫理」を哲学的に基礎づけた近代哲学の金字塔を徹底的に読み込む。現代の正義論もこの書なしにはあり得なかった!
【目次】
はじめに
序
緒論 実践理性批判の構想について
解説1
第1部 純粋実践理性の原理論
第1篇 純粋実践理性の分析論
第一章 純粋理性批判の原則について
第二章 純粋実践理性の概念について
第三章 純粋実践理性の分析論の批判的解明
解説2
解説3
第2篇 純粋実践理性の弁証論
第一章 純粋実践理性一派の弁証論について
第二章 最高善の概念規定における純粋実践理性の弁証論について
解説5
第2部 純粋実践理性の方法論
結び
解説6
あとがき
完全解読版『実践理性批判』詳細目次
索引

室町幕府論
講談社選書メチエ
朝廷権力の「肩代わり」から「主体」の政権へ。室町幕府を読み直す画期的論考。100メートルを超える大塔、眩く輝く金張りの仏閣、華やかな祭礼──首都京都の強大な経済力を背景に空前の「大規模造営」を将来した武家政権は、今や朝廷を凌ぐ威光を確立した。弱体政権論を覆し、武家政権が「権力」と「権威」を2つながら掌握してゆく過程を義満時代を中心に描く。(講談社選書メチエ)
朝廷権力の「肩代わり」から「主体」の政権へ
室町幕府を読み直す画期的論考
100メートルを超える大塔、眩く輝く金張りの仏閣、華やかな祭礼──首都京都の強大な経済力を背景に空前の「大規模造営」を将来した武家政権は、今や朝廷を凌ぐ威光を確立した。弱体政権論を覆し、武家政権が「権力」と「権威」を2つながら掌握してゆく過程を義満時代を中心に描く。

マニ教
講談社選書メチエ
キリスト教がもっとも恐れた謎の世界宗教の全貌
世界初の包括的入門書
ゾロアスター・イエス・仏陀の思想を綜合し、古代ローマ帝国から明代中国まで東西両世界に流布しながら今や完全に消失した「第4の世界宗教」。「この世」を悪の創造とし全否定する厭世的かつ魅力的なその思想の全貌を、イラク・イラン、中央アジア、北アフリカ、ヨーロッパ、中国に亘りあまねく紹介する世界初の試み。
【目次】
プロローグ――マーニー・ハイイェーとマーニー教
第1章 マーニー教研究資料の発見史――西域の砂漠から南シナ海沿岸の草庵まで
第2章 マーニー・ハイイェーの生涯――「イエス・キリストの使徒」にして「バビロニアの医師」
第3章 マーニー・ハイイェーの啓示――現世の否定と光の世界への帰還
第4章 マーニー教の完成
第5章 マーニー教教会史1――エーラーン・シャフル
第6章 マーニー教教会史2――ローマ帝国
第7章 マーニー教教会史3――ウンマ・イスラーミーヤ
第8章 マーニー教教会史4――中国

昭和の思想
講談社選書メチエ
昭和の思想を包括的に俯瞰する画期的論考
「戦前=戦後」だけでなく、昭和はつねに「2つの貌」を持っていた。皇国史観から安保・学生運動まで、相反する気分が対立しつつ同居する昭和の奇妙な精神風土の本質を、丸山眞男・平泉澄・西田幾多郎・蓑田胸喜らの思想を元に解読する。
【目次】
はじめに
第一章 日本思想は二つ以上ある
第二章 思想史からの靖国神社問題──松平永芳・平泉澄
第三章 思想史からの安保闘争・学生反乱──丸山眞男
第四章 思想史からの終戦と昭和天皇──阿南惟幾・平泉澄
第五章 思想史からの世界新秩序構想──西田幾多郎・京都学派
第六章 思想史からの言論迫害──蓑田胸喜
第七章 二〇世紀思想史としての昭和思想史
おわりに
註
索引

僧兵=祈りと暴力の力
講談社選書メチエ
「霊験」への帰依、異界への畏れ、俗世の「道理」を超えた論理
彼らはなぜ恐れられたか
祈りによって人々に安心と喜びをもたらす、仏法の徒たる僧侶たち。しかし、中世という時代がはじまるにつれて、彼らの中には武器をとって、合戦を引きおこし、人々に恐怖を与えた者たちがあらわれた。暴力と祈りの力をあわせもつ彼らは、いかなる原理のもとに行動したか。比叡山延暦寺を舞台に、多彩な「悪僧」たちが跋扈し、「冥顕の力」をもって世俗権力、社会とわたりあう姿を描き出す!
【目次】
序――祈りと暴力の中世史
第1章 悪僧跋扈の時代
第2章 冥顕の中世
第3章 天台仏法の擁護者・良源
第4章 恠異・飛礫・呪詛
第5章 霊験と帰依
第6章 都鄙を闊歩する大衆・神人
第7章 強訴とはなにか
第8章 善なる大衆の時代へ
結――中世と現代の間

〈主体〉のゆくえ-日本近代思想史への一視角
講談社選書メチエ
「主体」はもちろんsubjectの翻訳語である。明治以降、この語がわが国に入ってくると、「主観」「主体」「主語」などさまざまな翻訳語があらわれる。たとえば西田幾多郎は、初期は「主観」をつかっているが、後期になると「主体」しか出てこなくなる。この移行ははたして何を意味するのだろうか。戦後には、「主体性論争」がわき起こり、たとえば学生運動では「主体性」という言葉がキーワードとなった。明治期の受容から、戦後、そして現代に至るまで、それぞれの時代の趨勢となった思想に伏流する「主体」を追い続け、日本近代思想史にあらたな視座を提供する、知的興奮にあふれた1冊。
【目次】
序章 「体」のシニフィアン群
第一章 subjectの由来
第二章 翻訳語創出
第三章 主観から主体へ
第四章 先駆ける歴史的人間学
第五章 主体・身体・国体
第六章 戦後主体性論争
第七章 叛乱/氾濫する主体
終章 主体の消失?
あとがき
参考文献一覧